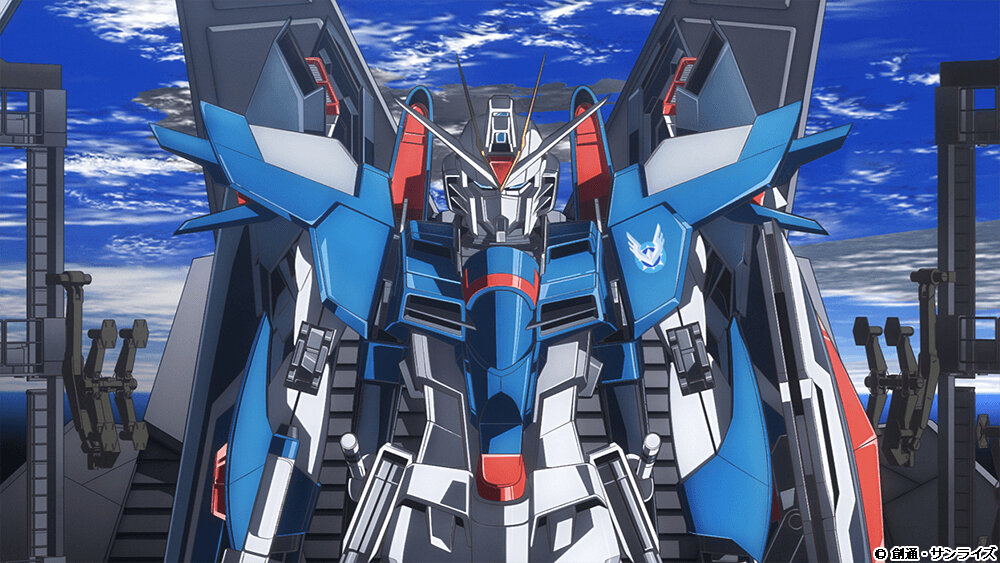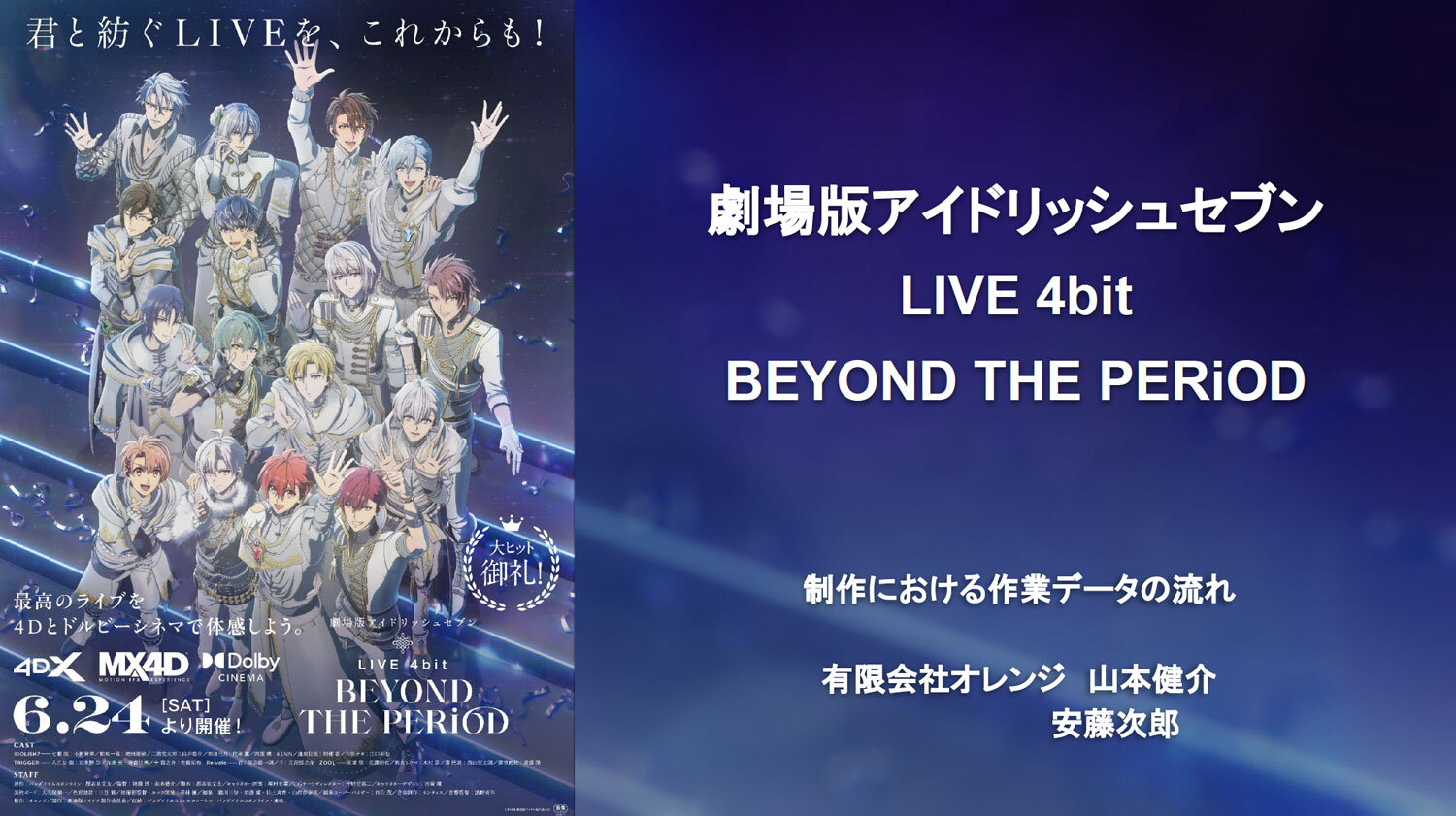日本における3DCG・映像教育の現状と課題を探るため、教育現場と制作現場、双方での経験をもつ方々に話を聞く本連載。最終回では、トンコハウスの堤 大介氏にご登場いただく。短編アニメーション映画の『ダム・キーパー』(2015)と『ムーム』(2016)を共同監督したことで知られる、堤氏とロバート・コンドウ氏。両氏は自分たちが培ってきた知識や経験を他の人へと伝えることにも意欲的で、『Painting with Light and Color』と題するライティングと色彩のビデオ講義(全9回)を制作し、オンラインスクールのSchoolismで配信している。
「先生として何かを教えるときも、映画監督として映画をつくるときも、同じアプローチ、同じ考え方をしています。受講者や観客、一緒につくる人たちに、伝えたいこと、感じてほしいことを一番良いかたちで提供する。そのための努力を惜しまないという点では、2つの仕事にちがいはありません」。本記事では、堤氏の『先生』としての一面にスポットをあて、これまでの道のりと今後の展望を紹介しよう。
映画を見ているような感覚で、最初から最後まで楽しめるビデオ講義
Pixar Animation Studios(以降、ピクサー)に所属していた頃から、堤氏はSchoolismでのビデオ講義配信に興味をもっていたという。「同僚の中にも講師をやっている人がおり、以前から誘われていました」。その時点でも、大学での講義やワークショップでの講師経験はあったものの、映画制作との兼業は難しく、どれも単発に終わっていたという。Schoolismのビデオ講義であれば、時間や場所の制約に縛られることなく、数多くの人に自分たちの知識や経験を伝えられると知った堤氏とロバート氏は、トンコハウス設立のタイミングでビデオ講義の制作に着手した。
『低価格で、世界中の人々に最高のアート教育を提供する』というSchoolismの理念に共感したのに加え、比較的時間の余裕もあったと堤氏はふり返る。「当時のトンコハウスには僕とロバートの2人しかおらず、やりたい放題の時代でした。しっかりした計画を立てず、身近にあった機材を使い、1レッスンずつノンビリつくっていきました。1〜2ヶ月で完成すると思っていたら、半年くらいかかりましたね」。ほかにも様々な仕事を並行して進めていたとはいえ、思った以上に時間をかけてしまったという。
-

-
堤 大介/Daisuke TsuTsumi
東京都出身。School of Visual Arts卒業。Lucas Learning、Blue Sky Studiosなどで『アイスエイジ』や『ロボッツ』などのコンセプトアートを担当。2007年、Pixar Animation Studiosへ入社。アートディレクターとして『トイ・ストーリー3』や『モンスターズ・ユニバーシティ』などを手がける。2014年7月にPixar Animation Studiosを去り、同時期に退社したロバート・コンドウ氏と共にトンコハウス(Tonko House)を設立。両氏の初監督作品である『ダム・キーパー』は、2015年米国アカデミー賞短編アニメーション部門にノミネートされた。オンラインスクールのSchoolismでは、両氏が制作した『Painting with Light and Color』と題する全9回のビデオ講義が配信されている。
できあがった両氏のビデオ講義はSchoolismのほかの講義とは一線を画する凝った内容で、関係者を驚かせた。今ではSchoolismの全受講者の20%が受講する、人気講義になっているという。「僕自身、好きなアーティストのデモビデオを昔はよく買っていました。でも、油絵を延々3時間くらい描いているだけの内容だと、どんなに好きなアーティストのビデオでも寝てしまうのです。10分くらいに分けて、少しずつ見ないと消化しきれませんでした。だから自分たちのビデオは、映画を見ているような感覚で、最初から最後まで楽しんでもらえる内容にすることを意識しました」。見る人に楽しんでもらえるよう伝え方を工夫するという点では、ビデオ講義の制作も、映画の制作も共通しているという。
ビデオ講義では、堤氏が専門とするライティングと、ロバート氏が専門とする世界観の構築や背景デザインについて、両氏が初心者向けに解説していく。「ロバートはプレゼンテーションがすごく上手で、ビデオ講義の制作でも様々なアイデアを出してくれました。例えば太陽からの直接光と、雲を介した間接光の解説図は、チョークで黒板に少しずつ描き、1コマずつ撮影しています。Photoshopを使えば簡単に描ける画を、あえてコマ撮りしたことで、わかりやすくて、楽しくて、印象深いシーンになりました」。
遊び心に溢れた解説図や美しい作例に加え、両氏による軽妙な口調のかけ合いも、この講義の魅力のひとつだ。「ビデオ講義にはインタラクティブ性がないので、それを補うため、僕が話すときには『これはどうなの?』『あれはこうだよね』とロバートにツッコミを入れてもらいました。ロバートが話すときには僕がツッコミ役になります。主観的な立場と客観的な立場、教える側と聞く側の両方が登場したことで、ビデオ講義の受講者が『僕もソレを聞きたかった』というように感情移入しやすくなったと思います」。
▶︎次ページ:ピクサーの採用哲学にも共通する、堤氏が伝えたいこと
[[SplitPage]]『就職するため』の受講か、『一生の仕事にするため』の受講か
前述の通り、両氏のビデオ講義は『Painting with Light and Color』と題されている。このタイトルを見て、『ライティングや配色のテクニックを学べるのだろう』と期待した人もいるだろう。筆者もその1人だ。しかし、テクニックの修得だけを追い求める人は、成長が頭打ちになると堤氏は釘を刺す。
「テクニックを伝えるだけなら、全9回もの講義は必要ありません。僕たちが伝えたいのは、絵を描くときの考え方、アプローチの方法、観察のやり方です」。絵筆の使い方、ソフトの操作方法などのテクニックを覚えても、そのテクニックを使う理由や目的を理解していなければ、学んだことを応用できない。結果として、その人のアーティスト人生は長続きしないという。
ビデオ講義を受けた瞬間に、何かが劇的に変わることを期待しないでほしい。受講後も、自分の力で学び続け、成長し続けるためのきっかけや道しるべを得たり、基盤をつくったりすることを目的にしてほしいと堤氏は語る。「『就職するため』に講義を受けている人と、『一生の仕事にするため』に受けている人とでは、5年先、10年先、20年先で大きな差がついてしまいます」。
数ヶ月先、数年先の就職だけに目を奪われている人は、テクニックを偏重する傾向にある。加えて、重いものを持ち上げるならこのポーズ、ジャンプするならこのポーズというように、その表現は過度にマニュアル化されがちだという。「教材や本に書かれたマニュアルを鵜呑みにするのではなく、実際の人間の動きを自分の目で観察し、そのポーズが生活のどんな場面に登場するのか、前後にどんな動きが発生するのかといったことまで分析しなければ、応用力は身に付きません。だからこそ、観察が全ての表現の基盤となるのです」。
今回のインタビューの直前、堤氏は空港から都心へ向かう電車の中で乗客をスケッチし、『日本人は似たような外見をしている』という先入観のまちがいに気付いたという。「スケッチをするときには上手く描きたいから、対象をすごく観察します。表面の化粧や服装、その下の骨格、内面の感情を反映する表情や仕草まで観察していくと、普通の人には捉えられないものが表現できるようになるのです。スケッチしながら観察した日本人は、顔の形も表情も様々で、ぱっと見の印象で判断してはいけないと思いました」。
観察力を重視する方針は、ディズニーやピクサーの採用哲学にも共通しているという。「僕は学生時代にディズニーのトレーニングを受けたことがあります。当時の僕は普通の絵描きで、アニメーションの勉強はまったくしていませんでした。しかし『私たちの仕事の本質は、世の中をどのように観察し、どのような物語として表現するかにあります。注目するのは、観察する力と、何を表現する人なのかということです。アニメーションの作り方は会社で教えますから安心してください』と言われました。この哲学は、現在のピクサーのインターンシップ採用にも踏襲されており、ピクサーへコンスタントに人を送り込む学校の教育方針にも反映されています」。
一方で、この採用哲学は『非常にぜいたくなもの』だと堤氏は補足する。「会社に入った後で教育することが前提になっており、会社には相応の負担がかかります。しかし、この哲学があるから今のディズニーやピクサーがあるのです」。
ディズニーやピクサーと比べれば予算も制作期間も少ない日本のCGプロダクションが、同じ哲学で人を採用することは難しい。多くの会社は、即戦力重視、テクニック重視の採用をしており、教育機関の多くもその方針にならった即戦力教育を行なっている。「教育現場、制作現場、市場はつながっており、どれかひとつが変わろうとしても変われないのが実情です。世界市場で売れるコンテンツをつくる日本の会社が増え、採用哲学が変わることで、教育現場の方針も変わっていくでしょう。そのための働きかけを、制作現場と教育現場の両方でやっていきたいですし、同じような行動に出る人が増えてくれることを期待しています」。
TEXT_尾形美幸(CGWORLD)
PHOTO_弘田 充