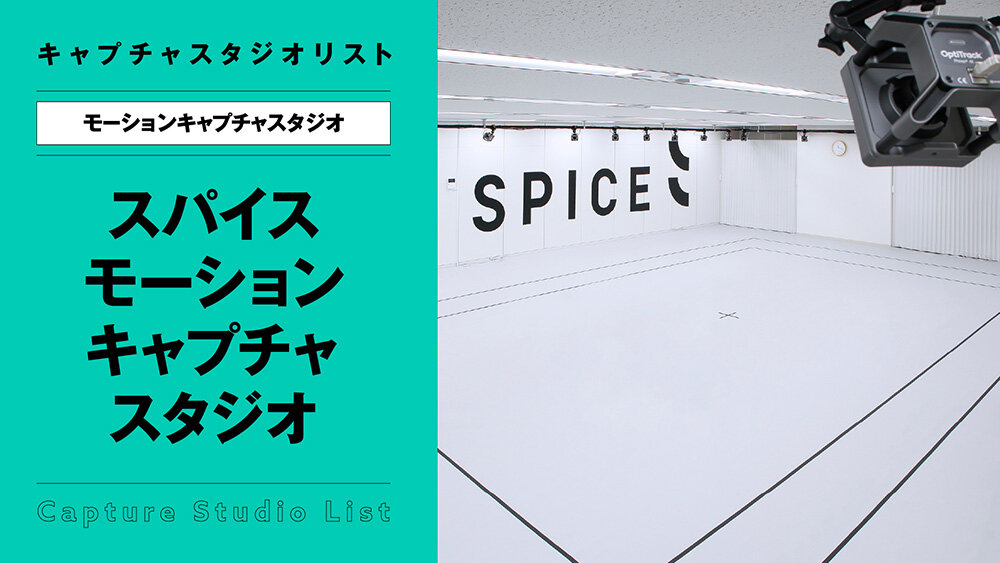ジェームズ・キャメロン×ロバート・ロドリゲスが、細やかな演出で「漫画絵」少女を映像化
ところで、『Battle Angel Alita』のはじまりは2000年の初めにまで遡る。『銃夢』のハリウッド映画が製作されるというニュースが報じられたものの、撮影開始までここから10数年もかかってしまったのだ。これは膨大な予算をかけるハリウッド映画では珍しいことではなく、その間もキャメロンは脚本を着実に仕上げていった。そして、満足のいく内容に至ったが、大ボリュームだったためシェイプアップする必要がある、という段階まで差し掛かった時点で、『アバター』の続編にGOがかかったという。しかも5作目まで予定されるシリーズものになりそうだった。加えて『ターミネーター』の新シリーズ、『ミクロの決死圏』のリメイクなど、ビッグ・プロジェクトが目白押しに。『Battle Angel Alita』の製作はさらに遅くなってしまうのか? と危ぶまれたそのときに、新たな人物が登場する。『デスペラード』、『シン・シティ』、『スパイキッズ』を監督したロバート・ロドリゲスだ。ここからはジョンの言葉を借りて経緯を説明しよう。
「ジェームズとロバートとビジネスランチをしていたときのことだ。ジェームズが『アバター 2』が始まることを話すと、ロバートは『え? じゃアリータは?』と言ったんだ。そのときすでにロバートはアリータのことを知っていたし、非常に興味をもっていてくれたからね。ジェームズが『満足のいく脚本は出来上がっているんだけどまだ長いんだ』と言いながらロバートを見てひらめいた。『脚本を仕上げてみないかい?』と。ロバートはすぐに引き受けて、脚本のシェイプアップに取りかかった。その半年後、ぼくらはロバートが仕上げた脚本を読んだ。そこにはジェ-ムズの書いた脚本に盛り込まれていた必要な要素が全て残されていたし、何より普遍的なテーマが完璧に受け継がれていたんだ。その脚本を読んですぐにジェ-ムズは言った『この作品の監督をやらないか?』。それで決まりだよ」。
こうして『アリータ:バトル・エンジェル』の製作が正式に決まり、撮影がスタートした。2016年のことである。
© 2017 Twentieth Century Fox Film Corporation
アリータたちの住むクズ鉄街(ジョンの言葉では「アイアン・シティ」)のセットは、米テキサス州につくられた。そこに原作者の木城氏を招いたことがあるという。ジョンは「木城は言葉少ない男だけど、彼の表情を見ればワクワクしていることがわかったよ」と語る。また、アイアン・シティの設定でも原作から変更した点があるという。それは実にキャメロンらしいエピソードだ。
原作の舞台は特に国を決めているわけではなく、木城氏は「強いて言えば北米か」と語っていたそうだが、舞台には軌道上に浮かぶ空中都市「ザレム」が存在し、地上からつながる数本のパイプと、おそらく中心には軌道エレベータのようなものがあったらしいことがわかる。この軌道上に浮かぶ都市が技術的に可能なのは赤道付近である。そこでキャメロンは舞台を赤道のある南米に変更させてくれ、とお願いしたそうだ。もちろん実際に軌道上にセットの都市を浮かべるわけがない。あくまでも設定上の話だ。だが、実はキャメロンの映画の設定は全て理由と技術考証がしっかりしている。『ターミネーター2』のT-800の変化の理由、タイタニック号の沈没の仕方、『アバター』のナヴィ語など、全てキャメロンが技術的に納得した内容になっているのだ。これは決して自己満足ではなく、そういった考証はそこから派生するあらゆる細かい設定に影響し、その上で展開される物語にしっかりとした地盤を与えてくれる。だからこそ空想の世界でありながらそこで繰り広げられる物語にわれわれは自然と心躍らせ、涙することができるのだ。
今回披露された最新の予告編でもアイアン・シティの様子を垣間見られたが、その街の密集した建物群と乾いた埃は実に現実味をもっており、この作品の世界観づくりに大きく役立っていることがわかる。これがキャメロンのこだわりの成せる技なのである。
地盤は整った。次は監督のロバート・ロドリゲスが思う存分に暴れる番だ。しかし、ジョンからこんなエピソードが飛び出した。
「ロバートが言ったんだ。『シン・シティ』では原作者フランク・ミラーのスタイルをきっちり再現できたと思う。今回の『アリータ』ではどんなスタイルで行こうか? ってね。だからこう答えたんだ。"ジェームズ・キャメロンのスタイルで頼む"と」。
意外と思慮深いのか、ロバート? と思わせるエピソードだが、これは一種の武者震いだろう。その証拠に今回のフッテージを観た限りでは、ジェームズ・キャメロンのスタイルを保ちつつ、ロバート・ロドリゲスらしい重力を感じさせながらもキレの良いアクションが心地よい。さらに、アリータの登場シーン(後述)での丁寧な演出は目を見張るばかりだ。
前述の通り、今回のプレゼンテーションで公開されたシーンは5シーン。まずアリータの目覚め、すなわちわれわれが初めてアリータと出会うシーン。続いてアリータが想いを寄せる男性ユーゴとの出会いのシーン。ここではアイアン・シティの雑多な様子がよくわかる。そしてアリータの初バトルのシーンへと続き、アリータの謎が次第に解明されていくシーンにつながっていく。全てのシーンを通した一番の感想は、このタイミングでなければできなかった作品なのだな、ということだ。
アイアン・シティや郊外のリアルな空気感、パフォーマンスキャプチャによるアリータの動きや表情、どれをとっても『アバター』での技術実績がなければ成し得ないものだ。キャメロンと作品との出会いから完成まで10数年かかったのは、まさにこのタイミングを待っていたからだと言っても過言ではない。
とは言え、今回上映されたのはわずか5シーン。これで『アリータ:バトル・エンジェル』という作品を語るのは到底無理である。しかし、その中であえて言わせてもらえば、注目すべきはアリータが目を覚ます、フェイシャルキャプチャを活かした冒頭シーンだ。
© 2017 Twentieth Century Fox Film Corporation
2017年12月に『アリータ:バトル・エンジェル』の予告編が公開されると、アリータの大きな目が賛否を呼んだ。それは日本の漫画キャラ特有のものだが、CGによるリアルな質感に対してその大きな目は一見不気味なのである。スタッフからは反対する意見もあったという。
しかし、大きな目はキャラの心を表現する窓で、日本の漫画文化においてとても大切な要素だということをキャメロンらは十分理解しており、それをきちんと受け継ごうとした。そのためにロドリゲス監督に課せられた課題は、観客がアリータに感情移入できることだ。
ジョンは語る。「今回のプレゼンの後半でパンチを繰り出すアリータを見ているとき、彼女の目の大きさはもう気にならなかったでしょ?」。キャラに感情移入してシーンに見入っていれば目の大きさなど気にならなくなる、ということだ。全編を通して見ていないのでバトルシーンに至るまでのアリータの描かれ方はわからないが、アリータの目覚めのシーンだけ見ても、十分感情移入できるだけのきめ細やかな演出がされていることがわかる。その例を、具体的に紹介しよう。
まず冒頭のアリータの寝顔のアップカット。ゆっくり寝顔を見せた後、まず最初に小鼻をひくつかせて呼吸し、白く美しいロボットの指で鼻をさわる。それからようやく目をゆっくり開けるのだ。アリータの皮膚の質感や瞳の光彩はもちろん見事だが、それらをキャラクターの一部として生かすのはこういった細かい演出だ。アリータに身体を与えたのはサイボーグ専門医師のイド。原作には登場しない女性の助手と一緒で、彼女の腕も機械だ。イドと助手は起きてきたアリータを、迷子の面倒を見る夫婦のような暖かい眼差しで迎える。この原作にはないシーンでCGキャラクターのアリータを一人の少女として映し出している。場面は他の部屋に移り、木製のテーブルでのオレンジをめぐる三人のやりとり。これはぜひ劇場で確認してもらいたい。アリータがさらに生き生きと輝くシーンで、観客はこのシーンからアリータを一人の少女として観ていくはずだ。街の荒廃ぶりや機械の身体の能力がどのようなものなのかを表現するのはその後で、まずはアリータの魅力を引き出すことに専念し、そのために原作にはないアレンジも行なっている。この、観客の気持ちをスムースに誘導するシーンの組み立てはまさにキャメロン・スタイルと言え、ロドリゲス監督は見事に期待に応えている。もちろん最後までアリータの目の大きさが気になる人もいるだろう。しかし、ここまで丁寧な演出をされた後ではそんなことはどうでも良い。後は好み次第、というわけだ。
© 2017 Twentieth Century Fox Film Corporation
今回のフッテージ・プレゼンテーションではCG技術の目新しい情報を得ることができず、作品の全貌もまだまだ未知数である。しかし、キャメロンとロドリゲスの『銃夢』に対するリスペクトはしっかり感じることができた。これは何よりの収穫である。というのも、これはあくまでも個人的見解だが、ハリウッド版『攻殻機動隊』が興行的に失敗に終わったのは、シーンや設定からサイバーパンクに対するわずかな嫌悪感というか距離感を感じるからだと思う。ホワイトウォッシュも取り沙汰されたが、そんなことより製作者がサイボーグや電脳に対してマイナスイメージをもっていたことの方が、原作を生かせず失速した原因だったのではないか。
サイバーパンクに対して、われわれ日本の漫画ファンはもちろん、『銃夢』をハリウッドに紹介したデルトロも、キャメロンも、ロバート・ロドリゲスも、おそらく口を揃えてこう言うはずだ。「カッコいいー!」と。この精神があれば『アバター』で培った技術を存分に生かしたエンターテインメント作品になることはほぼまちがいない。この数年のハリウッド映画で、日本の漫画、アニメ、特撮の世界観がハリウッドに正しく伝わり受け入れられていることがわかるが、この『アリータ:バトル・エンジェル』でそのことをより強く感じさせてほしい。
12月の公開より半年も早いタイミングで今回のプレゼンテーションが行われたことから、原作を生み出した日本のマーケットをいかに大切にしているかもわかる。おそらく今後も情報が小出しにされていくだろう。それを楽しみながら、12月まで待つとしよう。
「SXSW 2018」イベント時の集合写真。左から、キーアン・ジョンソン(ユーゴ役)、ジョン・ランドー(プロデューサー)、ローサ・サラザール(アリータ役)、ロバート・ロドリゲス(監督)