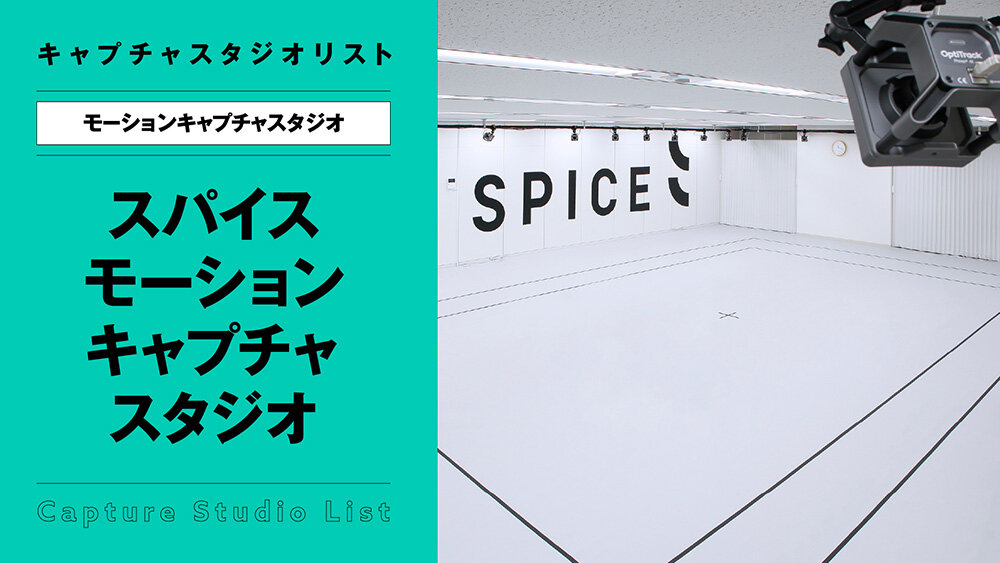<2> 8Kコンテンツの可能性と課題
続いて、8Kの映像作品を制作しているクリエイターとして、P.I.C.S.の池田一真氏とROBOTの諸石治之氏が登場。池田氏は広告、ミュージックビデオ、VRコンテンツ、インタラクティブコンテンツなど幅広いジャンルで活躍している映像ディレクターである。諸石氏は8K映像やプロジェクションマッピングなど新しいテクノロジーと組み合わせた映像作品を手がけている。
そして、両氏が参加し昨年制作された8K/HDRドラマ『LUNA』が上映された(会場の機材の都合上、HDRではなくSDRでの上映)。諸石氏によれば、8Kコンテンツはスポーツやライブなどノンフィクションのものが多いが、『LUNA』は8Kでフィクション、物語をつくることに挑戦した作品だという。
『LUNA』は現代版竹取物語とも言うべき青春ドラマで、夜のシーンが多いがHDRでの撮影ということで、月や夜空、夜景など光の表現の多様さを意識して、ストーリーが構築された。そのため、撮影現場ではSDRとHDR両方のモニタを用意してライティングやセットのつくり込みをチェックしながらの撮影となった(詳しくはCGWORLD 2017年1月号 vol.221でもメイキングを紹介しているので、そちらも参照されたい)。
池田氏と諸石氏による『LUNA』メイキングの解説の様子
本作で監督・編集を務めた池田氏は、8K映像と他の映像との最大のちがいは、空気感まで描かれることだと言う。「8KとHDRが組み合わされることで、2Dでも3Dに見える奥行き感が生じる」と諸石氏も続けた。ディスプレイの向こうに物語の世界があり、それを片隅から覗いているような感覚を憶える瞬間が何度もあったという。
それは演出にも影響し、説明的なカットを入れなくとも同じようなアングルで動きを追うだけで状況が伝わり、役者の微妙な表情がこれまで以上に雄弁に語る映像となった。司会の末岡氏も、作中で少女がカメラを見るシーンでは目が合って照れくさいといい、松村氏も観ているうちに作中で一緒に文化祭の準備をしているような目線になっていた、と8Kの生む現実感を体験したようだった。
もちろん8Kゆえの苦労もあり、役者の肌や衣装の質感などもリアルに映し出されるため、衣装の素材などはかなり細かくスタイリストと検討して衣装づくりを行なったという。そして、通常行う肌修正は空気感を損なうためやらなかったとのこと。
実写作品の多い8Kコンテンツだが、この作品ではCGと合成を多用しており、空の表現はほぼCGとなっている。合成の場合、不要な部分を色の情報を手がかりに切り取っていくが、2Kでは微妙にボケることでごまかされていたところが8Kではボケず、さらにHDRで色のレンジが広がったことでグリーンバックが残ってしまうという問題が起こり、結局1フレームずつ手作業で処理することになったという。またこれまでは、写真やCGは良いものであれば動画に問題なく馴染ませることができたが、8Kだと静止画の部分がまるわかりになってしまったとのこと。
撮影前に高精細画像での完成図を相当明確に設計しないと、撮影後の調整が容易ではない、というのも課題と言える。その分、事前の準備や計算が重要となる。またCGの制作環境がSDRであれば、最終的なHDRでの見え方が別物になるため、再構築が必要となってしまう。このあたりは8K映像の編集環境の進化次第だろう。
今後、8KでCG作品を制作する場合、小手先のごまかしは通用せず、実写作品・実写素材のリアリティが圧倒的になる分、むしろ大胆に"嘘"をつき、非現実的な形状や色をつくり出した方がいいのではないかと池田氏は語る。8Kはそういう表現によりインパクトを与えるものでもあるのだ。
そして解像度が向上すればもちろん扱うデータ量も増大する。本作は最終的なパッケージとしては5TBほどだが、撮影中は何本ものハードディスクを使い、撮影後夜中のうちにバックアップを取り、翌日にはデータを空にして撮影に臨む、という手間を要したという。またCGのレンダリングもこれまで数分規模の作業だったものが数時間はかかるようになった。
諸石氏は、8Kになるとキャンバスが非常に大きくなり、これまで0か1かで処理されていたその間に沢山のレイヤーが発生し、使える色の数が増え、もっと大きな画、あるいはとても小さな画も描ける。クリエイティブの世界が拡大していくというのが、これからのメディアに生まれる面白さだと語った。