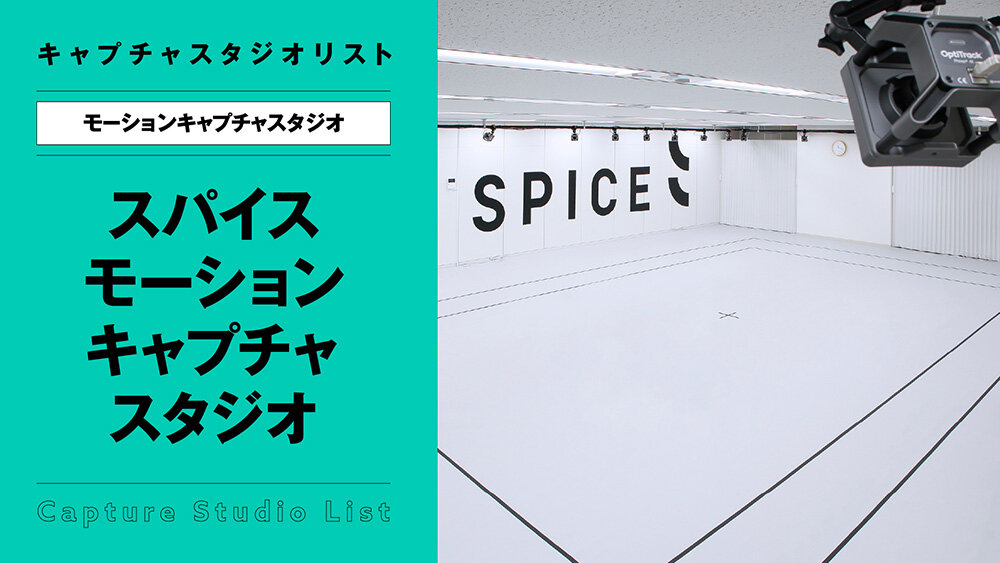<3>はるばる海を越えて参戦した日本勢
SCEを除くと、数少ない日本勢で最も目を引いたのは、ファイルIOや動画ストリーム再生に強みを持つCRI・ミドルウェアのブースだ。
今年のトレンドを意識してか、大きくアピールしていたのは「Sofdec2 for VR」というVR HMD「Oculus Rift」と「Gear VR」に対応するストリーム映像再生ミドルウェアだ。「Oculus Rift」の場合は4K、「Gear VR」の場合は2.5K解像度で60fpsの高フレームレートでの動画再生に対応する。ただ、「Oculus Rift」の最大フレームレートが90fpsであることを考えると、「Oculus Rift」版は若干物足りない。というのも、ストリーム映像にシームレスに切り替わるようなゲームのカットシーンの場合で、そのゲームが90fpsを死守するようにつくられていた場合を想定すると、通常のディスプレイで視聴するには十分な60fps動画が、直前のフレームレートとのギャップでどうしても滑らかさが落ちたように体感してしまうのではないかと危惧するからだ。
特に首を動かした際に、新たに視野に入ってくる部分が気になるのではないかと思われる。ソース動画の最大フレームレート自体は30fpsで構わないと思うので、ミドルウェアがデコードした後に中間フレームを生成してから描画エンジンに90fpsで渡してあげる機能があると、もっと良くなるのではないかと思えた。
VR HMDの活用が期待されるマーケットは、ゲームだけではなく、VR映像の視聴も大きな期待を集めている。高品質な圧縮、伸張、高フレームレートが出せるミドルウェアの需要は大いにあるだろう。また、従来のPC、コンソールゲームのクオリティを維持しながら、VR HMD用にすべてリアルタイムの3Dレンダリングを行うのは、パフォーマンス的に厳しい局面もあるだろう。そういった際に、最遠景など、ゲーム画面を構成する、ある一定部分のアニメーションに動画ストリームを活用するといったことも考えられる。CRI・ミドルウェアには、同社の強みを活かして、引き続きVR関連にも力を入れていただきたい。

▲CRI・ミドルウェアのブースも規模は小さくない

▲CRI・ミドルウェアの主力は動画再生ミドルウェア
例年通り比較的大きめのブースを構え、自社開発のリアルタイムレンダリングエンジン「Mizuchi」、「Maya」用ポストエフェクトプラグイン「YEBIS for Maya」、C#ゲームエンジン「Xenko」(ゼンコー)を出展していたのがシリコンスタジオだ。
同社ミドルウェア製品の品質には定評があり、日本の企業ということもあって同社が開発するタイトル以外にも日本のゲーム会社での採用実績は多い。海外でもランタイム版のポストエフェクトミドルウェア「YEBIS 3」が、アメリカやイタリアの会社で採用されている。今回のブース出展では、絶対数は必ずしも多くないものの、高品質なビジュアル出力に魅かれた来訪者が、ブースにアテンドするスタッフに対して熱心に質問する姿が見受けられた。

▲例年通り比較的規模の大きいシリコンスタジオのブース

▲シリコンスタジオの主力はMaya版のYEBISだろうか
その他、ペンタブレットのWACOMも中規模のブースを構えていた。誰もが認識しているデバイスであるためか、やはりブース内への人の入りはおだやかなもので、ブースへの来場者は、皆落ち着いて描き味を確かめているようだった。

▲WACOMブースでは、落ち着いて試すことができた
以上が、今回のGDC EXPOにおけるCG関連の出展状況だ。昨年との比較でいうと、CG関連の出展者数は、やや少なかったように思う。VR関連の華やかさの陰で、相対的に目立たなかったことと、エンジンと協業しているミドルウェアの定番化が進んだからだろうか。
実際、本稿で紹介した以外に、樹木生成ミドルウェアの「Speed Tree」(スピードツリー)やリダクションの「Simplygon」(シンプリゴン)も例年通り出展していたのだが、あまりアピール上手ではないのか、どうにも新たな驚きはなく定番感がにじみ出てしまっていた。
その一方で、今回意を決してGDCに参戦してくれたCIR・ミドルウェアには、日本人として賛辞を贈りたい。もちろん例年通りの出展を続けるシリコンスタジオにもだ。ワールドワイドで見ると、以前と比べておしょうゆ味のゲームのヒット作が減り、その結果として日本人スピーカーによるセッションが減ってしまったGDCだが、今現在、世界に通用するゲームをつくっている開発者が惜しげもなく自分たちのゲームの仕組みを教えてくれる数少ない機会には変わりない。たとえ言葉が分からなくても、視覚的にある程度は理解できるアーティストにとって、必ずしもハードルが高くないセッションもあるので、機会があれば是非参加していただきたい。
PHOTO & TEXT_谷川ハジメ(トリニティゲームスタジオ)