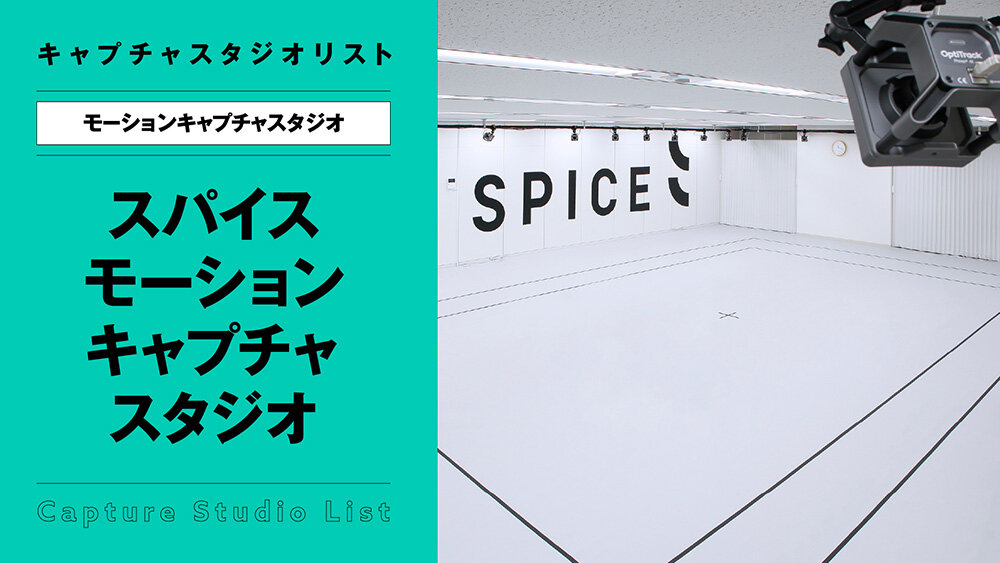ギャラリートーク「リアルとイマジネーション」/元内義則氏、木村俊幸氏
ギャラリートーク「リアルとイマジネーション」では、昨年に続いての参加となる、コンセプトアーティスト、マットアーティスト、美術家など多彩な活動をくり広げる木村俊幸氏と、映画『STAND BY ME ドラえもん』をはじめ、話題作に作品を提供してきた特殊造形作家の元内義則氏が、映像作品におけるアナログ技術の可能性、リアリティの表現について語った。
学生時代、映像会社でアルバイトをする中でマットペイントに触れ、そこから「変なことばかりやって」現在にいたる木村氏。様々な作品に関わってきた木村氏は、リアリティとは一義的に決まるものではなく、作品ごとに求められるリアリティは多様なものだと語る。高く評価されたオムニバス映画『ブルーハーツが聴こえる』内に登場した宇宙船のアートワークは、木村氏が捨てられようとしていたダンボールで制作したものだが、ダンボールの積層構造が実物のスペースシャトルのパネル構造を想起させ、SF世界を描き出すに充分なリアリティを備えた。
映画『ブルーハーツが聴こえる』のために制作されたダンボールの宇宙船
元内氏はSEとして働くかたわら趣味で模型等の制作を行なっていたが、白組の山崎 貴監督の新作にミニチュアスタッフとして応募、採用されたことがアーティストとしてのキャリアの開始点となった。映画『ALWAYS 三丁目の夕日』(2005)の古き良き昭和の町並みは、実際の町並みをそのまま再現したわけではなく、「記憶にあるリアル、若い人が見ても懐かしいと感じるもの、いわば嘘を描いた」と元内氏は語る。作品世界と見る人の記憶、感性を抵抗なく結びつけるリアリティの追求は、それ自体、正解のない表現行為と言える。CGかミニチュアか、デジタルかアナログか、という使い分けにも定式があるわけではない。ただ、データではなくそれが実在するというミニチュアのリアリティは今後も生き続けるだろう。
-

映画『GAMBA ガンバと仲間たち』(2015)コンセプトマケット
-

野比家ミニチュアの廊下
CGがますます発達していけば実物であるミニチュアに限りなく近づいていき、ミニチュアの出番はなくなっていくように思える。ミニチュアをつくって撮影までしたにもかかわらず、結局CGに差し替えられるケースもあるという。しかし、なお実物、ミニチュアの出番は絶えない。新作映画『ブレードランナー2049』でもミニチュアが使われている。『STAND BY ME ドラえもん』ではキャラクターはCGだが、家や町にはミニチュアを採用しているのも、畳の目や窓の影などの情報量が多くなれば、CGだと重くなってその都度時間がかかってしまうのに対し、ミニチュアであれば、様々なカットやライティングが容易に試せるからだ。また、爆破シーンなどは、ミニチュアをカメラに映らない後ろからハンマーで叩き壊すが、こうして生まれる迫力は廃れないだろう。
次ページ:
参加アーティスト4名によるギャラリートーク