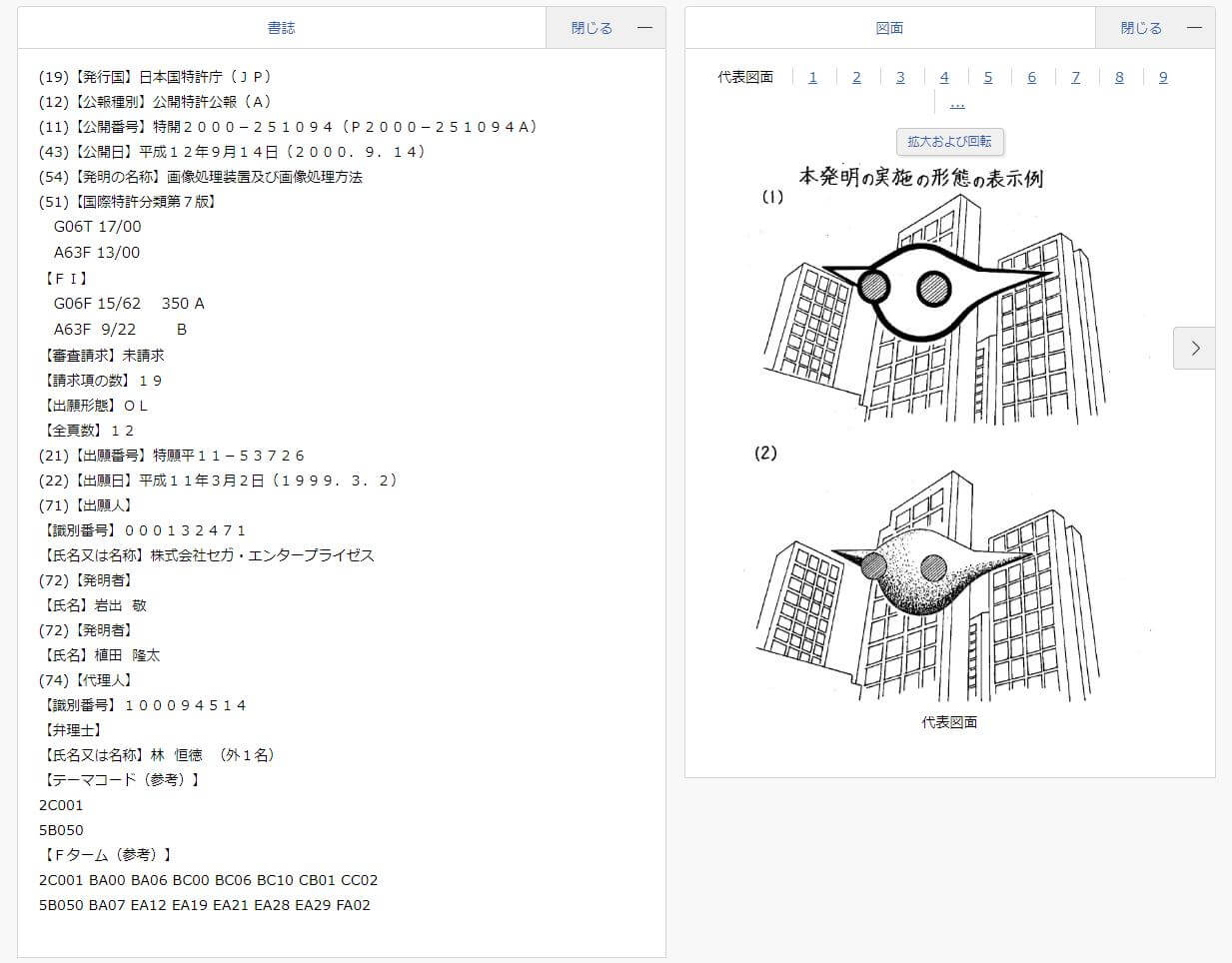「マンガディメンション」を発明し、ながれを変える
こうした岩出氏のエンジニアリング志向は、ゲーム史に大きなながれを生み出すことになる。アクションゲーム『ジェットセットラジオ』で用いられた「マンガディメンション」だ。本作はドリームキャストで2000年6月にリリースされ、その斬新な描画スタイルで大きな話題を呼んだ。
『ジェットセットラジオ』(2000) ©SEGA
当時、3DCGでセルルック表現を行うトゥーンシェーダはすでに知られていた。しかし、ドリームキャスト上でリアルタイムに表現するには処理負荷が高かった。そこでポリゴンのアウトラインを高速に描写する手法として考案されたのが本発明だ。マンガの輪郭線のように見えることから、「マンガディメンション」と名付けられた。
本発明の特許公開番号は「特開2000-251094」、正式名称が「画像処理装置及び画像処理方法」だ。岩出氏と並んで発明者に記されているのが植田隆太氏(現Yahoo! JAPAN)。岩出氏の2年後輩で、『ツヴァイ』、『AZEL』で岩出氏と共にエネミー制作を担当した。
足かけ3年にわたった『AZEL』がリリースされ、次のタイトルにアサインされることもない、空白の時期だった。それまでツールと格闘するように日々押し寄せてくる大量の技術をこなすだけで精一杯だった岩出氏にとって、ようやく落ち着いて自分のスキルを見直せる時期でもあった。
こうした中、岩出氏がCGツール上でエフェクトの周囲にアウトラインを表示させていたのを見て、植田氏はキャラクター表現に応用することを提案する。2人で続けた技術開発の成果が、本発明に結実する。
「僕は絵を描いたりするのが好きで、わりと大味なアーティスト気質なんですが、岩出さんは職人的なアーティストに近かったです。今でいうテクニカルアーティストのセミナーにも、すごく興味がある感じでした。そのため、2人で良い関係が築けていました」。
特許情報プラットフォームより
植田氏によれば、岩出氏は『ツヴァイ』のころからエフェクト的な表現に興味があったという。その背景にあるのが、前述したデザイナーとしてのこだわりだ。
「当時はテクスチャの解像度がすごく低い時代でした。それなのに、ものすごく高解像度で描き込んでいて。錆やネジや窓の人影まで描くんですよ。最終的に圧縮されて、ボケボケになったりするんですけどね。でも、そういった『誰にもわからないようなところ』までこだわっているところが、すごいなと。僕も影響を受けて、テクスチャの描き込みでけっこう遊んだりしました」。
もっとも、こうしたこだわりを実機上で表現するためには、テクニカルな知識が必要になる。中でもアートとエンジニアリングの関係性が求められるのがエフェクトだ。そこからエフェクトに興味が生まれたのではないか......というのが植田氏の見立てだ。
「エフェクトはキャラクターモデルの描画よりも、先端的な知識が活かしやすい分野です。描画エンジンをこう使えば、より綺麗に見せられるとか、いろんな裏ワザがあります。そもそも、そんなにポリゴンや処理負荷を、エフェクトに割けないですからね。しかもリアルタイムでやる必要がある。そうした特性と岩出さんの資質が、上手く合致していたんじゃないでしょうか」。
ともあれ、こうしてリリースされた『ジェットセットラジオ』は、ゲームグラフィックにトゥーンシェーダという大きなながれを生み出すことになる。前述の通り、トゥーンシェーダ自体はすでに知られた技術だったが、これをアクションゲームで大々的に使用したのは、本作が初めてだった。
「いち早く実現できたことで、国内外に『技術のセガ』をアピールできました。当時、ゲームハードの進化に合わせて3DゲームのCGがフォトリアルの方向に突き進み、画一的な進化を遂げていく中、表現としてまったくちがうものを追求したいという想いがありました」。
そこには、当時巨大な開発予算が投入され、リアル志向を追求していたアクション・アドベンチャー『シェンムー』シリーズとの差別化という側面もあったという。
実際に『ジェットセットラジオ』のリリース後、リアル一辺倒だったゲームグラフィックに、大きな揺り戻しが起きる。任天堂が『ゼルダの伝説 風のタクト』(2002)でトゥーンレンダリングを採用したことで、そのながれが強まった。
「この映像を見たとき、これからトゥーンシェーダはどんどん一般化されていくのだな、と確信をもちました」。
岩出氏と植田氏が発明した手法は、当時のドリームキャストでトゥーンシェーダを再現するアイデアだった。その後ハードの進化に伴い、各社で次々と独自のトゥーンシェーダが生み出されていく。
「トゥーンシェーダは単なるセルアニメの再現だけに留まらず、アーティスティックな表現(色・デザイン・演出など)を強められるため、ビジュアル面での個性が出しやすい特徴があります。映画『スパイダーマン:スパイダーバース』(2019)では、アメコミ的な演出と相まって独自のビジュアルスタイルを生み出しています。ゲームにおいても、これからいろいろな表現が出てくると思います」と植田氏は指摘する。
『龍が如く』(2005) ©SEGA
トゥーンシェーダはその後、2人のキャリアにも間接的につながっていく。『ジェットセットラジオ』リリース後、セガグループ内における開発子会社の統廃合を経て、岩出氏と植田氏は『龍が如く』チームに配属となる。現在までシリーズが続く、セガの看板タイトルのひとつだ。
もともと『龍が如く』は植田氏が提案した企画書がたたき台になった。こうした経緯から、『龍が如く』、『龍が如く2』(2006)では、植田氏がディレクターを務めている。任侠をテーマとしたことで、賛否両論が寄せられる中、発売されると関係者の予想を裏切る大ヒットとなった。
「実は『龍が如く』、『龍が如く2』ではトゥーンシェーダの技術を使い、当時のPS2で表示できる限界よりもポリゴン数を多く見せる工夫や、渋いライティング効果を実現しています。ゲーム自体はリアル系のビジュアルでしたが、これにより、ポリゴン臭さを軽減させられました。この技術を使っていなければ、もっと安っぽい3Dポリゴンゲームに見えていたと思います」。
このとき、岩出氏もまたエフェクトリーダーとして開発に関わったのは、前回紹介した通りだ。大ヒットシリーズ誕生の裏側に、『ジェットセットラジオ』からの系譜があったことは、もっと知られても良いだろう。