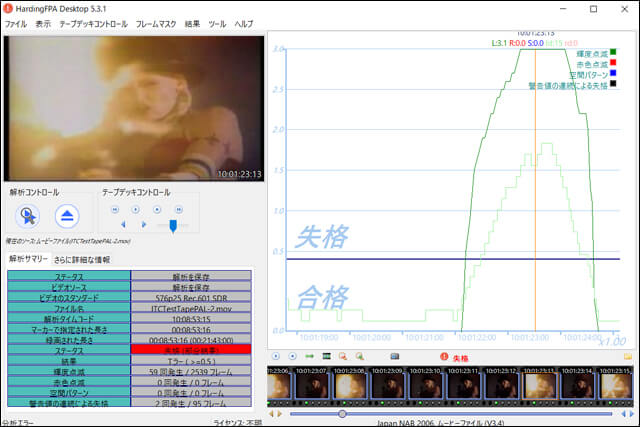長野オリンピックの映像ディレクターを経て解説委員に
CGW:そのままNHKに留まられる考え方もあったと思いますが、NHKを退局されるにあたり、何かきっかけはありましたか?
中谷:それも話すと長いんですが、1998年に長野オリンピックがありましたよね。東京オリンピックがあって、札幌オリンピックがあって、次に日本にオリンピックが来たら、絶対にオリンピックの映像演出をしたいと思っていたんです。開会式は自分の映像で始まるんだって、思い込んでいました。そうしたら長野でオリンピックが行われることになって。
長野オリンピック公式ホームページ
自分はNHKにいるんだけど、何とかして長野オリンピックの映像をつくりたい、どうしたら良いんだろう。「自分が開会式の映像演出をする」ことをゴールに、必要な要件を逆引きしていった結果、「NHKの映像ディレクターであること」を利用したらいいと思い至りました。
CGW:はいはい。
中谷:それで、いろんなつてを頼って、日本オリンピック委員会(JOC)に関係のあるNHKの偉い人に「映像をつくるにはどうしたらいいんでしょうか」と聞いたら、「わからないけど、オリンピック放送機構っていう、オリンピックの映像を管轄している機構にいろんな放送局の人が集まって、NHKの人が中心になってやっているはずだよ」と言われたんですよ。「あ、良いこと聞いちゃった」って。
それでまたまた飛び込みで、いろんなことをすっ飛ばして、当時オリンピック放送機構にいた、NHK出身の偉い人に相談したんです。そうしたら「今それをいろいろ考えていて、誰に映像演出を頼むか、非常に悩んでいると。僕の立場では中谷君にやってくれとは言えない。世の中にはオリンピックの映像をつくりたい人がいっぱいいるからね。ついては、中谷君に映像演出を頼める人を何人かラインアップほしい」と言われました。そこで8人ラインアップした中に、自分も入れたんです。
もちろん、いろいろ著名陣を並べましたよ。映画『東京オリンピック』にならって、当時有名だった映画監督も候補に挙げました。その上で「僕はその中でも一番、放送ということをわかっていて、誰よりもニーズに答えられると思う」とプレゼンテーションしたんです。そうしたら、中谷君に映像ディレクターを頼もうって、選ばれたんですよ。でも、それを上司に言ったら「ダメだ」って言われて。
CGW:ええ、なんでですか?
中谷:NHKの職員だから。民放も含めて、世界中に発信する映像だから、NHKの職員はダメだと言われて。「だったら辞めてやる」といったら、ちょっと待てと。出向してつくれば良いということになって。見事、長野オリンピックの映像に関することは全部、僕がつくらせていただけることになりました。
CGW:強キャラですね......。
中谷:その上JOCのデザイン委員にしていただいて、長野オリンピックのデザイン関連の仕事をさせていただきました。実際のデザインはアメリカのデザイン会社が行なっていますが、デザイン監修を担当しています。
そんなふうに長野オリンピックは思い出が深い大会でした。世界中に発信される映像を全部ディレクションさせていただいて、そこでも3DCGを活用しました。当時、東京・青山にあったPDIC(ピーディック)というCG制作会社のスタッフに総動員していただき、私のイメージを映像化してもらいました。
CGW:もう、今から20年以上も前の話ですね。でも、40代半ばでオリンピックの映像演出までやったら、やりたいことは全部、やり尽くした感じでしょう。
中谷:そうなんですよ。そうしたら、オリンピックが終わった瞬間にですね。「中谷君、君はね、もう散々好きなことを、自由にやっただろう。ついてはNHKにもっと貢献しなさい」って言われて。それで解説委員に任命されてしまいました。
CGW:コンテンツの制作ではなくて、説明する方なんですね。
中谷:ただ、解説委員だけだと、もやもやしてしまって。影でいろんな人を巻き込んで、やっぱり番組をつくりはじめました。
その頃から若いクリエイターを発掘して育てたいという思いが強くなっていって。それで『デジスタ』を1999年に立ち上げて、2000年に放送開始したんです。番組で様々な映像アーティストやメディアアーティストを発掘して、世に発信することができました。この番組から、幾多のトップクリエイターを育てることができて、非常に思い出深いですね。
NHKアーカイブスより
www.nhk.or.jp/archives/digital/search/freeword/#keyword=%E3%83%87%E3%82%B8%E3%82%B9%E3%82%BF
CGW:怒られませんでした?
中谷:怒られましたよ。何をやってるんだって言われて。でも企画だけじゃなくて、自分が出演すれば、解説委員だから良いってことになったんです。それで自分で番組をつくって、自分で出演するスタイルを確立しました。解説委員として番組を自らナビゲートをしたのは、そうした背景からです。いま自分が司会をしているWeb番組『木曜新美術館』も、そうした思いを受け継いでやっていますね。
『木曜新美術館』
技術だけでなく演出力をもったクリエイターを育てたい
CGW:その一方で、様々な大学で特任教授(非常勤)をされていますよね。教育にご興味があるんでしょうか?
中谷:ありますね。ずっと藝大受験の予備校で先生をやったり、多摩美術大学で先生をやったり、若い頃から機会を見つけて、いろいろな学校で芸術系の先生をしています。後進を育てたいんですね。
CGW:こういう言い方をするのもなんですが、常勤はともかく非常勤だと、講師業は労力の割に報われない面があるかと思います。どのあたりが魅力なんでしょうか?
中谷:生活はNHKの職員でしたので、ある程度は保証されていました。有給を使って講師業をしても、仕事に支障が出ない程度であれば、許されていました。実際NHKには、そういう人が多いんですよ。そのまま退局して、大学の先生になったりして。僕も同じキャリアですよね。
それに、非常勤だからこそ面白いってのもあったんですよ。常勤の先生は教授会をはじめ、様々な会議に出たり、業務を行なったりする必要がありますが、特任や非常勤だと、基本的には教えるだけですからね。今やっている京都大学大学院の特任教授もそうで、結構長く勤めていますね。
CGW:教えるという点では、解説委員と一緒ですね。解説委員を任命されたのも、何か才能を見出されたんでしょうか? 人に教えたり、説明したりするのが上手いという......。
中谷:どうでしょうか? もしかしたら、あったかもしれませんね。NHK時代からキーパーソンが必ず出現して、応援してくれたんです。解説委員になったときも、当時の解説委員長がとても良い人で、「中谷、お前は好きにやれ」と言ってくれました。
CGW:その後、2018年にNHKを退局されて、2020年4月から東京国際工科専門職大学の教授になられましたね。こちらは特任ではなく常勤の教員です。
中谷:本学のことは専修大学の文学部で教授をされている、福富忠和さんに教えていただきました。福富さんとは広告をやってる時代からの付き合いで、ずっと僕が教育に興味があることをご存じでした。そこで「中谷さんさあ、こういう話があるんだけど。専門職大学が新しくできるんだよね」って教えてもらえたんです。
僕は常勤でやるなら、新設校でやりたいと思っていました。もう大学の路線が決まっていたら、面白くない。新設校だったら、やりたいと言ったら、すぐに紹介してくれて。
東京国際工科専門職大学の開学発表会でパネルディスカッションのモデレータを務める中谷氏(左端)
CGW:専門職大学では、どんな授業をされているんですか。
中谷:今は1年生の前期で「企画発想法」の講義をやっていて、後期は「コミュニケーションと記号論」を担当します。どちらも演出に係わることなんですよ。
CGW:前者はアイデアのつくり方、後者はアイデアの伝え方ですね。
中谷:そうなんです。だから、本当に自分が教えたかったことの、ど真ん中で。ずっと番組制作を通して、自分がやってきたことなので、すごく楽しい。まさか、この科目を2つ受けもたせていただけるとは思わなかったので、この学校でしか学べない講義にしたいと思っています。
CGW:どんな学生を育てていきたいですか?
中谷:ゲーム業界でも映像業界でも、出口はいろいろだと思うんですが、やっぱり企画・演出力がある人間を育てたいですね。
CGW:演出力があるというのは、具体的にいうと?
中谷:技術偏重ではないクリエイターということですね。どうしても3DCGやゲームは、そのままでは技術偏重になってしまって、コンテンツとしての伸びが悪くなってしまうので。日本の教育が欧米に遅れているのは、そこなんですよね。実際にアルスエレクトロニカをはじめ、フランスの展示会の取材などを通して、現地の学校で演出力をものすごく教えていることを痛感しました。
実際、演出力の重要性は、これからの映像制作者には決して欠かすことができないと思います。この学校では、ゲームとかCGとか、エンターテインメントコンテンツをつくる人たちを育てるということなので、技術だけではない、企画・演出面についてしっかりと教えていきたいと思っています。
CGW:演出には「人の感情を、ある意図をもって動かす手法」という意味合いがありますね。どちらかというとアートではなく、デザインの領域の話です。実際にアートには、わかる人にだけわかれば良い、という側面がありますよね。一方で中谷さんは藝大のデザイン科という、アートとデザインの中間的な場所で学ばれました。アートとデザインの接点とは何でしょうか?
中谷:デザインの中にもアートがあるし、アートの中にもデザインが必要です。お互いに関連性があるんですよ。僕はグッドデザイン賞で20年以上も審査員を務めてきて、デザインの本質を自分でもわかってるつもりでいます。そうしたものを映像の世界にもち込むことが、すごく重要だと思っていて。まさにこれって、映像の記号化なんですね。これを講義で教えていきたいと思っています。
CGW:作家が作品にこめた価値や意味が、技術偏重だと上手く伝わらないことがあるんですね。
中谷:そうですね。若い人のクリエーションを見てても、記号化の基本的な意味を理解しないでつくっている場合が多くて。だからすごく表面的なんですよね。これじゃいかんなと、番組をずっとやっていて、思っていました。どうしてもアプリケーションをさわっていると、そっちが楽しくなってしまって。こんなこともできるんだ、あんなこともできるんだって、盛りまくった結果、みんな表面が一緒になってしまうという......。何ができるかではなくて、どんなふうに見た人に共感をもってもらえるかがポイントなので。
CGW:記号論という学問領域には、長い学問の蓄積があって、体系化されています。そこに最新のテクノロジーが組み合わさることで、さらなるアップデートが期待できそうですね。
中谷:そうですね。自分自身も記号化について、広告時代からずっと考えて、研究してきました。実際、広告は記号論のかたまりですからね。また、記号論を展開するうえで、メディアリテラシーという考え方があります。何を伝え、どう読み取ってもらうか。僕は、それをNHKの番組制作で、ずっと追求していました。こんなふうに仕事を進めるうえで、どんどん記号論の存在が大きくなっていったんです。
記号論を演出の中で、いかに上手く落とし込んでいくか。これは映画監督も同じですよね。そんなふうに記号論をベースとした、映画監督的な志向性を、エンターテインメントコンテンツのクリエイターであれば、もっていてほしい。
CGW:これからの授業が楽しみですね。
中谷:がんばります。
モーション・グラフィックス'98
CGW:お話を伺ってきて、中谷さんのキャリアの振れ幅がたいへん興味深いですね。特に、シルクスクリーンという静止画の世界から、映像という動きのある世界に移行された理由について、もう少し教えてください。カメラマンが典型的ですが、スチルとムービーは似て非なる世界で、どちらかに分かれる傾向がありますよね。そこを軽く飛び越えられたのが面白くて。
中谷:シルクスクリーンは複製媒体ですよね。複製媒体という意味では、雑誌も新聞もそうです。僕も学生時代は基本的に四角い画面の中で、モノをどういう風に配置して、メッセージを伝えるか、それをグラフィックデザインという世界で追求していました。それがあるとき、動き出したんです。それがモーショングラフィックスです。モーション(動き)+グラフィックス(図形、文字)という意味ですね。
モーショングラフィックスについて初めて知ったのは、MITメディアラボ時代でした。当時アメリカでモーショングラフィックスを使って、映画のオープニングタイトルなどをつくっている映像クリエイターがいました。後に映画『セブン』で有名になるカイル・クーパーなどですね。
それで帰国後にモーショングラフィックスを日本で紹介したいと思って、ナガオカケンメイさんと、菱川勢一さんと、3人でモーショングラフィックスの展覧会をやったんです。そこからすっかり、グラフィックが動くと格好良いという価値観に転身しました。
CGW:なるほど、ミッシングリングがつながりました。
中谷:当時は長野オリンピックとも絡んでいたので、スポーツで人体が描く軌跡を線で動かすといった表現に取り組みました。線で動くだけで、元になったスポーツを十分に感じさせるような表現がつくれるんじゃないかと思ったんです。そんなふうにモーショングラフィックスの研究をして、いろんなところで展覧会をしたら、結構人気が出ました。あれからモーショングラフィックスのブームが起きましたね。
CGW:他に若いクリエイターに対してメッセージがあればお願いします。
中谷:『デジスタ』のときに、若い人たちに新しい映像表現について教えたいと思って、書籍『新しい美術はじめましょ。』という本を執筆しました。そこで「3DCGも新しい美術なんだよ」っていう思いをこめたんです。同じように、若い人たちには新しい美術に取り組んでほしいと思っているんです。
CGW:今や、小学生でもゲームがつくれる時代ですからね。技術開発によって新しい表現が生まれても、技術がコモディティ化していくと、それだけでは差別化ができなくなっていきます。
中谷:そうなんですよね。そこで問われるのが演出力です。逆に枯れた技術でも、演出力がつくと、すごく面白くなっていくので。イノベーティブな演出力をつけてほしいなと思います。