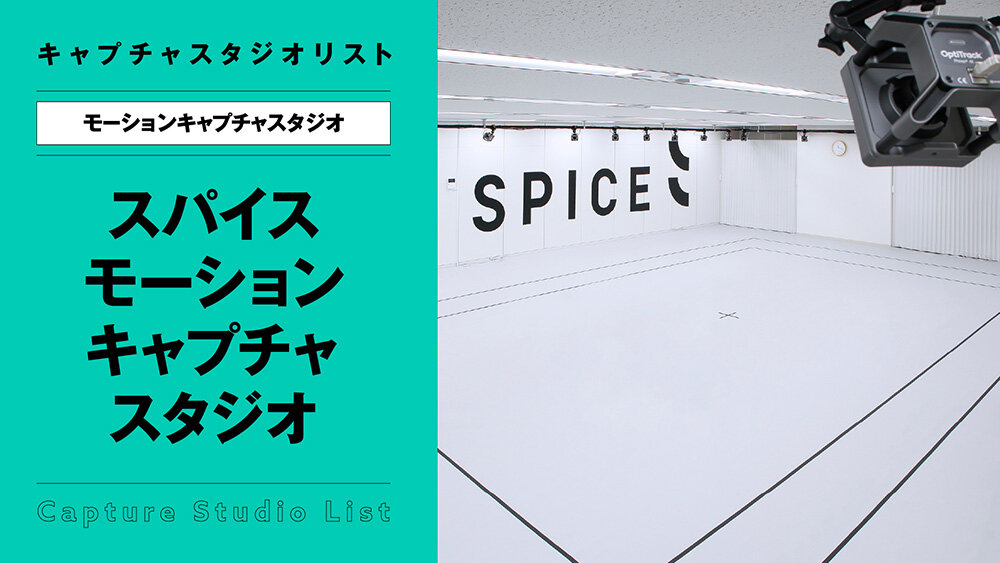プランナーとデザイナー、双方の対立を通して
さて、ここで時計の針を『AZEL-パンツァードラグーンRPG-(以下、AZEL)』開発の頃に戻して、またちがった視点から岩出氏の仕事ぶりをふり返ってみよう。
『AZEL』、『ハンドレッドソード』、『オルタ』と、3作にわたって岩出氏と開発を行いつつ、良くも悪くもぶつかってしまったプランナーがいる。向山彰彦氏(現フリーランス)だ。
1993年セガに入社し、『聖魔伝説3×3EYES MCD』(1993/メガCD)、『魔法戦士レイアース』(1995/セガサターン)、『サクラ大戦』(1996/セガサターン)と、コンソールでRPG要素のあるゲーム開発に携わってきた向山氏。
その経験を買われて、『AZEL』の開発途中からバトルパートに参加することになった。すると、開発スタイルのちがいに驚かされたという。
『AZEL-パンツァードラグーンRPG-』 ©SEGA
「それまでのチームでは企画が中心になって筋道を立てて、そこにデザイナーがビジュアル面で肉付けをしていくようなつくり方でした。少なくとも『サクラ大戦』は、そうしたつくり方をしていました」。
「しかし、『AZEL』ではデザイナーの発言力が強かったんですよ。そもそも『パンツァードラグーン』シリーズはゲームメカニクスもさることながら、ビジュアルが魅力のゲームでしたからね。アーケードから来た人が多いこともあって、デザイナーが物申す的な風潮が強いチームでした」。
前任者との入れ替わりでチームに合流した向山氏。そこで感じたのはデザイナー側とプログラマー側との、思惑のちがいだ。
当時、日本のゲームシーンは『FF』シリーズに代表される、大作RPGが高い人気を誇っていた。アクションゲーム中心でRPGに弱いとされるセガサターンで、『AZEL』の期待度は大きかった。「やった、RPGみたいなすごい画が出せる」。当時、チーム内でこうした声をデザイナー側から聞いた......向山氏はこのように語る。
その一方で、プログラマー側ではバトルにシューティング要素を加えたがっていた。過去2作が3Dシューティングで、高い評価を受けていたからだ。そのためのノウハウも豊富だった。ただ、3DシューティングとコマンドRPGをいかに融合させるかについては、誰もが未知数だった。
「もっと綺麗な画を見せたいデザイナー側と、もっとシューティング風にしたいプログラマー側とで、どのような落としどころをつけるか......。どうしたら良いんだっていうのが『AZEL』で、その象徴ともいえるのがバトルでした。最終的には良い感じの落としどころに落ち着いたのではないかと思いますが、とにかく形にするのが大変でしたね」。
この難題に共に取り組んだのが、エネミーをデザインした岩出氏と、メインバトルプログラマーの二川目氏だ。作業はつくり直しの連続で、次第に関係がギスギスしていった。
こうした雰囲気の中でも、岩出氏がデザイナーの職分を超えてバトルシステムに口を出してくることに驚かされたという。必死になって考えているのに、イラッとしたことも多かったとのこと。
もっとも、今にして思えば、こうしたプログラマー・デザイナー・プランナー間の衝突があったからこそ、『AZEL』はユニークなRPGになったのではないかと向山氏は語る。
『AZEL-パンツァードラグーンRPG-』 ©SEGA
象徴的だったのがバトル時のUI表現だ。『AZEL』では画面下側に必要に応じてレーダーや敵味方のヒットポイントが表示され、バトルが終了すると消える仕様になっている。また、ウィンドウも他のRPGのように長方形ではなく、世界観に合わせた不規則な形状となっている。
もっとも、開発途中のUIはこれとはちがった。画面の一定エリアがUIで埋まり、背景が隠れてしまう表示だったのだ。
これに異を唱えたのが岩出氏だった。「ベタッと表示するだけだと圧迫感があるので、形を工夫して背景を見せたいと言ってきました。UI担当の企画と岩出君との間ですごくもめた記憶がありますが、最終的には操作性、視認性、デザイン性を両立させたものになりました」。
作業が遅れ、チームの雰囲気が悪くなる中、他のデザイナーだったらあそこまで強く主張してくることはなかったかもしれないと、向山氏はふり返る。もっとも、だからこそ『AZEL』のバトルUIは機能的で、世界観にも則したものになった。
ただし、当時はまだキャラクターを実機上に表示させるだけで負担が大きかった時代だ。これがゲームUIともなると、その負荷が倍増する(だからこそ当時のゲームUIは画一的で、操作性に乏しいものが多かったわけだが......)。
また、岩出氏もゲーム全体のUIにツッコミを入れたわけではない。エネミー担当だったこともあり、バトルシーンのUIであれば自分のテリトリーということで、アイデアを出したのだ。
「おかげで、結果的に良いものになったとは思います。ただ、当時は『うるせえな』というのが本音でした」。