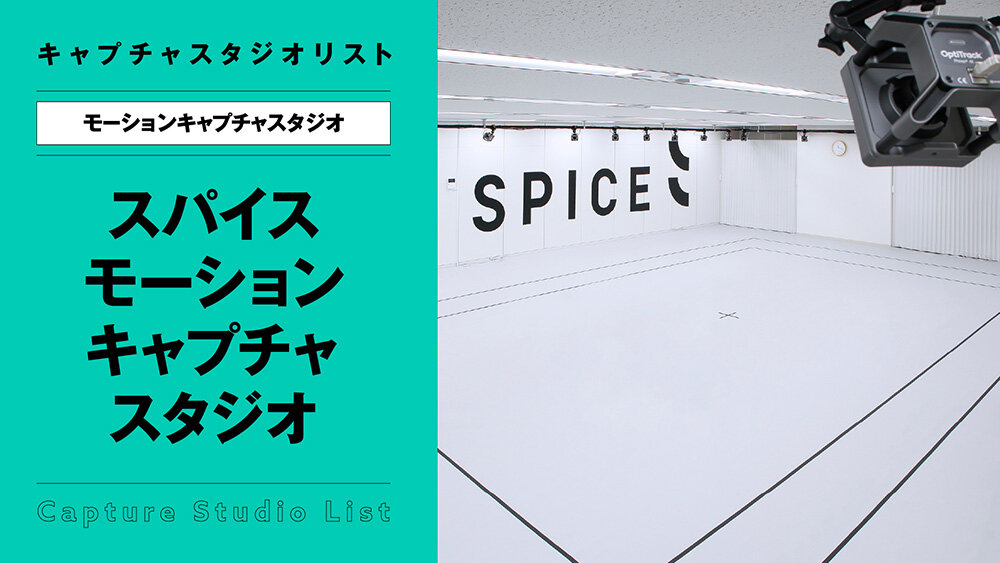『ハンドレッドソード』を成立させるための二者択一
これに対してプランナーとデザイナーでせめぎ合いが発生したのが『ハンドレッドソード』(2001)だ。本作は当時としては珍しいリアルタイムストラテジー(RTS)で、ドリームキャストの通信機能を活かして、4人までオンライン対戦ができた。
向山氏はチーフプランナーで、岩出氏はチーフアーティスト。チーフプログラマーは前述の厚 孝氏が担当している。余談だが、このチーム構成は『オルタ』でも引き継がれることになる。
また、岩出氏は『オルタ』後に『龍が如く』シリーズの起ち上げに参加。厚氏もシリーズがPS3に移行するタイミングで、2007年より参画する。その後、内製ゲームエンジンのドラゴンエンジンで開発責任者を務めるなど、長きにわたって関係が続くことになる。
本取材について、厚氏はメールで次のようなコメントを寄せた。
「岩出さんとは、『ハンドレッドソード』、『パンツァードラグーン オルタ』の2タイトルにわたり、プログラマーとデザイナーのチーフという立場で、約4年の期間共に仕事をしてきました。近年では作業の専業化が進み、直接やりとりする機会は減りましたが、20年にわたってずっと同部署でお互いに信頼できる同僚として頼りにしてきました」。
『ハンドレッドソード』 ©SEGA
閑話休題。当時PCゲームでヒットしていた『Age of Empires』に影響を受けて始まった本作。開発は技術検証とアートワークが先行していた。
再び前任者の引き継ぎでチームに合流した向山氏は、状況を聞いて頭を抱えることになる。RTSで4人対戦ゲームなのに、キャラクターが20体程度しか出せないというのだ。これではゲームにならないと、「せめて100体は出せるようにしてくれ」と主張したという。これが『ハンドレッドソード』というタイトルの由来だ。
なぜキャラクターが20体しか出せなかったのか。そこには2つの要因があった。第一にWindows CEをベースにMicrosoftが開発したOS、開発コードネーム「Dragon」 の存在があった。PCとの親和性が高く、高性能だったが、処理が重かったのだ。
もっとも、Dragonの採用はプログラマー側からの要求によるものだった。チーフプログラマーの厚氏が、セガでPCゲーム開発を行なっていたPC開発部の出身で、Windowsでのゲーム開発に慣れていたからだ。オンラインで4人対戦を実現させる上でも、Dragonの採用は必須だった。
もうひとつの要因がトゥーンシェーダだ。ポリゴンのエッジを強調するマンガディメンションを、岩出氏は本作で採用するよう主張した。前述の通り、本技術は植田氏と共に岩出氏が発明したものだ。もっとも、これによって処理負荷が高まり、キャラクターの数が出せないおそれがあった。
当時の事情を厚氏は次のようにコメントしている。
「岩出さん自身は『ジェットセットラジオ』には参加していなかったので、自分自身で手がけるプロジェクトにマンガディメンションを導入したいと考えていたようです。実際、『ハンドレッドソード』の開発初期は、エッジ付きのトゥーンシェードで進められていました。
ビジュアル的にはキャラクターの選択がわかりやすいなどのメリットもあり、岩出さんは強く採用を主張していましたが、ドリームキャストではエッジの処理にかかる負荷が許容できず、結局は不採用になったことを覚えています」。
もっとも、実態はもう少し複雑だ。
向山氏にすれば、RTSなのにキャラクターが20体しか出せないのはあり得ない。一方でDragonの採用は外せない。だとしたら、描画負荷を減らすしかない。そのためにはトゥーンシェーダを諦めることと、キャラクター1体あたりのポリゴン数を減らす必要があった。
しかし、岩出氏からすれば、どちらもあり得ない選択だった。ポリゴン数を減らすと、それだけキャラクターの魅力が減る。マンガディメンションも自分が発明したものだ。そのため、岩出氏は向山氏にこう告げた。
「20体で成立するゲームシステムを考えてください」。
最終的に向山氏は「トゥーンシェーダを不採用にする」、「キャラクター1体あたりのポリゴン数を減らす」ことを決断した。アドベンチャーパートで前半の主人公が騎馬民族という設定にもかかわらず、馬が四本足ではなく、二本足で鳥のような形状をしているのもこれが理由だ。足の数を減らさざるを得ないほど、処理負荷の軽減が求められたのだ。
一方で岩出氏は頑として反対していた。「トゥーンシェーダを採用しても処理負荷は上がりません」と、岩出氏自らプレゼンしたほどだ。
そこで向山氏は他のデザイナーに依頼してサンプルデータをつくってもらうなど、一種の裏工作をしたという。騎兵の足を4本から2本にしたのも、このときだ。「こんな風に岩出君には涙を呑んでもらいました」。
もっとも、それまでは強行に反対していたものの、一度そのように方針が決まると、黙々と仕事をしてくれたと、向山氏は語る。「本人としては忸怩たるものがあったかもしれませんが、結果的に少ないポリゴン数ながら映える画をつくってくれたのではないでしょうか」。
『ハンドレッドソード』 ©SEGA
実はこのエピソードにはもう一幕ある。処理負荷を下げるため、いっそのこと3Dではなく2Dゲームにしてはどうか、という話が飛び出したのだ。
これに対して岩出氏は「自分たちは3Dゲームしかつくったことがない。どうしても2Dゲームにするなら、デザイナーを全員入れ替えてほしい」と突っぱねたのだという。これには向山氏が折れるしかなかった。
「結局3Dで何とかする方法を考えることになりました。デザイナーとしての矜持だったのでしょうね」。
プランナーとデザイナーの対立は本開発でも続いた。UIの修正はそのひとつだ。
テストプレイを続けるうちに、レーダーの表現などで、より視認性を高める必要があるのではないか......プランナー側からそうした声が上がった。しかし、デザイナー側からすれば、仕様通りに納品しているのに手戻りが発生することについて、釈然としないものがあった。ビジュアル的にも満足がいくものだという自負があった。
「UI担当の企画と朝までかかって説得したんですが、結局ダメでした。企画側としては、RTSだし、視認性が良い方が遊びやすいし、そのためにはこうすべきだと、ロジックで説明しているわけです。しかし、岩出君にしてみれば、またちがう考えがあるわけですよ。黙ってしまって、てこでも動きませんでした。結局、こちらが折れました」。
向山氏は「この件について、どちらが良いのか今となっては判断がつかない」と語る。企画の言うことをハイハイと聞くだけが、デザイナーの仕事ではないからだ。デザイナー側からすれば、こうした修正指示はプランナーの無茶ぶりにも聞こえる。それに対して部下を守ることもチーフデザイナーの務めだ。
実際、岩出氏は部下に対して説明をしっかりと行い、スケジュールを守って仕事を進めるタイプのデザイナーだった。岩出氏が多くの人に慕われた理由のひとつには、こうした仕事の進め方もあった。
当時について厚氏も、「昔は岩のように頑固なところがあって、納得のいかないことがあるとミーティングが終わらないことが良くありました。結婚された頃からだいぶ柔軟になられました。面倒なまとめ作業もマメに行なってくれる、職務に忠実な方でした」とコメントを寄せている。