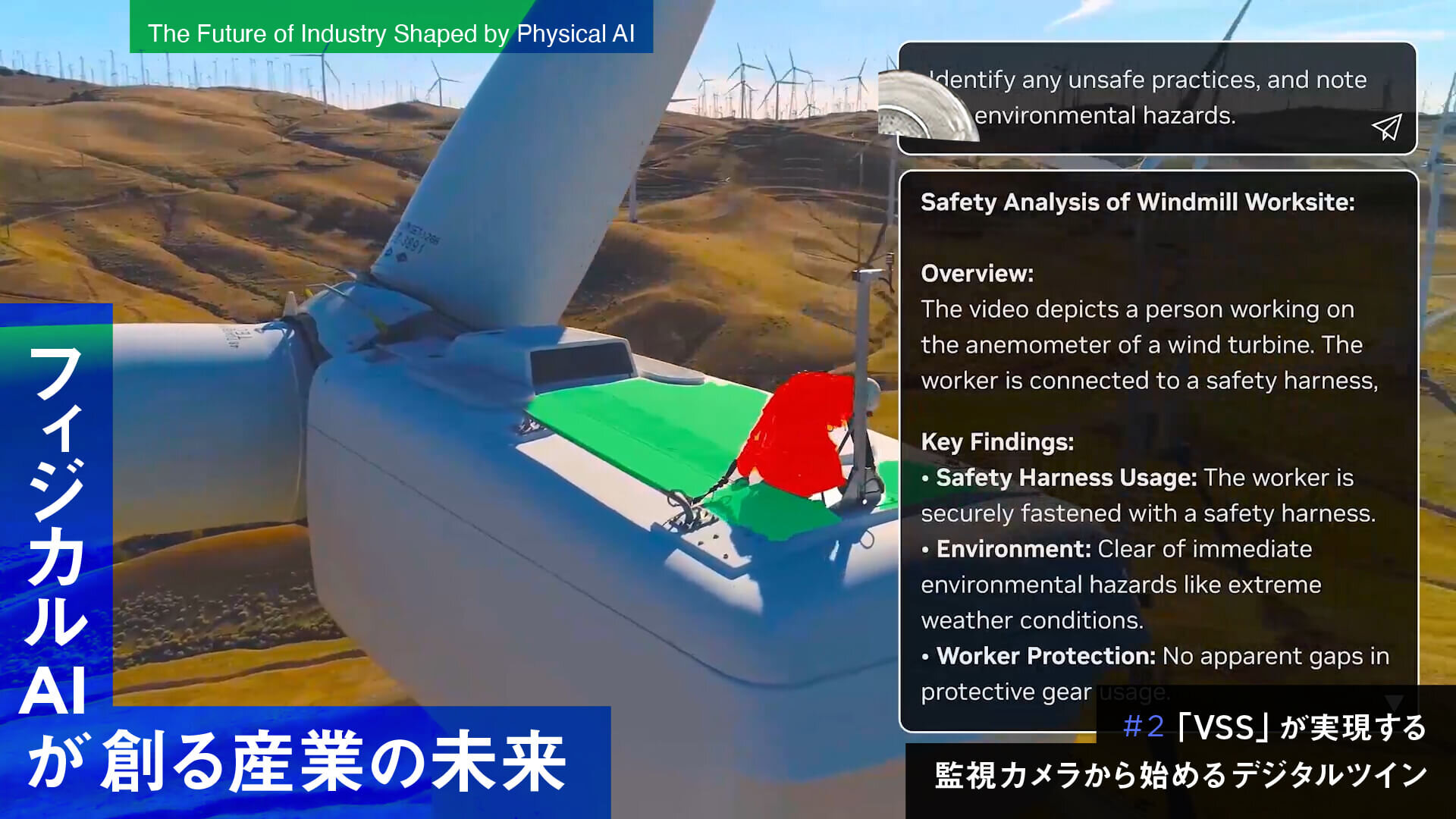ゲーム会社ならではの知見で体験の質を上げる
ここまでは、本コンテンツにおける企画面での工夫について紹介してきたが、ここからは制作面での工夫について取り上げていく。まずは『FALKEN VIRTUAL GARAGE』の開発を担当したグランディングの話から紹介していこう。同社は東京・京都・福岡にスタジオを構える老舗ゲーム開発会社だ。本作では、代表取締役CEOを務める二木幸生氏によるディレクションの下、福岡スタジオのメンバーが開発を担当することとなった。
ここで、改めて『FALKEN VIRTUAL GARAGE』の概要について整理しよう。クライアントの要望は、プレミアムタイヤの「AZENIS FK510」、VAN向けの「W11」、オールラウンドタイプ4×4タイヤの「WILDPEAK A/T3W」で、それぞれの特徴を体験者にしっかりと伝えることだ。その上で採用された方法論が、Oculus Quest 2でウォークスルー型のVRコンテンツを制作するというものだ。専用コントローラを両手に握らせ、バーチャルガレージの中を実際に歩かせながら、体験者にタイヤの装着を疑似体験させるというわけだ。コンテンツの体験時間は約5分となる。
体験シナリオは次のようなものだ。はじめに体験者に3種類のタイヤから1つを選ばせ、タイヤの選択を通してビジュアルや音声でタイヤの説明が行われる。その後、体験者がふり向くと目の前にバーチャルガレージが広がり、タイヤの種類に合った実寸大の自動車が表示される。体験者がVR内で4つのタイヤを持ち運び自動車に装着すると、クリアデモが再生される。クリアデモはタイヤと自動車の特性に合わせて異なり、タイヤの特性が体験的に理解できるという立て付けだ。クリアデモを含め、全てがリアルタイムで表現されている。
ちなみに、企画自体はOculus Quest向けのVRコンテンツとして立てられた。もっとも、Oculus Quest 2の発売予定がすでに明らかになっていたこともあり、開発の早い段階からOculus Quest 2にデバイスが切り替えられたという。過去に自動車ディーラー向けVRコンテンツ開発の経験があり、本作でもVRスーパーバイザーとして参加した柴崎孝仁氏が、公開情報を基に全体のポリゴン数などを算出。その内容に基づいて開発がスタートし、最適化などを踏まえて完成にいたっている。
コンテンツの内容自体は、生田氏の作成した企画案と絵コンテでおおむね決まっていた。グランディングに求められたものは、これを基に実際のVRコンテンツを開発することと、ゲーム会社ならではのノウハウを投入して体験の質を上げることだった。実際の開発期間は約3ヶ月弱となる。
まず提案されたのが、チュートリアルの追加だ。本作では両手に専用コントローラを持ち、タイヤを疑似的に持ち運ぶ操作が求められる。もっとも、大半の人にとってVRで何かを持つという行為は初めての体験である。これとは別に生田氏らから、FALKENのロゴをコンテンツ内で表示させたいという相談があった。
そこで二木氏から、FALKENのロゴをつくる行為自体をチュートリアルにするというアイデアが提案された。コンテンツが始まると、床から「L」の文字が描かれた箱とテーブルがせり上がってくる。箱を掴んでテーブルの空いたスペースに載せると、「FALKEN」のロゴが完成するというしくみだ。これにより、体験者は自然に専用コントローラの使い方を理解することができる。複数の課題を一度に解決する、ゲーム業界ならではの発想だろう(※4)。
※4:「アイデアというのは複数の問題を一気に解決するものである」。任天堂の宮本茂氏の名言の1つとして知られている
▲床に置かれた箱を実際に持ち上げ、テーブルの上に並べることでロゴが完成する。体験者に、チュートリアルを通してFALKENのロゴを印象付けるしくみだ
CADデータを基に複数サイズのタイヤを制作
話をタイヤの制作に移そう。モデリングは住友ゴムから提供されたCADデータをMayaにインポートし、リダクションすることで行われた。本作でアートディレクションと背景制作を担当した江崎正典氏は、「Mayaにインポートした時点で、タイヤ1つあたり80~100万ポリゴンほどあったのですが、Mayaのオートリダクション機能で20~30万ポリゴンまで削減し、そこから手作業でコツコツと作業を進めました。最適化を進める上でLOD(Level of Detail)が必要になり、最終的に約5万ポリゴン、約1万5,000ポリゴン、約1万ポリゴンと3段階のモデルをつくりました」と話す。
本作においてタイヤは「持ち運ぶ」という行為を通して、VRプレゼンスの中核となる存在だ。そのためには形状もさることながら、ゴムの質感表現が課題となる。もっとも、Substance PainterでPBRに対応したテクスチャを制作したのみで、シェーダなどは作成しなかったという。江崎氏は「予想以上に上手くいきました。逆に言えば、MayaとPhotoshopだけでは大変だったと思います」とふり返る。それでもタイヤの3DCGデータを仕上げるだけで、アーティストが付きっきりで2ヶ月程度かかったとのこと。「最後までチクチクと手直しをしていました」(江崎氏)。
▲ゴムの匂いすら感じられるタイヤの質感。テクスチャ制作はSubstance Painterのみで、Substance Designerは使用されていない。これに対して「タイヤが主役で自動車は脇役」というコンセプトの下、自動車の3DCGモデルはシンプルにつくられている。ポリゴン数も1万ポリゴン前後で、特殊なシェーダなども使用されていない。それでもタイヤを装着する軸受け部分については、ディスクブレーキの形状などがリアルに表現されている。開発チームの中で唯一、自動車に詳しい濱口氏のチェックの下、実車を参考にモデリングされた
コンテンツの実装はUnity上で行われている。メインプログラムを担当した園田智之氏は、「特別なことは何もしておらず、せいぜいOculusが提供しているOculus Integration Pluginを使った程度です。デバイスがOculus QuestからOculus Quest 2に変わったことでスペックが向上したことで、助けられた点もあります。後は動作を軽くするためにポリゴン数の異なるタイヤをつくってもらい、状況に合わせて切り替えたり、影のクオリティを少し落としたりしました」と語った。
他にリアル展示会が開催された場合、会場ブースで状況が許す限りコンテンツが連続再生されるという事態が想定された。そのため、メモリがリークしないようガベージコレクションに配慮したプログラムを構築。最適化で役立ったのが、Oculusが提供するOVR Metrics Toolだ。パフォーマンスがリアルタイムに実機上で確認できるツールで、これをプログラマー側で常駐させ、随時チェックしながら開発を進めたという。
タイヤの重さを表現する上で重要な役割を果たしたのは柴崎氏だ。はじめにタイヤは常に両手で持たなければならず、片手では落ちてしまうようにした。その上で、前述したように左右のコントローラの動きに対して、タイヤの移動が少し遅れるようにした。コントローラの位置とVR空間上の手の位置が多少ズレても違和感がないようコードを書いたという。空間上のコントローラの位置を正確にトレースするだけでは、かえって体験の質が下がってしまう。これもまた、ゲーム業界ならではの「気配り」というわけだ。
▲取材はグランディング東京スタジオと福岡スタジオをオンラインで結んで実施された。画面は柴田孝仁氏(左上)、濱口隆ノ助氏(右上)、園田智之氏(左下)、江崎正典氏(右下)
こうした気配りの有無は、VRコンテンツの体験で大きな役割を果たす。例えば、本作ではUnityのシーンファイルが1つしか存在せず、複数のシーンファイルをつくるとシーンファイルを読み込む際に切れ目が生じてしまう。その結果、プレゼンスの低下を招く恐れがあるのだ。そのため、バーチャルガレージとクリアデモでシーンファイルを分けることなく、タイムライン上でクリアデモを表現するといったシームレスな体験を保つ上で、細かい工夫がなされている。
バーチャルガレージでタイヤを装着する際、車体の中に頭部を入れると視界が暗転するという演出もそうした気配りの1つだ。VRコンテンツでは、体験者がどのような動作をするか予測がつかない。仮に車体の中に頭部を入れられても、車体の内側が覗けないようにすることで、体験が醒めてしまうことを防いでいるのだ。
また、体験中に移動できる範囲を体験者に自然に伝えるための工夫もなされている。本作では、本来開催される予定だったリアル展示会のブースサイズに合わせて、4×6mの移動空間が設定されている。自分の足でVR空間を歩いてもらうため、チュートリアルのロゴ制作からタイヤの選択、バーチャルガレージでの作業まで巧みに導線が設定されている。
もっとも、4×6mの全体を移動できるわけではなく、移動可能な範囲をそれよりひと回り小さく設定している。Oculus Quest 2の仕様で、移動可能なスペースに近づくと「ガーディアン」と呼ばれる境界線が表示されるためだ。これは体験者に危険を通知するためのしくみだが、コンテンツの体験中に表示されると体験が醒めてしまう。そのため、移動可能な範囲を周囲から少しくぼませ、視覚的に分かるようにしている。こうすることで、体験者に対して自然に境界情報を通知しているのだ。
絵コンテ上で描かれた演出をVR空間でどのように実現するかも課題だった。オールラウンドタイプ4×4タイヤの「WILDPEAK A/T3W」におけるクリアデモで、崖から岩が転がり落ちてくる演出は好例だ。せっかく岩が落ちてきても、体験者が別の方向を見ていては意味がない。仮に岩を見ていたとしても、体験者の立ち位置が少しズレるだけで体験として受ける迫力が大きく異なる。そのため、体験者が最後にはめたタイヤが前輪か後輪かで、岩の転がる位置が細かく変化するといった工夫が盛り込まれている。
このほか、前述したチュートリアルでは「左右のグリップボタンを押して、両手で目の前の箱を掴んでみましょう」という音声がながれるのだが、実際はどのボタンを押しても、箱が掴めるようになっている。続けて「コントローラを握るように持つことで、仮想空間の物を持つことができます」という音声も流れるのだが、グリップボタンがわからないユーザーがいることを想定。操作がわからなければ、体験者のプレゼンスが一気に低下してしまうので、それを防ぐために全てのボタンが反応するしくみとなっているのだ。これもまた、ゲーム開発者ならではの知見だと言えるだろう。
▲アニメーションなどを効果的に使用し、立体的にデザインされたUI表現。VRだからこそ映える演出だ
最後にUI/UX面での工夫についても聞いてみた。園田氏と共にプログラムを担当した濱口隆ノ助氏が、UI/UXデザイナーと二人三脚でつくり上げた。本作に限らず、首を振ると視界が動くVRコンテンツでは、UIを空間上に配置する手法が主流だ。このとき、UIを構成するパーツ群をレイヤー的に配置することで、立体的なUI表現が可能になる。タイヤを選択したときに表示されるスペック表現が本手法で行われており、アニメーションの活用と相まって、スタイリッシュな演出になっている。
「タイヤのPVを資料にいただいたので、それを参考に弊社のUI/UXデザイナーが素材をつくってくれました。UIに囲まれている感じを出したくて、三面鏡のように左右に角度を付けて、あまり首を動かさなくても全体が確認できるようにしています。ただし、Unityのエディタ上と実機上で見るのでは受ける感覚が大きく異なります。何度もUI/UXデザイナーとやりとりを重ねながら進めました」(濱口氏)。
これに限らず、「VRコンテンツの開発では実際にVR HMDを被ってみることが重要」だと、VRスーパーバイザーの柴崎氏は改めて実感したという。もっとも、コロナ禍によりグランディングでもテレワークが推奨されている。中には、ほとんど出社せずに進めるプロジェクトもあるほどだそうだ。それでも本作の開発では、毎週出社して対面ミーティングを行うことが欠かせなかった。「密にならないように換気を心がけましたが、おかげで寒さを感じたこともありました」(園田氏)。
こうして完成した『FALKEN VIRTUAL GARAGE』。中には、予算や納期的に断念したアイデアもあったという。「ハンドトラッキング」はその1つだ。Oculus Quest 2で実装されたハンドトラッキングを使えば、物を掴む感覚がより直感的になる可能性がある。オンラインで2人同時に体験させられるアイデアも同様だ。コロナ禍といえども、2人同時に体験させらることができたなら、イベント会場での回転数が上げられる。共に企画段階で生田氏と髙橋氏から提案されたもので、二木氏としても興味が惹かれたとのことだが、見送らざるを得なかった。次回こうした機会があればぜひ挑戦してみたいという。
セガ出身で『パンツァードラグーン』(1995)、『AZEL -パンツァードラグーンRPG-』(1998)の生みの親としても知られる二木氏。もともとVRに関心があり、『MI-TECH CONCEPT VR Experience』での監修業務を経て、今作でがっつりと開発に携わることができた。今後挑戦してみたい案件の中には、オリジナルのVRゲーム開発も含まれる。「今回、短期間でVRコンテンツを開発したことで様々な知見が得られました。今後の開発に活かしていきたいです」(二木氏)。