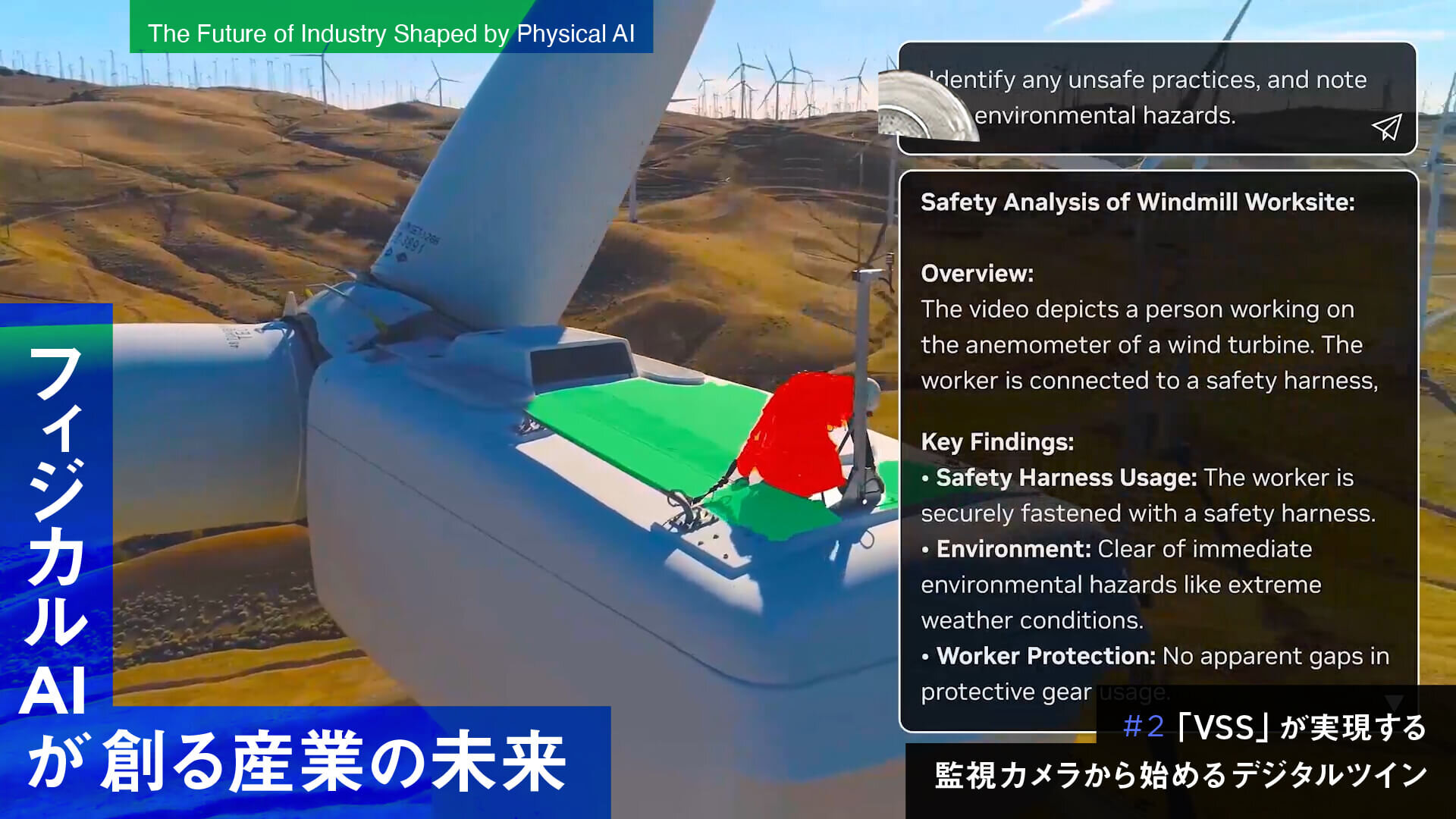地方創生RPGのゲームデザインと現状の課題
このように、1作ごとに新たな取り組みを続けてきた同社の地方創生RPGシリーズ。もっとも高久田氏は「中小企業ゆえの工夫を続けてきただけ」と語る。1作あたりの受注金額は700万円から1,000万円で、開発期間は8ヶ月前後だ。中でも時間がかかるのがシナリオ制作で、高久田氏が自ら手がけている。これもシナリオ業者に見積もりを取ったところ、コスト面で引き合わなかった点が大きいという。
一方でシナリオ・ゲームデザイン・マップ制作には、大学で歴史学を志した高久田氏ならではのこだわりが見られる。以下、『はじまりの島』を例に見ていこう。
まず、シナリオでは各自治体にまつわる民話・伝承が巧みに盛り込まれている。『はじまりの島』では、日本遺産を構成する4つの物語(イザナギとイザナミの「国生み神話」、弥生時代に金属器をもたらす過程を描いた「海の民」、塩づくりと航海術で大和時代の王権を支えた様子を描く「海人」、天皇の食膳を司ったことを示す「御食国」)と、前述した31の文化財を網羅するストーリーで構成されている。プレイヤーに対して押しつけがましくならないようにゲームに溶け込ませているのだ。
ちなみに同社では、他社との協業により全国の民話・伝承を地図データと組み合わせた独自のデータベースを構築中だ。Google Map上でクリックすれば、その場所にまつわる民話・伝承が表示され、Googleストリートビューで写真も見られるというもの。すでに6,000件以上が登録されており、シナリオ制作に活用されている。また、取材目的で何度も現地に足を運び、写真を撮影したり図書館などで資料を収集したりすることも多いという。
▲日本遺産を構成する4つの物語
▲文化財およびゲーム中での登場例
続いてマップでは、地域の人々が遊んで実感が湧きやすいように、できるだけ元の地形が忠実に再現されている。また、ゲーム内に現代でも見ることができる建造物を登場させるようにしている。ゲームが郷土の古典芸能で、国の重要無形民俗文化財にも指定されている人情浄瑠璃「あわじ人形座」の劇場からスタートするのは好例だ。歴史学に込められた「現在の興味からはじまり過去を手がかりにすることで、未来への展望を見出す」という意味を体験してもらう意味合いがある。
▲実際の淡路島を基にデザインされたフィールドマップ
最後にゲームデザインでは、観光とゲームを上手く組み合わせ、観光の充実度を高めるためのデザインが挙げられる。GPSチェックインを用いたアイテム収集や、GPSクーポンの配信などだ。この機能を活かすため、本シリーズでは序盤から街や村ごとにワープポイントがあり、すでに訪問した場所であれば自由に移動可能。これにより、ゲームの進行度に関係なくGPSチェックインが可能となっている。
一方、「予算」、「品質」、「広告」、「敷居」、「誘致」の5点は課題となっており、予算面ではゲームやアプリに高額な予算が充てられる地方自治体がまだまだ少ないことが挙げられる。すでに見てきたように、本シリーズは700~1,000万円の予算で開発されており、一般的なゲーム開発の水準より低いと言わざるを得ない。高久田氏は『はじまりの島』のように、複数の自治体がコラボレーションすることで費用を捻出する座組も考えられると指摘した。
品質面では、UI/UXに代表される「操作面でのつくりこみの粗さ」が残っており、予算との兼ね合いにもなるが、今後はこうした部分の改良も進めていきたいという。広告面も同様で、地方自治体の強みを活かしつつ低予算でもできるプロモーションを目指したいとのこと。また、敷居面ではRPGにこだわらず、より気軽に楽しめるコンテンツを開発することも検討中だと述べた。
最後に誘致についてだ。すでに見てきたように、本シリーズには「観光誘致」と「郷土理解」という2つの目的がある。一方でコロナ禍が続く中、観光客の増加が見込みにくい状況が続いている。コロナ終息後にどのような世界観が来るのか。観光ビジネスは元に戻るのか戻らないのか。戻らないとしたら、代わりとなる施策はあるのか。高久田氏は「コロナ後を見据えた施策の創出について考えていきたい」と話す。
このほか、今後取り組みたいゲーム開発として、日本の歴史を体験できるようなゲームが挙げられた。歴史を題材とした学習漫画のゲーム版といったもので、邪馬台国、古墳時代、飛鳥時代......といった具合に、それぞれの時代が数時間程度でプレイできるというもの。戦乱に巻き込まれた主人公が、それぞれの陣営に属することで、同じ戦乱でも異なった視点で捉えられるといった内容を想定しているという。
他に、繰り返しになるが、RPG以外の自治体向けゲームや、民話・伝承データベースを活用したゲーム・コンテンツ開発にも取り組んでいきたいと語った。
▲ゲームのメイン画面とキャラクターのメッセージウィンドウ(写真は開発中のもの)
産学官連携と新たなゲームの可能性
このように、1作ごとに進化を続けてきた同社の地域創生RPGシリーズ。そこには「地域の課題をヒアリングしゲームデザインやGPSなどの機能を活用して、それに即した課題解決を行う」という、理想的なシリアスゲームの姿がある。個人的にはRPGの「仲間と共に世界を冒険し、世界を危機から救う」展開が、平成の大合併によって生まれた地域社会の溝を埋める役割に適しているように感じられ、興味深かった。
これに対して高久田氏は、自治体側の熱意や協力体制があってこそ、これまでシリーズが進められてきたと補足した。実際、これまでも多くの自治体や団体から引き合いがあったが、途中で頓挫するケースも少なくなかったという。庁内や議会にプレゼンするための資料制作を無料で要求されるなどはその一例だ。一方で行政と事業者が適切にコラボすることで、多くの可能性が眠っていると指摘する。
最後に視野を少し広げて考えてみよう。地域創生RPGのリリースが可能になった背景に、行政側と事業者で双方の事情がある。行政側からすれば、ゆるキャラや観光PR動画の作成といったポップカルチャーの活用や、そこに税金を投入するためのノウハウ蓄積があるだろう。一方で事業者側からすれば、いわゆる「ゲームの民主化」がもたらした開発負荷の低減と開発費用の低下があることは言うまでもない。
こうした変化は今後も不可逆的に進むと思われる。これらがもたらす未来はどういったものだろうか。今やクオリティさえ考えなければ、誰にでもゲームが開発できると言っても過言ではない時代だ。地域創生RPGについても、GPSチェックイン機能を使わなければ、すでにコーディング不要で開発できる環境が整備されている。RPGにこだわらなければノベルゲームという選択肢もある。
そこから想像を広げると、地域の民話や伝承をモチーフとしたゲームを官学連携で開発し、自治体が発信する世界線が見えてくる。学校のプログラミング教育でご当地キャラクターのビジュアル素材を活用する、といったコラボレーションもあるだろう。そうした時代が到来したとき、本稿で取り上げた自治体と企業の協業も次の段階に進むはずだ。ゲームの公共利用のあり方について、今後も議論が進むことを期待したい。