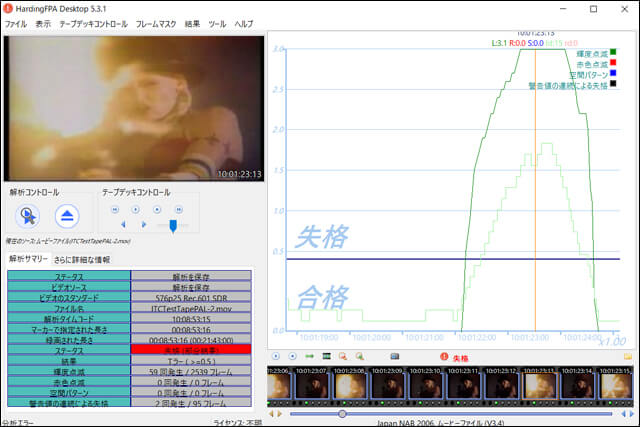研究すればするほど新しい研究をしたくなる
CGW:改めて、修士号と博士号とで、テーマの関連性について教えてください。
遠藤:修士のときに最初にやった調査が、冒頭の「ゲームの離脱理由」でした。そこでわかったことが、「プレイヤーがモチベーションを失っていないのにゲームを止める」現象があるということでした。それがあまりに実感とかけ離れていて。ゲームに対する人の振る舞いや、動作について、もうちょっと根本的に見ないといけないなっていうことに、気づかされたんですね。
CGW:修士で気づきを得て、博士で深堀りして、博士論文でそれまでの成果をまとめるというのは、研究の理想的なあり方ですね。
遠藤:まったく、その通りですね。だから、最初から「ゲーム道」ありきで研究を始めた訳じゃなくて。1つの研究がさらに別の研究につながっていき、全体をかたちづくっていきました。
難易度についての研究もそのひとつです。ゲームの難易度が合っていないと、人は遊ぶのを止めるんですよ。そこから理想の難易度設定について研究をしました。実際にゲームを試遊して、学生に遊んでもらい、その結果を分析しています。博士論文の中では「ネクストレベル選択研究」と「Dynamic Pressure Cycle Control~イリンクスを楽しむ動的難易度調整」として、第4章に掲載しています。
そんなふうに難易度について研究を進めていくと、次第に難易度だけではなくて、いろいろな要素がパーソナルなんだということに気づきました。ゲームのどこに面白さを感じて、どういう理由で固有の振る舞いをして、どういう理由で辞めてしまうのか。もっと多角的・総合的に見ていく必要があるぞと。
CGW:なるほど。
遠藤:このことがはっきりわかったのが、ジャンケンゲームを用いた「ゲームの戦略性に関する研究」でした。コンピュータが80%グーを出してくる「ぐー80じゃんけん」ゲームをつくって試遊してもらい、アンケートを集計して解析したんです。その結果、評価が二極化したんですよ。詳細は論文にゆずるとして、普通に考えれば、パーを出せば楽に勝てるから、つまらないですよね。これがルドゥサーのプレイヤーの反応です。
博士論文より
CGW:そうですよね。
遠藤:一方で「これって、いつグー以外を出してくるのか、当てるゲームだよね」と捉えた回答者が一定数いたんです。しかも7段階評価の5番目、「やや面白い」と感じた人の数が、最も多かったんですよ。
また、年齢が上がるにつれて、面白いと感じる傾向が高まることもわかりました。ジャンケンゲームのルールの本質とは全然ちがうんですけどね。そんなふうにルールを創発しながら遊ぶ人がいて、これがパイディアンの論拠のひとつになりました。
ところが、同じ調査を外国人に行なってみたところ、面白さの度合いが一気に減少しました。CEDECの講演から、フランス人とそれ以外で結果を分けてみましたが、特にちがいは見られませんでした。ここから、日本人には海外の人と比べて、パイディアンが多いことが推測されました。
CGW:興味深いですね。
遠藤:ただ、最近のトレンドを見ていると、世界も徐々に変わりつつあるという気がしています。『あつまれ どうぶつの森』(以下、あつもり)が全世界で1,300万本以上売れているのは、パイディアンの遊び方もあることを理解している人が、世界で増えているんだと思います。
CGW:自分も『あつもり』がなぜ面白いのか、よくわからないんですよね。典型的なルドゥサーなんだと思いますが、そういった遊び方があるのはわかります。
遠藤:ただ、『あつもり』を遊びながらゲーム機本体の時間を弄るプレイヤーがいて、そういうプレイヤーはルドゥサーの中でもアンフェアプレイヤーなんです。逆にカブの売買などで、何とかして効率良くお金を稼ごうというのは、フェアプレイヤー。好きな服を着たり、村全体を自由にカスタマイズしたりして楽しむのがパイディアンですね。
CGW:研究内容もさることながら、研究手法についても教えてください。アンケートを中心とされていますが、何か理由はありますか?
遠藤:一般の研究者が200人規模のアンケート調査を実施すると、調査費用が50万円ぐらいかかるんですよ。僕の場合は「こんなアンケートをつくったから、ちょっとやってみて」とツイートをするだけで、それくらい集まるんですね。これは他の研究者では、なかなか真似できないことです。そのため、できる限り僕がいろんなアンケート調査を行なって、その結果を明らかにしていくことが必要だと思っています。その結果を見て、他の研究者が活用してくれればいいなと。
CGW:それはまさに先ほど言われていた、「自分だからできること」なんですね。
遠藤:これがまた、アンケートを重ねれば重ねるほど、新しいことがどんどんわかっていくんですよ。これは博士論文には含まれていませんが、男性と女性でゲームを評価するタイミングがちがうことがわかってきました。調査の結果、女性は男性よりも、ゲームをプレイする前に、雰囲気で面白いか面白くないかを決める傾向が高い結果が見られたんです。この内容を基に、さらにデータを集めたものを2020年の春に学会発表する予定でしたが、コロナ禍で延期になってしまいました。
CGW:そんなふうに、研究室で明確なテーマを掲げて、学生と一緒に様々な調査をしていくというのは、理系的なアプローチですね。過去にそういった経験や、指導を受けたりしたことはありますか? 研究室の運営について、参考にされたりしたものでもかまいません。
遠藤:そこは会社経営と同じです。ゲーム会社のように、クリエイティブな組織では、若手が育ってくれなければ、自分が楽にならないじゃないですか。そのためには若手を育てて、権限を移譲して、任せて、強くしなきゃいけない。学生に対しても、そのような感じで指導しています。
CGW:文系の研究者にはなかなか出てこない発想かなと改めて思いました。
遠藤:とにかく学生に任せてみて、できる学生を伸ばしていく。幸いにして、うちの研究室には優秀な学生が集まってくるので、本当に助かります。「そのへんを勉強してみればいいんじゃない?」って言ったら、「わかりました」って。その後「先生ちょっとこの本を読んでみたんですけども、こんな感じですかね?」、「ああ、そうだね、面白そうだね」、「わかりました、もうちょっと攻めてみます」とか言ってきて。そんなふうに自分で進めながら、ちゃんと研究をモノにしてくる学生が毎年、必ず入ってくるんですよ。学生同士でディスカッションしながら、どんどん新しいところを切り拓いていくんですね。
CGW:甲子園の常連校における、先輩と後輩の関係といった印象ですね。
遠藤:本当にそんな感じです。ゼミで後輩が先輩たちを見ながら、先輩ってすげえよな、とてもじゃないけどあんなレベルまで到達できないよ、って言ったりしているんですが。実際にそういう立場になると、そのレベルまで成長している。
CGW:今後も様々な研究活動をされると思いますが、現在のアンケート手法がベースになっていきますか?
遠藤:そうですね。アンケート調査と試作ゲームによる実証実験を続けていく感じですね。そうして得られた成果を、最終的にゲームデザインに応用していくことが目標なので。実装して、成果を見ていくところが、一番大事ですね。特に近年はゲームエンジンの普及で、そうした実験用のゲームを学生がつくりやすくなったことが、追い風になっています。
CEDEC 2011「ペラ企画コンテスト」
CGW:大学の先生になる前から、DiGRA JAPANやCEDECをはじめ、学会やゲーム開発者コミュニティでの活動に積極的に関わられています。そういった活動がキャリアや博士号の取得について、何か影響を及ぼした点があったら教えてください。
遠藤:DiGRA JAPANは2006年の設立当初から参加していますね。ゲーム会社の経営者という立場で、学会運営に関してアドバイスしてほしいというながれだったと思います。そこで財政の強化やイベント開催、会員募集といったお手伝いをしていました。2008年には、それまでまともに研究したことがなかったのに、研究委員長を仰せつかって、2012年に夏期研究大会を起ち上げました。こうした活動を通して、徐々に学術について理解していきました。
ただ、最初のうちは「こんな学会、いつまでやるんだよ。潰れちゃえばいいのに」と言ってたんですよね。実際、学会設立後、初めて年次大会が開催されたのが2010年で、その間は学会としての活動が低調でしたから。
CGW:そういう時期もありましたね。
遠藤:そのときに三宅さん(三宅陽一郎氏/スクウェア・エニックス)が「潰さないでください」って頼み込んできて。「ゲームの学会は他にないですから」、「ゲームのことを考えるんだったら、潰さないでください」って。そのときに「三宅君が一番やりたいんだったら、責任をもって、いろいろやるんだよ」って言ったんです。実際に彼がいろいろやっているので、それに応えるために、学会の基礎の部分とか運営的なものをやっていけばいいかなと思って。それから役員の世代交代も進んで、いい形になっていると思うんですけど。
CGW:CEDECの方も長く運営委員をされていますね。
遠藤:運営委員を始めたきっかけは、今となってはちょっと思い出せないですね。ただ、運営委員を始めてから、CEDECはゲーム業界の良心だと思うようになりました。日本のゲーム業界が一丸となって、世界と対抗していこうみたいな集団になっています。
そのため批判する人もすごく多いんですが、僕は2008年から2011年の、吉岡直人さんが委員長を務めた時期が一番良かったと思っています。運営が組織的になって、きちんと外に対して戦えるようになった。そのため、僕は今でも心の中で吉岡さんが委員長だと思っています。
CGW:セッションの公募制も2010年から始まりましたし、幸か不幸か東日本大震災があり、印象に残る時期でしたね。
遠藤:ただ、運営委員には任期があるんですよ。そのため僕も辞める予定だったんですけど、いつの間にか任期規定がなくなって。遠藤さん続けてやってもらえますよねって言われて。なかなか引退させてもらえないでいます。
CEDEC 2015「企画初心者のための『ラピッドプランニング演習』」
CGW:CEDECを通して、ペラ企画コンテスト「PERACON」が始まって、そこで学生が発表できる場ができたりと、ゲームデザインの分野でも、産学連携的なものが進んだ気がします。
遠藤:そうですね。そういう意味でも、CEDECをゲームデザイナーの視点から、どのように盛り上げていくか、これからも関わっていくんだろうなと思っています。
ゲーム開発の暗黙知に研究の光を当てる
CGW:改めて、今後の研究活動や関心のある分野について教えてください。
遠藤:ゲームを楽しむプレイヤーの振る舞いの中で、変わったものを抽出して、なぜそれが起きるのか調べていきます。調べれば調べるほど、新しく調べたいことが出てくるので、そこを掘れる限り掘っていきたいですね。
CGW:例えば、どういったものがありますか?
遠藤:いま進めているものに、難易度が高くてゲームを諦める人が、諦めなくて良い方法に関する研究があります。
CGW:博士論文で引用されている「ネクストレベル選択研究」に連なる研究ですね。
遠藤:あらかじめ難易度の異なるステージを大量に用意しておき、ミスしたときに、プレイヤーに自分が適切だと思う難易度レベルを選ばせる方法論について、その有効性を実証実験した研究ですね。1つのやり方ですが、他にもいろいろ考えられます。
典型的なものに、何度も同じポイントでミスをしたら、自動的にゴールまで連れていってくれる「自動クリア」がありますね。でも、それがプレイヤーにとって気持ちがいいのか、という話になります。他に失敗すると難易度が下がっていく、動的難易度調整という考え方もあります。でも、難易度が操作されていることがわかれば、つまらないと感じる人が出てくるかもしれない。
そんなふうに、難易度が高いという状況とその解消策に関する捉え方は、プレイヤーによってちがいます。中でも注目したいのが、ゲームプレイのスキルを誤認しているプレイヤーです。
CGW:ああ、そういった人はいますね。
遠藤:本当は大して上手くないのに、自分は上手いと思っている人がいます。テレビ番組『ゲームセンターCX』の有野課長みたいな感じですね。有野課長は決してゲームが上手くないんですが、最終的にはゲームをクリアしているから、「自分はクリアしたし、上手いですよね」って言うんですよ。いや、それはちがうと思うんだけど......まあ、上手いでもいいやっていう。
そんなふうに、自分のスキルを誤認している人たちは、実はゲームに対する執着心が強いんです。このゲームに対する執着心の測定方法について考えています。
そもそも、ゲームの腕前って自分で決めるものじゃないですよね。自己申告してもらってもそれは嘘なので。自分が上手いと誤認しているプレイヤーは、どんどん上の難易度を選んでいきます。最高難易度でクリアできる自分以外、イメージできないので。
こんなふうに執着心が強い人であれば、やや高い難易度でも大丈夫なんですけど、執着心が弱い人に、高い難易度で遊ばせてはダメなんですよ。平均よりも難易度が低くて、もの足りない、つまらないというくらいのレベルから始めさせて、どんどんどんどんクリアさせていく。それが楽しい人たちもいるんですよね。
CGW:うちの妻もゲーム『Candy Crush Saga』だけを、ずっと無課金で300面くらいやっていて、しかもドラマを見ながら手慰み的に遊ぶんですよね。何が面白いのか、僕にはよくわからないんですが、いろんな楽しみ方があるんだなということは、改めて思います。
遠藤:そこで鍵となるのがゲームに対する執着心で、これを計測する方法について取り組んでいます。うちの研究室のエースが、何か実証実験してくれると嬉しいなと思ってます。
CGW:ゲームの研究者には、ゲーム自体について研究する人と、ゲームを取り巻く人々や、社会や経済について研究される方がいますが、遠藤さんはゲームをプレイする人の振る舞いを研究しつつ、ゲームの開発に応用させていく点が特徴的ですね。
遠藤:そこが大切だと思って研究しています。これまでの研究で、人が面白いと感じることは、人によってちがうことが客観的にわかりました。その上で、今はゲームのパーソナル化というところに注目しています。ゲームをどうやってパーソナル化していけばいいのか。そのためには人が面白いと感じるセンスと、それに合わせたゲームのアジャストについて、考えることが重要です。
DiGRA 2019懇親会
CGW:そういった要素は、ゲームの開発現場では主にディレクターやプロデューサーが、フォーカステストや長年の経験も踏まえつつ、最後は「えいや!」で決められてきたかと思います。そういった暗黙知に負う部分を、研究を通して客観的に明らかにしていこうということですね。
遠藤:そうですね。
CGW:その一方で、今回の学位の取得で、現場でゲームを開発されている方の中に、ゲームデザインの研究について興味をもたれた方が増えたと思うんですね。また、ゲーム業界志望の学生にとっても、ゲームデザインについて研究することがより身近に感じられたんじゃないかと思います。そういった、後に続く人に対するアドバイスや、学位を取るメリットなどがあれば教えてください。
遠藤:学位の取得もさることながら、そこに至る過程の中で、研究成果や研究手法、研究で得られたデータなどが、すごく実になりました。そういう努力とか、人との繋がりとか、他の先生方に示唆される部分も多かったですし。それが財産かなって思っています。
CGW:それはゲーム会社の中で、ゲームを開発するだけでは、得られなかったことでしょうか?
遠藤:そうですね。もうちょっとゲームに対して正面から向き合えないとダメなので。学術だと、経験則じゃダメじゃないですか。自分の中では経験則がいろいろありますが、それはただの思い込みかもしれない。最初に行なったゲームの離脱理由に関する調査がきっかけでした。
CGW:それはどういったことですか?
遠藤:DiGRA JAPAN の2012年次大会で「書込み式ループすごろくを使ったレベルデザイン演習」という口頭発表を行い、予稿集に掲載されました。そこでリプレイモチベーションについて書いた一節があります。要は「人はこれこれ、こういった理由でゲームを止めるとされている」というものです。
でも、その時点ではあくまで、自分の経験則によるものだったんですね。にもかかわらず、その箇所を他の論文で引用されたんですよ。それがすごく恥ずかしかったんです。そんな裏も取れていないようなものを引用されたら悔しいから、数の力でもって、調査で何とかしようとしたんです。
CGW:そこで実際に調査をしてみたら、思わぬ結果が出てきた。それが最終的に学位につながったわけですから、面白いものですね。
遠藤:本当にそのとおりですね。「何かの理由でゲームを中断したこと」が、ゲームを再開しない一番の理由だったことが、データで裏付けられたことにも笑いましたけどね。確かにその通りなんだよな、とは思いつつ。そこから「自己目標の達成」と「意識的停滞」という、見逃せないデータが出てきて。
CGW:今後も過去の経験則に科学的なメスを入れて、客観的に証明していく。そしてそこから思わぬことが出てくる、ということが起こっていくんでしょうか。
遠藤:毎回思わぬことが出てきて。思わぬことだらけで、どんどん増えてくるんですけどね。そういう方向性に研究が進むことは明らかですね。
CGW:一度ゲーム開発をプロの現場で経験された方の方が、もしかしたら引き出しが多くて、研究職に入って新しい発見をする可能性があるのかもしれませんね。
遠藤:本当にそう思います。そういう意味では、中村隆之先生(元『ことばのパズル もじぴったん』シリーズ プロデューサー/現・神奈川工科大学 特任准教授)に期待しています。
CGW:中村先生も今、博士課程に在籍されていて、ゲームデザイン研究を進められていますよね。そんなふうに、本分野でどんどん新しいながれが出てくれば、国産ゲームも、もっと盛り上がっていくと期待しています。最後に何かプッシュしたいところはありますか?
遠藤:特にないんですが、できれば日本だけでも、ルドゥサーやパイディアンという言葉が通じるようになってほしいなと思っています。
CGW:ありがとうございました。