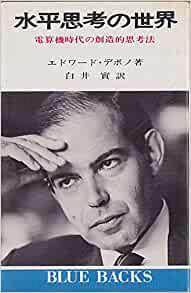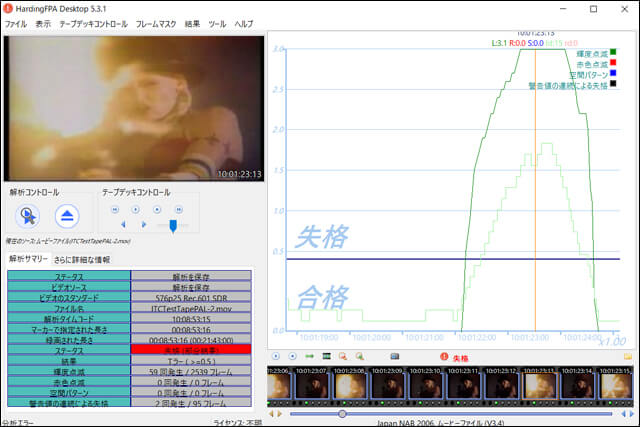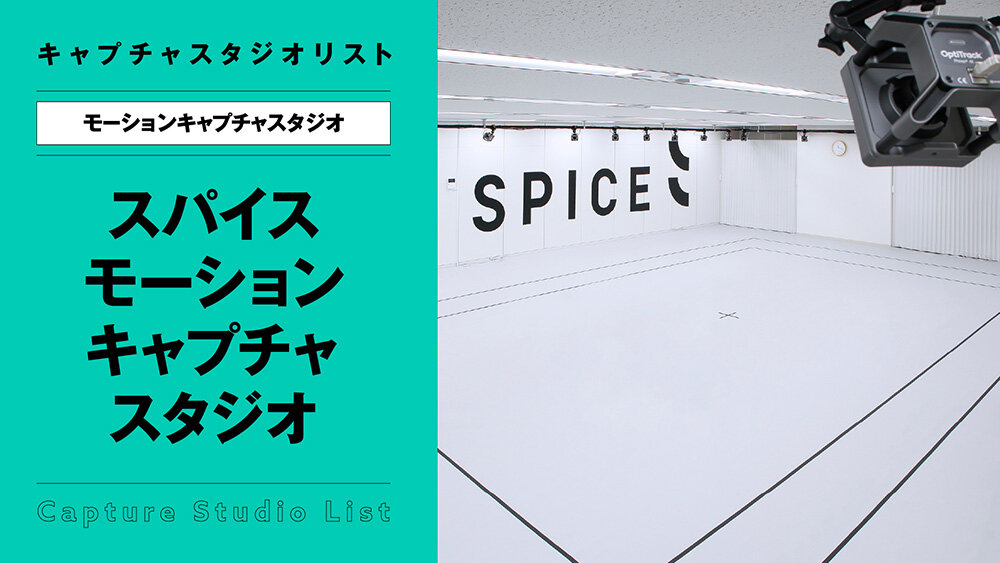ゲームエンジン制作を経て懐疑派になる
CGW:他にハル研でどういった仕事をされていたんですか?
藤田:いろいろなツールをつくったり、ゲームエンジン的なものをつくっていたんですが、だんだんと疑問に感じるようになってきて......。ちょっと話が逸れますが、そもそもツールやミドルウェアって、開発で楽をするためにつくるわけですよね。
CGW:はいはい。
藤田:その考え方を拡大させていくと、ゲーム機のハードウェアを抽象化して、ゲーム機が変わっても、同じプログラムが動くようにしたい......そんなふうに考えるようになるじゃないですか。それが、どんどんリッチに、汎用的になっていくと、ゲームエンジンにつながるわけです。ちなみに私の博士論文では、こうした概念を「抽象化レイヤー」と呼んでいます。
ただ、そうしたエンジンをつくっているうちに、ゲームのアイデアが抽象化レイヤーに引っ張られてしまって、斬新な発想が出なくなるんじゃないか......そんな風に考えるようになったんです。
CGW:興味深いですね。なにかきっかけはありましたか?
藤田:ゲームエンジンの仕事が一段落したころ、アニメ『ポケットモンスター』の映像素材を使って、何かつくれないかという相談がありました。ゲームキューブで光ディスクが採用されて大容量のアニメーションが入れられるようになったので、それを活かしたコンテンツができないかって。そんなふうに、ざっくりとした話をふられることが多かったんですけど。
CGW:目に浮かぶようですね(笑)。それで、何をつくられたんですか?
藤田:ゲームキューブで動く動画ビューアでも良かったんですが、せっかくなので、アニメを見ながらボタンを押すと、アニメが静止して塗り絵になって、デジタル塗り絵ができる。そういうシステムをつくったんです。最終的に『ポケモンチャンネル~ピカチュウといっしょ!~』(2003)というゲームで使われました。ゲームの開発自体はNINTENDO64で『ピカチュウげんきでちゅう』をつくったアンブレラでしたが、ハル研でつくったシステムを採用してもらったんです。
『ポケモンチャンネル~ピカチュウといっしょ!~』パッケージ
CGW:それはまた、斜め上のシステムを提案されましたね。でも、そのことと抽象化レイヤーの話が、どうつながるんですか?
藤田:ポイントはそこなんですが、アニメの絵を静止して塗り絵にする、なんて変わったアイデアを実現しようとすると、自分がつくったゲームエンジンが邪魔になったんです。ゲームエンジンを迂回して、直接ハードを叩く必要がありました。便利だろうと思って道具をつくったんですけど、いざその道具ができてみたら、それに縛られるのは嫌だっていう。矛盾ですよね。
CGW:ああ、なるほど。
藤田:プログラマーであれば、そういった発想は無意識のうちに避けるものなんです。互換性がなくなってしまいますからね。アプリケーションの側を、抽象化レイヤー(=ゲームエンジン)に納めなくちゃいけない、という発想になってしまう。でも、それだと効率的かもしれないけれど、突拍子もないことはできないわけで。反対する人もいましたが、そうしたシステムをつくったら、アンブレラさんの方で使ってもらえました。
CGW:ちょうど端境期でしたね。ゲーム機の性能がプアだから、ハードを直接叩いて、色んなことをやりたいっていう考え方と、そろそろ工数を考えると、抽象化してゲームエンジンみたいなものを使っていかないとヤバイっていう。
藤田:まさにそんな時期でしたね。
CGW:ハル研を退職されたのは?
藤田:岩田さんがハル研を辞めて任天堂の社長になって、すぐくらいですね。ニンテンドーDSが発売された頃は、もう退職していました。その後、フリーのゲームプログラマーとして、『CUBELEO』(2009)というゲームの開発に参加しました。
『CUBELEO』公式サイトより
CGW:Wiiウェアのタイトルでしたね。任天堂のタイトルの中でも、ちょっと尖った、実験的なゲームを出していこうという試みで、Art Styleというブランドで展開されていました。
藤田:そうそう。Art Styleは岩田さん肝煎りのプロジェクトだったんですね。Art Styleブランドの多くはスキップというゲーム開発会社が受託していました。そこでプログラマーが足りないからって、声をかけていただきました。
CGW:ということは、別に藝大に行くからハル研を辞めたとか、そういう話じゃないんですね。
藤田:ではないですね。
CGW:そのままフリーランスのゲームプログラマーとして仕事をされる道もあったと思うんですが、そこから学術の方に移られた理由は何でしたか?
藤田:あんまり思い出せないんですが......もともと、ちゃんとした人じゃないんで(笑)。
その頃、藤幡正樹さんというメディアアーティストが好きで、その人が書かれた本をずっと読んでいたんです。けっこう難解な本なんですが、くり返し読むうちに、だんだん理解できるようになってきて。藤幡さんは本の中で、メディアをつくることが表現なんだと、くり返し説かれていました。それが抽象化レイヤーの話と符合したんです。藤幡さんがメディアと呼んでいるものが、自分にとっては抽象化レイヤーで、抽象化レイヤーと表現は切り離せないんだって。
そんな頃、たまたま藤幡さんが中心になって、藝大の大学院に映像研究科が新設されると聞いたんです。残念ながら1年目は受験対策が間に合わなくてダメで、その翌年に2期生として入りました。
藝大の大学院でメディアアートについて学ぶ
CGW:翌年に受験し直すのがすごいですね。ある程度モチベーションが高くないと......。当然その間は仕事をしなくちゃいけないだろうし。
藤田:いや、あんまりなかったんですよね。キャリアアップのために、前のめりで、というわけじゃなかったんです。映像研究科の講師には佐藤雅彦さんもいて、ここに行けば何か面白いことがあるんじゃないかと。道具をつくるのはハル研で死ぬほどやって、つくったのは良いけど、自分で使いたくない。ゲームエンジンをつくっただけど、ゲームエンジン否定派になったという。
CGW:その考え方が面白いです。
藤田:そういえば、Art Styleのゲームって、ひとつとしてゲームエンジンをそのまま使ったものはなかったんですよ。当時はUnityやUnreal Engineの登場前夜でしたが、僕がゲームキューブでつくったように、各社が独自で内製ゲームエンジンをつくって、その上でゲームを開発する試みが増えていました。にもかかわらず、そうしたやり方を否定して、ハードを直接叩いていたんです。そういうつくり方をしたかった人たちが、集まっていたんですね。
CGW:年齢層も高かったんですか?
藤田:高かったです。僕と同じか、僕より上の人もいました。スキップの創業メンバー、西 健一さんもその1人でした。
CGW:旧スクウェア出身のゲームクリエイターで、ラブデリック時代に『moon』(1997)という伝説のRPGを開発されたメンバーの一人ですね。アンチRPGを掲げた異色のタイトルでした。
藤田:そうです。以前からの知り合いで、僕に声をかけてくれたのも西さんです。それもあって、ゲームの可能性を広げることがミッションでした。岩田さんも、Art Styleは最終的にゲームじゃなくても良いと言っていましたね。
CGW:当時は国産コンソールゲームの地盤沈下が進んでいた時期でしたね。そんな中、従来の延長線上ではないゲーム機としてDSやWiiが出てきて、その上で実験的なブランドとしてArt Styleのような取り組みがありました。フラストレーションが溜まってる人が集まっていたんでしょうか?
藤田:そう思いますね。それに、岩田さん自身もメディアアート的なものが好きでしたしね。岩井俊雄さんと、実際にゲームをつくっていましたよね。
CGW:Art Styleの前に、DSでTouch! Generationsというブランド展開があり、そこで『エレクトロプランクトン』(2005)というゲームが発売されていましたね。Touch! Generationsもまた、岩田さんが深く関わったブランドで、そこから『ニンテンドッグス』、『脳トレ』などのヒット作が生まれました。
藤田:ああいうのが好きな方だったので、たぶんその延長という考え方だったと思うんですけどね。ただ、そこで集まった人がみんな、ゲームエンジンが好きになれないおじさんたちだったので、結局自分たちがやりたいことをやりはじめたという。そういう時期があってからの藝大ですね。
CGW:産業でゲームをつくるよりも、大学の方が自由に色んなものができて、面白そうだなっていう思いがあったんでしょうか?
藤田:うーん......その程度だったんじゃないですかね。来なくて良いって言われたら、別に良いやっていうぐらいでしたね。
CGW:大学院ではどういった作品をつくられましたか?
藤田:いま藝大のゲームコースを統括されている桐山孝司さんや、佐藤雅彦さんと一緒に、『計算の庭』(2007)、『指紋の池』(2010)をつくりました。彼らがやりたいことを聞いて、そのための道具をつくるところから、共同制作をするといった感じです。藤幡正樹さんとも『予測不可能な文房具』(2014)をつくっています。
CGW:それぞれ、どういった作品ですか?
藤田:『計算の庭』は、参加者がゲートを歩いてくぐりながら、与えられた数字になるように、計算をしていくという作品ですね。『指紋の池』は指紋センサに指を押し当てると、自分の指紋がモニタに表示されて、その中で動く様子が見られるというもの。『文房具』はスマートフォンをテーマとした研究・制作プロジェクトでした。
CGW:修士課程で終わらず、博士課程に進まれた理由は何でしたか?
藤田:直接的には、藤幡さんから勧められたことですね。メディアアートの研究者にさせたい、という思いがあったんじゃないかなあ......。ただ、そのとおりになはらなかったんですけどね。でも、藤幡さんとは博士号を取ってからも作品制作に関わったり、いろいろやっているので。何でしょうね。
CGW:日本のアカデミアだと、博士課程に進むことは、博士号を取って研究者になることと、ほぼ同義ですよね。ゲーム開発の現場に戻るのであれば、修士号で終わったと思うんです。
実際に藤田さんは2012年に博士号を取られたあとも、ニンテンドー3DSで『実写でちびロボ!』(2013)の開発に参加されていますね。ただ、そのあとは学術の世界に軸足をおいて活躍されています。
『実写でチビロボ!』公式サイトより
藤田:なるほど。確かに、何がしか特定の問題意識をもって大学院に進むだけであれば、修士課程で十分かもしれませんね。ただ僕の場合は、機械に対して人間がどう反応するかという、より広いテーマに関心がありました。そうすると何年あっても足りないわけです。実際、心理学をいまだに科学として認めない人たちがいますよね。あれは心理学じゃない、統計学だっていう。だんだんと、そうしたレイヤーにまで興味が移っていきました。
CGW:ゲームをつくるよりも、学問的な問題意識の方が強まっていったんですね。
藤田:うーん、そうですね。コンピューター文化というか、そういったものに対する研究や教育を、それこそ小学生レベルから始めなければダメだというか......。そういった問題意識に対して、藤幡さんがどんなふうに考えているのか知りたいという。そういった思いがあったのかもしれませんね。
CGW:深いですね。
藤田:例えばパーソナルコンピュータの父と言われるアラン・ケイという研究者がいますよね。彼はあらゆるメディアを超えたメディアとしてコンピュータを位置づけ、メタメディアという概念を提唱しました。その上でスモールトークという、今で言うビジュアルプログラミング言語のようなものができれば、世界中の人が自分に必要なソフトウェアを自分でつくりはじめる世界が来る......そういった前提で「ダイナブック構想」を立ち上げたんです。ただ、今のところそんな世界にはなってないじゃないですか。
もちろんビジネスとか、経済的合理性に基づいて、商用アプリケーションの世界が広がっていくのはわかります。ただ、表現とか、芸術の領域で他人がつくったソフトウェアを使って何かつくったところで、結局それはそのソフトウェアの可能性のひとつを指し示したにすぎないとも言えるじゃないですか。そうなってくると、結局のところ技術側の人間が芸術を理解するか、芸術側の人間が技術を理解するかしないと、アラン・ケイが言ってるような世界は来ないんですよ。そこに興味があったというか。
岩田氏の価値観が研究者的なモノの見方を育てた
CGW:面白いですね。ちょっと話がずれますが、日本でゲームの実務家教員というと、東京工芸大学の岩谷 徹さんをはじめ、旧ナムコのOB率が高いんですよ。それは会社の社風と関係があると思っているんですね。
藤田:言われてみればそうですね。
CGW:同じように藤田さんが、そんなふうに考えられるようになったのも、SCEやハル研の社風と関係があったんでしょうか?
藤田:そういう意味では、やっぱり岩田さんから影響を受けましたね。お忙しい方だったので、それほど一緒に仕事をした訳じゃないですけど。やっぱりモノの考え方というか、何というか。
岩田氏の言動は『岩田さん 岩田聡はこんなことを話していた。』、『ゲーム界のトップに立ったプログラマー 岩田聡の原点』に詳しい
CGW:「プログラムの経験が会社の経営に活きてくる」と言われていましたね。
藤田:そうですね。すっごく面白いのは、あれだけ理系で、バリバリのプログラマーだったにもかかわらず、占いのような一見、非合理的なものを否定していなかったことなんです。ハル研のみんなで食事をしているとき、話が占いをはじめとした、エセ科学的なものを否定するようなながれになったことがあるんです。そのときも岩田さんは「いや、これだけ長い歴史で淘汰されなかったのだから、科学的に根拠がないからといって、意味がないとは言えない」と言ってましたね。
CGW:岩田さんらしいコメントですね。
藤田:自然科学的にではなく、人文科学的に捉えれば別の側面が見えてくると。これに限らず、岩田さんは理系一辺倒じゃなかったですしね。
CGW:アートとかグラフィックとか、文系的なものに対して関心が高かったと聞いています。
藤田:最終的に自分たちがやってるのは文化なんだという意識がありました。そこから「技術の完成で仕事は終わりじゃない。自分たちの仕事を文化にまで昇華させないと」という考え方を教えられたという感じです。余談ですが岩田さんといえば、Macが大好きな方でした。Macが瀕死状態だった時期も使い続けていて、Apple製品を文化と捉えて、大事にしていました。使えもしないNewtonなどもお持ちでした。
CGW:その話は聞いたことがあります。
藤田:だからこそ、WiiやDSで他のゲーム機と同じようなハイスペック路線をとることもできたはずなんです。でも、そういうことは言わずに、僕らがつくろうとしているのは文化だから、ゲーム機を完成させるだけでは不十分なんだと。それを見たとき、触ったときに、人間がどう感じるかっていうところまで、あわせて考える必要があるんだって。そんな風に考えられていた方なんですね。
CGW:まさに、機械と人間の関係性の話につながりますね。当時はまだUI/UXという言葉や、ゲーム体験といった言葉はありませんでしたが、そういったものが大事なんだということを、よく話されていましたね。
藤田:そうですね。だから、自分がそういった分野に興味関心が移っていったというのは、岩田さん自身の考え方に影響を受けた結果だというのは、あったかもしれないですね。
E3 2001でゲームキューブを発表する任天堂の宮本 茂氏(左)と岩田 聡氏(右)
CGW:それで博士論文「創作環境論」を書かれるわけですね。概要がWebに公開されていますが、3DCGプログラマーとして作品制作に係わってきた体験談がベースになっていますよね。
藤田:そうですね。基本的にはケーススタディです。
CGW:論文の主査に大学院時代の作品制作でもご一緒された、桐山孝司先生の名前がありますね。今はゲームコースの旗振り役を務められています。桐山先生から、何かアドバイスは受けましたか?
藤田:博士論文の査読で1年失敗してるんですよ。はじめに書いたものが、あまりにもまとまってなくて、1年延びてるんです。その1年で、それまで自分がやってきた、ありとあらゆる芸術家とのコラボレーションについて、メールのやりとりから徹底的に洗い出しました。中にはコンピュータとまったく関係ない芸術家もいるんですが、そういう人たちとの活動をアーカイブして、そこから抽象化された概念を見つけ出すように、桐山先生から指導を受けました。まがりなりにも博士論文をまとめられたのは、桐山先生のおかげです。
CGW:自分の体験談を書くだけでは、論文にならないですよね。
藤田:そうなんですよ。それでも修士課程までなら、作品主体でOKでした。それに藝大では博士課程でも、プラクティカルドクターとセオリティカルドクターという区分があり、前者であれば作品の新規性や社会に対する影響度が評価の対象になるので、論文の比重はそこまで大きくありません。それに対して僕は後者でしたので、作品も必要でしたが、論文の完成度が求められました。
CGW:博士論文で得られた知見を粗っぽくまとめると、「新しい作品をつくることと、新しい道具をつくることは、不可分の存在である」ということですよね。それ自体は良くわかりますし、クリエイターであれば感覚的に理解されていることではないかと思うのですが、それを体系化して論文化するのは、すごく大変だなと思いました。まさに茨の道というか。
藤田:ゲームの研究って、まだ本当にそのレベルだと思うんですよね。もう本当にケーススタディの集合体というか。自分が体験したものの中から抽象化された、本当に小さいものを結論として貯めていくしかない状況にあると思っていて。逆に言うと、他と比べるものがないから、博士論文として認められたんだと思うんですよ。それでも、これまで暗黙知的に「当たり前」だとされていたことを、あえて言語化、理論化、体系化しないと、研究の遡上に載らないという。
CGW:論文ではエドワード・デボノの水平思考や、そこから転じて横井軍平さんの「枯れた技術の水平思考」に関する引用もありますね。任天堂でゲーム&ウォッチやゲームキューブの開発を主導された、伝説のゲーム開発者の1人です。
デボノが提唱した水平思考(左)と、その思想を商品開発に生かした、故・横井軍平氏(右)
藤田:デボノの提唱した水平思考は、一般的には問題解決のために既成の理論や概念にとらわれずアイデアを生み出す方法だとされていますが、もう少し深く読み込んでいくと、元になった概念の粒度を変えるという考え方なんですね。粒度を変えるからこそ、別の見方が生まれてくるわけで。その上で横井さんが言われているのが「枯れた技術の」水平思考。既に普及していて、コストがかからない技術を応用すれば、アイデア次第でヒット商品が開発できるというものですね。
CGW:論文ではデボノの水平思考について引用されていて、その一例として横井さんのエピソードを示したというわけですね。
藤田:そうですね。例えば、一般的に太陽電池と言われる製品がある。それを文字通り受け止めると、発電のための装置になるわけですが、粒度を下げて素子レベルにまで広げると、光が当たると電圧が変わる物質になる。つまり光センサになるわけですね。横井さんはその性質を使って、光線銃をつくったと。
CGW:有名なエピソードですね。
藤田:同じように言葉をパズルのピースとして捉えると、ピースによってできる形は、ピースの組み合わせ方に限定されてしまう。その一方で、同じピースでも複数に分割できることに気づけば、そこで組み合わせのパターンが増える。それがデボノの言う水平思考です。
CGW:それが先ほどから言われている、仮想レイヤーの話につながるわけですね。
藤田:仮想レイヤーというピースがあまりにも良くできているので、今やそれを使ってゲームをつくることを当然のこととして受け止めている時代になっていると思うんですね。UnityやUE4はその好例で。しかもこれからUE5の時代になるわけで。ただ、それって確かに、ものすごく可能性が広いキャンバスなんだけど、結局はその範囲での可能性にすぎなくて。
CGW:お釈迦様の手のひらの上だという。
藤田:そうですね。そういう風に思えてしまうんですよね。
CGW:昔はそれほど可能性が広くなかったので、すぐに限界が見えましたね。
藤田:そうですね。PSやN64のころは、何か抽象化レイヤーができたとたんに、こういうゲームしかできないという風に、決まっていたわけで。ただ、今でもゲームエンジンには開発上の文脈があって、それぞれで向き不向きがあると思っています。