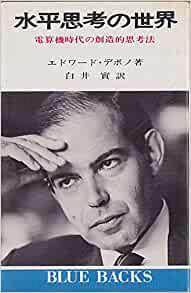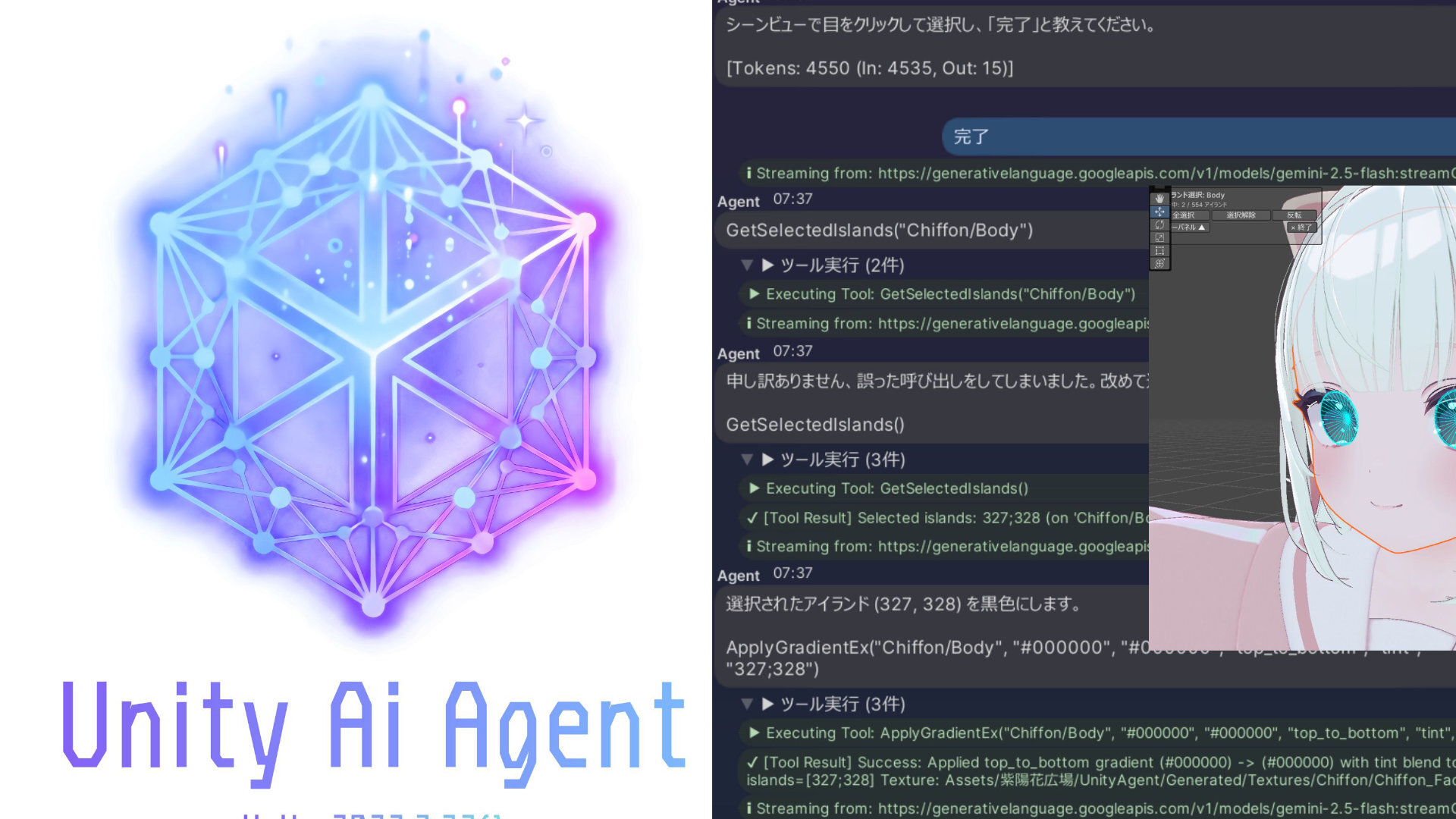企業や自治体などでの実務経験をもち、大学などで教育研究の指導を行う教員、いわゆる「実務家教員」の登用が続いている。2019年度から新設された専門職大学では、専任教員の4割以上を実務家教員とする規定があるほどだ。その中には豊富な実務経験だけでなく、学術研究を極めて「博士号」を併せもつ者もいる。
その一人が現在、東京国際工科専門職大学で専任講師を務める藤田至一氏だ。藤田氏は、ソニー・コンピュータエンタテインメント(当時)、ハル研究所でゲーム開発に従事し、東京藝術大学大学院で博士号を取得している。
産業界から学術界への転身の理由や、実務家が博士号を取る意味について、自身のキャリアをふり返りながら話を聞いた。
INTERVIEW_小野憲史 / Kenji Ono
EDIT_小村仁美 / Hitomi Komura(CGWORLD)、山田桃子 / Momoko Yamada
バンドブームの影響で音楽に夢中だった10代
CGWORLD(以下、CGW):藤田さんはプログラマーとしてゲーム開発に携わられた後、30代で大学院に入り直されたんですよね。社会人を対象としたリカレント(学び直し)教育が叫ばれる中、先駆けのようなキャリアですね。
藤田至一氏(以下、藤田):結果的にそうなっただけで、別にキャリアアップをねらってどうこう、といったわけではありませんけどね。
CGW:実はCGWORLD.jpの読者は30代を中心として、20代と40代が正規分布しているんです。30代ってキャリアについて考え始める時期じゃないですか。このままで良いのかなって。
藤田:はいはい。そういう意味では、自分はドンズバかもしれませんね。
CGW:しかも、修士課程だけでなく、博士課程に進まれて、博士号まで取られて。近年では実務家教員も増えていますが、なかなか博士号まで取る人は少ないと思うんですよ。なので、今日はキャリアをふり返りつつ、博士号や博士論文に関する話もお伺いできればと思っています。
藤田:はい、よろしくお願いします。
-

-
藤田至一/Yoshikazu Fujita
東京藝術大学大学院 映像研究科メディア映像専攻 修了。博士(映像メディア学)。研究分野は創作活動におけるシステム開発手法。株式会社ソニー・コンピュータエンタテインメント、株式会社ハル研究所などで、映像・ゲームの制作環境開発に従事。活動の場をメディア・アートにも拡大し、研究を続けている。CEDEC 2013登壇。東京藝術大学で非常勤講師を務め、現在に至る
CGW:ちなみに、何歳でいらっしゃいますか?
藤田:1969年生まれで、今年で51歳ですね。東京都練馬区の出身で、父親は大学の先生で、労働福祉が専門でした。母親はインテリアコーディネーターで、家具なども手がけていましたね。
CGW:先生の子どもが先生になったわけですね。
藤田:そうですね。分野はまったくちがいますが、何かこう研究的なところは受け継いだ感じですね。
CGW:子どもの頃は何をして遊んでいましたか?
藤田:野球とかサッカーとか、何かルールがあるものよりは、山とか川とかを駆け回るのが好きな子どもでした。ただ、家の近所にはそういった場所がなかったので、長期休暇で田舎に行ったとき、それまでの鬱屈を爆発させるような感じでしたね。
CGW:なるほど。
藤田:その思いが強すぎて、山の中で迷子になったりして。小学校低学年だったかな。近所の人に総出で探していただいて。あとで両親からこっぴどく叱られました。
CGW:外遊びがお好きだったんですね。
藤田:そうですね。ファミコンが発売されたのが中学2年生のときでしたが、あまり興味がなくて。電子ゲーム機なども友だちに時々、遊ばせてもらうくらいでした。
CGW:中~高校生のころはどんな感じでしたか?
藤田:基本はバンド系でした。当時「イカ天」(=『三宅裕司のいかすバンド天国』)とかが流行って、バンドブームだったんですよ。クラスに1つはバンドがあったくらいで。ちょうどあの世代だったので、みんなでイカ天に出ようとか、いろいろ話してましたね。
CGW:楽器は何を担当されたんですか?
藤田:ギターとベースとドラムと......。メンバーが足りないバンドに呼ばれていって、何でもやって。今でも音楽は好きですね。仕事はゲームプログラマーでしたが、表現となると、音楽の方が好きですね。
CGW:後にゲームプログラマーになるということは、理系が好きだったんですか?
藤田:数学は得意ではありませんでしたが、好きだったんですよね。幾何学の証明問題などが好きでした。補助線を1本引くと見え方が変わるというところがあって。博士論文で触れた水平思考にもかかわってくるんですが。
CGW:プログラミングなどのご経験は?
藤田:そのころ家庭用のテレビがモニタに使えるホビーパソコンが出てきて、ちょっとしたブームになったんですよ。あの頃のパソコンって、みんなBASICが入っていて、プログラムしてましたよね。自分もちょっとプログラムをしてみたら、わりと他の人たちよりできたんですよ。それで母親にねだって、ヤマハのMSXを買ってもらいました。音楽用のソフトがついていたので。
CGW:いろんな楽譜を入力して、自動演奏をさせて?
藤田:最初の頃はやっていました。ただ、あの頃のシーケンサって、しょぼすぎてすぐに飽きちゃって。あとはBASICでゲームをつくって。友達に遊んでもらって、面白がってもらえて。高校の頃ですね。
CGW:自分も小学生のときにPC-6001というホビーパソコンを買って、できることがあまりなかったので、PLAY文を使って音楽の自動演奏をさんざんやって、そこで飽きたくちです。
藤田:似ていますね。今日の話にも関係がありますが、道具が目の届く範囲にないと、あんまりつくる気がしないんですよね。当時はコンピュータで何かつくってみようと思えるぐらいの規模で、ちょうど良かったですよね。
CGW:映画、音楽、アニメなどには興味がありませんでしたか?
藤田:もっとお金をもっている友達はX68000をもってましたね。そこで、いろいろなゲームを遊んでいました。ただ、MSXはあまりそういったものがなくて(笑)。むしろ『トロン』や、『スター・ウォーズ』でもワイヤーフレーム的なアニメーションだとか。ああいった表現が好きでした。たぶん3DCGが好きだったんでしょうね。当時のゲームは2D表現が主流でしたから。ああ、だから同じ2Dでも『スペースハリアー』などは好きでした。
CGW:自分もフライトシミュレータが好きでした。
藤田:面白いですよね。没入感があって。
人工生命(ALife)を通して3DCGに触れる
CGW:高校卒業後、明治大学の農学部に進学されます。
藤田:ミーハーな話で。1987年に利根川 進博士がノーベル賞を受賞されて、バイオテクノロジーがブームになったんですよ。もともと山や川が好きで、農業に興味があったので、じゃあ農学部に行こうと。あんまり深く考えてなかったですね。なので、卒論も書かずに逃げてしまいました。卒業研究が必修科目ではなかったんですよ。卒業研究は大変な割に、4単位しかもらえないので、良いやって。
CGW:大学でプログラムなどは学ばれましたか?
藤田:学びましたが、まだFORTRANの時代でした。コンピュータルームが電算室と呼ばれていた時代です。ただ、当時としては先進的なワークステーションが導入されていて、学生でも予約すれば使用することができました。それなりに3DCGができて、Cのコンパイラも入っていました。そこでビビッときちゃったんですね。
CGW:おお、ビビッと。
藤田:確かワークステーションのスクリーンセーバーか何かが、ALife(Artificial Life、人工生命)だったんですよ。または、ALifeの研究者がいて、ALifeのプログラムか何かが、ワークステーションに入っていたのかな。当時ALifeを研究する手法として、3DCGに注目が集まっていました。それをみて物理的な生命ではなく、システムとしての「論理的な生命」に興味がわいたんです。
普通に考えれば、3DCGによる運動シミュレーションじゃないですか。ただ、そこに生命が感じられる瞬間がある。それって面白いなあと。
CGW:人工知能のようにトップダウンではなく、ボトムアップで運動が生成されている点がポイントですね。
藤田:そうそう。ちょっと後の話になりますが、PlayStation(PS)で『パペット ズー ピロミィ』(1996)や『パネキット』(1999)などのゲームが発売されたのを覚えていますか? ああいったアプローチです。
CGW:それにしても、どこでスイッチが入るかわからないものですね。
藤田:まったくそうですね。農学部に入ったのも、そこにワークステーションがあったのも、そこでALifeについて知ったのも、全部偶然なわけで。
CGW:そこから3DCGエンジニアになられた経緯というのは?
藤田:卒業して、何をするわけでもなく、しばらくフリーターをしていました。そんなころ、デジタルハリウッドが開校したんです。1994年のことですね。シリコングラフィックスが触り放題という話を聞いて、問い合わせてみたら、もう授業は始まっているけどプログラムコースに空きがあると聞いて、途中から入れてもらいました。本格的に3DCGを触り始めたのは、そこからですね。
CGW:これもまた、すごい偶然ですね。
藤田:しかも、当時Visual Science Lab (VSL)というCGプロダクションがあって、デジハリと関係性が深かったんですよ。なので、デジハリのプログラムコースに入学したら、いつの間にかVSLにあったモーションキャプチャのオペレーターとして働くことになってしまって。
CGW:絶妙ですね。そういう人たちが集まるところにいったら、それがきっかけで仕事を得たという。時代を感じさせますね。
藤田:まったくそうですね。VSLからソニー・コンピュータエンタテインメント(SCE、現・ソニー・インタラクティブエンタテインメント/SIE)に転職したのも、そのながれなんです。当時ゲーム業界は3DCGの人材を欲しがっていて、ちょっとでも3Dのプログラムができたり、ツールが触れたりしたら、引く手あまたでした。自分も、それまで1回もゲームなんてつくったことがなかったのに、それで転職できたという。
CGW:SCEではどのようなタイトルにかかわられましたか?
藤田:SCEに移ったのが1995年で、そこからPS2が出た頃、だいたい2000年くらいまでいました。『ACONCAGUA』(2000)というアドベンチャーゲームのチームにいて、モーションキャプチャのデータをスクリプトにながし込むためのツールをつくったり、ワークフローの整備をしていました。
『ACONCAGUA』パッケージ
CGW:何人くらいのチームでしたか?
藤田:15人くらいでしたね。まだ技術開発部などの概念がなくて、タイトルごとにツール開発などが行われていました。プロデューサーが同じタイトルであれば、ツールやプラグインなどの共有が行われることもありましたが、プロデューサーがちがうと、そうした共有はなかったですね。
CGW:PSではSCEからライブラリの提供もありましたが、結局は必要なツールを、みんな自分たちでつくっていましたよね。ツールの完成度のちがいでゲームのクオリティが決まるといったこともありました。その上ゲーム機が変わると、道具もつくり直しになって。特にPS2の立ち上げのときは、ポリゴンを1枚出すだけで大変で、皆さん苦労されていましたよね。
藤田:そうそう。それが嫌になって、任天堂の方に行こうと思って。それで2000年にハル研究所(以下、ハル研)に移籍したんです。ちょうどニンテンドーゲームキューブの立ち上げの時期で、後に任天堂の社長に就任された岩田 聡さん(故人)が陣頭指揮を執られていました。僕はハル研の東京スタジオで、ゲームキューブの発表に使用するデモをつくっていました。100体以上のポケモンを画面に表示させて、リアルタイムに動かすというもので、そのためのレンダリングエンジンというか、ゲームエンジン的なものをつくっていました。
CGW:懐かしいですね。僕もその発表会にいて、取材していました。
藤田:ああ、そうなんですね。会場ですれちがっていたかもしれませんね。
[[SplitPage]]ゲームエンジン制作を経て懐疑派になる
CGW:他にハル研でどういった仕事をされていたんですか?
藤田:いろいろなツールをつくったり、ゲームエンジン的なものをつくっていたんですが、だんだんと疑問に感じるようになってきて......。ちょっと話が逸れますが、そもそもツールやミドルウェアって、開発で楽をするためにつくるわけですよね。
CGW:はいはい。
藤田:その考え方を拡大させていくと、ゲーム機のハードウェアを抽象化して、ゲーム機が変わっても、同じプログラムが動くようにしたい......そんなふうに考えるようになるじゃないですか。それが、どんどんリッチに、汎用的になっていくと、ゲームエンジンにつながるわけです。ちなみに私の博士論文では、こうした概念を「抽象化レイヤー」と呼んでいます。
ただ、そうしたエンジンをつくっているうちに、ゲームのアイデアが抽象化レイヤーに引っ張られてしまって、斬新な発想が出なくなるんじゃないか......そんな風に考えるようになったんです。
CGW:興味深いですね。なにかきっかけはありましたか?
藤田:ゲームエンジンの仕事が一段落したころ、アニメ『ポケットモンスター』の映像素材を使って、何かつくれないかという相談がありました。ゲームキューブで光ディスクが採用されて大容量のアニメーションが入れられるようになったので、それを活かしたコンテンツができないかって。そんなふうに、ざっくりとした話をふられることが多かったんですけど。
CGW:目に浮かぶようですね(笑)。それで、何をつくられたんですか?
藤田:ゲームキューブで動く動画ビューアでも良かったんですが、せっかくなので、アニメを見ながらボタンを押すと、アニメが静止して塗り絵になって、デジタル塗り絵ができる。そういうシステムをつくったんです。最終的に『ポケモンチャンネル~ピカチュウといっしょ!~』(2003)というゲームで使われました。ゲームの開発自体はNINTENDO64で『ピカチュウげんきでちゅう』をつくったアンブレラでしたが、ハル研でつくったシステムを採用してもらったんです。
『ポケモンチャンネル~ピカチュウといっしょ!~』パッケージ
CGW:それはまた、斜め上のシステムを提案されましたね。でも、そのことと抽象化レイヤーの話が、どうつながるんですか?
藤田:ポイントはそこなんですが、アニメの絵を静止して塗り絵にする、なんて変わったアイデアを実現しようとすると、自分がつくったゲームエンジンが邪魔になったんです。ゲームエンジンを迂回して、直接ハードを叩く必要がありました。便利だろうと思って道具をつくったんですけど、いざその道具ができてみたら、それに縛られるのは嫌だっていう。矛盾ですよね。
CGW:ああ、なるほど。
藤田:プログラマーであれば、そういった発想は無意識のうちに避けるものなんです。互換性がなくなってしまいますからね。アプリケーションの側を、抽象化レイヤー(=ゲームエンジン)に納めなくちゃいけない、という発想になってしまう。でも、それだと効率的かもしれないけれど、突拍子もないことはできないわけで。反対する人もいましたが、そうしたシステムをつくったら、アンブレラさんの方で使ってもらえました。
CGW:ちょうど端境期でしたね。ゲーム機の性能がプアだから、ハードを直接叩いて、色んなことをやりたいっていう考え方と、そろそろ工数を考えると、抽象化してゲームエンジンみたいなものを使っていかないとヤバイっていう。
藤田:まさにそんな時期でしたね。
CGW:ハル研を退職されたのは?
藤田:岩田さんがハル研を辞めて任天堂の社長になって、すぐくらいですね。ニンテンドーDSが発売された頃は、もう退職していました。その後、フリーのゲームプログラマーとして、『CUBELEO』(2009)というゲームの開発に参加しました。
『CUBELEO』公式サイトより
CGW:Wiiウェアのタイトルでしたね。任天堂のタイトルの中でも、ちょっと尖った、実験的なゲームを出していこうという試みで、Art Styleというブランドで展開されていました。
藤田:そうそう。Art Styleは岩田さん肝煎りのプロジェクトだったんですね。Art Styleブランドの多くはスキップというゲーム開発会社が受託していました。そこでプログラマーが足りないからって、声をかけていただきました。
CGW:ということは、別に藝大に行くからハル研を辞めたとか、そういう話じゃないんですね。
藤田:ではないですね。
CGW:そのままフリーランスのゲームプログラマーとして仕事をされる道もあったと思うんですが、そこから学術の方に移られた理由は何でしたか?
藤田:あんまり思い出せないんですが......もともと、ちゃんとした人じゃないんで(笑)。
その頃、藤幡正樹さんというメディアアーティストが好きで、その人が書かれた本をずっと読んでいたんです。けっこう難解な本なんですが、くり返し読むうちに、だんだん理解できるようになってきて。藤幡さんは本の中で、メディアをつくることが表現なんだと、くり返し説かれていました。それが抽象化レイヤーの話と符合したんです。藤幡さんがメディアと呼んでいるものが、自分にとっては抽象化レイヤーで、抽象化レイヤーと表現は切り離せないんだって。
そんな頃、たまたま藤幡さんが中心になって、藝大の大学院に映像研究科が新設されると聞いたんです。残念ながら1年目は受験対策が間に合わなくてダメで、その翌年に2期生として入りました。
藝大の大学院でメディアアートについて学ぶ
CGW:翌年に受験し直すのがすごいですね。ある程度モチベーションが高くないと......。当然その間は仕事をしなくちゃいけないだろうし。
藤田:いや、あんまりなかったんですよね。キャリアアップのために、前のめりで、というわけじゃなかったんです。映像研究科の講師には佐藤雅彦さんもいて、ここに行けば何か面白いことがあるんじゃないかと。道具をつくるのはハル研で死ぬほどやって、つくったのは良いけど、自分で使いたくない。ゲームエンジンをつくっただけど、ゲームエンジン否定派になったという。
CGW:その考え方が面白いです。
藤田:そういえば、Art Styleのゲームって、ひとつとしてゲームエンジンをそのまま使ったものはなかったんですよ。当時はUnityやUnreal Engineの登場前夜でしたが、僕がゲームキューブでつくったように、各社が独自で内製ゲームエンジンをつくって、その上でゲームを開発する試みが増えていました。にもかかわらず、そうしたやり方を否定して、ハードを直接叩いていたんです。そういうつくり方をしたかった人たちが、集まっていたんですね。
CGW:年齢層も高かったんですか?
藤田:高かったです。僕と同じか、僕より上の人もいました。スキップの創業メンバー、西 健一さんもその1人でした。
CGW:旧スクウェア出身のゲームクリエイターで、ラブデリック時代に『moon』(1997)という伝説のRPGを開発されたメンバーの一人ですね。アンチRPGを掲げた異色のタイトルでした。
藤田:そうです。以前からの知り合いで、僕に声をかけてくれたのも西さんです。それもあって、ゲームの可能性を広げることがミッションでした。岩田さんも、Art Styleは最終的にゲームじゃなくても良いと言っていましたね。
CGW:当時は国産コンソールゲームの地盤沈下が進んでいた時期でしたね。そんな中、従来の延長線上ではないゲーム機としてDSやWiiが出てきて、その上で実験的なブランドとしてArt Styleのような取り組みがありました。フラストレーションが溜まってる人が集まっていたんでしょうか?
藤田:そう思いますね。それに、岩田さん自身もメディアアート的なものが好きでしたしね。岩井俊雄さんと、実際にゲームをつくっていましたよね。
CGW:Art Styleの前に、DSでTouch! Generationsというブランド展開があり、そこで『エレクトロプランクトン』(2005)というゲームが発売されていましたね。Touch! Generationsもまた、岩田さんが深く関わったブランドで、そこから『ニンテンドッグス』、『脳トレ』などのヒット作が生まれました。
藤田:ああいうのが好きな方だったので、たぶんその延長という考え方だったと思うんですけどね。ただ、そこで集まった人がみんな、ゲームエンジンが好きになれないおじさんたちだったので、結局自分たちがやりたいことをやりはじめたという。そういう時期があってからの藝大ですね。
CGW:産業でゲームをつくるよりも、大学の方が自由に色んなものができて、面白そうだなっていう思いがあったんでしょうか?
藤田:うーん......その程度だったんじゃないですかね。来なくて良いって言われたら、別に良いやっていうぐらいでしたね。
CGW:大学院ではどういった作品をつくられましたか?
藤田:いま藝大のゲームコースを統括されている桐山孝司さんや、佐藤雅彦さんと一緒に、『計算の庭』(2007)、『指紋の池』(2010)をつくりました。彼らがやりたいことを聞いて、そのための道具をつくるところから、共同制作をするといった感じです。藤幡正樹さんとも『予測不可能な文房具』(2014)をつくっています。
CGW:それぞれ、どういった作品ですか?
藤田:『計算の庭』は、参加者がゲートを歩いてくぐりながら、与えられた数字になるように、計算をしていくという作品ですね。『指紋の池』は指紋センサに指を押し当てると、自分の指紋がモニタに表示されて、その中で動く様子が見られるというもの。『文房具』はスマートフォンをテーマとした研究・制作プロジェクトでした。
CGW:修士課程で終わらず、博士課程に進まれた理由は何でしたか?
藤田:直接的には、藤幡さんから勧められたことですね。メディアアートの研究者にさせたい、という思いがあったんじゃないかなあ......。ただ、そのとおりになはらなかったんですけどね。でも、藤幡さんとは博士号を取ってからも作品制作に関わったり、いろいろやっているので。何でしょうね。
CGW:日本のアカデミアだと、博士課程に進むことは、博士号を取って研究者になることと、ほぼ同義ですよね。ゲーム開発の現場に戻るのであれば、修士号で終わったと思うんです。
実際に藤田さんは2012年に博士号を取られたあとも、ニンテンドー3DSで『実写でちびロボ!』(2013)の開発に参加されていますね。ただ、そのあとは学術の世界に軸足をおいて活躍されています。
『実写でチビロボ!』公式サイトより
藤田:なるほど。確かに、何がしか特定の問題意識をもって大学院に進むだけであれば、修士課程で十分かもしれませんね。ただ僕の場合は、機械に対して人間がどう反応するかという、より広いテーマに関心がありました。そうすると何年あっても足りないわけです。実際、心理学をいまだに科学として認めない人たちがいますよね。あれは心理学じゃない、統計学だっていう。だんだんと、そうしたレイヤーにまで興味が移っていきました。
CGW:ゲームをつくるよりも、学問的な問題意識の方が強まっていったんですね。
藤田:うーん、そうですね。コンピューター文化というか、そういったものに対する研究や教育を、それこそ小学生レベルから始めなければダメだというか......。そういった問題意識に対して、藤幡さんがどんなふうに考えているのか知りたいという。そういった思いがあったのかもしれませんね。
CGW:深いですね。
藤田:例えばパーソナルコンピュータの父と言われるアラン・ケイという研究者がいますよね。彼はあらゆるメディアを超えたメディアとしてコンピュータを位置づけ、メタメディアという概念を提唱しました。その上でスモールトークという、今で言うビジュアルプログラミング言語のようなものができれば、世界中の人が自分に必要なソフトウェアを自分でつくりはじめる世界が来る......そういった前提で「ダイナブック構想」を立ち上げたんです。ただ、今のところそんな世界にはなってないじゃないですか。
もちろんビジネスとか、経済的合理性に基づいて、商用アプリケーションの世界が広がっていくのはわかります。ただ、表現とか、芸術の領域で他人がつくったソフトウェアを使って何かつくったところで、結局それはそのソフトウェアの可能性のひとつを指し示したにすぎないとも言えるじゃないですか。そうなってくると、結局のところ技術側の人間が芸術を理解するか、芸術側の人間が技術を理解するかしないと、アラン・ケイが言ってるような世界は来ないんですよ。そこに興味があったというか。
岩田氏の価値観が研究者的なモノの見方を育てた
CGW:面白いですね。ちょっと話がずれますが、日本でゲームの実務家教員というと、東京工芸大学の岩谷 徹さんをはじめ、旧ナムコのOB率が高いんですよ。それは会社の社風と関係があると思っているんですね。
藤田:言われてみればそうですね。
CGW:同じように藤田さんが、そんなふうに考えられるようになったのも、SCEやハル研の社風と関係があったんでしょうか?
藤田:そういう意味では、やっぱり岩田さんから影響を受けましたね。お忙しい方だったので、それほど一緒に仕事をした訳じゃないですけど。やっぱりモノの考え方というか、何というか。
岩田氏の言動は『岩田さん 岩田聡はこんなことを話していた。』、『ゲーム界のトップに立ったプログラマー 岩田聡の原点』に詳しい
CGW:「プログラムの経験が会社の経営に活きてくる」と言われていましたね。
藤田:そうですね。すっごく面白いのは、あれだけ理系で、バリバリのプログラマーだったにもかかわらず、占いのような一見、非合理的なものを否定していなかったことなんです。ハル研のみんなで食事をしているとき、話が占いをはじめとした、エセ科学的なものを否定するようなながれになったことがあるんです。そのときも岩田さんは「いや、これだけ長い歴史で淘汰されなかったのだから、科学的に根拠がないからといって、意味がないとは言えない」と言ってましたね。
CGW:岩田さんらしいコメントですね。
藤田:自然科学的にではなく、人文科学的に捉えれば別の側面が見えてくると。これに限らず、岩田さんは理系一辺倒じゃなかったですしね。
CGW:アートとかグラフィックとか、文系的なものに対して関心が高かったと聞いています。
藤田:最終的に自分たちがやってるのは文化なんだという意識がありました。そこから「技術の完成で仕事は終わりじゃない。自分たちの仕事を文化にまで昇華させないと」という考え方を教えられたという感じです。余談ですが岩田さんといえば、Macが大好きな方でした。Macが瀕死状態だった時期も使い続けていて、Apple製品を文化と捉えて、大事にしていました。使えもしないNewtonなどもお持ちでした。
CGW:その話は聞いたことがあります。
藤田:だからこそ、WiiやDSで他のゲーム機と同じようなハイスペック路線をとることもできたはずなんです。でも、そういうことは言わずに、僕らがつくろうとしているのは文化だから、ゲーム機を完成させるだけでは不十分なんだと。それを見たとき、触ったときに、人間がどう感じるかっていうところまで、あわせて考える必要があるんだって。そんな風に考えられていた方なんですね。
CGW:まさに、機械と人間の関係性の話につながりますね。当時はまだUI/UXという言葉や、ゲーム体験といった言葉はありませんでしたが、そういったものが大事なんだということを、よく話されていましたね。
藤田:そうですね。だから、自分がそういった分野に興味関心が移っていったというのは、岩田さん自身の考え方に影響を受けた結果だというのは、あったかもしれないですね。
E3 2001でゲームキューブを発表する任天堂の宮本 茂氏(左)と岩田 聡氏(右)
CGW:それで博士論文「創作環境論」を書かれるわけですね。概要がWebに公開されていますが、3DCGプログラマーとして作品制作に係わってきた体験談がベースになっていますよね。
藤田:そうですね。基本的にはケーススタディです。
CGW:論文の主査に大学院時代の作品制作でもご一緒された、桐山孝司先生の名前がありますね。今はゲームコースの旗振り役を務められています。桐山先生から、何かアドバイスは受けましたか?
藤田:博士論文の査読で1年失敗してるんですよ。はじめに書いたものが、あまりにもまとまってなくて、1年延びてるんです。その1年で、それまで自分がやってきた、ありとあらゆる芸術家とのコラボレーションについて、メールのやりとりから徹底的に洗い出しました。中にはコンピュータとまったく関係ない芸術家もいるんですが、そういう人たちとの活動をアーカイブして、そこから抽象化された概念を見つけ出すように、桐山先生から指導を受けました。まがりなりにも博士論文をまとめられたのは、桐山先生のおかげです。
CGW:自分の体験談を書くだけでは、論文にならないですよね。
藤田:そうなんですよ。それでも修士課程までなら、作品主体でOKでした。それに藝大では博士課程でも、プラクティカルドクターとセオリティカルドクターという区分があり、前者であれば作品の新規性や社会に対する影響度が評価の対象になるので、論文の比重はそこまで大きくありません。それに対して僕は後者でしたので、作品も必要でしたが、論文の完成度が求められました。
CGW:博士論文で得られた知見を粗っぽくまとめると、「新しい作品をつくることと、新しい道具をつくることは、不可分の存在である」ということですよね。それ自体は良くわかりますし、クリエイターであれば感覚的に理解されていることではないかと思うのですが、それを体系化して論文化するのは、すごく大変だなと思いました。まさに茨の道というか。
藤田:ゲームの研究って、まだ本当にそのレベルだと思うんですよね。もう本当にケーススタディの集合体というか。自分が体験したものの中から抽象化された、本当に小さいものを結論として貯めていくしかない状況にあると思っていて。逆に言うと、他と比べるものがないから、博士論文として認められたんだと思うんですよ。それでも、これまで暗黙知的に「当たり前」だとされていたことを、あえて言語化、理論化、体系化しないと、研究の遡上に載らないという。
CGW:論文ではエドワード・デボノの水平思考や、そこから転じて横井軍平さんの「枯れた技術の水平思考」に関する引用もありますね。任天堂でゲーム&ウォッチやゲームキューブの開発を主導された、伝説のゲーム開発者の1人です。
デボノが提唱した水平思考(左)と、その思想を商品開発に生かした、故・横井軍平氏(右)
藤田:デボノの提唱した水平思考は、一般的には問題解決のために既成の理論や概念にとらわれずアイデアを生み出す方法だとされていますが、もう少し深く読み込んでいくと、元になった概念の粒度を変えるという考え方なんですね。粒度を変えるからこそ、別の見方が生まれてくるわけで。その上で横井さんが言われているのが「枯れた技術の」水平思考。既に普及していて、コストがかからない技術を応用すれば、アイデア次第でヒット商品が開発できるというものですね。
CGW:論文ではデボノの水平思考について引用されていて、その一例として横井さんのエピソードを示したというわけですね。
藤田:そうですね。例えば、一般的に太陽電池と言われる製品がある。それを文字通り受け止めると、発電のための装置になるわけですが、粒度を下げて素子レベルにまで広げると、光が当たると電圧が変わる物質になる。つまり光センサになるわけですね。横井さんはその性質を使って、光線銃をつくったと。
CGW:有名なエピソードですね。
藤田:同じように言葉をパズルのピースとして捉えると、ピースによってできる形は、ピースの組み合わせ方に限定されてしまう。その一方で、同じピースでも複数に分割できることに気づけば、そこで組み合わせのパターンが増える。それがデボノの言う水平思考です。
CGW:それが先ほどから言われている、仮想レイヤーの話につながるわけですね。
藤田:仮想レイヤーというピースがあまりにも良くできているので、今やそれを使ってゲームをつくることを当然のこととして受け止めている時代になっていると思うんですね。UnityやUE4はその好例で。しかもこれからUE5の時代になるわけで。ただ、それって確かに、ものすごく可能性が広いキャンバスなんだけど、結局はその範囲での可能性にすぎなくて。
CGW:お釈迦様の手のひらの上だという。
藤田:そうですね。そういう風に思えてしまうんですよね。
CGW:昔はそれほど可能性が広くなかったので、すぐに限界が見えましたね。
藤田:そうですね。PSやN64のころは、何か抽象化レイヤーができたとたんに、こういうゲームしかできないという風に、決まっていたわけで。ただ、今でもゲームエンジンには開発上の文脈があって、それぞれで向き不向きがあると思っています。
[[SplitPage]]エンジニアとアート、2つの接点を探る
CGW:道具づくりと作品表現が不可分だという指摘は、フルCGムービーの歴史がよく示していますね。映画『トイ・ストーリー』で玩具が主人公だったのは、テクスチャや質感の表現に限界があったからでした。そこから新作のビジョンに従って、群衆シミュレーション、ファーシェーダ、流体表現などと、様々な技術開発が行われ、作品の幅が広がっていきました。
同じようにゲーム開発でも、昔はゲームデザイナーが立てた企画をプログラマーが形にしていました。それが近年ではプログラマーがゲームエンジンをつくり、その中でゲームデザイナーがコンテンツをつくるといった具合に、変わってきています。そのためのコストが尋常ではなくなってきたので、UnityやUE4などの商用エンジンを活用する例が増えています。
もっとも、ゲームデザイナーがやりたいこととゲームエンジンの機能に齟齬が生まれることがあるので、プログラマーがプラグインをつくったり、機能を拡張したりといったことが、まだまだ必要なんですけどね。
藤田:そんなふうに齟齬が生まれるのであれば良いんですが、そのうちゲームデザイナーからゲームエンジンでできない表現が、提案されなくなっていくんじゃないか......それが怖いんですね。僕らの時代には、そもそも抽象化レイヤーがありませんでした。何かしようと思ったら、ツールからつくらざるを得ませんでした。それがいつの間にか主客逆転が進んでいて。
CGW:そういえば生前、横井さんにインタビューしたことがあるんですよ。『スーパーマリオブラザーズ』(1985)をはじめ、任天堂の中でも宮本さんが王道のゲームづくりをされていた一方で、横井さんは『ファミリーコンピュータ ロボット』(1985)のような、ちょっと変わった、玩具的なゲームもつくられていました。
その理由について、「それまで任天堂は玩具をつくっていた。玩具は飽きられる宿命にあるし、飽きられなければ新製品がつくれないので、逆に困る。だからファミコンが発売された直後から、ある程度は売れるように、延命策を考えていた。そのひとつが『ファミリーコンピュータ ロボット』だった。ただ、実際には予想を超えて売れてしまった」という話をされていました。その上ゲーム自体も飽きられることなく、今に至っているわけですが。
藤田:その話は面白いですね。
CGW:今までの議論に引き寄せて考えると、ファミコンを玩具と捉えると、いつかは飽きられるという発想になります。それがコンピュータだと捉えると、ソフトウェアで様々なゲーム体験ができますし、機能を拡張することもできる、そんな風に言えそうですね。
藤田:そうですね。飽きられない、というのは文化として考える上で、1つのキーワードになりそうですね。
CGW:話を戻すと、博論を取られた後も、学術にいらっしゃる訳ですよね。やっぱり教育とか、研究とかがお好きなんですか?
藤田:先ほどの話にちょっと被るんですが、僕は「抽象化レイヤーを自ら壊して再構築できる」ことが、アラン・ケイが言っていた、自分で必要なソフトをつくることだと思ってるんです。ただ、それをやるために、技術者が芸術を学ぶか、芸術家が技術を学ぶか、2つの道があると思っているんですね。
東京国際工科専門職大学で常勤講師をしながら、藝大のゲームコースで非常勤講師もやっているのも、そのためです。専門職大学では前者を、藝大では後者を教えたくて。
CGW:なるほど。
『Z』瀬尾 宙氏(ディレクター/東京藝術大学大学院映像研究科修了)、木村健太郎氏(メンター/スクウェア・エニックス)、藤田至一氏・室山順子氏(エンジニア)。藤田氏は藝大のゲームコースでも非常勤講師を務めつつ、学生の作品制作を支援している。
藤田:藝大のゲームコースでは、アーティスト志向の学生に対して、1対1でプログラムを教えつつ、作品制作のサポートをしています。最近ではVRをやりたい学生が多いんですよ。VRって正直、UnityやUE4でVRのプラグインをインストールすれば、割と手軽に実装できてしまうんですね。ただ、それだけでは不可能な表現が出てくる。なので、はじめに何がしたいかアイデアを出してもらって、その上で仮想レイヤーが1回ないものとして考えてみる、そういったことをやっています。まあ、試行錯誤の連続なんですが。
これに対して東京国際工科専門職大学では、技術者を志す学生に、もう少し文化とか、それを使う人間とか、そういった部分にまで視野を広げられるような人になってほしいと思っていて。技術を完成させるところでゴールじゃなくて、それが世の中に文化として認められるところまで、考えられるようになってねと。
CGW:実際、社会的な意味合いがないと、技術は広がりもしないし、定着もしないですよね。
藤田:そうそう。VRでいえばもう、3回くらい波が来ていますよね。それも結局、技術だけで終わっていて、それを活かしたキラーコンテンツがつくれなかったから。横井さんの言葉を借りれば、VRが飽きられないためにこう使えば良いんだっていうのが、まだ発見できてないからだと思います。
映像でいえば、ただの記録映画で始まったものが、フィルムを切って繋げたら、そこで物語がつくれるようになったわけですよね、そうしたVRならではのカット編集的な手法が、まだ見つかってないだけで。VRは常に主観視点だから、ゲームのようにカメラをプレイヤーから強制的に奪って、イベントシーンを挟み込むような演出ができませんよね。じゃあ、どうするかと。
CGW:まだまだVRは映画の歴史でいうと、見世物小屋の時代に留まっているのかもしれませんね。
藤田:それに当時は映写機といってもシンプルで、粒度が変えられるレベルの機械だったじゃないですか。今はハードウェアの上に、ソフトウェアのとんでもない厚いレイヤーができてしまって、なかなか粒度を変えられないですよね。そのためには、やっぱり技術を知らなくちゃいけなくて。技術で抽象化レイヤーを1回組み替えた上で、さらに文化まで到達できる手法。そこに興味があるし、学生にも、そこまでやれる人になってほしいんですよ。
CGW:ゲームやデジタルエンターテインメントは、技術の進化で表現の幅が広がっていきます。そのため答えがずっと出ないかもしれませんが、人生を通して、そうした可能性に挑戦し続けられる人っていうことですね。ゲームエンジンの中で新しい積み木の組み合わせ方を探るだけではなくて、ゲームエンジン自体をつくり替えていける人というか。
藤田:そうですね。
CGW:京都にBaiyonさんというクリエイターがいて、その方がQ-Gamesと『PixelJunk Eden』というゲームをPCとPS3でつくられたときの話を聞いたことがあります。Baiyonさんはアナログの世界のクリエイターなので、色指定がCMYKでしかできないんですね。でもゲームのアーティストはRGBの世界で生きてきたので、そこでたくさん意見のぶつかり合いがあって。でも、それがあったから、今までにはない色づかいのゲームができたそうです。
『PixelJunk Eden』(Steam版)
藤田:すごく面白いですね。その事例も色を色としてとらえず、色情報という粒度まで下げたからですよね。その上でCMYKとRGBの世界を繋ぐ「道具」の発明が必要だったと思うんですが、そんな風に道具レベルでつくっていくと、新しいアイデアが、どんどん出てくるんですね。それを博論では「事故」と称しています。実際、色を混ぜて白くなる人たちと、黒くなる人たちですから、相当ちがったと思うんですよね。
CGW:ゲームづくりはそうした事故の連続だと言いますね。もっと絵を描き込みたい人と、できるだけ速くプログラムを動かしたい人とでは、そもそもの考え方が異なるわけで。
藤田:そうですね。そうした事故はバグの遠因にもなりますが、ときにはバグを残したまま開発が進むこともあります。その方が、面白いからって。
博士号取得は結果ではなくプロセスに価値がある
CGW:いろいろと伺ってきて、たいへん面白かったんですが、最後に博士号を取る意味について教えてください。藤田さん自身、博士号を取って何か変わったことはありますかとか。
藤田:書くことで、より深く理解できるようになる。アーティストは作品をつくることで理解するといいますが、それと良く似ていて。博論で提唱した抽象化レイヤーの存在であったり、その解決策について、おぼろげながらにでも提示するなんてことは、大学院に行く前から、漠然と頭の中にあったと思うんです。ただ、それを言語化する行為に意味があったと思っています。
同じようなことが、プログラミング言語の世界でいう「デザインパターン」という概念にも似ています。はじめてデザインパターンについて聞いたとき、今さら言われなくても昔からやっていた、と感じたプログラマーが多かったと思います。ただ、そうした概念に対して名前を付けるという行為に、ものすごく意味があったわけです。
僕らが学問の領域でやっていることも同じで、博論でもそんなに大きい話はしていません。あくまで、自分なりの小さいブロックをつくったにすぎないんです。そうしたブロックが積み重なって、最終的にはデザインパターンのような、大きな研究になる。それに対して少なからず寄与できれば、今の段階では良しとするというか。
CGW:博士号は研究の入り口だと良く言われますよね。逆に博士論文を書かずに終わっていたとしたら、どうでしょうか?
藤田:う~ん、どうだろう。逆に質問させていただくと、博士論文を書くのは、それなりの労力なんだから、それを達成した人間は、何か前後でちがったんじゃないかって思われますか?
CGW:そうですね。正直、生半可な気持ちでは取れないと思いますし。それに実務家教員で、博士号がないことで、業務に支障を感じられている人もいるかと思います。遠藤雅伸さんも「博士号がないと海外で研究者として認められないから取った」と言われていましたね。
藤田:博士号取得が目的で、研究が手段というのは個人的には違和感があります。目的が研究で、結果が博士号取得が自然なながれではないでしょうか。私の場合、博士論文の中でアラン・ケイのいう「誰もが自分のためのソフトウエアを自分でつくる世界」を実現するためには、教育を含めた文化が重要だという結論にいたり、研究・教育のキャリアを本格的にスタートしたという感じです。
CGW:なるほど。
藤田:なので、やっぱり博士号は結果ではなくて、プロセスに価値があるんだと思います。博士論文って、主査と副査の先生方が数ヶ月ごとに集まって、指導と称して自分の論文に対してケチをつけてくれるんです。その面子が自分が昔から知っている藤幡真樹さんだったり、佐藤雅彦さんだったり、自分が若い頃に憧れていた人たちなんですよ。そういった人たちを2時間、椅子に座りつけて、自分の意見を述べて、反論を聞くなんて体験は、博士論文を書かないとできない。
CGW:贅沢な話ですね。
藤田:そうなんです。だから僕の場合、博士号で得た結論は本当にちっぽけなものなんで。むしろ僕としては、そうした特権にありつくために、博士論文を書いたのかもしれないですね。なにしろ分刻みで動いている人たちを2時間縛り付けて、俺の話を聞けっていう会を開くことができるわけで。もちろんボロクソに言われますし、凹みますけど、ありがたかったですね。いくらお金を払っても、そんな環境はつくれないですよ。
CGW:メディアの世界でも、会いたい人がいたら仕事にしろと、良く言われます。プライベートでは忙しくて会ってくれないけれど、取材なら会ってくれると。
藤田:それと同じかもしれませんね。
CGW:ありがとうございました。すごく納得できる話でした。