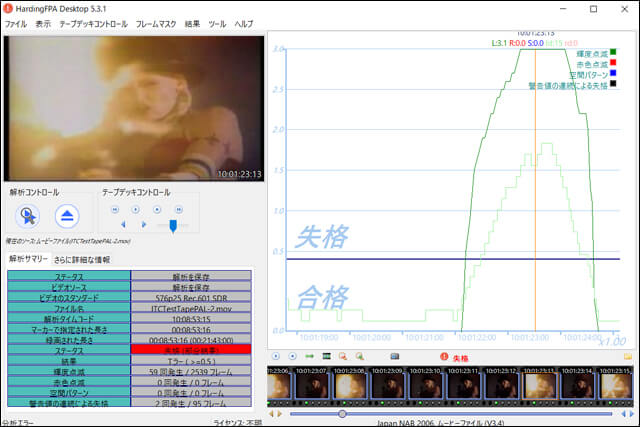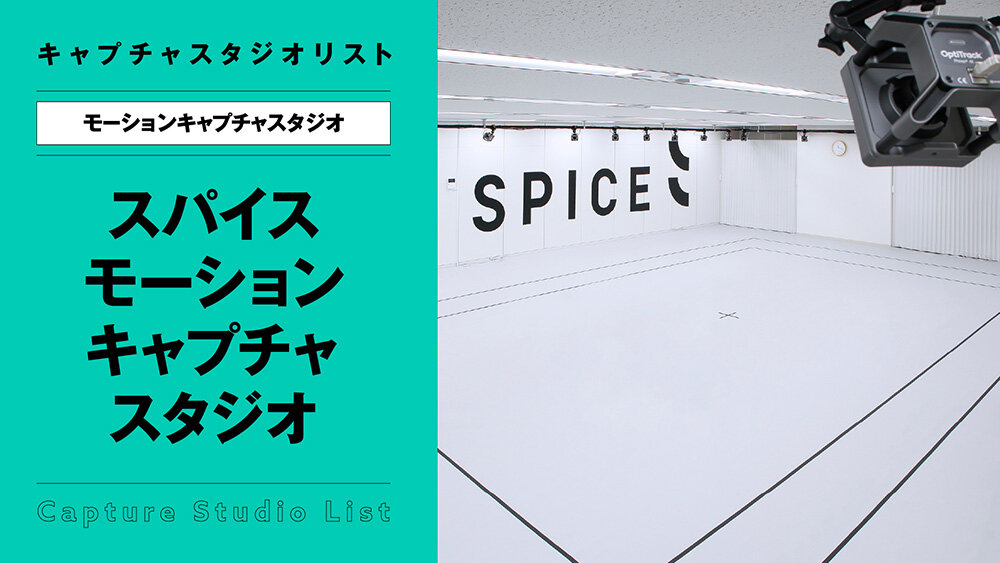エンジニアとアート、2つの接点を探る
CGW:道具づくりと作品表現が不可分だという指摘は、フルCGムービーの歴史がよく示していますね。映画『トイ・ストーリー』で玩具が主人公だったのは、テクスチャや質感の表現に限界があったからでした。そこから新作のビジョンに従って、群衆シミュレーション、ファーシェーダ、流体表現などと、様々な技術開発が行われ、作品の幅が広がっていきました。
同じようにゲーム開発でも、昔はゲームデザイナーが立てた企画をプログラマーが形にしていました。それが近年ではプログラマーがゲームエンジンをつくり、その中でゲームデザイナーがコンテンツをつくるといった具合に、変わってきています。そのためのコストが尋常ではなくなってきたので、UnityやUE4などの商用エンジンを活用する例が増えています。
もっとも、ゲームデザイナーがやりたいこととゲームエンジンの機能に齟齬が生まれることがあるので、プログラマーがプラグインをつくったり、機能を拡張したりといったことが、まだまだ必要なんですけどね。
藤田:そんなふうに齟齬が生まれるのであれば良いんですが、そのうちゲームデザイナーからゲームエンジンでできない表現が、提案されなくなっていくんじゃないか......それが怖いんですね。僕らの時代には、そもそも抽象化レイヤーがありませんでした。何かしようと思ったら、ツールからつくらざるを得ませんでした。それがいつの間にか主客逆転が進んでいて。
CGW:そういえば生前、横井さんにインタビューしたことがあるんですよ。『スーパーマリオブラザーズ』(1985)をはじめ、任天堂の中でも宮本さんが王道のゲームづくりをされていた一方で、横井さんは『ファミリーコンピュータ ロボット』(1985)のような、ちょっと変わった、玩具的なゲームもつくられていました。
その理由について、「それまで任天堂は玩具をつくっていた。玩具は飽きられる宿命にあるし、飽きられなければ新製品がつくれないので、逆に困る。だからファミコンが発売された直後から、ある程度は売れるように、延命策を考えていた。そのひとつが『ファミリーコンピュータ ロボット』だった。ただ、実際には予想を超えて売れてしまった」という話をされていました。その上ゲーム自体も飽きられることなく、今に至っているわけですが。
藤田:その話は面白いですね。
CGW:今までの議論に引き寄せて考えると、ファミコンを玩具と捉えると、いつかは飽きられるという発想になります。それがコンピュータだと捉えると、ソフトウェアで様々なゲーム体験ができますし、機能を拡張することもできる、そんな風に言えそうですね。
藤田:そうですね。飽きられない、というのは文化として考える上で、1つのキーワードになりそうですね。
CGW:話を戻すと、博論を取られた後も、学術にいらっしゃる訳ですよね。やっぱり教育とか、研究とかがお好きなんですか?
藤田:先ほどの話にちょっと被るんですが、僕は「抽象化レイヤーを自ら壊して再構築できる」ことが、アラン・ケイが言っていた、自分で必要なソフトをつくることだと思ってるんです。ただ、それをやるために、技術者が芸術を学ぶか、芸術家が技術を学ぶか、2つの道があると思っているんですね。
東京国際工科専門職大学で常勤講師をしながら、藝大のゲームコースで非常勤講師もやっているのも、そのためです。専門職大学では前者を、藝大では後者を教えたくて。
CGW:なるほど。
『Z』瀬尾 宙氏(ディレクター/東京藝術大学大学院映像研究科修了)、木村健太郎氏(メンター/スクウェア・エニックス)、藤田至一氏・室山順子氏(エンジニア)。藤田氏は藝大のゲームコースでも非常勤講師を務めつつ、学生の作品制作を支援している。
藤田:藝大のゲームコースでは、アーティスト志向の学生に対して、1対1でプログラムを教えつつ、作品制作のサポートをしています。最近ではVRをやりたい学生が多いんですよ。VRって正直、UnityやUE4でVRのプラグインをインストールすれば、割と手軽に実装できてしまうんですね。ただ、それだけでは不可能な表現が出てくる。なので、はじめに何がしたいかアイデアを出してもらって、その上で仮想レイヤーが1回ないものとして考えてみる、そういったことをやっています。まあ、試行錯誤の連続なんですが。
これに対して東京国際工科専門職大学では、技術者を志す学生に、もう少し文化とか、それを使う人間とか、そういった部分にまで視野を広げられるような人になってほしいと思っていて。技術を完成させるところでゴールじゃなくて、それが世の中に文化として認められるところまで、考えられるようになってねと。
CGW:実際、社会的な意味合いがないと、技術は広がりもしないし、定着もしないですよね。
藤田:そうそう。VRでいえばもう、3回くらい波が来ていますよね。それも結局、技術だけで終わっていて、それを活かしたキラーコンテンツがつくれなかったから。横井さんの言葉を借りれば、VRが飽きられないためにこう使えば良いんだっていうのが、まだ発見できてないからだと思います。
映像でいえば、ただの記録映画で始まったものが、フィルムを切って繋げたら、そこで物語がつくれるようになったわけですよね、そうしたVRならではのカット編集的な手法が、まだ見つかってないだけで。VRは常に主観視点だから、ゲームのようにカメラをプレイヤーから強制的に奪って、イベントシーンを挟み込むような演出ができませんよね。じゃあ、どうするかと。
CGW:まだまだVRは映画の歴史でいうと、見世物小屋の時代に留まっているのかもしれませんね。
藤田:それに当時は映写機といってもシンプルで、粒度が変えられるレベルの機械だったじゃないですか。今はハードウェアの上に、ソフトウェアのとんでもない厚いレイヤーができてしまって、なかなか粒度を変えられないですよね。そのためには、やっぱり技術を知らなくちゃいけなくて。技術で抽象化レイヤーを1回組み替えた上で、さらに文化まで到達できる手法。そこに興味があるし、学生にも、そこまでやれる人になってほしいんですよ。
CGW:ゲームやデジタルエンターテインメントは、技術の進化で表現の幅が広がっていきます。そのため答えがずっと出ないかもしれませんが、人生を通して、そうした可能性に挑戦し続けられる人っていうことですね。ゲームエンジンの中で新しい積み木の組み合わせ方を探るだけではなくて、ゲームエンジン自体をつくり替えていける人というか。
藤田:そうですね。
CGW:京都にBaiyonさんというクリエイターがいて、その方がQ-Gamesと『PixelJunk Eden』というゲームをPCとPS3でつくられたときの話を聞いたことがあります。Baiyonさんはアナログの世界のクリエイターなので、色指定がCMYKでしかできないんですね。でもゲームのアーティストはRGBの世界で生きてきたので、そこでたくさん意見のぶつかり合いがあって。でも、それがあったから、今までにはない色づかいのゲームができたそうです。
『PixelJunk Eden』(Steam版)
藤田:すごく面白いですね。その事例も色を色としてとらえず、色情報という粒度まで下げたからですよね。その上でCMYKとRGBの世界を繋ぐ「道具」の発明が必要だったと思うんですが、そんな風に道具レベルでつくっていくと、新しいアイデアが、どんどん出てくるんですね。それを博論では「事故」と称しています。実際、色を混ぜて白くなる人たちと、黒くなる人たちですから、相当ちがったと思うんですよね。
CGW:ゲームづくりはそうした事故の連続だと言いますね。もっと絵を描き込みたい人と、できるだけ速くプログラムを動かしたい人とでは、そもそもの考え方が異なるわけで。
藤田:そうですね。そうした事故はバグの遠因にもなりますが、ときにはバグを残したまま開発が進むこともあります。その方が、面白いからって。
博士号取得は結果ではなくプロセスに価値がある
CGW:いろいろと伺ってきて、たいへん面白かったんですが、最後に博士号を取る意味について教えてください。藤田さん自身、博士号を取って何か変わったことはありますかとか。
藤田:書くことで、より深く理解できるようになる。アーティストは作品をつくることで理解するといいますが、それと良く似ていて。博論で提唱した抽象化レイヤーの存在であったり、その解決策について、おぼろげながらにでも提示するなんてことは、大学院に行く前から、漠然と頭の中にあったと思うんです。ただ、それを言語化する行為に意味があったと思っています。
同じようなことが、プログラミング言語の世界でいう「デザインパターン」という概念にも似ています。はじめてデザインパターンについて聞いたとき、今さら言われなくても昔からやっていた、と感じたプログラマーが多かったと思います。ただ、そうした概念に対して名前を付けるという行為に、ものすごく意味があったわけです。
僕らが学問の領域でやっていることも同じで、博論でもそんなに大きい話はしていません。あくまで、自分なりの小さいブロックをつくったにすぎないんです。そうしたブロックが積み重なって、最終的にはデザインパターンのような、大きな研究になる。それに対して少なからず寄与できれば、今の段階では良しとするというか。
CGW:博士号は研究の入り口だと良く言われますよね。逆に博士論文を書かずに終わっていたとしたら、どうでしょうか?
藤田:う~ん、どうだろう。逆に質問させていただくと、博士論文を書くのは、それなりの労力なんだから、それを達成した人間は、何か前後でちがったんじゃないかって思われますか?
CGW:そうですね。正直、生半可な気持ちでは取れないと思いますし。それに実務家教員で、博士号がないことで、業務に支障を感じられている人もいるかと思います。遠藤雅伸さんも「博士号がないと海外で研究者として認められないから取った」と言われていましたね。
藤田:博士号取得が目的で、研究が手段というのは個人的には違和感があります。目的が研究で、結果が博士号取得が自然なながれではないでしょうか。私の場合、博士論文の中でアラン・ケイのいう「誰もが自分のためのソフトウエアを自分でつくる世界」を実現するためには、教育を含めた文化が重要だという結論にいたり、研究・教育のキャリアを本格的にスタートしたという感じです。
CGW:なるほど。
藤田:なので、やっぱり博士号は結果ではなくて、プロセスに価値があるんだと思います。博士論文って、主査と副査の先生方が数ヶ月ごとに集まって、指導と称して自分の論文に対してケチをつけてくれるんです。その面子が自分が昔から知っている藤幡真樹さんだったり、佐藤雅彦さんだったり、自分が若い頃に憧れていた人たちなんですよ。そういった人たちを2時間、椅子に座りつけて、自分の意見を述べて、反論を聞くなんて体験は、博士論文を書かないとできない。
CGW:贅沢な話ですね。
藤田:そうなんです。だから僕の場合、博士号で得た結論は本当にちっぽけなものなんで。むしろ僕としては、そうした特権にありつくために、博士論文を書いたのかもしれないですね。なにしろ分刻みで動いている人たちを2時間縛り付けて、俺の話を聞けっていう会を開くことができるわけで。もちろんボロクソに言われますし、凹みますけど、ありがたかったですね。いくらお金を払っても、そんな環境はつくれないですよ。
CGW:メディアの世界でも、会いたい人がいたら仕事にしろと、良く言われます。プライベートでは忙しくて会ってくれないけれど、取材なら会ってくれると。
藤田:それと同じかもしれませんね。
CGW:ありがとうございました。すごく納得できる話でした。