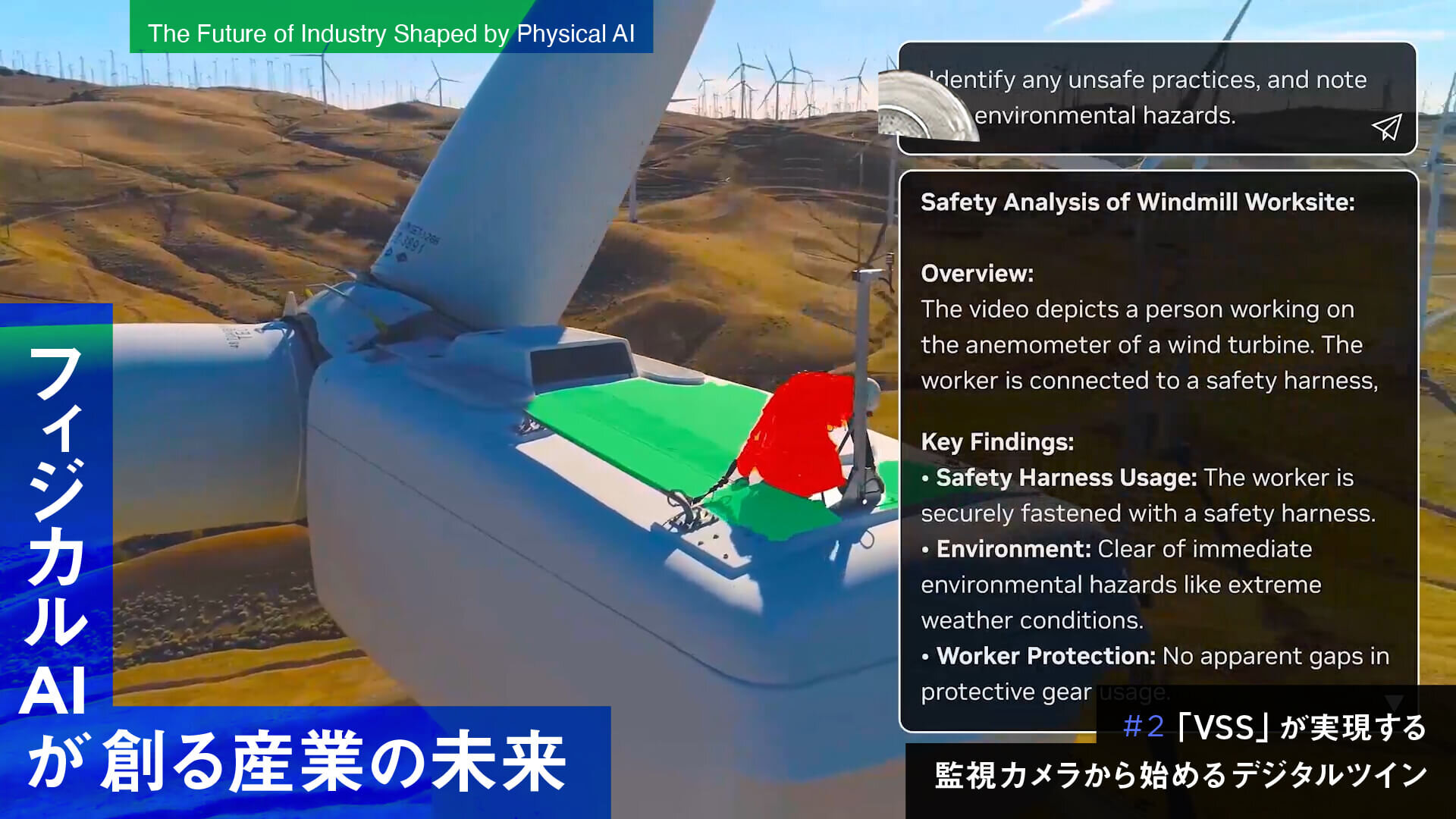相手のメリットへの不理解が落とし穴をつくる
CGW:上手く作用すれば、産学連携はうれしい事態に発展するわけですね。その一方で、上手く作用しない場合は、うれしくない事態になってしまいますよね。これまでに経験した課題を教えてください。
長谷川:先ほど、簗瀬さんが「研究費を大学に支払うかたちはとっていません」とおっしゃったのを聞いて驚きました。研究課題を発掘し、パートナーを選定し、共同研究を開始する段階まで進むと、一緒に共同研究をしている教員や学生以外の方々、例えば大学の産学連携機関や、TLO(Technology Licensing Organization:大学の研究者の研究成果を特許化し、それを企業へ技術移転する法人)の方々も関わってきて、研究成果を利用するためのライセンス契約が大前提となり、話が止まるケースがあります。当社が研究費を負担し、社内の知見や情報を提供した上で、その成果を使う際にはライセンス料が必要で、競合他社にも販売するとなると、その大学との共同研究の有用性を社内で説明できず、八方塞がりになってしまいます。
簗瀬:そういう展開になることが、私にとっては意外です。例えば私がUnityの機能開発のために大学に研究を委託するなら、研究費を支払うのは当然だと思います。しかし、そうではない先端的な研究で、研究費や特許使用料の支払いを必須にするのは無理があるのではないでしょうか。
三上:難しい課題で、よく聞く話でもありますね。2004年に国立大学が法人化して以降、運営費交付金は年々減少しており、国立大学も自力で運営費を集める必要に迫られています。その結果、外部から運営費を調達してくる組織や、知的財産をお金に変えるTLOのような組織が活性化したという背景があります。もちろん公立・私立大学においても運営費の確保は重要で、類似の組織がつくられています。共同研究に携わる先生が研究成果の利用に対して柔軟な考えをもっていたとしても、大学の内規で研究費や特許の運用方法が決まっていると、特約を設けるのは難しいだろうと思います。
長谷川:研究環境を維持するために運営費が必要であることは理解できますので、研究費などをお支払いすること自体は必要だと考えています。ただ、産学連携には様々なやり方があり、本格的な共同研究や特許出願にいたらないケースもあり得ます。例えば、岡山県立大学の横川智教先生と一緒にモデル検査をゲーム開発に適用する研究(詳細は月刊『CGWORLD』vol. 270で紹介)に取り組んだときには、課題共有をした後、早々に論文共著にいたりました。インターンの受け入れや、大学での講義の実施も産学連携に含まれると思いますし、それらが共同研究のきっかけになるケースもあるでしょう。最適なやり方を探っている段階で大学側の方針を大前提にされると、途端に話が進まなくなるので、幅広い選択肢をもつことが重要だと思います。
CGW:大学のメリット確保を大前提にしすぎると、企業のメリットがなくなってしまったり、産学連携の柔軟性が損なわれてしまうわけですね。
簗瀬:長谷川さんの話とは対照的に、企業が大学のメリットを理解していない場合もありますね。例えば、ある企業が新製品の評価実験を大学に委託した際に、「発表前の製品なので、実験結果の学外での発表は控えてください」という条件が付けられ、委託費用の支払いもなかったというケースがありました。成果を公表できず、費用もいただけないとなると、大学にはほとんどメリットがありません。成果の公表を了承し、研究費を出していたにも関わらず、明確なゴールが定まっておらず、成果の活用もしていなかったというケースもありました。共同研究は口実で、企業の目的は学生の採用だったというのが実情です。共同研究や講師の派遣を行なった結果、学生の採用につながったという事例は古今東西にあると思いますが、最初から採用を主目的にするのはおかしいと思います。
三上:お互いのメリットに対する理解が浅いと、思わぬ落とし穴にはまったり、暗礁に乗り上げたりしがちですね。私は、そもそも「産」と「学」を分けて考えること自体に問題があるように思っています。カンファレンスや学会で産業界と学術界の方々が情報交換をしたり、産学連携に関する抱負や考えを共有したりできる場が増えていけば、産学連携が上手く作用するケースも増えていくでしょう。実際、バンダイナムコスタジオさんとの共同研究はCEDECでのご縁がきっかけでスタートしました。同じ場所に集まって「仲間」になってしまえば、相互理解が深まり、物事がスムーズに進むようになるのでは? というのが私の意見です。
簗瀬:それはすごく思いますね。企業は修士課程や博士課程の修了生を積極的に採用してほしいですし、採用された方々は就職後も学術界との関係を切ることなく産学連携の旗振り役になってほしいです。実際、かつて所属していた研究室と一緒に共同研究を続けたり、企業に所属して仕事をしながら大学の博士課程で研究をしている人もいます。そういう方々が増えれば増えるほど、産学の壁が壊され、両者の関係性が地続きになっていくと思います。
CGW:例えば、オー・エル・エム・デジタルの四倉達夫さん(R&D Lead)や前島謙宣さん(シニアソフトウェアエンジニア)は、長いキャリアを通して幅広い産学のネットワークを培っており、その中には出身研究室(共に、早稲田大学 森島繁生教授の研究室出身)のつながりも含まれているようですね。ちなみに「こんな共同研究は失敗しやすい」という傾向はありますか?
三上:大学は、長期的な視点をもった研究が得意です。一方で、企業は仕事に即時活用できる成果を求める傾向にあります。この部分の相互理解が浅いと、失敗しやすいですね。それから、コンテンツ制作に関連する共同研究などで、商業作品と同等のクオリティラインの成果を大学に期待されても、応えるのは難しい場合が多いです。特に、企業の方々が学生のことを安価な労働力だと思っているようなケースは、往々にして失敗します。
簗瀬:短期的な視点で見てしまうと、産学連携は失敗しやすいという点は同感です。
長谷川:だからこそ、お互いの強みを活かせ、利害が一致する研究課題を見つけるのは簡単ではありません。産業界の課題の多くは、必要に迫られた現場の方々が、なんらかのかたちで解決しているのが実情です。学術的な新規性があり、産業界の成果にもつながる研究課題を発見し、論文投稿や現場展開などのアウトプットまでの道筋をつくることが私のミッションだと思っています。
簗瀬:産学連携にはメリットもデメリットもあり、片方だけが強調されるのは得策ではありません。すでに長谷川さんがCEDECで実践しているように「産学連携をやってみた結果、こういう点はうれしかった」という成功事例を発表することが非常に大切だと思います。その際、ありがちな落とし穴についても紹介すると良いでしょう。そうすれば、企業も大学も、その発表をモデルケースにしながら産学連携に取り組めます。今回の特集記事も、参考情報のひとつになればうれしいですね。加えて、企業の方々には、積極的に学会に参加し、論文の「目利き」ができるスキルを培ってほしいです。学会に参加すると、論文発表に加え、その論文に対する質問や議論も聞けるので、論文の実用性を見極める力が磨かれていきます。
カンファレンスや学会に出よう
CGW:先ほど三上先生は、カンファレンスや学会に産業界と学術界の方々が集まることで、相互理解が深まるだろうとおっしゃいました。簗瀬さんも、CEDECなどでの成功事例の発表や、企業の方々が学会に参加することの必要性を語っていました。産学連携を実践し、ちゃんと成果を得るためには、相手の領域に積極的に参加し、自分の領域に相手を迎え入れる姿勢が重要なのでしょうか?
三上:そうですね。カンファレンスや学会の懇親会だったり、運営会議の合間の雑談だったりが発端となり、産学連携がスタートすることもありますし、そこで出会った人を介して同じような課題をもつ方々を紹介してもらえることもあります。簗瀬さんはSAPPORO CEDEC 2014で、ゲーム開発者の学会参加を促す発表をしていましたよね?
簗瀬:はい。「書を手にし、学会に出よう」と題したセッションを実施しました。
三上:同様に「研究者は、産業界のカンファレンスにも出よう」という呼びかけも必要なんだと思います。すでに実践している研究者も多数いますが、呼びかけを続けることで、さらに多くの交流を促し、成功事例を紹介し、さらに交流を活性化させる......という好循環を生み出せると理想的だなと思っています。
長谷川:私は東京で開催されたSIGGRAPH Asia 2018で、Real-Time Live! のチェアを務めました。その経験を通して、国内外の学術界・産業界の方々とのつながりを深めることができ、本当に大きな価値があったと感じています。一方で、正直に言うと、やることが多くてすごく大変でした(苦笑)。当時は「二度とできない」と思っていたのですが、SIGGRAPH Asia 2021は再び東京で開催されることが決まり、カンファレンスチェアの塩田周三さん(ポリゴン・ピクチュアズ 代表取締役)からお声がけいただき、再度運営に参加することになっています。コロナ禍の影響で不確定の部分は多いですが、フィジカルなイベントとして開催することを想定し、準備を進めています。産学の方々が交流する絶好の機会なので、ぜひ活用していただきたいです。
▲SIGGRAPH Asia 2018 カンファレンスチェアの安生健一氏(オー・エル・エム・デジタル 技術顧問/イマジカ・ロボット・ホールディングス アドバンストリサーチグループ ディレクター/ビクトリア大学 CMIC 教授・ディレクター)の発案の下、その成功を祈願して多くの関係者がサインしたダルマ(河西 仁氏提供)
▲【左】ダルマを手にする安生氏/【右】同じく長谷川氏。なお、SIGGRAPH Asia 2021は2021年12月14日〜17日に開催予定。そのカンファレンスチェアを務める塩田氏も、このダルマにサインしている
CGW:本業の傍ら、SIGGRAPH Asiaの運営に参加するのは大変そうですね。実際のところ、皆さんは業務の何%程度の時間を社外、あるいは学外での活動に割いているのでしょうか?
長谷川:SIGGRAPH Asiaのチェアは片手間でできる役割ではなく、ピーク時にはほぼかかりっきりになってしまうことがわかっていたので、事前にしっかり上長に説明して許可を得ました。そこで得た経験、情報、つながりなどが本来の業務に役立つものであれば、業務の一環として取り組むことを認めてもらえます。一方で、情報処理学会 ソフトウェア工学研究会の運営委員も長らく務めてきましたが、ゲーム開発との関連は薄いので、業務時間内での活動は短時間に抑えるようにしてきました。
簗瀬:私の場合は学術界で成果を出すことが仕事なので、全て業務時間内に行なっています。共同研究先が10ヶ所あったなら、1ヶ所に毎月1日訪問するだけで120日を要します。年間の就業日数が260日だとすると、それだけで半分弱に相当します。ほかにも、情報処理学会のIPSJ-ONEの開催支援、未踏IT人材発掘・育成事業の合宿、CEDECの公募やPERACONの審査などに携わり、各種カンファレンスや学会にも参加しているので、1年の大半を社外での活動に割いています。
三上:大学教員は裁量労働制に近いので、学外の活動に割いてよい時間の明確な上限はありませんが、活動には届出と上長の許可が必要です。学内の業務は積極的に引き受け、外部での活動が承認されやすい環境をつくっています。また、公的な研究費の申請では、業務時間における研究課題のエフォート率(時間配分率)を記載する場合があるので、全体の時間配分は管理しています。産業界とのつながりを維持し、様々なものを吸収し、教育と研究に還元していかないと、「実学主義」は体現できないと考えています。
長谷川:私は自分の時間を使って、学会誌論文の査読もするようにしています。論文査読は得るものが多く、先ほど簗瀬さんがおっしゃった論文の「目利き」のスキルを培う上でも有効です。もっと積極的に論文査読を企業の方々にもお願いしてみると、産学の交流が活性化するかもしれません。推薦制度などがあると敷居が下がるのではないでしょうか。
簗瀬:強制力が強すぎると、すごくブラックな事態になりそうなので、そこは慎重に対応してもらうとして(笑)、企業の方々による論文査読は奨励したいです。実際、私も時間の許す範囲で引き受けるようにしています。査読をすると、関連論文にも目を通すので勉強になります。学会から「この人は、論文の読み書きができる」と認められなければ査読は依頼されないので、依頼がきたことを評価する企業が増えると良いですね。ただ、企業の方々は本業が優先になるので、本来の査読者3名に加え、ゲスト査読者1名を企業の方々に依頼する枠組みをつくってはどうでしょう? 万が一、本業が忙しくて査読の締切に間に合わなくても、その論文を採択するか否かの判断への影響がないようにできると依頼する敷居が低くなると思います。
三上:論文査読の前段階として、自分が選んだ論文の内容を紹介し合う輪講に参加するのもオススメです。研究室のゼミでは、よく輪講を通して学生を鍛えています。最近は有志によるテレビ会議システムなどを使った輪講も実施されているので、そういうものを活用すれば、企業の方々も参加できます。



![[産学連携のトリセツ]「産」と「学」を分けない。壁を壊し、地続きにする](https://cgworld.jp/feature/202102_sangaku_main1.jpg)