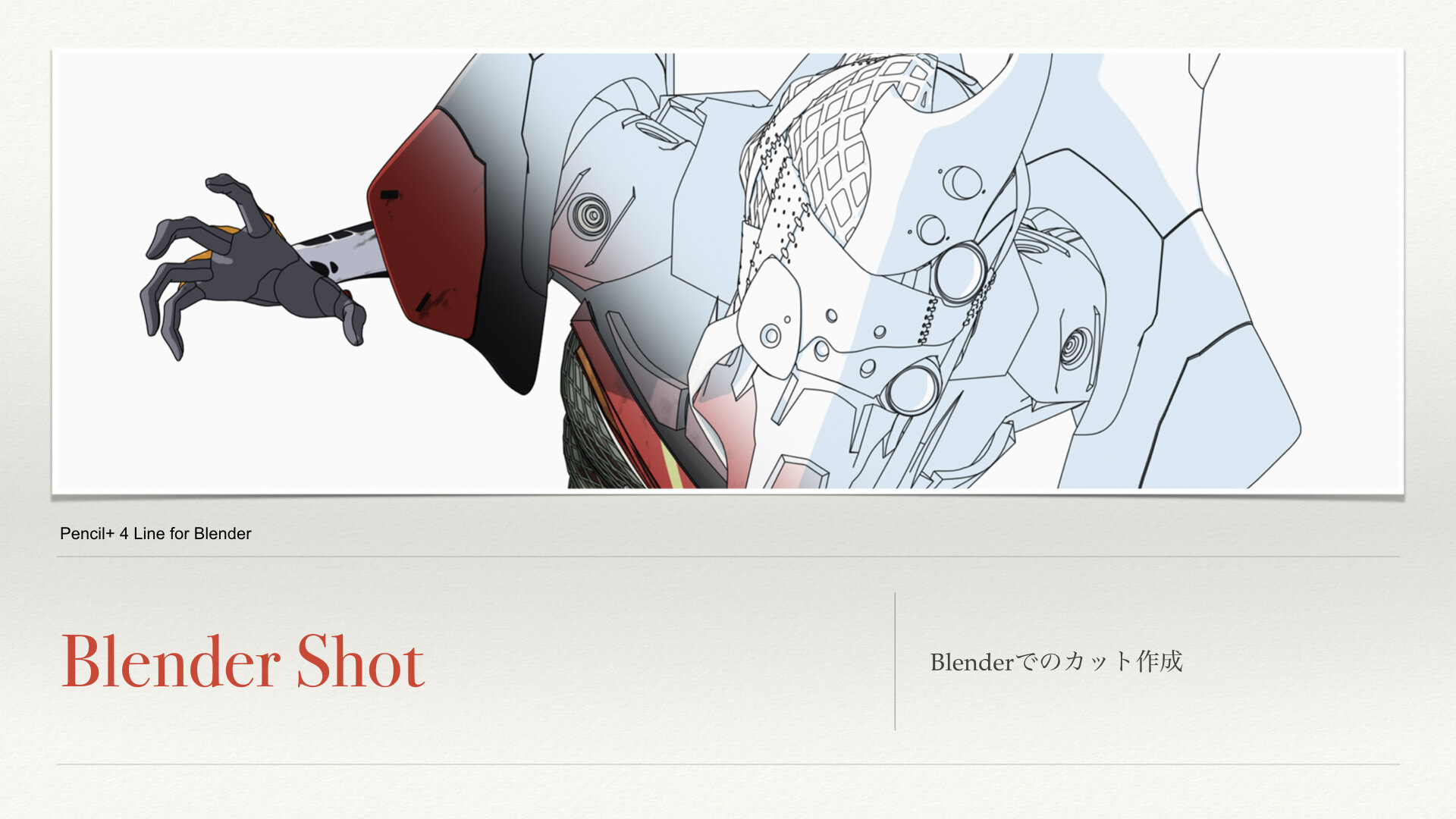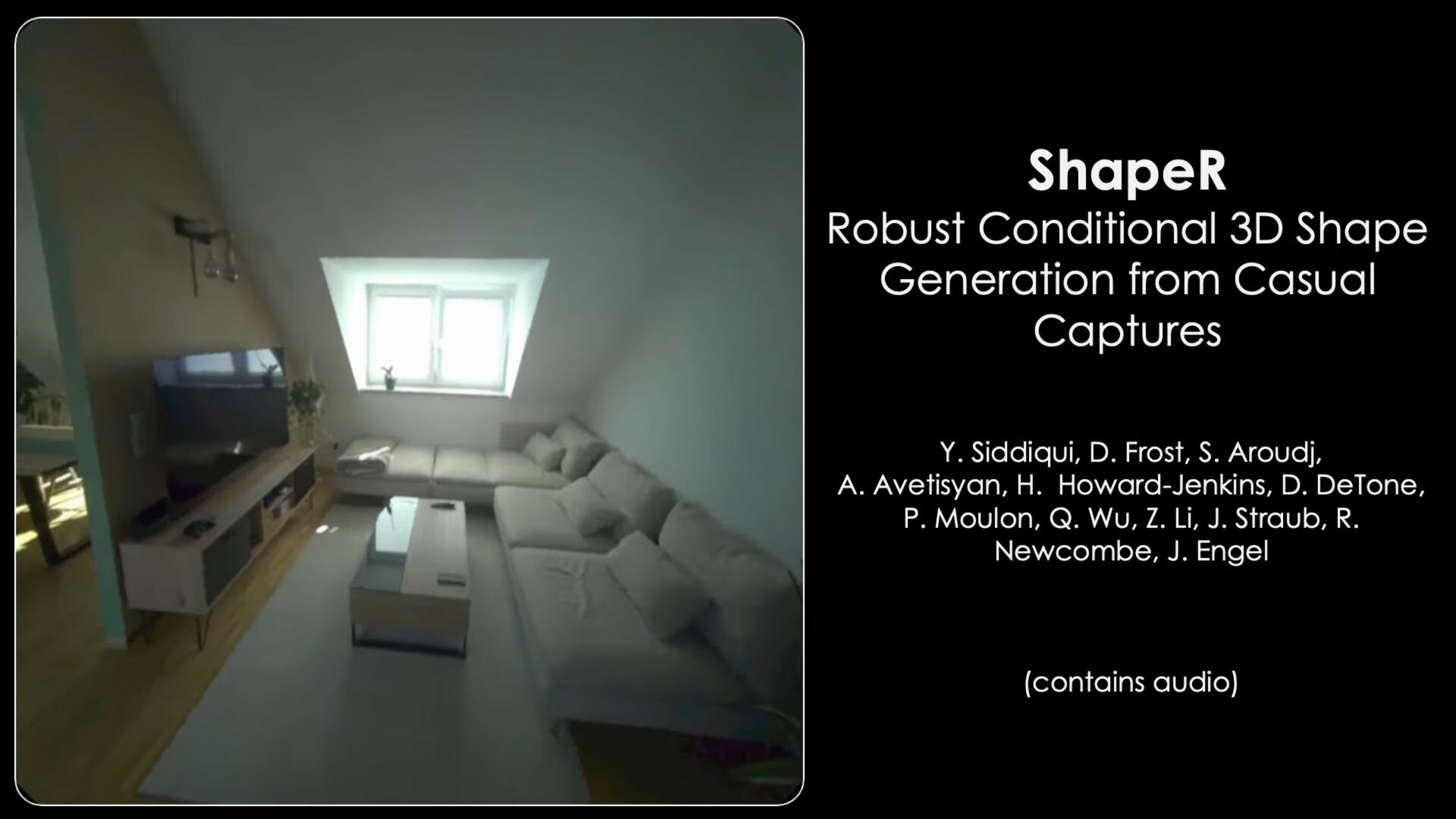たった一人で開発されたインディーゲームであったにも関わらず、200万本を超える大ヒットを記録し、異例とも言える実写映画化まで果たした『8番出口』。各種コンソールやVRなど幅広い展開を続ける本作だが、その新たな展開が『8番出口 for Roblox』だ。
近年急拡大を見せるオンラインゲーミングプラットフォーム・Robloxにおいて『8番出口』はどのような形で実現されたのか、Robloxならではのマルチプレイやコミュニティ要素はどのように実装されたのか。開発を手がけたMyDearestと、移植をサポートしたランド・ホーに、通常の移植とは異なるRoblox開発の課題や工夫、そこから得られた知見について話を聞いた。
MyDearest
オリジナルVRゲームの開発 & パブリッシングを行なっており、代表作は『BRAZEN BLAZE』『DEVIL'S ROULETTE』『BAZOOKA STUDIO』『ALTDEUS: Beyond Chronos』など。
『8番出口』シリーズでは『8番出口VR VRChat World』、『8番出口VR』などを手掛ける。
ランド・ホー

代表作に競走馬育成シミュレーションゲーム『ダービースタリオン』など。
近年では、Robloxへの移植開発サポートも手掛ける。
ゲーム機を手に取る前にRobloxに触れる子供たち

――配信から2年が経ったいまも大ヒット中の『8番出口』ですが、こちらの作品をRobloxに移植することになったきっかけから教えてください。

後藤 功士
MyDearest ディレクター&プランナー&etc
後藤功士氏(以下、後藤):
本作の包括ディレクターを務めました、MyDearestの後藤です。本作、『8番出口 for Roblox』開発のきっかけは、『8番出口』というタイトルが当初の想像を遥かに超えて低年齢層に流行していると感じたからです。
オリジナル版は最低でも高校生・大学生以上の年齢に向けられたものだったと思うのですが、近年はコロコロコミックのような児童誌でもコミカライズされており、とうとう幼稚園くらいの子供にまで普及し始めているんです。そこで、キッズからティーン層をメインターゲットとするプラットフォーム・Robloxで本作を展開することになりました。
――『8番出口』はすでにNintendo Switchなどでも展開されていますが、Robloxをプレイする層はそことはまた異なるのでしょうか?
後藤:
そうですね。Robloxでプレイしているのは、Nintendo Switchを遊ぶ子供たちよりも、より年齢層が低い子供、という感じがしています。

阪野 祐太朗
ランド・ホー ディレクター
阪野 祐太朗氏(以下、阪野):
SwitchやPlayStationを手に取るようになるさらに前の段階、親御さんのiPadで遊んだりするものとしてRobloxが位置しているという印象ですね。
後藤:
あとは、Roblox自体が「ゲームを作れるプラットフォーム」を標榜しているので、プログラミング学習教材や知育玩具の感覚で親子で触れている方も多いみたいです。
――Robloxでは今作リリース以前にもすでに『8番出口』を模したゲームが数多くつくられていたと思うのですが、VR版も手掛けられたMyDearestさんが直々に『8番出口』を制作する必要もないのでは……とは考えませんでしたか?
後藤:
それは特にないですね。我々の方がいいものをつくれるという確信がありましたし、Robloxのメインプレイヤー層が子供だからこそ、その違いはきちんと伝わるだろうという想いがありました。これは前職で子供向けの商品をいくつも作って感じたことでもあるのですが、子供こそモノの良し悪しを本当に見抜くと思うんですよ。だからこそ、我々が本物の『8番出口』をRobloxにつくるべきだと思ったんです。
エンジンも言語もまったく違う。限られた機能で挑むRoblox開発

――Robloxでゲームを制作する際は独自エンジン・Roblox Studioとプログラミング言語・Luaで開発を行うこととなりますが、PCやコンソールでのそれとはどのような違いを感じられましたか?
後藤:
オリジナル版の『8番出口』はUnreal Engineで動いているのですが、Robloxはエンジンも言語も違いますし、我々にもまったくノウハウが無かったので、より良いものをリリースするために、開発パートナーとして、ランド・ホーさんにお声がけしました。
阪野:
そもそも、Roblox Studioでやれること自体がUnityやUnreal Engineのようなゲームエンジンに比べるとかなり制限されています。なので、その限られた機能で原作をどう再現するかを考えたり、アセットの流用がどれくらいできるかの検証から始めないといけないんです。
――流用できないものというと、どのようなものがあるのでしょう?
阪野:
fbxファイルをインポートしてくるといったことそのものは可能なのですが、ポリゴン数の上限や構造に対して制限が数多くあるんです。たとえば、シェーダーも使えないので原作のような見た目を再現するために調整は必須ですし、ソースコードも作り直さなくてはいけません。
――それらについて、どのように対応されたのか伺えますか?

笠野健志
MyDearest リードデザイナー
笠野健志氏(以下、笠野):
対応した、というにはそもそもが手探りで始めたのと、Roblox全体を見ても本作のようにフォトリアル調のゲームは少数派なのもあり、まずは何ができて、何ができないのか確認からのスタートでした。一例ですが、床の点字ブロックのためにノーマルマップを貼っても立体感が全然表現されず、その原因がまるでわからなかったりしましたね。
後藤:
Roblox公式のドキュメント通りにやろうとしてもなかなか思った通りにいかない部分もあったりして……。なので、今回の開発ではRobloxで公開されている他の作品を見ながら、どうやって実装しているのか考察して実験してみることを繰り返して開発していきましたね。
――今回、ランド・ホーさんが途中から手助けに入る形で参加されたのは、そういったRoblox独自の環境での開発ノウハウの蓄積があったからなのでしょうか?

閨 隆文
ランド・ホー プログラマー
閨 隆文(以下、閨):
そうですね。そういった点をサポートする目的でお声がけいただきました。とはいっても、弊社も1、2年ほど研究したにすぎないのですが。
ただ、ランド・ホーでも基本的には、実験を積み重ねて少しずつ壁を乗り越えていき、それを蓄積していくような形で進めています。Roblox側の規約変更やアップデートで環境ががらりと変わることもありますから、Roblox開発をメインで手掛けられている会社含め、他の会社さんも同じように、都度調べて対応していると思います。
――そういったノウハウの蓄積と試行錯誤がありながらも、元のゲームから諦めなければならない要素などはあったのでしょうか?
後藤:
実は、『8番出口 for Roblox』は開発当初の想定からスペックアップしてリリースすることができました。
もちろん、最初はどれを諦めるかという話もしていました。開発期間も限られている中、環境的な制約もありますので、少なくとも、原作の31種類ある異変全てを実装するのは不可能じゃないかという想定だったんです。
例えば、原作では照明がチラつく異変があると思うのですが、Robloxはライト周りの機能があまり強くないんですよ。それで諦めようかという話をしていたんですが、結局、みなさんの頑張りのおかげで異変についてもすべて実装することができました。
なので、最初は思い描いた計画からスペックダウンしてリリースするのも覚悟していたのに、結果としては、逆にマルチプレイ機能なども含めたスペックアップで完成することができました。
Robloxならではの『8番出口』をめざして

――Roblox版『8番出口』ですが、原作にはないマルチプレイ機能があります。こちらはどのように制作されていったのでしょう?
後藤:
せっかくRobloxで『8番出口』をやるならマルチプレイを実装することは大前提だと思っていたので、それをどのように実現するか、から検討を始めました。
それに、基本的にRobloxはすべての動作をサーバーを介して行うので、原作ではローカル環境で完結していた内容をそのまま再現するにしても、結局ネットワーク周りの対応をする必要がありましたし。
閨:
そうですね。マルチプレイについては最初に後藤さんから頂いた仕様がしっかりしていたので、こちらからはRobloxで起こる問題と仕様をお伝えしつつ、あまり大きな手戻りはなく一つずつ仕様を固めながら進められましたね。
――間違い探しが主体のゲームをマルチプレイ化するというのは、ともするとプレイヤー同士で意見が割れたりしてフラストレーションが溜まりかねないようにも思えますが、そこはどのように解決したのでしょう?

後藤:
誰かのせいで嫌な思いをするということは避けたかったので、そこは気をつけました。誰かが失敗してみんなでやりなおし、というのはマルチプレイに付き物だとは思うんですけど、それでも「こいつのせいで0番まで戻された(※『8番出口』では異変の有無を正解できた場合、1番出口、2番出口と看板で表示される数字のカウントが進み、不正解の場合は0番出口にリセットされる)」と仲が悪くなるような事態は良くないと思ったんです。
だから、マルチプレイで遊ぶ場合でも連帯責任にはせず、異変の有無を正解できたプレイヤーは次に進んでもらって、不正解のプレイヤーはスパっと離脱し地下広場(ロビー)に戻ってもらって、次のプレイを楽しんでもらおうと決めました。
ただ、ゲームオーバーにされるにしても0番出口を見る絶望感だけは絶対に必要だな、と思っていたので、マルチプレイだとしても『8番出口』のゲーム体験として守るべきところは守る、といったような形で仕様はつくっていきましたね。
閨:
不正解のプレイヤーに0番出口を見せたいけれど、正解したプレイヤーがゲームを続けられるようにもしなければならないじゃないですか。ですから、正解ユーザーのために不正解側の通路の変更が行われるまでの最短の時間を計算し、その範囲内で設定をしていきました。

後藤:
基本的に『8番出口』というゲームは2つの遊び方があると思うんです。1つは、怖がりながらプレイするクラシックなホラーゲームのスタイル。もう1つは、ゲーム実況などに見られるようなみんなで異変を指摘したりしながらワイワイと遊ぶスタイル。その2つを両方実現することを心がけましたね。
マルチモードの「吹き出し」による簡易チャットがその例です。Robloxはボイスチャットの敷居が高いので、ボイス以外で意思の疎通ができないか、を検討しました。結果的に、新たに追加したエイトレスモード(不正解になるまでやり続けられるエンドレスモード)と合わせて楽しんで頂けているのを感じています。
制作管理は難しいがアイデアを形にできるまでは早い
――2社でRobloxゲームの開発をする際の役割分担はどのようにされたのでしょう? 2社で制作するにあたってトラブルなどはありませんでしたか?
後藤:
開発人員は合計8人くらいと小規模なチームですし、ランド・ホーさんがインゲーム、MyDearestがパブリックロビーを作るということで持ち場もはっきりと切り分けたのですが、最初に「Robloxのゲームを複数社でつくるのは大変ですよ」とは言われました。

伊藤佑樹
ランド・ホー プログラマー
伊藤佑樹氏(以下、伊藤):
Robloxから提供されている共同開発のためのツールを使用して開発をするのですが、どうしても普段使用しているGithubとは違う部分も多いんですよね。スクリプトについてはコミットのような仕組みがあるのに、オブジェクトについてはすべて即時反映されてしまうので、複数人で同時に触るとエラーが出てしまうとか。

来栖チェスター
MyDearest リードプログラマー
来栖チェスター(以下、来栖):
参照していたフォルダの構造が変わってエラーを吐いてしまったり、スタジオ内のオブジェクト編集時のコミットコメント機能がないのでロールバックもできず、ひたすら変更箇所を探したこともありました。
ですので、ファイルを触ったりデータを持って行くたびに、周囲に宣言と連絡を徹底する必要なんですよね。1社でやっているなら同じフロアや隣の席にいたりしてすぐに声をかけあえますが、別々の場所にオフィスを構えた2社で連携してともなるとこれが大変で……。
――そこはどうクリアされたんですか?
後藤:
もう、毎日ミーティングを欠かさずやることに尽きますね。最初は1日30分の朝礼のようなイメージでやっていたんですが、次第に長いミーティングも行うようになって、ときには2時間くらい話していることもありました。
閨:
完全に同じ会社でやっているような距離感でしたよね。
後藤:
そうですね。ミーティングもどんどん濃密な内容になっていきましたし。
でも、時間をかけてでもそこで話し合っていろいろ解決できたおかげで手戻りが防げました。当初の想定以上の内容でリリースできたのも、ミーティングの場で皆さんが前向きに、より良くしていくための話し合いを進めてくれたおかげです。あれがなければ分散開発は難しかったと思います。
――これからRobloxに参入することを考えているクリエイターもいると思うのですが、何かアドバイスなどいただけますか。
笠野:
では、私から3つほど……。
1つ目に「アンカーを押すこと」。Robloxにはアンカーという機能があるのですが、これを押さないとモデルを入れて再生したときにすべてがバラバラに崩壊していきます。初めての人は絶対に驚いて混乱するので、アンカーは必ず押してください(笑)。


2つ目に、「1つのメッシュに対してマテリアルは1つしか使えない」など、他のゲームエンジンでは当たり前に出来ていたことが出来なかったりするので気を付けてください。
3つ目に、「公式ドキュメントは英語版も一緒に読む」。おそらくまだ各国の言語にあわせて整え切れていないのだと思うのですが、日本語版だと翻訳の都合でわかりにくい表現になってしまっていることがあるので、英語版も合わせて読むようにするとよりわかりやすいと思います。
来栖:
ただ、正直、本当にノウハウがない会社でイチからやるなら、どれだけ小規模なものを作るにしても数カ月は見ておく方がよいと思います。それか、ランド・ホーさんのようなRobloxでの開発経験がある会社と組んだ方がいいです。
後藤:
なんなら、まずはランド・ホーさんのブログを読んだ方がいいです(笑)。
阪野:
ありがとうございます(笑)。宣伝みたいになってしまうのですが、弊社でも技術ブログのようなものを公開しているので、開発するうえでわからないことがあった際には参照してもらえるとお役に立てるかなと思います。
――逆に、現在Robloxに触れていないクリエイターに向けて、なにかRobloxをオススメできる点などあればそちらも教えてください。

後藤:
Robloxという場そのものは、自分のアイデアを形にするのに非常に手っ取り早い舞台だと思います。デザイン素材もサーバー環境も、プログラムの参考になるものも一通り揃っている。また、ユーザー層が比較的若いのもあり、良くも悪くも、AAAタイトルに求められるようなビジュアルの美しさや圧倒的なゲームボリュームなどではなく、ゲームデザインやプレイ体験そのもので評価されやすい空間でもあります。
なので、プログラミングをやったことがなくても、絵や3Dモデルが作れないとしても、自分が面白いと思っているものを信じて、ゲームとして完成させられる場所だと思います。
阪野:
それに、ユーザーとの距離が非常に近いプラットフォームだと思います。
いきなり完成品が出せなくとも、モックの段階で遊んでくれたユーザーの声を聞きながらアップデートをしていくことが許されるような場所なので、ユーザーと一緒にワイワイと作っていくことを楽しんでみるのがオススメかなと思います。いろいろとお試しをしてみるにはいい場所です。
8番出口 for Roblox

『8番出口 for Roblox』
原作: KOTAKE CREATE
開発: KOTAKE CREATE、MyDearest
パブリッシング: MyDearest
TEXT_稲庭 淳
EDIT_遠藤佳乃(CGWORLD)