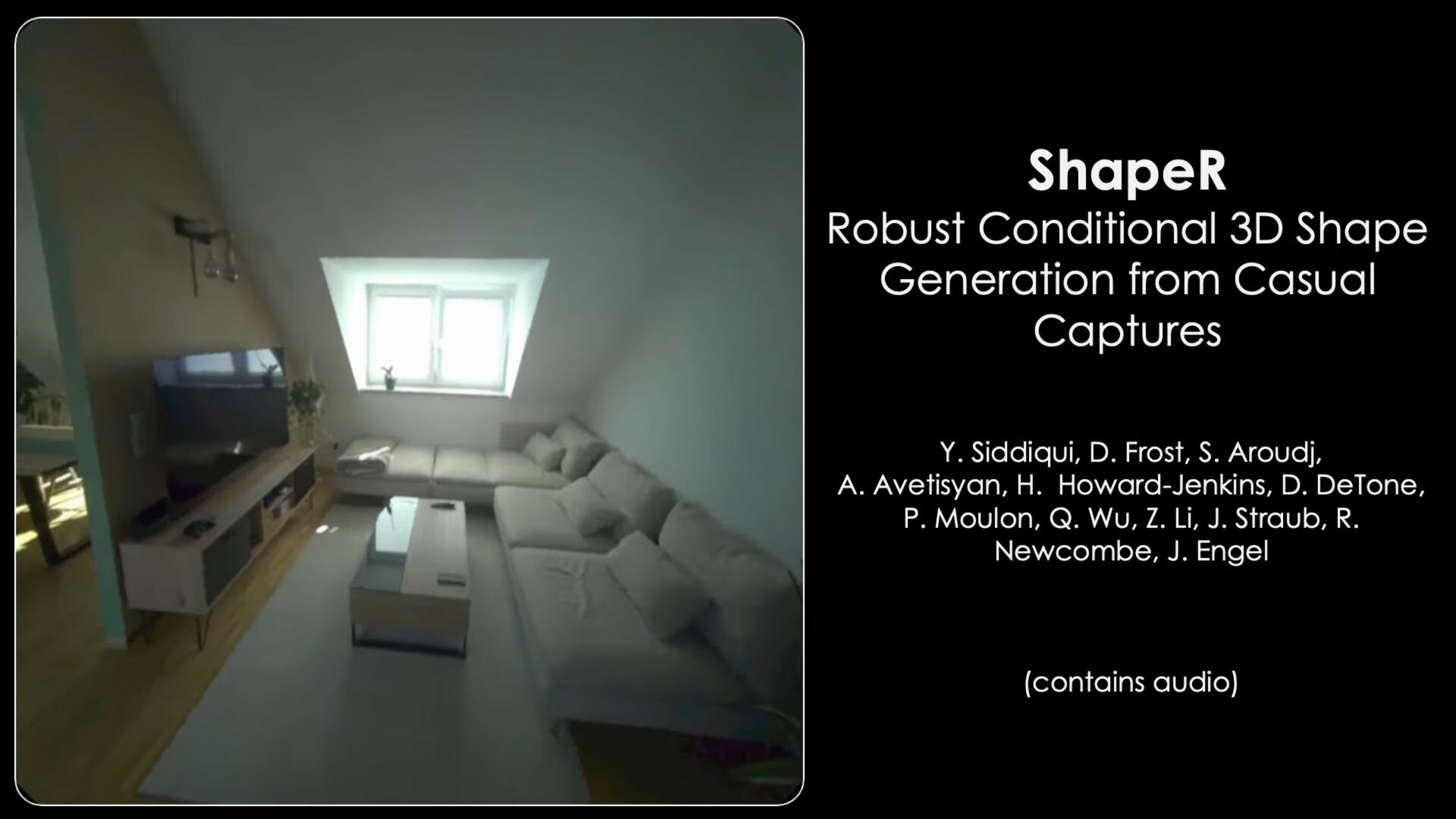クリエイティブに必要な発想力・表現力・突破力を有する次世代クリエイターを育成することを目的に、WOWが主催する学生向けプログラム「WOW Student Program 2025—Ignite Your Creativity」が今年も開催された。
本プログラムでは、WOWが設定したテーマに基づき、参加者から独自の企画案を募集。選考を通過した参加者たちは、国内外で幅広いビジュアルワークを手掛けるWOWのクリエイティブチームによるレビューを受けながら、約6週間にわたり制作を進めた。
今回の制作テーマは、「見えない時間」。普段は気づかずに過ぎてしまう時間や、社会の中で置き去りにされている時間など、“見えない時間”を自分なりの視点で捉え、表現することが求められた。
学生のうちに「自分の視点」を鍛え、それを社会とつなげる技術を磨く経験ができるこの取り組みに賛同し、CGWORLDと、同メディアを運営するボーンデジタルが協賛として参加。本記事では、8月26日(火)に行われたレビューおよび9月20日(土)に行われた発表会の様子をレポートする。
イベント概要
エントリー期間:2025年6月10日(火)〜7月22日(火)17:00
プログラム期間:2025年8月5日(火)〜9月23日(火・祝)
「WOW Student Program 2025—Ignite Your Creativity」は、映像制作、グラフィックデザイン、インスタレーション、UI/UXデザインの分野での活躍を志す学生を対象としたクリエイティブプログラムだ。
制作期間は8月5日(火)から9月19日(金)までのおよそ6週間。期間中には計3回、企画・作品進捗・作品仕上げについて、WOWのクリエイティブチームによるレビューが都度行われる。レビューを踏まえて学生は自らの作品をブラッシュアップし完成へと作品を練り上げていく。
完成した作品はギャラリースペース「SLOTH」で展示されたほか、優秀作品に選ばれた1名には、11月23日(日)開催のCG業界向けカンファレンス「CGWORLD 2025 CREATIVE CONFERENCE」にて作品発表の機会が提供されることとなる。
レビュアーには、WOWのビジュアルアートディレクター・工藤 薫氏、テクニカルディレクター/プロダクトマネージャー・荒川健介氏、シニアビジュアルディレクター・中間耕平氏、ディレクター・牧野 滋氏、デザイナー・多賀柊子氏、クリエイティブストラテジスト・白石今日美氏が参加。



発表作品
ではまずは、本プログラムに参加した学生たちが、約6週間という制作期間を経て完成させた最終発表作品を紹介していこう。
今回のテーマは「見えない時間」。
普段は気づかずに過ぎてしまう時間や、社会の中で置き去りにされている時間など、それぞれが“時間”という抽象的な概念を、自分なりの視点と方法で掘り下げ、可視化することが求められた。
その成果として並んだのは、アニメーション、静止画、インスタレーション、プロダクトなど、ジャンルもアプローチも実に多様な作品群だ。わずか6週間という短期間の制作とは思えない完成度と深みを備えている。何より、自分自身が「面白い」「美しい」と感じた価値を出発点にしながら、鑑賞を前提とした作品としてしっかりと着地させたことが素晴らしい。
<映像作品>
1.ROOM(蓑 いづみ)
作者の自室を1日1回ずつ1ヶ月に渡ってスキャンした3Dデータから成る映像作品。一見変化がなさそうな生活空間を繋げることで、「見えない時間」を可視化している。3Dスキャンにはスマートフォンアプリ「Scaniverse」を使用しており、撮影のムラが非現実感の演出へと繋がっている。
<WOW講評>
「単純に好きです。3Dスキャンという最先端技術と、それが崩れていることによるホラーテイストが同居していて、観終わった後にクエスチョンマークが浮かぶ一方で、伝えたい意図は伝わって来る。この方向を突き進んで欲しいと思います」(中間)
2.LAST PULSE(向後恵梨) 【作品賞】
厚塗りイラスト調のフル3DCGアニメ作品。舞台はイタリアの漁村。1~4FPSで動く別世界が見えるようになってしまった主人公とサイケデリックな映像を通して、同じ時間に対しても認知できる世界が異なるのではないかという形而上学的な世界観を描いている。
<WOW講評>
「FPSを題材にする視点も非常にデジタルネイティブ的で新鮮な上に、絵、色使い、アングル、カメラの動かし方、どれも上手で非常に趣味が良い作品だと思います。レビューで指摘されたポイントをアジャストする能力も高いのに、尺も2分を超えているという衝撃的な作品でした」(中間)
3.変容するヴィーナス(伊藤琴音)


ヴィーナスを象った静止画作品。身体の上から下にかけて各部で年齢が異なっており、若さと老いの両方を一身で表現している。ボッティチェリの『ヴィーナスの誕生』を引用しつつ、時間で変化する身体の状態それぞれに普遍的な造形の美しさがあることを表現した作品。
<WOW講評>
「1つの彫像の中に複数の時間が含まれているというアイデアに驚きました。難しいアイデアだったと思うのですが、最後までよくやりきってもらったなと思います。おもしろいアイデアなので表現手法や媒体を含めて、他の可能性も探ってみてもらいたいです」(中間)
4.One Month Before 27 Years Club(オウ シュウマン)
近く27歳を迎える作者が、自身の過ごした26年をアルファベット26文字になぞらえて制作された映像作品。画面は2分割され、左半分には人生のキーアイテムをCDジャケット風にレイアウトし、右半分にはその思い出がテキストで語られるという構成になっている。
<WOW講評>
「ミュージシャンの享年から生まれたフレーズである27クラブを題材にして自分の人生を表現するというので私小説的で暗い雰囲気になるのかと思いましたが、ポップで可愛らしい作品に仕上げられていると思います」(荒川)
5.Sealed Letter(日浅明梨)
2Dアニメーションでミュージシャンの元に届いたファンレターとその送り主の日々を描いた映像作品。ロトスコープで繊細な動きを作画しつつ、音楽に励まされながら過ごした日々を描いている。
<WOW講評>
「本当にきゅんとする作品です。レビュー段階からすでに完成度は高かったのですが、完成版を見て改めてそれを感じました。映像の処理もすごくしっかりしていて、このままこのテイストでプロをやっていけるんじゃないかと思います」(牧野)
6.ゆうゆうえんち(治部 晶)【作品賞】
色鉛筆の赤と緑を基調に遊園地の世界を描いた映像作品。楽しい時間があっという間に過ぎていく感覚を、自作した音楽や身の回りにあるもので制作したSEに合わせて踊る遊具やアトラクションで表現している。
<WOW講評>
「ポートフォリオを見せてもらった段階からかなり多才で、なんでもできちゃう方だったので楽しみにしていました。期待していた通り、すごくすてきにつくってもらったと思います。映像をつくるのは初挑戦と聞いていましたが、まったくそれを感じさせない出来です」(多賀)
<プロダクト作品>
7.3D Calendar(大石凛太郎)【ジャンプアップ賞】


毎日の印象を記録するカレンダーというプロダクトの作品。毎月末に次の1ヶ月の予定を見ながら、各日を「予定がパンパンな一日」「詰め込みすぎてしまった一日」「少しゆとりのある一日」「ドキドキする一日」などをコマ型の造形の中で表し、カレンダー枠にコマを埋め込んでいくことで日々を可視化するとともに手触りも感じることができる。
<WOW講評>
「カレンダーという平面に対して、実際の時間には深みや奥行きがあるということを示す、ハッとするようなコンセプトの作品でした。何もはめられていないマスがミラーになっていて朧げな自分の姿が映る仕掛けになっているのもすごい」(荒川)
<R&D作品>
8.Moment(テイロ)【作品賞】
モーターで制御された鏡と、それが映す景色を切り取ったインスタレーション作品。鏡を回転させるための制御はプログラミングによって行われており、筐体も3Dプリンタで自作されたもの。
<WOW講評>
「小さなミラーで身の回りの風景を切り取ることでそれを抽象化して、何が映っているのか鑑賞者に不思議に思わせる部分がよかったです。特に夜のシーンでは、パチンコ屋の電飾がミラーの上ではすごく美しく見えたり、そのギャップがおもしろかったです」(工藤)
9.ずれの場(オウアカネ)
体験者の姿をリアルタイムに投影しながら、体験者が目を瞑ったりする間、モニターに映る体験者の映像に遅延や加工が加わるインタラクティブな映像装置。4台のモニターがRaspberry Piによるシンプルな時間遅延を表現し、もう4台はTouchDesignerで複雑に変化した映像を表現している。
<WOW講評>
「自分でも体験したくなるような映像装置になっていると思います。アームとポールを使った造作は生物のようで面白いですし、自分の身体で感じる時間の不確かさや儚さをうまく表現できていると思います。Raspberry PiやTouchDesignerのような技術を使いながら、あくまで技術ドリブンにはなっていないのも良いですね」(荒川)
参加学生が語る WOW Student Program 2025 の気づきと成長

本プログラムに参加した学生はこのプログラムを修了しどんな学びを得たのだろうか。参加者に本プログラムに参加しての感想などを尋ねた。
――今回のプログラムを知ったきっかけはなんでしたか?
大石凛太郎さん(以下、大石):僕は、Instagramの広告だったかなと思います。ストーリーを見ている際に目にして、映像だけでなくプロダクトでも参加できるとのことだったので、応募してみました。
蓑 いづみさん(以下、蓑):私は、通っている武蔵野美術大学の授業で教授からプログラムを紹介されて応募しました。
――クリエイターからレビューを受けるのはどうでしたか?
大石:学校の授業で教授からレビューを受けることはあるのですが、外部では初めてなので本当に緊張しました。相手は現役でプロの方々なので、厳しい目線から滅茶苦茶に怒られて責められるのかなと身構えていたのですが、思ったより怒られなかったです。褒めるところは褒めていただいて、対応が必要なところはがんばろうと思えるような言葉をかけて頂いたかなと思います。
蓑:私は、そもそも計画的にものをつくったり、それを他人にプレゼンテーションしたりするという経験自体が無かったので、とにかく新鮮でした。
――なにかレビューで印象に残ったことはありましたか?
大石:お恥ずかしながら、企画段階から制作の過程で少し迷走してしまい、やることを広げすぎてしまった部分がありました。そこに対して「一度最初の案に立ち返って、芯や軸を見定めてみては」とアドバイスをいただいたことで、迷っていた中に道が見えたような感覚がありました。
蓑:ユニークさというか、自分らしさをもっと出すようにと言われたことが印象に残っています。その言葉がずっと心に残りました。

向後恵梨さん(以下、向後):毎回のレビューが本当に貴重で、真剣に受け止めなければならないことをたくさん学びました。途中、完成しないのではと不安に思う時期もありましたが、なんとか発表までたどり着き、さらに賞までいただけて本当に嬉しかったです。
治部 晶さん(以下、治部):少し前まで自分の作品やテイストに悩んでいたのですが、今回のプログラムでの制作を通して自分の中でのバランスがうまいかたちに見つかった気がします。今回のことがなかったら、どうなっていたかと思う程度にはうまく折り合ってよかったです。
テイロさん(以下、テイ):1人では踏み切れなかったであろう企画を、レビューを通して少しずつ背中を押してもらいながら制作できたのでよかったです。現場の方の視点を通して、洗練することを教えてもらったと思います。
――学生が夏休みの少なくない時間をこの制作に充てるというのは大きなことだと思うのですが、感想はいかがですか。
大石:どうなんでしょう。僕はこれ以外にも企業インターンを受けていたり、コンペに応募していたり、大学の研究もあるので、とにかく忙しくて大変という印象だけがあります。
蓑:私は自分に合う会社が見つからなくてインターンに行けていないのですが、そうした中で、人と一緒に作品をつくる機会があり、企業の人から見てもらえる機会があるというのはいいのかなと思っています。
――他の参加者の作品を見て感じたことはありますか?
大石:やっぱり、みんなすごいなと思います。コンセプトは人それぞれでも、その緻密さというか、細部を詰めていくという意識やこだわりをすごく感じました。
蓑:私は、さっきもお話した通り、プレゼン経験自体が少なかったので、他人が作品を発表しているのを見ながら「発表をするのがうまいな」ということばかり感じてしまいました。
大石:レビューの度にプロの方にコメントを頂いて、自分の思考がいかに曖昧であやふやなのかを思い知らされるのがありがたかったです。制作を前に進めるために必要な考え方、思考の積み方を教えて頂いたと思います。
――レビュアーのコメントとして「よくここまで仕上げてきた」といったフレーズが散見されましたが、ラストスパートは大変でしたか?
大石:僕は最後の1週間の追い込みがかなり大変でした。
向後:私は、徹夜が続けられないので、睡眠時間はちゃんと確保しながら制作しました。ただ、使える時間は全部使うといったかたちでした。
治部:私も、大変ではありました。
テイ:でも楽しかったです。

――次回の参加者に対してなにかコメントをもらえますか?
大石:大変だけど、参加したら楽しいイベントだと思います。また、綺麗にまとまったアイデアでなくてもうまくいくかもしれないので、気軽に出してみると良いと思います。僕は締め切り2日前にプログラムのことを知って、締め切り30分前に企画書を提出したくらいなので、みなさんも何か思いついたら応募してみると良いのではないでしょうか。
向後:私からもおすすめです。
治部:レビューでかなり的確なアドバイスを頂けて、方向性のブレや迷いはかなり解決してもらえると思います。他の方の作品やレビューにも立ち会うことができますし、そういった今後に活きるプログラムとしておすすめです。
テイ:普段のインターンシップや実習、学校の課題とは全く違いながら、社会のそれとも違う体験が得られるプログラムなので、そこがオススメできると思います。みんなでがんばって、みんなで一緒に成功しようとするのに取り組める、希少な機会でした。
WOW レビュー担当者の声

一方で、2年目となる本プログラムを終え、レビュアーは何を感じたのか。レビュアーを務めたWOWシニアビジュアルディレクターの中間耕平氏、同社クリエイティブストラテジストの白石今日美氏にも話を伺った。
――WOW Student Programは2回目の開催になりますが、前回との違いはありますか?
中間耕平氏(以下、中間):前回は作品発表までオンラインだったんですけど、今回はその経過に1回オフラインを入れるようにしてみた、というのが明確に前回と違うところですね。
――オフラインの場を入れてみて、なにか感じたことはありますか?
中間:直接顔を合わせて話が聞けるようになったので、作品とあわせて、人となりが見えやすくなったのは大きいと思います。また、参加者同士でも直接会って交流する機会をつくることで互助や交流が加速しているのを感じますね。
――レビューを行う際に意識されていたことなどありますか?
中間:そもそも会社内で人に何かを教えるという機会がなかなかないので、意識すること以前に人にアドバイスをすること自体が本当に難しいなと思います。だから、ベテランが若者に教えてあげるとかでなく、アイデアを出し合いながら一緒になにか作れたらな、という感じですよね。そんな中で、「これに気づくといい方向に向かうかもな」ということをちょっと言うくらいがいいのかなと思っています。
――学生からは、「作品を形にするための芯や軸を見定めるよう言って頂いた」といった声がありましたが、そこは意識されていますか?
中間:そうですね、とにかく形にする、それを人に見てもらうというのが大事なのかなとは思っています。それを通じて、制作の楽しさややりがいを感じてもらうとか、就職活動のポートフォリオに入れてもらうとか、そういったことができるといいなと。あとは、学生の時間だからこそできる自由な制作に打ち込んでもらいたいですね。
白石今日美氏(以下、白石):その作りたいものの衝動を大事するというのはWOWという会社のいいところでもありますよね。生成AIや自動化がどんどんクリエイティブに導入される中で、個人として何をしたいのかという部分はより重要になってくるんじゃないかと思います。通常の企業インターンでは、成績や就職など気にすることもたくさんあると思うんですけど、このプログラムはものを作っていく上で支えになる原石のような体験になって欲しいという思いで進めています。
――実際、レビューでもやりたいことの部分と、それを鑑賞者に伝えるための橋渡しの部分についての言及をすごくされていた印象でした。
中間:やっぱりそこが大事なのと、本人には意外とわからない部分でもあるんですよね。仕事やプロとしてやってきた分、僕らにはその試行錯誤があるので、その衝動的な部分の魅力を削がないかたちでうまく人に伝わるように意識させてあげられたらな、と思います。
――プログラムを終えていかがですか?
白石:本プログラムは今回で2回目ですが、昨年に引き続き、このプログラムの存在が学生の背中を少しでも押すことができていたらいいなと考えています。特に、3回目のレビューから今日に至るまでの最後の追い込みではクオリティがグッと上がるのが感じられて良かったです。
中間:WOW主催のプログラムとして普通のインターンやコンテストとは違う選考をした結果ではありますが、単純な上手下手に留まらない個性豊かな作品が揃って良かったと思います。
――今年のテーマは「見えない時間」でしたが、テーマに対する学生たちのアプローチはいかがでしたか?
中間:すごく難しいテーマを設定してしまったと思うんですが、ときには僕らが思いつかなかったような視点のアイデアもあって嬉しかったです。結果的に選考で通してあげられなかった作品も多いですが、自分の視点を大事にしてほしいと思います。
白石:一応、我々にもテーマに対する想定解のようなものはあるのですが、それとは全然違う視点の企画書もいただいて、我々自身が型にはめようとしていたことに気付かされる瞬間も多かったです。学生さんとお互いに学び合っていく関係が得られて、非常にありがたかったですね。
――そう聞くと、一般的なプログラムに比べて学生とレビュアーの関係は少し特殊に感じます。
中間:今回のプログラムについて、他社の方から「WOWと学生がフラットでいいですね」と言われたことがあります。僕ら自身もこのプログラムではそうした関係を大切にしていて、雇う・雇われるに留まらない「仲間」としてのつながりを築いてこそ、伝えられるものがあると思っています。
白石:だから、一般的なインターンとも就活の面接とも違う雰囲気になっていますよね。いい意味でみんなリラックスしてる。

――プログラムを通じて学生に感じた変化などはありますか?
中間:基本的には自由に、個々人がやりたいことに近づくためのアドバイスだけをさせてもらったと思います。手助けはできたのかな、と。
白石:最初の企画書の段階では、あまり自分の内側から発せられたものではないのかも、という言葉が並んでいたりもするのですが、それが次第に自分の言葉になってきたというのが1番大きな変化だと思います。表面的な言葉に留まらない、思考から出てきた言葉が聞けたときは嬉しかったです。
――自分の言葉を持ち合わせない学生も多い中、企画はどのようにして選ばれたのですか?
白石:なるべくその人ならではの要素、原体験のようなものが滲み出てるものを選びました。逆に、アイデアや企画書の仕上がりは素晴らしいけれど、既視感があるものは外しましたね。
中間:やっぱり、正直な企画は強いと思うんですよ。もっともらしい言葉を並べてそれらしいことを言うより、自分を曝け出して芯が通っているものの方がいい。そういうものが根にないと、作者も完成まで付き合えないと思うんです。
白石:実際、空き時間のすべてをこれに割いたという方もいましたよね。
中間:結局、本当に自分のためにつくっている作品が1番強いんですよね。もちろん観客への意識とかも必要ではあるけど、それは完成という成功体験を積み重ねながら徐々に身に着ければいいと思う。だから、それを我々も褒めたいと思いますし、創り続けて欲しいなと思います。
――来年開催される場合に向けて、参加を検討している学生へのメッセージをお願いします。
中間:つくり方がうまくなくてもいいので、まずは、何かつくりたいという人や、何か思っていることや考えていることがあるという人が来て欲しいです。僕らは完成まで伴走するので、一緒にやれる人が来てくれると嬉しい。
白石:技術の変化が激しい昨今、本当に自分がやりたいことは何かと考える機会は増え続けると思います。そうした中で自分の持ち味や核を見出したいという人に応募してもらえるといいなと思います。
総括(CGWORLD編集部より)
WOW Student Program 2025では、学生たちがそれぞれの“見えない時間”をテーマに、自身の視点と技術で作品を形にした。短期間ながら、プロのレビューを受けながら試行錯誤を重ねる過程は、技術以上に「自分で考え、創り出す力」を育む時間だったと言える。完成した作品はいずれも、個性と誠実さが息づくものばかり。就職や評価のためではなく、純粋に「つくりたい」という衝動から生まれた作品が持つエネルギーを感じさせてくれた。CGWORLDとしても、こうした次世代の挑戦を今後も継続的に伝えていきたい。
-

作品発表はSLOTH JINNAN にて行われた。
写真提供:WOW -

写真提供:WOW

TEXT_稲庭 淳
PHOTO_弘田 充