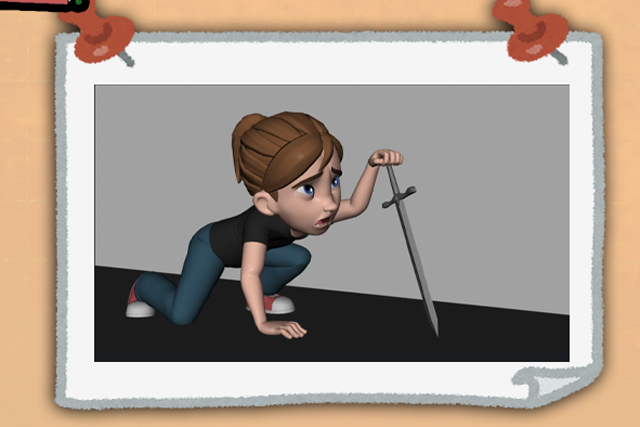黎明期における日本のアニメーション制作
野口:移籍された当初から演出家としてスタートしたわけですよね?
勝間田:来たらすぐに監督にするという誘いだったけど、さすがに移籍した当初は『狼少年ケン』で2話ほど演出助手を担当したよ。当時の東映動画は第一と第二に制作部が分かれていて、第一が長編、第二がTVシリーズを作っていた。京都からの移籍組はみんな第一で入ったんだけど劇場だと年に1、2本しかなかったから、テレビの演出もやっていたな。
野口:なるほど。
勝間田:今から思えば、酷かったな(苦笑)。絵コンテはなんとか出来るんだけど、タイムシートができない。それでも監督やっていたわけだからね。初めて演出を手掛けたのが、『狼少年ケン』の第28話「ぬすまれた天国」だったけど、やってみたら我ながら酷いんだよ。自分が思ってるのとぜんぜん違う。次に担当した 『少年忍者風のフジ丸』(1964~1965)では、(市川)雷蔵 さんの 「円月殺法」(※市川雷蔵が演じた剣客・眠狂四郎 の必殺技)みたいなことをやろうとして、絵コンテに2秒と書いたら凄く速くてね。「なんでこんなに速いんだ?」って問い詰めたら、助手に「勝間田監督がコンテで2秒と指示を書いたんじゃないですか』って言うんだよ。確かに僕の指定が2秒になってたわけだけれども、実写とアニメのコマ数のギャップに最初は苦しめられたなあ(苦笑)。
モーションビッツ/林 伸彦氏(以下、林):京都撮影所では、絵コンテを描く風習があったのですか?
勝間田:人数は少ないけど、撮影前にコンテを描く演出はいたよ。僕はそうした人たちの存在を実際に知っていたからアニメに活かせた。
林:アニメの演出は絵コンテが基本になると思うのですが、すぐに慣れたわけですね。
勝間田:そうだね。絵コンテには殆ど抵抗はなかったな。
野口:勝間田さんのアニメ演出スタイルは、カット割りするような形でそれを絵に起こしてというやり方ですか?
勝間田:絵を描くのが本職ではないから、アニメーターみたいには描けないんだよ。絵コンテとしては問題ないレベルでね。
野口:ある演出家さんが、「絵コンテを上手く描きすぎてはいけない」と言われてました。
勝間田:そうなんだよ、当時の演出の中にもすごい絵が上手い人がいたけどね。ただ、そうした連中はアニメーターが自分のイメージ通り描かれてないと細かくリテイクを出すから嫌われたりはしたな。逆に僕の絵コンテは〇×で位置を決めてるだけだから「自由に発想できる」ってアニメーターには好かれていたよ。芝居の指示も、怒っていたら口はへの字にするとか、その程度は判るぐらいだからね。
野口:演出の骨子だけ明確にして、後はアニメーターのクリエイティビティに委ねる演出手法ですね。
勝間田:ただし、僕は "実写の感覚でかなり動かす"(アニメーション制作の都合を無視して演出する)から、みんな四苦八苦していたけどね(笑)。さっき話題に出した 『少年忍者風のフジ丸』 の演出は、時代劇に精通しているということで全て京都組がやってたんだよ。だけど時代劇そのものには詳しくても自分では描けない。そこで、『風のフジ丸』で作画監督だった 楠部大吉郎 さんにそのことを話したら、「俯瞰で描きたいなら三角を逆にして頭と手足を描けばいい。逆に煽りは、三角のまま」と教えてもらったよ。

勝間田:この作品では50メートルの崖からフジ丸がロープを引くというシーンがあった。絵コンテで描く際に定規で真っ直ぐに描いちゃったから、コンテ打ちの際に「50メートルでしょ? ロープは撓(しな)るよ!」って指摘されたりね、とにかく、演出には自信があったけど、画そのものについては始めの頃は終始そんな調子だった(笑)。
野口:ははは。
勝間田:次にやった、『レインボー戦隊ロビン』(1966〜1967) では、逆に作画スタッフが煽りで描けないことがあったな。見るとスコーンと平行なんだよ。
野口:へえ。
勝間田:そして、この頃から全てを内製するのではなく外部にも手伝ってもらうようになり始めた、タツノコプロ系とか、元・東映動画の人が起ち上げたプロダクションとかね。そうした外部パートナーの中に、窪 詔之(つぐゆき) さんがいて、『マッハGoGoGo』(1967〜1968) のオープニングやりながら、『レインボー戦隊ロビン』も手伝ってくれていた。彼はアオリ画が凄く上手かったんだ。そのときに、「なるほど原画が上手いと、動画枚数が少なくても大丈夫なのか」と学んだね。当時は、TVシリーズ1話あたりの平均が3,500枚くらいだったけど、『レインボー戦隊ロビン』では2,900枚くらいに収めることができた回もあったな。
野口:そうでしたか。
勝間田:とまあ、そんな感じで実際に演出をしながらタイムシートや構図を覚えていくという感じだったね。構図は、実写ならカメラのファインダー覗き込んで調整できるけど、アニメの場合は上がってきた原画でチェックしなければならない。当たり前の話なんだけど、その違いが大きかったなあ。アニメの場合は、演出家は基本的には動画以降は手が出せない(直接、手直しできない)わけなので、コンテを描く際にさっき話した三角形と逆三角形のルールを頭の中に叩きこんで、とにかく明瞭簡潔に指示することを心掛けたね。
野口:なるほど、勉強になります。3DCG の場合も用いられる技術が高度化する一方なので、演出意図を明確にすることが欠かせません。
勝間田:あとは、"間" だね。タイムシートで、間を描こうとするとなかなか思うようにいかない。実写なら、キャメラマンや役者に「もうちょっと、ためてくれ」と口頭で伝えるだけで事足りるけれど、アニメの場合は動画用紙をペラペラって、めくってはまた戻してとかやって把握する必要がある。その感覚が最初の1年くらいは全然分からなかったよ。
野口:移籍された際に、タイムシートや作画チェックの方法について、教えてくださる方はいなかったのですか?
勝間田:誰も教えてくれないよ、とにかく黎明期だったからね。そんなわけで、最初は24コマ(24枚の動画用紙)が10秒分ぐらいあるように感じた。同じようにタイムシートでは1枚6秒になっていても、それが30秒くらいに思えてしまう、その計算が最初は全然できなかった(笑)。


野口:少し話を戻しますが、先ほどTVシリーズ1話あたりの作画の枚数が話題に出ました。アニメの場合、作画枚数がコストに直結するので1話あたりの作画枚数について縛りがありますよね。現在の東映アニメーションでは、3,500枚がひとつの目安になっていますが、当時(1960〜70年代)はどのような感じでしたか?
勝間田:あの頃だと4,200枚くらいはみんな使ってたけどね。ただ、僕のキャリアの中では3,000枚という時期もあったな。
野口:なるほど。今と昔でそれほど変わってないのですね。
勝間田:例えば全体で3,000枚という上限があるとする。日常芝居のシーンは5〜6枚ぐらいに抑えて、アクションが大きいところは30枚使うといった配慮は商業制作なわけだから当然求められたけど、演出する上ではあまり作画の枚数を意識することはなかったね。1話で最高6,400枚使ったこともあるけど、逆に2,400枚で済んでしまったときもある。そして、枚数が少ないエピソードの方が出来が良かったりもするんだよ。
野口:そうしたエピソードはアクションが少ないということでしょうか?
勝間田:いや、ちゃんとアクションシーンもあるよ。
CGWORLD/沼倉:ということは、動きの緩急とか、間の取り方みたいな部分で演出的な配慮がされていたということでしょうか?
勝間田:そうとも言えるかな。例えば、これは劇場長編だけど 『さらば宇宙戦艦ヤマト 愛の戦士たち』(1978) で、ヤマトを側面からフォローするという演出を4秒でまとめようとしたことがあった。すると、西﨑(義展) さん が「音楽があれば1分持たせることができる」と言われて、実際に試してみたら見事に成立したんだよ。これこそ少ない作画枚数で長尺の表現を効果的に演出できた好例だ。とにかく、間の取り方は悩ましいものだよ。正直言って、今でも自分の中で明確なポリシーがあるわけではない。ただし、間が短いよりも長い方が結果として良い表現になる場合が多いとは思うけどね。