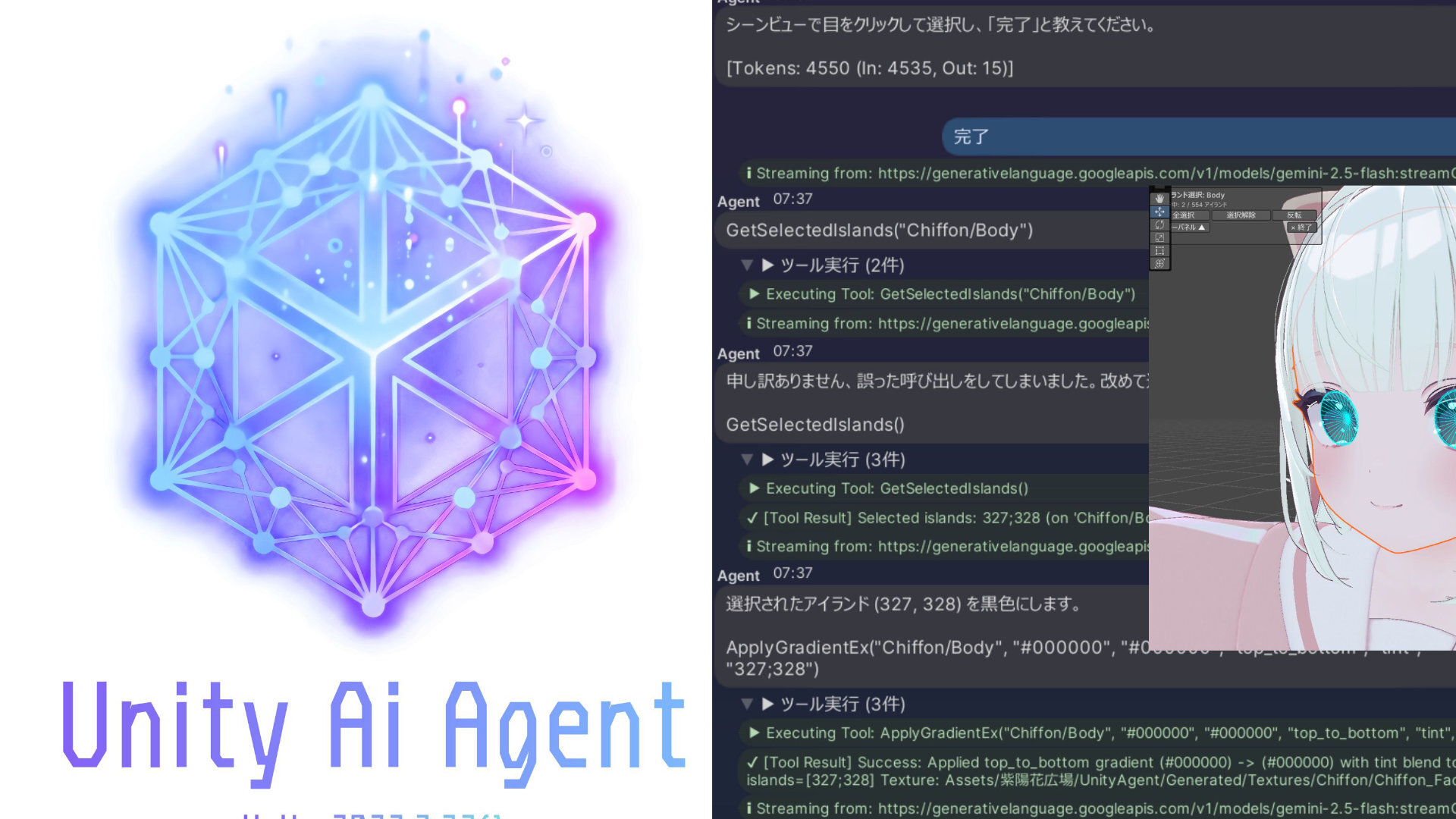日本におけるフル CG アニメーション制作への理解と振興を目指す本連載。今回の語り手は、ポリゴン・ピクチュアズ代表取締役の塩田周三氏だ。ポリゴン・ピクチュアズは、日本の CG 黎明期に当たる1983 年に設立されて以来、常に前人未踏の挑戦を続けてきた。2012 年にはアメリカで放映されたテレビシリーズ『超ロボット生命体 トランスフォーマー プライム(原題:Transformers Prime)』がデイタイム・エミー賞(アニメーション番組特別部門)最優秀賞を獲得し、これまで以上に注目を集める存在となっている。そんな同社の舵取りを担う塩田氏に、今日までの同社の道のりや今後の展望、さらに塩田氏が考える日本のCG アニメの未来を語ってもらった。
【聞き手:野口光一(東映アニメーション)】
Supported by EnhancedEndorphin
Shuzo Shiota
1967 年生まれ。兵庫県出身。幼少期の9 年間をアメリカで過ごし、上智大学法学部国際関係法学科を卒業。新日本製鐵を経た後、ビジネス・コンサルタントとしてポリゴン・ピクチュアズのコンテンツ企画を担当。1997 年にはドリーム・ピクチュアズ・スタジオ(DPS)の設立に協力。1999 年よりポリゴン・ピクチュアズに所属し、2003 年に同社代表取締役に就任。
創業者のポリシーが会社を生かし続けてきた
東映アニメーション/野口光一(以下、野口):ポリゴン・ピクチュアズ は1983年の設立以来、社名を変えることなくブランドを守り続けてきました。世界中を見渡しても、これに匹敵する歴史を持つ会社は多くはありません。それだけ CG プロダクションのビジネスは難しいのだと思います。ポリゴン・ピクチュアズが継続してこれた理由は何なのか。まず最初に、その辺をお聞かせいただけますか?
ポリゴン・ピクチュアズ/塩田周三(以下、塩田):設立は 83 年ですが、CG プロダクションとして機能し始めたのは88 年からですね。設立後の数年間はレーザーディスクの映像作品制作やPOP広告向けの DTP 開発がメインで、あまり CG らしいことはやっていませんでした。当時はまだまだコンピュータが高価で、いわゆる第一次 3DCG バブルの時代だったのです。独立系ゆえに 3DCG をやりたくても手を出せなかった。高額な投資をしなかったことで、結果的にバブル崩壊の痛手を被らなかったのは幸運でしたね。
野口:同時期に設立された JCGL や トーヨーリンクス と並んで、ポリゴン・ピクチュアズは高い技術力や表現力を持っていて、世界的にも認められる存在でした。ただ、ポリゴン・ピクチュアズが本格的に 3DCG 制作に乗り出したのは、88 年以降だったということですね。
塩田:ナムコ(現 バンダイナムコゲームス )の中村雅哉会長に出資していただき、88 年に最初の SGI ワークステーションを導入しました。その頃に、創業者の河原敏文さんが「ビッグバンプロジェクト」を起ち上げたのです。このプロジェクトは、河原さんらしい非常にわかりやすいコンセプトを持っていました。それまでの 3DCG は無機質なハードサーフェス表現ばかりだったので、有機的なソフトサーフェスを表現できれば世界一になれるんじゃないかと考えたのです。その挑戦的なコンセプトに多くの才能ある人たちが魅せられて、ディスカッションを始めた。当時はみんな手弁当で集まっていましたね。河原さんの功績は、プロジェクトを上手くパッケージングしたことです。当時の 3DCG 開発は技術アピールが重視されていて、パッケージングはダサいものが多かった。3DCG をかっこ良く見せたことで、SIGGRAPH でも注目され一気にポリゴン・ピクチュアズの存在が知られるようになりました。



SIGGRAPH 1989に出品された『XYZ』(『XYZ 河原敏文とポリゴン・ピクチュアズのコンンピュータ・グラフィックス』(パイオニアLDC)より)
野口:技術はもちろん、それをどう表現するかも重視していたわけですね。
塩田:河原さんは、技術よりも映像の面白さに重きを置かれる方だったのです。UCLA(カリフォルニア大学ロサンゼルス校) 在学中に何気なく受講した 3DCG のクラスが面白くて、そのままのめり込んだそうです。彼は新しいことへの挑戦が大好きなんです。誰もやっていないことを、圧倒的なクオリティで世界に向け発信していくのが河原さんのポリシーで、ポリゴン・ピクチュアズはこのポリシーを今なおミッションとしています。
野口:河原さんのポリシーを実践する上で、当時は 3DCG が最適なツールだったと。
塩田:そうです。その頃は技術力と表現力を磨いていれば、世界一になれると思っていました。93 年には『Michael the Dinosaur』という 3DCG アニメーションを制作しました。スケルトンによるアニメーションシステムや、バンプマッピング、3D ペイントなど、当時としては先進的な挑戦をしていましたね。ところが、同年に『ジュラシック・パーク』が公開されたのです。



1993年『Michael the Dinosaur/恐竜マイケル』1'00"(監督:河原敏文)
© POLYGON PICTURES
野口:あの映像は衝撃的でしたね。
塩田:90 年代初頭から、ハリウッドがもの凄い勢いで 3DCG に力を入れ始めたのです。一方で、日本は 80 年代の博覧会映像ブームが終焉を迎えていて、それを代替できるようなパワーは生まれなかった。開発力と資金力の差をみせつけられて、河原さんはそれまでの考えを改めたのです。研究開発や技術革新への深追いはせずに、キャラクタービジネスやアニメーションに特化する方針へと転換しました。
野口:その方針転換が、『資生堂 HG Series Penguin Version』(イワトビペンギン ロッキー X ホッパー)シリーズ(1995 〜1997)のヒットへとつながるわけですね。
塩田:そう。ロッキー X ホッパーがヒットして、キャラクターの版権ビジネスで攻めていこう、第二のロッキー X ホッパーを考えようという流れになりました。僕がポリゴン・ピクチュアズと関わり始めたのはその頃ですね。95 年は『トイ・ストーリー』が公開された年で(日本での公開は96 年)、「ピクサーに続け」というのがキーワードになっていました。一方、ゲーム業界では 3DCG ムービーの需要が高まってきて、3DCG が凄く万能なツールのように思われ始めた時代でした。そんな時代の勢いを感じて、ナムコの中村さんも映画をつくりたいと考えたのです。これに河原さんも賛同し、我々もハリウッドに対抗できるような映画を生み出そうという話になりました。



1995〜1997年 資生堂『HGスーパーハード』TVCMシリーズ
© SHISEIDO・ © POLYGON PICTURES
野口:その話から、ドリーム・ピクチュアズ・スタジオ(※ 1)の設立にいたったと。
※1:ドリーム・ピクチュアズ・スタジオ
通称DPS。ナムコ、ソニー・コンピュータエンタテインメント、ポリゴン・ピクチュアズの出資によって1997 年に設立された 3DCG 制作会社。総制作費 80 億円のフル 3DCG 映画の制作に取り組んだが、映画は完成することなく1999 年に解散となった。
塩田:でも結局その勢いはバブルに過ぎず、2000 年頃には崩壊しました。ゲーム業界も徐々に勢いを失い、3DCG が万能でないことは出資者の目にも明らかになった。「CG 憎し」みたいな風潮まで出てきました。ポリゴン・ピクチュアズも目標半ばで破綻しそうになったのですが、DPS で培ったハリウッド基準の制作ノウハウ、技術、70 人近い人材といった財産だけは何としても留めなきゃいけないと、河原さんや僕を含む関係者で話し合いました。当時のポリゴン・ピクチュアズではロッキー X ホッパーの TV シリーズの企画が進行していたので、DPS のインフラを構築したスタッフの大半に移籍してもらったのです。でも突然50 〜60 人体制になったことで、1 年も経たないうちに経営が厳しくなりました。
野口:ちょうど私がポリゴン・ピクチュアズに所属していた時代ですね。その頃に会社の舵取りをしていたのは塩田さんですか?
塩田:99 年以降は基本的に僕がやってきました。この厳しい時代を乗りきれたのは資本のお陰ですね。当時は『ポケットモンスター』の成功などもあり、キャラクタービジネスへの期待感が一般経済の中にも蔓延していました。ロッキー X ホッパーをヒットさせたポリゴン・ピクチュアズなら、次も当てられるだろうという判断から、今では考えられない株価で投資会社の資本が入ってきたのです。そこで時間を稼ぎながら、受注中心のビジネスへと転換していきました。その際に、当時の日本ではまだまだ認知されていなかった大規模制作の受注を中心に営業していこうと決めたのです。
野口:DPS で培った大規模制作のインフラやワークフローを活かせるプロジェクトを探したわけですね。
塩田:アメリカは大規模制作の流れに乗っていましたし、日本にもいずれその流れがくるにちがいないと思いました。国内他社との差別化にもなりますしね。『デジタル所さん』(2000〜2001)、『げんき げんき ノンタン』(2002〜) といった国内の TV シリーズや、ゲーム向け 3DCG ムービーを受注する一方で、DPS 時代のコネクションを使って海外への営業も地道にやっていきました。そうして 2005 年にディズニーの 『プーさんといっしょ』(原題:My Friends Tigger and Pooh) を受注するに至ったわけです。

野口:海外への営業を始めてから、大規模制作を受注するまでに 5 年を要したわけですね。
塩田:それまでに小規模な制作やテストを何度も実施して、ようやく受注できました(苦笑)。最初に質問された会社継続の秘訣と言えるようなものは何もないですね。ただ、強いて言うなら 「創業者の "DNA"」 でしょうか。河原さんという創業者の、常に他人とちがうことをちがうスケールでやろうとするポリシーが、ポリゴン・ピクチュアズには脈々と受け継がれています。今の社内には、河原さんをはじめ創業時にいらした方は誰も残っていませんが、河原さんの DNA を受け継ぐための人や資金は、その時々の必要に応じて自然と集まってきました。日本の法律では、会社を "法人" と呼び、一方で人間を "個人" と呼びますよね。どちらにも人という字を当てる。英語の場合は Enterprise と Individual だから、まったく異なる概念の言葉です。日本語の場合は会社にも人格があると考えている。この考え方は凄く正しいと僕は思っています。会社は、それを生み出した人の DNA に多かれ少なかれ支配される運命にあるのです。子供が親元を巣立って、親とは別の存在だと思っていても、最終的には親に似てしまうようなものですね。河原さんのタダでは死なない生命力や強い意志が、ポリゴン・ピクチュアズを生かし続けてきたのだと思います。
3DCG のパイプラインに 2D アニメの良さを融合させたい
野口:では続いて、3DCG アニメに関する塩田さんの考えをお伺いします。ポリゴン・ピクチュアズは国内市場を主なターゲットとせず、早い時期から海外で営業をなさってきた。その理由を教えていただけますか?
塩田:我々が大規模制作体制を維持していくと決めた 1999 年当時、国内には 3DCG アニメの市場が存在しなかったのです。アニメ市場はありましたが、絶頂期でさえ 1 話当たりの制作予算は 2,000 〜2,500 万円程度でした。この予算で 3DCG が作画に勝つ術があるとは思えなかったのです。3DCG で勝ち目のある表現をするには、絶対に一定額のバジェットが必要だという思いがありました。それがなけれな、本来のポテンシャルを発揮できないままに負けてしまう。だとしたら、そのバジェットを得られる北米市場で勝負をかけるしかない。だから北米を中心に営業を始めたわけです。
野口:ポリゴン・ピクチュアズが北米向けに制作した 『超ロボット生命体 トランスフォーマー プライム』(原題:Transformers Prime、2010〜) などの TV シリーズは、日本でも放送し始めていますよね。いずれ制作コストが下がれば、日本でも 3DCG アニメが制作されるようになると思われますか?
塩田:はい。その時代は間近にきていると思います。アメリカであっても子供向けの TV シリーズはそれほど大きなマーケットを形成していませんし、かつてほどのバジェット獲得は難しくなってきています。『トランスフォーマー プライム』の続編を作るとしても、コストダウンは避けられないでしょう。世界ターゲットの作品であっても、国による制作コストの格差は減っていくと思います。これに対応するには、カナダやイギリスのような政府による優遇措置のある土地で制作するか、高付加価値の仕事だけを国内で行う体制に移行するしかありません。つまり日本のアニメ業界が実践してきたような、設計や試作くらいまでは日本でやって、それ以降の量産は制作コストの安い海外に流していくというやり方です。我々の場合は、マレーシアの 3DCG プロダクションと合弁会社を設立しました(※2)。
※2:マレーシアの合弁会社
2012年10月17日、ポリゴン・ピクチュアズはマレーシア有数のデジタルアニメーションスタジオ 「Silver Ant Sdn. Bhd.」 との合弁会社 「Silver Ant PPI Sdn. Bhd.」(資本金:3,200 千リンギット、出資比率:ポリゴン・ピクチュアズ 51%・Silver Ant 49%)を設立することを発表した。同社は2013年1月1日設立を目指しており、第一弾制作作品は『Transformers Prime 3rd season』になる予定(プレスリリース)
『超ロボット生命体 トランスフォーマー プライム』PV
© 2010 Hub Television Networks, LLC, All Rights Reserved.
野口:海外で制作するのであれば、やはりターゲットは世界市場でしょうか?
塩田:制作する場所に関わらず、世界市場に向けた作品をつくる必要はあると思います。むしろ日本の場合は従来よりも制作コストを上げて、世界ターゲットの作品を集中してつくっていった方が良い。世界に向けた作品を我々が主体性を持って商品化するためには、今一度日本のアニメ業界に立ち戻っていく必要があると感じています。ポリゴン・ピクチュアズは海外の TV 業界では相当知られていると思いますが、日本ではほとんど知られていません。国内の仲間を増やすために、日本の既存のアニメ制作のシステムに入っていくことも検討しています。
野口:なるほど。ですが、日本の既存システムの中で 3DCG アニメをつくるためには、大前提として 3DCG アニメの認知度をさらに高める必要がある気がしてなりません。この連載もそうした活動の一環として始めました。ゲームムービーのフル 3DCG に慣れ親しんできた若い世代は、『プリキュア』シリーズ の 3DCG でつくられたエンディング映像も違和感なく受け容れてくれている。だけど国産 3DCG アニメの成功事例はまだまだ少ないゆえに、3DCG だと流行らないんじゃないかという恐怖心を制作者側が払拭しきれないのではないかと。
塩田:だったら「3DCG でつくります」って言わなきゃ良いんですよ(笑)。CG だ、作画だ、Flash だといった制作方法でアニメーションを分類することに意味があるのだろうかって、凄く疑問に思うのです。なので、最近のポリゴン・ピクチュアズは "デジタルアニメーションスタジオ" って、名乗っているんですよ。
野口:CG プロダクションではなく、あえてアニメーション制作会社だと表明しているわけですね。
塩田:そうです。媒体や使える予算、マーケットなどに応じて、手描き風のルック、セルっぽいルック、フル3D ならではのルックなどを柔軟に選択すれば良いのです。セルっぽいルックで輪郭線を付けるにしても、3DCG でつくった方が確実に効率的で良いものができるなら、3DCG を使えば良い。一方で特定のアニメーターさんでなければ表現できない画であれば、作画すれば良いのです。3DCG だ、作画だというのは作品内に占めるパーセンテージの問題であって、作品自体を区別するものではないように思います。観る側が期待するのは、コンテンツそのものの魅力。キャラクターの可愛さ、子供にアピールする力、ストーリーの面白さなどが大切なのであって、画のクオリティは二の次なんですよ。


野口:アニメーションとして気持ち良く見える画を予算内でつくることができれば、ツールは何でも良いと。そうすると、いずれはポリゴン・ピクチュアズが作画チームを持つようになるのでしょうか?
塩田:持ちますよ。現状の 3DCG のパイプラインに、日本の作画アニメの良さを融合させるための設計を既に始めているのですが、世界標準であるデジタルベースの 2D アニメーションパイプラインを増設するつもりです。日本の 3DCG は歴史が浅いので、ストーリーや場面の構成力、キャラクターや世界観の設定力、色彩設計といった点でまだまだ作画にはおよばない。なぜなら CG 業界にはストーリー・テラーがまだ少ないのです。作画の長い歴史の中で培われたノウハウを吸収して、構成力を上げていく必要があります。
野口:今はアニメ会社がデジタル部門として 3DCG 制作部隊を構築し始めていますが、CG プロダクションが作画(2Dアニメーション)部門を設けるという逆転現象が起こってもおかしくないというわけですね。けれど作画のアニメーターが CG プロダクションに移っても、「3D は面倒くさい」という理由で結局は定着しないという現象が起こってきましたよね。システム自体を変えないと、作画の方々が 3DCG 側にくるのは難しいのではないでしょうか?
塩田:3DCG アニメーションをつくる以上は、それなりに 3DCG のインターフェイスや仕事のやり方を覚えていただく必要があるでしょう。ですが、今後は 3DCG アニメに純粋な作画を盛り込む比率がどんどん上がっていくと思いますし、上げるべきだとも思います。作画の方々が培ってきた力を発揮する場は広がっていくでしょう。
大規模制作というコンセプトを常に意識している
野口:ポリゴン・ピクチュアズは早い時期から大規模制作という明確なコンセプトを打ち出していて、それを実践できるプロジェクトを積極的に推進してきたわけですね。僕自身、これからの時代の CG プロダクションは得意ジャンルをしっかりと表明していく必要があるのではと感じています。
塩田:本当にそうだと思いますよ。会社を起ち上げた直後はジャンルを問わず仕事を受けざるを得ないでしょうが、自分たちの会社がどんなスタイルで存在していくのかというコンセプトは明確にしておいた方が良いでしょう。我々はここ十数年、大規模制作、量産、ビッグプロジェクトをねらうという方針でやってきている。だからコンセプトに合わせて、大規模制作を担える体制を構築してきました。
野口:分業制を敷き、数多くのスペシャリストを抱えるということですね。
塩田:そうです。量産するなら分業しなくちゃいけないし、スタッフも数百人規模で雇用する必要がある。30 人の会社が量産しますといっても無理ですからね。受注内容に合わせて、会社のスタイルや規模を構築する必要があります。例えばアメリカの Blur Studio は予算規模の大きい様々な作品を手がけていますが、最小限の分業しかしていません。彼らは 80 人くらいのゼネラリスト集団なんですよ。何故かというと、彼らが受注する仕事は基本的に 3 ~ 4 ヶ月単位で制作するからです。このスピードで、高いクオリティの作品をつくっていこうとすると、我々のような完全分業では間に合いません。仮に Blur Studio が手がけているような仕事を我々が受注するなら、汎用的なパイプラインを構築する必要があるでしょう。

野口:アニメーションの話から逸れますが、コンセプトに関連して伺いたいことがあります。ポリゴン・ピクチュアズは VFX の受注を早々に止めましたよね。どうしてでしょうか?
塩田:VFX では世界で勝てないと思ったから止めたのです。アメリカやイギリスで圧倒的に多いのは VFX スタジオですよね。市場を考えると、アニメーションよりも VFX の方が雇用力があります。でも薄利のビジネスで、今後予算が上昇する見通しもない。僕自身に VFX の経験がないこともあって、勝てる気がしないのです。ただし VFX のバックグラウンドがある人、例えば海外の VFX スタジオで経験を積んだ人であれば、日本のプロダクションからでも営業ができると思います。VFX スーパーバイザーの経験があって、現場を知っていて、英語が話せて、ワークフローに精通している人材が必要ですね。そんな人さえいれば、日本人はきめ細かくて真面目だから、もっともっと仕事を引っ張ってこられるはずです。
野口:海外での制作経験があって、海外の人たちとの横のつながりを持っている人なら、受注しやすいのでしょうか?
塩田:友人関係にあるような、信頼できる相手に依頼することはよくありますからね。そうった点で、イギリスのソーホー(※3)の仕組みから学べることは多いように思いますね。Double Negative は、ここ数年でいきなり 1,000人規模になりましたよね。どうして複数の 3DCG プロダクションが共存しながら繁栄できたのか、その要因を分析することは有効だと思います。もともとソーホーには広告代理店が集まっていて、VFX スタジオをつくっていたんですよ。彼らは別々の会社で働いていますが、仕事が終わったらパブで交流しています。仮に日本の代理店や VFX スタジオが 1 箇所に集結していたとしても、どこかの居酒屋に毎晩集まって気軽に交流するかどうかはわかりませんが。
※3:イギリスのソーホー
ロンドンのソーホー(Soho)地区のこと。イギリスの4大 VFX スタジオと呼ばれる The Moving Pictures Company(MPC)、Double Negative、Framestore、Cinesite をはじめ、様々な映像を制作するプロダクションが数多く集まっている。

野口:日本の場合、皆さん夜も働いてますしね(苦笑)。横のつながりに加えて、ポリゴン・ピクチュアズのような世界標準のパイプラインをつくらないと、海外の仕事を受注するのは難しいでしょうか?
塩田:確かに我々のように TV シリーズを受注するのであれば、規模の大きさやシステムが問われます。でも数カットだけとかセットアップだけといった部分発注であれば、それほど厳密なことは要求されませんよ。むしろ重要なのは、どの程度相手を知っているかどうかという信頼関係です。僕自身、付き合いのあった ILM のディレクターやプロデューサーに連絡をとって、何度もテストを受けた結果、ようやく受注にこぎ着けましたから。

ポリゴン・ピクチュアズは、山村浩二監督のアニメーション短編 『マイブリッジの糸』(2011) 製作に参加(出資)。こうした活動からも、アニメ制作会社としてより包括的な事業展開を目指していることが窺える
© 2011 National Film Board of Canada / NHK / Polygon Pictures
野口:会社間のパイプラインの共有に関しては、どう思われますか? 人材流動を促進するには、共有が必要だという意見をよく聞くのですが。
塩田:資本を共有しない限り、会社間のパイプライン共有は難しいと思います。外注の際に外注用のリグを用意して、データを引き戻せるようにする、といったことならやりますけれど。パイプラインには各社固有の癖があります。ソフトウェアやインターフェイス、データの処理方法などを各社で統一させようとすると、会議とやり取りのために長い時間や手間がかかるでしょう。よほどの信頼関係や資本共有がなければ実現は困難ですね。ただし、ワークフローであれば共有できます。日本はまず、世界標準のワークフローの共有から始めた方が良いでしょう。
野口:おっしゃる通り、アニメ業界、VFX 業界を問わず、ある程度のワークフローの共有は必要でしょうね。今日のお話で、塩田さんとポリゴン・ピクチュアズの目指すビジョンがよく理解できました。ありがとうございました。
Supported by Enhanced Endorphin
INTERVIEWER_野口光一(東映アニメーション)
EDIT_尾形美幸(EduCat)、沼倉有人(CGWORLD)
PHOTO_弘田 充
LOCATION_hanabi
Enhanced Endorphin 展開中
シリーズ企画「日本にフル CG アニメは根付くのか?」は、 "日本におけるフル CG アニメーションの振興を目指す" Enhanced Endorphin(通称:EE) との共同企画。EE では、フル CG アニメーションの制作工程などをわかりやすく紹介するオリジナルコンテンツなども用意されているので、ぜひアクセスしてもらいたい。