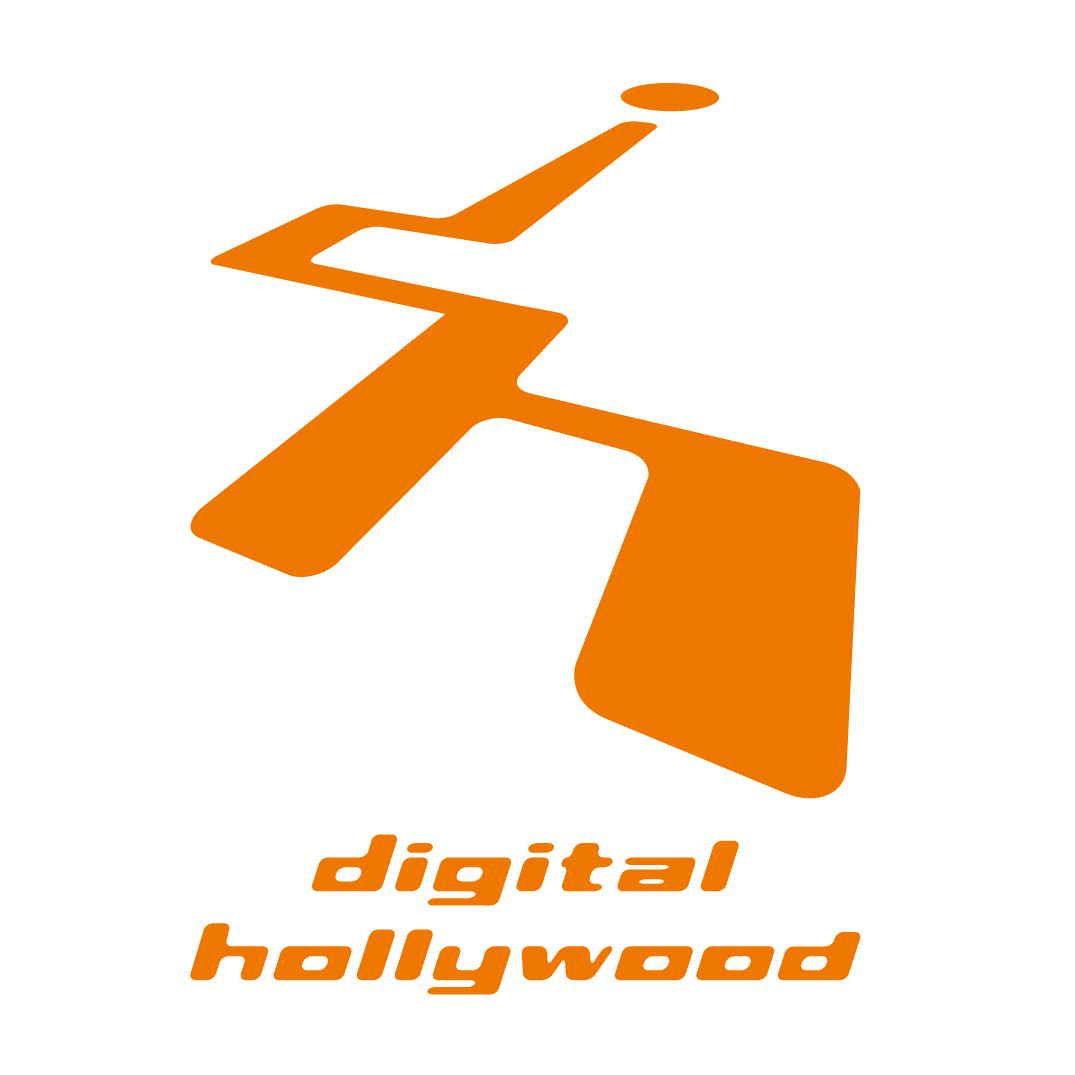早野海兵氏と祭田俊作氏に聞いてみた。「CGはツールからインフラに」CGのこれからについて思うこと

[PR]
ほんの数年前までは「特殊技術」として認識されていたCGだが、ここ最近で急激に需要が伸び始めた。
周りを見渡してみてほしい。いたるところにCG技術によって生み出されたものが目に入ってくるはずだ。それも数え切れないほどに。いつの間にかCGは、人々の生活を支える存在となりつつあるようだ。
様々なテクノロジーとの親和性が高いCGはこれからどのように変化していくのだろう。30年以上にわたってCG業界の第一線で活躍してきた早野海兵氏と、2014年にデジタルハリウッドでCGを学び3DCGアーティストとして活躍中の祭田俊作氏に話を聞いた。
CGにのめり込むことができた貴重な学生時代
CGWORLD(以下、CGW):お二人は、祭田さんが「KLab Creative Fes'15」(KCF'15)の静止画部門で特別賞を受賞した際、早野さんが審査員をされていたという接点があったとお聞きしました。まずは、祭田さんがKCF'15へ応募した背景から現在にいたるまでの経緯をお聞かせいただけますか?
祭田俊作氏(以下、祭田):美大を休学してデジタルハリウッドで1年間CGを学び、復学後に卒業制作としてつくった作品をKCF'15に応募しました。卒業後はVRを制作する会社に入ってキャラクター制作やモデリング、映像制作、企画、ディレクション等々を担当し、2年前にフリーランスとして独立しました。VRの知見を活かしてリアルタイム系の案件やバーチャルプロダクションなどの依頼も増え、現在は幅広く映像制作のお仕事に携わっています。
CGW:早野さんは30年以上にわたりCGの現場で活躍されていますが、CGを始めたきっかけはどのようなものだったのですか?
早野海兵氏(以下、早野):もう随分昔の話になりますね(笑)。当時はまだCGが一般的ではなく、ごく限られた一部の人しかCGをやっていませんでした。ちょうど『ターミネーター2』(1991)や『ジュラシック・パーク』(1993)が劇場公開され話題になっていた頃ですね。「CGが一般的ではなかった」というより、そもそも自宅にPCすらない時代だったので、まさか自分がCGの仕事に就くとは想像していませんでした。

早野海兵氏/Kaihei Hayano
株式会社画龍
日本大学芸術学部卒。ソニー・ミュージックエンタテインメント、ソニー・コンピュータエンタテインメントを経て創作活動の世界へ。2007年に画龍を設立。現在、CGWORLD.jpにて「+画」連載中。アートディレクターを務めながら講師や執筆等、幅広くCG業界に貢献している。
kaihei.net
www.ga-ryu.co.jp
Twitter:@Kai_ryu_Kai
CGW:遠い存在だったCGとの接点はどこにあったのですか?
早野:大学のゼミでCGを触ったのがきっかけです。リンクス・デジワークス(現:IMAGICA Lab.)から講師を招いた授業があり、そこではじめて「CGの仕事」が存在することを知りました。これを機にCGを始めてみたらすごく面白くて、「CGでもっといろんなことができるんじゃないか」とどんどんのめり込んでいきました。CGと出会うきっかけとして学校の存在は大きく、のめりこめる環境であったことはとても重要だったと思います。
CGW:祭田さんがCGを始めたきっかけはどのようなものだったのですか?
祭田:大学に進学した頃、『スター・ウォーズ』シリーズや『ロード・オブ・ザ・リング』(2002)のメイキングを観て「マットペインター」という職業を知ったのがそもそものきっかけです。アナログのセットで撮影してデジタルに取り込むといった時代で、ガラスの板に絵を描いている様子が映像に収められていました。

祭田俊作氏 /Shunsaku Matsurida
フリーランス
多摩美術大学グラフィックデザイン学科卒。デジタルハリウッド本科CG/VFX専攻卒。大学とデジタルハリウッドのダブルスクールを経て、ティフォンでVR作品の制作やディレクションを経験。MANISPINの設立に協力。現在はフリーランスのCGゼネラリストとして様々な分野の制作に携わっている。
www.drawnlot.com
Twitter:@floody104
CGW:映画の裏側の世界にも興味を持たれたということですね。
祭田:はい。またちょうど同じくらいの時期に、国内外のアーティストの作品を見ている中でとても高精細な絵を描いている人たちがいて、「どうやって描いてるんだろう」と疑問に思い調べてみたところCGが使われていることがわかりました。大学ではグラフィックデザインを専攻していたのですが、広告デザインや手描きアニメーションの授業が中心だったので、CGも学べるよう大学に直談判しました。でも結局、教えてくれる先生が学内にいなくて、「じゃあ、4年間大学で何をしたら良いのかな」という状態になってしまって(笑)。
早野:なるほど(笑)。大学でCGを教えるようになったのはごく最近ですもんね。
祭田:そうなんです。CGに関するチュートリアルもあまりなかったので、独学で学ぶことに限界を感じていました。やはり専門学校に行くのが良さそうだと思ってデジタルハリウッドに連絡したんです。
CGW:他の専門学校にもCGのコースはあったと思うのですが、デジタルハリウッドを選んだのはなぜですか?
祭田:1年間の短期集中コースがあったのはデジタルハリウッドだけだったからです。大学を2年休学すると除籍されてしまうので、何年か通う必要のあるコースには通えませんでした。ということで、復学後に独りでもある程度の作品がつくれるレベルになることを目標に、1年間学べるだけ学ぶつもりでデジタルハリウッド本科CG/VFX専攻を受講することにしました。
CGW:「1年でつくれるようになれる」といったカリキュラムだったのですか?
祭田:正直、授業に出るだけでは難しいと思います。ただ、デジタルハリウッドにはオールナイトで制作できるシステムがあって、月曜日以外は24時間教室が空いているんですよ。自宅にはCG制作ができるほどハイスペックなPCがなかったし、「だったら24時間デジタルハリウッドにいれば良いんじゃないか」と(笑)。
CGW:「朝から晩までPCの前にいた」と話すCGクリエイターは多いように思います。それほどの魅力がCGにはあるんですね!
CGの魅力は「終わらない楽しさ」それこそが長く続けられる理由
CGW:CGへの関心はいつまでも色褪せないものなのでしょうか? お二人がCGを続けている理由を聞かせてください。
早野:それはもう「楽しいから」のひと言です。僕は真面目なタイプの人間じゃないしすごく飽きっぽいんですよ。何をやっても続かないんだけど、CGだけはやってもやっても底がないし、表現の幅が本当に広くて終わりがないんですよね。技術の進歩により、できることがどんどん増えていくのでCGには強い発展性を感じます。今、こうやって身の回りを見渡してみても、CGでつくられているものであふれていますからね。
祭田:あと、良い意味で「何かと楽ができる」のも続けられる理由かもしれません(笑)。CGだと頭の中で想像したものを最短でアウトプットできるので、「どんなものをつくろうか」とクリエイティブなことに時間を割けるんです。新しいことがどんどん出てきてそのたびに挑戦できるのでルーティンに陥ることもなく、選択肢がどんどん増えていくので楽しいんですよね。
早野:楽しいと思えることはとても重要ですね。われわれのようにエンターテインメントの仕事をしている以上、そこには必ず「楽しい」という要素が存在します。人を楽しませたり和ませたりする仕事なので、つくっている自分たちが「楽しい」と思う気持ちをもって長く続けていきたいですよね。
CGW:30年以上CGのお仕事をされてきて、ご自身の中でいつまでも変わらない部分と大きく変わった部分はありますか?
早野:いちアーティストとして、つくるもののテーマや好きなものはそれほど大きく変わりませんが、CGの世界は変化も進化もとにかく早いですからね。しかも、アウトプットする先がゲームだったり映画だったりVRだったりと様々なので、「必然的に手段が変わる」という感じです。
CGW:ものごとの考え方やアーティストとしての心境の変化などはいかがですか?
早野:考え方が大きく変わったことがあります。若い頃は、自分なりに「人のためにつくっているつもり」でいたのですが、それでもやはり自分のために作品をつくっていた傾向があったように思います。しかしあるときから「人のために、誰かのために」、極端に言えば「世界平和のために」と考えるようになりました。人それぞれ、いろんな変わり方があると思いますが、僕の場合は「自分の喜び」から「誰かの喜び」に視線を向けたことで、物事の見え方や捉え方が大きく広がったように思います。
CGW:早野さんは20年以上にわたりCGWORLDで連載を続けられていますが、毎回、読者がポジティブな気持ちになるよう配慮されていますよね。
早野:そうですね。映像制作において、見る人のことを考えて制作するという意識は非常に重要です。文章や音楽なども人に影響を与えますが、脳が理解するまでに少し時間が必要ですよね。でも画像や映像はダイレクトに頭の中に入ってくるので、人に与える影響が非常に大きいんです。誰かの人生を変えてしまうほど大きな力をもっているので、使い方を間違えてはいけません。楽しんで観てもらえるよう常に意識して制作することは、クリエイターの責任でもあると考えています。
CGW:「自分のためにつくる」という考えから「人のためにつくる」という考えに変わったのはなぜですか?
早野:きっかけとなったのは東日本大震災でした。僕は東北出身なので被災した実家を手伝いに戻ったのですが、力になろうと応援に行ったにも関わらず、まったく役に立てなかったんです。体力はないしセメント1つつくれないし、本当に何もできなかった。むしろボランティアの弁当を食べて邪魔しに来てしまったようで、「いったいここまで何をしに来たんだ」と心底情けなくなりました。それ以来、「何のためにここに存在しているのか」を真剣に考えるようになり、気がついたら「人に教える」ということに興味をもちはじめました。そんな経緯で「自分にできる範囲のことで、人のためにできることを」と考えていたときに、ちょうどデジタルハリウッドからお話をいただき、講師を始めることになりました。現在もオンラインで「3DCGクリエイター講座[3ds Max]」の講師を務めています。

「ツール」から「インフラ」に生活の一部になりつつあるCG技術
CGW:先ほど早野さんは「CGは身の回りにあふれている」とおっしゃっていました。お二人に伺いますが、CGの活用の幅や可能性は今後どのように広がっていくとお考えですか?
祭田:テクノロジーの新しい使い方を見つけて挑戦する人たちが増えています。特にCGの分野は2~3年でガラリと様子が変わりますし、ことエンタメにおいてはどこからどのようなものが生まれてくるか、もう予測できません。僕自身、仕事を通してはじめて「どのようにつくられているのか」を知ったりしますからね(笑)。ただ、ゲームだろうと映画だろうと「個人でできること」がさらに増えていくと思うので、挑戦したいことを見つけたらすぐに飛びつけるようにはしておきたいですね。
早野:ほんの数年前までCGは単なる特殊技術でしかありませんでしたが、これからは「生活」とか「世界」に関わってくるんじゃないかな。仮にメタバースがもっと発展すればCGは単なるツールから「コミュニケーションツール」や「インフラツール」になり得ます。そうじゃなくても、CGが少しでも使えたら様々なものとの接点が生まれ、いろんなものをつくり出すことができます。実際、すでに生活のいたるところにCGが深く関わっています。これがさらに広がると「生き方」に関わるツールになってもおかしくないですよね。
祭田:CGソフトの技術が上がり、無料で手に入れることもできますからね。もうすでに、CGでつくることが特殊なことではなく「ちょっと本気で勉強すれば誰にでもできること」になっていますし。
早野:そう。そうなると、今までのように「ここからここまでをCGで制作している」といった分け方ではなく、もはやCGかどうかすら考えることがなくなるほど「生活の一部」として浸透してくるのではないかと思います。これはもう「CGの活用の幅が広がる」といった小さな話ではなく、「生活の基盤を担う技術」として人々の暮らしを支える存在になる可能性すら考えられますよね。今から少しでもCGの技術を身につけておくときっと何かしらの助けになるだろうし、「プラスアルファ」で人生を楽しくする秘訣になるかもしれませんね。
祭田:実際、CGの世界へのハードルが下がったことで需要が生まれているように感じます。今後は「CGクリエイター」という職業的なカテゴリーではなく、「CGを使うことができる」という一般の人が増えていくはずです。CGはSNSやインターネットとの親和性が高いので、個人が世界に向けて作品や情報を発信できるようになったことが、さらなる追い風になっていますよね。
CGW:とても自由で未知なる可能性を感じますね。可能性の芽を摘まないよう、個人個人の発想力と行動力を大切に育てていきたいですね。
早野:これは余談かもしれませんが、僕がデジタルハリウッドで講師をさせていただこうと決めた背景には、学びの環境として一切の強制がなくとても自由なイメージがあったからです。しかもその自由は教える側にも及んでいて、カリキュラムなども講師に全て任せてくれるんですよね。僕としては、生徒の皆さんにCGの仕事についてちゃんと伝えたかったし、オンラインでの授業に挑戦してみたかったという思いがありました。こういった姿勢から、クリエイターに挑戦をさせてくれる「自由な土壌」があるんじゃないかと思ったんです。デジタルハリウッドからは非常に多くのクリエイターが輩出されており、皆さん大変活躍されていますが、やはり「学びの環境として自由であること」が大きな理由かもしれません。
CGW:「誰に教わるか」が重視されがちですが、「どのような環境で学ぶか」も重要なんですね。
早野:もしかすると「講師」はそこまで重要ではないかもしれません。もちろん、講師の影響を受けることもあるでしょうけど、結局は自分がそれを「やるか、やらないか」なんです。いくら素晴らしい講師の下で学んでも、自分が行動を起こさなければ何も変わりません。自分で行動を起こそうとしたときに、実行できる環境があるかどうかが重要なんです。CGを学ぶにふさわしいPCがあって、質問に答えてくれる講師がいて、志を同じくする仲間がいて。そういったものがキチンと揃っている環境は非常に貴重ですし、ものすごく恵まれた場所なんですよね。
祭田:自分が好きなものを楽しくつくっていれば、技術的なことは自然と身につくものですからね。つくってみて納得がいかなかったら「なぜ上手くいかなかったのか」をその都度考えて、そしてまた新しいものをつくってみる。これをくり返していくうちに「何が良くて何が良くなかったのか」がわかってくるんですよ。僕はこの過程を楽しみすぎて結局就活しなかったんですけど、それでも業界の方々は優しく迎え入れてくれたので(笑)。そのためにも、やはり早野さんが話されたように「まずはやってみる」。何もつくらずそのままじっとしていては何も起きませんが、自分でつくった作品を発表すると必ず何かしらが返ってくるものです。
早野:CGを始める前は不安が多いと思いますが、興味があったらまずは挑戦してほしいですね。なぜかCGをやっている人は優しい人が多いですし(笑)、場所も年齢も関係ありません。心配しないでCGがある環境に一歩踏み込んでみましょう。
CGW:お二人のお話を聞いてCGの未来への勇気と自信が湧いてきました。早野さん、祭田さん、本当にありがとうございました!
デジハリ卒業生に聞く!
1994年の設立以来、プロを養成する場として常に最先端のまなびを提供し、CG・映像業界に多くの人材を輩出し続けているデジタルハリウッド。ここでは、同校を卒業し、現場で活躍するお二人にCGの仕事の魅力やこれから業界を目指す人たちへのメッセージを聞いた。
榊原將師さん(2016年本科CG/VFX専攻卒)に聞く!

榊原將師氏/Masanori Sakakibara
FXアーティスト
プロダンサーから、セカンドキャリアとしてCG業界を目指し、2015年に27歳でデジタルハリウッド本科CG/VFX専攻へ入学。卒業後はFXアーティストとして数々の作品に参加。2021年に参加作品にて、アニメーション界のアカデミー賞とされる、第48回アニー賞で「Best FX for TV/Media」にノミネートされる。アーティストとして活躍しながら、デジタルハリウッドでHoudini講師も務める。
LinkedIn:www.linkedin.com/in/masanorivfx
Twitter:@masatroy
Q1.CGを仕事にして、良かったと思うことを教えてください。
もともと映画やアニメ、ゲームが大好きで、いつか仕事にしたいと思っていました。セカンドキャリアでこの業界に移ったのも、とにかく「好き」という気持ちを変わらずもっていたからだと思います。
この仕事に就くことができて、初めてエンドロールに自分の名前を見つけた時は映画館で泣きそうなほど嬉しかったのを今でも覚えています。
あとは、小さなことかもしれませんが、Houdiniを使って良い感じのエフェクトをつくれた瞬間「自分、天才かも?」と思ったり、その後、すぐ壁にぶつかって「自分、才能ないわ」って思うこと(笑)や、つくった画を周りに認めてもらえたときの、単純にうれしいって感情だったり、それらのくり返しがこの仕事をして数年経った今でも日々感じられるのが「この仕事を選んで良かった」と思えることですね。
目標というか夢もあるので、やめる気は一切ないですし、年を重ねるごとに楽しくなっています。
Q2.CGは、今後どういった分野で、活用が広がっていくと思いますか?
映像以外の分野でも使われているのは、すでに皆さんご存じだと思います。具体的にどう広がっていくかは、可能性の幅がすごく広いなと感じるので、正直わからないです(笑)。
ただ、前職のダンスをしていたときの仲間から「これってCGでできないかな」と、CGでつくった背景で踊りたいといった相談を受けるようになってきたので、最近ではCGをやっていない人にとっても、より身近なものになってきているのかなと思います。
Q3.これからCGスキルを身につけようと思っている人たちへメッセージをお願いします。
自分が好きなことを仕事にしたいと思っていて、それがCGなら今はネットの動画など学習環境が豊富なので始めやすいと思います。
そのなかでも学校に通うのはオススメです。自分以外の人の制作の様子が見れたり、先生や先輩、同期から自分の作品を見て評価してもらったり、アドバイスをもらえたりと、とにかく刺激が多いと思うので、ぜひ選択肢に入れてみてほしいです。あとは卒業後ほとんどの方がCG業界のキャリアに進むと思うので、単純に人脈が増えます。
プログラマー経験や美大出身でもなく、画づくりに関してゼロからスタートした自分みたいなセカンドキャリアで志す方は、仕事をしながらで大変だとは思いますが、短期集中といった意味でも良いと思います。
ありきたりな言い方かもしれないですが、好きだからがんばれるし、なにより楽しめると思います。好きなことを仕事にできるのは本当に素晴らしいことだと思うので、ぜひ一歩踏み出してみてください!
竹本明日香さん(2014年本科3DCGアーティスト専攻卒)に聞く!

竹本明日香氏/Asuka Takemoto
デジタル・ドメイン シニアモデラー
大学とのダブルスクールで2013年デジタルハリウッド本科3DCGアーティスト専攻に入学。卒業後は、フリーランスとしてキャリアをスタートし、その後フラックスに在籍。2018年にカナダへ渡り、アイコンクリエイティブスタジオを経て、現在はデジタル・ドメインでシニアモデラーとして活躍している。
Q1.CGを仕事にして、良かったと思うことを教えてください。
やはり自分がもともと好きだったことに関われることです。私でいえば3Dアニメや映画ですが、何度仕事しても撮影の裏側を見れること、つくったものをスクリーンで見れることは感動します。
もうひとつ最近とくに感じているのは、どこに移住したとしても職に困らないことですね。国内でも国外でも大体需要があるので、どこかに移住したいと思ったときには、仕事の心配をせずに計画を立てられるのはこの仕事の隠れた良さだと感じています。
Q2.CGは、今後どういった分野で活用が広がっていくと思いますか?
個人がコンテンツを発信する時代になっているので、大きい会社で大きなプロジェクトに取り組む映画やゲーム産業などでの需要とは別に、個人のプロジェクトに映像や技術を提供する規模の小さなところにもCGの可能性が無限に広がってくると思います。
最近の興味深い例をあげると、アメリカでNFTアートをつくっている個人の方が、自身のアートを3D化したいと考えていて、その方のイラストがこのぐらいの価値で取引されてるので、3D化したらこのぐらいの価値で取引されるのでは、というような話をしていただいたときに、コンテンツ自体に価値がつくというのがすごく新しいなあと単純に感銘を受けたと同時に、また別の可能性が私たちに開いたんだなと強く感じました。
昔、それこデジタルハリウッドで映像を学んでいた学生の頃に、カフェテリアで「私たちは会社に勤めたいのか、それともアーティストになりたいのか」みたいな青臭い熱い討論を同期と繰り広げていたんですね(笑)。
社会の荒波にもまれるうちに、そんなことすっかり忘れていたのですが、NFTという技術が確立し、デジタル作品が伝統的なアート作品と同じように評価される世の中で、伝統的な芸術家のようになれる未来があるかもしれないという時代に立っている今、しっかりした技術を身につければ、今まで通り会社や個人でかっこいい作品にかかわることもできるし、自分でかっこいい作品をつくって価値を生み出すこともできる。そういった意味で、CGの可能性はさらに広がっていると思います。
Q3.これからCGスキルを身につけようと思っている人たちへメッセージをお願いします。
どんなことでも必要な情報は検索すれば出てくる時代ですが、基本的にはやはり自分で試行錯誤し、新しい知識を吸収しつづける姿勢が、この業界でもっとも求めれるものだと思います。
ですが、はじめはもしかしたら、何がわからないのかわからない状態かもしれません。私も実際、Photoshopのデータのセーブの仕方すらわからない状態からはじめたので、自分には向いてないのではないかと幾度か感じた記憶があります。そういった場合に、デジタルハリウッドのような学校で仲間とともに同じことを学べるというのは、授業以上の大きな支えになります。
日本と海外の両方で仕事をして感じるのは、コミュニケーションの大切さです。CGスキルはもちろんですが、監督やスーパーバイザーが意図することを理解するために、しっかりとコミュニケーションをとることは海外では特に重要だと感じています。仲間と一緒に学ぶというのはそういった下地にもなるのではないでしょうか。
CGスキルを身につけたいなと思っている方は、まず小さな作品づくりから始めてみて、もしそれで行き詰まりを感じるのであれば、思い切って学校に通ってみると、仲間たちの勢いと先生のサポートがまた一歩先のレベルへいく手助けになるのではと思います。とっても楽しい業界なので、がんばってください!
お問い合わせ
デジタルハリウッド
URL:school.dhw.co.jp/
東京本校(御茶ノ水):0120-386-810
大阪本校(梅田):0120-804-810
STUDIO新宿:0120-202-136
STUDIO吉祥寺:0120-362-810
STUDIO立川:0120-311-810
TEXT_三村ゆにこ / Uniko Mimura(@UNIKO_LITTLE)
EDIT_山田桃子 / Momoko Yamada
PHOTO_弘田 充 / Mitsuru Hirota