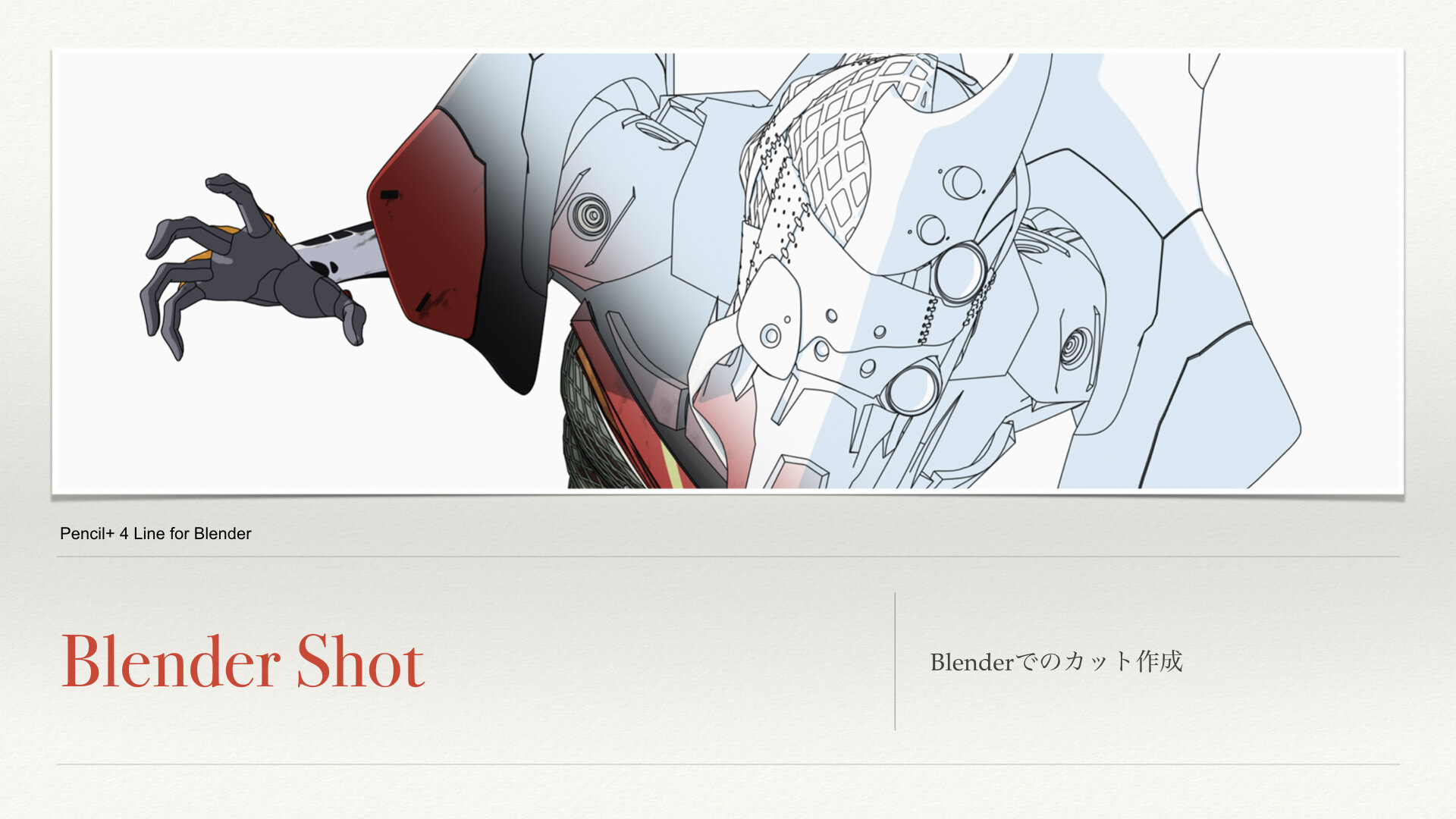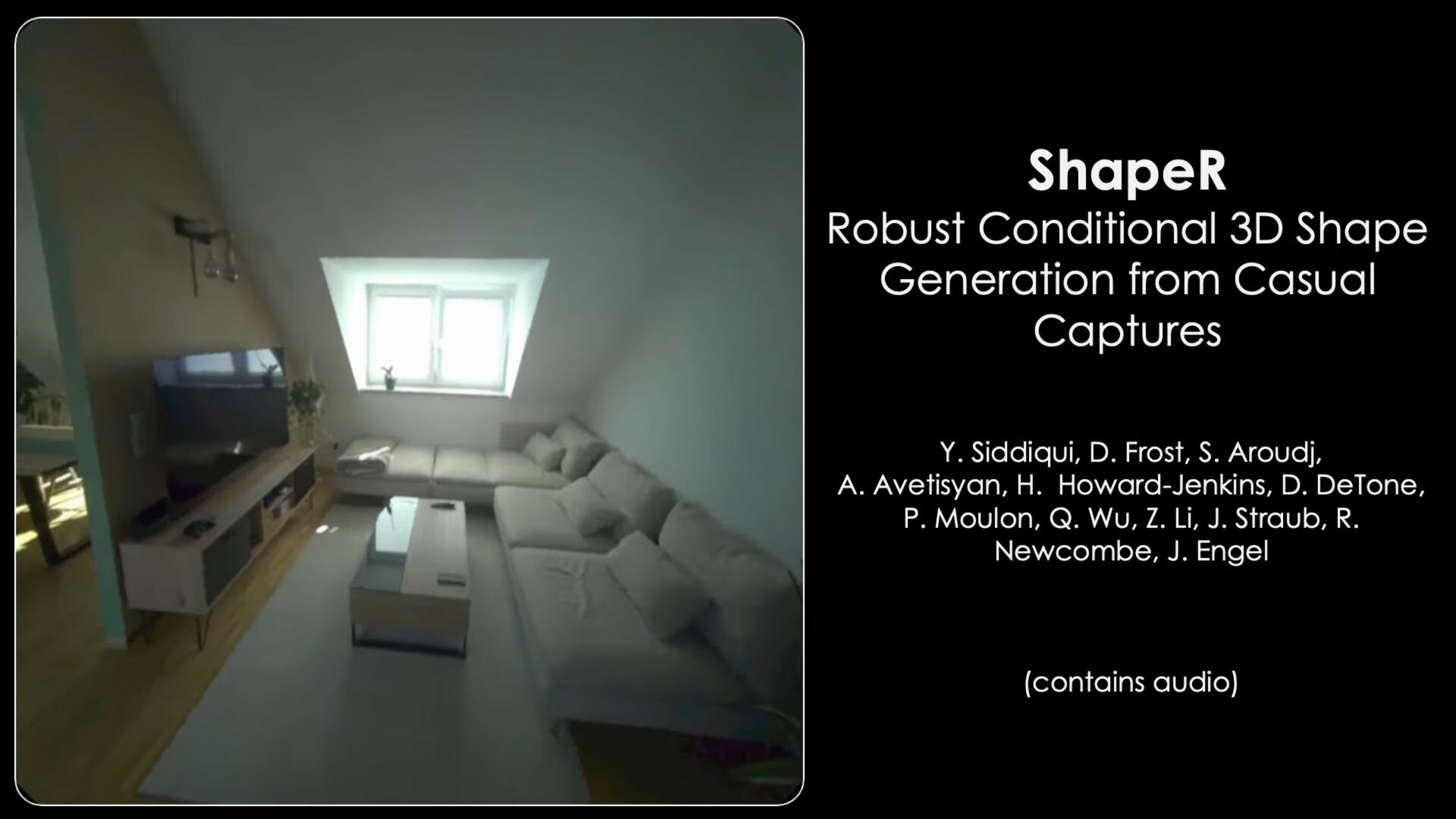東京から1時間、次世代制作拠点「静岡市」のポテンシャルを探る。進出企業と教育機関に聞くデジタル人材の採用と育成の今。

日本のエンタテインメント関連企業の多くは東京に集中しているため、首都圏に拠点を置くことは、クリエイターにとってもプロダクションにとっても、営業の効率を高める上で効果的と言える。しかしその一方で、東京に一極集中していることで人材採用が思うように進まなかったり、近年の物価高騰などによる暮らしにくさは無視できない。
そこで本記事では、新幹線で東京まで1時間というアクセスの良さがあり、かつ東京にはない暮らしやすさを両立させることができる、静岡への拠点設立や移住という選択肢を提案したい。今回、静岡でデジタルエンタテインメント産業に関わる企業と教育機関、それぞれに、インタビューを実施した。
<静岡進出企業の声> 都市圏へアクセスしやすく、同業他社はほとんどいない好立地が魅力

テックチャオ株式会社
代表取締役社長
五十嵐平馬氏
創業4年目ながら26名のスタッフが在籍。スタッフのほぼ全員がエンジニアで、スマホ向けのソーシャルゲーム開発に特化した高い技術力と海外運用ノウハウを持ち、開発案件を安定的に受託している。
techqiao.co.jp
CGWORLD(以下、CGW):五十嵐さんはもともと神奈川で働かれていたと聞きました。
五十嵐平馬氏 (以下、五十嵐):はい、私はもともと神奈川でフリーランスとして仕事をしていたんですが、結婚を期に静岡市へと引っ越してきました。
CGW:奥様の仕事の関係で静岡市に転居されたということですね。静岡市でもフリーランスとして働く選択肢もあったかと思いますが、起業を選ばれた理由は何なのでしょうか。
五十嵐:フリーランスとして働いてきた中で、エンジニアの労働環境の問題やキャリア構築の難しさ、プロジェクトの炎上などIT業界特有の課題を強く感じていました。会社としてさらに大きな開発に挑戦したい想いもありましたので、静岡市にやって来たことを機にエンジニアやクリエイターのための理想的な職場環境をつくりたいと考えて、起業に踏み切りました。
CGW:馴染みのない場所での起業でしたが、決断を後押しする理由があったのでしょうか?
五十嵐:私自身、本当に静岡市で起業をしていいのかどうか悩みました。しかし色々と調べていく中で、静岡市はクリエイターやプロダクションにとっていい土地だなという気付きがあったんです。例えば、東京や名古屋にすぐ出られるという点です。
CGW:確かに、新幹線を使えば一時間程度ですもんね。
五十嵐:それに駅前にはコワーキングスペースのような、小規模起業に適した施設が沢山あるんです。
またそういった民間の施設だけでなく、SHIP(shizuoka innovation platform)という、静岡県が運営している企業支援のための施設もあります。当初は一人でリスクを抑えて開業しつつ、やがて会社を拡大するときにスケールすることもできるような立地として、静岡市ってとてもいい場所だなと気付いたんです。
CGW:企業として静岡市に拠点を置くことのメリットについて改めてお聞かせください。
五十嵐:やはり東京と比べると、家賃が圧倒的に安いというのは大きなメリットですね。それに、同業他社がまだほとんどいないので採用面で有利です。
CGW:現在、スタッフは何人くらいですか?また、採用者の比率は県内・県外でどれくらいなのでしょうか?
五十嵐:26名で、半数が静岡県内からの採用で、半数が静岡県外からの採用です。
新卒は地元の専門学校から採用することが多いですね。あとは中途採用も多いです。リモートワークも併用していますが基本的には出社が必要なので、県外から採用した方は静岡に移住していただくことになります。引っ越し費用10万円の支援があったりしますし、そもそも東京と比べてだいぶ家賃が安いので、移住への決断はしやすいと思います。
CGW:入社に際して静岡に移住してきたスタッフは、静岡のことをどう言っていますか?
五十嵐:東京に比べると刺激が少ないという点を言う方もいますが、自然と都会がいい塩梅で併存している点を気に入ってくれてますね。
CGW:なんといっても、中心市街から車で10分で海や温泉が待ってますからね!
現在のスタッフさんが静岡で働く理由を聞いていますか?
五十嵐:やはり「静岡県内でゲーム開発をしている会社が他にないから」という理由は大きいみたい。
県内からの採用者はみんな口を揃えてそう言いますね。スタッフの数も来期には30名を超える見込みです。
CGW:新規スタッフを採用するだけでなく、これまで就職した方々が辞めていくこともほとんどないと聞いています。
スタッフが定着する理由は何なのでしょうか。
五十嵐:ひとつには、なるべく自由度高く働けるフレックスタイム制を採用していることがあると思います。
朝の八時から夜の八時まで、好きな時間に自由に勤務していただいていいということになっています。
中抜けや休みも自由に取れるようにしています。
CGW:静岡市の働きやすさに加えて、会社としても働きやすい環境を整えていることが、高い定着率の理由というわけですね。
全国からも人が集まっている理由もわかる気がします。
-

静岡駅からも近い用宗(もちむね)周辺の風景。賑やかな市内から10分程度で豊かな自然が広がる。 -

桜の名所として知られる駿府城公園。かつて徳川家康の居城があったというこの場所は、住みやすい都市であると同時に、歴史も身近に感じられるだろう
<静岡の人材育成の今は?>業界最先端の技術を静岡で。産官学連携による人材の育成の今
静岡市に拠点を置く企業の採用事情が聞けたところで、続いては、静岡市におけるクリエイターの教育事情について、静岡県デジタル戦略局の山口武史氏と静岡理工科大学グループ静岡デザイン専門学校の大川直樹氏をお招きし、静岡のデジタル系教育現場で何が起きているのかについてお話を伺った。

静岡県デジタル戦略局 参与
山口武史氏
静岡県の初代のデジタル部長として、基本的なDXから、静岡県全体の三次元点群データをオープンデータ化するプロジェクト「VIRTUAL SHIZUOKA」に携わった。
現在はXR分野を中心にデジタル人材の育成に注力。
CGW:まずは自己紹介をお願いします。
山口武史氏(以下、山口):静岡県職員の山口です。4年前に国がデジタル庁を作った時、静岡県もデジタルの部署を刷新しようということになり、私が初代のデジタル部長として、基本的なDXから、「VIRTUAL SHIZUOKA」という、静岡県全体の三次元点群データをオープンデータ化するプロジェクトに携わってきました。これは静岡という街のデジタルツインを作り上げることで、それが新たな社会インフラとして防災や公共物の維持管理などに活用されることを目指した取り組みです。
https://www.pref.shizuoka.jp/machizukuri/1049255/1052183.html
山口:そうやって作り上げられた「VIRTUAL SHIZUOKA」なども含め、静岡県が持っているデジタル資産をどんどん活用しなければいけないという意識があり、そこで具体的に何をすべきかと考えていたときに、ゲーム会社の代表の方から「TECH BEAT Shizuoka」でXRの人材育成というのはどこの行政もやっていないというお話を伺ったんです。
であれば我々静岡県がやろうということで、今年度から始めています。そんな中で、静岡市さんも、人口がどんどん首都圏に流出しているということについて対策しなければいけないという同じ危機感を持っていることがわかったので、企業さんが静岡へ来ていただくときにアテンドしたり、意見交換したりなど、県と市でいい関係で仕事をさせていただいています。
CGW:静岡県が主導でXR寄附講座を開催しているそうですが、その開催までの経緯はどういったものだったんでしょうか?
山口:先ほども申し上げた「TECH BEAT Shizuoka」を機会に、ひとつは人材を育成すること、もうひとつは育成した人材が静岡に留まってくれること、この二本を柱にして産学官の取り組みで何かできないか考えることにしました。
そのために、大学や高等教育科、専門学校と組んでやっていこうという話になりました。その時に我々がまずパートナーとして決めたのが、静岡理工科大学グループさんだったんです。
CGW:講座の狙いについて、改めて教えてください。
山口:先ほど申し上げました二本柱にもとづいて、専門的なカリキュラムをどんどん入れていって生徒を育てていくという部分と、産学でのコミュニティを形成して、このコミュニティに地元静岡の企業さんにどんんどん入ってもらって、育った生徒とマッチングすることで化学反応が起きたり、地元企業に就職してもらったりということですね。
さらに言えば、企業さんが、現在は自分たちの業態と関係ないと考えていないようなことでも、XRなりCGなりという世界を体験することで、これはうちの事業にも使えるな、なんていう形で事業を拡張してもらったり、そしてまたそういう分野に生徒が就職していったりという、好循環を作り出せれば理想ですね。

学校法人静岡理工科大学グループ付属
静岡デザイン専門学校
CGデザイン科 学科長
大川 直樹 氏
www.sdc.ac.jp
大川直樹 氏(以下 大川):もともと本校には25年以上前にグラフィックデザイン科が立ちあがり、現在の新校舎・新学科が設立される前は学生の半数近くが所属しているほどフラグシップ学科になっていたという状況でした。
ただ、この20年でネットを含めてデジタル表現を取り巻く状況が変化して社会のニーズも変わっていきました。また入学してくる学生も、デザインをやりたくて入学してくるというよりは、自分の好きなことを仕事にしたいという思いを持っている傾向もあり、そのニーズにあわせるかたちで昨年CGデザイン科を新設しました。
もともとこの業界は、全国的に上位20%しか就職できないと言われています。そんな就職状況のなか、CG分野の中でも特に力を入れて教えているのがモーションとエフェクトです。コンテンツがリッチになったことで、業界的にモーションやエフェクトを専門的に作れる人材の需要は高まっていまして、そのニーズに応えるかたちをとっています。
CGW:モーションとエフェクト職はまさに業界でも不足している職種ですね!

大川:その他にも、スタジオブロスさんのご協力のもと、県内初のバーチャルプロダクションも導入しました。バーチャルプロダクションやUnreal Engineを使うための専用のカリキュラムも設けました。
CGW:おそらく教育現場でバーチャルプロダクションをしっかり教えるカリキュラムがあるのは、国内でもかなり珍しいと思います。
大川:そして技術を教えるだけではなく、意識付けにも力を入れています。制作や就職のモチベーションを維持して上げ続けるためにも、様々なCGコンテストへの参加を奨励しています。
そうすることで、全国の企業さんにも学校名を認知していただけると考えています。こうした取り組みを通じて、先ほど業界に就職できるのは20%と言いましたが、いずれはその3倍の60%の生徒が業界に就職できることを目標にしています。

CGW:学生さんの就職状況はいかがでしょう?
大川:CGデザイン科を立ちあげにあたって問題となったのは、卒業生の受け皿となる就職先が地元の静岡にはないということでした。入学者は集められるんですが、入学の時点で「就職をするには都心部に行くことを前提としてください」と言わざるを得なかったんです。
山口:学生の就職については我々もジレンマを抱えながらやっている部分があって、寄付講座を最初に静岡デザイン専門学校さんとご相談したときに、県内に留まって学生が就職するということをKPI(中間目標)にしようという話があったんです。ですが、現実の就職事情からすると優秀な学生ほど首都圏に行ってしまう傾向があることを知りました。
一方で我々県としては、若者が県外に流出することを防ぎたいという思いがあります。ただ県内に就職先となる企業がないために首都圏に行かざるを得ないという状況となっています。専門学校の学生に話を聞いても、首都圏の企業に就職したいという方より、県内で就職したいという方のほうが実は多いんです。10年先でも20年先でもいいので、学生の受け皿になれるような企業を静岡県内に増やしていきたいです。
また、札幌や福岡のように、静岡を「デジタル業界の企業が集積していく場」にしていきたいという思いがあり、静岡市さんと連携してやっていきたい部分です。
大川:確かに福岡市などは、クリエイティブから観ると成功例だと思います。フラグシップとなるような企業がいくつかあって、そこに関連企業も集まってひとつの文化が生まれているし、行政もちゃんとそこに対して働きかけている。地方であればこそ、企業と行政と教育が三位一体で動いていないと成功しないと思います。この静岡でどうやってそういうモデルを作っていくかということが、これから先すごく大事なんじゃないかと感じています。
CGW:首都圏のプロダクションが地方に移転する時に、困るのは人材の確保だと聞きます。そんな時に、ニーズの高いモーションやエフェクト、そしてバーチャルプロダクションへの知見もある学生さんが大勢いるとなると、静岡への移転も検討しやすいと思います。一方で企業・行政・教育が連携して、静岡県内の企業にXRやCGの活動を促しつつ、首都圏から静岡にもスタジオが移転しやすい環境を整えていくという両面から、静岡の未来が変わっていくとすばらしいですね。
今回はありがとうございました。
TEXT_オムライス 駆
PHOTO_大沼洋平
INTERVIEW_池田大樹(CGWORLD)