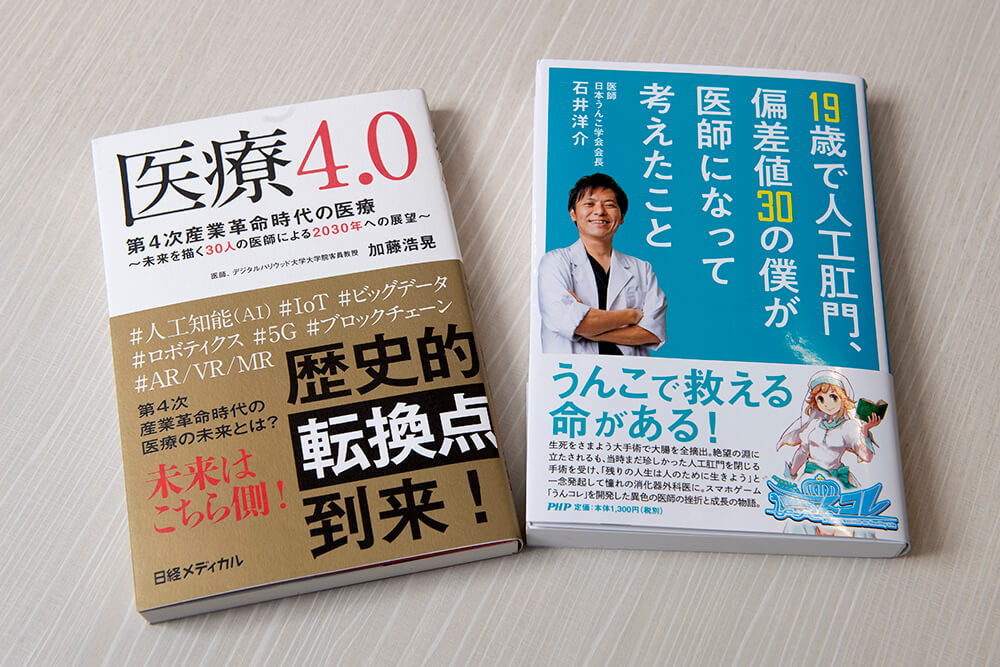2018年12月23日、第2回 デジタルヘルス学会 学術大会がデジタルハリウッド大学駿河台キャンパスで開催された。大会長である五十嵐健祐氏は、お茶の水循環器内科の院長を務める傍ら、デジタルハリウッド大学校医 兼 同大学院専任准教授としてデジタルヘルス分野の研究、サービス・プロトタイプ開発、起業家支援などにも従事している。そんな五十嵐氏を含む同分野の研究者4名に「そもそも、デジタルヘルスとは何ですか?」「同分野でのCG活用の展望はどの程度ですか?」といった疑問に答えていただいた。
TEXT_尾形美幸 / Miyuki Ogata(CGWORLD)
PHOTO_弘田 充 / Mitsuru Hirota
患者さんを楽しませることで、自発的な行動変容を目指す
CGWORLD(以下、C):まずは、「そもそも、デジタルヘルスとは何ですか?」という基本的なことから教えていただけますか?
五十嵐健祐氏(以下、五十嵐):ざっくり言いますと、われわれは「デジタルテクノロジーとクリエイティブの力を使い、医療における課題を解決する」という目標を掲げて活動しています。従来の医療は、薬や医療機器を開発したり、より安全で確実な検査や手術を目指したりといった方面で発展してきました。その結果、糖尿病にしろ、高血圧にしろ、かなり正確な検査ができるようになり、副作用の少ない薬も開発されました。確実な治療を受けられる環境はおおむね整ってきたにも関わらず、患者さんが減るかと思いきや、全然減っていないんです。
なぜかと言うと、自覚症状がないから、検査で指摘されても病院に来ない。あるいは治療を開始しても、軽度のものであれば食事療法、運動療法、お薬の摂取などで十分改善するため、途中で治療を止めてしまう人が非常に多いんです。例えば国内の糖尿病患者の場合、年間の治療中断率は10%程度と言われています。この割合は、5年間で半数程度が治療離脱するという離脱率です。
-
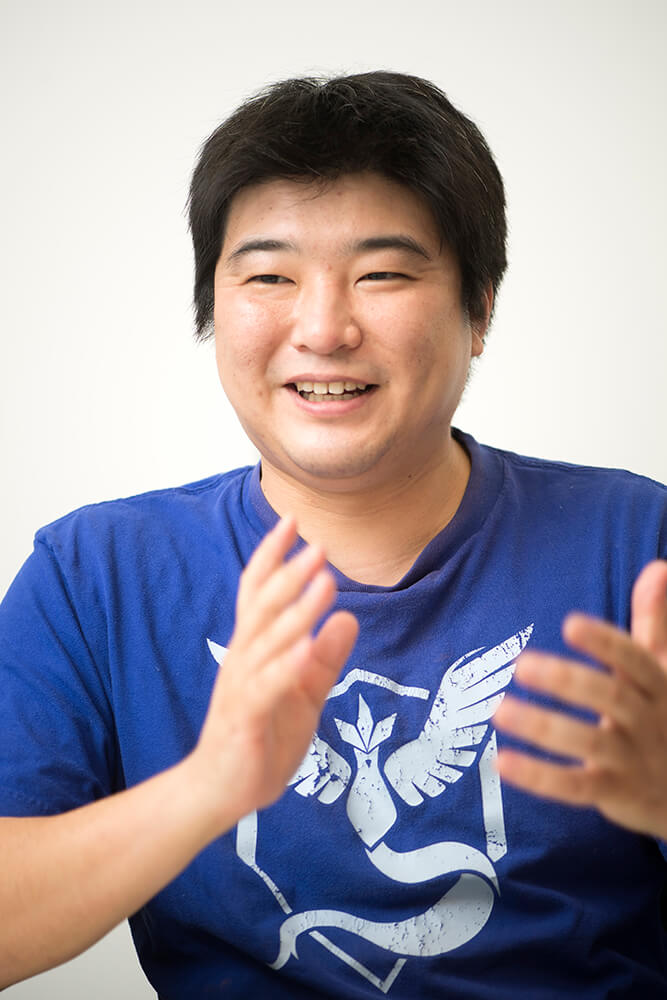
-
五十嵐健祐
お茶の水循環器内科 院長。デジタルハリウッド大学校医 兼 同大学院専任准教授。2012年、慶應義塾大学医学部卒。群馬の脳卒中専門病院にて救急、循環器内科、神経内科、精神科、緩和ケアに従事。2013年、国立循環器病研究センターにて短期研修。新宿、渋谷、池袋、上野、秋葉原にて総合内科、心療内科、整形外科、皮膚科に従事。2014年、東京都千代田区にお茶の水内科開設。2018年、医療法人社団お茶会設立、お茶の水循環器内科院長。高血圧症、脂質異常症、糖尿病、メタボリック症候群などの生活習慣病、心房細動、喫煙、ストレス性疾患などの心血管疾患の危険因子の予防と治療、心血管疾患の一次予防がライフワーク。心房細動検出アプリ『ハートリズム』、応急救護支援アプリ『ハートレスキュー』、睡眠時無呼吸検出アプリ『イビキー』などを開発。デジタルハリウッド大学院にてデジタルヘルスラボの立ち上げに携わり、デジタルヘルス分野の未来を探究しつつ、デジタルヘルス好きの人たちが集まる場づくりに力を入れている。
C:かなりの離脱率ですね。
五十嵐:痛くもかゆくもないのに、お金はかかるわ、通院で待たされるわで、短期的にはメリットを非常に自覚しにくい。デメリットの方が大きいんじゃないかと患者さんに感じさせてしまっている点が、今の医療における大きな課題のひとつなのです。その課題を解決する手段が、デジタルテクノロジーであり、エンターテインメントやゲーミフィケーションのノウハウであると、われわれは考えています。
従来の医療は「糖尿病を放置したら、心筋梗塞を起こしますよ」とか、「腎臓病が悪化して、透析が必要になりますよ」とか、「脳卒中を起こして、寝たきりになりますよ」といった警告を通して患者さんを怖がらせることで、その行動を変えようとしてきました。でも実際のところ、それでは人は動いてくれなかったわけです。今後は、患者さんを楽しませることで検査を受けたくなる、治療を続けたくなるような気持ちにさせる。つまりは患者さんの自発的な行動変容を目指すことが医療における課題解決の主軸になっていくと思います。
C:デジタルテクノロジーに加え、エンターテインメントなどのノウハウも活かせるから、デジタルハリウッド大学院がデジタルヘルス分野の研究を推進しているというわけですね。
五十嵐:そうです。病院で患者さんが来るのを待っているだけではなく、社会に対して医師の方からアプローチをして、人々の行動変容を促す必要があると、そんなことを4年ほど前に本学の杉山知之学長にお話しました。ちょうど、僕が本学の校医になったタイミングでしたね。そうしたら「本学は主にCG、ゲーム、映像などの制作や研究をやってきましたが、それらの最終目標は人々を幸せにすることです。デジタルテクノロジーやエンターテインメントの力で医療の課題が解決でき、人々が幸せになるのであれば、ぜひ取り組んでいきたいです」とおっしゃいました。
その翌年、加藤浩晃先生らと共にデジタルヘルスラボを立ち上げ、徐々にメンバーを増やし、現在は2名の教員と16名の学生が所属する組織になりました。2017年にデジタルヘルス学会も立ち上げ、論文発表や学術大会などの活動も行なっています。
加藤浩晃氏(以下、加藤):デジタルテクノロジーが進歩した結果、インターネット、スマホ、VR、AIなど、課題解決のための選択肢が増え、医療と患者さんとの接点も多様化しています。例えば、僕自身は眼科医ですが、他分野の医師と協力し、テクノロジーを使った遠隔医療サービスなどの開発もしています。
一例を挙げると、患者さんの喉の写真を撮影し、インフルエンザかどうかをAIが判定するシステムを開発中です。現在普及しているインフルエンザの検査(スワブ検査:綿棒のようなスティックで喉の粘膜を採取して菌などの有無を確認する検査)の精度は6割程度で、4割は見逃されているんです。一方で、インフルエンザ患者の喉には9割以上の確率で濾胞(ろほう)というつぶつぶが発生するんですが、これを人間の目で判別するには長年の経験が必要で、経験の浅い医師だと見逃してしまいます。そこで画像診断とディープラーニングを組み合わせた、高精度の新しいインフルエンザ検査のシステムをつくれないかと考えたわけです。
-

-
加藤浩晃
眼科医。デジタルハリウッド大学大学院 客員教授。アイリス株式会社 取締役CSO(最高戦略責任者)。千葉大学附属病院メドテックリンクセンター 客員准教授。東北大学 非常勤講師。日本遠隔医療学会 分科会長。元厚生労働省 室長補佐。2007年、浜松医科大学卒。京都府立医科大学附属病院で眼科専門医として従事し、1,500件以上の手術を執刀、33冊の医療系書籍(単著&共著)を発刊。近著に『医療4.0 第4次産業革命時代の医療』(日経BP社/2018)などがある。医師のキャリアの傍ら、多くの医療新規プロジェクトに従事。白内障手術機器の「二刀流チョッパー(加藤式核分割チョッパー)」や、遠隔医療サービス「メミルちゃん」などを開発。その後、厚生労働省に入省し、医療制度改革に取り組む。主に、G7伊勢志摩サミットでの医療提供体制や高難度新規医療制度、臨床研究法の成立などに関わった。現在は医師として働きながら、ヘルスケアビジネスに必要な「医療現場」「医療制度」「ビジネス」の3領域を理解する数少ない存在として企業の顧問・アドバイザーを務めると共に、ベンチャーにも参画する。
五十嵐:画像診断とディープラーニングの組み合わせは、今すごく盛り上がっています。ようやく日本でも、2018年の12月に先行研究のひとつが医療機器として承認されました。
加藤:われわれが開発中のインフルエンザ検査システムも、2020年くらいの承認を目指してがんばっています。僕は現役の眼科医であると同時にスタートアップ企業の人間でもあるので、デジタルヘルスラボの学生や各地の医療関係者などと一緒に、新しいヘルスケアビジネスやシステムのあり方を模索しています。
C:患者さんの喉の写真を撮るだけでインフルエンザ検査ができるなら、お医者さんがいない環境でも機能しそうですね。
加藤:最終的な診断や治療は医師が行うでしょうが、その前段階で患者さんたちに働きかけ、行動変容を促すことがデジタルヘルスの目的です。僕の自著の中では、デジタルヘルスが発展すれば、医療の民主化が促進するだろうと紹介しています。
C:日本でUnityが普及し始めた2010年頃、ゲーム開発の民主化が始まるだろうと言われていたことを思い出しますね。
ユニティちゃんで視野欠損を測定する、緑内障簡易発見ツール
木野瀬友人氏(以下、木野瀬):僕の場合は、まさにUnityを使って緑内障を発見するツールを開発しています。本学の大学院に進学する以前、僕はニワンゴの取締役、兼エンジニアとしてニコニコ動画の周辺サービスの企画・開発・実装を担当していたので、CGWORLDの読者さんにとっては比較的馴染みのある分野の出身者だと思います。今はデジタルヘルスラボに所属して、プレイフルヘルスの研究をしています。
-

-
木野瀬友人
デジタルハリウッド大学院 デジタルヘルスラボ所属。現在は修士課程2年。高校生の頃から技術の実用化に興味をもち、AIとサイバーセキュリティーの研究を経て、株式会社ニワンゴの取締役としてニコニコ動画の周辺サービスの企画・開発を担当する。2013年、医師の石井洋介氏と共に日本うんこ学会を設立し、スマホゲーム『うんコレ』の総監修を担当。デジタルヘルスラボでは、親しみやすい医療の姿を届けるプレイフルヘルスを研究。
C:プレイフルヘルスとは何ですか?
木野瀬:まるで遊んでいるかのような体験を通して、医療や健康のことを自発的に考えられるようになることを目指すシステムやユーザー体験(User Experience。以下、UX)です。例えば緑内障簡易発見ツールの場合は、緑内障の早期発見につながるVRコンテンツの開発を目指しています。緑内障の患者さんは、約90%が未発見の潜在患者だと言われています。治療によって視野欠損の進行速度を遅らせることができるので、早期に発見し、早期に治療を始めてもらうことが大切なのです。
-

- 緑内障簡易発見ツールをプレイ中の木野瀬氏。アプリをインストールしたスマホとVRゴーグルを組み合わせることで、プレイヤーの視野欠損の状態を片目あたり約1分で測定できる。なお、本アプリは開発中のため一般公開はしていない
▲本アプリの画面。木野瀬氏がUnityを使い、15日(1日約8時間、合計120時間)の期間をかけて開発した。【左】起動直後の画面。視点を動かして検査したい方の目を見つめると、測定対象の目の画面だけが表示される/【右】右眼の視野欠損を測定中の画面。4×4に分割した16領域に対して、指標となるキャラクター(ユニティちゃん)がランダムな位置と表示時間で出現する。特定領域のユニティちゃんが視認できない場合は、その領域の視野が欠損している可能性がある。この結果を基に、潜在患者の行動変容(医療機関での受診)を促すことが本アプリの目的だ。なお、本研究は日本緑内障学会の優秀学術展示賞を受賞している。医師以外の発表者の受賞は異例なことだという
C:私自身が緑内障患者なので、とても身近なテーマですし、人の役に立つツールだと思います。私の視野も一部欠損していますが、日常生活では両目でものを見て、頭を動かして視野を補間するので、全く不自由を感じません。視野欠損に気づいておらず、知らぬ間に症状が悪化している人が多いと聞きますね。
木野瀬:例えば内視鏡のような医療器具を僕みたいな一般人がつくるのはハードルが高いですが、スマホやVR技術を活用できるとなれば、参入障壁はぐっと下がります。慣れ親しんできたデジタルツールや技術を使い、身の回りの医療課題を解決したり、患者さんを支援できると知り、だんだんとデジタルヘルスに興味をもつようになりました。デジタルヘルスラボでは現役の医師でもある五十嵐先生や加藤先生の指導を受けられるので、医師が感じている課題と、患者さんが感じている課題の両方を学びながら研究を進めています。
五十嵐:僕自身も、これまでに6つのアプリを開発してきました。例えば『ハートリズム』は、スマホのカメラを使って患者さんの脈拍を測定し、脳梗塞の発症リスクを調べるアプリです。
▲『ハートリズム』は、スマホのカメラを使って指の脈拍を測定し、心房細動と呼ばれる不整脈の早期発見を目指すアプリ。心房細動は最もよくある不整脈で、加齢と共に有病率が増大し、80代の10%は心房細動を有すると言われている。心房細動があると心臓内に血の固まり(血栓)ができやすくなり、その血栓が血流に乗って脳の血管を突然閉塞させる「心原性脳塞栓症」を発症するリスクが高まる。ただし予防法や治療法は確立されているため、心房細動の早期発見と受診が、心原性脳塞栓症の予防につながるというわけだ
C:スマホのカメラに指をあてるだけで不整脈を検出できるなら、めんどくさがりの人でも「やっても良いかな」と思うかもしれませんね。
五十嵐:木野瀬さんのような技術者と僕のような医師が協力することで、新しいビジネスやシステムを生み出せる余地はまだまだあると思います。第一線でVR映像やゲームをつくっている人から見ればローテクノロジーな手段でも、医療と組み合わせることで革新的なシステムに化ける可能性があります。アイデア次第で新しい価値につながる点も、デジタルヘルスの面白いところです。木野瀬さんが石井洋介先生と一緒に開発している『うんコレ』というスマホゲームにも期待しています。
次ページ:
課金する代わりに快便報告をする
スマホゲーム『うんコレ』
課金する代わりに快便報告をする、スマホゲーム『うんコレ』
石井洋介氏(以下、石井):僕の場合は現役の医師をやりつつ、大学院生としてデジタルヘルスラボに所属し、テクノロジーやエンターテインメントについて学んでいます。僕の専門は消化器外科なので、以前は大腸がんなどの手術をしていました。今は医療技術が進歩しており、僕のような若い医師でもかなり上手に手術ができるようになっています。でも、中には「開腹手術をしてみたら、既に手遅れだった」というケースもありました。どれだけ手術の腕を磨いても、手遅れの患者さんを助けることはできないのです。
先人たちが努力を重ね医療技術がすごく進歩した結果、今も取り組みが足りていないのは、わりと原始的な患者さんの気持ちの部分、例えば「赤色の便が出ているのに病院に来てくれない」とか「薬を出したのに飲んでくれない」といった人たちへの向き合い方を考えることだろうと思うようになりました。
-
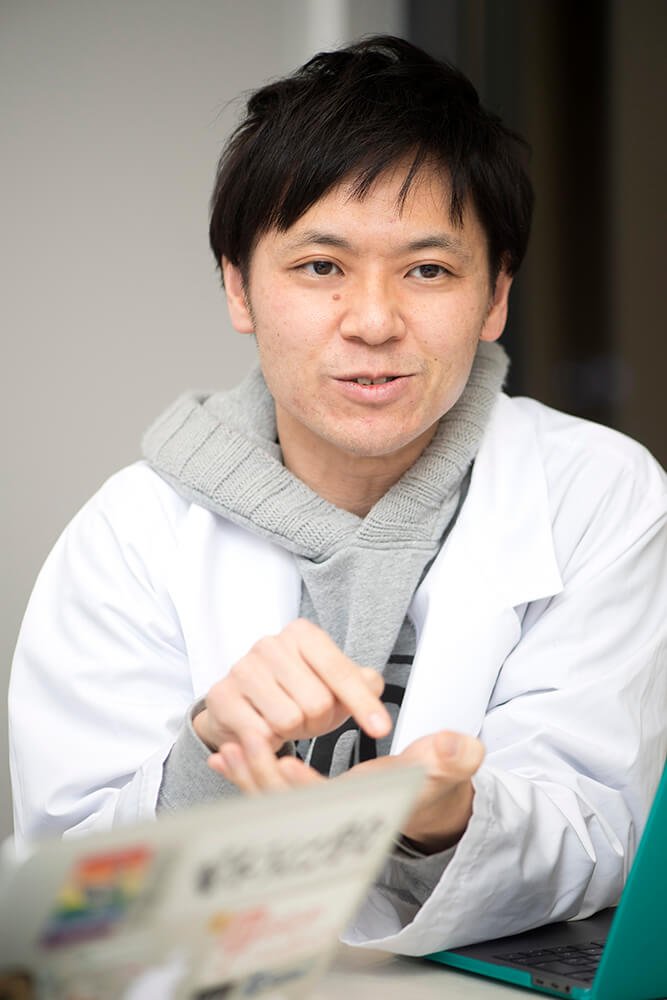
-
石井洋介
日本うんこ学会 会長。秋葉原内科saveクリニック共同代表。2010年、高知大学医学部を卒業後、医療法人 近森会 近森病院での初期臨床研修中に高知県の臨床研修環境に大きな変化をもたらした「コーチレジ」を立ち上げた。その後、大腸がん検診の普及を目的とした日本うんこ学会を設立し、スマホゲーム『うんコレ』の開発・監修を手がけるなど、医療環境の改善に向け特にクリエイティブ領域から幅広く活動している。横浜市立市民病院 外科・IBD科 医師、高知医療再生機構企画戦略室 特命医師、厚生労働省 医系技官を経て、現在は在宅医療を行う傍ら、デジタルハリウッド大学院でコミュニケーションデザインを専攻、ハイズ株式会社でプロジェクト運営なども行なっている。近著に『19歳で人工肛門、偏差値30の僕が医師になって考えたこと』(PHP研究所/2018)などがある。
C:先の緑内障や脳梗塞と同じく、まずは自身の大腸がんの発症リスクを知ってもらい、行動変容を促すことが先決というわけですね。
石井:はい。とはいえ今後は情報の発信手段がますます多様化し、誰もが個別最適化された情報を受け取る時代が来ると思います。そうなれば、自分が好きなことや興味のあることしか調べなくなり、大腸がんの情報を生涯受け取らない人が増えていくでしょう。だったらゲームなどのエンターテインメントの中に大腸がんの情報を溶け込ませ、より多くの人に情報が届くようにしたい、しかも1回だけではなく継続的に情報を届けることで「ひょっとして大腸がんかも?」と感じたときにちゃんと受診へとつながるようにしたいと思うようになりました。
僕自身がすごくゲームに課金していたので、課金する代わりに快便報告をするゲームなら行動変容につながるかもしれないと考えたものの、僕にはアイデアをスマホに実装する能力がなく、どうしたものかと思っているときに木野瀬さんと出会ったのです。その後は2人で意気投合し、2013年の日本うんこ学会設立後、『うんコレ』というスマホゲームの開発・監修をするようになりました。
▲スマホゲーム『うんコレ』を紹介するポスター。なお本作は開発中で、現在は事前登録を受付中だ
▲開発中の『うんコレ』のプレイ画面。その日の便の色と形を報告する【左】と、キャラクターがアドバイスをしてくれる【右】。「開発初期にはスマホのカメラで自分の便を撮影して画像診断する機能を実装しようとしたのですが、カメラロールに自分の便の写真が残る精神的苦痛はすさまじく、このUXはダメだと思い今のかたちに落ち着きました」(石井氏)
▲ニコニコ超会議での出展の様子
▲『触覚体験うんこツンツン 〜排泄ケアへの挑戦〜』の紹介動画。こちらは、日本うんこ学会が東北学院大学 佐瀬研究室、ケイズデザインラボらと共に開発した、便を触るVRコンテンツ。VR空間内で便や大腸壁を触りつつ音声解説を聞くことで、医療や介護に関するユーザーの理解を深めることを目的としている。便を触るという仮想体験は多くの人の好奇心を惹きつけるため、楽しみながら体験するうちに排泄ケアの心理的ハードルが下がる効果を期待しているという
C:緑内障簡易発見ツールにしろ、『うんコレ』にしろ、使われている技術はエンターテインメント産業のコンテンツと大差ない点がおもしろいですね。
木野瀬:はい。ですから、CGやゲーム制作のノウハウを活用する余地はまだまだあると思っています。
臨床のさらに川上でも、問題解決に取り組みたい
加藤:デジタルヘルスはまだまだ医療の主流ではなくキワモノ分野のように捉えられがちですが、厚生労働省がジャパン・ヘルスケアベンチャー・サミットという医療系ベンチャーを支援する展示会を定期的に開催するなど、徐々にその必要性が認知されつつあります。10月にパシフィコ横浜で開催された展示会には、デジタルヘルスラボも出展しました。
五十嵐:最近は製薬会社からの問い合わせが多いですね。今後、もしデジタルヘルスというアプローチが医療の主軸のひとつになるとしたら、製薬会社としてどう向き合っていけばいいのか。従来のように病気を治すための薬をつくる以外にどんな方法があるのか。ヒントがほしいから、デジタルヘルスについて詳しく知りたいという問い合わせです。
製薬会社の最終目的は人々を健康にすることなので、薬をつくる以外の手段でビジネスを始める会社が出てくるかもしれません。実際、加藤先生や石井先生は「デジタルヘルス分野での新規事業の開発について、講演をしてほしい」という依頼を受ける機会が増えてきています。
▲加藤氏の近著『医療4.0 第4次産業革命時代の医療』(日経BP社/2018)【左】と、石井氏の近著『19歳で人工肛門、偏差値30の僕が医師になって考えたこと』(PHP研究所/2018)【右】。いずれもデジタルヘルス分野の現在と、今後の可能性を紹介している
加藤:医療分野には厳格な制度があるので、日本でやれること、やれないことを理解する必要があります。どんなやり方であれば可能なのか、アドバイスや意見を求められることも増えてきましたね。厚生労働省や業界団体も含め、デジタルヘルスをどう扱い、どう審査すればいいのか手探り状態というのが実情なので、問い合わせが増えてきたのだと思います。
五十嵐:デジタルヘルスに対して興味や理解を示してくれる人が増えてきたのは嬉しいことですね。最近はそれほどでもないですが、以前は「デジタルハリウッドに医師が集まって、変なことをやっている。あいつらは臨床をやる気がないのか」というように言われることが多かったんですよ(笑)。
石井:3人とも、ちゃんと現役で臨床をやっているにも関わらず、今でもまあまあ言われますよ(笑)。
加藤:言われますね(笑)。
石井:「はぐれキャリア」みたいな......。
五十嵐:臨床で人の命を救うことはわかりやすい善の行為なので、言ってみれば「インスタ映え」するんですよ。
C:確かに、スマホで快便報告するよりは、圧倒的にインスタ映えしますね(苦笑)。
五十嵐:もちろん臨床もすごく大切ですが、われわれはより川上での問題解決にも取り組みたいと思っています。例え話になりますが、川に赤ちゃんが流されてきたとき、川に入って目の前の赤ちゃんを助けるという選択肢が既存の臨床における問題解決です。川で溺れている赤ちゃんを助ける姿はインスタ映えします。
でも赤ちゃんが次々と流されてくるとしたら、赤ちゃんが川に落ちる原因があるはずです。もしかしたら、川上に行けば赤ちゃんを次々と川に投げ込んでいる奴が見つかるかもしれない。それなら川上に行って、赤ちゃんを投げ込んでいる奴を川に投げ込んでしまった方が根本的な問題解決になるはずです。そういうアプローチの仕方が、デジタルヘルスにおける問題解決です。広い意味で公衆衛生学なんですが、デジタルテクノロジーやクリエイティブの力を武器にアプローチしていく点で新しい解決方法と言えます。
C:臨床のさらに川上で、潜在患者さんが抱える問題を発見し、解決のための行動変容を促すことがデジタルヘルスケアの役割というわけですね。
五十嵐:そうです。デジタルヘルス分野は今後も発展させていく必要がありますが、まだまだ圧倒的に人材が足りていません。興味のある方、人々を幸せにしたいと思っている方には、ぜひ一緒に取り組んでほしいです。先ほども言いましたが、CGの専門家にとってはローテクノロジーな手段でも、医療と組み合わせることで新しい価値を生み出せます。もちろんハイテクノロジーな手段も、どんどん導入されていくと思います。
木野瀬:患者さんの気持ちを盛り上げ、行動変容を促そうとするとき、エンターテインメント産業のノウハウが不可欠になってくると思います。例えば、デジタルヘルス学会ではUI/UXの分科会をつくり、もっと医療を身近に感じてもらうためのUI/UXデザインの勉強や研究も始めています。
C:デジタルヘルス分野の発展、特にCGWORLDとしては、CGやゲーム産業の専門家とのコラボレーションに期待したいですね。お話いただき、ありがとうございました。