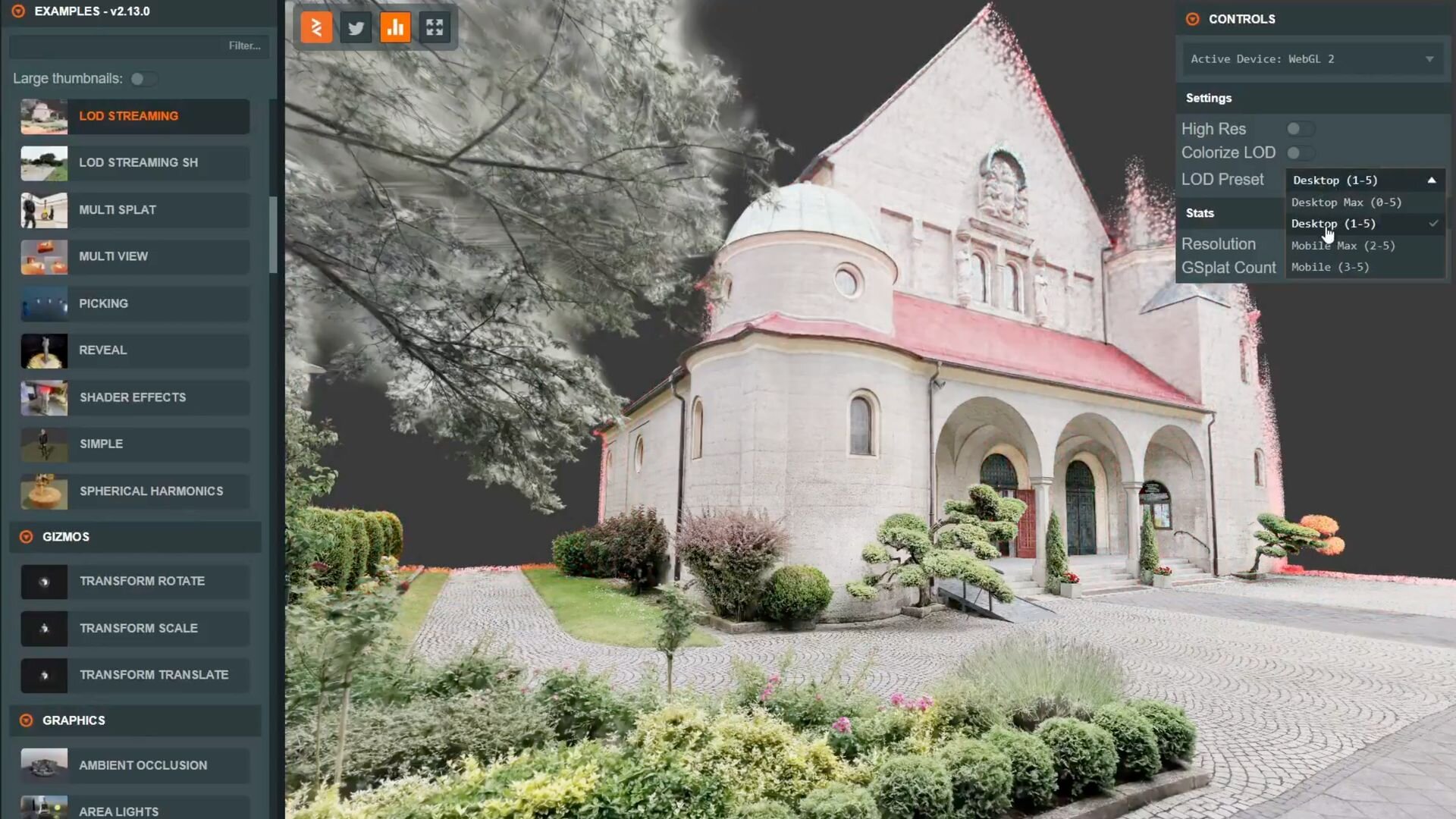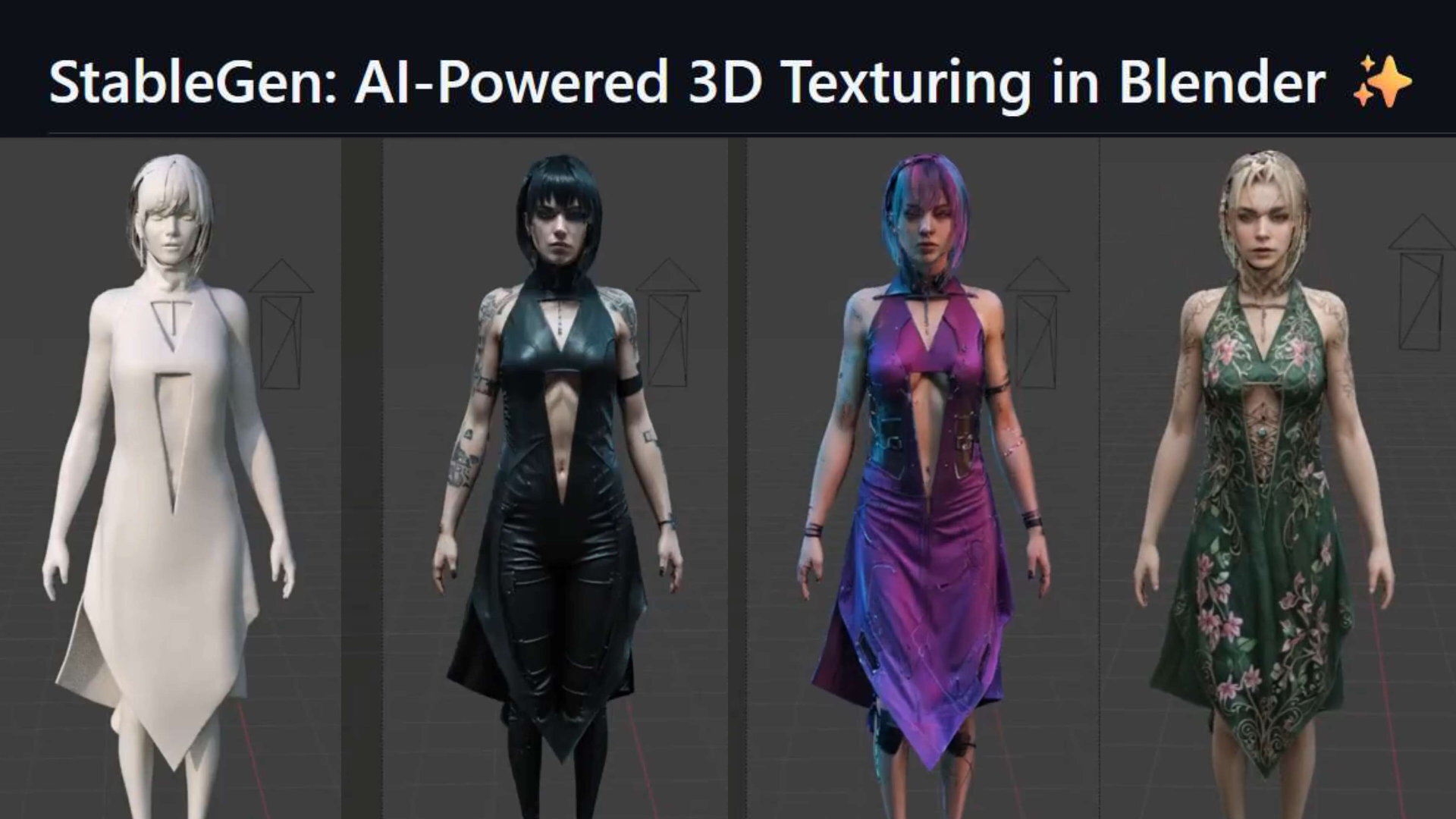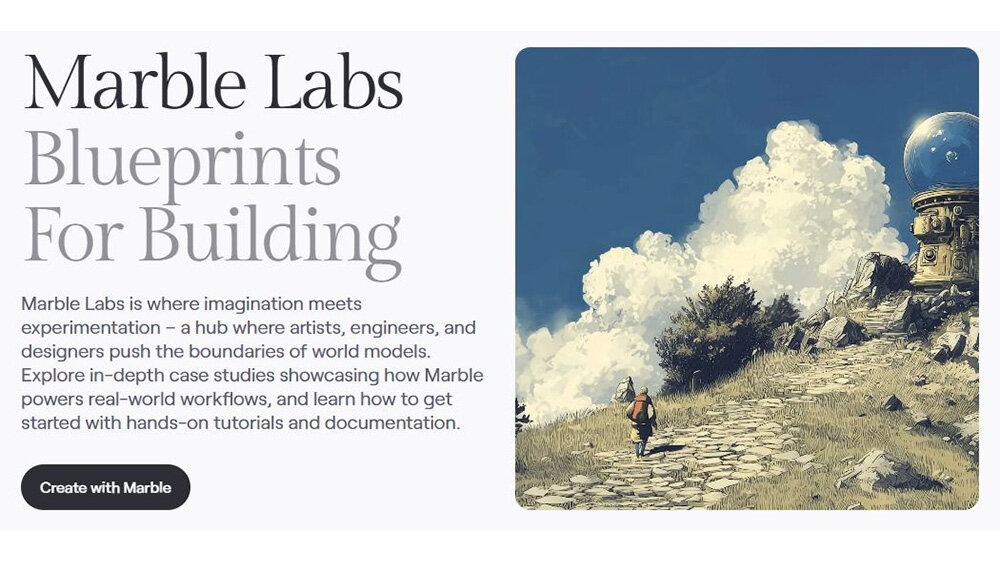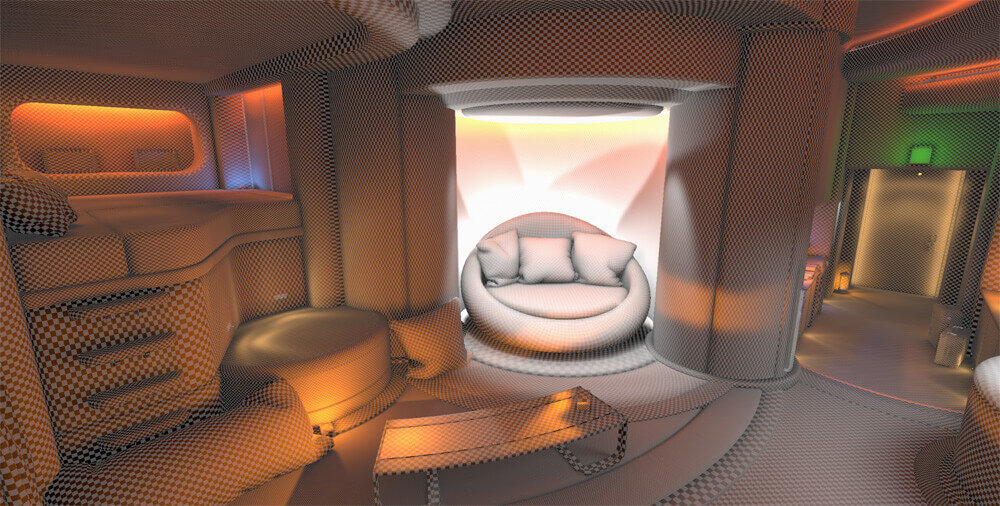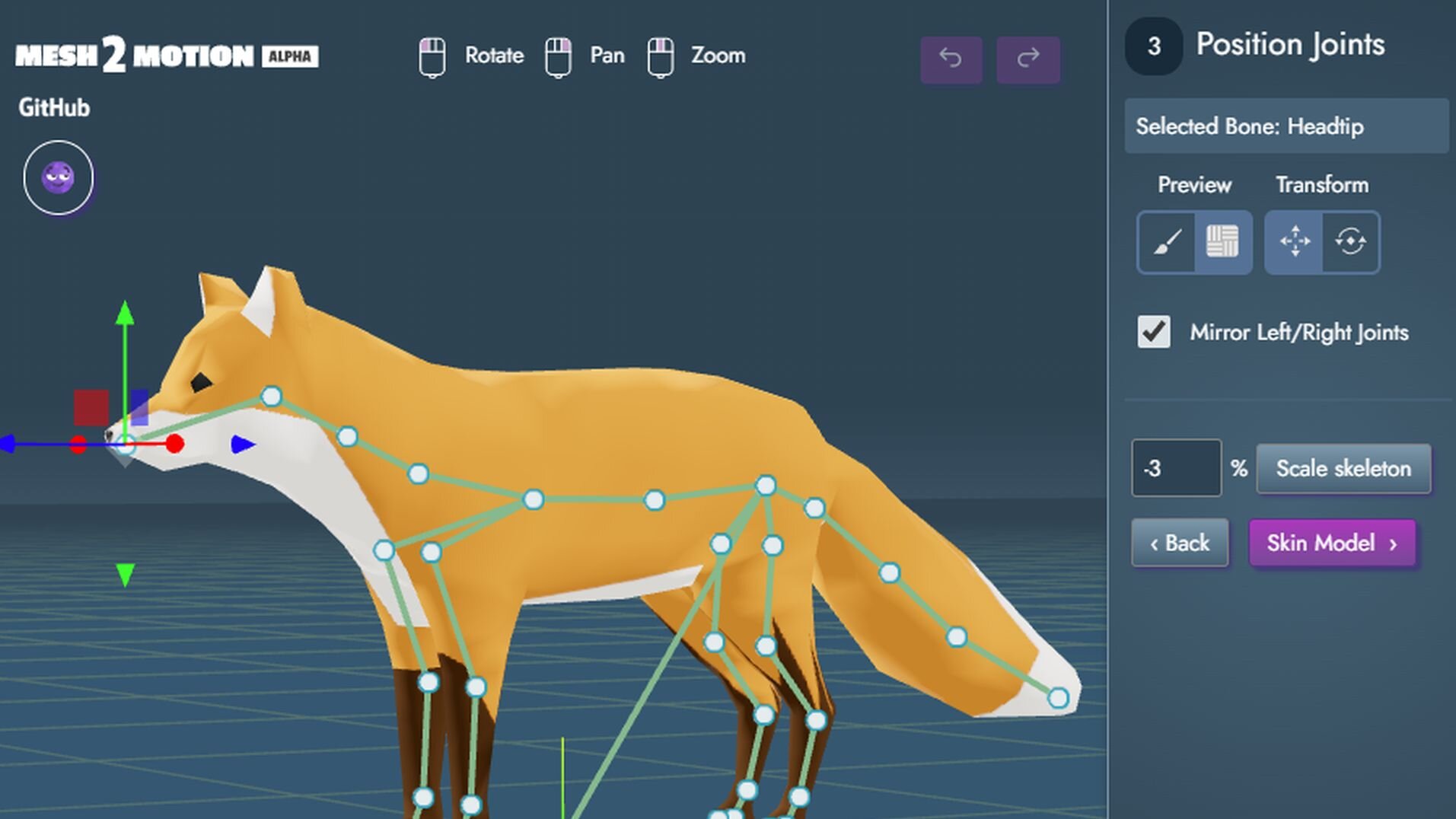「第1回 CGWORLDノベルズコンテスト」では、受賞候補2作品を選出し、CGWORLD.jpにて各作品を全12回にわたって掲載いたします。その後読者投票により各賞を決定し、それぞれ書籍として刊行する予定です。
「CGWORLDノベルズコンテスト」概要
第1回 CGWORLDノベルズコンテスト

■今後の予定
12月8日(金)〜:CGWORLD 305号とCGWORLD.jpで掲載と読者投票スタート
2024年3月頃:書籍時の扉絵イラスト募集
2024年6月頃:読者投票&扉絵イラスト結果発表
本文
ローラはそう言って再び微笑んだ。森には立ち入れないとか、本気であの話を信じているのかとか、言いたいことはたくさんあった。でも何かが始まる予感がして、どうしようもなく胸が高鳴ってしまった。いやいや、と首を振る。一部始終を見てもらうにはマレの森に案内しなければいけないじゃないか。今まで森に興味を持ったか僕を怪しんだかわからないが、勝手に知らない人間が後をつけてくることがあった。しかし僕が森に入ってしばらくすると、彼らの姿は消えていた。ローラだって同じに違いない。
僕が黙り込んでいても、ローラは立ち去る様子を見せなかった。市場の喧騒が遠くに聞こえた。ポツ、とうつむいた頭に水が当たる。気付けば周囲はかなり暗くなっている。分厚く重たそうな雲が雨を連れてくる。たいていの市場の人間は屋台で商売をしているから、急な雨に動じた様子もない。そもそも秋と冬の間の時期は冷たい雨が降りやすい。対策をしていない僕の方が珍しいのだ。僕は雨や雪が降ったら肉を卸すだけで森に引き返してまた絵を描く、貴族みたいな生活をしているから、煮込み料理屋の男からたまに舌打ちを食らう。
「わ、雨ですか。困りましたねえ……」
思いのほか焦った声がした。ローラが細い腕で大きなリュックを抱え上げて頭をガードしていた。濡れることを気にしたりするのか、と意外に思った。少ししか話していないが、雨ごときを気にするというのはここまでの押しの強さや何事も気にしなさそうな鷹揚さに似つかわしくない気がした。
「すみませんが、ジルさん。一旦避難させてくれませんか? 森にお住まいなんでしょう?」
ローラは心底困った顔で僕を見る。そこで初めて気付いた。リュックもそれを支えている彼女の腕も、濡れている場所がどこにもない。目を見開いて彼女を凝視していると、雫が彼女をすり抜けるようにして地面に落ちていった。彼女は濡れるから困っているのではない。濡れていないことに気付かれることに焦っているのだ。さっきと言われていることは同じだが、状況が変わってしまった。怪しまれて奇異の目を向けられる気持ちはわからないでもない。どれだけ無関心を装っても少しずつ心が削れていく感覚だ。気付けば僕は荷物をまとめて彼女の手を引いていた。彼女の持っていたリュックがずり落ちてしまったが、彼女はなんなく片手でそれを支えた。
「……僕の家。たどり着けるかは、わからないけど」
ローラは驚いたように目を瞬かせたが、ほっとしたようにリュックを下ろして片手で背負い直した。僕は足早に森へ向かいながら、雨に濡れず同じ輝きを放つブロンドをじっと見つめた。
マレの森には、僕しか立ち入れないのだと思っていた。どうやら通り雨だったようで、僕の住む小屋に着く頃には、ほとんど雨は止んでいた。僕の後ろには、一滴も水が付かなかったローラがけろりとした顔で立っている。
「おや。どうやら私、歓迎されたみたいです」
僕のことを見失うこともなく、町へ帰されるわけでもなく、ローラは木々がなくぽっかりと開いたその空間に立っていた。重そうなリュックを勢いよく下ろし、のんきに足なんか伸ばして座っている。
今まで、興味本位で僕が帰る後をつけてきた人間がいないわけではなかった。それでも皆マレの森に立ち入りを拒否され、気付けばいなくなっている。その後は何か恐ろしいものを見るような目で僕を見るか、あるいはもう見かけなくなってしまうかのどちらかだった。どうやら僕は、このローラという得体の知れない少女も同じようなものだと、心のどこかでたかを括っていたらしい。
マレの森は町の住民が恐るにふさわしい程度には暗く、しかし町の子どもたちが冒険に繰り出したくなる程度には開けていた。本来は両立し得ない二つの特徴が合わさっているというのは、よく考えなくても薄気味悪い。住民や子どもたちからしてみたら、先が見えているのに気付いたら元の位置に戻されているのだから尚更だ。
物珍しそうに周囲を見回しているローラを放って小屋へ入ろうとすると、後ろから「ジルさん」と声が飛んできた。
「それでは約束通り、見せていただきましょうか」
「…………僕、君に名乗ったっけ?」
「鳥籠の絵に署名がしてありましたから」
そういえばそうだったか。細かいところまでよく見ているのは、美術商という職業柄だろうか。僕は肩をすくめて了承の意を返し、小屋の中にある描きかけのキャンバスを取り出した。森に入ってこられた時点で、今更何かに怯えたり怖気付いたりするような人間(かどうかもちょっと怪しい)でないことはわかっている。だったら別に見せてしまってもいいものだった。
森で絵を描くと、必ずそれは本物の体を持って森のどこかへ身を潜めてしまう。間違いなくマレの森が紙から動物を連れて行っている。しかし森側も多少の譲歩をしているようで、完成していない動物は連れていかない。耳だの目だの描いた端から連れていかれたのでは、森がスプラッタになってしまうのだし当然と言えば当然かもしれない。森は僕の「気に入った箇所は最後に塗る」ルールをしっかり把握していて、最後まで真っ白に残しておいた部分に色がついた瞬間、出来上がったそれを森へと放つのだ。逆に言えば、絵に残しておきたい動物は一箇所だけ塗らずに白いままにしておけばよい。それに気付いてからは、何枚か手元に未完成の絵を残しておくことにしていた。僕はなにも動き回る動物が見たいのではなくて、ただひたすらに絵としての動物を眺めたいのだから。
「これ、描きかけのリス。これに色を塗ると、絵からリスが逃げていく」
言いながら筆を手に取った。胡桃を持ち、下を向いているリスの絵だ。水を付け、少し赤みのある茶色で塗っていく。濃いところは少し暗めの焦茶色に、ただ柔らかさは失われないように。リスの尻尾はふわふわと軽く、飛び跳ねるような毛並みでなければならない。この丸くてふさふさした尻尾こそが、リスをリスたらしめていると思う。
半分くらい息が止まっていた。僕が筆を置いてふっと息をついた直後、紙がひとりでに動き出す。紙は風になびかれたわけでもないのにひらひらと端っこを揺らし、やがて立ち上がった。絵から胡桃が飛び出し、それを追いかけるようにしてリスがこちら側に足を出した。紙が盛り上がるようにしてリスだけがぬるりと地面に降り立ち、先に転がっていった胡桃を取られまいと捕まえる。その動作の中で、軽く柔らかく塗った尻尾がふわりと揺れた。リスは忙しなく顔をあちこちに動かした後、窓から飛び出し、ぱっと森の木と木の間に潜り込んでしまった。残されたのはもはや主役不在となった紙と、僕と、目を見開いているローラだけだった。
続きは毎週月・木曜に順次公開予定です!(祝日及び年末年始を除く)
日程は公開リストよりご確認ください。
『龍が泳ぐは星の海』はこちらに掲載しています。
読者投票
読者投票は以下からご参加ください。ぜひお気に入りの作品に投票をお願いします!
読者投票はこちらから※締切:2024年1月25日(木)23:59まで
※回答は1人1回までとさせていただきます。