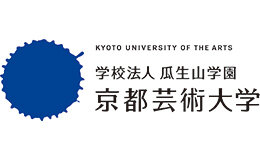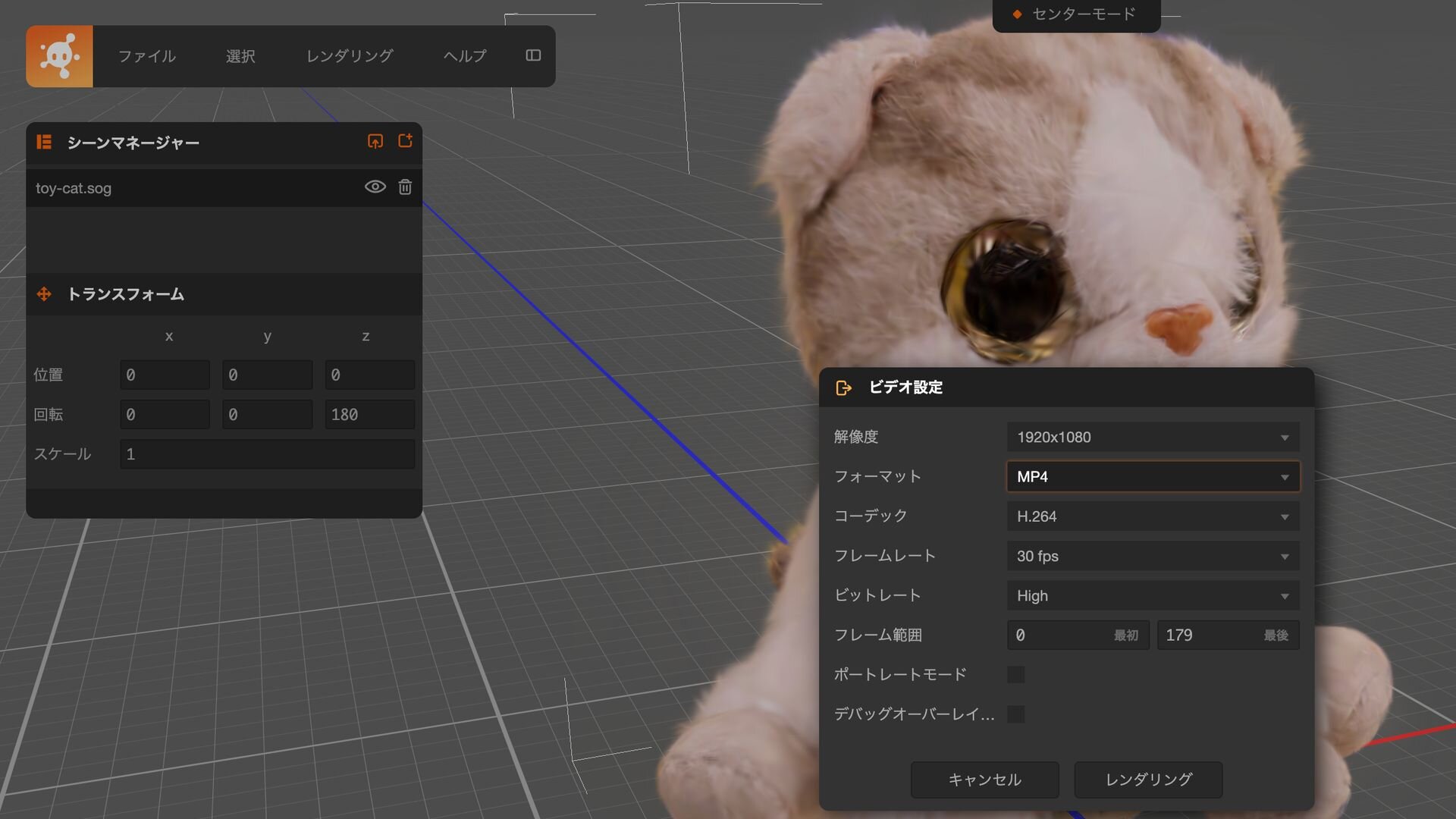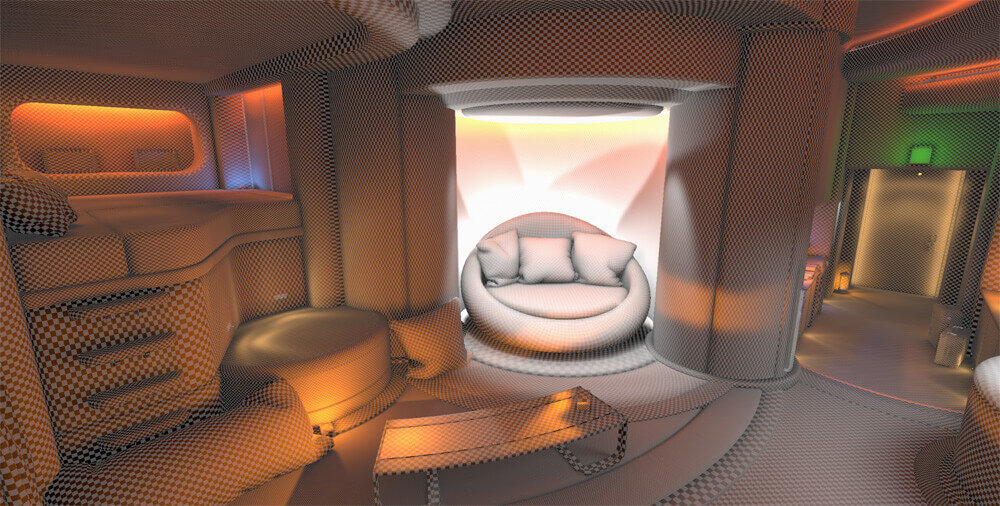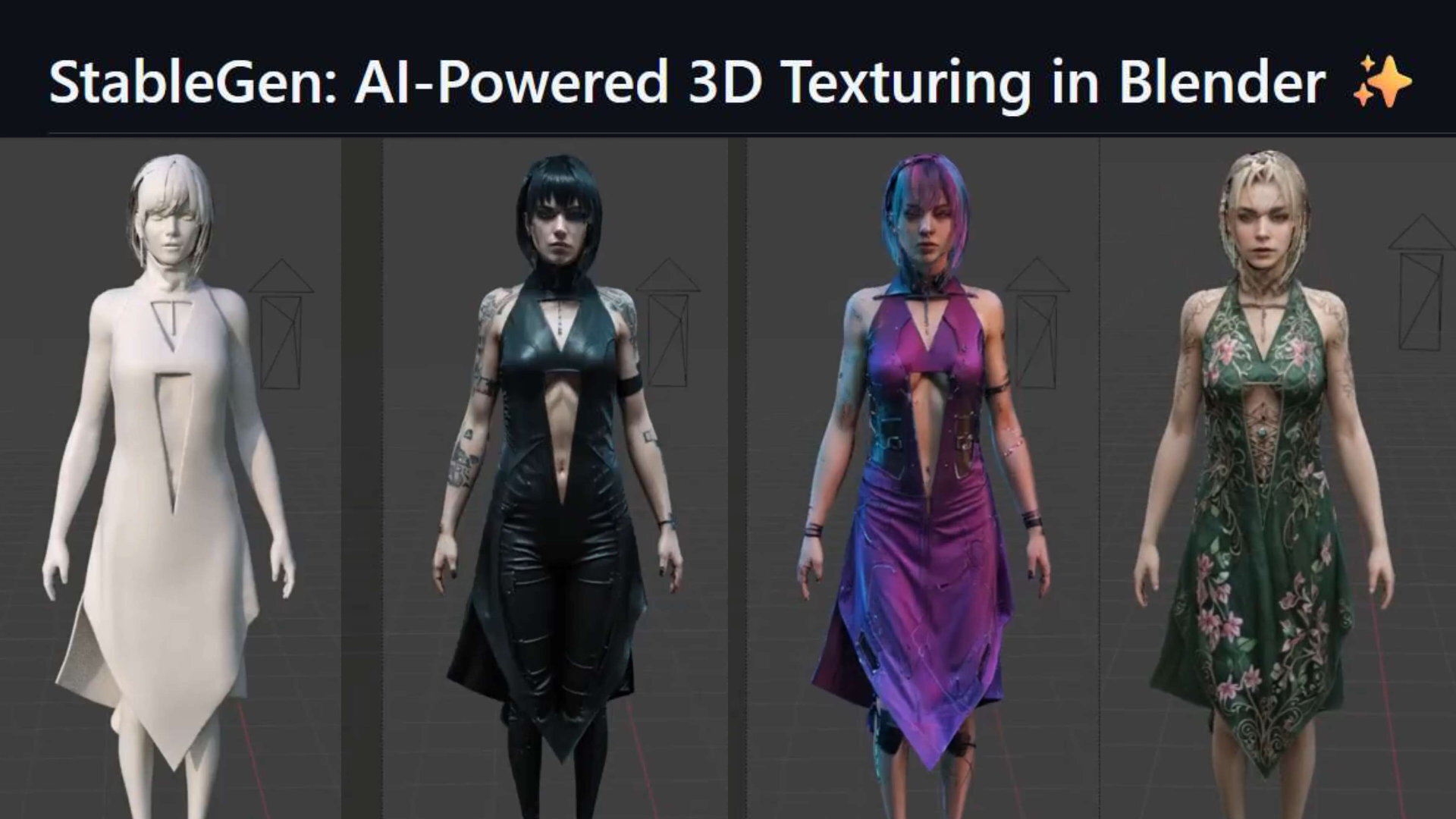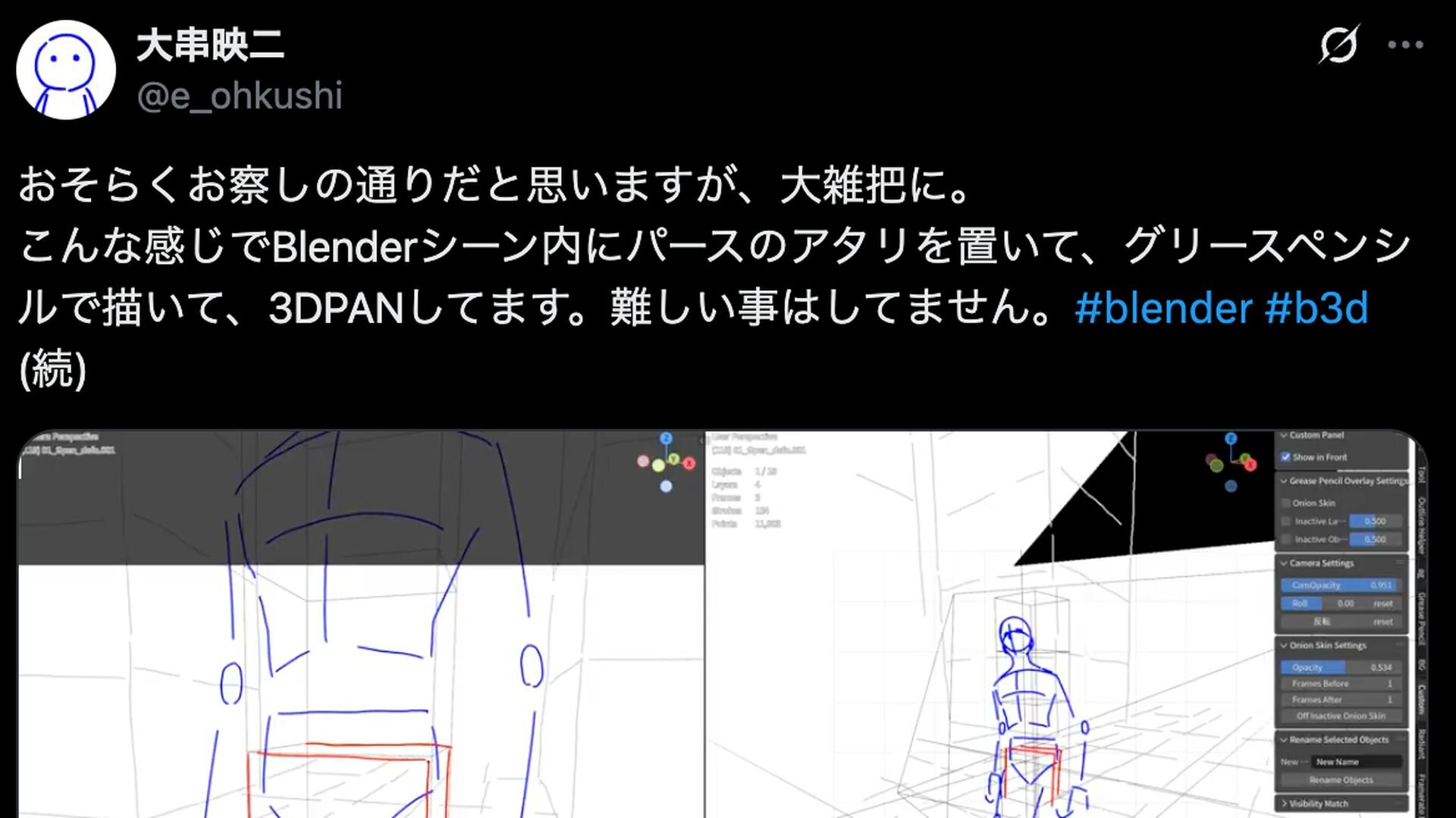「第1回 CGWORLDノベルズコンテスト」では、受賞候補2作品を選出し、CGWORLD.jpにて各作品を全12回にわたって掲載いたします。その後読者投票により各賞を決定し、それぞれ書籍として刊行する予定です。
「CGWORLDノベルズコンテスト」概要
第1回 CGWORLDノベルズコンテスト

■今後の予定
12月8日(金)〜:CGWORLD 305号とCGWORLD.jpで掲載と読者投票スタート
2024年3月頃:書籍時の扉絵イラスト募集
2024年6月頃:読者投票&扉絵イラスト結果発表
本文
二宮と所員との会話が耳に入ってはいたものの、純一はコクーンから目を離せず、これから起きるであろうことをすべて記憶しようと構えていた。
「細胞置換用のナノマシン、バッファータンクも正常に動作しています」
「始めろ」
所員の報告を受けた二宮が開始の合図を出す。モニターに目をやると、コクーンが微振動し、それに揺さぶられた周囲の地面の土が動いていた。
「出力正常。溶解プロセスに移行」
(溶解? 何のことだ)
と純一が思ったのも束の間、微振動の後、カプセルのハッチ部分が眩い光を放った。
中庭の様子を見ている純一を含めたギャラリーは光に言葉を奪われ、管制室内には機材の作動音だけが鳴っていた。
やがて、コクーンのハッチが開くと、その隙間から水蒸気が漏れ出していく。
―次の瞬間、純一には信じられないことが起こった。鋭利な棘に包まれた、緑色の物体が、さっきまで女性が入っていたコクーンからゆっくりと伸びてきたのだ。
その物体は、前足だった。出てきた足を軸とし、棘に包まれた、巨大な体躯を持つ生物が這い出てきた。大きな顎はワニを思わせるが、茶色い鋭利な棘がびっしりと生えた皮膚といい、筋骨隆々の四本の足といい、そのシルエットは、純一がそれまで見たことがないまったく異質な生物だった。
「彼女はシーナ。水中の移動はもちろん、重量物の輸送も可能なノウムだ」
気付けば、二宮が純一の隣に立っていた。
「“ノウム”って、なんですか?」
純一は、中庭内の池に入っていくシーナからは目を離さないまま、質問した。
「ああ。あのコクーンで変異した被検体のことを、そう呼んでいるんだ」
そんな説明を聞いている間に、今度はカプセルに痩せた男性が入っていく。
コクーンが光を放った後、今度は長い胴を持つ爬虫類が現れた。蛇のようだが、その顔には四つの目が付いており、一つひとつが独自に動いて周囲を見回している。薄い緑色の鱗に包まれたその体表は、研磨に研磨を重ねた石のようで、不気味さと美しさの両方を見る者に感じさせる。
「あれは?」
「彼はティト。感覚器官を強化し、狭い場所にも侵入、偵察を行うことができる」
モニターに目をやると、より近くからの映像が映っている。純一には、画面に映された四つの瞳の輝きに、一般的な蛇の無感情なそれとは違う、人の心がこもっているように見えた。
(僕はこんなところで、何をしているんだ)
最初こそ驚きとある種の感動を持ってノウムたちを受け止めていた純一だったが、彼らこそが、二宮の言っていた“未来”。そう考えただけで、胸のざわめきが抑えられなかった。何者でもない自分と彼らとの差を、変異という形で、視覚的にはっきりと見せつけられた気がしたのだ。まったく自分とは違う人生や境遇の彼らに劣等感を持っても仕方がないが、そう感じずにはいられない。
「彼女で最後だ」
思わず目を伏せていた純一を、二宮の声が動かした。
中庭に視線を落とすと、三人目、青白い髪をした少女だったものが、コクーンから飛び出す瞬間が見えた。
その姿は、六本足の狼だ。体表は、体毛に覆われており、その色は、少女の髪の色をさらに深くした、夜空や海のような蒼色だ。その一つひとつが周囲の光を受け、月のような輝きを全身から放っている。モニターに目をやると、頭部には鋭い瞳が付いているのがわかった。咲き乱れる紫陽花を彷彿とさせる淡い紫の瞳は、何もかもを吸い込んでしまいそうだ。
「彼女は、マレ。先のティトとは違って、機動力と嗅覚を活かしたアプローチで、危険が予想される地帯の偵察をすることが可能だ」
「はい……」
そう答えつつ、純一は上の空だった。人が変異した三体のノウムの躍動する姿は、想像を越えていたからだ。
見学の後、純一は研究所の応接室に通されていた。灰色の壁と天井に囲まれた無機質な部屋で、机を挟んで二つ置かれたソファだけが黒い光沢を放っており、異物感があった。
「いや、すまない。来客への挨拶が長引いた」
ドアが開き、二宮が姿を見せた。
「さっき見せたあの三人が、私の研究成果だ」
純一の正面に座った二宮は、来客からの質問攻めにあったのだろう。やや疲れた様子だった。一方の純一は、この部屋に来てからも上の空で、さきほど所員から出された紅茶は、彼に一口も飲まれないまま湯気が消えようとしていた。
「聞いているか?」
「あっ、はい。すみません!」
おそらく、今日一日中喋り続けていたであろう二宮は、男性所員が運んできたカップをすぐにつかみ、紅茶を一口飲んだ。
「初めて見たら、そうなるのも無理はないさ」
つられるように、純一も紅茶を飲む。
「二宮さん、彼らはどうやって、あのノウムになっているんですか? あんな技術は初めて見ます」
「それはそうだ。まだ公開していないからな」
と言って、二宮がほくそ笑む。そして、質問への答えとして、懐から四角い樹脂製のケースを取り出した。
「これだよ」
透明なケースの中には、緑色の物体が封入されている。ゼリー状のそれは、アメーバやスライムのような質感だ。
「それは?」
「生体インプラント“シード”だ」
「―僕らの体に入っているのも、インプラントですよね?」
手の甲を見る純一に対して、二宮はうなずき、語り出した。
「我々の肉体に埋め込まれている機械式インプラントは、生命活動、及び日常生活を補助するナノマシンだ。このシードはすべてが有機体で構成されており、注入された肉体の細胞そのものに変化を及ぼす」
純一がシードを眺めると、表面がわずかにうごめいているのがわかった。
「シードには二つの機能がある。一つ目は、君が見たコクーンを介して肉体を変異させる機能。そしてもう一つが、変異後のノウムの細胞構成と、元の人間の肉体の細胞構成を記憶する機能だ。前者はノウムになる際に、後者は二つの肉体を行き来するのに必要なのはわかるな?」
眉毛を吊り上げた二宮の表情は、「これだけ噛み砕いて説明すれば、わかって当然だろう」と言っているようだ。
「はい」
わかっていてもいなくても、純一にはそう答えるしかなかった。
「ノウムになることで、惑星開拓任務で活躍ができる……ということですね」
「本来は君のご両親が惑星に到着した後、第二波として我々も向かうつもりだったのだが、我々の所属していた部署はあのウィア計画の凍結をきっかけに解散されそうになってね」
わざとらしく、二宮は肩をすくめる。
「途方に暮れていたとき、ISCが出資者として自由な研究を約束してくれたんだ。それで、このケージを建てることができた。今はまだ昔からの被検体が三人だけだが……」
紅茶を飲もうとした純一の手が止まった。
「これから被検体も増えるんですか?」
「―そうだな。クアドロではあの三人で精一杯だったが、これからはさらなる人材を増やすことになるだろうし、それは必要だ」
純一は唾を飲み込み、一拍置いてから口を開く。
「僕も、被検体にしてくれませんか?」
空虚な日々を過ごす純一に、大きなショックを与えてくれたのが、先ほどのノウムたちだ。不可逆ではないとはいえ、異形の生物に自らの体を変異させることへの抵抗がないわけではない。
だが、自分もここでなら何者かになれるかもしれない。
その気持ちが、目の前にわずかに差し込んだ光明を掴もうとさせる。
理由はもう一つある。彼の脳裏には、未だにあの蒼い狼“マレ”の姿が焼き付いていたのだ。
短い時間だったが、あんなにも美しい生物を見たのは、純一の人生の中で、初めての経験だった。
二・変異
純一の頼みに対し、二宮は素直にうなずきはしなかった。
「私の実験に魅力を感じてくれたのはうれしいことだ。だが、『僕もやりたい』と言われて、『わかった』と、簡単に君にこれを投与するわけにはいかないんだよ」
二宮はシードが入ったケースを少し眺めた後、懐に収めた。
「これまで三人しか被検体の成功例がなかった理由がわかるかい?」
純一が答えられずにいると、
「シードに適合し、ノウムへの変異に耐えられたのが彼らだけだったからだ。残念ながら、まだ量産し、普及させるほどの完成度には至っていないのが現実だ。それに、副作用だってある」
その言葉は、未だ目標を達成していない、自分たちの不甲斐なさに対しても向けられているようだった。
「再来年……いや、来年には、万人に適合するシードを実用化したいと考えているから、その日を楽しみにしていてくれ。あくまで君を呼んだのは、見識を深めてもらいたかっただけで―」
「危険でもかまいません。二宮さん、僕で試してください!」
二宮がため息をつく。
「聞いてなかったのか? 少し待てば、きっと君だろうが、街を歩いている老人だろうが、ノウムとして宇宙で活躍できる時代が来るはず。いや、そうする。だから……」
二宮の目をまっすぐ見つめた後、純一は首を横に振った。
「―大学の進学だってあるはずだ」
「適性テストのようなものがあるなら、それだけでも受けさせてください。後悔はしませんから」
先ほどよりも一段大きなため息の音が、応接室内に響き渡った。
結論から言うと、純一のしつこさに根負けした二宮は、近々行うノウム適性テストだけでも受けさせることに決めた。一人でも多くの被検体を探したいという、科学者としての欲があったことは否定できない。
「一度ここの被検体になれば、もう元の人生には戻れない。すべて管理下に置かれる生活だ」
「かまいません」
重力に縛られた空虚な人生なら、いらない。
「私はここの責任者だ。仮に君がノウムになる適性を満たしていたとしても、人格面などを理由に落とすことだってできるんだぞ?」
「多分、二宮さんは、そういうタイプじゃありませんよ」
純一が帰った後、二宮は自身の書斎で、ISCから送られてきた何十人もの候補者のリストを眺めていた。
この候補者は、ISCが選抜した心身共に優秀と判断された者たちだ。ケージにいる三人の被検体と同様、幼少期から体格や健康状態などを逐一管理・記録された中で育ってきており、いわば、ノウムになるために育てられてきたような人間たちだ。もちろん、そのような優秀な人間を被検体にすることだって意味はある。だが、昨日まで一般社会の中で暮らしてきた人間がノウムとして活動したという実例ができれば、コクーン・プロジェクトにとってはこれまでで最も大きな前進となるだろう。二宮の想定では、このような実験は、もう少し後に行う予定だったが……。
帰宅し、叔父と叔母に報告した純一を迎えたのは、叔父の怒鳴り声だった。
「何を考えているんだ! そんなことより、大学の進学の方が現実的じゃないか」
純一としては、十分に考えたつもりだった。だが、純一の叔父は、そう強く彼を問い詰める。
「だまされているんじゃない? 宇宙に行きたがっていたあなたを利用して……」
叔母もそう言ったが、特に純一は選択を覆すつもりはなかった。
「二人に迷惑はかけないよ。それに大学に使うお金は、父さんと母さんの遺産だから」
卑怯な言い方であることは自覚していた。
「まだ受かるとも決まってないし、勝手だとは思うけど、僕はもう決めたんだ。これで宇宙に行くって」
これまで純一は、宇宙に行く目標を持った自分は、特別だと思っていた。両親が宇宙に行くことに反対していた叔父や叔母のような人間と、自分は違う。新天地に行く自分や両親に比べれば、死ぬまで地球で暮らす人々の人生は、なんとつまらないものだろうと。
それが傲慢な考えと指摘してくれる者はいない。今回の適性テストは、両親の死によって自分とは違うと感じていた人々と同じ地点に堕とされた自分にとっての光だ。そう、純一は思っていた。
(たとえ落ちたとしても……いや、受かることだけを今は考えよう)
続きは毎週月・木曜に順次公開予定です!(祝日及び年末年始を除く)
日程は公開リストよりご確認ください。
『美術商ローラと家路を急ぐ青年』はこちらに掲載しています。
読者投票
読者投票は以下からご参加ください。ぜひお気に入りの作品に投票をお願いします!
読者投票はこちらから※締切:2024年1月25日(木)23:59まで
※回答は1人1回までとさせていただきます。