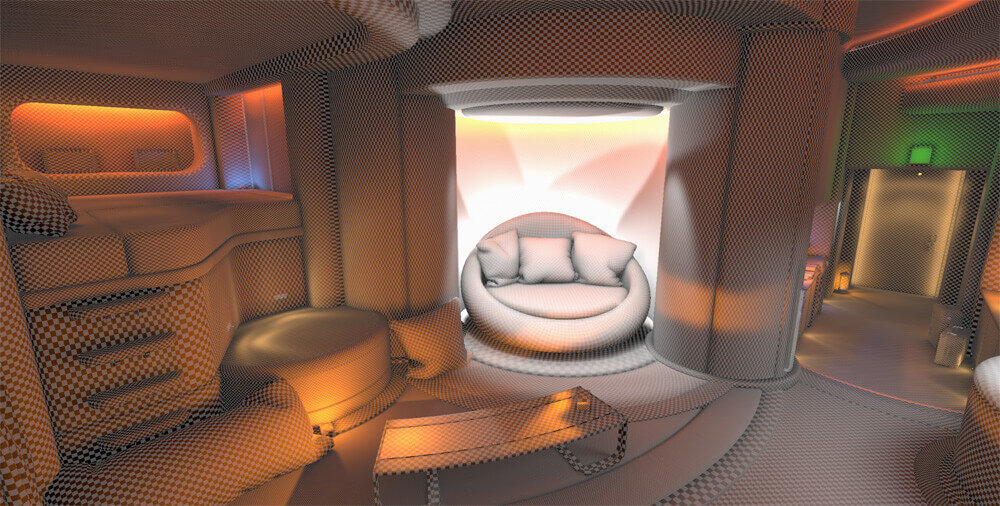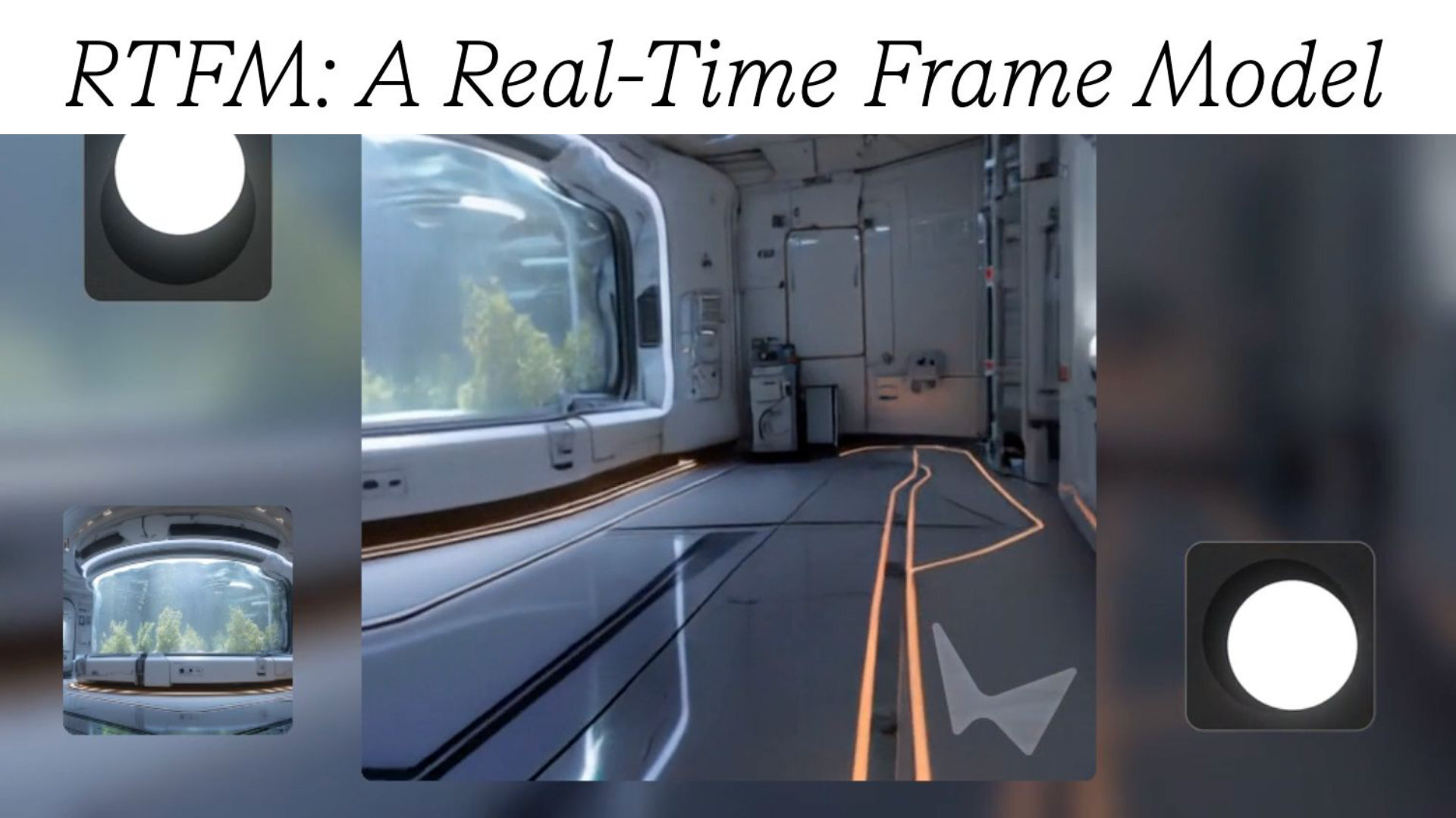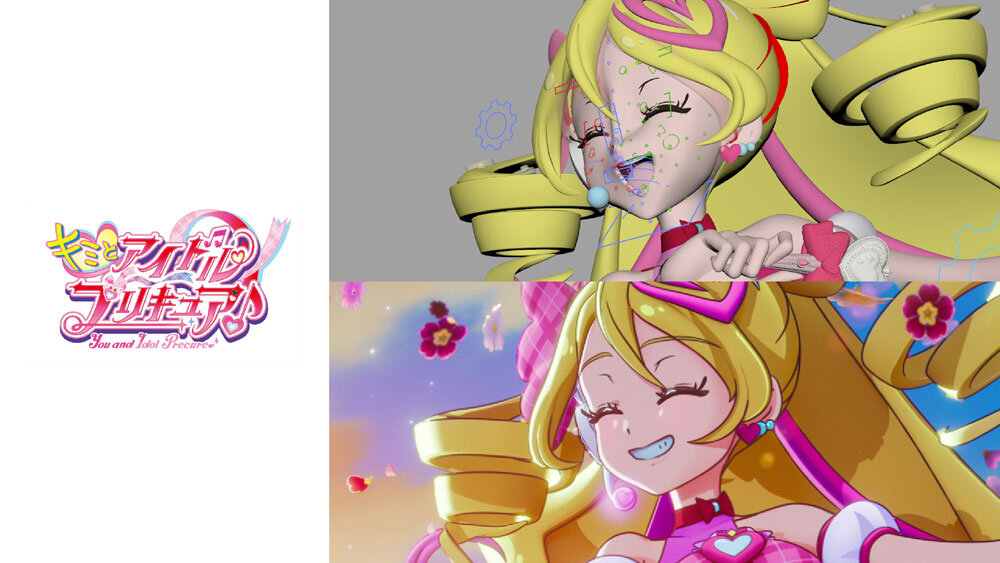「第1回 CGWORLDノベルズコンテスト」では、受賞候補2作品を選出し、CGWORLD.jpにて各作品を全12回にわたって掲載いたします。その後読者投票により各賞を決定し、それぞれ書籍として刊行する予定です。
「CGWORLDノベルズコンテスト」概要
第1回 CGWORLDノベルズコンテスト

■今後の予定
12月8日(金)〜:CGWORLD 305号とCGWORLD.jpで掲載と読者投票スタート
2024年3月頃:書籍時の扉絵イラスト募集
2024年6月頃:読者投票&扉絵イラスト結果発表
本文
説明を聞きながら僕はあらゆることが腑に落ちた思いでいた。どうりでローラはこの森に入れるわけだ。もともと森側が呼んだ存在だったのだ。いろいろわかると「僕しか立ち入れない」とたかをくくっていたことが少し恥ずかしくなる。この森に主がいたというのは初耳だったし、「人間との付き合い方」なんて本を読みたがっていることが気にならないわけではなかったが、ひとまず聞き流した。
「それで、僕の空っぽの動物画もどこかで売れるわけ?」
「売れるのはそっちじゃありません。現実に連れてこられた動物たちの方です」
「はあ」
「ジルさんだってやっていたじゃないですか。煮込み料理屋の方に卸していた鶏、あれは絵から出てきたものでしょう?」
「…………君、いつからどこまで見てたわけ?」
「あなたが鶏を店の方に渡すところからですね。あ、違いますよ、ただの偶然です。私はあのスープが食べたくて寄ったらジルさんがいた。森に向かおうとしたらジルさんがその近くで絵を描いていたのです」
それで、森に住んでいるならちょうどいいと案内させたわけだ。本当に偶然なのかは疑わしいが、とにかくそういうことらしい。
確かに僕は煮込み料理屋の男に絵から出てきた鶏を卸していた。マレの森に本物の生き物は存在しない。森から出られず絵も売れなかった頃、食うに困ってダメもとで絵から出てきたウサギを焼いたことが始まりだった。まさか絵に描いたものを焼いて食べられると思っていなかったし、それがお金になるなんてもっと思っていなかったが。それにしてもそれを売るということは──
「絵描きから肉屋に転職しろって?」
「違いますよ。先ほど鳥籠の絵を拝見しましたが、あの鳥はいかがです? それかさっき描いてた猫とか。毛並みの良い猫は種別問わず人気ですよ」
「いや、あれはだめだ。あの猫は──」
にゃおん。僕の言葉を遮るようにして影が一つ、小屋から躍り出る。真っ黒な毛並みと丸い目を持つ猫は、ローラを値踏みするようにじっと見た後、僕の足にまとわりついてきた。その頭を撫でてやりながら、地べたに座る。
「あの猫は、この子……リラが寂しくないように描いていたものだから。売るならリラと一緒に」
ローラも座りながらリラに手を伸ばす。リラはローラを一瞥した後、ふいと横を向いた。どうやらお気に召さなかったらしい。ローラは拒否された手をうろうろさせながら少し不満そうに口を尖らせた。
「猫にも森にも嫌われますね」
「あんまり人に懐かないんだ。実家にいたときも僕と母の膝にしか乗らなかったし──」
「おや。この子はあなたの故郷から連れてきたのですか?」
ハッとして膝に乗る黒い毛玉を見た。リラは不思議そうな顔で僕を見上げる。「違う」と気付けば口にしていた。このリラは、僕の家にいたリラではない。
「実家にいた猫を思い出しながら描いたんだ。だからかな? 性格もよく似てる」
「……帰りたいですか?」
僕はゆっくりとリラからローラへ視線を移す。唐突なこの質問は思ったよりも心の柔らかいところに刺さったらしい。
「あ、当たり前じゃないか!」
思ったよりも大きな声が出た。僕の声に驚いたのか、リラが膝から飛び降りて逃げてしまう。ローラは泰然とした表情で僕とリラを見比べ、ゆっくり口を開いた。
「あなたをこの森から解放してあげると言ったら?」
さっきまでの子どもっぽい態度とは打って変わり、静かに言葉を発した。解放、この森から。顔を上げるとローラは真剣な顔で僕を見ていた。冗談ではなさそうだった。
「どういうこと? 君はこの森の何を知ってるんだ?」
「まだ何も。随分と森があなたのことを気に入っているとしか……ただ春になるまでには、必ずあなたをここから出してあげられます。私、これでも交渉をお仕事にしていますし」
「本当に……?」
「ええ、帰りたいんでしょう? あなたの故郷に」
言われた途端、僕の頭の中に故郷の我が家が浮かんだ。腰の悪い母のために父が作った特製の椅子、冬になると薪を積み上げていた暖炉、家の近くにあった小さな川………
「帰りたい」
気付けば僕はローラの肩を掴んでいた。迷子のように「帰りたい」と呟いてローラを見つめた。
「本当に帰れるの?」
「ええ……あ、ただ代わりと言ってはなんですが、お願いしたいことが」
「僕にできることならなんでもするよ。言って」
「ではまず、冬の間こちらに住まわせていただけませんか?」
「ええ?」
「私、これから行くところがないのですが……冬を越えるまで、こちらに居させていただいても?」
「……ええ」
僕はぽかんと口を開けた。確かに「春までに」森と交渉してくれるという話だったが、無計画でこの森まで来ていたとは思わなかった。聞けばローラは、美術商として各地を転々としているがこの町に来たのは初めてで、まさか冬の間中はへたに出歩けないところだとは思っていなかったという。
「どこでもいいので寝る場所だけ貸してほしいのです。最初はこの森に頼むことも考えましたけど、私には意地悪みたいですから」
また口を尖らせたローラはそんなことを言う。そしてリュックから寝袋やら大きなテントやらを取り出して「土地さえ貸していただければ!」などと言う。そのリュック便利だなと関係ないことが頭に浮かんだ。
あのひどい絵を実体化しなかったことが意地悪かどうかは後で審議するとして、僕はこれでも男である。見知らぬ少女と一つ屋根の下で生活することにラッキーと思えるほど倫理観のない人間ではないし、何より自宅に他人がいるのはひどく緊張する。
しかしローラは粘り強かった。
「これでも長く生きていますから。料理に洗濯、掃除もできます」
「いや、家政婦を雇いたいわけじゃないんだよ……そういう意味で君を負担に思っているわけではないし……」
「この辺りで一冬越そうと思うと宿泊費も馬鹿になりませんし……それに私、あまり不特定多数の人々に覚えられてしまうと困るのです」
言動や表情からして、ただの人間でもなさそうなことはわかっていた。リュックから明らかにサイズオーバーのものを引っ張り出してくるし、雨にも濡れない。きっと僕よりもマレの森に近い存在なんだろう。ただ人の形をしているというだけで。
「この身が少女であるのが気になりますか? よろしければ少年でもオジサンでもお好きなようにできますが」
ローラは少々考え込む素振りを見せた後、なんの前振りもなくふわりと一回転した。目の前の少女は、突然髪の短い少年へと変化する。あの美しいブロンドがなければ、彼女(もはや彼女かも怪しい)だとわからなかったかもしれない。ローラはポンポンと姿を変えてみせる。青年に、中年の男に、女性に、果ては腰の曲がった老人にまで。くるりくるりと僕の好みを探るように見た目を変化させていく。
「ちょっと……ちょっとストップ!」
ローラは妙に露出の多い女の姿で変身を止めた。からかうような視線で僕を見下ろす。身長まで自由自在のようだ。僕はその辺にあった椅子に座り込んで頭を抱えた。
「この姿がよろしいので? 随分と刺激的ですが……」
「いや、もう元に戻っていいよ……君がワケわかんない存在なのはよくわかったから……」
ローラは元の少女の姿に戻った。少女のローラは座った僕とちょうど視線が合うくらいの背丈で、「やっぱり青年かなんかの見た目で固定してもらえばよかったかな」と考えてしまった。とはいえこれだけ妙な人間(かも怪しい)とわかってしまうと抵抗感も少し薄れる。
「……いいよ、うちに泊まって。なんでもするって言ったのは僕だしね」
「ありがとうございます。あ、それともう一点。龍を一匹、お願いできますか?」
「ああ、わかった。…………え?」
衣・食・住……龍? 首をかしげた僕の横で、戻ってきたリラがのんきにあくびをした。
続きは毎週月・木曜に順次公開予定です!(祝日及び年末年始を除く)
日程は公開リストよりご確認ください。
『龍が泳ぐは星の海』はこちらに掲載しています。
読者投票
読者投票は以下からご参加ください。ぜひお気に入りの作品に投票をお願いします!
読者投票はこちらから※締切:2024年1月25日(木)23:59まで
※回答は1人1回までとさせていただきます。