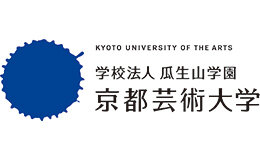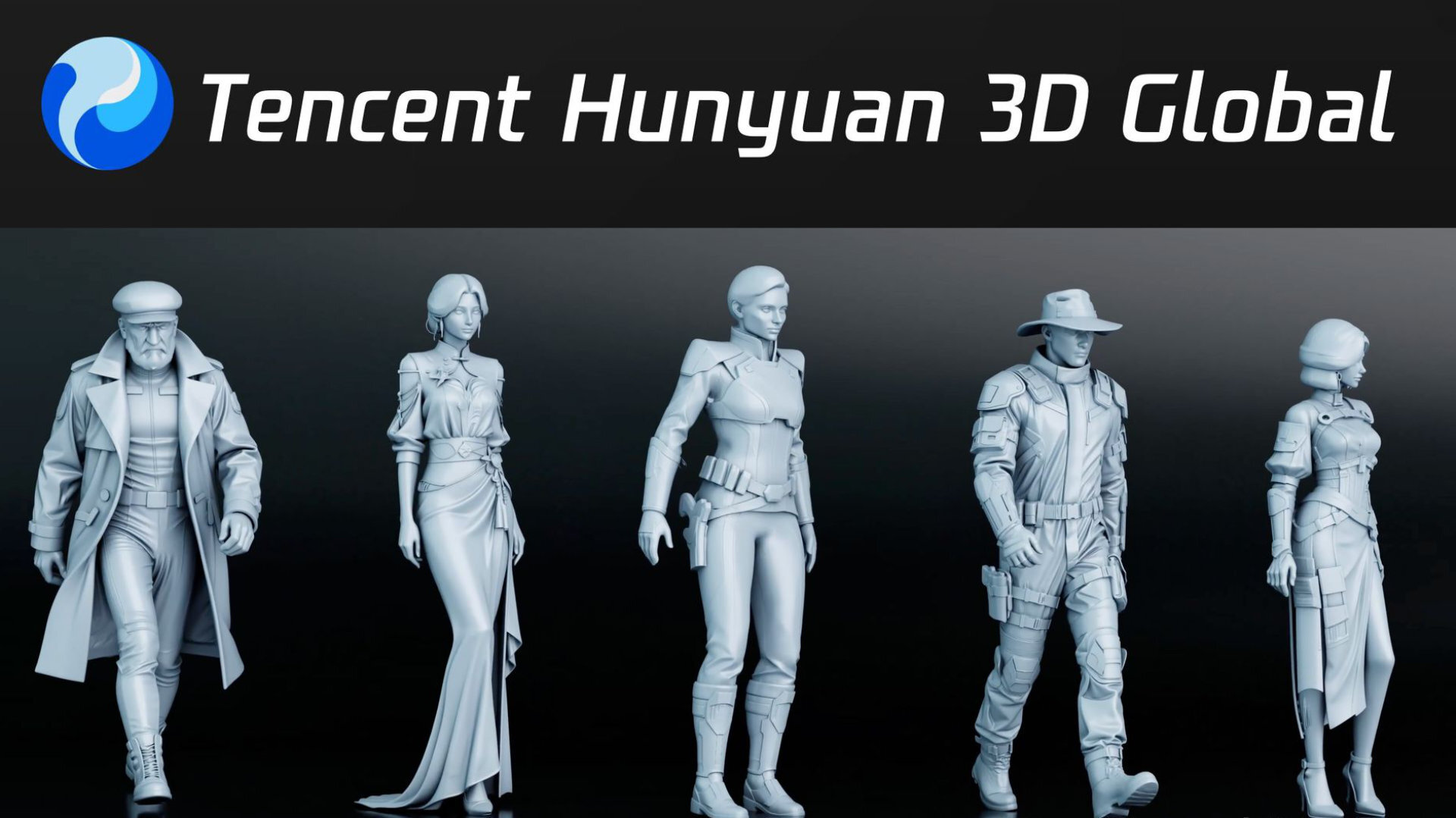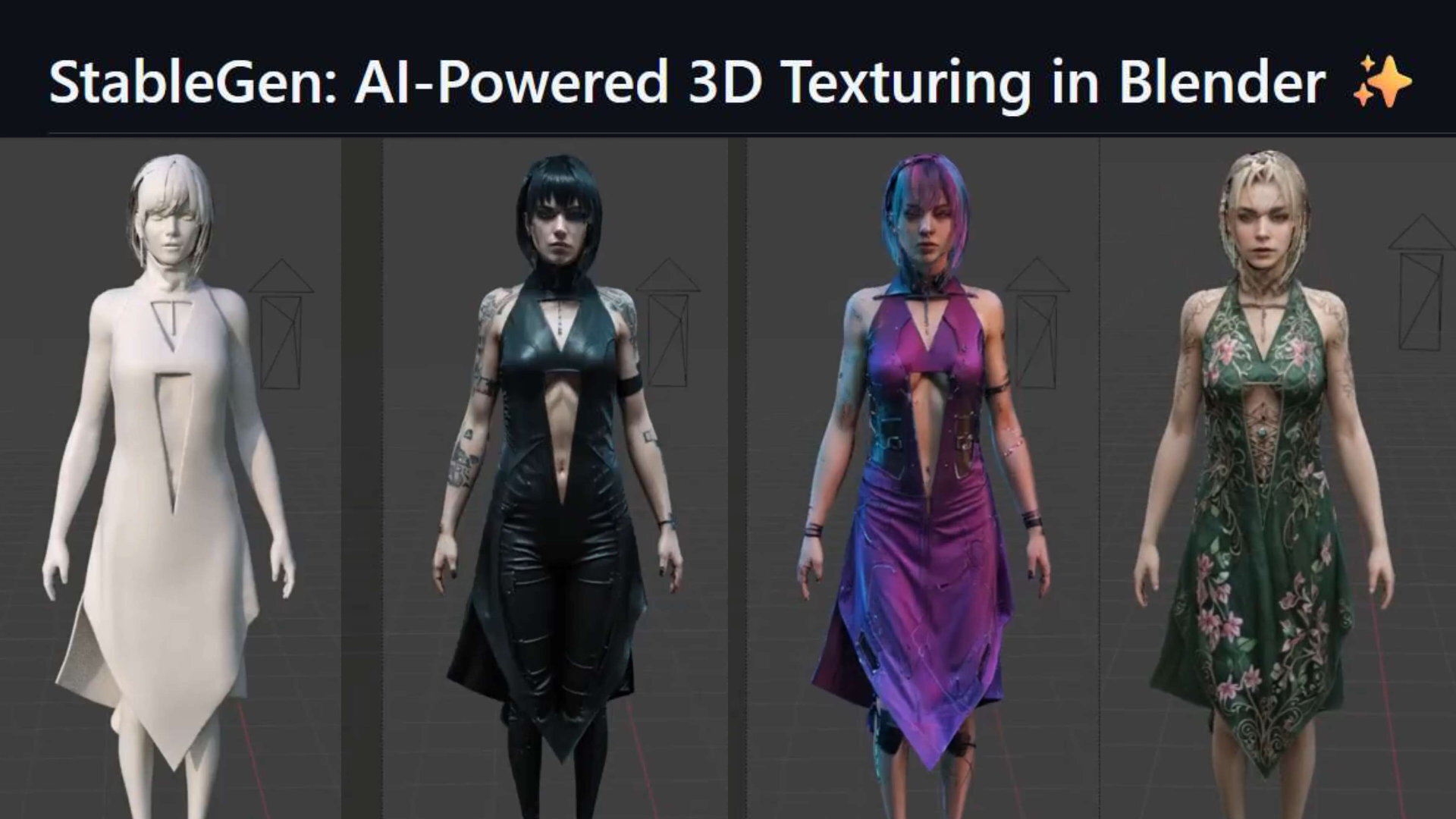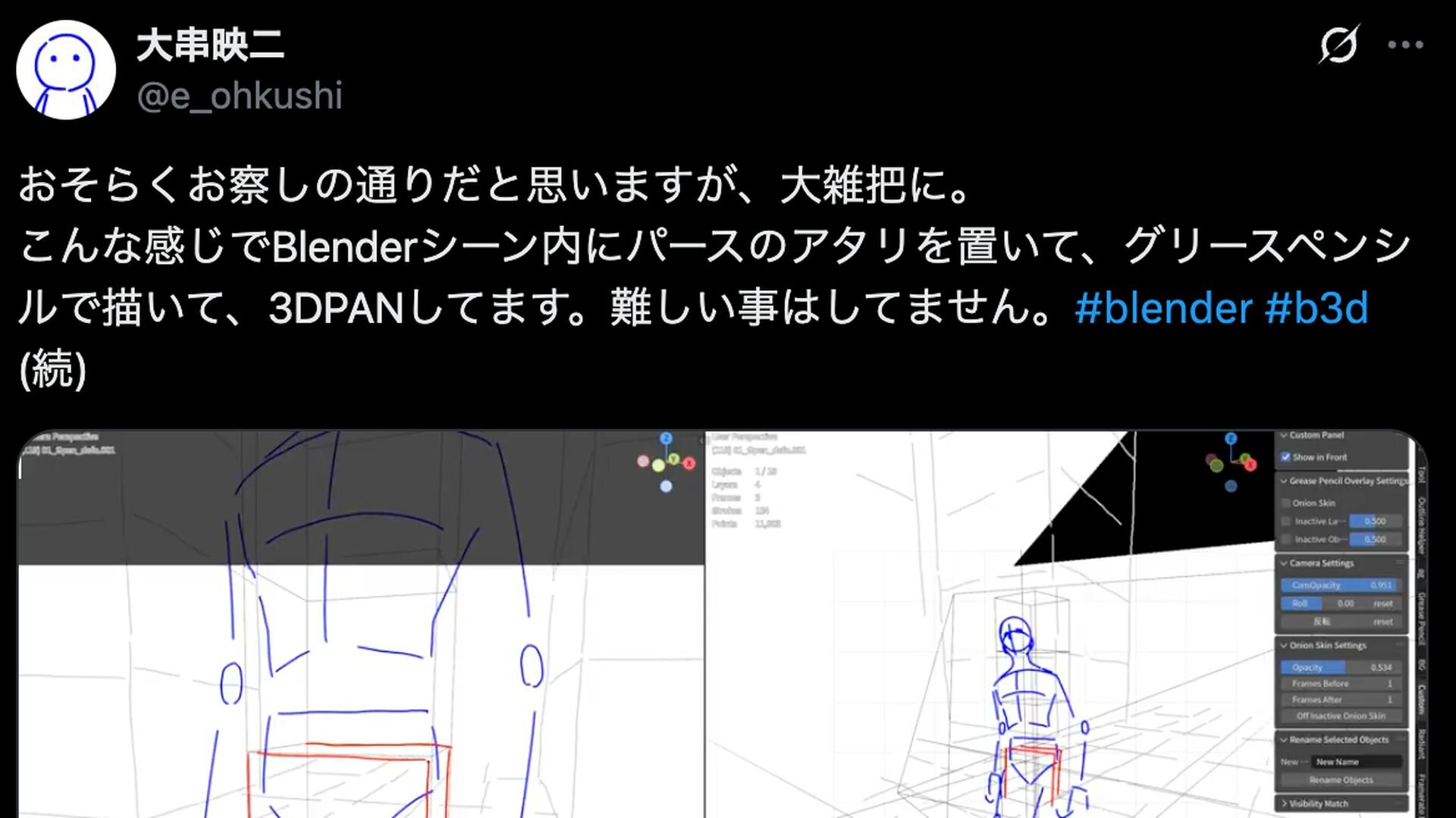「第1回 CGWORLDノベルズコンテスト」では、受賞候補2作品を選出し、CGWORLD.jpにて各作品を全12回にわたって掲載いたします。その後読者投票により各賞を決定し、それぞれ書籍として刊行する予定です。
「CGWORLDノベルズコンテスト」概要
第1回 CGWORLDノベルズコンテスト

■今後の予定
12月8日(金)〜:CGWORLD 305号とCGWORLD.jpで掲載と読者投票スタート
2024年3月頃:書籍時の扉絵イラスト募集
2024年6月頃:読者投票&扉絵イラスト結果発表
本文
三・飛翔
純一が初の変異に成功し、飛翔に失敗するまでの風景を、管制室から見ている三人がいた。
「おい、出てこないじゃねえか」
痩せた男性、ティトが、鋭い目を細めながら呟く。その頬は、鱗で覆われている。
「失敗したんじゃない?」
と言って、隣に立っているシーナが、唇の端を吊り上げた。その首の真ん中、喉にあたる部分からは太い棘が生え、まるでチョーカーのように首を覆っていた。
「いくら適合したからって、鈍臭いんじゃなあ……」
ティトが、シーナを見て笑う。彼女のほうが背が高いため、ティトからすると少し見上げる形だ。
「そうだね。結果が出なきゃ意味がないし……」
そんな二人のやりとりを尻目に、中庭を覗いていた青白い髪の少女、マレが呟いた。
「出てきた……」
ティトとシーナがマレの目線の先を見ると、巨大な鳥が、這いずりながらゲートを通って中庭へと入ってくる。
「あれじゃ、鳥の意味ないじゃん」
シーナが苦笑した。
「先が思いやられるなあ」
ティトもため息をつく。
「マレはどう思う? 彼」
シーナが話を振ると、マレは首を振る。
「別に。誰が来ようと興味ないよ」
そう呟いて、淡い紫の瞳で空を見上げた。
目を覚ました純一の視界に入ったのは、医務室の真っ白な天井だった。首を上げて自分の体を見ると、慣れ親しんだ手足が生えており、溶けた痕跡も、黄金の羽毛も存在しなかった。意識を失っている間にコクーンに入れられ、体が元の状態に戻ったのだ。周囲を見渡すと、ベッドの右側には、薄いモニターが設置してある。純一の血圧や心拍数、そのほかさまざまな体内の情報が、シードを介して送られ、表示されているのだ。再構成されたことを確認した純一は体を起こそうとするが、うまくいかなかった。とてつもなく体が重い。
「目を覚ましました」
と所員が声を発した。インプラント越しに連絡したのだろう。その後すぐに、早歩きで二宮が医務室に入ってきた。
「無事目覚めたようで何より。意識が戻ったならば、少し確認したいことがある」
と言って、二宮はベッドの横に座り、純一の手を持つと、手の平に懐から出した針を軽く押し当てた。
「痛っ! 何するんですか!」
「痛覚はあるな」
コクーンによって再構成された人体が、正常な機能を果たしているかの確認らしい。しばらくの間、純一は五感が元通りになっているかを検査された。
「よし! まずは成功だな。“逆流”もない!」
一通り終わった後、二宮は上機嫌で、純一の肩を叩いた。
「逆流?」
「ああ。今までの被検体は、ノウムの情報が人の体にも転写される現象があった。それを我々は逆流と呼んでおり、今回君に注入したシードは、逆流現象を防ぐために改良を施したものだ」
それで、マレと呼ばれる彼女は青白い髪を持っていたのかと純一は納得した。
「成功って言いますけど、僕は飛べなかったんですよね?」
ノウムになっている間のことはおぼろげにしか覚えていないが、床に体を打ち付けた痛みだけは、はっきりと覚えている。
「ああ。だが、無事にノウムになって、無事に戻ることができた。今はそれで十分だ。徐々に体を慣らしていけばいい」
「わかりました」
「体調はどうだ? さっきから体が重くて、だるい感じがするんじゃないか?」
二宮は、今の純一の体の状況を言い当てた。
「……そうです。なんとかなりませんか?」
「コクーンを使用した直後は、体に非常に負荷がかかるからな。……テトラオキシンを出してくれ」
部屋の隅で作業をしていた所員が、冷蔵庫からシリンジを取り出し、二宮に手渡した。
「専用の刺激薬だ。これを打てば、少しは楽になる」
テトラオキシンと二宮が呼んだその薬剤を打ち込まれた瞬間、純一の心臓は激しく高鳴り始め、冷えた手先と足先に血が送り込まれていくのがわかった。
おかげで、純一はベッドから起き上がることができた。しかし、だるさはなくなったが……。
「うう、ちょっと気持ち悪い……」
体が常にざわつく感覚に襲われ、快適とは言えない。
このとき純一は、左腕の中を何かがうごめくような感覚に襲われていたが、検査で特に異常が見当たらなかったため、周囲に伝えることはなかった。
純一が起き上がるのを確認した二宮は、咳払いの後、今後の指針を語り始めた。
「二か月後、君が以前見学に来た日のように、ISCの人間たちが我々の成果を確認しにこのケージを訪れる。内覧会というやつだな。そこで、これまでの三人に加え、新たな被検体である君の性能のお披露目をしたいと考えている。それまでには飛べるようになっていてもらいたい」
「どうやって慣れればいいんです?」
純一は眉間にしわを寄せた。
「ノウムには必要な動きの知識や記憶が設計時に刻印されている。ノウムの感覚に慣れていけば、次第に飛べるようになるはずだ。……入ってくれ」
ひとしきり話した後、二宮はドアに向かって、そう言った。するとドアがスライドし、三人の男女が医務室へと入室してくる。
入ってくる人影を見て、純一は全身が硬直するかのような感覚になった。実際のマレの髪と瞳の色は、モニターで見たとき以上に色鮮やかで、長い手袋の先からは、しなやかな指が伸びている。
「彼は杉崎純一。話していた新しい被検体だ」
二宮は三人の方を向いて言ってから
「純一くん、先日ノウムになる姿を見てもらったが、彼らは君の先輩にあたる被検体たちだ。青白い髪の子がマレ、そしてこの二人がティトとシーナ。二人は兄妹だ」
と、再び純一の方を向いて、三人の被検体を紹介した。
「大丈夫か?」
「え、は、はい! 杉崎です。よ、よろしくお願いします!」
純一は、マレに見惚れる余り、少し呆けていたことに気付くと、慌てて自己紹介をした。
選ばれた者たちの中に、自分も入れる。純一はその事実に胸が高鳴ったが……。
「マレ、挨拶して」
「―はい」
二宮に言われ、純一に軽く会釈したマレに、興奮している様子は感じられなかった。
「ほら、二人も挨拶するんだ」
二宮が兄妹にも促す。
「ティトだ」
「シーナ。よろしく」
ティトとシーナは素っ気なく、簡素な挨拶をした。その際、純一は二人の一部分が、明らかに人間とは違うことに気付いた。間近で見たティトは、頬の部分が皮膚ではなくうっすら鱗に覆われており、シーナは首筋に棘を生やしている。これが彼らに起きた“逆流”だ。つい眺めていると、蛇と同じ瞳孔を持つティトにじろりと睨まれ、純一は視線を逸らした。
「私はコクーンとノウムについて、設計者としての視点でアドバイスはできる。だが、肝心の体の動かし方については、彼らに聞くのが一番早い。この三人に、これからコツを教えてもらってくれ」
「わかりました」
「で、明日以降の予定は?」
二宮が眉を吊り上げながら、純一に聞いた。
「ありません。一度、着替えを取りに帰ってもいいですか?」
「タン、彼の家まで送ってやってくれ」
二宮がそう指示すると、タンは頷く。
「わかりました」
着替えを取りに行き、叔父母への挨拶を済ませた純一は、その日の夕食を初めてケージの食堂で済ますことになった。テトラオキシンを打たれても、ノウムへの変異は激しく体力を消耗させているらしい。昨日までとは違う、激しい空腹感が純一を襲った。
「もう好きにしろ」
反対されていただけに、怒鳴られると思った純一だったが、インプラントを捨てたこと、しばらく家には帰れないことを黙って聞いていた叔父から、吐き捨てるようにそう言われたのは、かえって効くものがあった。
「―あの! ここいいですか?」
初めて訪れた広い食堂を見渡すと、その隅のテーブルに、三人の被検体が集まっているのを発見した純一は、交流のチャンスと思い、声をかけてみることにした。叔父に言われた言葉を、早く振り切りたかったのも、理由の一つである。自分の人生はここから始まるのだ。
「別にいいけど」
ティトとマレは無言で、シーナが代表して答えた。
「ありがとうございます。みんな、すごいですね……」
「何がだ?」
ティトが純一の目を見た。
「だって、ここにいるってことは、何人もの中から選ばれたってことじゃないですか。それで、第二波として宇宙に出ることができる……こんなにすごいことって、ないですよ。海外から参加しに来ているんですか?」
三人の被検体は、自分と肌や目の色が異なるし、何よりも名前が海外のものだ。
「ああ。俺と妹は、ここにいれば食っていけるからいるだけだ。すごいと思ったことはない」
そう言って、ティトはブロック状のノウム専用食をフォークで切り、口に運ぶ。専用食は、宇宙食を改良した、ノウムに必要な多くの栄養素を摂取できる優れものだ。だが、その灰色の外見とぼそぼそとした食感には改善の余地があり、この施設のあらゆるものが新鮮に、輝いて見えた純一でも、口にした瞬間、(これは慣れる必要がある)と思った。
「スギザキ、アンタはなんでここに来たの?」
「元々は大学に進学して、卒業後は第一波で宇宙に行った両親に追いついて、僕も宇宙で働こうと思っていたんです。でも、両親は半年前の事故で亡くなって……。そのとき、二宮さんにコクーンを見せてもらって、ここなら何か特別なことができる。何者かになれるんじゃないかと思って」
「なるほど……ねえ……」
と言いながらシーナは目をそらした。いかにも何か言いたそうな態度に、少し純一は苛立ちを覚える。
「二人はここにいて楽しくないんですか?」
ティトとシーナは目を見合わせた。
「お前がそこまで望んでここに来てるのかわからないくらいにはな。大体お前、家も名前もあるのに何が不満なんだ?」
水を飲み干したティトが、純一にそう投げかけた。
「名前くらい、あなたたちだってあるでしょう?」
「いや、スギザキとかあの二宮みたいな、苗字ってやつはないぞ」
「何者かになりたいって言ったけど、その名前があるだけで十分じゃないの?」
ティトとシーナは、口を揃えて言った。
「みんなにはないんですか?」
ティトが、「へっ」と鼻で笑い、鋭い目を細める。そうすると、ノウムになったときの瞳と同じだと純一は思った。
「昔は番号で呼ばれてたからな。この名前は被検体になってから付けられたんだよ」
純一はしまったと思った。自分にあって、この研究所で育った者にないものがあるなど、想像すらしていなかったのだ。
しばしの沈黙の後、純一はマレのほうを見た。
「マレ……さんは、どうして被検体になったんですか?」
「言う必要あるの?」
紫の瞳を純一に向けてそう言い、彼女は黙々と食事に戻った。
「いや、あの狼の姿……本当にすごかった。感動して、僕もああなりたいと思ったんです」
純一は諦めず、自分の憧れを口にし続けた。それは会話ではなく、一方的に感想を述べているだけだ。
「やめときな。マレはそういう馴れ馴れしいのはあんまり……」
というシーナの声も、耳に入らなかった。
「宇宙に行ったら何がしたいとか……目標はないんですか?」
次の瞬間、マレは純一の肩を掴んで引き寄せると、顎に鋭いものを突きつけた。その正体は、手袋の先端から飛び出した爪だ。
「私には構わないで」
そう言って純一から手を放すと、マレは空になった食器を持ってその場を立ち去った。
「あーあ」
この日の食事の時間は、その後、誰も一言も発することなく終わった。
ケージ内に用意された個室に入ってすぐ、純一はベッドに倒れ込んだ。一人になった瞬間に一日の疲れがどっと湧いてきて、へばりつくような睡魔に襲われた。ほかの部屋と同様に真っ白な室内は無機質で、普段なら落ち着かなかったのかもしれないが、今日ばかりは気にならない。
翌日、変異室に純一と三人の被検体が集まり、コクーンとノウムに関する講義が開催された。
「二宮さんは忙しいから、俺がお前らの見張りだ。ちゃんと教えてやれよ。あと、喧嘩すんなよ」
タンは、食堂で爪を突きつけられた純一の姿を見ていたらしい。
「はいはい。お前がヘマこくと俺たちにも迷惑がかかる。ちゃんと飛べるようになれよ」
ティトが目を細める。
「―わかってますよ」
純一はムッとしたが、飛べないのは事実だ。
「最初にノウムになったときのことは、どこまで覚えてる?」
そうシーナに言われた純一は、記憶を遡るが、明瞭な記憶は少ない。
「あまりよく覚えていないですね。はっきりしているのは、コクーンに入って溶けたのと、地面に叩きつけられたことだけです」
ティトがうなずいた。
「俺たちはあのコクーンの中でバラバラに溶かされて、ノウムの姿に再構成される。何も考えずに変わると、体は再構成されても意識がバラバラのままだ」
「だから、まず大切なのは、コクーンに入るときは、考えを一つにまとめておくこと」
ティトの説明に、シーナが補足した。
純一の先輩たちはそう語ったが、思考の統一は、言われて実行できるほど簡単なものではない。講義の後、純一はコクーンに入れられ、二度目の変異を遂げることになった。
「飛ぶ……とぶ……と……ぶ……!」
純一は、溶けていく自分の体に意識を奪われないよう固く目をつぶり、溶けつつある口でそう連呼した。
すると、ノウムとして再構成された純一は、以前よりもやや思考が明瞭な感覚があった。起き上がり、飛び乗ったコクーンの縁をしっかりと掴めたのは、完全ではなくとも、四肢の末端まで感覚が行き届いている証拠。それは、大きな前進だ。
続いて、飛べるかを試す。……人の体にはない大きな翼を広げ、振るい、飛び立つ。
足の先が、コクーンの縁から離れた。
(できた!)
そう感情が大きく動いた瞬間、純一が編み上げた意識は一気にほつれてしまい、以前と同様に墜落してしまった。
「今、一瞬だけど飛んでたな!」
コクーンから出た純一に、テトラオキシンを打ち込みながらタンが言った。
「―飛べましたか……」
純一は、数秒間滑空していたらしい。だが、飛び立つことに無我夢中だったため、その記憶はない。
「あれをずっと繰り返せば、飛べる。簡単な話だ!」
「繰り返せればな」
タンの前向きな意見に対し、小声でティトが付け加えていたのも、聞こえていた。
純一は、ティトとシーナの横で話を聞いていたマレの反応が気になり、その姿を探した。だが、既に彼女は変異室を出るところで、青白い髪をなびかせる後ろ姿しか見ることができなかった。
続きは毎週月・木曜に順次公開予定です!(祝日及び年末年始を除く)
日程は公開リストよりご確認ください。
『美術商ローラと家路を急ぐ青年』はこちらに掲載しています。
読者投票
読者投票は以下からご参加ください。ぜひお気に入りの作品に投票をお願いします!
読者投票はこちらから※締切:2024年1月25日(木)23:59まで
※回答は1人1回までとさせていただきます。