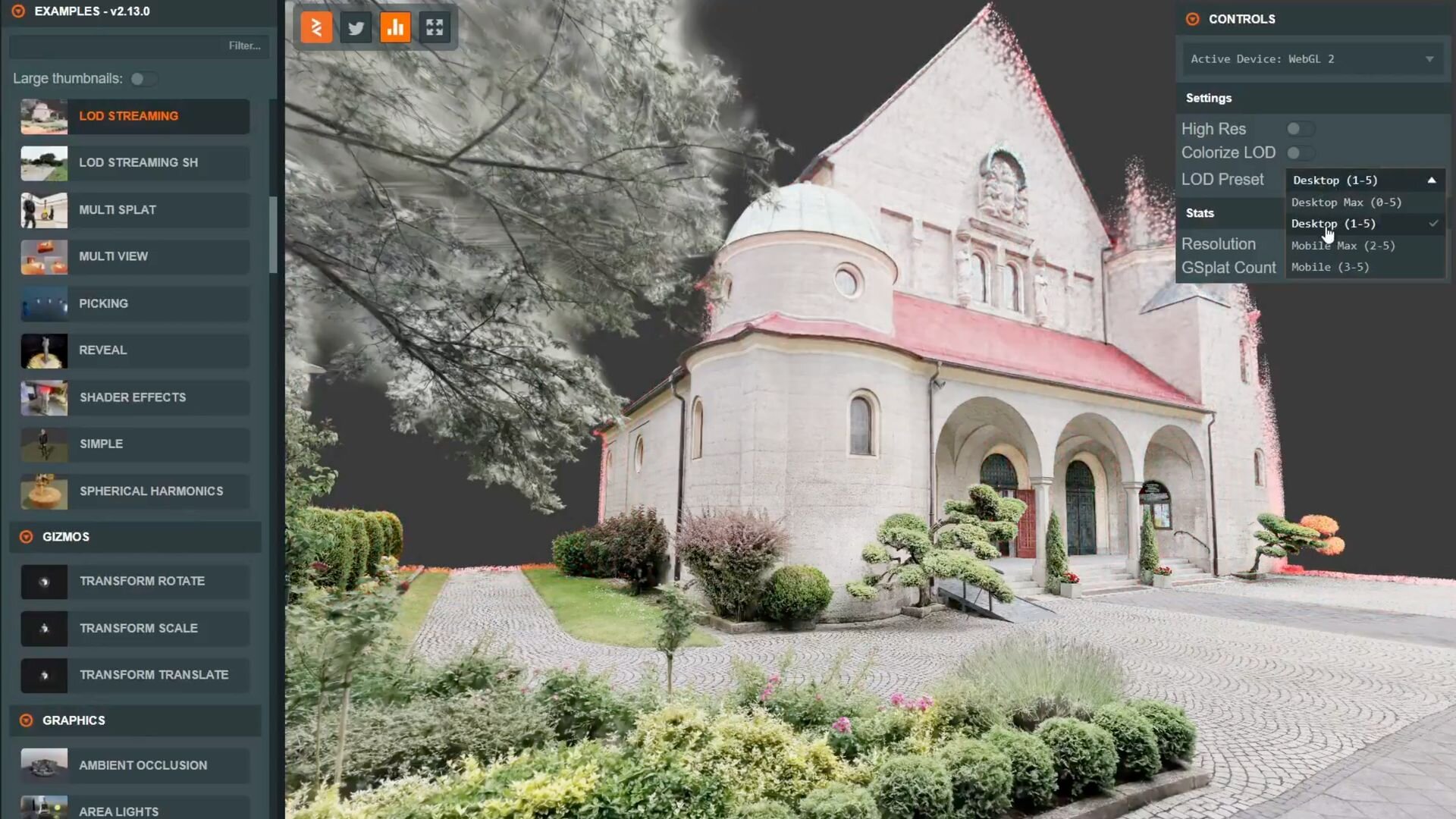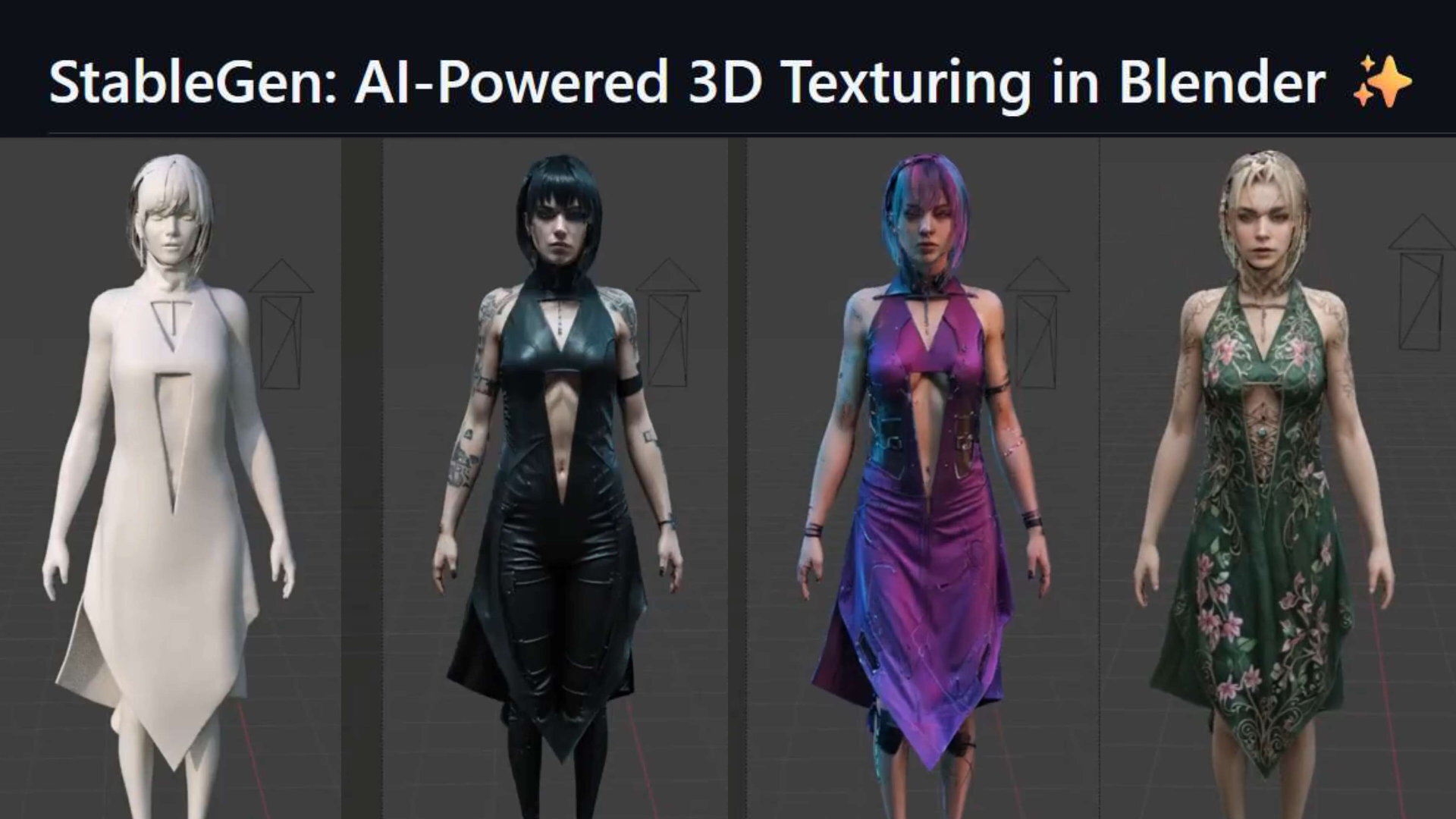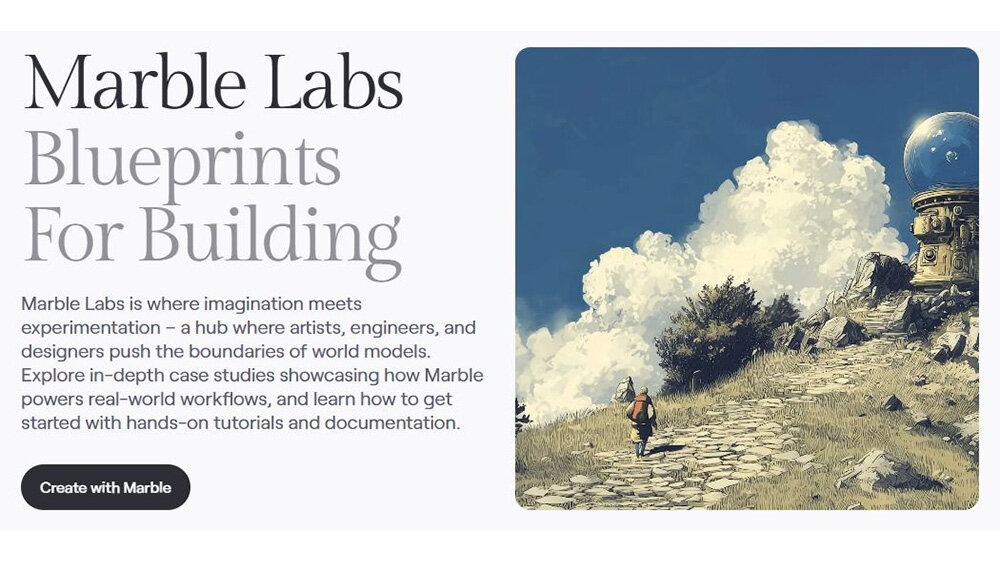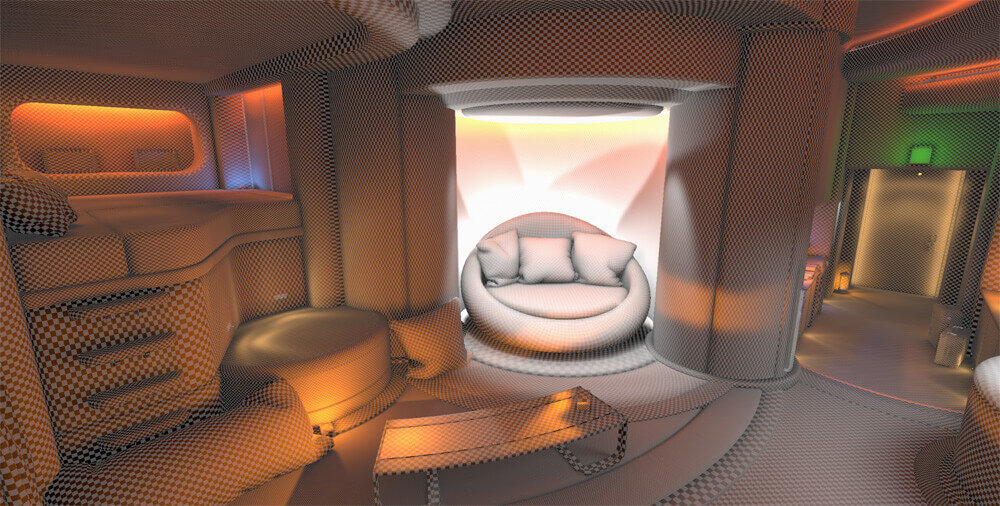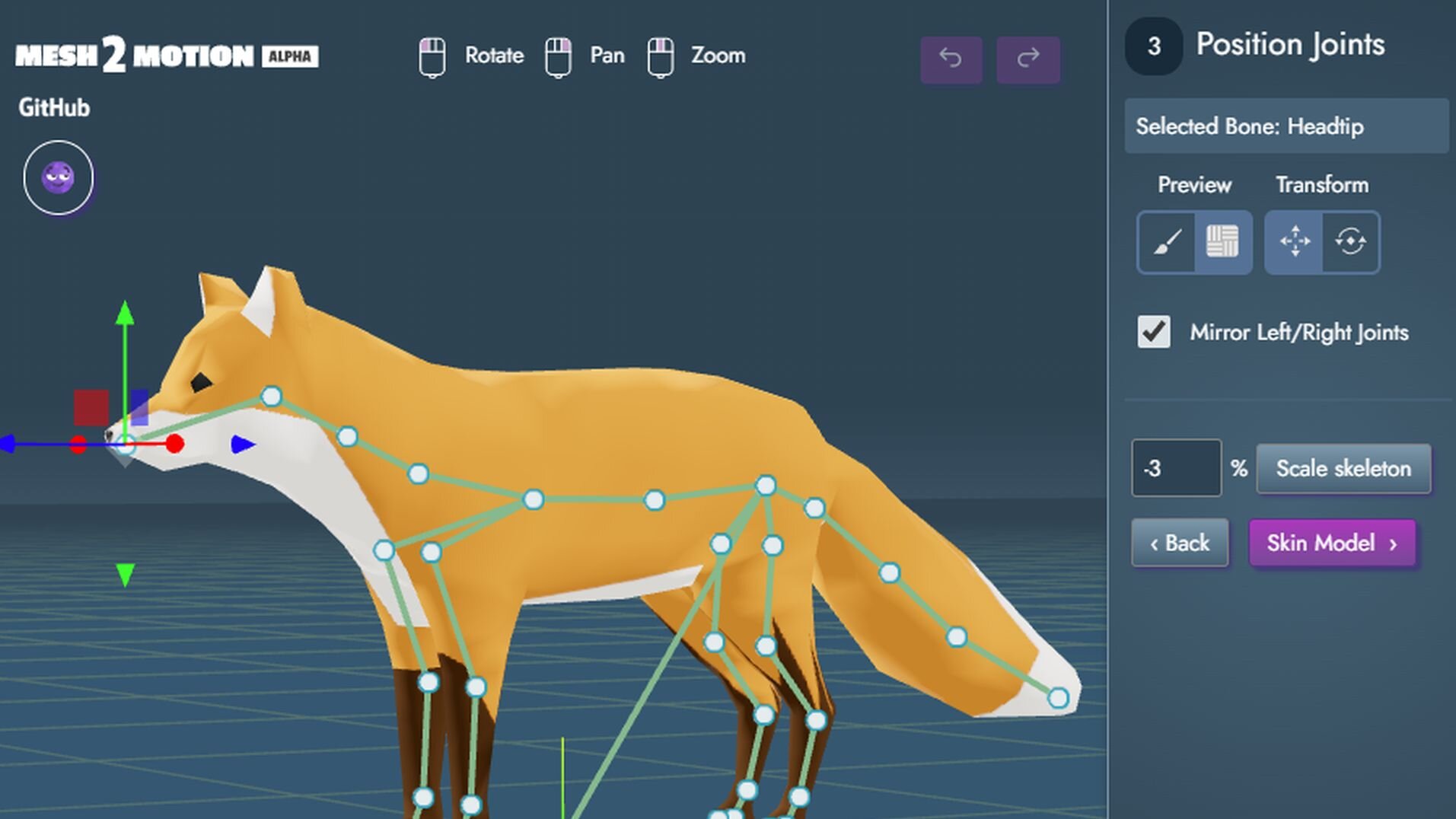「第1回 CGWORLDノベルズコンテスト」では、受賞候補2作品を選出し、CGWORLD.jpにて各作品を全12回にわたって掲載いたします。その後読者投票により各賞を決定し、それぞれ書籍として刊行する予定です。
「CGWORLDノベルズコンテスト」概要
第1回 CGWORLDノベルズコンテスト

■今後の予定
12月8日(金)〜:CGWORLD 305号とCGWORLD.jpで掲載と読者投票スタート
2024年3月頃:書籍時の扉絵イラスト募集
2024年6月頃:読者投票&扉絵イラスト結果発表
本文
六・変貌
森の中、木々の隙間を蒼い影が駆け抜けていく。
外の世界を駆け抜けていくのは、この影にとって初めてのことだ。彼女は緊張、恐怖、不安、後悔といった感情が胸中に渦巻く中、肌を撫でながら軽やかにすり抜けていく風の感触に、どこか心地よさも感じていた。
なぜ、こんなことをしてしまったのだろう。
そんな思いが浮かび上がってきたとき、影はぴたりと動きを止め、六本の足を持つ、美しい狼へと姿を変える。
葉と葉がこすれ合う音と、鳥たちの鳴き声に耳をすませながら、狼は考えた。
確かに、みんなのことを思えば、あのまま従う以外に道はない。それが正解だった。今までだって、どんな選択の中からも正解を嗅ぎ取り、選んできたではないか。だが、今回は、どうしようもなく―自分の願いを諦めきれなかったのだ。行きたくないと言えば、きっとみんなは抗議し、辞退させてくれただろう。そうすれば、自分が子どもの頃から、お金だけを浪費すると周囲から言われ続けていたこの研究は、今度こそなくなっていたかもしれない。
だから……だから、引き受けることにした。
さっきまでは、そう自分を納得させたはずだった。だが、中庭から空を見上げたとき、空を昇っていく一筋の雲が目に入った。この前見に行った、宇宙港から出る定期便だったのだろう。
その瞬間、心の奥底から、沈めておいたはずの夢と願いが、引きずり出されてしまった。
狼は、前足に埋め込まれたシードを噛みちぎり、中庭の外壁を駆け上がっていた。
マレは外の世界のことを、施設の中の資料と、この間の外出でしか知らない。
今の状況で脱走したところで、何の解決にもならないことくらいは理解している。なのに、ISCの申し出を断る以上に、みんなに迷惑をかける事態を引き起こしてしまった。
そのことを考える度に、マレは胸の底に、じんわりと痛みが生じるのを感じていた。
初めてコクーンに入った日、彼女はもう一つの姿―ノウムと、青白い髪と体毛、そして鋭い爪を手に入れた。そのため、彼女はずっと好奇の目を向けられ続け、そんな視線への嫌悪感は、ここでない場所……宇宙への憧れへと変わっていった。
「無理はするな。訓練はしてもらうが、自分の体を第一に考えるんだ」
そう二宮は言ったが、長く過ごす中で、彼は自分を労っているわけではなく、マレが才能を発揮した先にある、研究のさらなる発展に関心があるのだと、感じるようになった。
マレは、宇宙へ行くまで自らの心を動かさず、自身の性能を追求することだけに集中しようとした。しかし、心の水面は、何かが落ちてくると、必ず波紋が生じる。機械のように何者にも心をかき乱されずに目標に進みたかった彼女にとって、それは嫌悪の象徴だった。
そんなマレの心に入ってくる者の中でも、訓練を共にする被検体たちだけは、彼女の心に新鮮な感情をもたらしてくれた。何かと自分を気にかけてくれるティトとシーナ、宇宙へ行く気持ちを共有できた純一……。
最初は自分のことを気にかけてくるのを鬱陶しく感じることもあったが、同じ境遇の者たちと共に過ごす中で、初めて誰かと感情を共有できた。心を動かされるにしても、そうした体験は彼女にとって得がたいものになっていった。
(そうだ……行かなきゃ)
マレは、純一の顔と共に、改めて自分の憧れた宇宙のことを思い出した。
(宇宙港に行けば、なんとかなるかもしれない……)
この孤独な狼がそう判断したのは、前足の噛み傷による失血で、判断力が落ちていることの何よりの証明だったかもしれない。
森を飛び出すと、何人かの人間とすれ違った。
「……!」
誰もが悲鳴を上げている。マレは、今更誰からどんな声をかけられようとも、止まるつもりはなかった。
「動くな!」
しばらく走ると、正面に眩い照明が点き、マレの目がくらむ。マレは鋭い目を細めつつも、駆け抜ける。
次の瞬間―マレは全身を細く鋭い糸に貫かれるような痛みに襲われた。六本ある足の筋肉が弛緩していくのがわかる。
そして、彼女の意識は暗転した。
「今日はここで待機だ」
そう言って、タンは純一の部屋の扉を閉め、ロックした。純一は、まだ事態の全貌を把握していない。
だが、これだけはわかる。マレは、おそらく生まれて初めて心を砕いて決心し、それでも夢には抗えず、あのような行動に出たのだろう。
「なんで言ってくれなかったんだ」
そう呟きつつ、純一は予算が施設に下りると聞いた瞬間にマレが表情を変えたとき、「僕らのことは気にしなくていい」という言葉がかけられなかったことを、深く後悔していた。
落ち着かず、ベッドから立ち上がって部屋の中を動き回っては座り、また立ち上がるということを繰り返していると、ドアをノックする音がした。
「―どうぞ」
「よお」
ティトだ。
「どうやって来たの? ティトの部屋だってロックされてたでしょ」
「俺を部屋に連れてくやつのポケットから拝借したのさ」
そう言って、ティトは懐から所員用のIDカードを取り出した。
「マレのこと、わかったぜ。あいつら、廊下で話してた」
「本当に!?」
純一は、思わず立ち上がった。
「ああ。さっき捕まって、連れ戻されたらしい」
ティトは純一の部屋にある椅子に座りながら、そう答えた。
「怪我とかしてないかな」
純一は、脱走を考えたことなど一度もなかったため、それを実行した者がどのような処遇を受けるのか、想像がつかなかった。
「さあ……」
「また、会えるかな?」
ティトが首を振る。
「わからん。あいつ、シードを壊して逃げただろ? 人の姿に戻れるかも……」
「戻れるよ、きっと……」
純一がそう答えたのは、彼の勝手な願望だ。ティトもそれをわかっていたが、あえて否定はしなかった。
「ん、そうだな……」
彼は立ち上がり、部屋の扉へと向かっていく。
「まあ、それだけ伝えときたかったんだ。どうせ明日の朝には伝えられたろうが、気になって、夜も寝れないんじゃ気の毒だと思ってな」
「ありがとう。でも、二人のほうが付き合いも長いし、心配なんじゃない?」
純一が半端な返事をする。
「まあ、もし次に会えたら、気の利いたことでも言ってやれよ」
ティトがそう言って改めて部屋から出ようとすると、彼の目は床に落ちている“何か”を捉えた。
「これ……お前のか?」
ティトが拾い上げたのは、黄金の小さな羽毛だ。
「知らないけど、枕から出てきたんじゃない?」
「いやいや、こんな色はしてないだろ」
部屋の照明を反射するその色に、ティトは見覚えがあった。ノウムになったときの純一と、同じ色をしているからだ。
「まあいい……何かあったら、検査してもらったほうがいいぞ」
翌日、ティトの言っていた通りに、タンからマレの脱走事件が“解決”したと伝えられたが、マレが姿を見せることはなかった。廊下ですれ違う二宮に質問をしても、
「お前たちに伝えられることは何もない」
と言う。所員も同様だ。
「早く自室に戻れ」
タンも、何を聞いても冷淡に答えるだけになり、その態度の豹変は、純一たちに少なからずショックを与えた。
廊下には、以前はいなかった装備を固めた警備員が立つようになり、すれ違う度、鋭い目を被検体たちに向けてくる。
過日の脱走事件により、被検体に対する警戒心が強まったことは明らかだ。だが、残された三人の被検体は、マレの心情を理解していたがゆえに、彼女を恨もうとはしなかった。
いつも通りに訓練の日々が始まると、先日ティトが発見した羽毛の正体が発覚した。
「逆流が起きたか……」
二宮の声に失望の色が混じっていたのを、純一は感じていた。訓練を終えた純一の左肘から、一本の羽毛が伸びているのをめざとくタンが発見し、報告したのだ。
「そう……ですか」
純一のシードは、被検体の肉体に逆流が起きない改良を施した新型だ。実際、それまで純一の肉体には何の変化も起きていなかったが、それは従来よりも逆流が遅延していただけのこと。二宮たちは、純一から採取したデータを基に、シードを再設計しなければならない。
「別の被検体を用意して、試しますか?」
「いや、適合者を選ぶようではこれまでと同じだ」
そんな会話をする二人と自分の間には、とても大きな溝ができていると、純一は感じた。
通常、逆流は一定まで進むと、止まる。マレ、ティト、シーナ、そしてタンがそうだった。だが、純一の身に起きた逆流は止まることがなく、変化をもたらし続けている。コクーンに入る度、左腕を中心に羽毛の範囲は広がっていき、その様子を二宮たちは逐一記録していった。
「ねえ。それ、大丈夫なの?」
「うん。みんなと一緒になれたみたいで……ちょっとうれしいんだ」
シーナが心配そうに声をかけると、純一はそう言って左手を動かす。風で黄金の羽毛が揺らめいた。
そのような楽天的なことを純一が言えたのも、わずかな期間だけだった。次第に、純一の肉体は、毎晩巨大な虫が皮下を這い回るような激痛に襲われ始める。
「君はもうコクーンに入るな」
ある朝、二宮はやつれた顔の純一にそう告げた。
「でも、宇宙に行くときのために、万全の状態で……」
「その姿が万全の状態だと思うか?」
純一は、そう言う二宮の視線の先にある自分の左腕を見た。万全でないのは、自分にもわかっている。純一の左腕は、肩からその指先まで、細長く鋭い、鳥の翼へと変化する途上にあった。
二宮たちによってシードの活動を抑制する薬剤を投与されても、純一の体が元に戻ることはなかった。彼らの技術の結晶であるコクーンに関しても、今回ばかりは望んだ結果をもたらすことは不可能だ。コクーンの機能は、あくまでシードに記録された通りの姿に肉体を再構成するのみ。シードが肉体の情報を改変してしまった以上、ノウムとしての姿と、ノウムと人の中間の姿を行き来することしかできない。
「―僕は、どうなるんですか?」
純一が二宮を見る。その瞳は、緑色の虹彩を有していた。
「しばらくは経過観察だ。抑制剤の投与量を増やしてみよう」
と言いながら、二宮は別の資料に目を通している。もう二宮の関心は、純一には向いていない。
その後、足の骨格や筋肉にも逆流が起き始めたことで、純一はまともに二本足で立つこともできなくなり、部屋で食事が運ばれるのを待つだけの日々が続いた。
「こいつと二人だけだとつまんないからな。とっとと戻って来いよ」
「それはこっちのセリフだよ!」
というやりとりを、タンに頼み込んで、部屋に押しかけたティトとシーナが繰り広げている。純一にはその優しさがうれしかったが、同時に二人の気遣いに、事態の深刻さを実感させられていた。
「起きろ」
純一はタンの冷たい声で目覚めた。
声のした方向を見ると、タンたち所員が担架と共に部屋の入口に立っている。彼らは純一を担架に縛り付けると、そのまま部屋から連れ出した。
純一はしばらく視界を流れていく無機質な天井を眺めた後、エレベーターへと乗せられた。呻き声のような作動音を響かせながら、エレベーターは地下へと向かっていく。
扉が開くと、担架に横になったままの純一には、大小さまざまな金属のパイプで埋め尽くされた天井が目に入った。顔を起こすと、長い廊下の左右にガラス張りの部屋が並んでいる。
「ここに……入るんですか?」
顔を元の位置に戻し、天井に向かって呟くと、横にいるタンが答えた。
「ああ。ここは上では処置しきれない被検体用の部屋でな。つい最近までは使うこともなかったが」
担架が廊下の奥へと進んでいく。純一は不安を感じたが、拘束されているため、動けない。天井か、視界を通り過ぎていくガラス張りの部屋を眺めることしかできなかった。
そのとき、彼の視界に、青白い塊が映った。
代わり映えのない景色を見せられ続け、鈍化しつつあった純一の意識が、一気に明瞭になった。それは、青白い塊ではない。うずくまった六本足の狼、マレだ。
「―マレ?」
声はガラスに跳ね返り、廊下に響いていく。
「マレ! マレだろ!?」
狼はうずくまったままだ。
「そうだ」
純一の隣に立つタンが、代わりに答えた。
「どうしてこんなところに……彼女を戻してやれないんですか!?」
「ノウムの姿で過ごし続けて、不調が起きないかを試しているんだ」
タンの、無機質な声が響く。
「なんでそんなこと……」
「あれを見てみろよ」
タンが指を差し、純一は改めてマレの姿を見た。目覚めた際に暴れたのか、彼女の体は傷だらけで、艶を失った蒼い毛が床に散乱している。
「あんな状態じゃ、ISCに引き渡しても突っ返されるだけだからな。もうあれには価値がない」
「マレを物みたいに言うな!」
タンは肩をすくめた。
「まあ、彼女にもお前にも、エサは出してやるから心配するな。食べられるうちはな」
純一は、マレの隣の部屋に運び込まれていった。
続きは毎週月・木曜に順次公開予定です!
日程は公開リストよりご確認ください。
『美術商ローラと家路を急ぐ青年』はこちらに掲載しています。
読者投票
読者投票は以下からご参加ください。ぜひお気に入りの作品に投票をお願いします!
読者投票はこちらから※締切:1月25日(木)23:59まで
※回答は1人1回までとさせていただきます。