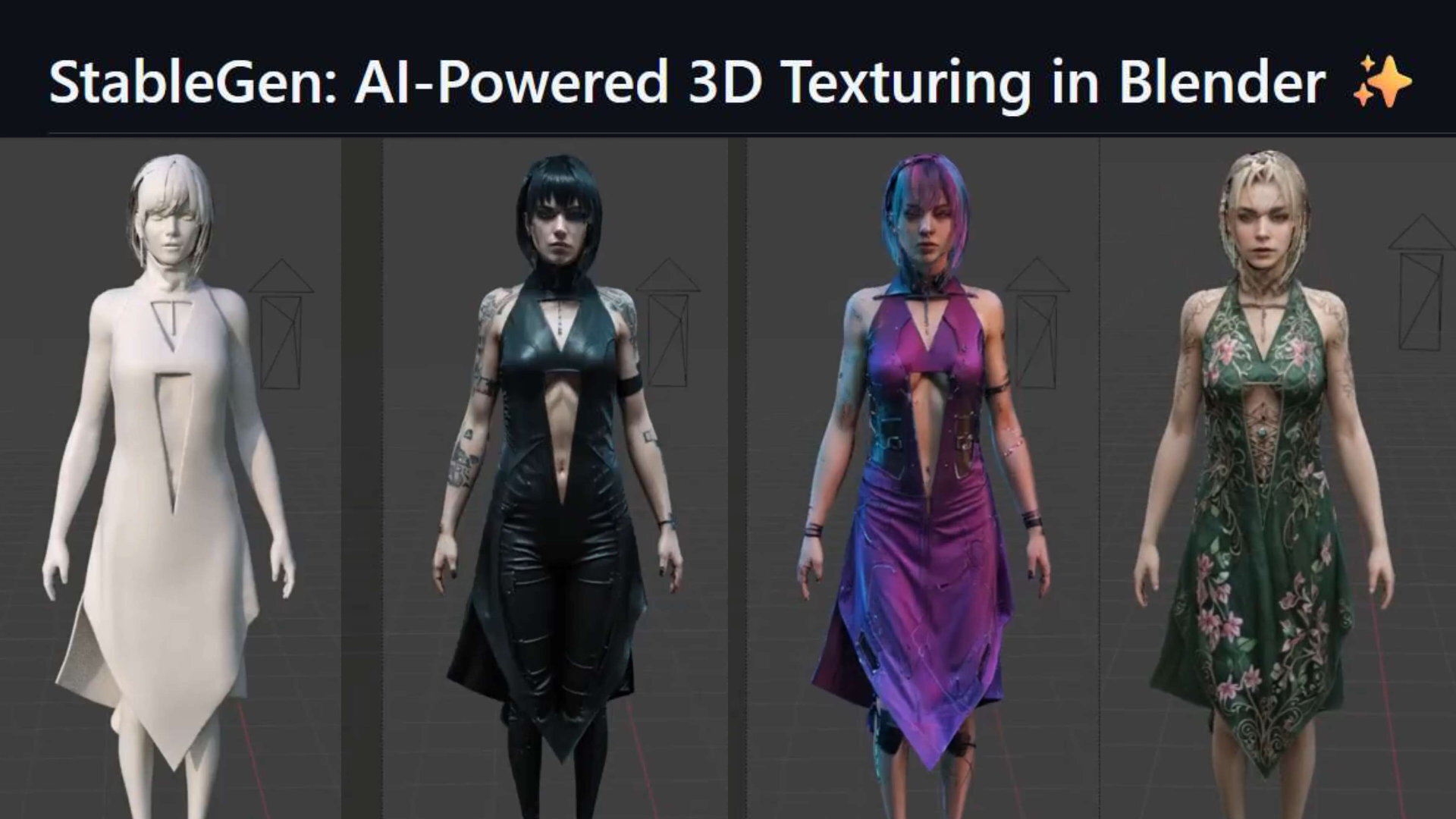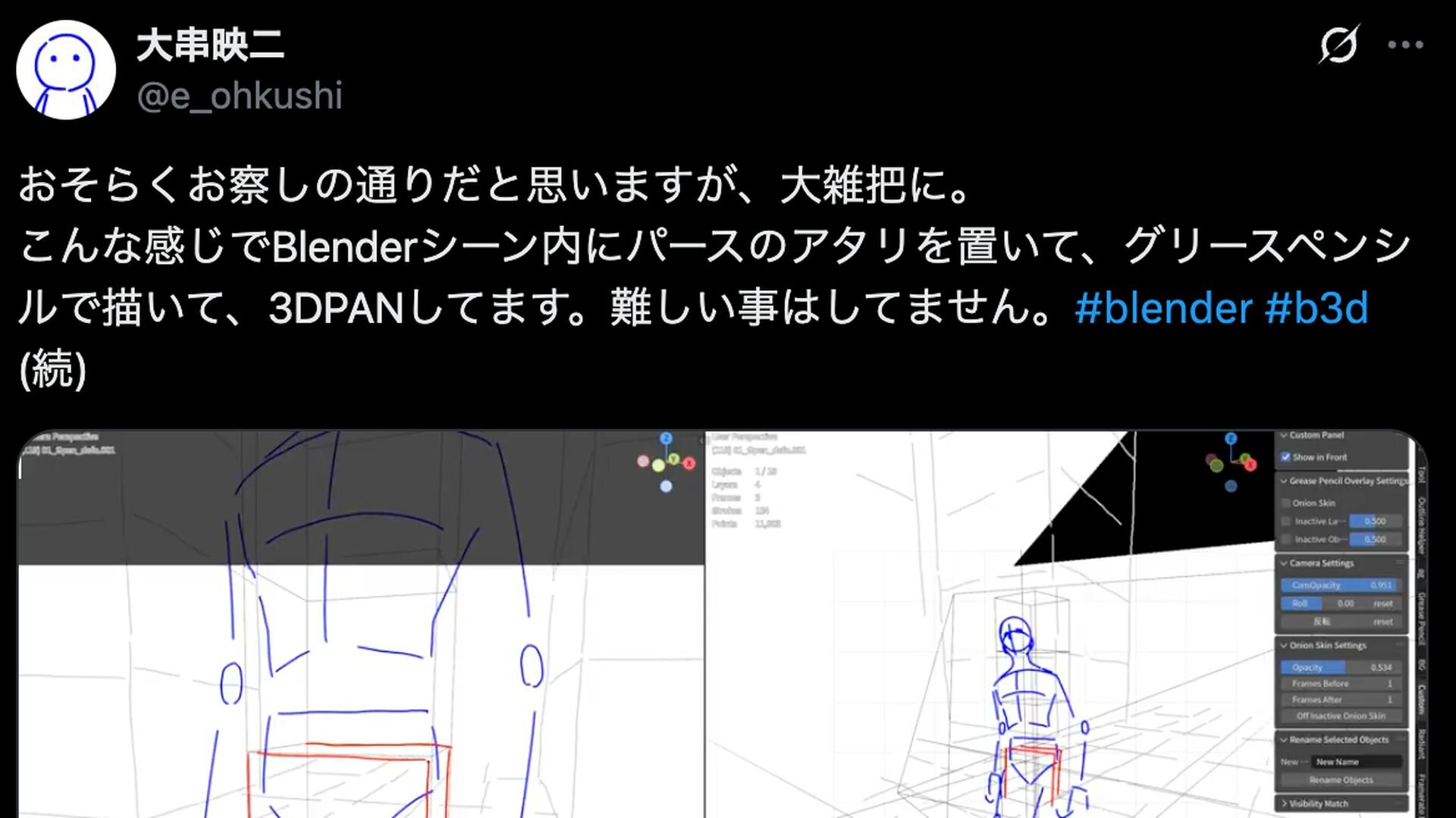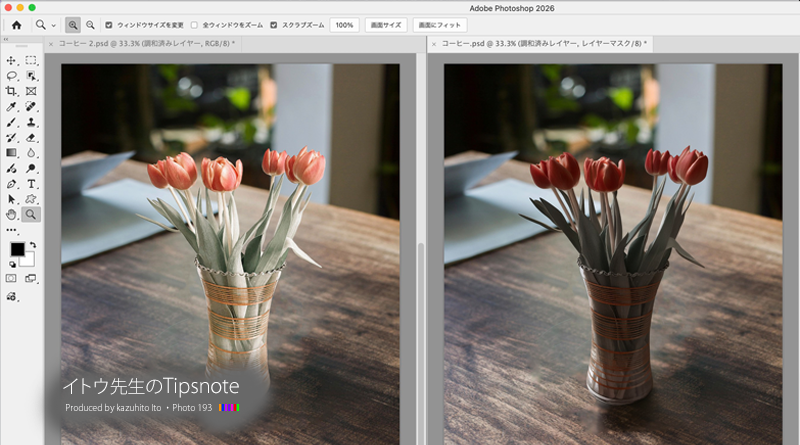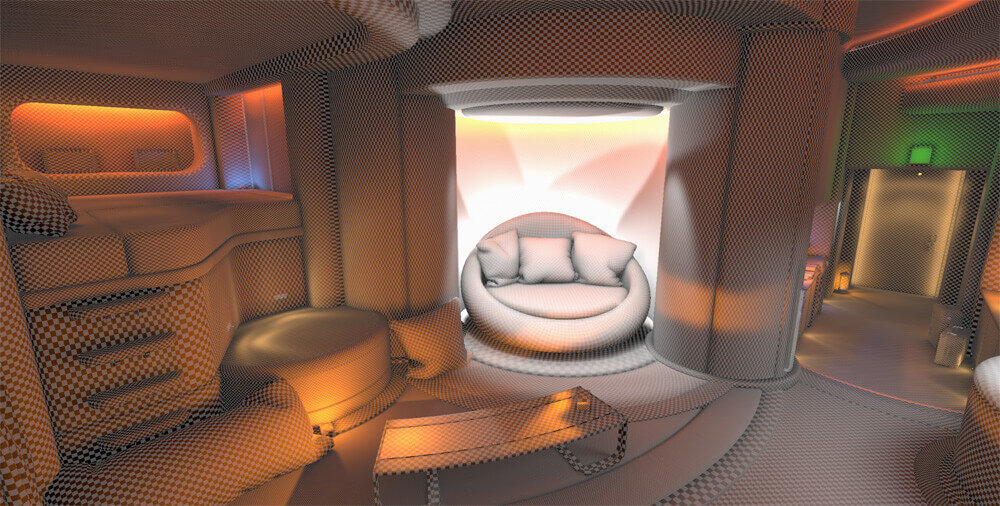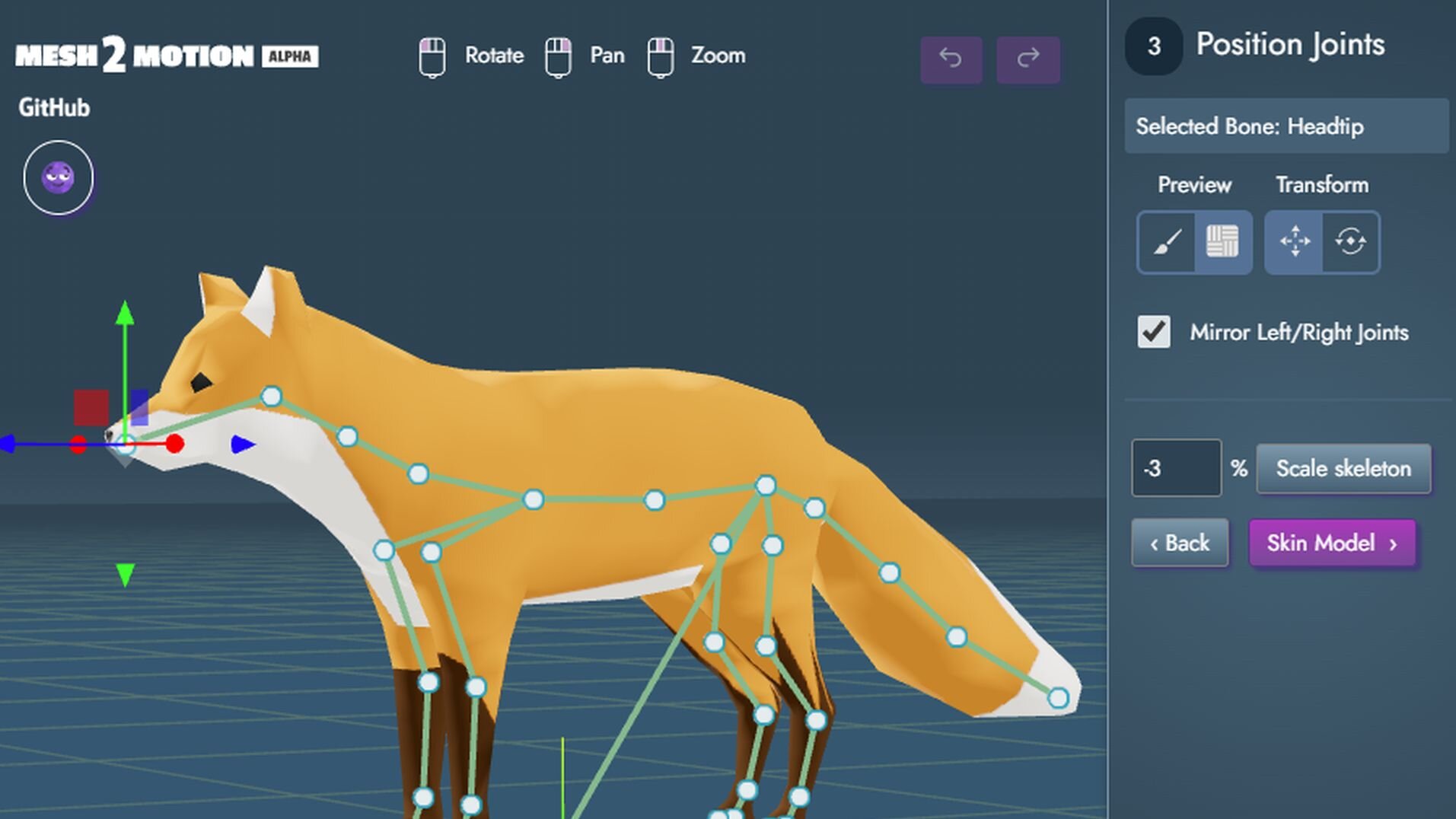「第1回 CGWORLDノベルズコンテスト」では、受賞候補2作品を選出し、CGWORLD.jpにて各作品を全12回にわたって掲載いたします。その後読者投票により各賞を決定し、それぞれ書籍として刊行する予定です。
「CGWORLDノベルズコンテスト」概要
第1回 CGWORLDノベルズコンテスト

■今後の予定
12月8日(金)〜:CGWORLD 305号とCGWORLD.jpで掲載と読者投票スタート
2024年3月頃:書籍時の扉絵イラスト募集
2024年6月頃:読者投票&扉絵イラスト結果発表
本文
「みんな、よくやってくれた」
その夜、食堂には被検体から所員まで、この施設に常駐する者たちが集まっていた。それぞれが思い思いの姿勢で料理が並ぶ席に座り、前に立つ二宮に注目している。
「今回の内覧会の反応は上々だ。きっと、数週間のうちにみんなにもよい報告ができることだろう。我々はまた一歩、未来へと前進した」
食堂内で拍手が起きると、二宮は手で場を静めるようなジェスチャーをした。
「いや、拍手を受けるべきは、私ではない。来るべき人の姿を提示してくれた、被検体の四人に対してだ。ティト、シーナ、マレ、純一……ありがとう!」
二宮が大きく拍手し、続いて食堂中に拍手と歓声の音が充満していく。
「明日からまた忙しくなる」
拍手の音が徐々に小さくなってきたタイミングを見計らって、二宮が再び声を発した。
「少しの間の休息だが、どうか互いを労ってくれ……乾杯!」
ティトは早速鶏肉をほおばり始めた。
「ま、このくらいはやってもらわないとな」
今日だけは、ノウム専用食以外のものを食べる許可が下りていたのだ。もっとも、四人はつい最近も外の食事を食べていたが。
「ひとまず無事に終わって、ほんとよかった!」
と向かいに座っているシーナが笑うと、隣のマレも静かにうなずく。
「一番歓声が大きかったのは、やっぱりマレだよな」
「ビジュアルが違うからねえ。私たちも、手堅い性能では負けてないと思うけど」
ティトとシーナがマレを見る。
「そ、そんなことないよ。みんな注目されたんじゃないかな?」
マレは助けを求めるように純一を見た。
「そうだね。緊張してたとしても、それを表に出さないのは本当にすごい」
「純一、お前もすごかった。最初はすぐに墜落してたのにな」
「いや、ティトもだけど、みんなのおかげだよ」
と、純一が三人を見渡したところで、二宮と目が合った。
「今日はありがとう」
いつの間にか近付いてきていた二宮が、マレとシーナの後ろに立っていたのだ。
「マレ、少し話がある」
「はい……」
無機質な二宮の声に対し、マレが立ち上がりながら返事をする。短く発した声の震えには、緊張と、少しの期待が混じっているように純一には思えた。
「あいつだけ?」
二人が食堂を出て行く姿を目で追いつつ、ティトがこぼした。
「何の話だろうね。僕ら全員に言わないっていうのは」
「うーん……」
「マレが一人でどこかに呼ばれるとかはあるかも?」
真っ白な天井を見上げながら、シーナが言った。
「どこかって、どこに!?」
「純一、でけー声出すな。あと、座れ」
純一はそう言われて、思わず立ち上がっていたことに気付いた。
「うーん、二宮の研究が認められて、マレだけが宇宙に行く候補になったってことは、あるかもね」
「そういうこともあるの?」
純一は、全員で宇宙に行くのが当たり前のことだと思っていた。
「だってさ、全員を第二波の調査船で宇宙に送りたいっていうのは二宮たちの都合じゃない? 調査船に乗りたい人は世界中にいるだろうし、選ばれた一人が試験的に乗せられることだって、そりゃあるでしょ」
「彼女だけでも宇宙に行けるなら―いいか」
純一の顔に、悔しさと寂しさが浮かんでいたことに、ティトとシーナが気付いたらしい。
「い、いや、あくまで私の想像だからね!?」
「そうとは限らねえって話だよ」
二人はそう言ったものの、黒い靄がかかってしまったような純一の気分は、マレ本人から直接聞くまで、晴れそうになかった。
翌朝、純一はロビーのソファに座り、一人ため息をついていた。
「はあ……」
あの後、結局マレが食堂に戻ってくることはなかった。今日の訓練は休みだが、ロビーにいれば、昨日のように彼女がまたやってくるかもしれない。そんなことをせずとも、直にマレの部屋に向かい、ノックをすればいいのだが。なんとなく、純一はそれができないでいた。
(ここにいたって来るとは限らないし、何やってるんだろうな)
しばらく、純一が床と窓から見える景色を交互に眺めながら時を過ごしていると……
「何してるの?」
背後から澄んだ声が聞こえてきた。
「昨日あれから戻ってこなかったでしょ? どうしたかと思ってさ」
「ここ、私の部屋じゃないけど……」
「はは。ほんとそうだね」
マレが、純一の隣に座り、口を開き始めた。
「―昨日来ていたISCの人が、私を借りたがってるって」
「借りるって?」
「広告塔にしたいみたい。少しの期間だって先生は言っていたけれど……」
うつむくマレを見て、純一は腕を組み、しばし考えた。彼女にとって何が一番よい選択か。一緒にいてほしいからといって、無理に引き留めてはいけない。
「広告塔なら、確実に宇宙に行けるかもしれない」
マレが純一を見る。
「昨日シーナから聞いた話の受け売りだけど……。調査船にだって定員はあるし、僕ら全員が性能を評価されて、乗れるとは限らない。でも、マレだけはコクーンの技術のアピールの一貫として、一人だけ行くとかさ」
一人だけ行くと聞いて心配そうな表情をしたマレを見て、純一が笑った。
「いや、もし今回が駄目でも次があるよ。すぐにみんなで追いつく。不安なのはわかるけれど、ここにいたってそれは同じだからね」
「―そう」
マレが立ち上がった。青白い髪が、風を受けて揺れる。
「ありがとう。考えてみる」
その日の昼食時、マレはティトとシーナにもこの件を話した。
「しばらく食いっぱぐれずに暮らせるんなら、それでいいんじゃねえの?」
その日の食事に困らなければいい、というのがティトの信条だ。そこにブレはない。
「マレが後悔しないなら、いいと思うよ」
そんなティトに対して、シーナは優しげな声をマレにかけた。
「うん。先生に話してみる」
そう答えるマレの顔からは、不安の色が今朝より減っているように純一には見えた。彼女と離れることになるのが寂しくないと言えば嘘になる。
(でも、これでいいんだ)
純一はそう思っていた。
後日、純一たちが応接室に集められた。二宮の横には、高級そうなスーツに身を包んだ男が立っている。
「みんな、もうマレから聞いているかもしれないが……」
二宮がゆっくりと話し始めた。
「この前の内覧会を受けて、ISCの方からマレを広告塔にしたいという話があった」
「初めまして。国際宇宙局の広報担当の如月と申します」
硬質な声が部屋に響いた。
「これまでも何度か訓練の様子を拝見させてもらいましたが、先日は特に素晴らしかった。あなたたちの才能に、局員一同感動しています」
如月と名乗ったその男は、丁寧にゆっくりとお辞儀をすると、それぞれの顔を順番に眺め、マレの顔と、手にはめた長手袋に目をやった。
「あなたには、先日ご挨拶させていただきましたね」
マレがうなずく。
「我々は、彼女を新たに宇宙に挑戦する者たちの象徴として、登用したいと考えています」
先ほどから口では褒めながら、感情のこもっていないその声が、純一には耳障りだった。続いて、如月は、ティト、シーナ、純一を見ると。
「あなたたち三人が宇宙に行っている五年間、彼女には地球の各所を回り、広報活動に協力してもらいます」
と言った。
「五年……?」
マレが小さな驚きの声を漏らすのを、その部屋の全員が耳にした。
沈黙が支配する応接室で、純一の手は、震えが止まらなくなっている。
「彼女が代表として、宇宙に行くんじゃないんですか?」
純一は二宮と如月を交互に見る。二宮は目を背け、うつむいた。
「いや、宇宙に行くのは君たち三人です。ただし、新惑星に辿り着いて成果を挙げるまでには、膨大な時間がかかる。その間、我々は調査隊第三波を送るプロジェクトに向けて地球で活動を続けなければなりません。当然その中には、人々の心から宇宙と我々国際宇宙局の存在を忘れさせないための、広報活動も」
「で、でも、僕らがすぐに惑星開拓に参加して成功すれば、彼女も……」
純一がこのとき言っていたのは、ただの願望に過ぎなかった。
「あなたは第一波に参加していた杉崎夫妻のご子息でしたね?」
「……はい」
「それなら、宇宙旅行にどれくらいの年月と予算がかかるかを、少しは耳にしているのでは?」
純一は目の前が真っ暗になりそうだった。
(そうだ、マレは……)
横に座っているマレを見ると、彼女の顔からは一切の感情が消えている。
「マレ……?」
小さく呼びかけても、返事はない。
「少しの間、彼女と別れるのは寂しいかもしれません。ですが、我々は今後この施設に多大な資金を提供し、研究をこれまで以上に支援し続けることを約束します」
最後に如月がそう言った瞬間、マレがぴくりと反応したのを、純一だけが気付いた。
「―わかりました」
そう返事をすると、マレは部屋を出て行ってしまった。
「では、私はこれで……」
如月がお辞儀をする。
「今日はありがとうございました。玄関までお送りします」
二宮と如月が退室していき、ティトとシーナは、マレを追いかけて部屋を出て、応接室には、純一一人だけが取り残された。
少しして、如月を送り出した二宮が、部屋に戻ってきた。
「なんだ。まだいたのか」
その声はいつもより冷たかった。
「マレを売ったんですか?」
純一は二宮に単刀直入に聞く。今、純一に言い方を考える余裕はない。
「そういう言い方はよせ」
首を振る二宮は、いかにもうんざりとした様子だった。
「でも、それ以外にありますか!?」
純一の声が室内に響く。
「私が心を痛めていないとでも思うのか! 彼女を渡すことは、我々の未来のために仕方のない方法だ。君たちはこのまま訓練を重ねれば宇宙に行けるのだから、それでいいだろう!」
二宮が机を激しく叩いた。
「マレは……」
純一が、二宮の目を見る。
「―マレはもっと傷ついていると思います」
そのとき、純一は左腕の内側に、皮下をミミズが這い回っているような強い違和感を覚え、思わず腕を抑えた。
「どうした?」
「いや、なんでもありません。言いたかったのはそれだけです」
震える足を動かし、純一は廊下に出ていった。去り際に、拳で机を叩いたような大きな音が響いたが、振り返る気にはなれない。
マレが施設を去る日は、一か月後に決まった。
それからというもの、彼女は虚ろな顔で日々を過ごしている。
「大丈夫か?」
と三人は口々に声をかけたが、
「私は大丈夫だから」
としか答えない。どう見ても大丈夫ではない姿でそう言う彼女を見て、三人は、余計に不安を募らせていった。
その日の夜、珍しく純一の部屋に来訪者が現れた。ティトとシーナが、マレの件について話しに来たのだ。
「あれ、まずいよなあ。ずっと地球にいるって話、あいつは聞いてたのか?」
ティトも、仲間の一人が落ち込みっぱなしなことに心を痛めている。
「多分聞いてないよ。僕らやこの施設のことを考えて、引き受けることにしたんだと思うけど……」
「見てらんないね」
シーナが窓から見える月明かりを見つめながら、そう言った。
とはいえ、彼らにできることは虚ろな顔のマレを励ますくらいだ。
「いや、俺に言われてもあればっかりは無理だろ。俺たちは、ISCの支援がなきゃ、何もできない立場なんだからな」
翌日、純一がタンに相談しても、彼は残念そうにうなだれるだけだった。ケージがISCの管理下に置かれている以上、決定を覆すことはできない。
「マレ!」
ある日、訓練前に廊下を歩いているマレを見つけた純一が彼女へと駆け寄る。
「―何?」
「その……気を落とさないで。絶対になんとかなるから」
マレは首を横に振る。
「気にしなくていい。三人だけで、私の代わりに宇宙に行って。みんなと話はできなくなるけど、噂はきっと聞こえてくる。私は行けなくても、それで十分だから」
そう言って、彼女は廊下の向こうへと歩いていく。明らかに本意ではないが、その静かな決意に、純一は何の言葉もかけることはできなかった。
その日の訓練内容は、高温下での耐久試験だった。中庭の温度を七十度まで上昇させ、その環境下でどれだけの時間、意識を保って行動できるかを試そうというものだ。そもそもが集中力を求められるノウムへの変異中、過酷な環境もプラスされるこの訓練が純一は苦手であり、ティトとシーナもこの訓練が近付くとぼやき始める。すでにケージを出ることが決まっていたマレはこの訓練を受ける義務はなかったのだが、彼女が「みんなと一緒にいたい」と希望したため、共に参加することが決定した。
「―ありがとう」
変異室に向かう廊下で、不意にマレが三人に対してそう呟いた。
「なんだよ」
「私たち、そんなお礼を言われることした?」
兄妹二人は苦笑する。
「純一も、ありがとう」
「そんな……」
このときの三人は、当然マレがなぜこんなことを言うかは理解していた。もう何度このように訓練を共にする機会があるかもわからない。だから、伝えられるうちに伝えたいと思ったのだろう、と。
変異室に入ると、最初にマレがコクーンへと入る。
『シードの認証完了。ノウム・シーケンス、開始します』
無機質な音声が、密閉された変異室内に反響する。マレがコクーンにより溶解、再構成されていく様子を、三人は無言で見つめ続ける。
ゲートが開いたタイミングで、マレの変異も完了した。コクーンから出てきたマレは、名残惜しそうに純一たちの方を向いた後、中庭へと向かっていく。その瞬間の、紫の瞳の中に満たされた寂しげな光が、彼女の本心だった。
「ほら、お前らも入って」
タンが三人を急かす。
「俺らも行くか」
ティトとシーナが変異を遂げた後、純一もコクーンの中に横たわり、目をつむった。
―コクーンの中で目を覚ました純一は、ハッチ越しに、所員たちが駆け回っている様子を視界に捉えた。その様子が尋常ではないことは、曖昧な意識でもわかる。だが、聴覚や肉体の組織はまだ完全に再構成されておらず、聞き耳を立てることも、外を見渡すこともできない。
「被検体……01……の位置……!」
「食いち……ぎ……!」
体組織の再構成が進むにつれて、ゆっくりと、外の会話の音量が上がっていく。
ようやく変異が完了し、純一がコクーンから顔を出すと、ティトとシーナと、声の主であろうタンたち研究所員の、青ざめた表情が目に入った。
「被検体01、マレが脱走した!」
所員の一人がそう叫んだ。純一が周囲を見渡すと、地面に、鮮血に染まったシードの破片が落ちているのが見えた。シードには毛が付着しており、それは染み込んだ血で真っ赤になっていたが誰のものかは聞くまでもない。マレだ。
「今日の訓練は中止だ! 変異を解いて部屋に戻れ!」
二宮の声だ。声がした方向を見ると、二宮の顔は、湧き上がる感情を押し殺そうとしているからか、これまで見たこともない、歪な形の表情を見せている。
「マレ!?」
純一は、呆然と空を見上げることしかできなかった。
続きは毎週月・木曜に順次公開予定です!
日程は公開リストよりご確認ください。
『美術商ローラと家路を急ぐ青年』はこちらに掲載しています。
読者投票
読者投票は以下からご参加ください。ぜひお気に入りの作品に投票をお願いします!
読者投票はこちらから※締切:1月25日(木)23:59まで
※回答は1人1回までとさせていただきます。