2020年末に発表され、約2500万回再生(2023年3月時点)を記録したヒカキン & セイキンによる楽曲『光』のミュージックビデオ。この作品のVFXスーパーバイザーを担当した木村俊幸氏は、宇多田ヒカルのMVの数々でVFXを担当したほか、マットペイントや現代美術をリードする存在として知られる。そんな彼がこの10年で新たに力を注いでいるのがアナログの温かみをデジタル表現と融合させる試みだ。驚くべきことに、それをダンボール工作を使うことで実現しているという。もちろん本作でも様々な箇所に効果的に用いられ世界観の構築に一役買っている。本稿ではその制作過程はもちろん、ハートウォーミングなきっかけも語っていただいた。
木村氏によるダンボールで制作された宇宙ステーションのシーンは0:34〜
Hikakin Youtube チャンネル www.youtube.com/@HikakinTV/featured
Seikin Youtube チャンネル www.youtube.com/@SeikinTV/featured

コンセプト・マットアーティスト・VFXスーパーヴァイザー・美術家 岩手県出身。マリンポストプロダクション、イマジカ特撮部を経て独立。美術家としてVFX studio LOOPHOLEを活動の中心とし、コンセプトデザイン、マットアートを用いた絵画的なVFXを打ち出し続けている。VFXと現代美術を結ぶ同ギャラリーでの個展、MATIMシリーズを世界に発信する他、若手作家の展覧会をオーガナイズする。平成ゴジラシリーズ、SPAWN THE MOVIEで早くからデジタルマット画を導入、CASSHERN(第10回 記念 AMD Award ’04Best Visual Designer賞)、映画「ブルーハーツが聴こえる/人にやさしく」ではダンボール宇宙船を単独造形しVFX-JAPAN アワード2017 優秀賞を獲得。
宇宙ステーションをダンボールでつくるVFXのスタイル
CGWORLD(以下、CGW):日本を代表するYouTuberのヒカキン・セイキン両氏のミュージックビデオに、数々の画期的な作品を手がけられてきたVFXアーティストの木村さんが参加するという組み合わせをとても興味深く思いました。まず、この接点はどのように生まれたのかをお聞かせください。
木村俊幸氏(以下、木村):以前にミュージックビデオのお仕事をしたエイベックスのプロデューサーからご連絡を頂いたのがきっかけでした。そのときに「ヒカキンさん・セイキンさんのMVなんですけど……」と説明をされたのですが、僕はYouTuberの界隈に詳しくなく、お二人のことを存じ上げなかったんです。新人アーティストだと思っていて、だとすると作品に携わるには相当な覚悟とエネルギーが必要になるので、保留させていただいていたんです(苦笑)。
CGW:本当ですか!?
木村:それでどうしようかなと迷っていたところ、ウチの末っ子が聞きつけて、「ヒカキンさんって、超売れっ子アーティストだよ!?」とか騒ぎ出して、家内まで出てきて「どれだけ世間から隔離されてるの!?」って呆れられて(笑)。それで慌ててプロデューサーに「ぜひ引き受けます!」と電話したんです。
CGW:(笑)。その段階でお仕事のコンセプトのご説明はあったんですか?
木村:いいえ。「SFっぽくするかもしれない」ぐらいのニュアンスでした。それでZUMI監督とプロデューサーと打ち合わせをすることになり、過去につくったモノも参考としてお見せしたかったので、LOOP HOLE(木村氏が主催するスタジオ)に来ていただきました。そのときはちょうどグループ展を開催していて、絵画とかオブジェとかが所狭しとあって、それをお見せしたとき二人とも「これは普通の会議と違うぞ」みたいな雰囲気になったのを覚えています(笑)。そこで「宇宙ステーションをダンボールでつくるという手もありますよ」と、簡単につくったモノの写真をお見せして軽く話をしたんです。
CGW:なるほど。CG・VFXアーティストとして木村さんにオファーしたのに、いきなりダンボールを持ってこられたら先方も驚くでしょうから。
木村:そういうことです。それで監督に、「手づくり感が満載な感じで」とお見せしたところ「そういうのも面白そうですね」と盛り上がって、それまで考えられていたハイテクSFというコンセプトから、ローテクの切ない雰囲気のものに切り替わったような気がしました。
CGW:やはり初期状態でのコンセプトの共有は重要なんですね。
木村:やはり方向性を示すのは監督ですから、それを受け止めてくれるかどうかはとても重要なんです。以前、2017年の映画「ブルーハーツが聴こえる/人にやさしく」で、ダンボール宇宙船をつくったときも(VFX-JAPAN アワード2017 優秀賞)、下山(天)監督が「この世界観で行ける」と踏みこんでくれたことが大きかったです。
メイキング



ダンボールVFXとマットペイントの合せ技で惑星の地表を表現
CGW:木村さんは本作ではVFXスーパーバイザーという肩書ですが、どんな作業をされたのでしょうか?
木村:まずはコンセプトアートを何枚か描いて、そのあとダンボールアートのコンセプトを作成しました。制作したのはDumn Board Learns (ダンボーラーズ)です("メグロヤツメウナギ"=コンセプトアーティストの富安健一郎氏、"アリンチュ"=特殊造形家の元内義則氏、"コツメカワウソ"=木村氏からなる創作ユニット)。支柱にダンボールやペットボトルとかビールの缶とか付けていくと、巨大なポッドの設定が浮かんでくるんです。そこからさらに、ピザの箱皿を付けたりディティールを足したりしていきました。
CGW:制作プロセスとしては全体の形をつくってから色を塗るような形でしょうか?
木村:そうですね。最初は黒く塗って、その上からグレーで少しずつ掘り起こしていくように塗る感じです。プラモデル塗装でいうエイジングのようなものですね。スペースシャトルが飛ぶ時に表面が陶器のように剥がれますよね? それを今回の宇宙ステーションで表現しています。これはダンボールですから、表面をどう切ったら質感が出るかを考える必要があります。こんなふうにつくっていると、宇宙ステーションの中に300人ぐらいの人々がいるように見えてくるんです。つくっているときはひたすら楽しくて、その熱気を撮影に持ち込んでいくように心がけました。
CGW:ダンボールVFXに携わった方は何人ぐらいでしょうか?
木村:CGディレクターの庄野(晴彦)さん、CGアーティストの丹羽(学)さん、コンポジットの仲西(規人)さん、弊社のアートディレクションの原(満陽子)さんと僕の5人ほどですね。あとは基本的な編集室合成のスタッフは別にいます。
CGW:作業の中で特に大変だったことは何でしょうか?
木村:世界観としてまとめて行くのがやはり大変でした。ダンボールを出すにしても1回だけだと映像の中で浮いてしまいますので、どこかでまた出さなくてはという懸念をずっと抱えていました。ただ、この段階でスケジュールが相当迫っていたので進行をしなければなりません。そこで監督の絵コンテを見せていただくと、得体の知れない敵の宇宙船が登場するとあったんです。「今からこれをCGで1からつくるのは難しいな……」と考えときに、ふと思いついたんです、「ブルーハーツが聴こえる/人にやさしく」の時のダンボール宇宙船を使おうと。
CGW:なるほど。そこでダンボールアートも出せるし、時短にもなるし、まさにピッタリですね!
木村:ちょうどそのとき、友人のアーティスト集団に頼まれて六本木のギャラリーでそれを展示していたので、急いで撮りに行き、2D上でキットバッシュ的なコラージュをして監督にコンセプトとして見せたところ「これ、凄く格好いいですね」とOKが出ました。時間的に3DCGでつくることは厳しかったのですが、画面上であまり動かない巨大宇宙船だったことが幸いし、キャメラマップでつくることができました。この画面は上半分がプロジェクションマッピングで、下半分がマットペイントという、2.5D的なつくりになっています。
木村:実は最初、もうちょっと簡易なCGで済ませられないかなと思ってつくってみたら、監督が「これ、CGじゃないですか」って、もうミニチュアじゃないと物足りなくなっているんです(笑)。それでパーツを付けたり、キャメラマップを入れたりとOKが出るまでつくり続けたという裏話があります。他にも一行が漂着した惑星の地表をマットペイントとキャメラマップ、あとは廃墟の部分のミニチュアをダンボールでつくっています。

宇宙塵や隕石、水槽の部屋/CGIは庄野晴彦による


最新のCGよりも新しい、ダンボールでしか表現できない温かみ
CGW:こうしたミニチュアは撮影も楽しそうですね。
木村:楽しいですよ! 今回の現場はスタッフが若くて、こうしたミニチュアを撮るのも初めてだから、感性もビビッドなんです。ライティングのチーフはミニチュアに対してどちら側から光を当てれば美しいかすぐに理解してくれましたし、それに合わせて操演のスタッフがゆっくり回るようなワイヤーの貼り方をして、キャメラマンがハイスピードで撮影するという連携も見事でした。僕も「この部分が格好良いから良い感じに撮ってよ」と指示を出すと「しっかり当てていきます!」と上手いことやってくれたりして。そういった現場の熱気や盛り上がりを体感できるのは、ミニチュア撮影ならではですね。ダンボールのミニチュアはプラモデルとは違って、段々と形が変わっていくんです。ミニチュアの元内さんはそれにいち早く気づいて、「あと2時間ぐらいしか保たないよ?」とか言ったりして(笑)。

CGW:撮影中に印象的だった出来事は何かありましたか?
木村:感化されたのかどうかはわかりませんが、監督もミニチュアをつくってきたことですね。この映像のなかで、宇宙の敵が攻撃してくるのですが、それは実はヒカキンさんたちの一行にいた仲間の親だったという設定があります。そこで親子のキューブを合わせると一つになって、実は敵味方ではなかったんだというストーリーでした。監督もそのメッセージを映像の中に込めたくて、ご自身でキューブをつくってきたそうなんです。そんな監督の心意気をこちらとしても汲みたいじゃないですか。そこで映像上で10mくらいのサイズにして、宇宙船の目玉の近くに埋め込んでいます。
CGW:そうしたアイディアに対応ができるのも、物理的なダンボールだったからですよね。
木村:そうですね。そういった連携が見事に作品に集約されていて、その意味でもつくり甲斐がありました。あとは裏話中の裏話を言うと、宇宙服を繋ぎ止めるケーブルを発注ミスでつくり忘れていたことに気づいた瞬間がありました。しかも納品当日の朝に。

CGW:それはお疲れ様でした。つくり終えたときの感想はいかがでしたか?
木村:なんというか、「終わったんだな……」と感傷的な気分になって、スンッ……となったんですよね。このプロジェクトの中で、監督も常に一生懸命でした。さっき言ったようにキューブをつくってきたり、グリーンバックでは監督本人が転がって芝居付けをしたりと、自分できちんと伝えようとする姿勢を見せてくれたんです。

木村:そういったクリエイティブな精神が最高でした。それはヒカキンさんたちもそうで、走っているシーンはウォーキングマシーンとの合成なんですけど、そういう場面がいくつもあるんです。普通であれば疲れて機嫌が悪くなって当然の状態でも、彼らは僕らの撮影を見て「すごい出来映えですね!」と、率先して現場を盛り上げようとしてくれました。宇宙服のシーンだって、吊るとなると結構な負担がかかるのですが、そこでも彼らが頑張っているのをみると、僕らVFXチームも「頑張っていこうぜ!」という気にさせられますよ。僕は最初に言った通り、YouTuberの界隈のことを知りませんでしたが、彼らは「新しいメディアでやっていくんだ」という明確な意識を持っていたんだなと、振り返って思います。自分の存在や居場所に真剣だという意味において、今ここにしかないダンボールのミニチュアとも通ずる部分があるのではないかなと感じました。いつかまたお会いして、同じチームで映画とかつくってみたいですね。そのときはまた、さまざまな素材を使って、全力で臨みたいと思います。

CGW:最後にお聞かせください。こうしたダンボールを使ったVFXのような、実際の物を使って表現することの魅力を木村さんはどのように捉えていますか?
木村:ちょっと昔話をすると、僕がダンボールVFXを始めたきっかけのアイテムは、妻が結婚当初にダンボールと紙パックでつくってくれた座椅子でした。当時はそれに座ってちゃぶ台で飯を食っていたんだけど、時が流れてそれは家の片隅に追いやられていた。それを最近になって見つけたんです。そのときに、なぜか胸を打たれましてね。何度も敷かれて、ひん曲がったりよじれたりしているけれども、窓辺に持っていて見つめていると、段々と宇宙のカーゴに見えてきて、「表面のグシャとなった感じはCGではとても無理だな」とか「この凹んでいる表面のライティングは大変だな」とか、それを見ながらメモ帳にスケッチしてる自分がいました。それが、先ほどから何度か名前を出している「ブルーハーツが聴こえる/人にやさしく」のとき。

CGW:では、近年のダンボールVFXでの創作活動はそこから。
木村:そう。それまではCinema 4Dで宇宙船の外観をつくっていたんですが、全部やめてダンボールとゴミをくっつけ始めて、何遍もテストをしていきました。やがて出来上がり、朝方4時半ぐらいかな。電灯1つを太陽に見立てて付けてみたところ、会心の出来に仕上がりました。「まさにこのライティング、このディティールだよ!」って、もう神様に感謝したくなりましたね。その喜びを、しばらくご無沙汰していた川北紘一さん(主に平成期の『ゴジラ』シリーズの特技監督)にお伝えしようと連絡をとったら、お亡くなりになっていました……。結局、送れず仕舞いだった後悔は残りつつも、「また何かやってやろう」という気持ちが残りましてね。あれから10年。来年こそはの繰り返しで時が経っていた。それと同時に「クリエイティブって何なんだろう」みたいなことを考えて、最新のUnreal Engineを使っていると、「忘れないでね」と後ろから肩を叩く声がするのが、アナログのVFXでした。正直に言えば、僕は特撮から逃げてきた人間でした。20代のときにCGと出会って、従来の特撮とは違う世界が見えて、どんどん新しい世界が拓けてきた。そうやって逃げてきたのに、今はかつての特撮が持っていた「荒ぶる何か」に向かってフィードバックしている自分がいる。「これって何なんだろう?」と、自分でも思うんです。
CGW:アナログにしか出せない”何か”があるわけなんですね。
木村:そういう自分のなかでのクリエイティブの流れみたいなものがあって、誰からも認められないよく分からないものと合体し始めて、違うものになったりする。答えは分からないんだけど。今は宇宙船の形をしているけれども、何か別のものに変容しようとしている。つくったものが何か別のものを引き寄せるというのはアナログの持っている得意技で、その時の空気や匂いをまた触発してくれる。自分としてはそれを体で感じ取って、またデジタルに押し返したりその逆をしてみたいですね。Unreal Engineでつくったモデルをダンボールでつくってみたりして(笑)。そういう衝動が今はあります。

INFORMATION

亡き惑星遊女のためのパヴァ-ヌ
"Pavane for a Dead Sex Odyssey "
youtu.be/SZpo1i4tOkk(sound noise by Toad)
3/2-26 ナディッフWindow gallery
http://www.nadiff.com/?cat=9
Buzz..破壊され宇宙の塵となったダンボールミニチュアがアートとなって蘇らずにブラ下がる!buz..
3/12日.19時-同ギャラリーにて、悪名高いデスメタル"Bucher ABC/GRAVAVGRAV"はるまげTV"関根成年×藪前知子(キュレーター)×HI-VISIONSのカオスな トークショーあり
¥1200
LOOP HOLE 個展同時開催
http://studioloophole.com
CLEAR Gallery " パヴァーヌTV" by
HI -VISIONS (3月5日ー4月8日)
https://cleargallerytokyo.com/hi-visions-2023
"穴"と"宮" 画家OJUNと2日だけの2人展
2023.03.18【土】―2023.03.19【日】営業時
https://anatomia.nicephoto.jp/
TOSHIYUKI KIMURA Art Works
https://bijutsutecho.com/exhibitions/9978
HP
https://kim9179.wixsite.com/loophole/home
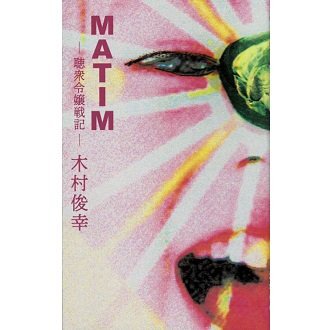
木村俊幸『MATIM-聴衆令嬢戦記ー』
https://www.nadiff-online.com/?pid=154451370
TEXT_日詰明嘉
PHOTO_竹下朋宏
INTERVIEW_阿部祐司(CGWORLD)
























