日本初となるVR映画の上映・コンペティションに特化した国際映画祭「Beyond The Frame Festival」が2月12日(金)〜2月21日(日)に開催された。本記事では同イベント内で行われたオンラインイベントをレポートする。2月17日(水)は、「エンタメ業界のキーパーソンが『VR映画』を語る。世界で戦うための戦略とは?」がテーマのトークセッションが行われ、日本と海外におけるVR市場のちがいや、VRコンテンツで今後求められることなど、登壇者それぞれの視点から熱く語られた。
TEXT_土居りさ子 / Risako Doi(Playce)
EDIT_小村仁美 / Hitomi Komura(CGWORLD)
●Information
-

-
「Beyond the Frame Festival」
開催日程:2月12日(金)~2月21日(日)
開催場所:オンライン
言語対応:日本語・英語
審査員:園 子温氏、大宮エリー氏、福田 淳氏
ナビゲーター:届木ウカ氏
主催:株式会社CinemaLeap
協力:文化庁委託事業「文化芸術収益力強化事業」/HTCVIVE/VIVEPORT/VeeR
btffjp.com
twitter:@btffjp
YouTube:https://youtu.be/90UUyMahbkg
VRの魅力のひとつは、2Dでは体感できない「没入感」
本イベントの登壇者は、株式会社WOWOWの藤岡寛子氏、株式会社講談社VRラボの石丸健二氏、株式会社ソニー・ミュージックエンタテインメントの田中茂樹氏、株式会社プロダクション・アイジーの郡司幹雄氏の4名。モデレーターは、株式会社Moguraの代表取締役社長でMogura VR News編集長の久保田 瞬氏が務めた。
-
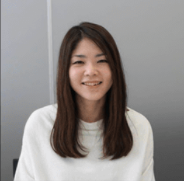
-
藤岡寛子氏
(株式会社WOWOW 技術局技術企画部プロデューサー)
2020年に株式会社CinemaLeapと共同でVRアニメーション『Beat』を製作。同作品が先進映像協会主催のルミエール・ジャパン・アワード2020授賞式にてVR部門優秀作品賞を受賞した
-

-
石丸健二氏
(株式会社講談社VRラボ 代表取締役社長/エグゼクティブプロデューサー)
2017年から18年にかけて上映された劇場映画『GODZILLA』三部作の制作プロデュースなど数々の作品に携わる。2017年からはVRアイドル『Hop Step Sing!』のVRコンテンツ、プロモーションビデオの企画・プロデュースなども行なっている
-

-
田中茂樹氏
(株式会社ソニー・ミュージックエンタテインメント ゼネラルマネージャ、株式会社レーベルゲート 執行役員)
VRやARのエンターテインメントに取り組むソニーグループ横断プロジェクト「Project Lindbergh」にてプロジェクトリーダーを務める。同プロジェクトが制作したVRコンテンツ『ミヅキ討魔伝~五芒を継ぐもの~』がルミエール・ジャパン・アワード2020でグランプリを受賞
-

-
郡司幹雄氏
(株式会社プロダクション・アイジー プロデューサー)
『宇宙戦艦ヤマト2199』『GREAT PRETENDER』『銀河英雄伝説』など数々の2Dアニメーション作品に携わる。2015年には『宇宙戦艦ヤマト2199』のVR作品をプロモーションとして自社製作し、以降VRアニメーション作品のプロデュースも行なっている
トークセッションは、「VRのどのようなところに魅力を感じているのか」という久保田氏の質問からスタート。登壇者それぞれの答えで共通していたのは、2Dとは異なる「没入感」が感じられるということだった。
なかでも石丸氏はVR製作に関わった初めてのコンテンツとして、講談社発の新世代VRアイドル『Hop Step Sing !』を挙げ、「360度映像の中に入ることで、2Dでは行けなかったところに行けたり、自分自身の大きさが変化したり...とてつもないフィードバックがあるところが魅力です」と回答した。
▲講談社発のVRアイドル『Hop Step Sing!』。日本だけでなく北米向けにVRライブの配信を行うなど、様々な試みが行われている
これに対して田中氏も、自身が体験した、2015年公開の映画『ザ・ウォーク』のVRプロモーションコンテンツを挙げ、魅力を語った。「VRコンテンツで、映画の主人公と同じようにワールドトレードセンターのツインタワーの間を綱渡りしたのですが、平地の上を歩いているだけなのにとても恐怖を感じ、まったく歩くことができませんでした。この経験から四角の画面とは違う没入感を味わうことができるVRに、新しいメディアとしての可能性を感じました」。
現時点で大切なのは、「誰もが見たいと思えるVRコンテンツをつくる」こと
登壇者たちが揃って「新しいエンターテインメントだ」と語るVRコンテンツ。今回のトークテーマである「VR映画」も今まさに注目され始めている。続いては、「VRコンテンツを発展させるためにはどのようなことが必要なのか」というテーマでトークが展開していった。
藤岡氏は「現時点で大切なのは、まず『誰もが見たいコンテンツをつくること』だと思います」と語り、そのためにはまず、登壇者たちがVRの魅力として語った「没入感」をいかに味わわせるかということがポイントになると指摘。郡司氏もこの意見に賛同し、「デバイスを購入してでも見たいと思えるコンテンツをつくることが大切で、ストーリーと上手く結びついた『演出』を考えることもひとつのポイントになると思います。そうしたコンテンツが増えることがブレークスルーのきっかけになるのではないでしょうか」と述べた。VR映像のどの部分にインタラクティブなしかけをするのか、どのような演出にするのが効果的なのか、といった作品づくりにおける試行錯誤が今まさに行われている。
▲藤岡氏がプロデューサーを務めたVRアニメ―ション『Beat』。Haptics(触覚)技術を用いたデバイスを使用し、作品に登場するロボットとユーザーの心臓の鼓動を連動させるなどVRならではの演出がなされている
また、魅力的なVRコンテンツをつくることと並行して、コンテンツを楽しむための「土台づくり」にも取り組んでいく必要がある。田中氏は、「研究開発や設備投資にかなりのコストがかかっているのが現状です。そのため『フォーマット』が出来上がれば、VRコンテンツはよりつくりやすくなるのではないでしょうか」とコメント。石丸氏も、「5Gとクラウンドレンダリングの組み合わせでハイエンドなものがスマートフォンでも楽しめるようになるなど、技術の進歩による様々な可能性を感じています。今はこうしたテクノロジーの発展に合わせつつ、VRコンテンツの制作を続けていく必要があると思います」と語った。
続いての話題は、日本と海外のVR市場のちがいについて。藤岡氏は、「VRをけん引するのはゲームコンテンツなので、まずは日本の人気アニメ―ション作品を題材としたVRゲームを制作すれば、デバイス自体の普及につながるのではないでしょうか」とコメント。それに対して田中氏は、「海外と比べると、日本はスマートフォンでゲームをする人が多く、ハイスペックなゲームデバイスはアメリカなどの方が断然人気。そうしたところも、日本でVRの普及が遅れている要因だと思います」と日本の課題を説明した。
さらに田中氏は、日本は漫画やアニメなど2Dの文化が強いことを指摘。それと比較して「アメリカではピクサーやディズニーが3DCGの作品をつくっています。3DCGからVRを制作することはそこまで困難ではなく、おそらく『二次利用としてVRを制作する』こともあらかじめ考慮して作品を制作しているのではないでしょうか。その点は日本と異なっているところだと感じています」と述べた。
アニメーション制作に携わる郡司氏も田中氏に同意。「日本では一度つくられたCGアセットがその後使われることはほとんどなく、とてももったいなく感じています。そのため私は、自分が製作委員会に入っているアニメーション作品では、二次利用ができるようあらかじめ権利処理を行うことを心がけています。今後も権利処理をはじめ、VRの制作を見越してアセットをつくったりしていく必要があるのではないでしょうか」と語った。
▲プロダクション・アイジーのグループ会社WIT STUDIOが第3期まで制作を手がけたアニメ『進撃の巨人』。同作品のVRライド型アトラクション「hexaRide」向けコンテンツでは、郡司氏も演出に携わった
そのほか日本と海外のちがいについて石丸氏は、VR映画の作り手が日本ではまだ少ないことを指摘。「VR映画の制作は、通常の横型フレームの映画づくりとは異なるため、企画や脚本をVR的に理解している人でなければ難しいです。VR映画の作り手を増やしていくことは、私たちの役目でもあると感じています」と語った。これに対して藤岡氏も、海外は国からの支援金があるが日本ではまだ少ないことを補足し、「海外と共同製作するということも、今後ひとつの手段として考えられるのではないでしょうか」と述べた。
黎明期だからこそ、アイデア次第で誰も体験したことのない作品が生まれる
最後に久保田氏から、これから日本のVR市場をさらに盛り上げていくために「VRコンテンツの制作にチャレンジする人を増やすためにはどうすれば良いのか」という質問が投げかけられた。
石丸氏は、「VRコンテンツを制作するときには、なるべく同じ監督に依頼しないようにするなど、いろいろな人に関わってもらうことを意識しています」と回答。講談社VRラボのオリジナルVR映画『Last Dance』では、海外でも有名なダンサー・北村明子氏がダンスの振り付けを行なった。このように、「こちらから働きかけることで、様々なフィールドの人がVRに興味をもってくれる」と石丸氏はすでに手ごたえも感じている。VRを体験したことがない人が周りに多くいるという田中氏も、「国際的なVR映画祭を日本でも開催するなど、VRに触れる機会を増やしていくことが大切だと思います」と語った。
▲田中氏がプロジェクトリーダーを務める「Project Lindbergh」が手がけたコンテンツは2年連続で賞を受賞。「作品を発表する場があるからこそチャレンジできる」と語る
藤岡氏は「VRの催しがあれば積極的に足を運び、その中で人脈をつくっていくことで様々なきっかけが生まれると思います」と自身の経験も踏まえてコメント。また、少ない資金でVRコンテンツを製作した経験のある郡司氏は「『失敗してもいいからとりあえず1回チャレンジしてみよう』という考え方をもっと広げていくことが大切だと感じています」と述べた。
エンタメ業界のキーパーソンたちが「VRは面白くて新しいエンターテインメント」と自信をもって語った今回のトークセッション。なかでもVR映画の市場はまだまだ黎明期で、演出やつくりかたなどアイデア次第で勝負できるところにも魅力がある。どのような作品が生まれてくるのか、今後も目が離せない。
























