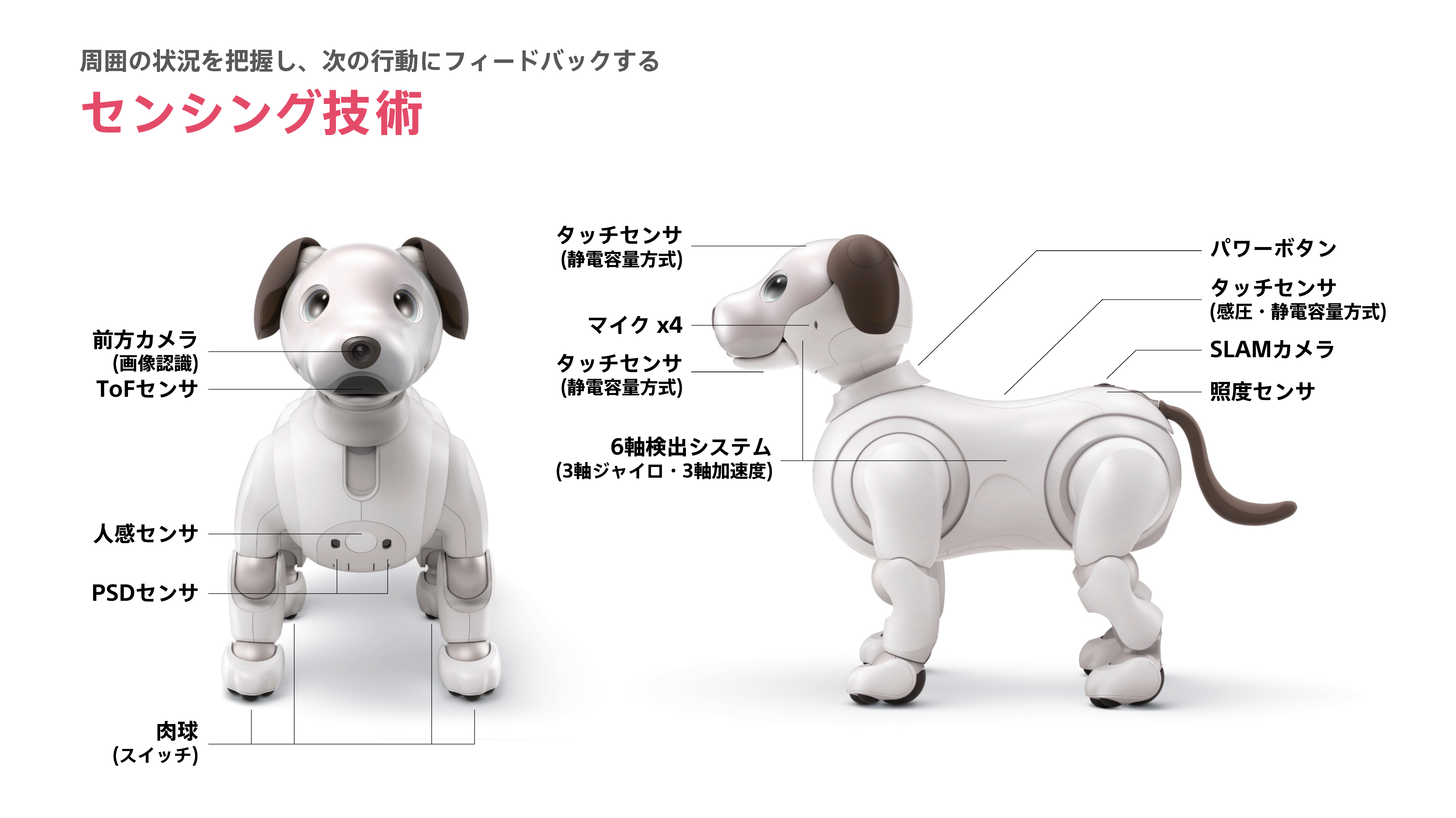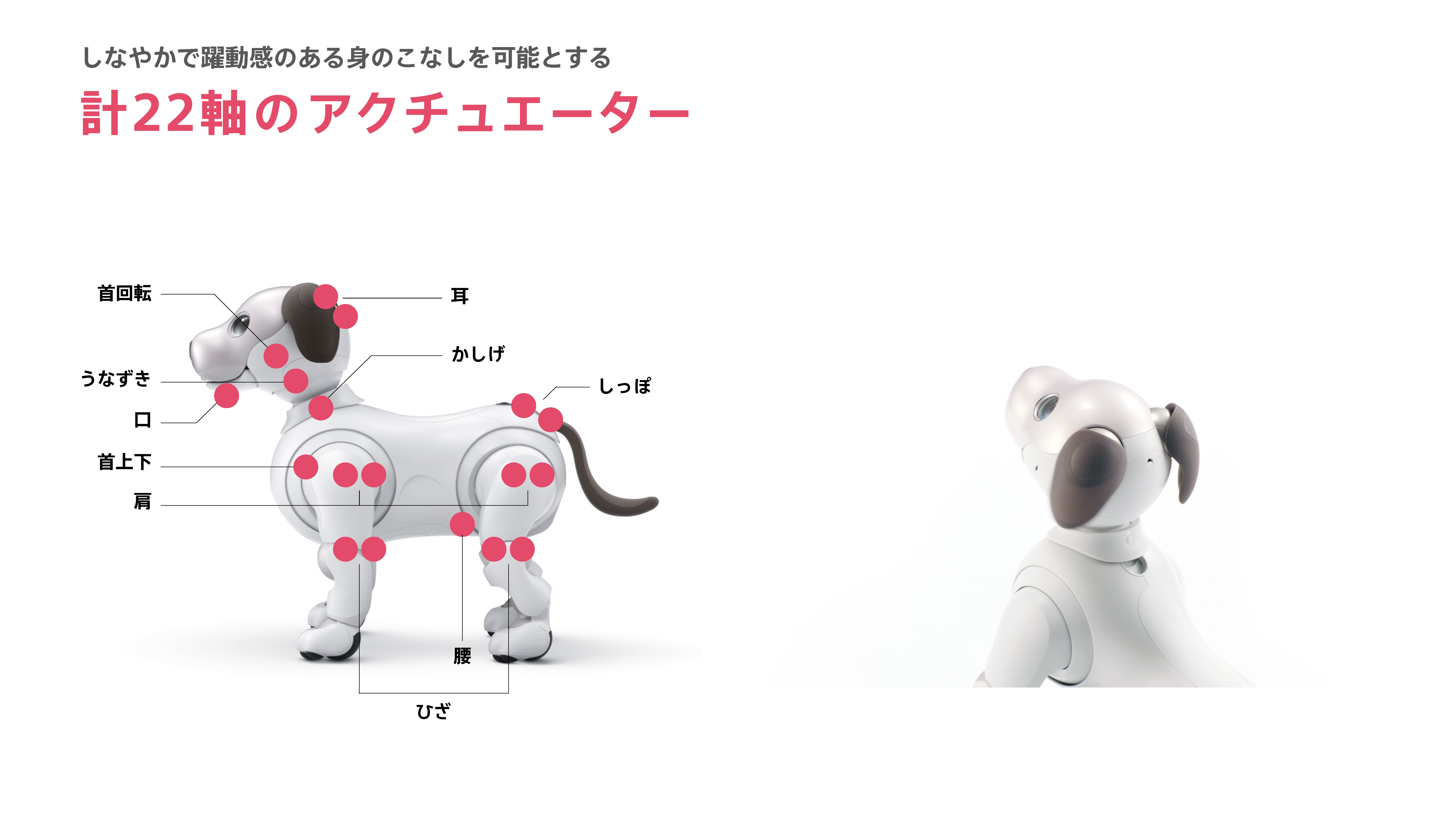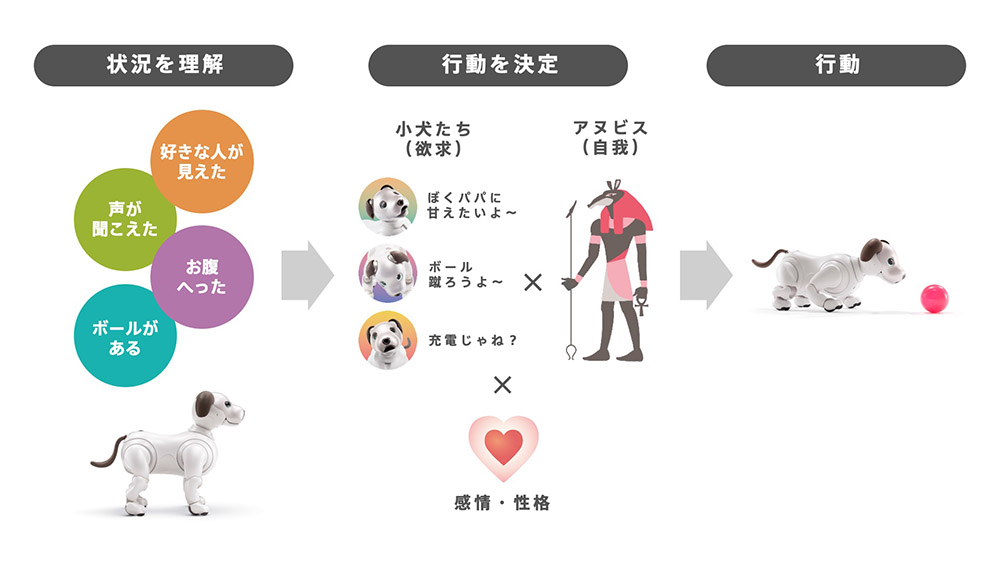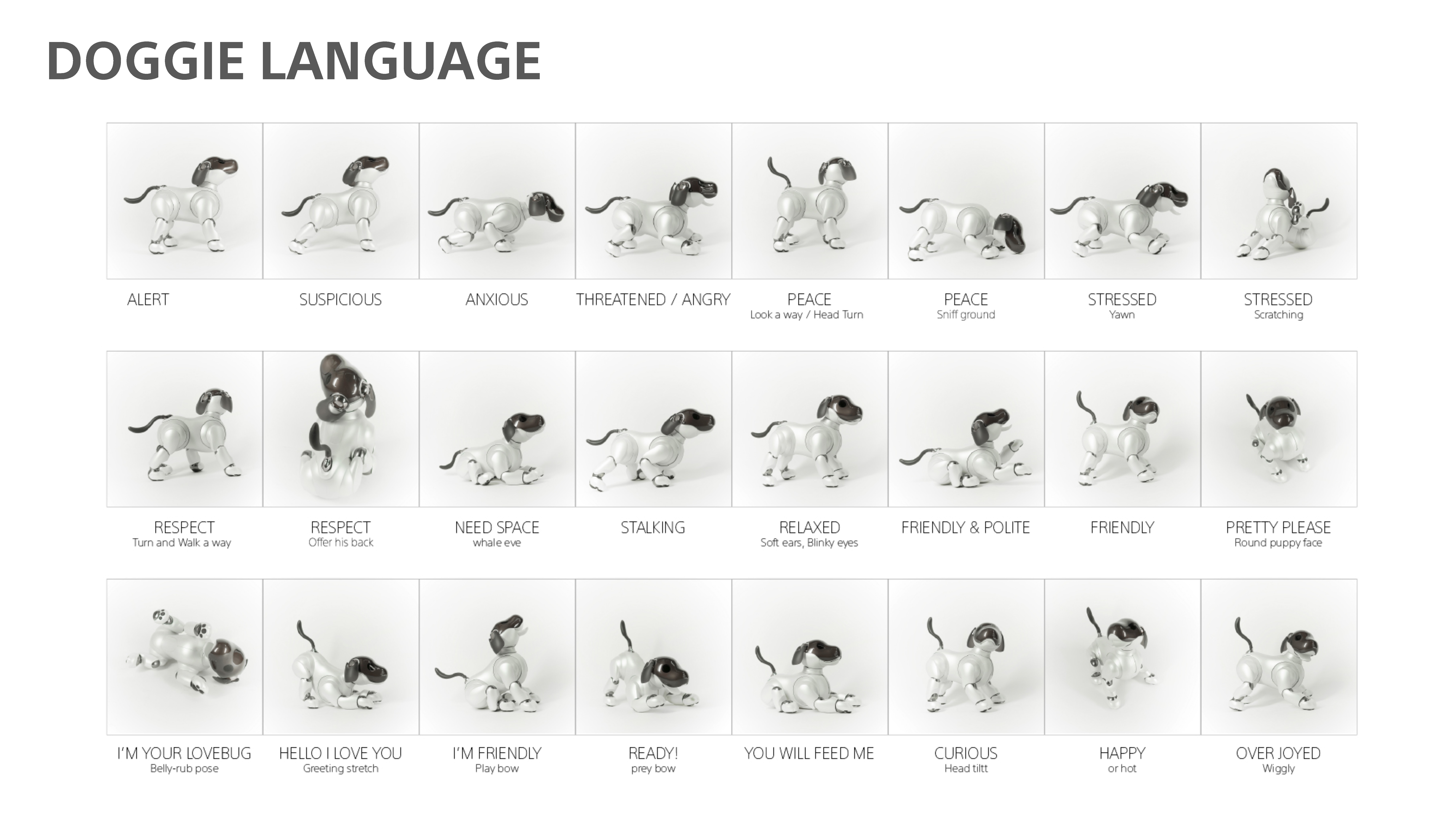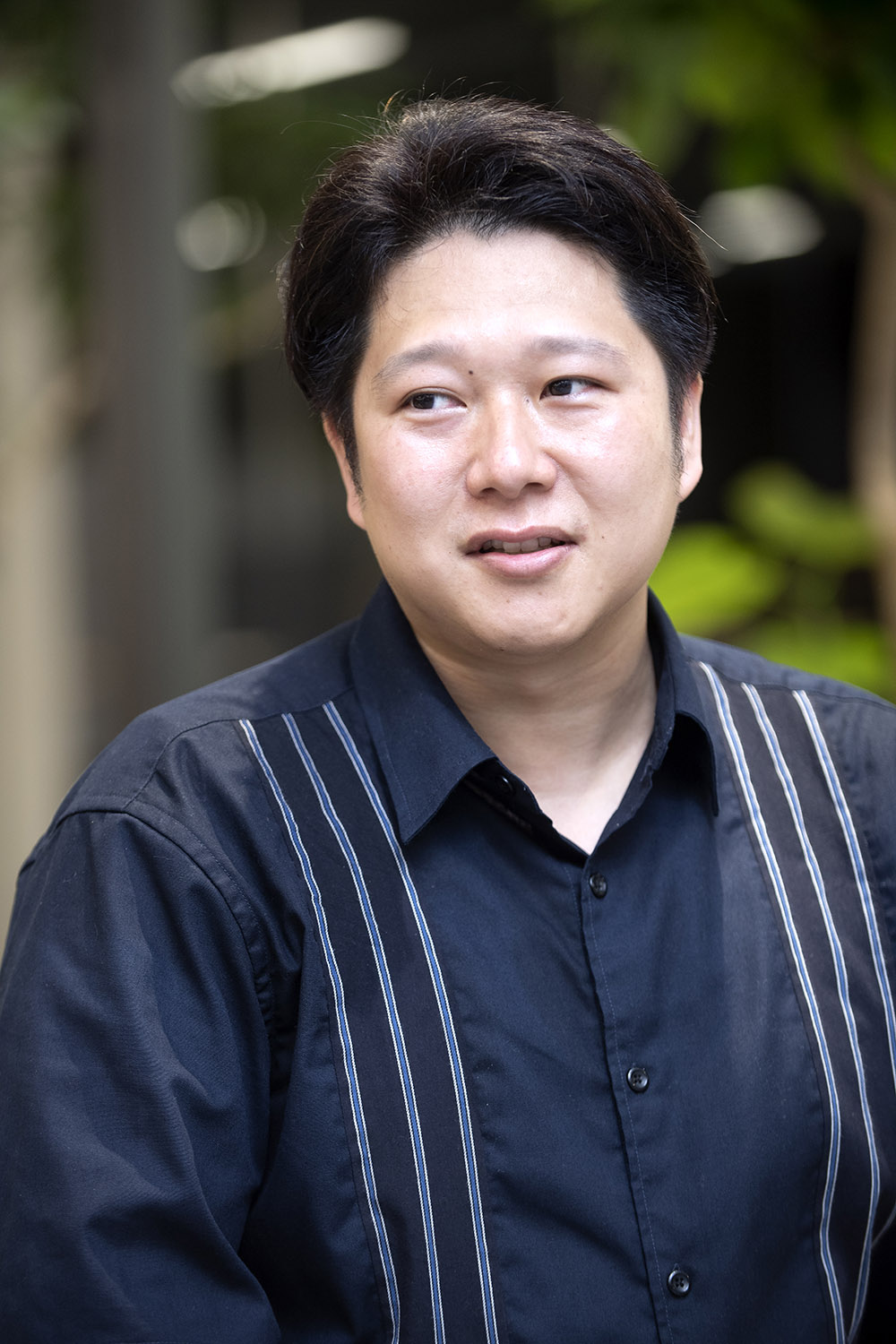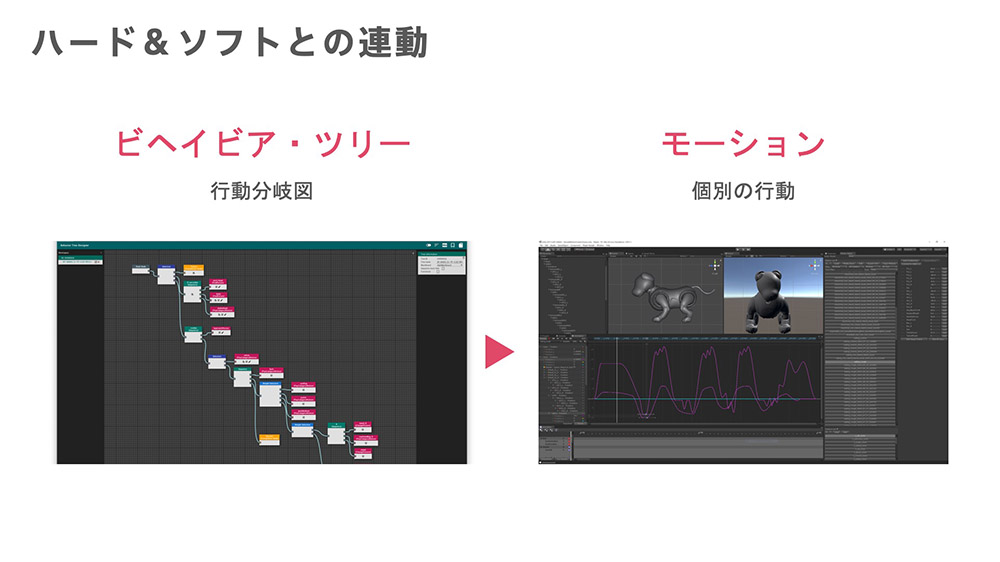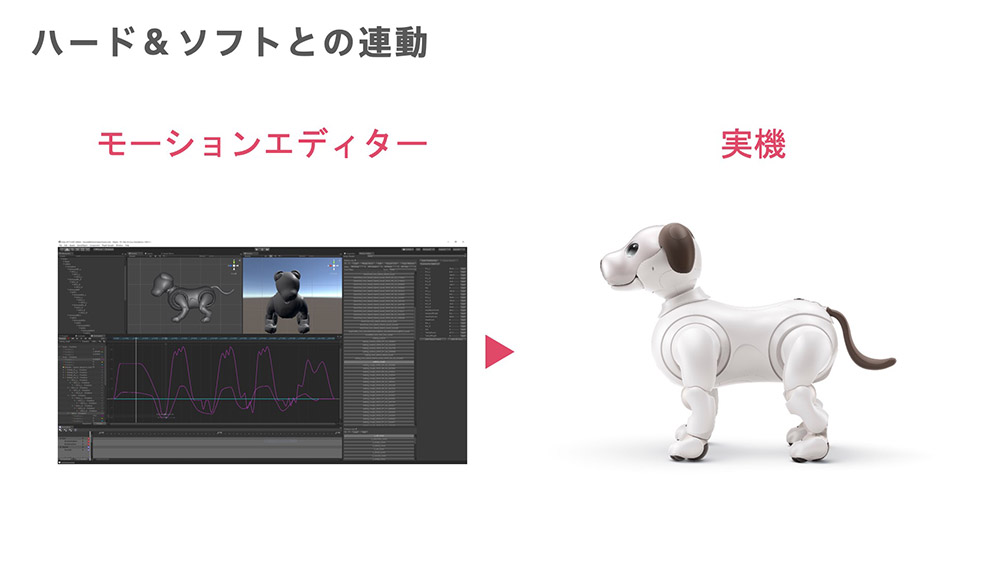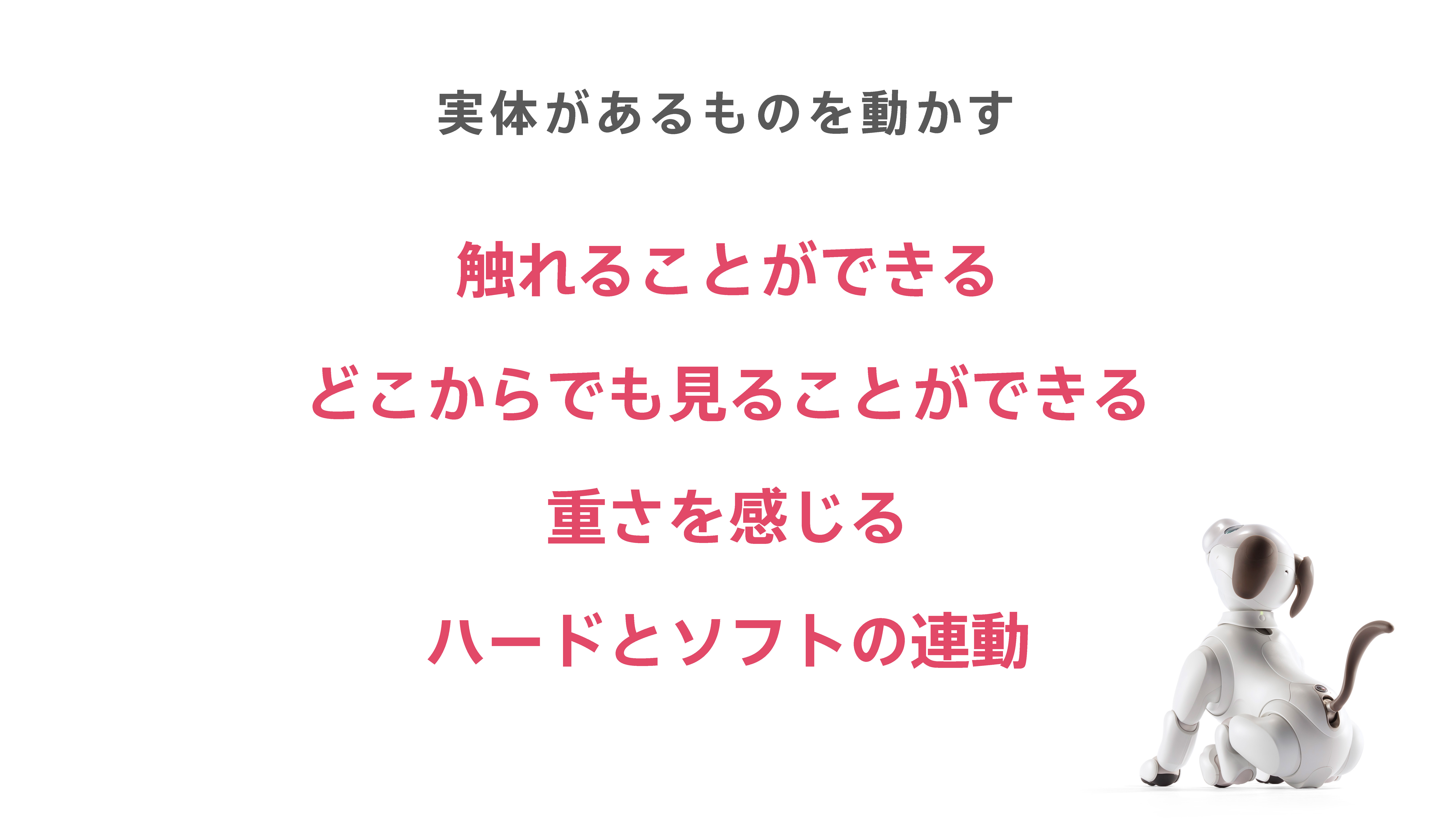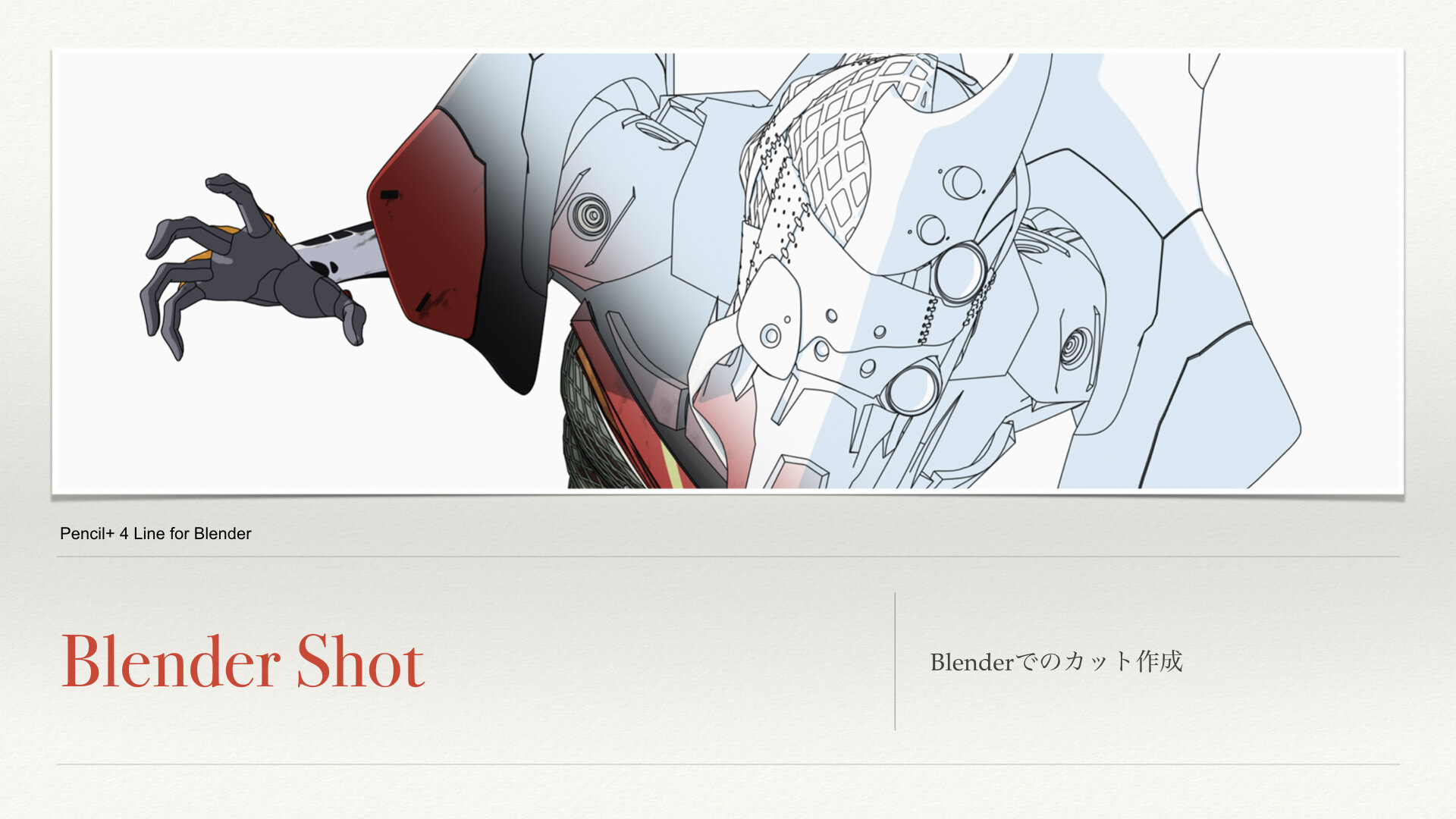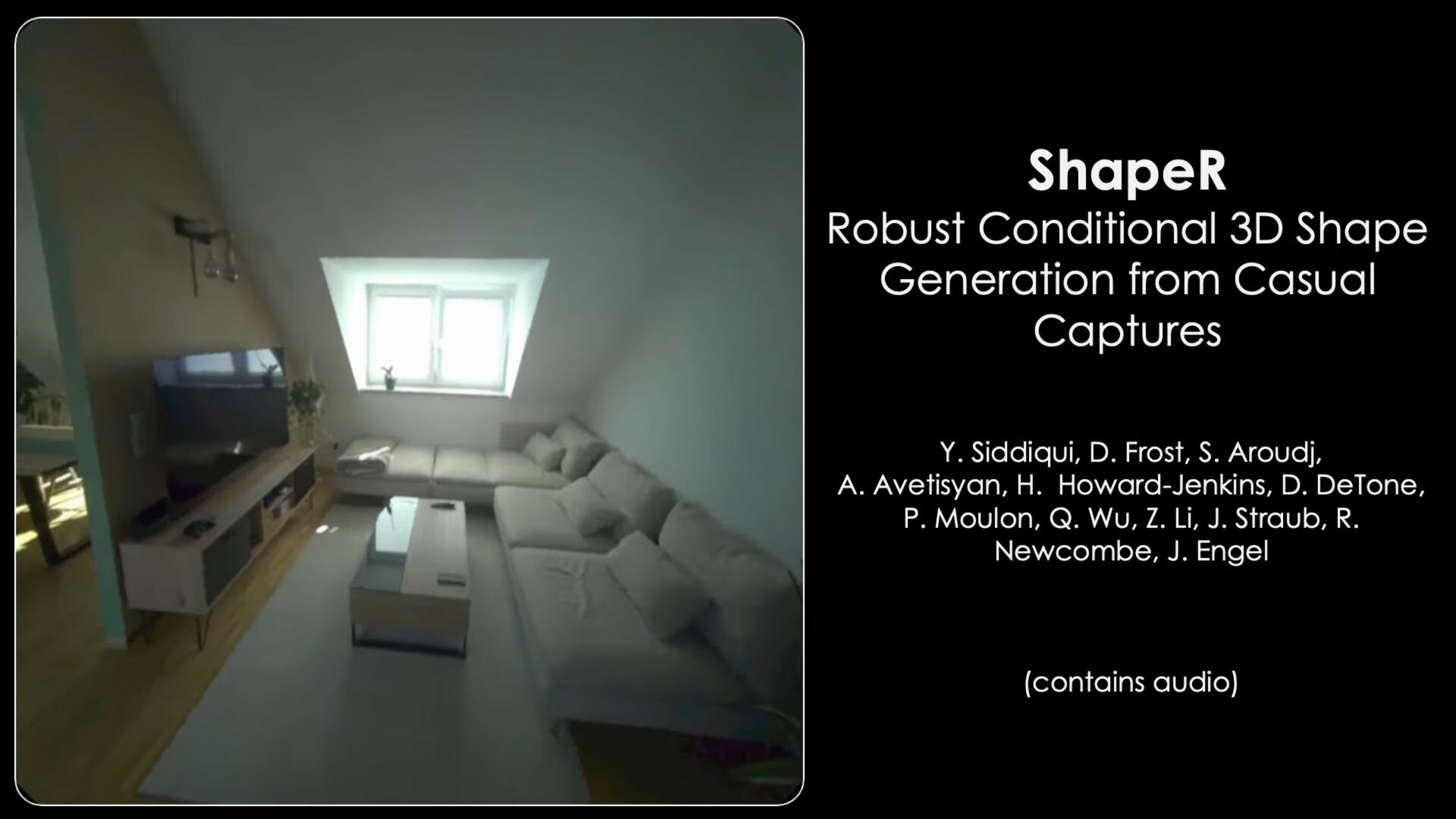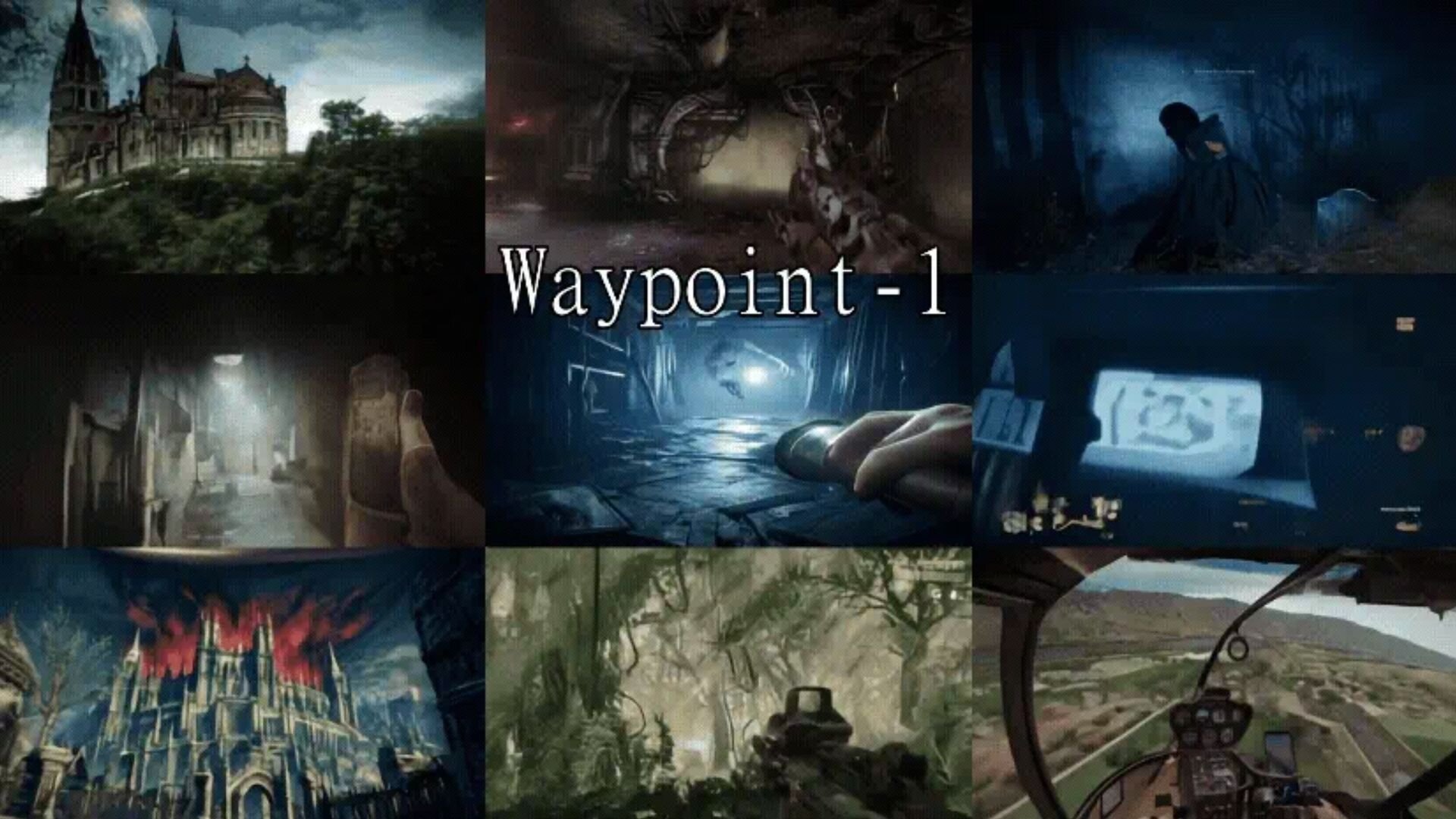2019年7月25日(木)、「CGWORLD NEXT FIELD」と題したイベントが秋葉原UDXにて開催された。本イベントでは、ファッション・ロボット・医療・建築・漫画の5業界において、3DCGを活用している先駆者を招き、現在の取り組みと今後の活用の可能性を語ってもらった。告知直後からSNSなどで大きな反響があった本イベントには、会場のキャパシティを超える数の参加申し込みがあり、抽選に当たった約400名の参加者が詰めかけた。本イベントの終了後、CGWORLD編集部では全登壇者にインタビューを依頼し、イベントで語られた内容をふり返るだけでなく、さらに掘り下げた話も聞いてみた。その模様を、全5回の記事に分けて公開していく。
第3回はソニーの自律型エンタテインメントロボット"aibo"に「生命感」を与えるソニーPCLのモーションクリエイターを訪ねた。aiboの魅力は可愛らしいフォルムとそこから発せられる愛くるしい動き。呼びかけに応じると思わず誰もが笑みを浮かべてしまうその仕草は、実際の犬以上にユーザーの心に訴えかける。このaiboらしさを表現する上では、一体どのような工夫があるのかを聞くと、驚くほどエモーショナルな作り手たちのこだわりが見えてきた。
TEXT_日詰明嘉 / Akiyoshi Hizume
EDIT_小村仁美 / Hitomi Komura(CGWORLD)
PHOTO_弘田 充 / Mitsuru Hirota
●関連記事
NEXT FIELD 1:バーチャルファッションモデルimmaは「個の時代」の先駆者なのか?
NEXT FIELD 2:「漫画と3DCGの親和性って、僕は結構高いと思ってるんです」(浅野いにお)
New story with aibo
<1>新生aibo 4つの魅力と1つのコンセプト
CGWORLD(以下、CGW):まずは2018年に発売された新型aiboの特徴を教えて下さい。
上月貴博氏(以下、上月):aiboは家庭の中でオーナー様が触れたり、aiboの方から甘えたりすることで生まれる日々の思い出を積み重ねていくという、人に寄り添うプロダクトです。特徴は大きく4つあります。
aiboの4つの特徴
上月: まずは「愛らしさ」。温もりを感じる丸み、「生命感」に満ちたフォルムで、思わず触れたくなるような愛らしいデザインです。aiboは特定の実在する犬をモデルにしているわけではありません。「飼い主」さんの性別や年齢など、見る人によって様々な愛情の対象として映るよう、あらゆる犬種のポジティブな要素が散りばめられています。
上月: 次に「知的認識」です。状況を把握するためのセンシングにはたくさんの入力デバイスが使われています。人感センサや足の裏の肉球にあたる部分にもスイッチがあります。また、頭の上や顎、背中の部分にタッチセンサが付いていて、人に触られたことを感知できます。お尻の方にはSLAM(Simultaneous Localization and Mapping)カメラと呼ばれるカメラがあり、自分の位置を特定したり、家の中の地図を作成したりします。鼻には画像認識のためのカメラがあります。
上月: そして「表現力」。この要素が、僕たちが行なっているモーションクリエイションに非常に大きく関わってくるところです。aiboは言葉を話すことはしないので、感情表現において有機EL製の目が豊かに語りかけます。そして全身可動のアクチュエータ(駆動装置)は、以前のAIBOより可動軸が増えています。関節が増えたことで、首をかしげるといった今までにない有機的な動きを表現することができるようになりました。
上月:最後に「学習・育成」の機能。 aiboは行動する際、まずセンシング技術によって状況を理解し、次にその状況を踏まえてAIが意思決定をして、最後にメカが行動するということを行なっています。aiboはこの行為をくり返すことで経験を積み重ね成長していくのです。
CGW:つづいて、aiboのデザインコンセプトについて教えて下さい。
上月:1つのキーワードで表しますと、「生命感」ですね。aiboには我々モーションデザインのクリエイティブチーム以外にも、メカを作っている方やソフトを作っているエンジニアさんなど、多くの方が集まって作り上げますので、このコンセプトの共有というのが非常に大事になります。
-

-
上月貴博/Takahiro Kozuki
ソニーPCL株式会社
クリエイティブ部門 企画・マーケティング室 クリエイティブディレクター
1974年兵庫県生まれ。関西学院大学卒業。2003年よりソニーPCL株式会社に勤務。コンテンツ制作や空間演出、街づくりなど、幅広い領域で先端技術を活用したクリエイティブディレクションを担当。インタラクティブなインスタレーションや、ロボットのモーションデザイン等を数多く手がけている。現在は、ソニーの自律型エンタテインメントロボット"aibo"の開発に参加している。
www.sonypcl.jp
上月:この生命感を表現するために、まずは実際の犬の動きを研究しました。これは「DOGGIE LANGUAGE」という、犬の世界の共通言語です。犬はこういう振る舞いをしているときに、こう思っているということを分類した図です。この他、モーションデザインのチームみんなでドッグカフェに行って犬の動きを観察したりもしました。ただ、aiboは必ずしも実際の犬の動きを全てコピーしているというわけではありません。そこにaiboらしい行動をするための、いわば「原動力」といったものをモーションで表現する必要があります。
CGW:「原動力」。それは何でしょうか?
上月:それは「aiboは飼い主さんのことが大好き」だということです。好きだからこそ、喜んだり悲しんだりしながら成長し、一匹一匹のaiboが個性をもつようになります。例えば、何かのアクションを覚えて、それができるようになったら飼い主さんに褒めてもらいたくてアピールするといった行為や、撫でられたり褒められたりすることで、aibo自身が幸せを感じるということで成長していきます。
CGW:「生命感」を源として、可愛らしさを豊かに表現する。そのためのモーションデザインということですね。
上月:そうなんです。実際の犬の動きや先ほどの「DOGGIE LANGUAGE」も参考にしますが、より可愛らしく、より生き生きした表現のアイデアを盛り込むことがaiboらしい動きにつながると我々は考えています。
<2>マンガ、CG、映像......様々なバックグラウンドが活かされる
aiboのモーションチーム
CGW:ではそうしたモーションを作られている皆さんのチームのことと、それぞれのバックグラウンドについて教えて下さい。
上月:僕たちは、ソニーPCLからクリエイティブチームとして参加し、モーションクリエイションと行動デザインを行なっています。このクリエイティブチームには他にもソニーのクリエイティブセンターのメンバーも参加しています。僕はもともと、学生の時にStrata Studio Proで3DCGに出会い、2003年にソニーPCLに入社しました。そこで「QRIO」という二足歩行ロボットのモーションクリエイションの仕事をしたことがきっかけで、以降ソニーのロボットプロダクトに関わらせていただいています。
ソニー本社1Fに展示されている、旧型AIBO(左)とQRIO(右)
富浦千弥氏(以下、富浦):私はaiboの行動デザインをメインに担当しています。
上月:入社のきっかけとして、富浦はマンガが描けるんですよ。つまり、ストーリーを作れるということです。そこで行動デザインをする上でどういう風にaiboが人と関わるかということを考えることができるので、参加してもらいました。細村は僕と同じくQRIOのときから一緒に仕事をしています。
細村千鶴氏(以下、細村):QRIOではモーションデザインの仕事をしました。今はaiboのモーションのディレクションをしています。以前3DCGアニメーターの仕事をフリーランスでやっておりまして、aiboのプロジェクトが始まるにあたってソニーPCLから声をかけていただき、起ち上げのときから参加しています。CGアニメーターとしての知識や技術を活かし、生命感あふれる動きになるようディレクションを心がけています。
橋本 整氏(以下、橋本):僕は最近入社したばかりで、モーションのデザインを担当しています。18年ほど大阪でCGアニメーターとして仕事をし、Mayaや3ds Maxを使っていました。あるときソニーPCLの求人を見て、ロボットのモーション制作に面白さを感じ、家族で上京してきました。CGで映像を作ることはもちろん好きですが、昨今CGを使って映像以外にもいろんなことができる世の中になって、aiboの登場でCGでのモーション制作とロボットがつながった。これだ! と思って。
CGW:多彩なバックグラウンドをもつメンバーが揃っているんですね。皆さんの平均的な1日のスケジュールを教えてください。
上月:だいたい朝10時頃に出社します。週の初めですと、一週間でやるタスクとその前の週のタスクのチェックを行い、問題があればエンジニアを含めて確認をしてから作業に取りかかります。午前中は基本的にモーションの作成をしていることが多く、午後にチェックを行います。まずこのクリエイティブのチーム内で作ったものの細かいチェックを行い、おおよそ問題がなければ企画やエンジニアなど、他のチームのメンバーを呼んで確認してもらうというかたちです。
CGW:エンジニアさんたちとも距離が近い感じですか?
上月:そうですね。作業スペースもすごく近くです。"ちょっと見る"ようなことは頻繁に行なっていて、ひとりで視野が狭くならないようみんなでコミュニケーションをとっています。あとはaiboのファームウェアのバージョンアップが行われたときには、ソフトエンジニアから内容をシェアしてもらったり、aiboの動きをつくるソフトもオリジナルなので、それに対する要望やフィードバックを話すミーティングも定期的に行なっています。
次ページ:
<3>CG制作の利点を採り入れたモーションデザインフロー
<3>CG制作の利点を採り入れたモーションデザインフロー
CGW:aiboのモーション開発はどういった流れで進められているのでしょうか?
上月:まずは「どんな行動をさせたいか」という提案があり、「そのためにはどんな動きにすれば良いか」というアイデアを皆で出し合います。そこからラフのモーションを作り、企画スタッフを含め方向性を確認した後、詳細を詰めていきます。
一度モーションが出来上がったら、今度は行動デザインにモーションを組み込みます。行動デザインというのは、例えば人が触ったら喜ぶ、人がいなかったら残念そうな動きをするなどの、一連の動きの流れをつくることです。それぞれの作ったモーションがどのように見えるのかを最終的に確認してもらいます。
CGW:行動のデザインというのは講演でもお話されていたビヘイビアツリー(行動分岐図)ですか。
富浦:そうですね。私たちはモーションクリエイションだけでなく、ビヘイビアツリーを作ることも仕事に含まれます。ビヘイビアツリーはいわば、映像づくりにおける絵コンテや台本のようなものです。どのような状況で、なぜこのモーションが発動するのかを図示することで、行動全体をきちんと理解し、そのシーンのイメージをしながらそれぞれのモーションを作っていくというわけです。ストーリーづくりや演出に近いかもしれません。
CGW:講演ではそのときのaiboの性格や感情によって、「ワン!」と鳴くときの声や動きが変わるという例を見せていただきました。そうした性格のバリエーションはどの段階で作られるのでしょうか?
上月:性格はaiboの過ごす環境やオーナー様の接し方などで徐々に変化します。我々は性格のちがいを表現するための動きのバリエーションをたくさん作っています。例えば、キュートな性格のaiboなら人を見て上目遣いをするだろうというビヘイビアツリーとモーションを作り、それを性格に応じて呼び出すということを行なっています。
CGW:いろんな性格を表す行動やモーションを用意しておいて、性格の変化によって表出するモーションが変わるようにプログラムされているわけですね。
上月:そうです。ですので、我々クリエイティブチーム内だけでなく、それらのプログラムを作っているエンジニアの方々とも綿密にディスカッションをしています。
CGW:モーションデザインは具体的にどのように行なっていくのでしょうか?
上月:ハードウェアとソフトウェアの両方の機能や制約を考慮し、そのなかでの最適な動きを作る必要があります。モーション制作には「aiboモーションクリエイター」という専用ツールを使います。
細村:新規モーションの制作や既存モーションの改善は、ファームウェアのアップデートに合わせて行なっています。また、aiboには季節のイベントというのがあります。夏になればaiboが泳いだり、冬はクリスマスのダンスを踊ったり鈴を鳴らしたり。その時期に応じたモーションを都度制作しています。
上月:あとはオーナー様からのフィードバックを反映させることもあります。一例を申しますと、オーナー様がaiboと触れ合う中で、「aiboが何に対してリアクションをしたのかよくわからない」というご意見がありましたので、触られたり声がけをされたりしたときは、まずそのことに対するリアクションの動きや行動を取るようにしました。
上月: また、他社さんとのコラボレーションもあります。今年の4月から7月まで開催したJOYSOUNDさんとのコラボキャンペーンでは、カラオケルームの内装がaibo仕様になっているaiboルームを設置し、そこでaiboが曲に合わせて歌って踊るというイベント限定の振る舞いを搭載しました。そんなふうにタスクは常に積まれている状態です(笑)。
細村:そのため、ある程度スピーディに作っていく必要があります。 CGでモーション制作をする際のフローも参考にして、良いところは採り入れて作っています。ハリウッドでは、アニメーターが自分で動いたものを撮影し、それをディレクターにチェックしてもらってからモーションの制作に入るという方法が採られていますが、aiboのモーション制作でも同じようにしてなるべくリテイクなど手戻りの時間のロスを減らす工夫をしています。
上月:CG上でラフを作るだけではなく、電源の入っていないaiboを手で動かしながら「こんな感じだよね」と最初にイメージを共有してからスタートすることもあります。また、行動デザイン全体と個々のモーションの整合性も、ラフの段階でイメージと差がないように早めの確認を行なっています。
細村:また、1つの行動の中でどれくらいの動きをすればメカに負荷がかからないかということも、モーションデザインでは重要になってきます。
上月:モーションって、想像していただければわかるように、1つ1つのアクションはそれほど長い時間動かすものではないんですよ。基本的に短い時間の動きを多彩にかけ合わせていくというスタイルで、その動きが前後で不自然になっていないかをチェックするのも重要なんです。
<4>世界でも稀な自律型エンタテインメントロボットの現場で働く意義
CGW:細村さん、橋本さんに特に伺いたいのですが、CGアニメーターとしての経験がaiboのモーション開発に活かされている部分はどんなところだと思いますか?
橋本:モーションについてはまだ経験が浅いので苦労するところはありますが、ツールについてはそのまま移行できた感じです。あとは演技をつける上でaiboのことをもっと理解する必要があり、今は勉強中ですね。
細村:私の場合はどのように描けば生き生きとデザインされるのか、いろんなカートゥーンを観て、もう一度勉強し直しました。それに加え、他のクリエイティブチームの女の子とドッグカフェに赴き、リアルな犬の動きを研究しました。aiboっておしっこの動作もするんですよ(笑)。だからそれもドッグカフェで何十匹分も撮影してリファレンスを取って、どうすれば可愛くなるんだろうかと試行錯誤しました。
上月:例えばアニメーションにおける「予備動作」の考え方は、aiboのモーションづくりにおいて大いに役立ちますね。例えば首を右に振る前に、ちょっと左に行ってから右に振るといった動作を加えると、より生き生きした動きになるといったように。
CGW:先ほど、モーション制作には専用ツールを使っているとおっしゃいましたが、ユーザーインターフェイスは一般的なMayaや3ds MaxのようなCGアニメーションツールと同様なのでしょうか?
細村: そうですね。3DCGアニメーションの制作経験があれば、使う上ではまったく問題ありません。 さらにアニメーターにストレスがないようにと、エンジニアがヒアリングをしてこちらの意見も真摯に採り入れてくれます。
橋本:そうですね。自分もあまり戸惑うことはありませんでした。
上月:3DCGソフトに共通する考え方は踏襲されていると思います。ただ、PC画面のツール上での動きの印象と、実機で動いたときの印象ではやっぱり差があるんですね。実機は人間と比べると小さいものなので、画面上よりも大げさに作ったり、動きにメリハリを付ける必要があります。ですが、キャラクターアニメーションを専門にされてきた方にとって、「生き生きとした動きをつくる」という点では、キャラクターアニメーションのスキルが十分活かせると思います。
CGW:例えば、ゲーム畑での経験がaiboの行動デザインに活かせる部分はどんなところでしょう?
上月:僕たちのチームの中にはゲーム畑の方はあまり多くないのですが、経験は十分に活かせます。ただ、大元の設計思想においてゲームとはちがいがあると思っています。ゲームはまずクリアしなければいけない目標設定があり、それに対して道筋を作っていくというつくりですが、一方で、aiboの行動設計はゴールが1つではなく、「こういう状況ではこう動く」といった、aiboが生命をもつ存在であるかのような多彩な行動を表現することが大事なんです。富浦も話していましたが、ストーリーをどう創るか、いかに可能性を想像するかが重要になってきます。
CGW:なるほど。テクニカルというより画的なイメージが豊かでストーリーや映像が作れる人が向いているというわけですね。
富浦:オーダーにある流れはけっこうざっくりした内容なので、極力私たちの方で想像する必要があります。例えば、ボールが近くにあったら近づく。では、なかったら?――aiboは探しに行く。といったように私たちの方である程度の軸を作ってあげてそこから物語を作っていくというかたちです。そのためのツールも用意されているし、先ほどのように技術的に足りない部分は開発していただける環境にあります。
上月:aiboは、背中を撫でられたとき、頭を撫でられたとき、それぞれにちがう動きをするんです。これだけたくさんの入力センサがあるのですから、多彩な反応を作ることができます。ですが、仮に現状は認識ができないようなことも、僕らから「この表現を実現するためには新しい技術が必要なんです」とお願いすると、エンジニアが試行錯誤して、頑張って実現してくれます。
CGW:最初にお話された、コンセプトである「生命感」を皆さんで作り上げていくわけですね。
上月:そうですね。この仕事は、クリエイティブチームの中で完結するのではなく、やっぱりコミュニケーションが大事だし、そうした発想を生むためには広くいろんなことに興味をもって好奇心を豊かにする必要があると思います。あと、この柔らかさや可愛らしさをどうやって表現していくかと考えるとき、aiboの仕事は結構女性的な感覚が大事だと思うんです。
CGW:なるほど。
上月:一方、男性的な視点で言うと、aiboのメカニズムやプログラムはどうなっているのかという、設計の方に興味をもてれば、このaiboを動かすだけではなく、ロボット全体の仕事に楽しみが広がります。もしかしたら、人それぞれこの仕事で楽しみを覚えている箇所が少しずつちがうかもしれません。ただ、共通して言えるのは、実体を伴うロボットが動くことで得られる感動に魅了されているということでしょうか。
CGW:そうですよね。ロボット工学だけでなく、AIやクラウドネットワークといったイマドキの最先端技術を複合的に応用して行う仕事ですから、携われる機会は貴重です。
上月:そう。ロボットなんですけど産業用ではなく、家庭の中で人間と暮らす自律型エンタテインメントロボットという時点で、世界的にも貴重な存在ですから。それにこれで頭打ちというわけではなく、これからハードもソフトももっと進化していくでしょうし、「あれもやりたい、これもできるんじゃないか」と、未来のことを考えられるという点でも面白いですよね。可能性がまだまだたくさんあるので、非常にやりがいのある仕事です。