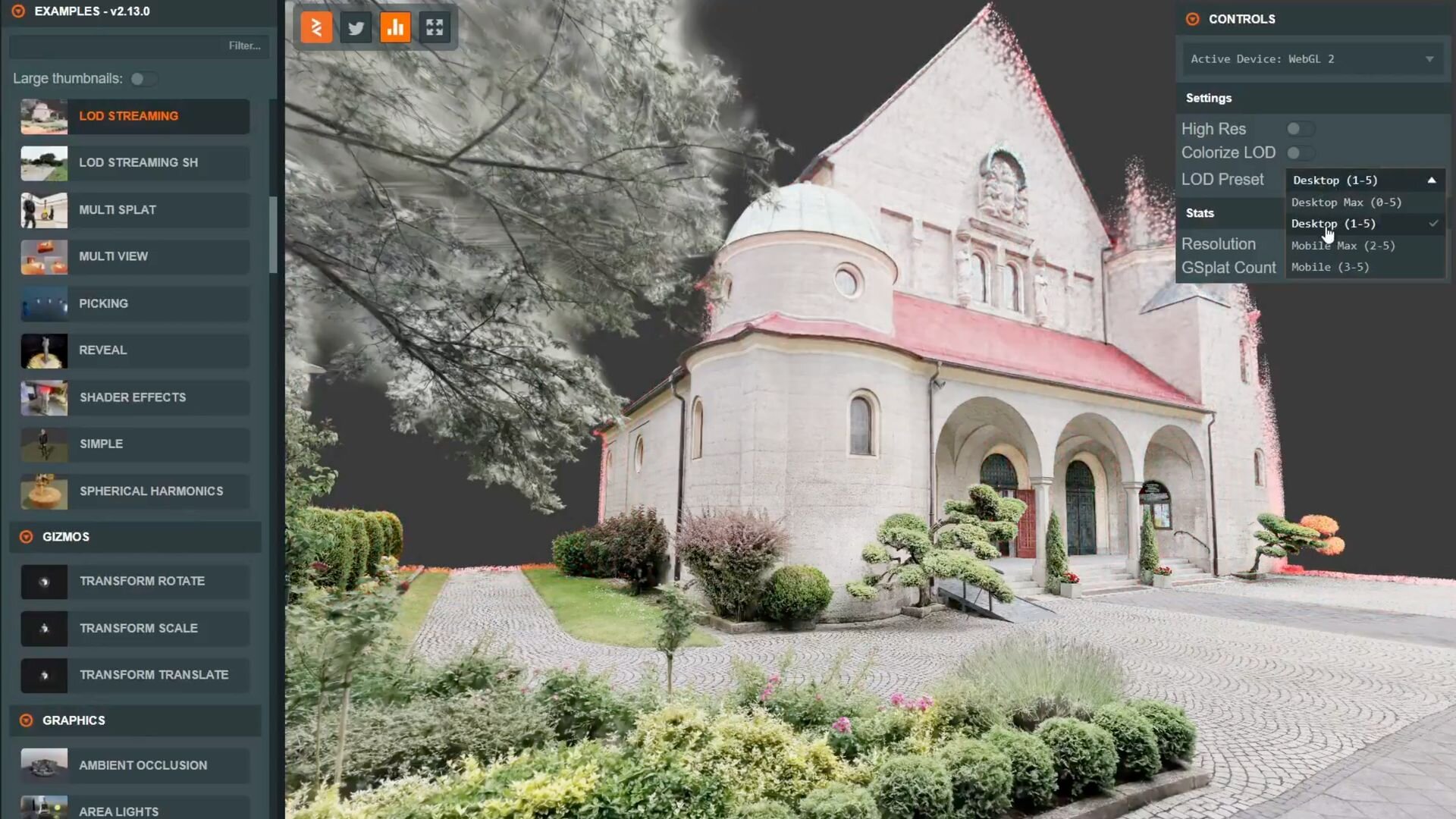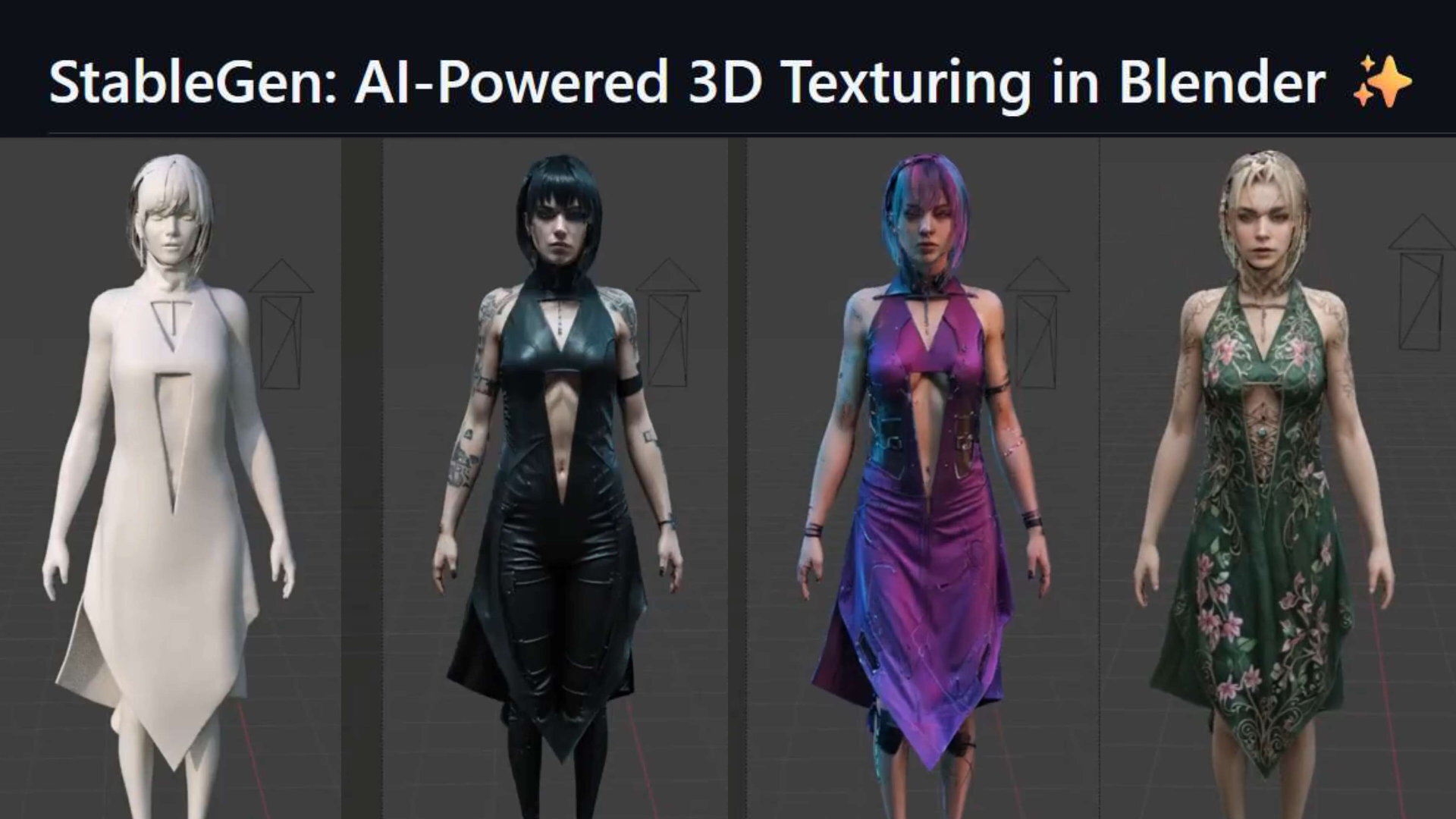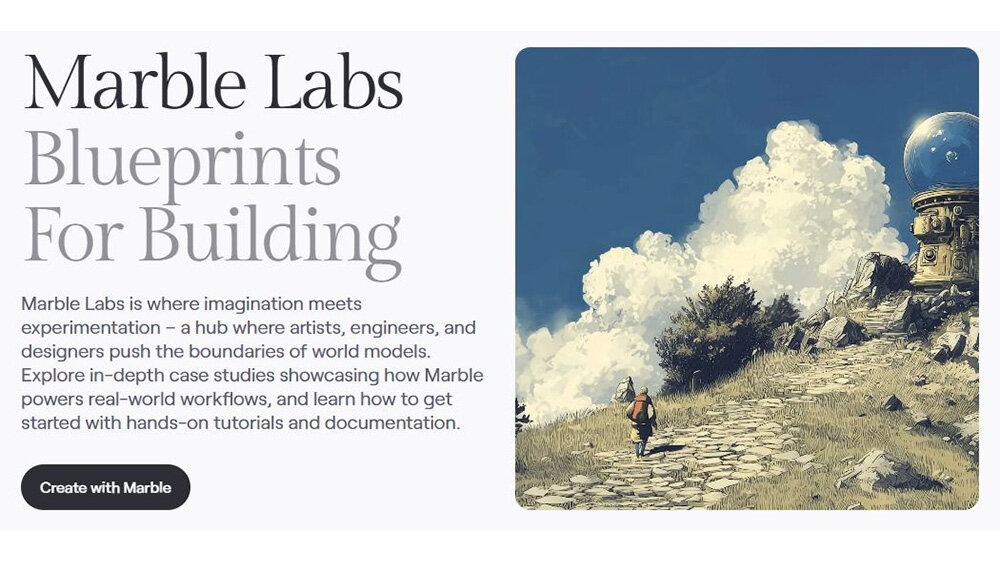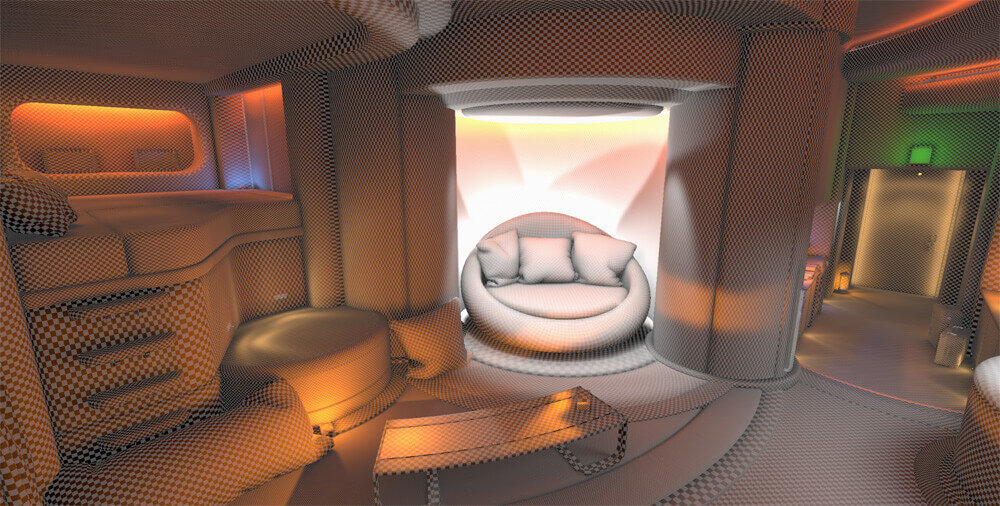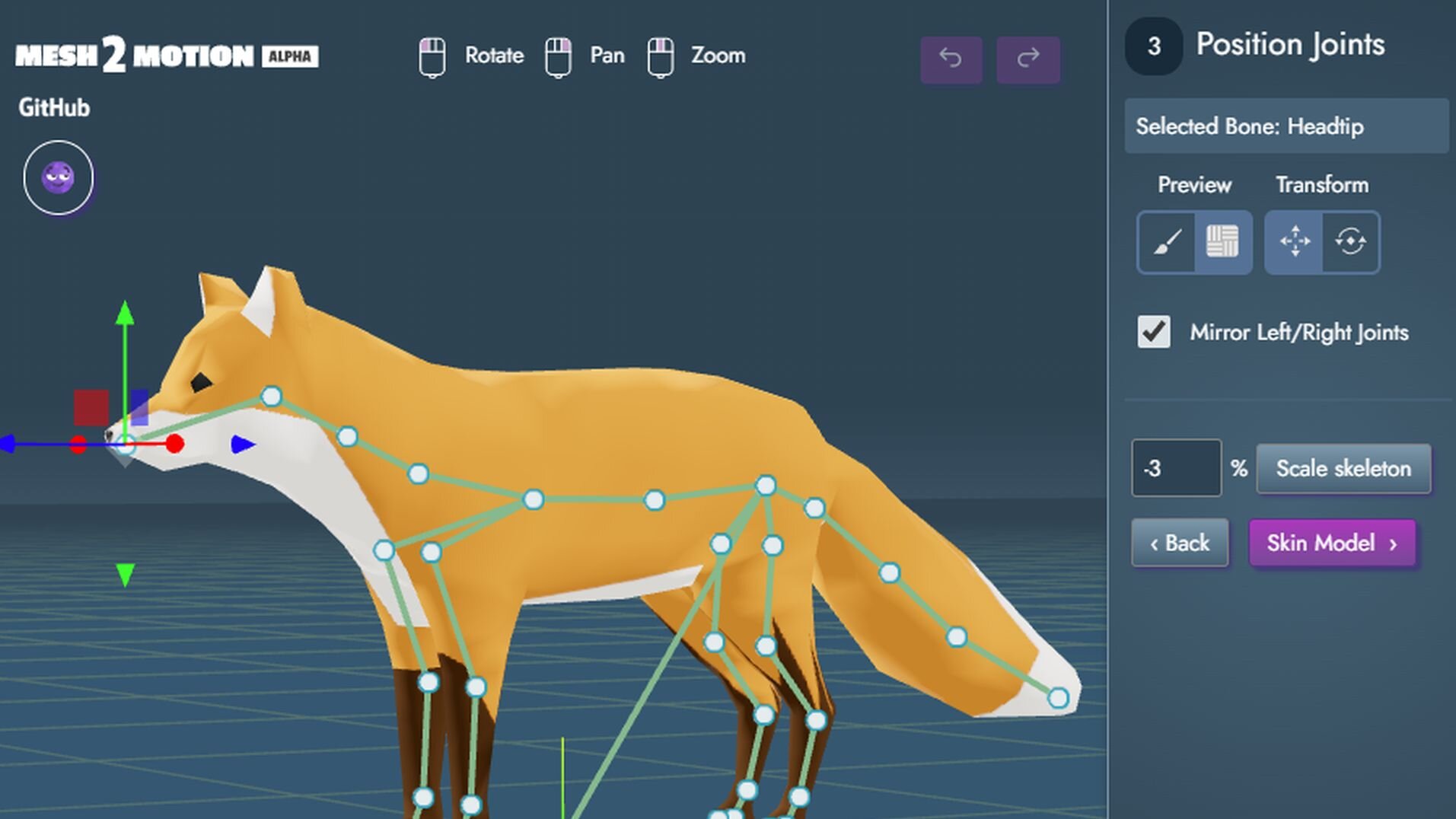「第1回 CGWORLDノベルズコンテスト」では、受賞候補2作品を選出し、CGWORLD.jpにて各作品を全12回にわたって掲載いたします。その後読者投票により各賞を決定し、それぞれ書籍として刊行する予定です。
「CGWORLDノベルズコンテスト」概要
第1回 CGWORLDノベルズコンテスト

■今後の予定
12月8日(金)〜:CGWORLD 305号とCGWORLD.jpで掲載と読者投票スタート
2024年3月頃:書籍時の扉絵イラスト募集
2024年6月頃:読者投票&扉絵イラスト結果発表
本文
四
気付くと空の上にいた。さらに一拍遅れて「夢だ」と理解する。僕は故郷の山から村を見下ろすよりもさらに高い場所に這いつくばるような姿勢で浮いている。真下にはまっすぐ前を見据えているヘビのような顔があった。龍だ、と見たことがないのにすぐわかった。鱗は銀色の光沢があり、太陽の光に反射してキラキラ光っている。コウモリの翼は力強く上下に羽ばたき、ぐんぐん上へと進んでいく。眼下に人間の姿はもう見えない。自由で孤独で美しい──これが龍か。これでいて主にはよく懐き、俗っぽい人間の料理なんかを好むのか。そっと首の鱗を撫でると、龍はこちらに目だけを向けてきた。深淵のように深くて暗い瞳に、確かな優しさと知性が込められている。こんなに美しい生き物に、果たして僕は乗せてもらえるんだろうか。手を伸ばした瞬間、空へ逃げられてしまうかもしれない。そしてたとえそうだったとしても、それは仕方ないことだと思った。
圧倒されたことによる諦めは、いっそう魅惑的な輝きを放っていた。せめて夢の中だけでも、と龍にしがみついた瞬間、龍が加速する。気付けば空が暗くなっていた。雨が降るのだ。龍はさっきまで余力を残していたらしい翼を力いっぱい羽ばたかせ、景色をどんどん後ろへ下へ置いていく。風を切って飛ぶ音に混ざってシャン、シャンと不思議な音色が混ざっていた。僕は振り落とされないように腕に力を込める。龍は上へ上へと昇っていき、ついに雲の上へ出た。さっきまでの暗さが嘘のように晴れ渡り、向こう側に山の頂上が少しだけ見えていた。龍は僕を乗せて太陽を目指し、雲の上を軽々と飛んでいく──そこでぽっかりと目が覚めた。あまりにも唐突な目覚めにパシパシと何度も瞬きをしてしまう。
外を見るとまだ真っ暗で、どうやら妙な時間帯に目覚めてしまったらしいと気付く。隣で少年の姿のローラが小さく寝息を立てていた。このままもう一度寝てしまうわけにはいかない。僕はスケッチブックと筆を取りに走った。
龍の存在を疑っていたわけではなかった。それでも見たことのないものの存在を、自然の摂理と同じように信じることは難しい。龍に乗って空を飛んだ、あの夢の感触を覚えているうちに描かなければならなかった。
昨日までに描いていた絵は、あの手触りの龍には遠かった。描きかけのそれに筆を重ねていく。すっかり乾いている薄青色の体に水を重ねて体を浮かび上がらせ、銀色に輝く鱗をナイフで削る。今まで鳥の足と同じように描いていた爪は、もっと大きく鋭くする。迷いなくこれが龍だと言える姿に近づいた頃、僕はスケッチブックを持って外に出た。完成して絵から抜け出してしまったら、小屋はひとたまりもなく壊れてしまうから。
薄暗い空だった。息は吐いたそばから白く凍ったが、雪は降っていない。静謐な空間には生き物の気配が息づいていて、僕が来たばかりの頃の森とは違うのだと今更実感した。スケッチブックを開いて、かじかんできた手で筆を持つ。真っ黒の中に思慮深さの白を置いた瞳を描き終えると、紙が空へと舞い上がった。音もなく細長い体がゆっくりと現れる。龍は上へ上へと高く昇っていき、やがてその全貌を明らかにした。
銀の鱗が昇ってきたばかりの太陽に呼応するように輝き、繊細な線を描く翼は力強く風を切る。宙で自在に踊る龍は、雲を切って軌跡を描くばかりでこちらに降りてはこない。
「なんと美しい……」
いつの間にか僕の隣にローラが立っていた。起きたばかりだからか、少年の姿のままだ。龍が起こす風にあおられブロンドの髪が揺れている。目が驚きと感動で入り混じった色に満たされていたが、その表情はどこか懐かしい何かを思い出しているようだった。
このままどこかへ飛んで行ってしまうのではないかと心配したが、龍はしばらく飛行の感覚を確かめるように宙を舞った後、ゆっくりとこちらに首を向けた。羽ばたき一つで僕たちの視線まで急降下してきた龍は、鋭くて大きな爪で真っ白な雪に足跡をつけた。まっすぐこちらを見据えてくる龍にひるんでいると、ローラがさっさと走っていってなんのためらいもなく龍にまたがった。
「さ、それじゃ行きましょう!」
馬にでも乗ったかのような気軽さに、僕はため息をついて龍に駆け寄った。後ろ足を畳んで器用に座っている龍は、ローラの暴挙にも動じず長い首を空に向けている。
「もうちょっとこう、情緒をさあ……」
「ほら、ジルさんも乗りますよ」
少年の細腕が僕を抱え上げる。浮遊感に驚いている間に、ぐんと高い場所に乗せられていた。太ももにひんやりとした鱗が当たって緊張する。このまま振り落とされたりしないだろうか。
「さて、まずは試しに飛んでもらいましょう」
ローラはポケットからハムを取り出すと、天高く放り投げた。その瞬間、龍が勢いよく空に向かって飛び立った。僕は振り落とされないように慌てて目の前のローラにしがみつく。ローラは慣れた様子で角をつかんで平然としていた。上から思い切り風に叩かれる感覚に目を閉じていると、龍のスピードが落ちてきた。どうやらハムを捕まえることに成功したらしい。
「ジルさん、ほら見てください」
「え……」
恐る恐る目を開けると、目の前に深い青色が広がっていた。下を見るとマレの森の真上に飛んだようで、木々に積もった雪が反射して白く光っているのがわかった。すぐ近くに市場もあって、長方形の屋台が道に沿って立ち並び、一直線に伸びている。春にはまだ遠く、肌を撫でていく風も氷のように冷たい。しかし青色の雲を薄藍に染め上げながら昇ってくる太陽は、まぶしくて暖かかった。龍が翼を振るたびにシャン、シャンと涼しい音が鳴る。夢の中で聞いたあの音は龍の羽ばたきだったのだ。
景色も音も今まで経験したことのないものを頭に直接流し込まれている。言葉を紡げず、代わりに涙がこぼれそうになった。
「美しいでしょう。私が長く生きてきた中でも、五指に入る景色です」
ローラが独り言のように言った。まるきり少年の姿のローラが言うと少しおかしい。おそらくローラの百分の一も生きていない僕からしてみれば、人生で一番美しい景色だ。涙を雑に拭い、ごまかすように明るい声を出した。
「そういえば、本当に龍はハムが好きなんだね。こんなに言うことを聞いてくれるなんて思わなかった」
「ええ、私もです。あれ、嘘ですし」
「……えっ」
「ジルさんが想像したとおりに絵が実体化するのを逆手にとりました。ジルさんに嘘の知識を吹き込めば、私に扱いやすい龍が作れるのではないかと」
君はよい子ですねえ、とローラが龍の鱗を撫でる。
「え、じゃあ龍は最初に乗った人間を主とみなして一生連れ添うっていうのは」
「嘘です」
「懐くとどこにでもついてきて、絶対主人を見失わないっていうのは」
「嘘ですね」
「じゃあ最初に話してた、プライドが馬鹿みたいに高くて乗せてって言ったら鼻で笑われるっていうのは」
「それは本当。でも、そんな龍になってしまったら困るではないですか。だからジルさんの中にあるイメージを上書きしました。誇り高いけど主にさえなればちょっと大きくて飛べる犬くらいの認識で描いてもらえればちょうどよかったのです」
つまり一冬かけて僕が描いたのは、ローラ専用のオーダーメイド龍だったわけだ。僕は深々とため息をついて「君、本当にそれでいいわけ?」と龍の背中を叩く。龍は知らん顔でまっすぐ明け方の空を見つめている。そういえば最初に龍に飛び乗ったのはローラだった。これもすべて計算のうちなんだろう。嘘をつかれたことに反射的に怒れず、というよりも僕が故郷に帰り、ローラがその後面倒を見るためには必要な嘘だったことを考えると、もはや怒りもなくただ脱力してしまった。
「それにしても、やはり良い音で飛びましたねえ。知っていますか、ジルさん。龍の羽ばたきの音は住んでいる場所によってそれぞれ違うんですよ」
「……それも嘘?」
「いいえ、本当です。私もこの音は聞いたことがありませんので、あなたの想像力に感謝しなくてはいけませんね」
嘘だったとしてもここまで断言されると「そうなのか」と思わざるを得ない。ローラが美術商で本当に良かった。この話術、詐欺師としても一流だろう。僕がそんなことを考えているなんて思ってもみないであろうローラは「さ、試運転も済んだし戻りましょ」と言って龍の背を叩いた。
ローラの言葉に従って、龍がマレの森へと降下していく。いっさいバランスを崩さず丁寧に着地した龍に「ありがとう」と返したが、龍はまたも僕のことを無視した。どうせ嘘をつくなら「主の同乗者には優しい」なんて条件くらい付けてくれればよかったのに、と少しだけローラを恨めしく思った。
龍の背中から軽やかに降りたローラは、雪の上に転がるように着地した僕を振り返って微笑んだ。その表情は、大変無様な格好になっている僕をからかう顔ではなかった。
「さて、随分かかってしまいましたが。ジルさんの故郷に帰りましょう」
その言葉に息をのむ。そうだった。ついに帰れるのだ、僕の村に。慌てて立ち上がると小屋に向かって走り出す。外はすっかり太陽が昇って明るくなっていた。
食料と水と画材。持っていくのはそれだけだった。五年間過ごした小屋で、それしか物を持たなかったとも言える。持ってはいけない絵なんかは全部小屋に置いていくつもりだったから(ローラが良しなにしてくれるらしいし、任せてしまった)思ったよりも小屋は空っぽにならなかった。
「それじゃ、行きましょう」
ローラはすっかり懐いた龍を慣れた手つきで撫でている。「今行く」と返事をして、小屋の扉を閉めた。雪は少しずつ解けて、地面からはもう黒い土が見え始めている。龍に乗ってローラの腰につかまった。この体勢が一番安定すると、何度か試運転をしてわかったのだ。ローラが軽く龍の首筋を叩くと、翼が大きく持ち上がり体が宙に浮いた。一度の羽ばたきで小屋の高さまで視点が持ち上がる。そのまま風を感じていると、木々が生い茂るかつて真っ暗だった森は、もう眼下にあった。龍は迷わず北へ飛ぶ。マレの森は、追いすがってくることも迷わせてくることもなく、ただずっと僕の後ろ側にあった。
流れていく雲をぼんやり眺めていると、ローラが振り向いた。
「静かですね。やっと帰れるのに」
「あー……まあ、うん。ちょっと現実味がなくて」
「本当に帰れると思ってなかったから、いざ帰れるってなるとちょっと森の方に後ろ髪引かれるなあ、みたいな顔してますよ」
「いやに具体的だね」
実際ローラの見立ては間違っていない。僕は龍の背に揺られながら、このまま森へ引き返すことはないだろうかなんて考えてしまっていた。帰りたいと言ったのは僕なのに。この身勝手な気持ちは、いったいどこから来たのだろう。今年の冬は前と違って夢を見る回数も格段に減っていたからだろうか。あるいはマレの森から無理に逃げ出そうとしなかったから、森に対する余計な敵愾心を抱かなくて済んだからだろうか。あるいは一冬を、ローラと共に過ごしたからだろうか。
「森から出られたら、もっとせいせいするものだと思ってたんだ。なのにどうしてこんな気持ちにならなきゃいけないんだ」
「そりゃあ、不本意だろうと長く住んだらそこが帰る場所みたいなものでしょう。離れるときに寂しくなるのは仕方がないことですよ」
「……寂しい? 僕が?」
「ええ。とっても寂しそうな顔をしていますよ」
ペタペタと自分の顔を触る。当然、自分の表情は読めなかった。僕が返答に困っているうちに、ローラは前を向いてしまう。空は冬の終わりらしい澄んだ青い色をたたえていて、僕と一緒に悩んでくれそうな天気でもなかった。
「明日の昼には着きますからね」
それは龍に言って聞かせたのか、僕に言っているのかわからなかった。ただその落ち着いたトーンに「気の利いた別れでも考えておけ」とでも言われているようで、突き放された気持ちになった。そうだ、僕はきっとローラと別れることが寂しいのだ。いつまでも龍に揺られたままでいたいと思ってしまうのは、あの森を懐かしんだことでは、きっとない。
続きは毎週月・木曜に順次公開予定です!
日程は公開リストよりご確認ください。
『龍が泳ぐは星の海』はこちらに掲載しています。
読者投票
読者投票は以下からご参加ください。ぜひお気に入りの作品に投票をお願いします!
読者投票はこちらから※締切:1月25日(木)23:59まで
※回答は1人1回までとさせていただきます。