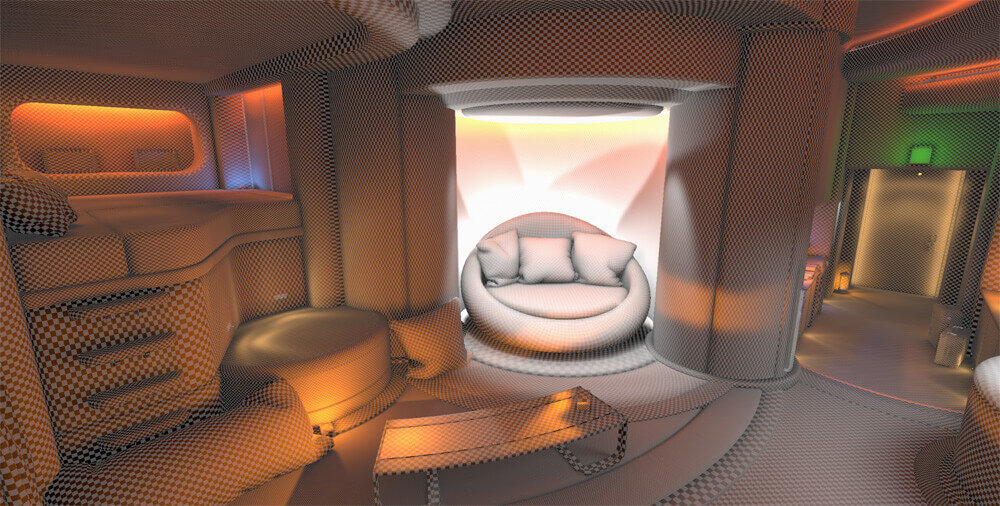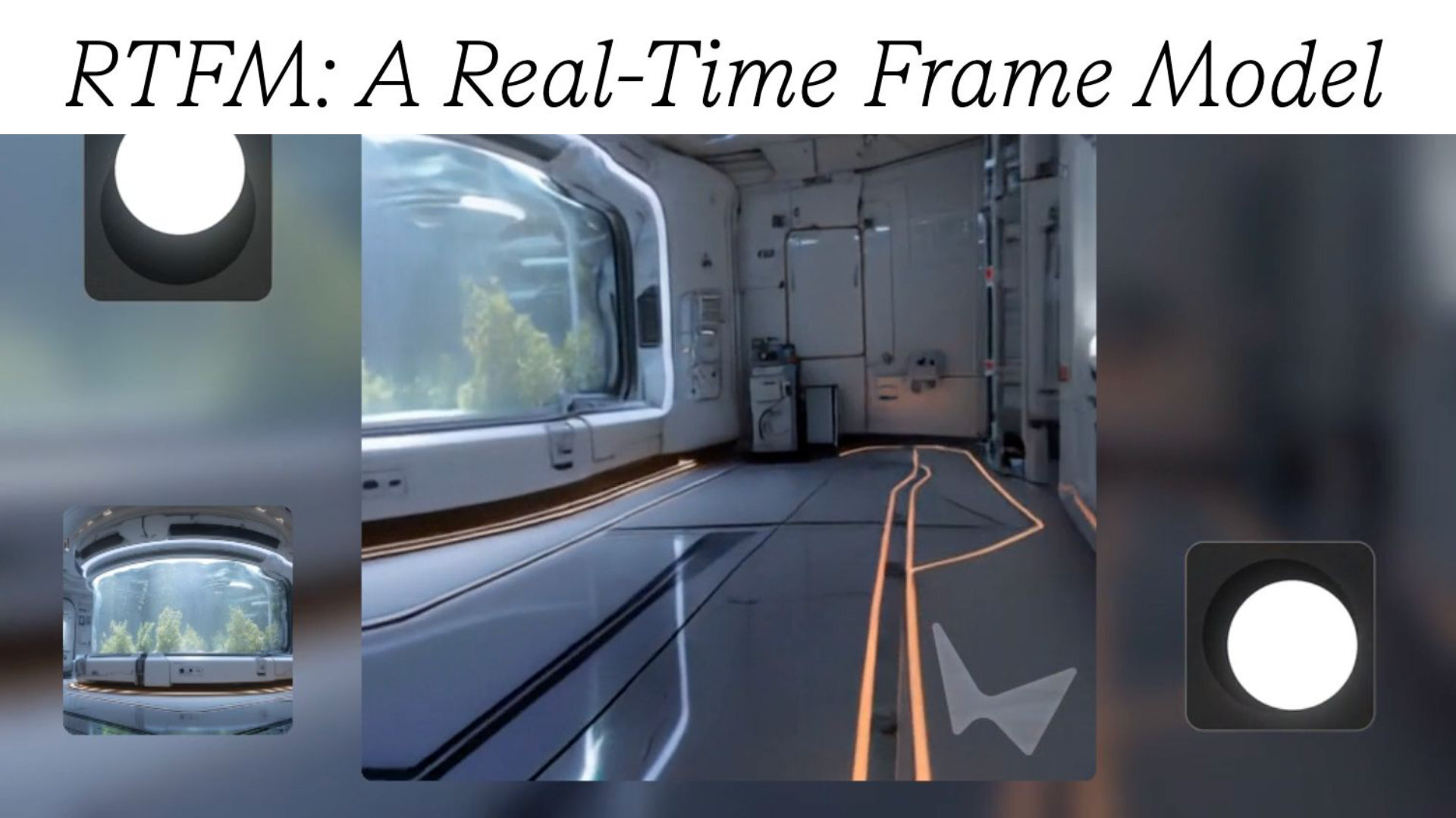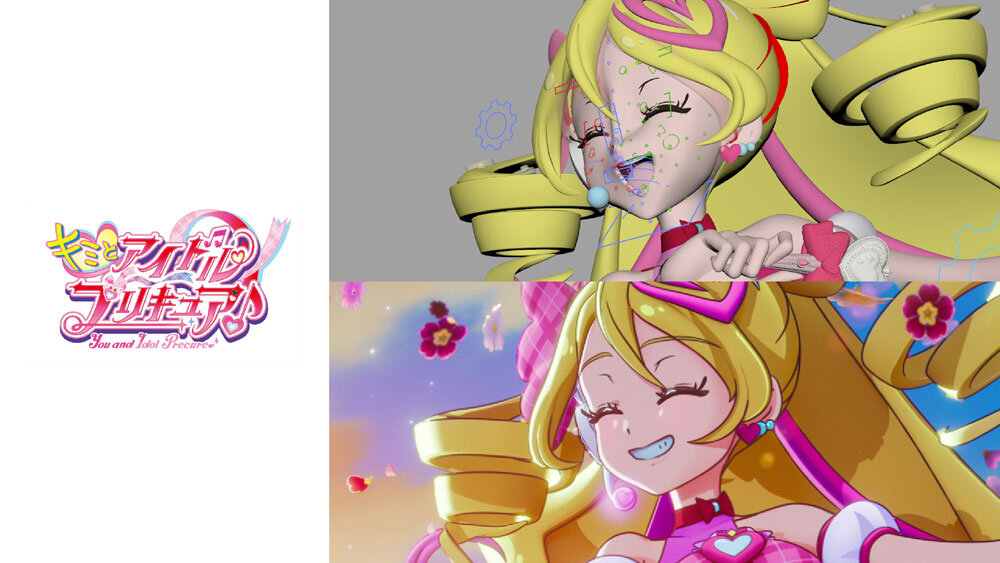「第1回 CGWORLDノベルズコンテスト」では、受賞候補2作品を選出し、CGWORLD.jpにて各作品を全12回にわたって掲載いたします。その後読者投票により各賞を決定し、それぞれ書籍として刊行する予定です。
「CGWORLDノベルズコンテスト」概要
第1回 CGWORLDノベルズコンテスト

■今後の予定
12月8日(金)〜:CGWORLD 305号とCGWORLD.jpで掲載と読者投票スタート
2024年3月頃:書籍時の扉絵イラスト募集
2024年6月頃:読者投票&扉絵イラスト結果発表
本文
二
僕は故郷の家にいた。夢だとすぐに気が付いた。父がロッキングチェアに座り本を読んでいる。母が鍋をかき混ぜている。リラが母にまとわりついて、前足で足を叩いていた。僕はそれを眺めている。手にはスケッチブックと、画材を詰め込んだバッグがあった。ずっとここにいたいのに、口が勝手に動き出す。
「いってきます」
母が振り向いて小さく微笑んだ。父も本から僕に目を移す。リラだけは僕の方を見向きもせず、母がかき混ぜている鍋の中身をどうにかひと舐めできないかと画策していた。
「いってらっしゃい」
夢の中で、夢だとわかっていて、僕の視点で動いているのに意思とは違う方向に体が動く。僕はスケッチブックを持って山へ行く。動物のスケッチをするためだ。父から絵を描く基本を教えてもらった後は、ずっと山の動物を模写してきた。動物たちはじっとしていないから、短い時間で特徴を捉えることを覚えた。
故郷の山はまだ開かれていない場所も多く、特に冬の間は立ち入ってはいけないとされている場所があった。その地帯に生えている木にはピンク色の紐が結んであって、真っ白な世界の中でポツンと浮いているように見えた。
その日も適当な岩に腰かけてスケッチブックを開いていた。幼少の頃から口を酸っぱくして「奥へ行くな」と言われ続けていたし、大人の言いつけを破るほど豪胆な子どもではなかった僕は、ピンク色のラインを越えるつもりなんてなかった。本当になかったのだ。
見たことがない鳥がいた。頭が青くて、羽の先に向かってだんだん白が広がる美しい鳥だった。初めて見るものだったから思わず追いかけた。やがてピンク色の紐が見えて、反射的に立ち止まった。鳥は山の奥へ飛び立っていく。不思議な焦燥感に駆られ、この鳥を逃がしてはならないと妙な気持ちに支配された。山の奥に興味すらなかった僕は、その日、軽々とピンク色のラインを越えた。
振り返ると、見慣れた故郷がはるか遠くに見えた。慌てて引き返そうと走っているのに僕の家がどんどん遠ざかる。それなのに食卓を囲む楽しそうな家族の光景だけが目の前に浮かんできて、僕は思い切り手を伸ばした。
「いかないで……!」
手を伸ばした瞬間に家族が遠ざかる。気付いてもらえない。どうして、どうして僕だけがこんな目に遭わないといけないんだ──
目が覚めた。何度見てもこの夢の後味は最悪で、僕は眠りながら伸ばしていたらしい手をぱたりとベッドに落とした。
「おや? お目覚めですか」
「…………だれ?」
エプロンを着た三つ編みのブロンド美女が食卓についていた。美女は「朝ご飯ですよ」と言いながら僕のもとへやってくる。その間に身長が縮み、ブロンドがほどけてウェーブのかかったボブに変わり、顔立ちがそばかすの散らばった幼く地味なものへと変化していく。
「おはようございます。ずいぶんうなされていましたね。朝ご飯にしましょう。たいていのことは食事をすればなんとかなります」
「……はい」
見た目のインパクトというのは、それ以外の感覚を忘れさせる威力があるらしい。僕はローラが食卓に戻っていく後ろ姿を見送ってようやく、パンとバターの香りが小屋中に充満していることに気付いた。夢見の悪さと寝起き一発目に飛び込んできた映像のせいで、痛みを訴える頭を起こしてどうにか食卓につく。トーストとスクランブルエッグと、昨日も食べたハム。
「い、いただきます……」
「召し上がれ。あ、鶏が卵を産んでいたので頂きましたよ。昼は市場で何か買ってきてくださいね。さすがに三回連続で同じハムをメインディッシュにするわけにもいきませんし」
スクランブルエッグとハムをトーストに挟んで大口を開けながらローラが言う。朝食を食べながら昼食の話をされてもピンとこない。とりあえずうなずいておいた。
「今日は私、森の奥に行ってみることにします。ジルさんは試しに龍を描いてみてください。私とジルさん、二人くらい乗れる大きさでお願いしますよ」
「簡単に言うなあ……え、君も乗るの?」
「当たり前じゃないですか」
ローラは当然とばかりに胸を張る。曰く龍を扱うにはそれなりに気を遣うため、慣れている彼女に任せた方がいいらしい。トーストに載せた具材をこぼしながら、ローラはにやにや笑っている。
「龍がいれば商売も格段に楽になりますからねえ。海を渡るのに船を使う必要もないし、雲の上にお住まいのお客様のもとへも一直線ですし……」
「え、ちょっと待って。君、僕が龍を出したら自分のものにする気?」
「ええ、ジルさんを故郷まで送り届けられたらそのまま頂いて帰ろうかと」
「僕が描くのに?」
「絵を連れ出してくれるのは森でしょう?」
「それはそうだけど……」
「だいたいジルさんが龍なんか持っててもしょうがないでしょう。故郷に帰ったらそのままそこで暮らすんですから」
それはそうかもしれないが、故郷を出されると弱い。ということにローラはとっくに気付いているのだろう。不器用にパンをかじる姿を見て「だから昨日は二口で食べたのか」なんて考えが浮かぶ。ちまちま食べているとこぼすから。
話を聞く限り、龍は地上からは雲がかかって見えないくらいの山のてっぺんで静かに暮らしているのだとか。
「僕は見たことないけど、本物に乗せてもらえばいいんじゃないの? 住んでいる場所は知っているんだろう?」
「わかってないですねえ。あの方々は住んでる場所も高ければプライドも高いんですよ。足元みられて高いお金を取られて山のふもとまでしか送ってくれないのがオチです」
「へー」
「ごちそうさまでした! では私、交渉に行ってまいります」
「え、あ、うん。お願いします……」
うまいことかわされた気がする。龍の所有権は絵から出してからゆっくり話し合うことにしよう。そもそもまだ一枚も描いていないわけだし。僕もパンを飲み込むと手を合わせて立ち上がった。頭の痛みは消えている。たいていのことは食べればなんとかなる、なんて。ローラの言葉もあながち嘘ではないらしい。
続きは毎週月・木曜に順次公開予定です!(祝日及び年末年始を除く)
日程は公開リストよりご確認ください。
『龍が泳ぐは星の海』はこちらに掲載しています。
読者投票
読者投票は以下からご参加ください。ぜひお気に入りの作品に投票をお願いします!
読者投票はこちらから※締切:2024年1月25日(木)23:59まで
※回答は1人1回までとさせていただきます。