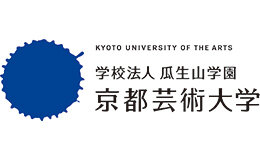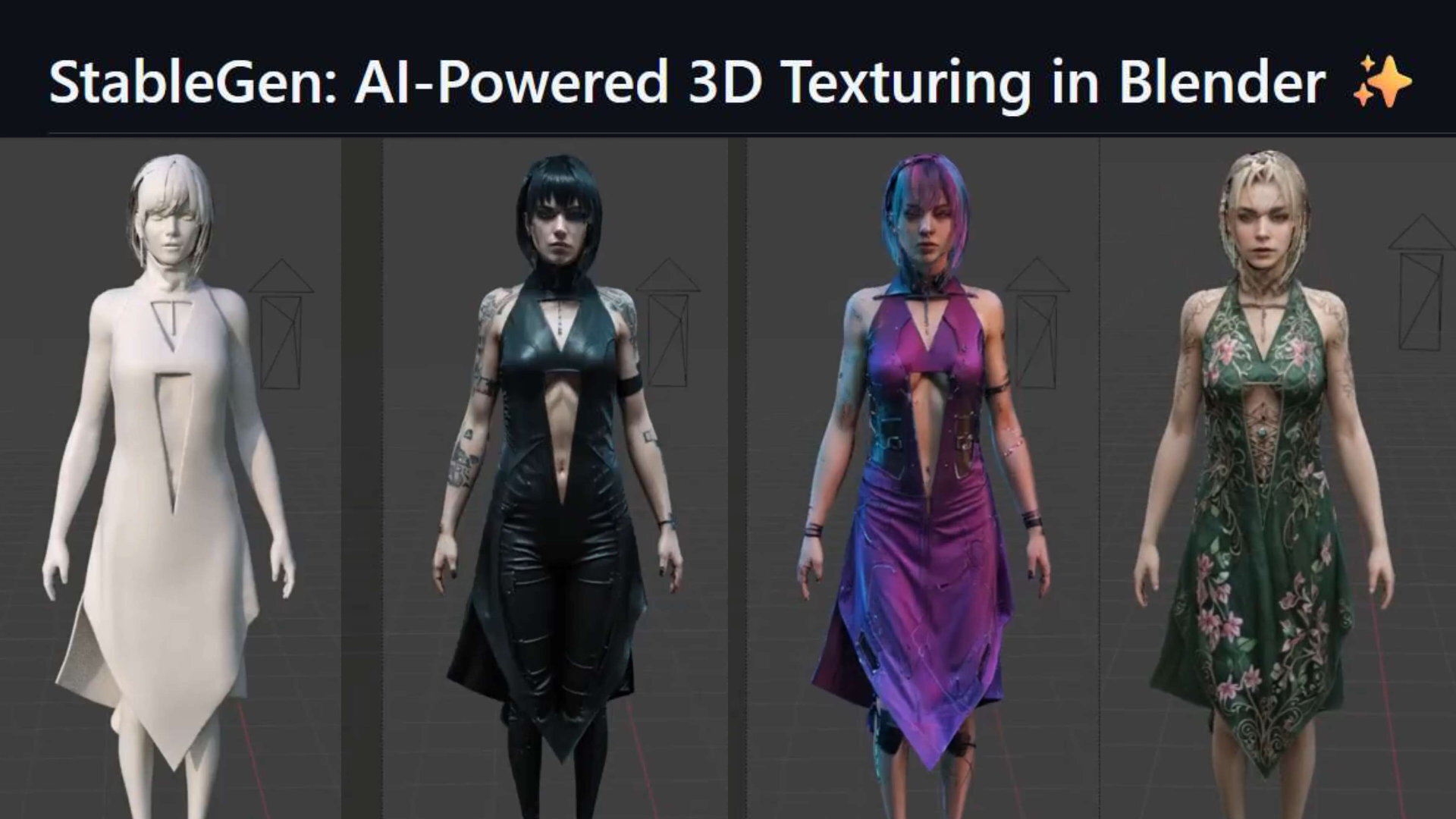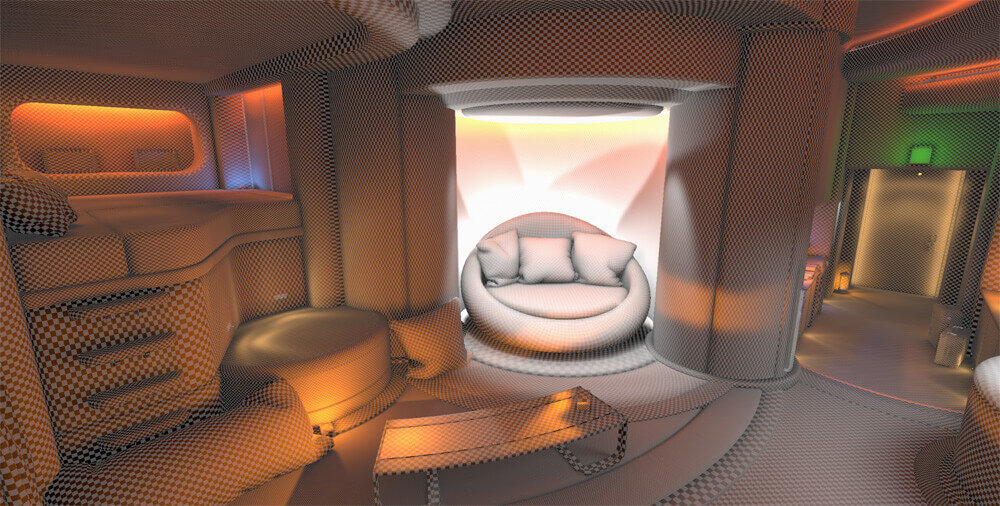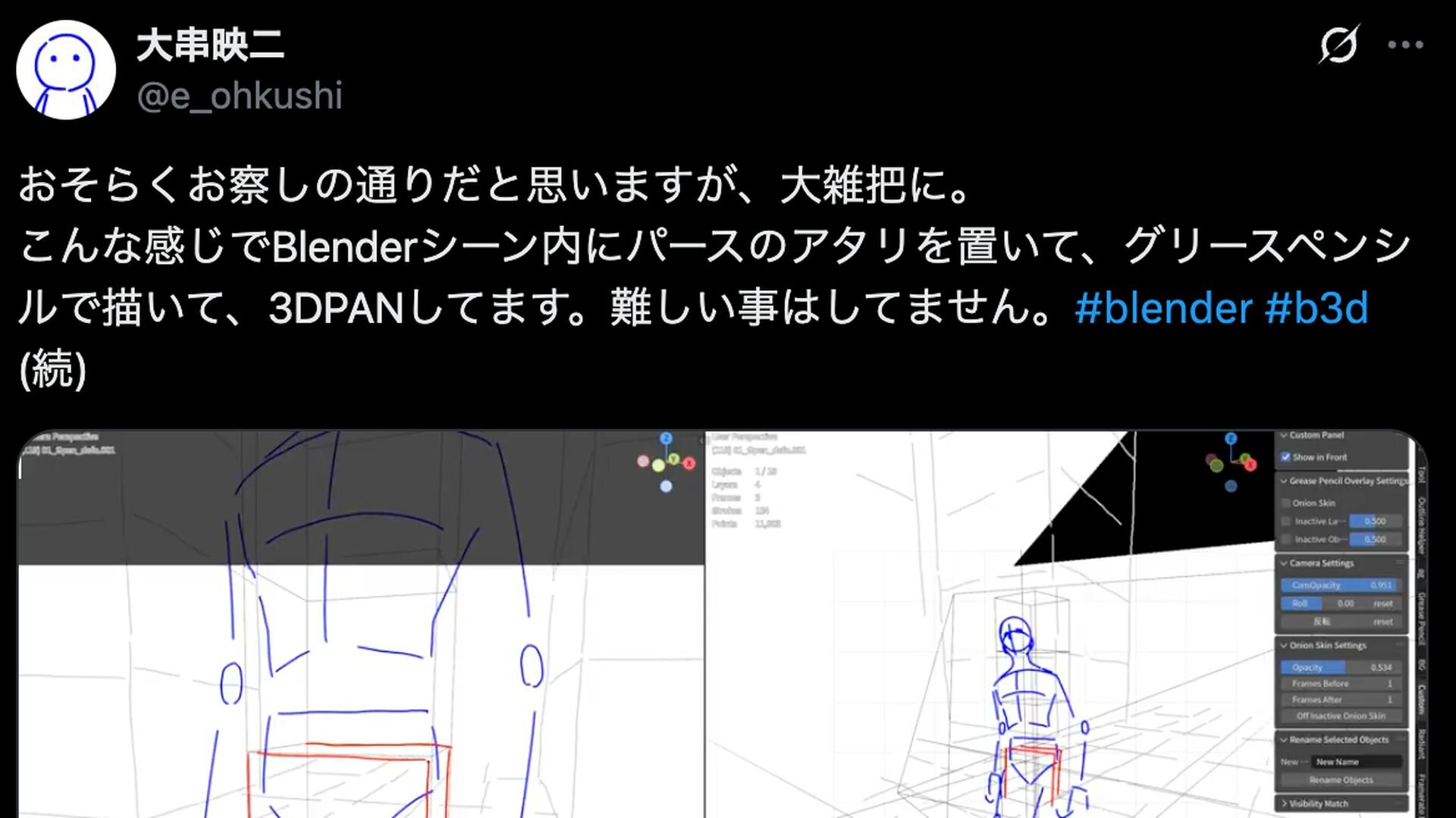「第1回 CGWORLDノベルズコンテスト」では、受賞候補2作品を選出し、CGWORLD.jpにて各作品を全12回にわたって掲載いたします。その後読者投票により各賞を決定し、それぞれ書籍として刊行する予定です。
「CGWORLDノベルズコンテスト」概要
第1回 CGWORLDノベルズコンテスト

■今後の予定
12月8日(金)〜:CGWORLD 305号とCGWORLD.jpで掲載と読者投票スタート
2024年3月頃:書籍時の扉絵イラスト募集
2024年6月頃:読者投票&扉絵イラスト結果発表
本文
―しばらく、訓練の日々が続いた中でのこと。
「なあ、純一。外ってどんな感じだ?」
と食堂で聞かれ、純一は一瞬、ティトの言葉の意味がよくわからなかった。
「外だよ、外」
「どうって……あんまりおもしろくはないよ」
純一の心の中に、空虚な日々が浮かび上がる。自宅には戻らないままずいぶんと日が経っているが、特に戻りたいとも思っていなかった。
「もっと具体的な話だよ。この町には何があるんだ?」
そう言われ、純一はこの川浜市の特徴を賢明に記憶の中から捻り出そうとした。
「ええと、まず海のほうに宇宙港があるよね。今は、軌道上に物資と人員を送る定期便が出てる。中心部はそんなに大した繁華街じゃないけれど、飲食店とか、そこそこお店はあったかな。あとは郊外。このケージの近くに、ショッピングモールがある。そんなとこ」
「ああ、あれ! ケージに行くとき、車の窓から見えて、気になってたんだ〜」
シーナはティトに比べて丸い目を輝かせ、人よりやや大きめの口を、にんまりと横に広げた。
「そんなに珍しいかな?」
「いや、だって私たち、全然外出られないし!」
ノウムに一刻も早く慣れることに集中しており、純一はまったく外出していないことに気付いていなかった。
「いつから出かけてないの?」
「俺は八歳、シーナは六歳の頃にクアドロに連れてこられてから、一度もない」
純一の目が見開かれた。
「なんか……ごめん」
そんな言葉が口をついて出た。最初に出会ったとき、純一は彼らを特別な存在だと思い込んでいたが、海外から連れてこられてきた彼らは、ノウムとしての力を高めるためだけに日々を過ごしていく中で、純一が普通と思い、通過してきたものをまったく経験していない。彼らも人間なのだから、外出もしたくなるし、未知の体験に興味を持つのは当然のことだ。少しの期間を彼らと共に過ごしてきたことで、彼らを理解した気になっていた自分の不見識を、謝りたくなったのだ。
「謝られてもな。もうずっとこんな暮らしだからな」
「どんなだったか、聞かせてくれればそれでいいし……」
「そっか」
純一は、そんな会話の間も、黙々と食事をしているマレが気になった。
「マレは? いつからいるの?」
「私はクアドロで生まれて、ずっとケージにいるから」
「そう」
こうなったら、やるべきことは一つだ。
「僕から聞くより、見たほうが早いよ。一日くらい外出できないか二宮さんに聞いてみる」
その日の訓練の後、純一は早速、タンと予定を話し合う二宮に、この件を聞いてみた。
「だめだ」
有無を言わさず、二宮は首を振る。何度聞き返しても答えは同じ、と言っているようだ。
「内覧会まであと一か月。当日はみんなにはベストを尽くしてもらいたいと思っている。そのためには、適切な管理下で最大限集中できる環境を維持するべきだ。余計な情報を入れて欲しくない」
どうしたら、この壁を崩せるだろうか。そう純一が考えていたとき。
「先生、私からもお願いします」
声が聞こえた。
「マレ?」
二宮のまとう硬質な空気が、ほんの少しだけ緩んだように純一には感じられた。おそらく、こんなお願いをマレがするのは初めてのことなのだろう。
「二宮さん、お願いします。こう……外の世界を知っておいたほうが、訓練をする上でも、今後のイメージをしやすいと思うんです」
適当に思いついた理由を並べてみただけだ。二宮は、少しうつむいた後に、
「いや―」
と言いかけたが、それをタンが遮った。
「俺が監視役として付いて行きますよ。ちょっと離れたとこから見張る感じで」
「その間の仕事はどうするつもりだ?」
タンはギョロッとした目を空に向けた。どうも、考え事をするときはこうなるらしい。
「―まあ、前日の内に……なんとか済ませておきましょう! どうにかして空けますから」
二宮は、大きくため息をついた。
「わかった。一度だけだぞ。それと、くれぐれも目を離すな」
「ありがとうございます!」
「―ありがとうございます」
二宮が去っていった後、純一とマレは二人でタンに礼を言った。思わぬ助け船だ。
「でもなんでああ言ってくれたんですか? こう言ったらなんですけど、忙しくなるだけじゃないですか」
タンが笑った。
「いや、俺も元々は被検体の一人だったからな。シードに半端な適正しか出せなくて、今は所員になってるが。だから、お前たちの気持ちもわかる」
「そうだったんですね」
やや驚く中で、純一はある違和感に気付いた。
「タンさんはノウム経験者なのに、逆流が起きていないですよね?」
「ああ、それ。俺は“ここ”に出たから」
タンが口を大きく開けると、その舌がゆっくりと伸びていき、首の根元まで届いた。
「すごい……ですね」
「だろ? 丸めたまま喋るの、大変なんだよ」
純一は、早速ロッカールームでティトに先ほどの件を報告した。
「行けることになったよ。今週末だって。条件はついてるけど……」
「ほんとか!?」
ティトは鋭い目を大きく見開いて喜ぶ。その表情は、シーナと同じだ。
「いや、素晴らしい! さすがだぜ!」
「最後の一押しはマレとタンさんだったんだ。僕だけではだめだっただろうな」
それをティトは笑って否定し、
「お前のおかげだよ。いやー、だいぶ前に俺とシーナが二宮に言ったときは、通じなかったからな。お前が頼んだからこそ、マレも乗っかってきたんだろ? 多分」
「そうかな? でも、みんな外を知らないのはさすがにどうかと思ったし、喜んでくれるならうれしいよ」
ティトは強くうなずいた。
「ああ! 可哀想な感じを出してお前に頼んだらいいってシーナが言ってたんだけどよ。うまくいって本当によかった」
「なんだって?」
話を聞くに、どうもティトとシーナは、外出許可を得るために純一を誘導していたらしい。少し腹は立ったが、これも三人と交流を深めるチャンスだし、何よりも、純一自身、彼らの外への憧れを聞いているうちに、少しだけ外が恋しくなってきたのも確かだ。気分転換も兼ねて、少しでも外出を楽しもうと頭を切り替えた。あまり好きな町ではないが。
かくして、週末が訪れ、外出の日がやってきた。やや曇っているが、雲の隙間から日が差しており、外出にはちょうどよい天気と言える。
当日までティトとシーナは外でやりたいことを考えてばかりで、ある日、中庭の屋根を閉じての低酸素下訓練では、ノウムになっている間に集中力を欠き、その場に昏倒してしまうという事態になった。ばつの悪そうな顔をしてコクーンから出てくるティトとシーナを初めて見たことにも純一は驚いたが、
「これが続くなら、外出はなしだ!」
と二宮が怒りを見せた途端、凄まじい精度でノウムとしての訓練をこなす姿にも驚かされた。
「―ようやくこの日が来たな!」
と言うティトは、マスクをしている。逆流によって頬に出ている鱗が、人目につかないようにするためだ。
「今までの人生分遊ぶ!」
と高らかに宣言するシーナは、首にストールを巻いていた。こちらも、首を覆う棘を隠すためである。
「よし、行くぞ」
そう言って、タンはバンのドアを開けた。彼が運転席に乗り込むと、続いて四人の被検体も、後部座席に乗り込んでいく。
「まずは……」
と、運転席のタンが口を開いた瞬間、
「宇宙港です」
と、いつものように長い手袋を手にはめたマレが言う。青白い髪が目立ちすぎないように、今日はフード付きの服も着ていた。食堂でこの日の計画を立てたときも、ティトとシーナがそれぞれの行きたい場所を挙げる中で、彼女は宇宙港の全貌を見ることを希望していた。そのため、本日は、宇宙港に行った後、町の中心部に向かうというルートだ。
「わかった、わかった」
車に電源が入り、車内をわずかな振動が包み込む。
「マレは本当に宇宙が好きだからなー」
とシーナが言うと、
「そ、そんなことないって」
少し恥ずかしそうにマレが答える。その言葉とは反対に、その紫の瞳には、いつもと違う光が灯っているように純一には感じられた。
宇宙港の近隣にある、丘の上の駐車場に一行は到着した。宇宙港にはコンテナや格納庫が並んでおり、その中心には、巨大な筒がある。その先端部は、空に向かって傾斜していた。
「へえ、こんな見晴らしのいいところがあったんだな。前も来てたのか?」
タンが少し感心した様子だった。
「両親が生きてた頃は、連れてきてもらったりしてましたね」
「―確かにいい眺めだな。海も見えるし、よく晴れてるし」
ティトが漏らす。宇宙港への言及がないことから、まったく興味がないことがわかった。
「そうだね。ここから一日に何度か定期便が出るんだ」
「あれって何?」
飛行場でいう滑走路の代わりに配置されている筒をシーナが指で指したとき、
「マスドライバー」
と、純一とマレが同時に答え、目を見合わせた。
「マス……? ああー、ちょっと映像では観たことある。そうか、あれが本物かー」
「クアドロで、ちょっとじゃなく観たと思うけど」
マレがぼやくのを聞きつつ、純一は説明を始めた。
「ここにあるのは、砲身内にあるコイルと飛翔体のコイルを使った電磁誘導型なんだよね」
「そ、そうなんだ」
早口でまくしたてる純一に対して、シーナはややうろたえている。
「ええと、私たちが宇宙に行くのにもそれが使われるの?」
純一は笑顔でうなずく。
「けど、ここのマスドライバーは少し型式が古いんだよね。もっと大規模な港からなら、今は二本のレールで打ち上げる」
「レールガン」
純一とマレの声が重なり、ティトとシーナが苦笑しながらため息をつく。
「あー、わかったわかった。お前らが宇宙大好きなのはわかったよ。そろそろ街のほうに行こうぜ」
純一はもう少しこの光景を見ていたかったが、ティトは一刻も早く中心街に行きたいらしい。今日はあくまで外の世界をよく知らない彼らを優先すべきだろう。そう思ったとき
「ねえ、定期便っていつ出るの?」
マレがそう言った。
「えっと……」
純一は今までのようにインプラントを見ようとして、シードには時計機能がなく、腕時計を着けていることを思い出した。
「今が十時半だから、あと三十分後ってとこかな」
「みんなさえよければ、見ていきたいな……」
マレが純一たちを見る。
「僕はいいよ」
純一がうなずくと、ティトとシーナも、
「―しょうがねえなあ」
「しょうがないね」
と了解した。
定期便が出るまで、ティトとシーナとタンは車で待機していたが、マレだけはずっと宇宙港を見続けており、それが気になった純一も、マレの隣に立っていた。だが……
「そんなに宇宙のことが好きだったの?」
「まあ……ね」
最初にした質問から、会話が発展せず、二人の間には沈黙が流れている。
海から吹く風が、宇宙港の格納庫やコンテナの間をすり抜けて、二人の真横を通り過ぎていったとき、
「その……なんでそんなに宇宙が好きなの?」
と、純一は聞いてみた。すると、マレは純一のほうを向く。
「そんなびくっとしなくてもいいでしょ。この前は、私こそごめん。爪を立てたりして……」
そう言って、マレは手袋に覆われた自分の爪を見た。大分時間が経っていたが、最初に会ったとき、感情にまかせて爪を突きつけたことを、ずっと彼女は気にしていたのだ。
「それはもういいって。あのときは、僕も悪かったから……」
マレがうなずく。
(そこはうなずくんだな。しょうがないけど)
「私は……」
そう呟いて、マレは再び宇宙港を見た。
「あそこから続いている場所だけが、行くべきところだと思っているから」
至るまでの過程は違えど、その思いは自分と同じだと純一が感じたとき、宇宙港の方から推進剤の燃焼する轟音が響いてきた。
物資や人員を搭載した定期便は、マスドライバーの中で大きく加速し、打ち上げられていく。空に描かれていく白い軌跡を、二人はしばらくの間見つめ続けていた。
続きは毎週月・木曜に順次公開予定です!(祝日及び年末年始を除く)
日程は公開リストよりご確認ください。
『美術商ローラと家路を急ぐ青年』はこちらに掲載しています。
読者投票
読者投票は以下からご参加ください。ぜひお気に入りの作品に投票をお願いします!
読者投票はこちらから※締切:2024年1月25日(木)23:59まで
※回答は1人1回までとさせていただきます。