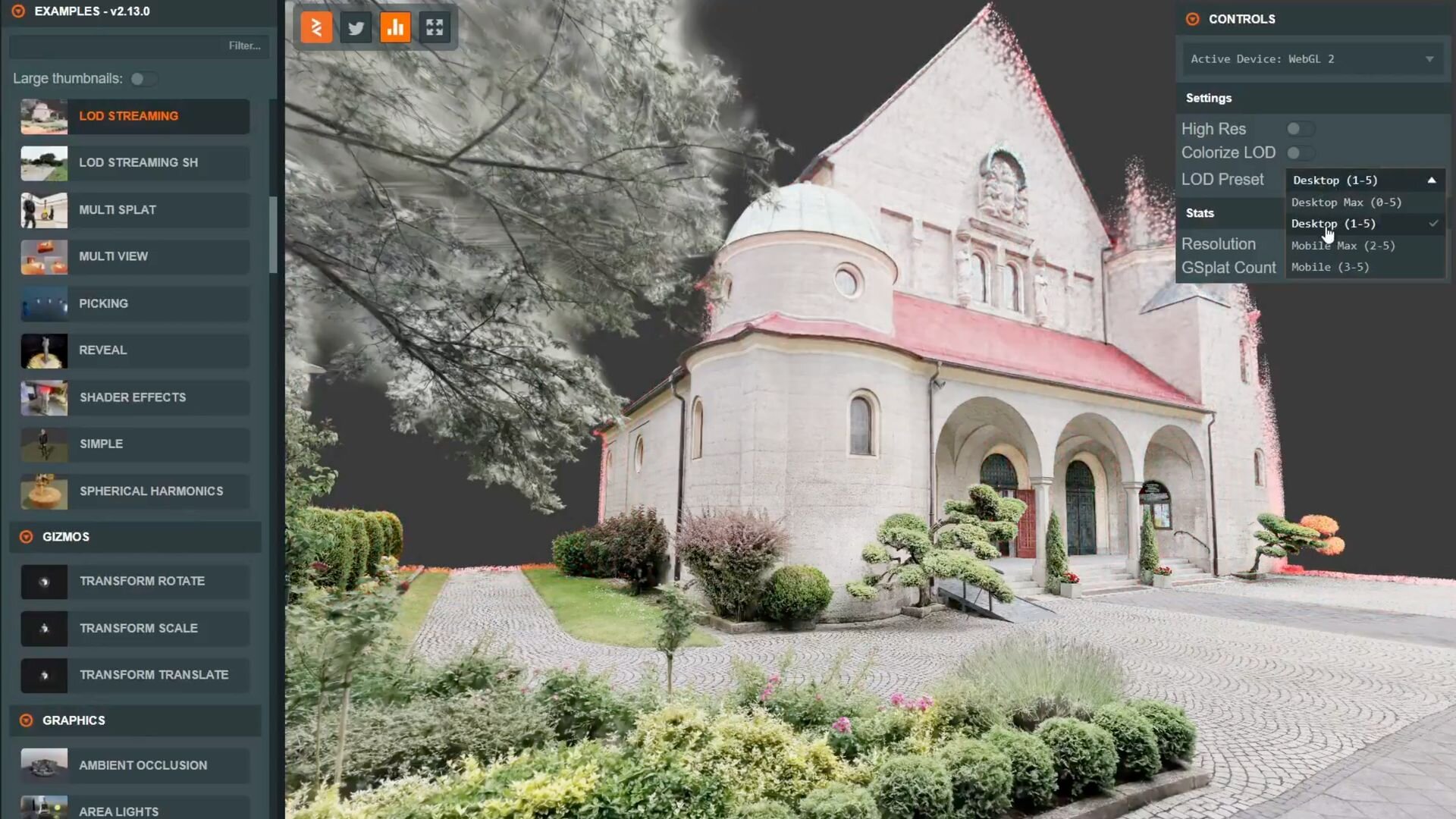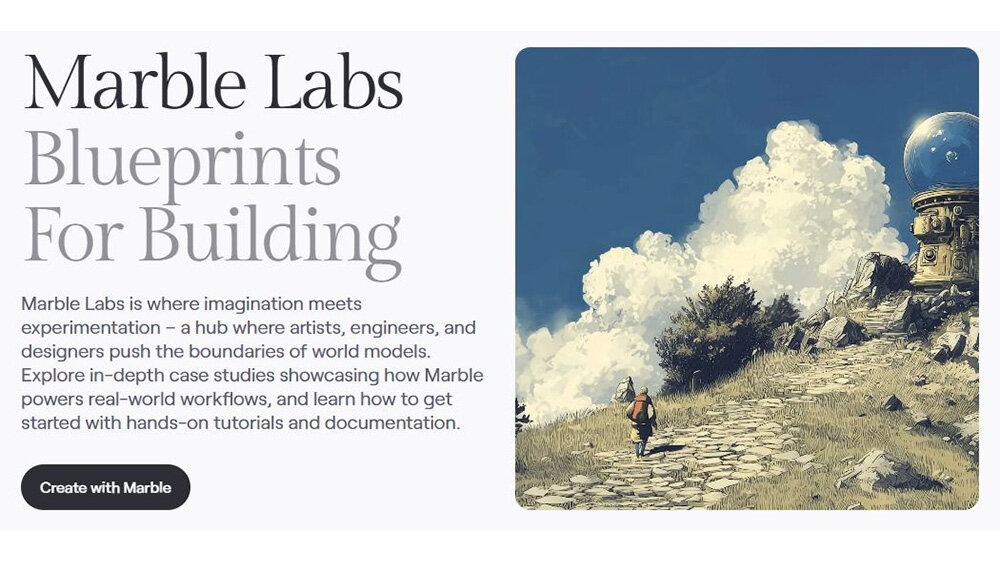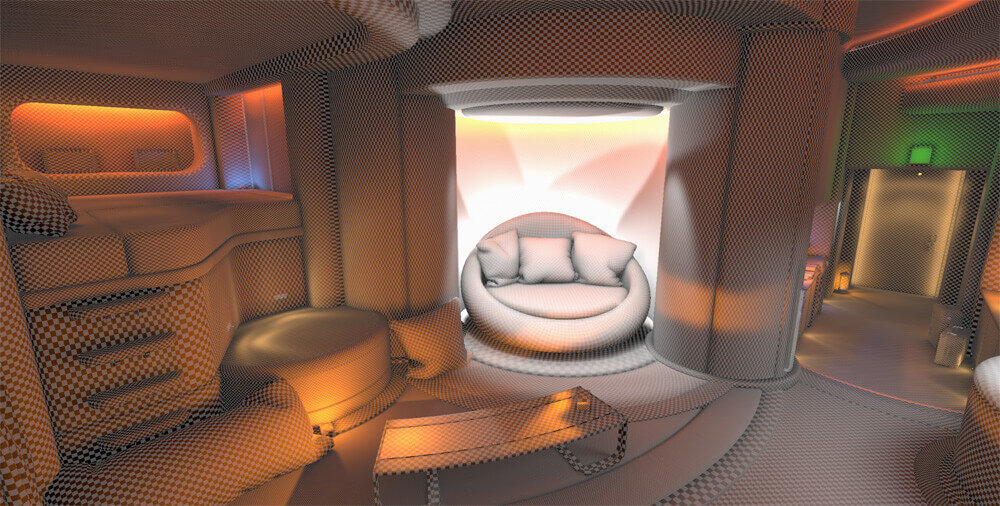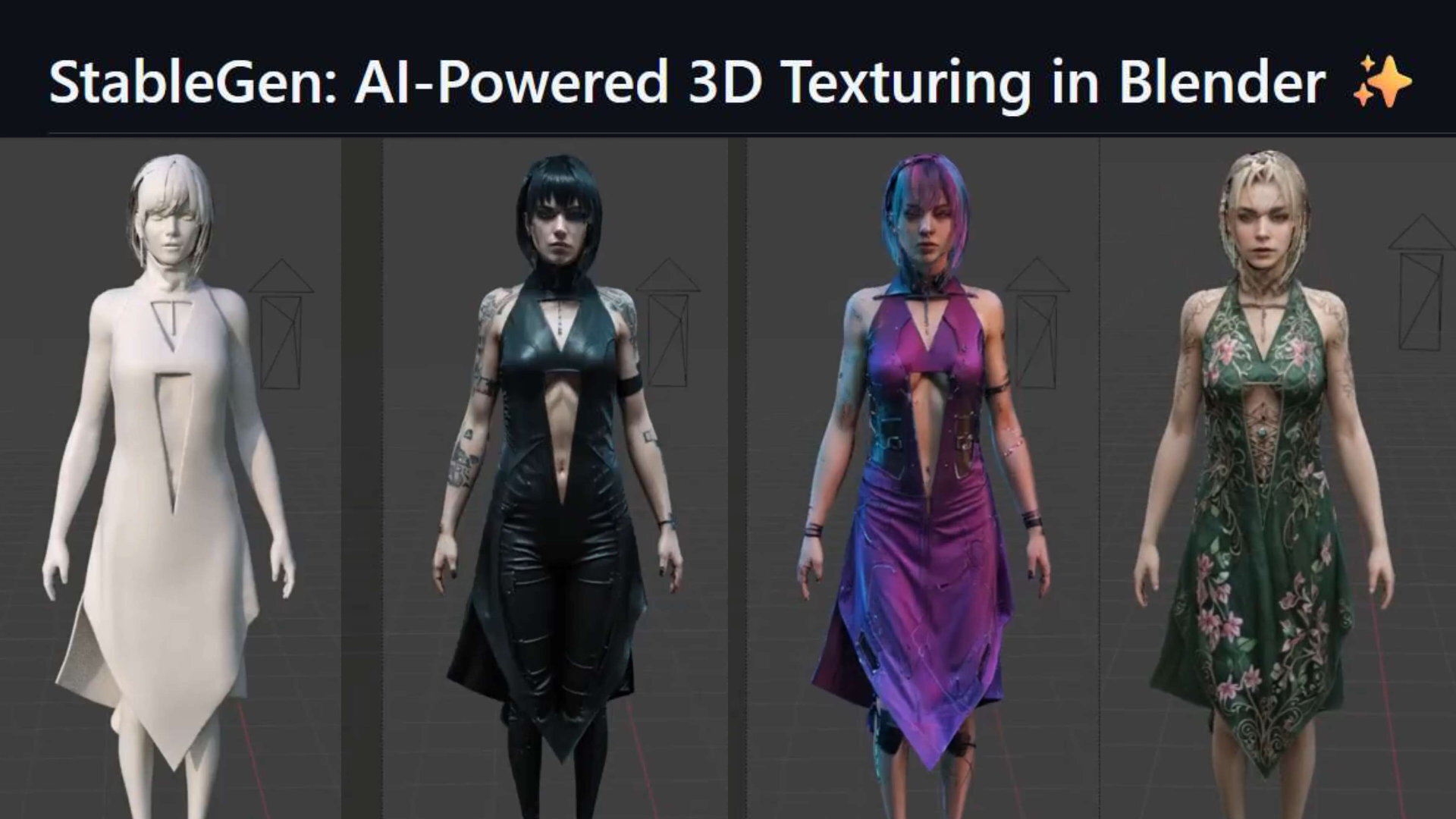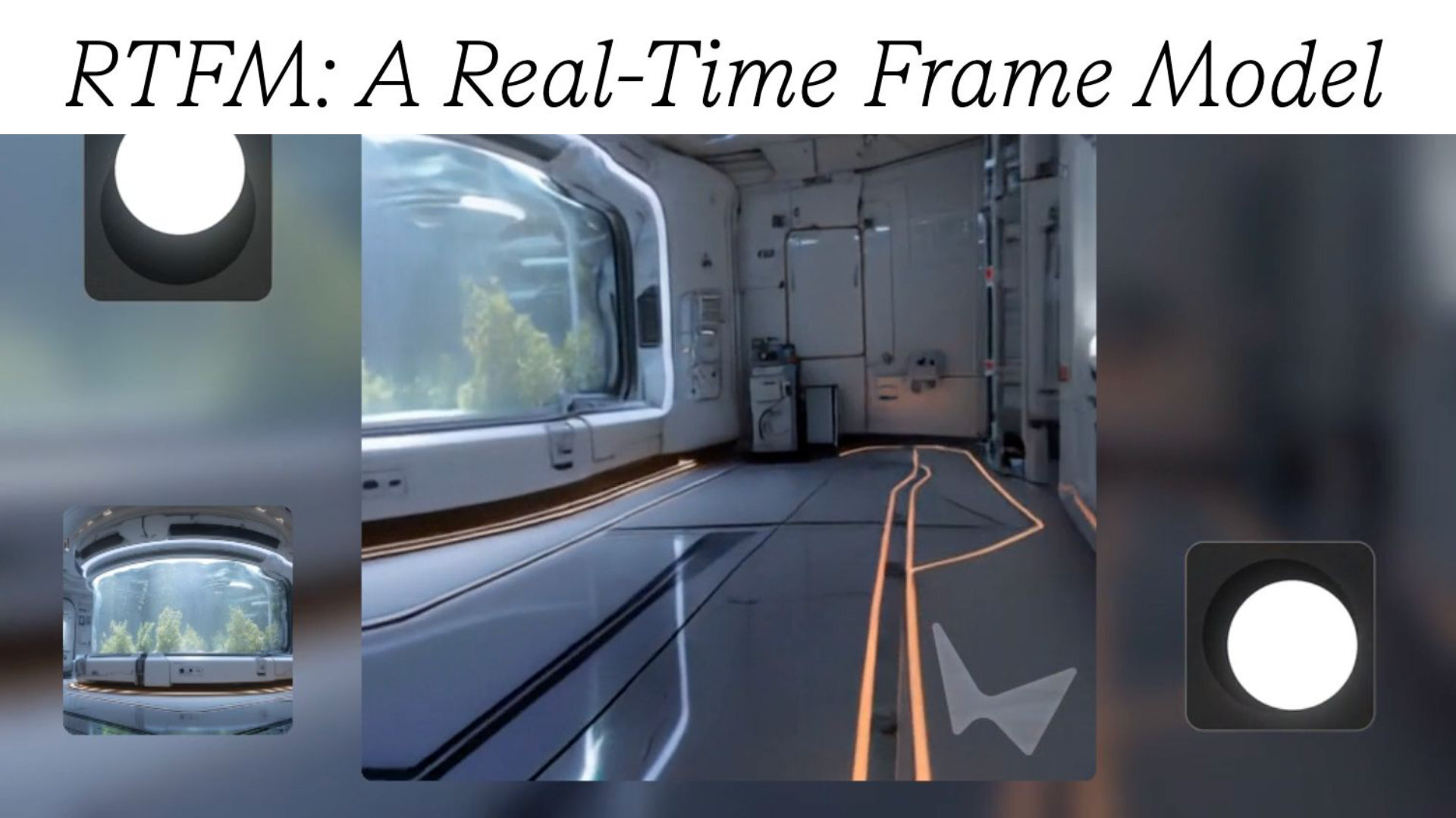「第1回 CGWORLDノベルズコンテスト」では、受賞候補2作品を選出し、CGWORLD.jpにて各作品を全12回にわたって掲載いたします。その後読者投票により各賞を決定し、それぞれ書籍として刊行する予定です。
「CGWORLDノベルズコンテスト」概要
第1回 CGWORLDノベルズコンテスト

■今後の予定
12月8日(金)〜:CGWORLD 305号とCGWORLD.jpで掲載と読者投票スタート
2024年3月頃:書籍時の扉絵イラスト募集
2024年6月頃:読者投票&扉絵イラスト結果発表
本文
七・月光
二宮には、過日のマレの行動が理解できなかった。
かつて自分がクアドロに所属していた時代、初めてコクーンに入った女性が妊娠していたのがマレだ。
マレが産まれたときに彼女は死んだが、以来、二宮はマレを初の被検体として保護し、大切に育ててきた。彼女は貪欲に知識を吸収し、宇宙で活躍する人材として成長していった。そんな彼女を、二宮は娘のように思い、常に気にかけていた。彼女も、その気持ちに応え、過酷な訓練などにも耐えていた。それが二宮の認識だ。
そんな彼女がISCの広告塔になることで才能を消耗していくのは、不本意極まりない選択だっただろう。だが、二宮としては、今まで自分が大切に見守ってきたマレならば、自分の願いを聞いてくれると確信していたし、それを裏切るなど、ありえないことだと思っていた。
結果、マレは二宮を裏切り、走り去っていくことで、彼の心に亀裂を入れた。
「あのインプラントを注入された者は、彼女のように情緒不安定になる。―それがあなたの実験なら、支援について再び考え直す必要があります」
脱走事件の後、如月の決して光を灯さない瞳にそう告げられたとき、二宮は壊れた。
ティトは低酸素環境で活動する訓練を終え、更衣室にいた。
ここ最近は、妹のシーナと二人で訓練する日々が続いている。
“あの二人”が姿を見せなくなった後、何人かの新たな被検体がケージに姿を見せた。みな決まって明るく希望に満ちた表情で挨拶をしてくるが、ティトとシーナは答えようとしない。親しくしたところで、意味がないからだ。
新たな被検体たちは、みな改良を加えたシードを注入されている。それに欠陥があるのだろう。何度かコクーンに入った後、彼らはみなノウムへの変異不良を起こして死亡した。
すぐに死んでいく新入りたちに無愛想でも、自分たちの評価には特に響かない。このままそつなく訓練さえこなしていけば、妹と共に宇宙に行き、安寧な人生を送ることができる。ただ、彼とその妹は、宇宙に行くことに関して感慨は持っていなかった。最も行きたがっていたのは、自分でも妹でもない。数か月前に姿を消したあの二人だ。
「ちっ……」
着替える途中、あるロッカーに目をやり、ティトは舌打ちした。そのロッカーには、ネームプレートを剥がされた跡がある。
この部屋を使う度に、“あいつ”のことが記憶の海から浮かんでくる。その感覚が、彼には不快だった。自分はこのまま飯に困らなければそれでいい。そう言っているのに、キラキラと目を輝かせて、宇宙の魅力なんてものを語ってくる。それが、鬱陶しくて仕方がなかった。最初は失敗して早くこの施設を出て行くことを願っていたが、共にさまざまな体験を共有するうちに、心の中でその存在は多少大きくなった。だからこそ、嫌なのだ。マレや純一と出会うまでの幼少期のティトは、妹と二人だけで、冒険などない、平穏な人生を過ごすことこそが望みだったのだから。
「いつまで着替えてるんだ! さっさと出ろ」
ドアが開き、タンの怒鳴り声が響く。ティトはそれに気のない返事をし、更衣室を出た。タンが率いる警備員たちと共に、食堂へと向かう。廊下はどこか薄汚れており、設置された観葉植物は枯れ果てている。
タンは徐々に、被検体たちへの警戒心を強めたというよりも、尊大な態度を取るようになっていった。その理由は、以前から不満が溜まっていたからではない。
「飯を食ったら、さっさと部屋に戻れ」
そう言って、彼はティトを席に着かせた。しばらくすると、シーナも同じように連れてこられ、向かいの席へと座る。
「―お疲れ様」
シーナがそう呟くと、ティトは返事の代わりにうなずいた。二人になってからは、黙々と食事することが恒例になっている。余計なことを喋ると、警備員とタンに睨まれるからだ。
ノウム専用食を黙々と口に運んでいると、廊下から怒鳴り声が響いてきた。
「こんなやつらを何人連れてきても変わらん! もっと特別な、選ばれた人間だけが欲しいんだ!」
新しい被検体候補の話だろうか。二宮は、日増しに焦燥感を募らせ、その精神が限界を迎えつつあることは誰の目にも明らかだった。
「やれやれ……」
シーナがため息をついた。彼女とティトは、二宮の下をマレと純一が去って以降、ケージとISCとの関係が悪化しているのではないかと推察している。というよりも、ほぼ確信していた。
怒鳴り声が響いている廊下を見たタンの顔に一瞬不安の色が浮かび、長い舌が乾いた唇の表面を一周したのを、ティトは見逃さなかった。タンが尊大に振る舞うのは、自分は被検体たちを抑圧し、服従させる仕事を忠実に行っていると二宮に示すためなのだ。それが自己の生存に繋がるからで、本当は何の信念もないだろうと、被検体の兄妹は感じていた。二宮が寛容だった頃、優しい世話役として振る舞っていたのもそれが理由だろう。
そんなことを考えていると、ティトはシーナが自分の目を見ていることに気付いた。その瞳は「これからどうすんの?」と言っている。
うんざりこそしていたが、今のままでも耐えられないことはない。ティトは、頬の鱗を撫でた後に首を横に振り、食器を持って席を立った。去り際、背後から「そうかなあ」と呟く声が聞こえたが、自分たちに何ができると言うのだ。マレのように中庭から飛び出して、ほんの少しの自由を謳歌して行方不明になる? そんなのは俺たちの柄じゃない。
だが、ティトは抑圧される日々を過ごす中で、マレと純一がこの星に抱いていただろう閉塞感が、少しだけ理解できたような気がした。
その夜、ティトは部屋を抜け出し、食堂へと向かった。目当てのものは、食堂のバックヤードにある冷蔵庫。そして、その中にある所員用の食事だ。彼がこうして夜に抜け出すことは初めてではなかった。外の食事が癖になったティトは、所員から盗み取ったキーを使って、たまに夜食を求めて忍び込んでいたのだ。
監視カメラの死角は把握しているし、盗む食料はほんの少し―食堂の人間が誤差と認識する程度の量にするのがコツだ。しかし、毎晩通っていては、食料が減りすぎる。せいぜい一、二か月に一度が限度だ。食事内容も統一し、正確な数値を求めて被検体を実験台にしているケージの所員たちからすれば迷惑この上ない行為だが、彼の行動はこれまで露見することもなく夜食を調達し続けていた。最近のティトには、日中息の詰まるような空気が支配しているこの研究所において、妹とわずかな会話をする以外の唯一の楽しみだった。
廊下を抜けて真っ暗な食堂の手前まで来たところで、ティトはバックヤードの扉が半開きになっているのを目撃し、足を止めた。その隙間から、ぼんやりと照明の光が漏れ出ている。しばらくすると、聞き覚えのある声が耳に入ってきた。
「くそっ、コクーンの定期点検で時間を食った」
タンだ。
「別にタンさんがやらなくてもいいのでは?」
声からして、おそらく最近施設に来た警備員だろう。
「いや、被検体の中でも特に危険なやつらだからな。これは俺の仕事なのさ」
そうタンが答えた後、ティトの元に足音が近付いてくる。
咄嗟にティトは柱の陰に隠れ、タンたちを見送った。食料を持って、二人は廊下の奥へと消えていく。気付かれない距離を保ちつつ、ティトは二人の行く先を追うことにした。
「危険な被検体?」
誰もいない廊下では、小声の会話でもよく響く。
「ああ。一人は脱走して、もう一人はシードの暴走で化け物みたいな姿になっちまった。いや、どっちにしろ化け物か……」
「なるほど……」
警備員の声からは、少しの好奇心が漏れ出ている。
そんなやりとりを聞く中、ティトの頭にケージから姿を消した、二人の顔が浮かぶ。
「噂くらいは聞いてたんだろう? だから今日はついてくることに決めたんだ。違うか?」
タンが意地の悪い声を出す。ティトはその声だけで、彼のギョロッとした目が動く様子が脳裏に浮かび、やや不愉快な気分になった。
「まあ、そうですね。見たくないと言えば嘘になりますよ」
警備員が苦笑する。彼らは搬入エレベーターの前に辿り着くと、引き続き談笑しながら乗り込んでいった。
「―どう思う?」
ティトのシーナへの説明は、その言葉で締めくくられた。
「どうって……実際に見てみないとわかんないじゃん」
「それができないから相談してんだろ?」
シーナはため息をついた。
「えらっそうだなー。手っ取り早いのは二宮に聞くことでしょ」
「あんなことになったあいつが、答えてくれるか?」
「本当なら開き直るなり、勘付いた私たちの警備を厳しくするなりあるでしょ? 本人と周りの動きそのものが答えになると思う」
ティトは静かにうなずいた。簡単な話だ。そんなことにも思い至らなかったのは、彼が少なからず動揺していたからかもしれない。
「私の所有物だ。どうしようが勝手だろう」
昼過ぎに中庭で行われた訓練の後、不意に疑問を投げかけてきたティトに対して、二宮はあっけなく答えた。
「あいつのこと、娘みたいに思ってたんじゃなかったのか?」
そう言ってから、ティトは後悔した。二宮が血走った目で睨み付けてきたからだ。警備員に指示をすれば、殺すことだってできる。それはさすがに勘弁願いたい。
「あれは違う。私の指示も聞かない、ただの獣に成り果てた」
目元を痙攣させながら、二宮が呟いた。
「そりゃ、いくらなんでも……」
反論しようとしたところで、ティトの肩を掴む者がいる。シーナだ。
「私の言うことを聞いていれば……なのに、私から逃げて……私の……」
ティトたちのことなど目に入っていない様子で不明瞭な言葉を呟きながら、二宮は中庭を出て行ってしまった。
「お前ら、余計な口を聞くな! とっとと部屋に戻れ!」
そう叫んだタンが警備員に向かって顎で合図すると、警備員たちが兄妹を中庭から連れ出した。
そんな昼間の出来事もあって、シーナはなかなか眠れないでいた。彼女の頭の中には、二人がいる地下のことが浮かぶ。
(知っちゃったからにはね)
シーナは、就寝中に棘が干渉することを避けるために首に巻いている、クッションを外した。散々悩んだが、最初からその心は決まっている。
「おい、俺だ、俺」
不意に声が聞こえ、シーナはドアを見た。
「何しに来たの?」
ドア越しに聞こえる声の主、ティトに質問する。なんとなく、その考えはわかっていたが。
「いいから開けてくれ」
シーナがロックを外しドアを開くと、補助灯だけが点く暗い廊下に、ティトが立っている。
「ここを出るんでしょ?」
シーナがティトの心中を言い当てると
「なんでわかった?」
ティトが首をかしげる。
「そりゃあ、私もそのつもりだったし? もちろん……」
シーナは部屋のとある一点を見つめた。
「あの二人も一緒にね」
「―さすがにこのままってのは寝覚めが悪いからな」
そう言って、ティトもシーナが見ている場所、窓に目を向ける。そこから差し込む月の光が、室内を青白く照らしていた。
続きは毎週月・木曜に順次公開予定です!
日程は公開リストよりご確認ください。
『美術商ローラと家路を急ぐ青年』はこちらに掲載しています。
読者投票
読者投票は以下からご参加ください。ぜひお気に入りの作品に投票をお願いします!
読者投票はこちらから※締切:1月25日(木)23:59まで
※回答は1人1回までとさせていただきます。