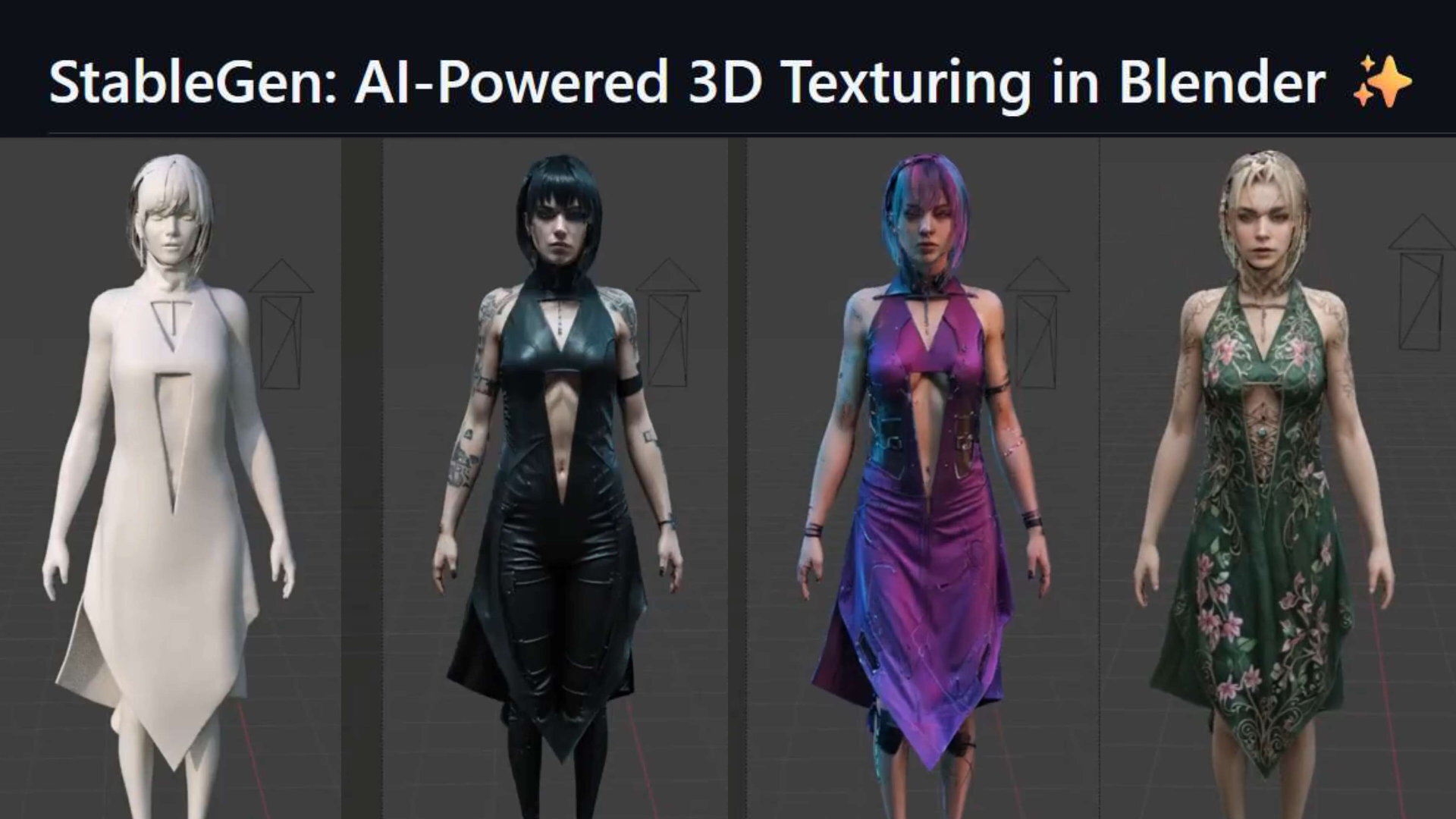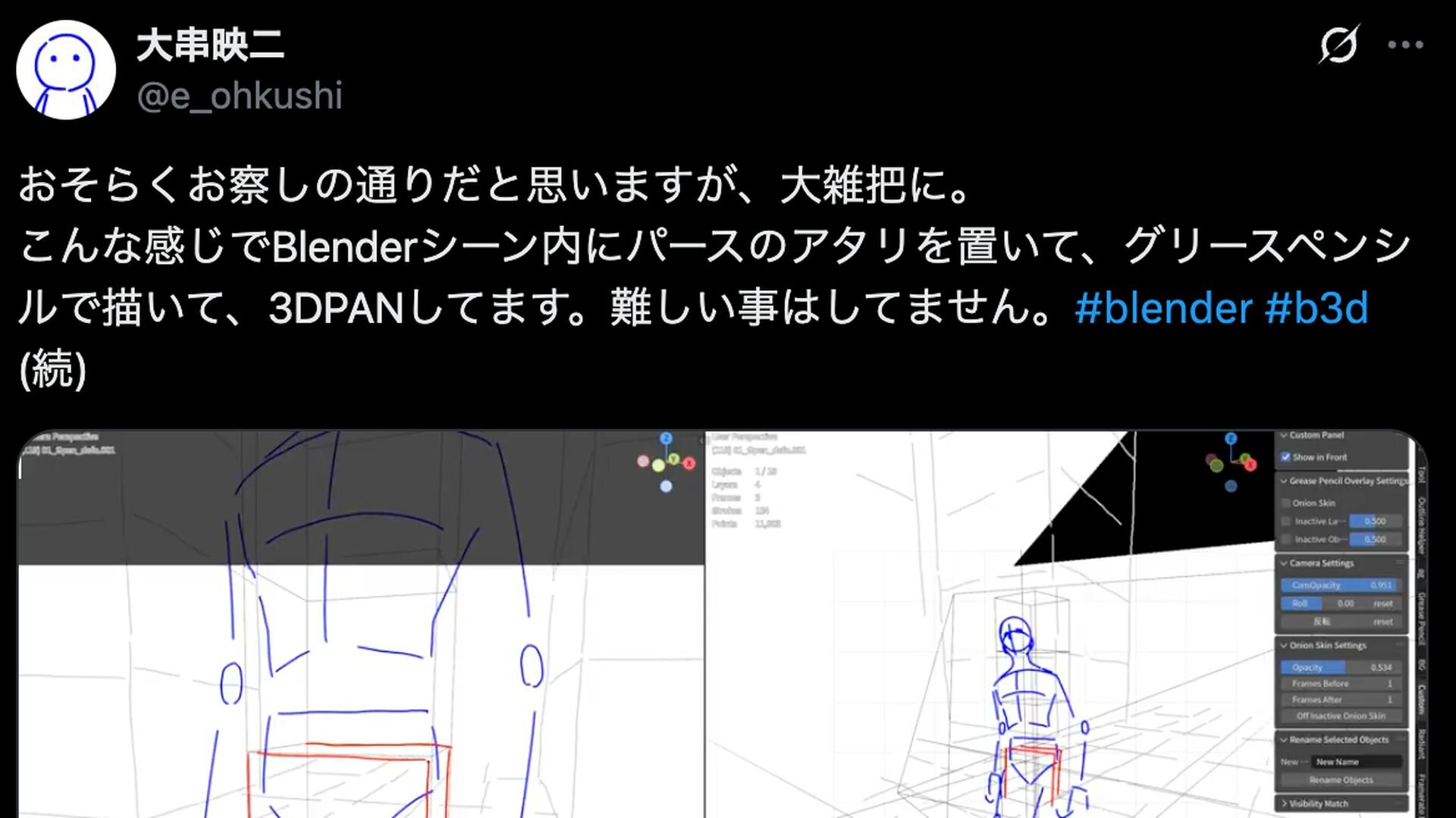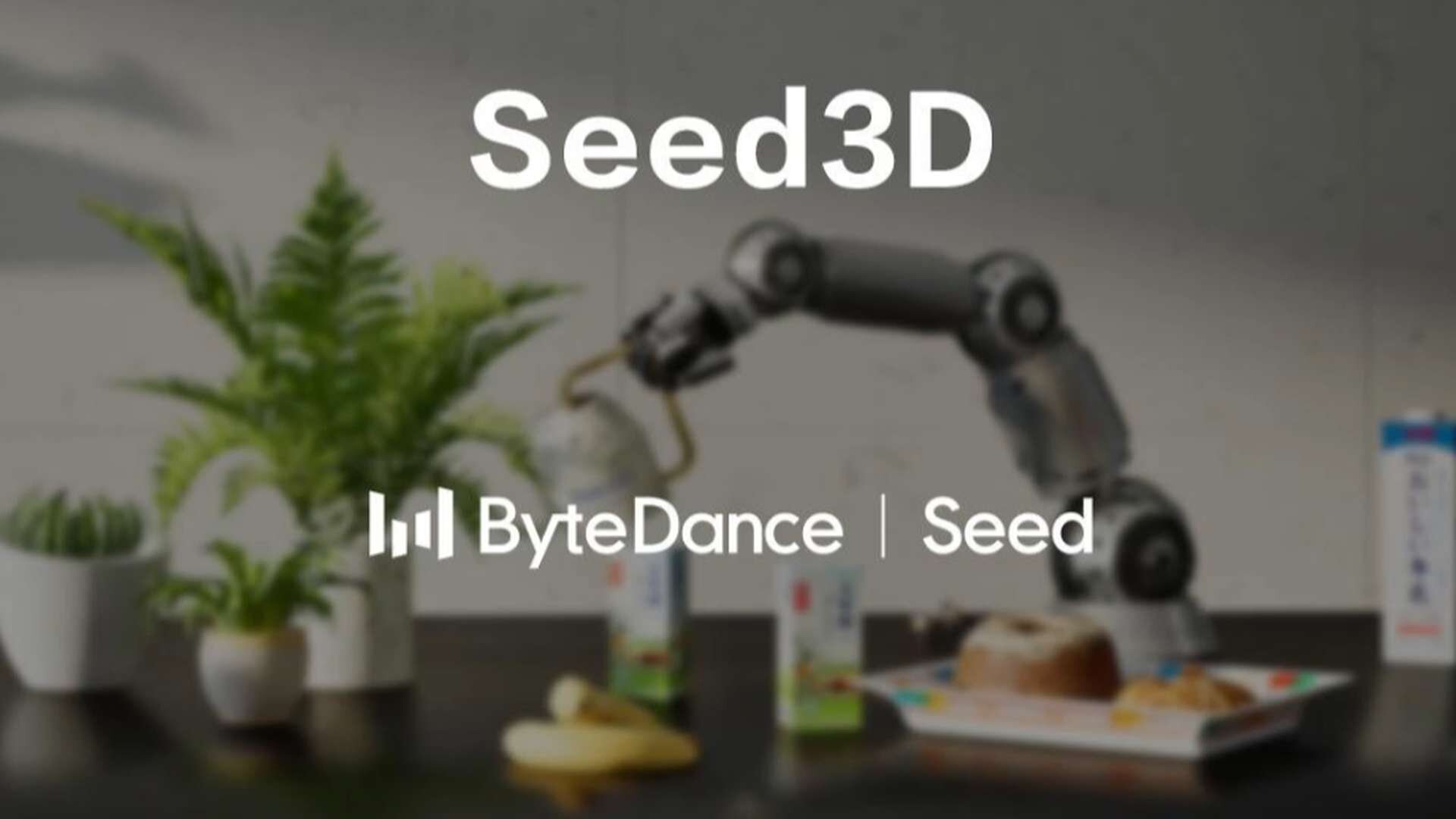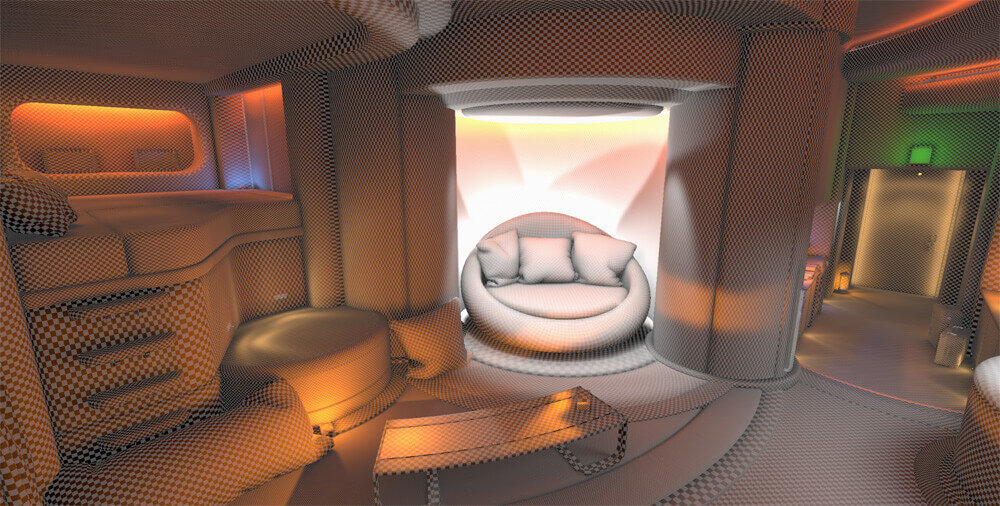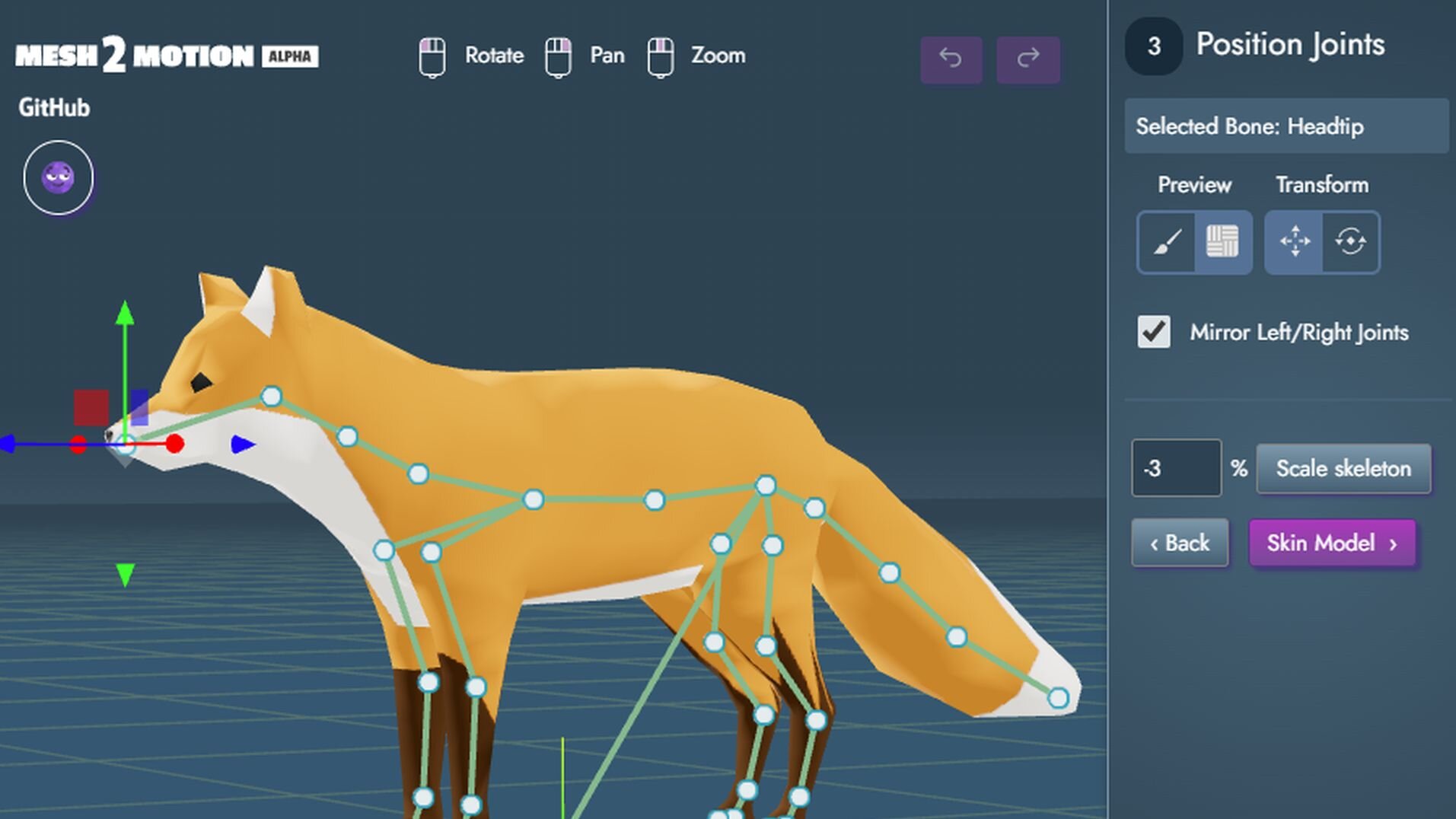「第1回 CGWORLDノベルズコンテスト」では、受賞候補2作品を選出し、CGWORLD.jpにて各作品を全12回にわたって掲載いたします。その後読者投票により各賞を決定し、それぞれ書籍として刊行する予定です。
「CGWORLDノベルズコンテスト」概要
第1回 CGWORLDノベルズコンテスト

■今後の予定
12月8日(金)〜:CGWORLD 305号とCGWORLD.jpで掲載と読者投票スタート
2024年3月頃:書籍時の扉絵イラスト募集
2024年6月頃:読者投票&扉絵イラスト結果発表
本文
八・龍が泳ぐは星の海
薄暗い廊下を、ガラス張りの部屋から漏れ出る光がぼんやりと照らしている。この空間にいる生命体は、二匹だけだ。一匹は、半鳥半人の異形となった純一。体の六割が鳥で、四割が人間だ。その風貌は、一日に一度覗きに来る人間の笑いを誘った。もう一匹は、蒼い体毛に包まれた狼、マレだ。かつては輝きを放っていたが、今はそれも失われ、ぼろきれと見紛うような外見になっている。
純一には抑制剤の投与も効果がなく、体内のシードは、着々と彼の肉体を書き換えつつあった。毎日マレがいる隣の部屋に向かって叫ぶ彼をうるさく思ったタンが鎮静剤を投与するようになったことで彼の意識は朦朧としていき、隣の部屋に投げかけていた声は日に日に痩せ細った音へと変わって、消えた。
配管からの水漏れだろうか、水滴が床に落ちる音が地下の空間に響き続けていた。その音がいつから聞こえ始めていたかも、彼はもう覚えていない。水滴? 雨音? 何かを思い出せる気がしたが、無駄だ。すべては、ほかの記憶と共に埋もれていく。頭の中が、真綿に置き換わってしまったようだ。
隣で、何かがもぞもぞと動く音が聞こえる。純一は、その音を聞くと、なぜか胸が痛んだ。何か……そこにも大切なものがあったのかもしれない。だが、今は意識も巡らず、指を動かすこともおぼつかない状況だ。何もできないならば、過去に思いを馳せても意味がないだろう。
そのとき、廊下と部屋を仕切る強化ガラスの板がスライドする音が聞こえた。ゆっくりと顔を向けると、男……タンが入ってくるのが見える。彼が持っているのは見かけも味も無機質な食事の載ったトレーではなく、見覚えのある太いシリンジだ。
「わ、わかった。わかったから……」
背後にいる何かに急かされたタンは、純一の腕を掴むと、シリンジを射し、ボタンを押した。
鋭い痛みが走る中、純一はシリンジの中の液体が減っていき、自分の体内に注入されていく様を見た。急速に意識が明瞭となり、体にも感覚が戻っていく。起き上がった純一の顔を見たタンは、振り向いて言った。
「これでいいんだろ……くそっ」
タンが振り向いた先の廊下から、見覚えのある友人が姿を見せる。
「シーナ……?」
彼女は純一の体を見回した後、うつむいた。
一時間前。
ティトとシーナの立てた作戦は、二手に分かれ、ティトが脱出経路を確保し、シーナが地下にいる純一とマレを連れ出すというシンプルなものだった。だが、それには地下に入れる人間が必要だ。
コクーンの点検の後、廊下を歩いていたタンは警備員と別れ、一人になった瞬間……掃除用具入れの中に吸い込まれていった。もちろん、兄妹の仕業だ。
「……!?」
シーナに口を塞がれ、タンは声にならない声を上げている。
「余計なことを喋ったら殺す。―わかったな?」
ティトが食堂から拝借したナイフを、首筋に突き立てた。タンは、眼球をぐるぐると回して周囲を見ると、ほかの者が通りかかる気配がないことを悟って、少しの沈黙の後にうなずいた。
「お前ら!?」
口元から手を離されたタンが声を出す。
「地下には入れるよな?」
「それがどうしたっていうんだよ!」
ティトとシーナが目を合わせ、うなずく。
「……そんなことをしたら俺は殺される! 俺に関係のないところでやってくれ!」
「今殺されるのと、どっちがいい?」
ティトが、それまでよりも強く、ナイフをタンの喉に突き付けた。
「ケージを出るって……そんなことをして大丈夫なの?」
逆流の影響か、その声は細い筒から絞り出されるような音になっていた。
「―出たくないの?」
「いや、出たい。早く出たいよ」
純一は腕を動かし、次にベッドから立ち上がった。それまで、テトラオキシンによる血が一気に巡る感覚は好きではなかったが、今だけはありがたい。体を動かす度に激痛が走り、投与されていなければ、気を失ってもおかしくなかったからだ。
一歩、また一歩、独房の出口へと向かっていく。短い距離だが、左足がかぎ爪へと変異した純一にとっては、歩くことさえ至難の業だ。
「あっ!」
バランスを崩し、倒れそうになる。純一の左手はほぼ翼になっているため、人間の肉体の感覚で床に手をついたら、へし折れてしまうかもしれない―と思ったとき、純一の体は受け止められた。シーナだ。
「ちっ! お前が出来損ないじゃなかったらなあ」
シーナが鋭い眼光で、タンの口を閉じさせた。だが、純一はタンの発言を否定することはできない。ほかの被検体とは違う、歪な変化を遂げた肉体では、こうして歩くこともままならないのだ。
(何者かになりたいとか、思ってたっけ……笑っちゃうな)
思えば、叔父母が自分の決断を止め、最終的には呆れ返りつつ送り出したのは、このような結果を見越していたからかもしれない。そう思うと、自然と苦い笑みがこぼれた。
「そっちも開けて」
タンはため息をつき、隣の部屋の扉を開けた。
「マレ……マレ……!」
ぼろきれのようになったマレに、純一は足を引きずりながら近付く。その名前を呼ぶ度に、意識が明瞭になっていく気がした。
「マレ!」
マレも純一と同じくテトラオキシンを打ち込まれており、意識はあるはずだった。だが、その瞳に意志はなく、声をかけられても反応はない。まるで、この世のすべてをあきらめてしまっているようだった。そんな彼女の姿を見ているうちに、自然と純一の目からは涙がこぼれ落ちた。
「いつまでそうしてるんだよ」
手の甲をさすりながら、タンが呟く。しばらく純一とマレの様子を見ていたシーナは、その言葉に苛立ちつつも、マレを背負った。
「だ、大丈夫?」
軽々と持ち上げる姿を見て、純一は思わず声が出た。
「鍛え方が違うんだよ。自分の心配してな」
シーナは、タンと共にエレベーターへと向かっていく。そんな中でも、背負われたマレは何の反応も見せなかった。
「マレ。もうすぐここを出られるから……」
純一は、マレを案じて声をかける。
「あのまま従ってれば安泰だったのにな。お前が変な夢見させなけりゃ、俺だって……」
マレを案じる純一に対して、前を歩くタンが毒づいた。
マレを背負うシーナが食ってかかろうとしたのを、純一は静止した。自分がいなければ、マレは今のようになっていなかったかもしれない。それは事実だ。
「ノウムになれなくて、逆流だけ起きた俺は、外に出ても何の価値もない。ここにへばりついているしかないんだ」
タンの言葉は誰に向けられているのか、純一にはわからない。
「そう言って許してもらいたいの? ただ二宮にくっついて回ってたやつが……」
シーナが鼻を鳴らした。
「別に。言っておきたかっただけだ」
正面を向いたまま、タンはそう呟いた。その表情は、純一たちには見えない。
脱出に使うのは、食料から各種機材まで、施設で使用するあらゆる物資が保管されている倉庫の搬入口だ。
「おう。遅かったな。―大丈夫か?」
その手前で、ティトが一行に合流する。
「久しぶり、ティト。僕は大丈夫だよ……」
「そうは見えないけどな」
純一はぎこちない笑顔を返した。その顔面の左半分がノウムに変異しつつあるため、笑顔もうまくできない。ティトがマレに目をやると、彼女はシーナの背の上で、微動だにしない。その姿に、ティトも胸を締め付けられたが、何も言わなかった。施設にいるかどうかは定かではなかったものの、彼女が脱走を試みた日から、この姿をどこかで想像していたからだ。
倉庫の搬入口のシャッターは閉ざされており、暗闇と静寂に包まれていた。広い空間の中で、一人ひとりの足音が大きく響く。
「そこで待ってろ」
ティトは壁に手を這わせ、指先で照明のスイッチを探した。
灯りを点けて、シャッターの開閉ボタンを押して、外に出る。それで終わりだ。後のことは、そのとき考える。思えば、子どもの頃に売られてからここまで、自分たちの行く先が決まりきっていたこと自体、おかしかったのかもしれない。初めて自分たちで行き先を決めると思うと、壁に這わせている手がわずかに震えてくる。恐怖と興奮、その両方によって。
指先が照明のスイッチを探り当てたところで、ティトは違和感を覚えた。あまりにも、事態が綺麗に運びすぎている。
「おい、シーナ。そいつ―タンが手を動かしたところ、見たか?」
「いや、そこまでは」
暗闇の中で、シーナが首を横に振ったのがティトには見える。
「インプラントか!」
純一が唸った。
「戻るぞ!」
ティトの声が倉庫に響いた。
「いや、もう戻らなくていい」
ティトたちが入って来た廊下の方向から声がした。二宮だ。その後ろには、捕縛用のテーザー銃を持った四名の警備員たちを従えている。純一が初めてこの施設を訪れたときに見たものよりも、さらに大きい。純一のあずかり知らぬことだが、この銃はマレの脱走時にも使用されたもので、太い電極を突き刺し、人間時よりも大型化するノウムもすぐに昏倒させることが可能なものだ。
「揃いも揃って私の指示に従わない。そして貴重な被検体を逃がそうとする」
「もうあんたには愛想が尽きたんだよ!」
シーナがそう叫ぶ。すると、二宮が手を上げて合図をした。
「悪いな」
警備員たちが構えると、タンが純一たちからゆっくりと離れていく。
「僕は失敗作だった……」
純一は、二宮の濁った瞳を見た。
「―けど、三人は別でしょう!?」
そう叫ぶ拍子に、いくつかの羽毛が床に落ちる。
「従わない被検体なら、もう不要だ。また、別の者を探す」
おそらく、それはもう叶わないことだろう。だが、平静さを失っている二宮は、あくまで自分を邪魔するものを処理することを優先していた。
―そんなとき、無気力に、意識の底をたゆたっていたマレが、目を開け始めていた。
「起きたの……? 動かないでね」
自分を背負っているのがシーナだと、マレはその声で気付いた。周囲を見渡すと、警備員たちが銃をみんなに構えていた。その指揮を執っているのは二宮だ。
自分たちは、危機的な状況にある。そう感じたマレが、次にやるべきことは決まっていた。みんなの心を裏切り、一度はケージを飛び出してしまったが、今度こそ、私の心を動かしてくれた人たちのためにこの体を使おうと。
(今の私には、それくらいしかできない)
二宮が手を振り下ろそうとした瞬間、ティトはシーナの背に乗っているマレがぴくりと動いたのを見逃さなかった。
「マレ!」
マレは、シーナの叫び声に逆らい、彼女の背を踏み台にして飛び出すと―その長く鋭い爪で二宮の喉を切り裂いた。
「―マレ……どうして……」
そう呟きながら、二宮は倒れた。最初から彼女と心は繋がっていなかったのだが、彼は最期までそれを信じることができないでいた。
「う、撃て!」
警備員の誰かが叫ぶのを、全員が耳にした。
「やめろ!」
純一がそう叫んだが、テーザー銃の音にかき消される。マレは一人に飛びかかり、その喉笛を噛みちぎる。ほかの者がそんな彼女に銃口を向けたが、それは床に落ちていた資材で殴りつけた、ティトとシーナによって制された。
だが、もう一人が、仲間を倒したティトとシーナを撃とうとしていた。純一は飛び出そうとするが、思うように動ける体ではない。
「逃げろ!」
警備員に飛びついたタンが叫んだ。
「タン! どうして……」
「わかんねえよ。とっととどこにでも行っちまえ! 早くしろ!」
純一とティトとシーナ……そしてマレも、声に従って廊下へと飛び出す。少し後に、背後から銃声が響いてきた。
急いで駆けつけた警備員以外にも、施設には常駐している所員がいる。この騒ぎなら、出入り口はすべて抑えられているはずだ。
「―どうしたもんかな」
ティトが天井を見上げた。そこには幾層にも配線が駆け巡っている。彼らは、ケージの中でも強度が確保されている、変異室へと逃げ込んだのだ。
「マレ、大丈夫?」
純一が声をかけると、マレはうなずいたが、よろよろと歩いた後、床に倒れ込んだ。
「マレ!?」
「おい!」
マレの周囲に、赤い血の海が広がっていく。胴体を見ると、テーザー銃から放たれたいくつもの太い電極が突き刺さっていた。
「どうしよう! ねえ、ティト! シーナ!」
「……」
純一の訴えに、ティトとシーナは答えを出せなかった。この部屋に傷の治療ができる設備はないし、外に出ればあっという間に取り囲まれる。負傷をしている上に、人を傷つけた彼女は真っ先に“処置”されるだろう。
純一の脳内を、さまざまな提案が浮かんでは消えていった。投与されていたテトラオキシンはすでに切れ、全身を走る激痛への対抗策はもうなかったが、アドレナリンによるものか、不思議と痛みを感じない。
そうして考え、周囲を見渡す中、一つだけ道を見つけた。
「マレと僕をコクーンに入れて、変異させてほしい」
「―そんなこと、できるわけねえだろ!」
ティトの怒鳴り声が、変異室に響く。
「でも、今、彼女を生かすには、これしかない」
純一は、鎮座するコクーンに目をやった。彼の提案は、マレをコクーンで再構成させようというものだ。だが、シードを自ら摘出したマレは、そのままコクーンに入っても、溶解されたきり元に戻ることはない。
そのため純一は、自分も共に入ることを提案したのだ。
「お前はそれでいいのかよ」
溶解され、純一の体内にあるシードが正常に作動したとしても、この場合、シードにとってマレの肉体が不純物となる。どんな形に再構成されるかは、誰にもわからない。
「助けてもらって悪いけど、ここから外に出られたって、たぶん僕はもう生きられないよ。こんな体になっちゃったし……」
純一は、わざとらしく左腕だった翼を広げてみせた。
「笑えないって。大体さ、二人揃って結合せずに溶けたら、意味がないでしょ? そうなったら……」
「それは……」
純一がふと膝の上に頭を載せているマレに目をやると、彼女は首を振っていた。拒絶しているのだ。先ほどから、みるみるうちに体温が失われているのが、肌を通して純一にも伝わっている。
純一は、マレの瞳を見た。かつて、淡い紫に輝いていたその瞳に灰色が差している。
「マレ、ごめん。本当にわがままだと思う。でも……どんな形でも、マレに生きていてもらいたい。僕の体を使えるなら、使って欲しい。もう二度と、私は行けなくてもいいなんて言わないでほしいんだ」
変異により歪んだ喉から、純一は必死に言葉を絞り出した。たどたどしいのは、感情があふれ出ているからでもあった。気付けば、純一の緑色になった瞳から涙が流れ落ち始め、彼は顔を伏せた。
マレはしばらく黙っていたが、純一の目元に前足を添え、薄汚れた体毛で、彼の涙を拭う。
「マレ……」
純一が彼女を見ると―ゆっくりとうなずいた。
「見よう見まねだからな……」
そう言って、ティトがスイッチを入れる。コクーンの作動音は聞き慣れていたが、今夜は、まるで巨大な怪物が唸り声を上げているように感じられた。
まず純一が入ったが、一人では入れないため、シーナに抱えてもらいながらなんとかコクーンの中に潜り込んだ。鳥類の形状に変異している足では、内部に入るだけでも一人では不可能だった。
「いい?」
とシーナが声をかけた。
「うん……」
シーナはうなずき、マレを純一の隣にそっと横たわらせた。
「ちょっと狭いけど、我慢してね」
「あ、そうだ……」
純一はあることに気付き、自分の思い至らなさへの後悔が出てきた。
「何? 怖くなった?」
「いや、この後二人は……」
シーナは笑顔を見せる。
「私たちのことは気にしないで。初めて自分たちの意志で考えて、動いて―結構楽しかったから。うまくいったら、また会おうよ。今度は、もっといろんな場所を教えてね」
「……ありがとう」
軽く手を振って、シーナはコクーンから離れた。
「あー、そうだ。純一」
気の抜けた声が聞こえてきた。
「これ、逃げるときに持ってきてやったんだけど……」
ティトが自身の荷物から取り出したのは、街で買った本『星の海の夜明け』だった。
「いるだろうと思ったんだけど、読める感じじゃあないよな?」
純一に向けている目を細め、ティトはわざと苦笑してみせた。
「そうだね……また会えたら、返しに来てよ」
「ああ、またな」
そう言って、ティトがハッチの開閉スイッチを押した。モーター音を立てながら、コクーンのハッチが閉まっていく。
静寂がコクーンの中を満たしている。
『ノウム・シーケンス、開始します』
これまでに何度も聞いた無機質な声が、内部に響き渡る。その中で、マレと純一の瞳が交錯した。
「マレ。うまくいったら宇宙へ……」
喉が溶け落ちたため、その言葉を最後まで言うことはできなかった。その代わりに、純一はボロボロになったマレを柔らかく抱きしめることで伝えた。
次第に二人の皮膚が、肉が、骨が溶け落ち、液体へと変わっていく。その過程で、純一の意識は曖昧になっていったが、自分の中をマレの見た景色が流れ、通り過ぎていくことを認識できた。初めてノウム化の実験が成功し、二宮たちに祝福された時。ノウムに近付いた自身の肉体が、周囲に好奇の目で見られる日々。ティトとシーナ、そして純一に出会った時。四人で過ごした日々。そして、脱走した時の、憧れに抗えなかった心情までが、手に取るようにわかる。
やがてそんな感覚も抜け落ちていき、二人の肉体は完全に溶液へと分解された。純一に埋め込まれていたシードは、愚直に肉体を再構成し、ノウムへと変えるプロセスを開始した。
ノウムへの変異プロセスが終了すると、“それ”はコクーンを破壊しながら、外へと這い出ていく。過程を見ていたティトとシーナは、変異したその姿に思わず息を呑む。
背中に畳まれている翼から、かろうじて元々シードに刻まれていたノウムの形を察することはできる。だが、全身は灰色の泥のような皮膚に覆われ、四本の足をはじめとする体の各所に膨張しきった気泡のようなこぶがあり、細い血管の群れがその表面を彩っている。その姿は、そこに至った原理は同じでも、自分たちとはまったく異質の、この世のどこにもいなかった生物だ。
ティトとシーナは、自分たちがマレと純一をあの姿にしたことを認識し、体がこわばるのを感じたが、歪な形状の頭部についた、紫と緑に輝く瞳を見たとき……少しだけ安心を覚えた。
(あそこに……いるのは?)
“それ”もまた、二人を視界に収めていた。そのとき、かつての共に過ごした日々が蘇る。輪郭は曖昧だが、間違いなく過去に存在した時間が、心の中に刻まれていた。
ティトが、変異室のゲートを開く。
(そうだ……行かなきゃ)
“それ”は、外の空気に導かれるように歩を進め、中庭へと出て行く。空を見上げると、満天の星空が広がっており―その星々を二つの瞳に収めた瞬間、心の空っぽだった部分が、満たされるような感覚をもたらした。
そして、体の中心から突き抜けるような衝動に駆られ、左前足を噛みちぎる。シードが埋め込まれていては、飛び立つのに支障が出ると、意識の奥底に沈められている記憶が訴えかけていたからだ。
どんな人間が見ても醜悪に感じられる異形さを持っていたが、翼を広げ、月光を浴びながら咆吼する姿には、この世に生まれ落ちたときから神など信じていなかったティトとシーナから見ても、神々しいと感じられるものがあった。
“それ”は、思い切り地面を蹴る。
(本当に、これでよかった?)
(僕はこれでよかったよ、行こう……)
飛び立つ醜悪な灰色の“それ”の中で、二人の意識は混ざり合い、同じ一つの目標に向かって行動している。それは、これまでずっと、純一とマレがノウムになる際に精神統一のための軸としていたこと―宇宙への旅立ちだ。すべての枷から解き放たれ、溶け合った二人の意識は、今幸せに満ちていた。
飛び上がり、風を受けながら、二人は高度を上げていく。
眼下に広がる夜の街の光は小さくなっていき―代わりに、頭上に輝く光は一秒ごとに大きくなる。
星々の海は、生まれ落ち、飛翔した龍を優しく包み込んでいった。
最後までご覧いただき有難うございました!
今後、書籍化の際の扉絵イラストを募集する予定です。
読者投票と扉絵イラストの結果は合わせて発表予定です。
これまでのエピソードは公開リストよりご確認ください。
『美術商ローラと家路を急ぐ青年』はこちらに掲載しています。
読者投票
読者投票はこちらから※締切:1月25日(木)23:59まで
※回答は1人1回までとさせていただきます。