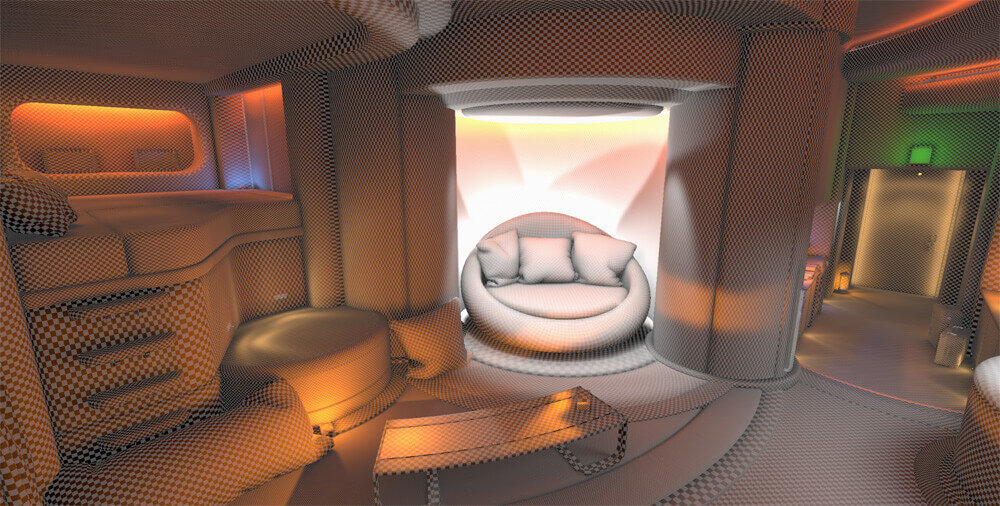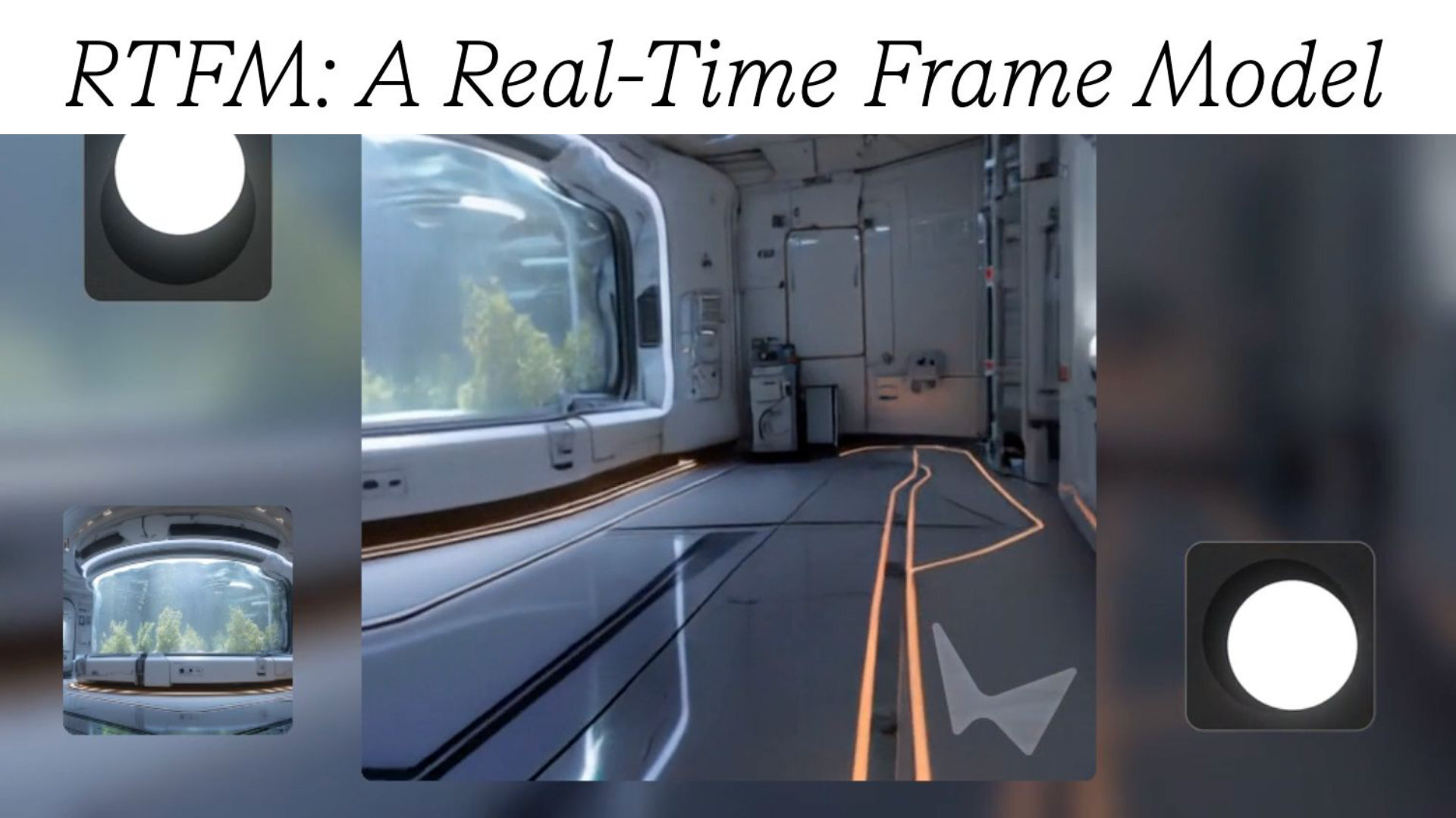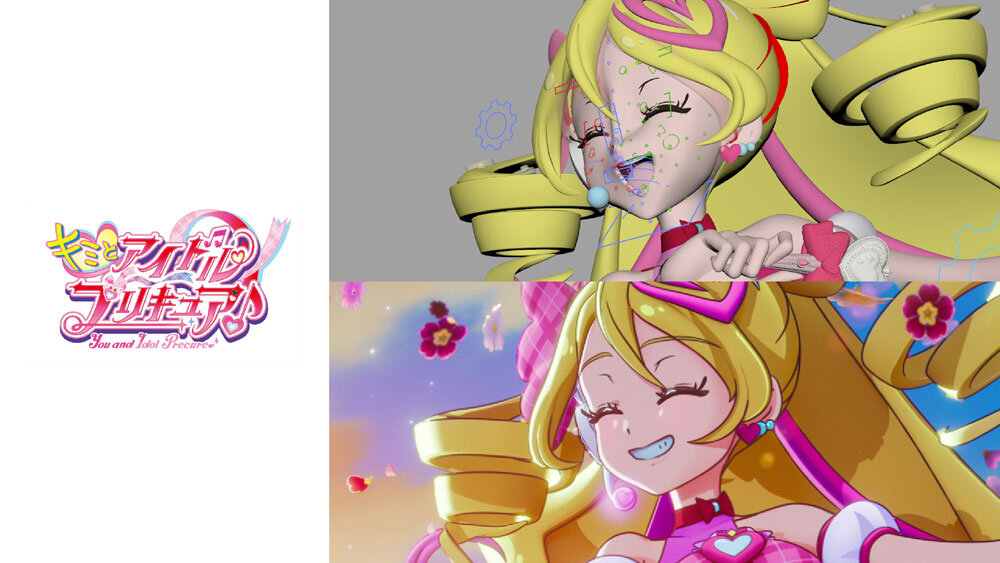「第1回 CGWORLDノベルズコンテスト」では、受賞候補2作品を選出し、CGWORLD.jpにて各作品を全12回にわたって掲載いたします。その後読者投票により各賞を決定し、それぞれ書籍として刊行する予定です。
「CGWORLDノベルズコンテスト」概要
第1回 CGWORLDノベルズコンテスト

■今後の予定
12月8日(金)〜:CGWORLD 305号とCGWORLD.jpで掲載と読者投票スタート
2024年3月頃:書籍時の扉絵イラスト募集
2024年6月頃:読者投票&扉絵イラスト結果発表
本文
六
また同じ夢を見ていた。故郷の山に僕はいた。もっとも今は実際に同じ地に立っているのだけれど、この夢の中の僕は一歩たりとも動けない。手を伸ばせば届きそうな距離で、故郷の家族が楽しそうに食卓を囲んでいる。
「まって」
手を伸ばした瞬間に家族が遠ざかる。気付いてもらえない。どうして、どうして僕だけがこんな目に遭うんだ──常ならこれで目覚めだった。僕は飛び起きて、マレの森に閉じ込められていることを実感してため息をつく。しかしこの夢には続きがあった。
目の前の映像が勢いよく火に飲み込まれていく。家族も友人も隣の家の叔母さんも、さっきまで追いかけていたリスも、すべてが等しく炎の向こうへ消える。僕はまた手を伸ばした。今度は違う意味で。山が燃える。火が、木を伝って村へ侵入していく。やっぱり僕は動けない。僕の叫び声は炎にまかれ、喉が焼けるように痛かった。
これは間違いなく夢だけど、この光景は僕が作り出した妄想ではなかった。僕は村が燃えた日に山にいて、村が焼けるのを為すすべなく見ていた。僕は動けなかった。ただ炎がすべてを焼き尽くしていくのを、じっと見ていた。今まで夢の中で何度も問うた「どうして」のその先は、自分がマレの森に取り込まれた恨み言だった。実際この後にマレの森に飛ばされていて、僕はそれまでの記憶が曖昧だったからそんな中途半端な夢を見ていたんだろう。でも実際の僕の心は違ったらしい。
どうして僕だけがここにいて無事なんだろう。僕があの火事で炎にまかれる直前まで思っていたのは、そういうことだった。本当ならあの場所で家族もろとも焼け死んでいるところだったのに。僕はここで何をしているんだろう。記憶をなくしてからもずっと、頭のどこかにその気持ちが残っていたのだろう。だからずっと帰りたいと思っていた。帰った先に故郷がないことも、覚えていなかったくせに。
いつもなら木の枝葉で隠されていくその先を見せられているうちに、ふと今までマレの森に取り込まれる夢で終わっていたのは、あの森の優しさだったのではないかと直感した。マレの森は僕を取り込んだのではなく、故郷の燃える山からすくい上げてくれたのではないか。森の付近に僕の行動範囲を制限してどこにも行かせなかったのも、僕に帰る場所がないことを知っていたからではないのか。だとしたら僕はなんて薄情なヤツだったんだろう。
だんだん視界から炎が遠ざかり、穴が閉じられるようにして僕は真っ暗な世界に放り出された。夢の中なのに思考はどこまでもハッキリしていた。体がどこかへ落ちていく感覚だけがあったが、どこへ向かっているのかはわからなかった。黒い浮遊感の中で「もういいかな」と力を抜いて流れに身を任せた。
もはや僕に帰る場所はない。故郷は燃えて、今は知らない人間が知らないコミュニティを築いている。マレの森は今までにあんな仕打ちをした僕を許さないだろう。市場の人間だって、僕のことを覚えているか怪しい。仮に覚えていたとしても「出られるなら今すぐ出て行ってやる」くらいのことを思っていた人間のことを歓迎してくれる人は少ないはずだ。僕は、僕のことを省みてくれる人間がいない事実を飲み込みながら、一人で生きていくエネルギーをもはや持っていなかった。
落ちていく中でふと、腕を引かれた気がした。誰だろう。思わず振り払う。しかしその手はしつこく僕の腕を掴み、無理やり上へ引き上げようとした。もういい、そっちには行かない。そう思っているのに僕はすでにそれに抵抗する気力もない。暗闇から夜明けの光のような白が差し込み、徐々に強くなっていく。目を開けていられなくなって、思わず目を閉じた。
「……大丈夫ですか」
「……ローラ?」
夢の中では目を閉じた感覚があったのに、実際には目を覚ました状態だったらしい。何度か瞬きをしていると、ぼんやりとしていた視界がはっきりしてくる。心配そうな八の字眉に青い瞳……ジェーンだった。その雰囲気といい顔のつくりといい、まったくもってローラには似ていない。ジェーンは人違いを責めるわけでもなく、僕を抱き起こしてくれた。
「びっくりしました……山の真ん中で倒れているものだから」
「いや、すみません。ちょっと急にめまいがしたもので」
自分でもどうかと思うくらい苦しい言い訳だったが、ジェーンは特に怪しんだ様子もなく「そうですか」と言った。
「ひどい夢を見ていたんですね。うなされていましたよ、『帰りたい』って」
「ええ、まあ……。いろいろあったものですから」
夢の内容を反芻してため息をついた。そうだ、もういいと思ったのに帰ってきてしまったのだった。こちら側の世界でもう行く場所などないのに。起こしてくれなくてもよかったのに、とジェーンに対して八つ当たりまがいの気持ちが湧いてくる。
「あなた、私たちが来る前の住民だったのね。びっくりしたでしょう、久しぶりに帰ってきたら全然知らない人間が我が物顔でここに住んでいるんだもの」
「あ、いや……まあ」
あまりはっきりした返事をするのも悪いかと濁していると、ジェーンは「どうぞ」と水を差し出してくる。ありがたく受け取って喉を潤しながら、彼女が一人でここまできたことを不思議に思った。あれだけ睨んでいた彼女の夫は一緒に来ていないのだろうか。自分の妻が怪しい人間と会っているというのに。もしかしたら内緒で探しに来てくれたのかもしれない。
「私もね、故郷から移り住んできた人間ですから気持ちは少しだけわかりますよ。あなたみたいに丸ごと失ってしまったわけじゃないけれど、かなり遠い場所に嫁いできましたから」
「……そうでしたか」
「今までも何度か帰ってますけどね、居心地悪いんですよ、これが。いくら故郷といっても、住んでいる人たちが作る空気と言いますか……雰囲気? もう自分の知っていた頃の村じゃないんだなって思うんですよ」
「なるほど」
話の軸を掴みかね、間の抜けた返事ばかりしてしまう。ジェーンは僕が返した水の入った瓶をバスケットにしまうと、今度はサンドイッチを差し出してくる。どこまでも至れり尽くせりで、何もかもがおかしい。というか、この一度断るまでどんどんいろいろなものをよこしてくる人を、僕は知っている気がする。
ジェーンは自分でもサンドイッチをかじりつつ、話を続けた。
「つまりね。帰りたいって、誰かに迎え入れられたいってことだと思うんですよ。家族とか親戚とか、知っている人に『おかえり』って言ってほしいってことなんです」
「……おかえり、ですか」
「はい。帰りたいって気持ちは故郷限定じゃないですよ。あなたも帰りたい場所があるんじゃないですか? こんな、知らない人ばかりの村じゃないところに」
サンドイッチにはレタスとハムが挟まれている。ちょっとだけ胡椒が効いているみたいで、舌がぴりぴりした。僕は明らかに知っている味のそれを気にしないふりをして飲み込み、膝を抱えた。
「帰りたいといえば、そうなのかもしれない。でも迎え入れてくれなかったら? 僕は立ち直れなくなってしまう」
ジェーンは鷹揚に笑ってまた一つサンドイッチを差し出してきた。さりげなく辞退すると、彼女はそれを迷いなく自分の口に入れた。
「大丈夫ですよ。送り出されてきたんでしょう? さようならって言われたわけじゃないんでしょう?」
そう言われて僕は、故郷へ旅立つ前のことを思い出した。共に冬を越し、次の仕事場所へと向かう彼女は、どういうわけか僕に言ったのだ。「いってらっしゃい」と。
「……ねえ、僕帰っていいと思う?」
「私に聞かれてもわかりません」
ジェーンは最後にツンと澄ました顔を見せると、唐突に立ち上がった。バスケットを持ち、スカートをひるがえして「それでは」と会釈した。
「主人が下で待ってますから」
八の字眉をさらに下げて笑った彼女は、軽やかに僕の元を去っていった。その姿を見送って、僕は笑ってしまった。あまりにも嘘が下手すぎる、優しすぎる彼女に。
「……帰るか」
呟いて立ち上がった。マレの森は怒るだろうか。囲われたことを嘆き、脱出したにも関わらずすぐ帰ってこようとした僕を。もし森に受け入れてもらえなかったら、あの市場のある町に住もう。今度こそあの喧騒に慣れて、煮込み料理屋の男のスープをもらって、そこを「帰る場所」とさせてもらおう。そう考えてから僕は、思いのほかあの町に思い入れがあったことに気付いて驚いた。五年も住めば、どれだけ不本意でも愛着が湧くのかもしれない。故郷だと思っていた場所が変わり果てていたと知った後は、特に。
山を出て、ぽつりぽつりと建っている家たちを見ながら歩いていると「あの」と小さく声がかけられた。振り向くと、ジェーンだった。八の字眉が似合う困り顔で「もう行かれるの?」と言った。僕はその変わりようにちょっと笑ってからうなずいた。
「ええ、もう帰ります。お邪魔しました」
きっとその変わりように驚いたのはお互い様なんだろう。目を丸くしたジェーンに一礼して、僕はかつて故郷だった場所を後にした。
七
そこからすんなり帰れると思っていたが、話はそううまくはいかなかった。僕が自分で描いた龍に乗って三日でたどり着いた故郷は、どうやらマレの森からは遠く離れた場所だったらしい。海を渡り、馬車に乗せてもらい、さらにその何倍もの距離を歩いていく必要があった。ローラやマレの森に甘えっぱなしだったことを実感し、つくづく自分が恥ずかしくなった。
あちこちの人に道を聞きながら、絵を売って旅をした。動物が抜け出さなくなった僕の絵は、それなりに買ってくれる人がいた。動物ばかり描いているわけにもいかず、道端で適当な人に声をかけて似顔絵をその場で仕上げて売るなんてこともやった。そんなことをしていたら、馬車に乗せてもらう機会が増えた。途中まで道が同じだという演劇小屋の座長は、船で海を渡るところまで助けてもらった。人と関わるたびに、自分という人間がどんどん開かれていく気がした。一度故郷に帰らなければこの道中はなかったと思えば、ジェーンの家で過ごしたあの一夜も優しく受け止められる気がした。もっともそう思えたのは、ようやくパサロの市場の入口まで到達したときだったけど。
冬にローラと出会い、春を迎えて旅立った僕は、今度は冬を迎える直前の市場に立っていた。日が短くなったこの時期は、すでに向こう側の空が赤くなっている。季節がだいたい一巡りしてしまうほどに長い旅だった。ここにきてようやく、僕は市場の入口というものを知った。
どれだけ長いのか確かめるつもりで一歩一歩踏み締めていると、思ったよりもこの市場が長く続いていることに気付く。ようやく嗅ぎ慣れた香りが漂ってきた頃には、ほとんど日が沈みかけていた。
「おい、もしかしてジルか?」
煮込み料理屋の男が目を丸くして叫んだ。それを聞いて僕は「ああ、帰ってきたのか」とぼんやり実感した。まさかこの男に出会ってそう思うことになるとは想像していなかったけど。僕は「お久しぶりです」と会釈した。
「なんだよお前、急にいなくなりやがってよお。お前のせいで鶏が高くなって全然売れねえんだぞ」
「すみませんね、ちょっと実家に帰ってたんで。それ、僕が買いますよ。あとスープもください。また鶏を卸すから、安くしてくれません?」
男はパチパチと瞬きをした後、からからと笑った。
「ずいぶんと言うようになったなあ! おら、持ってきな」
「え、いいんですか」
「ああ。その代わり、今度店の看板描いてくれよ。あと鶏な」
「は、はい。ありがとうございます!」
揚げ鶏とスープを抱えた僕はさぞや目立つだろう。僕の顔くらいある肉をちみちみかじりながら歩いていると、森の入口まで辿り着いた。立ち止まって背の高い木が並ぶそこを見つめる。何も変わらず、うっそうとしているのに明るい、少し怖い森だった。うっかり止まってしまったものだから、迂闊に足を踏み入れられなくなってしまった。僕は森の入口に座り込むと、男からもらった料理を口に運ぶことに没頭した。優しい甘みのあるスープには野菜と肉がごろごろ入っていて、さらにそこに揚げ鶏があるものだから、食べ切る頃にはだいぶお腹が重くなっていた。貧乏旅行をしてきた身に、急にこれはキツい。
食べ切ってしまったからには、向き合わなければならない。恐る恐る一歩踏み出し、あとはもう夢中で歩いた。弾き出されてしまうなら、すぐに森の入口へ戻される。一歩一歩、この森に「入れますように」と祈りながら歩くのは初めてのことだった。
二十歩、まだ森の中だ。四十歩、入口はまだ見えない。無心で歩き続けていたら開けた場所に辿り着いた。まさか戻されたかと顔を上げるとそこにはなつかしい顔が立っていた。
「おかえりなさい、ジルさん」
好奇心が散らばる瞳に、誰よりも美しいブロンド。ローラが僕の小屋の前で仁王立ちしていた。僕は泣きそうになるのをグッと堪えて、その小さな影に向かって走り出した。
「ただいま!」
あの濃密な時間が嘘だったみたいに、ローラは小屋から消えてしまった。もちろん何も言わずに立ち去ったのではない。きちんと「明日、ここを発ちます」と言われ、ここを出ていくときにも「さようなら」と言われた。それでも僕は、またローラが帰ってくるのではないかと思ってしまった。ローラは「いってきます」とは言わなかったのに。
マレの森の主は、最初の頃よりは確実に人間の機微がわかるようになっていた。それでもこの森に住む人間が「帰ってこない」ことを恐れているようで、遠出した日なんかは強制的に森へ連れ戻されるときがある。もはや僕は慣れてしまって、森の主に忠言することもない。僕が生涯を全うした後に来る人間が、彼のその悪癖を正してくれることを祈るしかないだろう。
僕は今日も絵を描いている。相変わらず描いたら紙に定着せずに森へ出て行ってしまうので、紙に置いておきたいものたちは未完成のまま物置にしまうようにしている。その物置の一等地──ドアを開けたら真っ先に目に入るその場所に、もう何年も未完成のままの絵はあった。
絵の中では軽やかに裾をひるがえした少女がこちらを見ている。青い瞳の垂れ目、顔にはそばかすがあって、鼻は少し低い。淡い水彩で描いたその少女の髪──僕が今まで見てきた中で一番美しかったその髪だけは、一切の色が塗られていない。あの色を塗れば、彼女はまたここへ現れるだろうか。少女のように笑い、老婆のように諭してくれた彼女は、ずっと同じ姿でいることがほとんどなかったから、この絵が完成しても紙から連れ出されてくることはないのかもしれない。そもそも彼女のあの美しい髪色に合う絵具を、僕はまだ見つけられていない。
未完成の少女の絵を眺め一つ息をついた僕は、今日もその絵を物置の一番いい場所にしまい込む。ドアを閉める直前、真っ白な髪の彼女が小さく微笑んだ気がした。
最後までご覧いただき有難うございました!
今後、書籍化の際の扉絵イラストを募集する予定です。
読者投票と扉絵イラストの結果は合わせて発表予定です。
これまでのエピソードは公開リストよりご確認ください。
『龍が泳ぐは星の海』はこちらに掲載しています。
読者投票
読者投票はこちらから※締切:1月25日(木)23:59まで
※回答は1人1回までとさせていただきます。