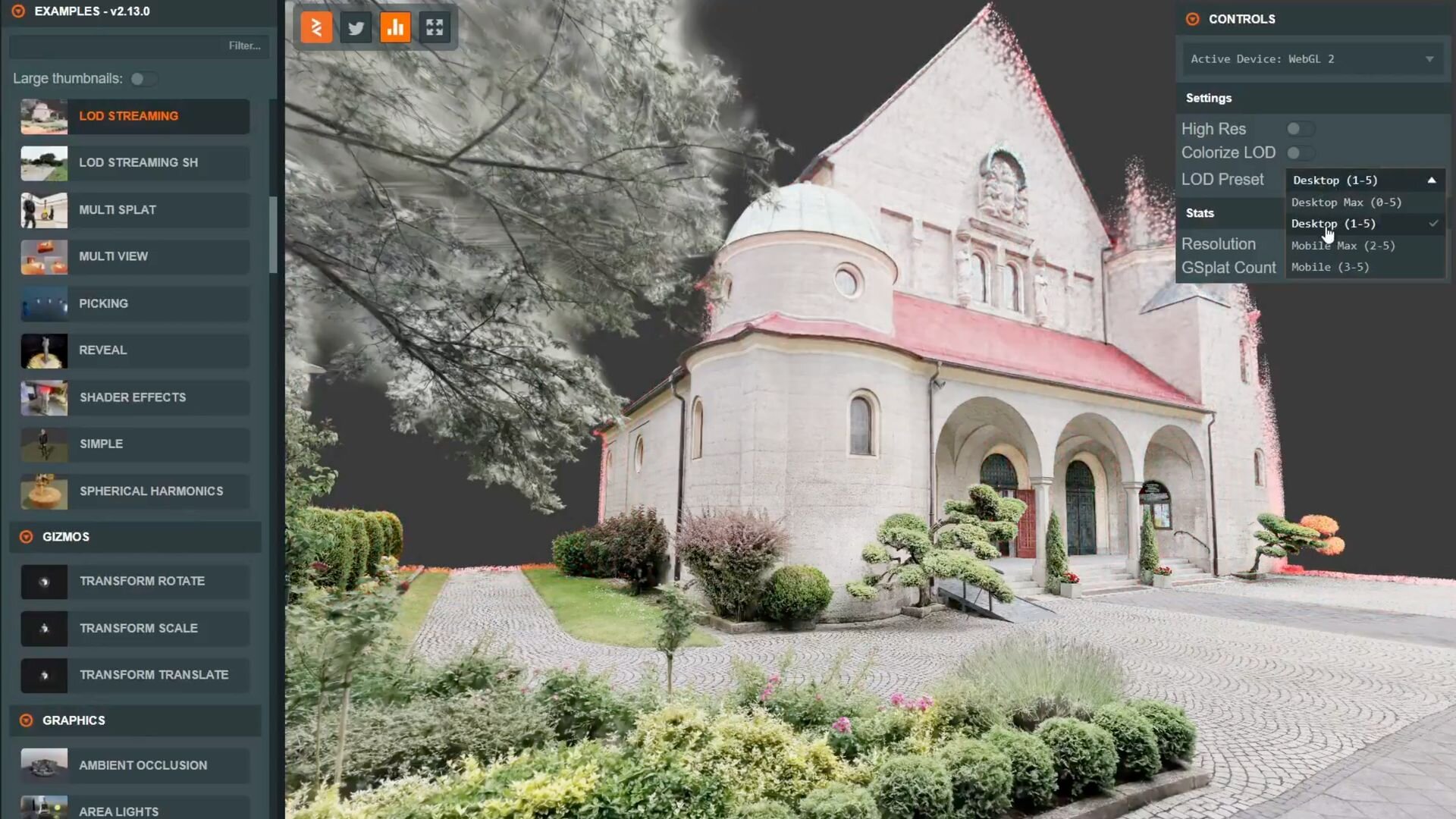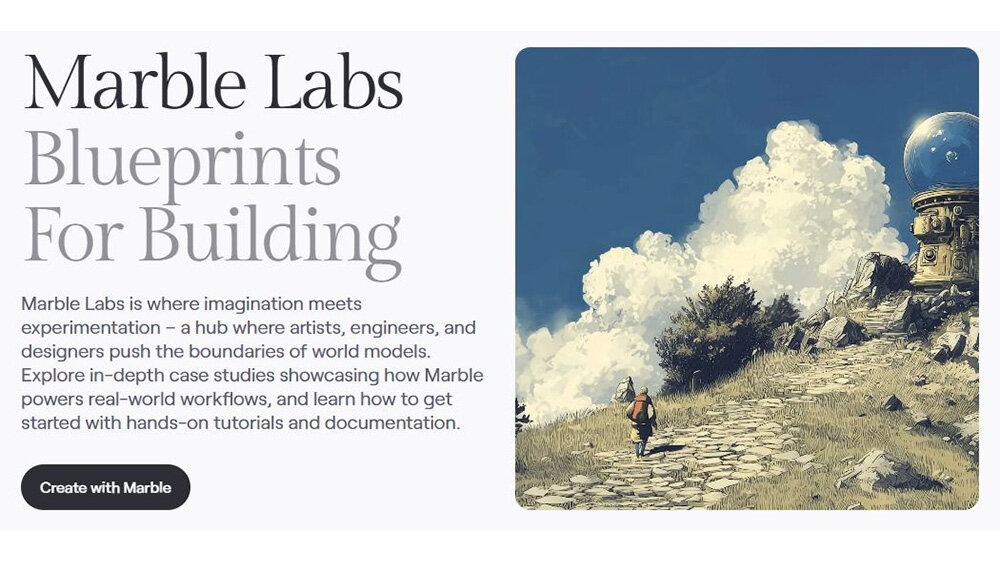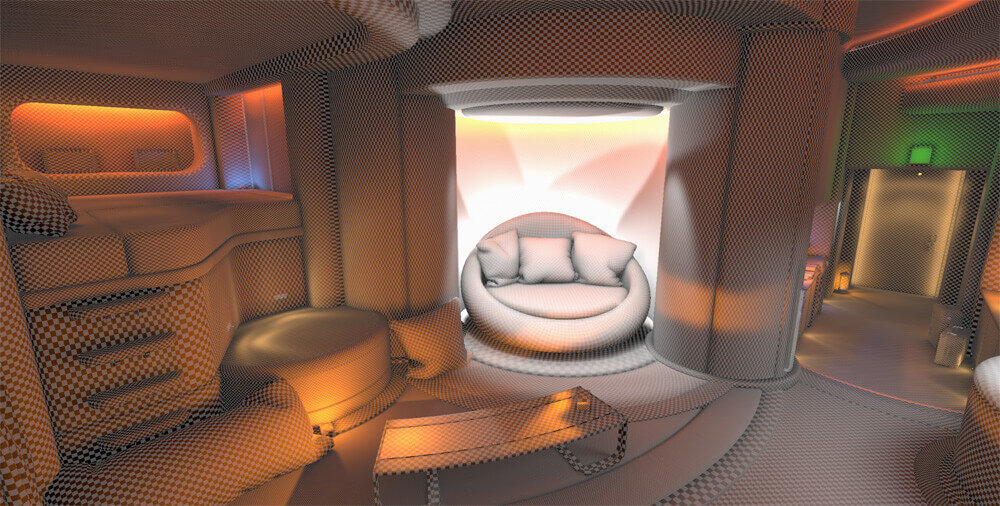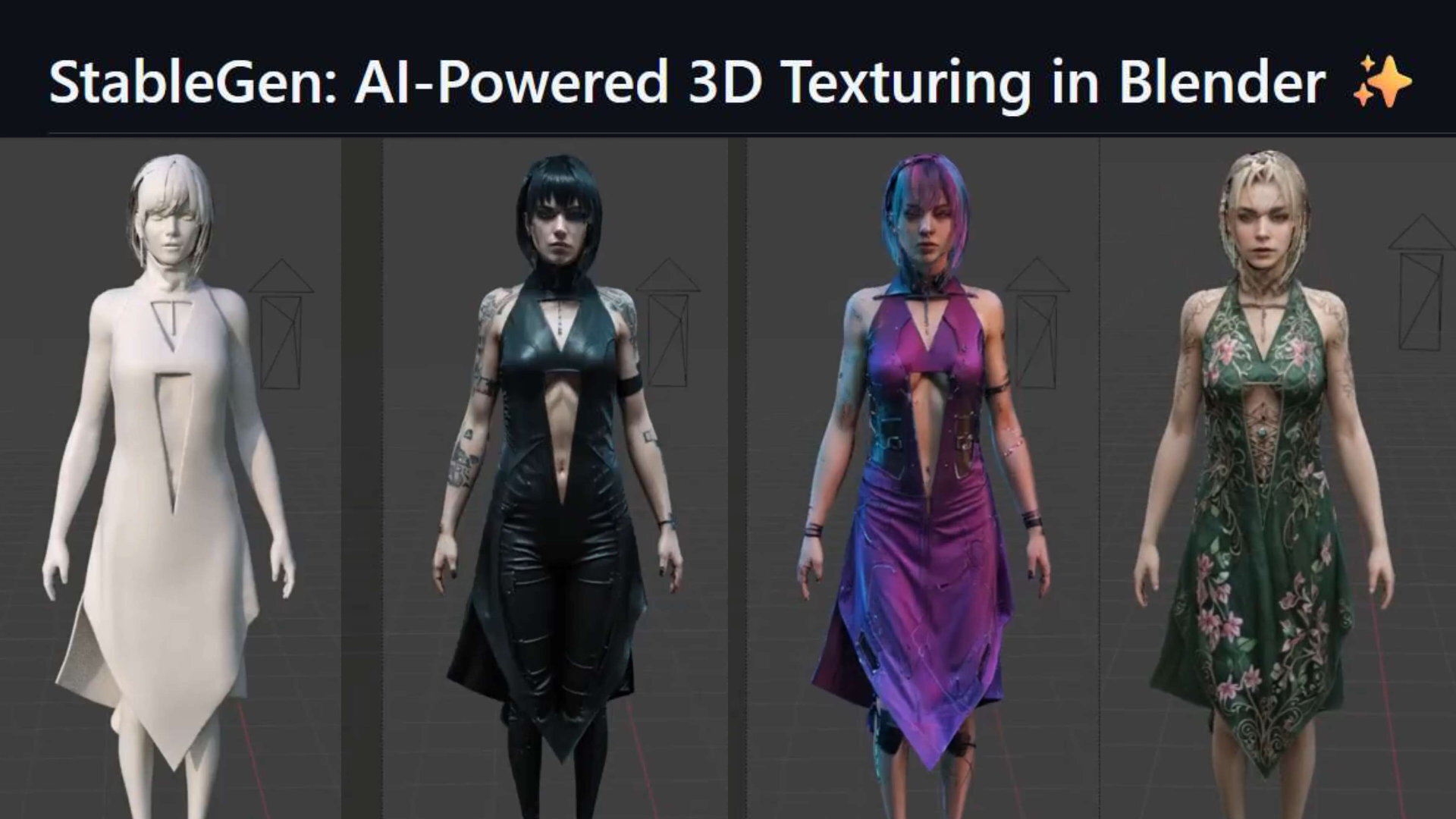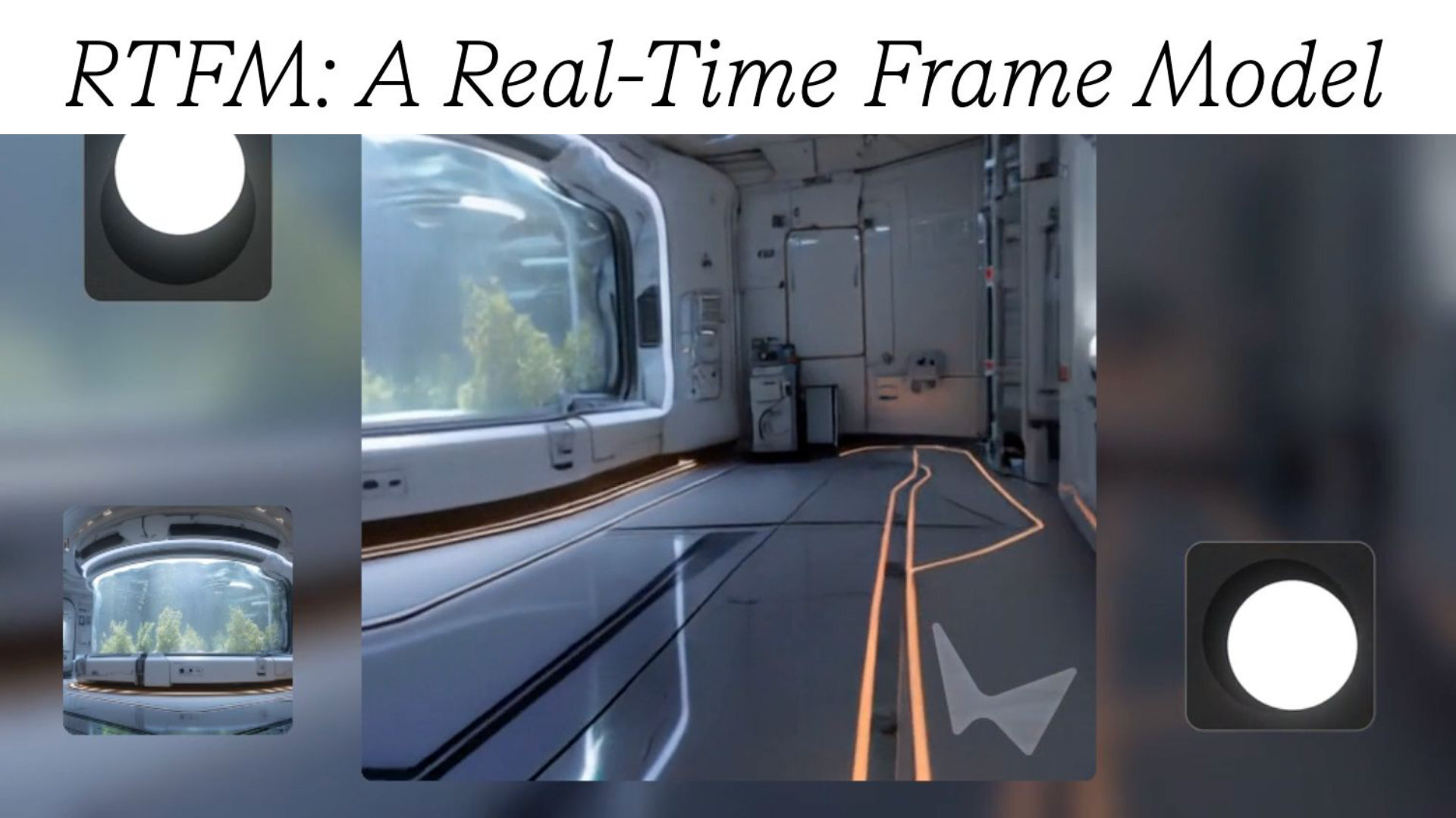「第1回 CGWORLDノベルズコンテスト」では、受賞候補2作品を選出し、CGWORLD.jpにて各作品を全12回にわたって掲載いたします。その後読者投票により各賞を決定し、それぞれ書籍として刊行する予定です。
「CGWORLDノベルズコンテスト」概要
第1回 CGWORLDノベルズコンテスト

■今後の予定
12月8日(金)〜:CGWORLD 305号とCGWORLD.jpで掲載と読者投票スタート
2024年3月頃:書籍時の扉絵イラスト募集
2024年6月頃:読者投票&扉絵イラスト結果発表
本文
ケージの引戸門扉を開けると、純一は先日と同様、受付の女性に出迎えられた。
「おはようございます」
彼女に改めて自身の経歴のデータを渡すことから、適性テストは始まる。両親が爆発事故で死去するまでの純一の人生は、宇宙港のあるこの町で生まれ育ち、宇宙旅行についての知識を多少身につけてきたこと以外は、普通そのものと言ってもよい。いや、地球全体から見れば、大いに恵まれたほうだろうか。
受付の女性が純一のインプラントにデータを送ってきた。開くと、手の甲の上に、長大な同意書のテキストが浮かび上がる。その内容は、実験の際に生命の危機にさらされるケースもあることへの注意はもちろん、徹底した守秘義務など、多岐に渡るものだった。
同意書をざっと読んで承諾した後、純一は医務室へと通された。純一の知識ではその機能を推測できない医療機器が並んでおり、床や壁はもちろん、そういった医療機器の外装までもが真っ白な部屋だ。先日訪れた応接室、ひいてはこの施設全体に通ずることだが、その清潔さが逆に不気味さを醸し出しているように純一には思えた。
次に純一は、身長、体重、体脂肪率、血圧、持病などのインプラントに記録されている膨大な身体データと、現在の実際の肉体の状態に誤差がないかをチェックされた。体内に機械式インプラント以外の異物がないことを確認するためだ。
長い身体検査の後、純一は腕に時計のような形の装置を巻かれた。
「これは、シードの成分を再現した装置だ。これで大まかに適合している人間かわかる」
そう言う所員の顔には見覚えがあった。あのギョロ目の人だ。
「突然だけど、好きな食べ物は?」
「え? ええと……」
所員がスイッチを押すと、装置から針が飛び出し、皮膚を貫く。
「……!」
「痛くなかっただろ?」
十分に痛い。へらへらと笑うギョロ目に少し苛立ちを覚えながらも、純一は医務室を出て、身体測定へと連れて行かれた。
小手調べのランニングの後、休憩を挟みながらあらゆる筋力トレーニングの種目をやらされた。純一は決して運動が得意なほうではなかったが、研究所の広い中庭を再び訪れることができたのは、うれしかった。
(僕もきっと、美しいノウムに変わって、この中庭を走り回る……)
そう思うだけで、このテストも乗り越えられる気がしたが、それは最初だけ。精神だけがたかぶっていても、運動不足の肉体はついて来れない。
「はあ……はあ……!」
ランニングだけで心臓が暴れ出しそうだった純一は、筋力トレーニングもろくにこなせないことに、絶望感を覚えていた。もう少し体を動かしておけば、そう思っても後の祭りだ。
「お疲れ様、純一くん」
夕方、受付で疲労困憊して座り込んでいる純一の耳に、聞き覚えのある声が聞こえてきた。二宮だ。
「ずいぶん遅れをとっていたな」
見上げる純一の顔に、始める前の余裕と興奮の色はない。こんな結果になることは、火を見るよりも明らかだったのだろう。その態度に、純一は少し苛立ちを覚えた。
「まあ……やれるだけは……やりましたよ」
「そうらしいな。だが、身体測定のデータでは、ダントツの最下位だ」
二宮がそのように言ったのは、純一のために時間を割かれたことへの嫌味か、それとも試験ではねられてもめげないようにという彼なりの優しさか、純一にはわからなかった。
帰宅後、緊張と数々の検査によって疲労した純一に、期待に胸を躍らせる余裕などない。汗まみれの服のままベッドへと倒れ込み、気付けば朝を迎えてしまった。
「絶対に落ちたな……」
テストの後、純一は暗澹たる気持ちだった。自分の想像力と知識では、どう考えても合格する未来が考えられなかったからだ。最初から絶望的な気持ちでいるよりも、一瞬希望を見せられてからのほうが、落差に落ち込む。そんなことを考えながら、日々を過ごしていた。
そんな適性テストから一か月後。
【△月◯日、朝七時にケージまで来てくれ。スケジュールは一日空けておくように】
拍子抜けするくらいあっさりとした文面で、純一のインプラントに二宮からメッセージが届いた。
まだ安心はできない。諦めきれずに押しかけて来るような事態が今後ないよう、丁重に断りを入れるということだって考えられる。だが、一日空けておく必要があるだろうか?
胸中で不安と期待が渦巻いていたが、ひとまず純一はその日を待つしかなかった。
「君さえよければ、このケージでの新しい被検体になってもらいたい」
先日と同じ応接室で、二宮の声が響いた。
「え……? それは……」
「嫌か?」
「い、いえ。そんなことは! ―やります。やらせてもらいます」
こうもあっさり告げられると、飛び跳ねて喜んだりはできないものだ。
「身体測定の結果は、あれでよかったんですか?」
純一が上目遣いで恐る恐る聞くと、二宮がふっ……と少し笑ったように見えた。
「あれは、肉体にシードに対する拒絶反応が出ないかを試すためのものだ。加えて、どれだけ適合率が高いかも計測していた。そして君の適合率は高かった。だから身体測定でへばっているだとか、そういうことは関係がない。まあ、体力があるに越したことはないが……」
「そうですか……」
純一はほっと胸をなで下ろした。
「そうだ。言われた通り、今日一日空けてきたんですけれど」
「ありがとう。早速だが、君にはノウムへの変異を体験してもらおうと思う」
純一の心臓は急激に鼓動を強めた。
「え、今日ですか!?」
「ああ、そうだ。家族は承諾してくれそうか?」
「―はい」
純一は嘘をついた。
「すぐタンについていき、着替えと準備を済ませたまえ」
そう言い終わると、部屋にギョロ目の所員、タンが入ってきた。
「よう。注射のときに会ったな」
「ど、どうも」
「今まで何してたんだ?」
廊下を歩いている間、タンは緊張をほぐそうという意識からか、純一にずっと話しかけていた。
「高校を卒業した後、勉強はしてて……大学への入学は決まっていました」
「進学はしないのか?」
「こっちのほうが、僕には魅力的だったから」
「そうか……まあ、願いが叶ってよかったな。でも、楽とは思わないほうがいいぞ」
どこか軽薄に話すタンに連れて行かれ、純一は医務室へと通された。最初に行われたのは、今まで純一の手に入っていた機械式インプラントの摘出だ。
「コクーンは細胞を丸ごと組み替える。変異の過程で想定外の異物があった場合、肉体の再構成時に致命的なエラーが起きるんだ。たとえうまくノウムになれたとしても、異物を脳や主要臓器の内部に巻き込んだら……」
「あんまり脅さないでください」
タンはニヤッとしながら、純一の手の甲に掃除機のようなパイプ状の器具をあてがった。その根元には箱形の装置が付いている。
「ちょっと痛いが、インプラントを抜くにはこれが一番手っ取り早いからな」
そう言って、タンがその箱の側面に付いているパネルを操作すると、低い振動音が鳴り、純一の手の甲に刺すような痛みが発生する。
「痛っ!」
「よし、終わりだ」
純一の手の甲の小さな傷に、タンはテープを貼った。続いてパイプの根元に付いていた箱を開くと、中には小さな球体が入っている。インプラントだ。思えば五歳の頃から、このインプラントと共に生きてきていたのだ。これからの人生ががらりと変わることを、摘出され、血にまみれた小さな球体が示していた。
「摘出は終わったか?」
これは、医務室に入ってきた二宮の声だ。
「はい。ばっちりですよ」
タンがニヤニヤとしながら、返事をした。
「じゃあ、純一くん。これから君にシードを注入する。タン、出してくれ」
タンが冷蔵庫から取り出したのは、緑色の液体が詰まった無骨なシリンジ。シード注入の専用器具だ。
「僕は、何になるんですか?」
純一は、ずっと気になっていた疑問を口にした。
「ん? ああ、すまない。説明がまだだった。その確認をしておかなければな……」
二宮が手の甲のインプラントを操作し、医務室にあるモニターに映像を表示させようとしている。それを眺めながら、
(この人は研究に熱中する中で、自分が知っていることを他人は理解して当然と思っている節があるんだな……)
と純一は思った。
「これだ」
そう言って、二宮がモニターに映し出したのは、黄金の羽毛に包まれ、大きな翼を生やした鳥だった。
「鳥?」
「そうだ。君のシードへの適合率なら、“これ”がいけるんじゃないかと思ってな。飛行能力を持つノウムを設計してみたのは初めてだが、君も被検体として初めてのケースだ。ちょうどいいだろう」
「―ほかの被検体の人と比べると、色以外は普通の鳥の外見ですね。大きくはありますけど」
これまで見てきた三体のノウムは、棘を生やしていたり、目が四つあったり、足が六本生えているなど、何かと身体的な特徴があった。それに比べると、やや大型だが、猛禽類のようなシルエットは、普通に見える。
「羽毛は、ただの羽毛じゃない。一つひとつが衝撃を受けた際に収縮し、硬度を増すようになっている」
二宮はモニターに映るノウムの、翼部分を指差した。純一はそれを見て、その機能が必要となる日が来ないことを少し願った。
「なるほど。鳥っていうことは、飛べるんですね?」
二宮が大きくうなずく。
「だが、慣れるまで多少時間がかかるだろうな。ほかのノウムも慣れがいるが、飛行するときは今までの体とはまったく異なる感覚が要求されるはずだ」
ふと身体測定の際の苦い記憶が蘇ったが、純一はそれを無理にでも忘れるために
「わかりました。いつでもなりますよ!」
と、二宮に告げた。
「よし。じゃあ、早速始めよう。タン」
二宮がタンを見ると、彼はうなずき、純一の左手の甲にシードを打ち込んだ。
「っ……!」
適性テストで打ち込まれた装置と、刺された瞬間の痛みは同質だった。だが、その後が異なる。針の塊が、その先端を伸ばしながら、その勢力を広げていくような痛み……数分間の間、純一はそれに耐える必要があった。
「馴染んだようですね」
「そうだな」
あくまで冷静な二宮とタンだったが、当事者である純一の体は、すっかり脂汗まみれになっていた。
シャワーで全身の汗を流し、消毒された後、純一はノウムへ変異する被検体専用の着替えを渡された。乳白色のシャツと、ズボンだ。
「コクーンに対応したものです」
と、着替えを渡してきた所員は言った。湿ってもいないのに、ぬるぬるとした肌触りがあり、純一にはそれがやや不快だった。
ロッカールームには、多少使用された痕跡があった。同性なら、あの蛇の男だろうか?
純一は彼に出会うのが少し楽しみになった。
準備を経て、ようやく純一は変異室へと足を踏み入れた。大量のケーブルに繋がれた、金属製のカプセル、コクーンを間近に見るのは初めてのことだ。
「ここから中庭に出られるんですか?」
純一が疑問を投げかけると、二宮は得意気に笑い、タンに顎で合図をした。
タンが機器を操作すると、それまで純一が壁だと思っていた部屋の一面がスライドし、日光が差し込んできた。ノウムはこのゲートを通って、中庭に出るわけだ。
「やっとだ……」
思わず心情が口に出ていたことに、純一は気付いていなかった。
「そう。やっとだ」
と、二宮も言う。無機質な作動音を立てながら、コクーンが展開した。
「よし、あの中に……」
二宮が何か言っていたが、もう純一の耳に、指示は聞こえない。いや、言われなくともわかっていた。入って、ノウムになればいい。
コクーンの中に入ると、モーター音と共にハッチがゆっくりと閉じる。狭く、外部の音がほぼ遮断されて、中で響くのは純一の呼吸音だけだ。
「では、これより第四被検体の変異実験を開始する。純一くん、準備はいいな?」
二宮の声がカプセル内に響いた。先日見た被検体たちはコクーンから光が放たれた後、ノウムと化していたが、一体どのようなプロセスを経て肉体の溶解・再構成がなされるのだろうか。
「返事は?」
という声で、純一は現実に戻ってきた。
(そんなことを今更気にしても、仕方がない。ここまで来たのだから、やってみればわかることだ)
と自分に言い聞かせ、
「はい。準備できています」
と答えた。
『ノウム・シーケンス、開始します』
無機質な声が響き渡った後、カプセルの内部を照明が照らした。やがて、振動と低い音が内部に充満し始め―純一の期待が、徐々に不安に塗り潰されていく。
『異物除去を開始』
まず、先ほど着替えさせられた純一の服が液化し、取り除かれた。少し恥ずかしさを覚えたが、今更気にしても仕方がない。
『溶解プロセスに移行』
そして、変異は始まった。
最初に自分の肉体の変化に純一が気付いたのは、音を立て始めたコクーンの中で、不意に顔をかこうと思ったときだ。顔をかこうとする指だけでなく、腕そのものの感覚が消えていた。顔を起こし、自らの体に目をやると、腕が、足が、胸が溶け始め、血と肌の色が混じったピンクの液体となってとめどなく体から流れ出している。純一は痛みも感じずに自身の体が溶解している光景に、思わず叫び声をあげようと試みた。―が、それも無駄に終わった。すでに、喉が溶け落ちていたのだ。
「……!! ……!」
動くこともできず、当初はパニックに陥っていた純一であったが、眼球の溶解と共に視力も消失し、やがて、意識から不快感すらもなくなっていった。純一には見ることができないが、脳が溶け始めたのだ。
それから少しすると、純一だったもの―ピンクの液体はカプセルを満たし、彼の意識は、深い深い闇の底に消えていった。
ここまでは想定通り。二宮はそう考えていた。問題は、この液体となった純一が、ノウムの形に再構成され、生命活動を行えるかだ。
モニターには、ピンクの溶液と化した純一を、シードが記録された情報に基づいて、ノウムへと再構成していく様が映し出されていた。骨、筋肉、皮膚、羽毛など驚異的な速度で部位が出来上がっていき―黄金の鳥が、鉄の蛹から羽化しようとしていた。
純一の意識が最初に感じたのは、眩しさだった。次に、肌に触れるコクーン内部の空気、そしてコクーンの機械音が、徐々に聞こえてくる。だが、いくら五感を取り戻しても、思考の外周に霧がかかっている感触が消えない。
「大丈夫か? 動けるか?」
という声が聞こえてきた。「はい」と言おうとして、純一は自身の口から低い声とは言えない音が飛び出してきたことに驚いた。
その音を返事と認識してもらえたのか、コクーンのハッチが開いた。
「言葉がわかるなら、自分の体を見てみろ」
と言われて起き上がり、周囲を見渡すと、まず周囲の色がおかしいことに気付いた。絞りを開いたカメラのように、視界の中で変異室の光が強調されている。
「開けろ」
と声が聞こえ、ゲートが開いた。そうだ。ここは中庭に繋がっているのだ。
木々が生い茂っているのが見える。陽の光が、いつもより眩しい。純一がふと自身の体を見ると、陽の光で羽毛がキラキラと輝いているのがわかった。そうか、自分はノウムへと変わったのだ。
「飛べるか、試してみてくれ」
と言われた純一だったが、そう言われてもやり方がわからない。体を作り替えられても、腕の代わりについている翼をどう振るえばよいか、コクーンは教えてくれなかった。鈍い思考の中で、純一が思いついたのは、ひとまず翼を広げ、思い切りジャンプしてみることだった。
力一杯羽ばたき、ジャンプをした瞬間、純一の体に衝撃が走った。中庭にすら届かず、純一の肉体は重力に引っ張られ、変異室の金属の床に思い切りたたきつけられたのだ。
気を失う直前、純一は金属の床に映り込む自分の顔を見た。黄金の鳥と化し、その瞳は緑色に輝いている。
続きは毎週月・木曜に順次公開予定です!(祝日及び年末年始を除く)
日程は公開リストよりご確認ください。
『美術商ローラと家路を急ぐ青年』はこちらに掲載しています。
読者投票
読者投票は以下からご参加ください。ぜひお気に入りの作品に投票をお願いします!
読者投票はこちらから※締切:2024年1月25日(木)23:59まで
※回答は1人1回までとさせていただきます。