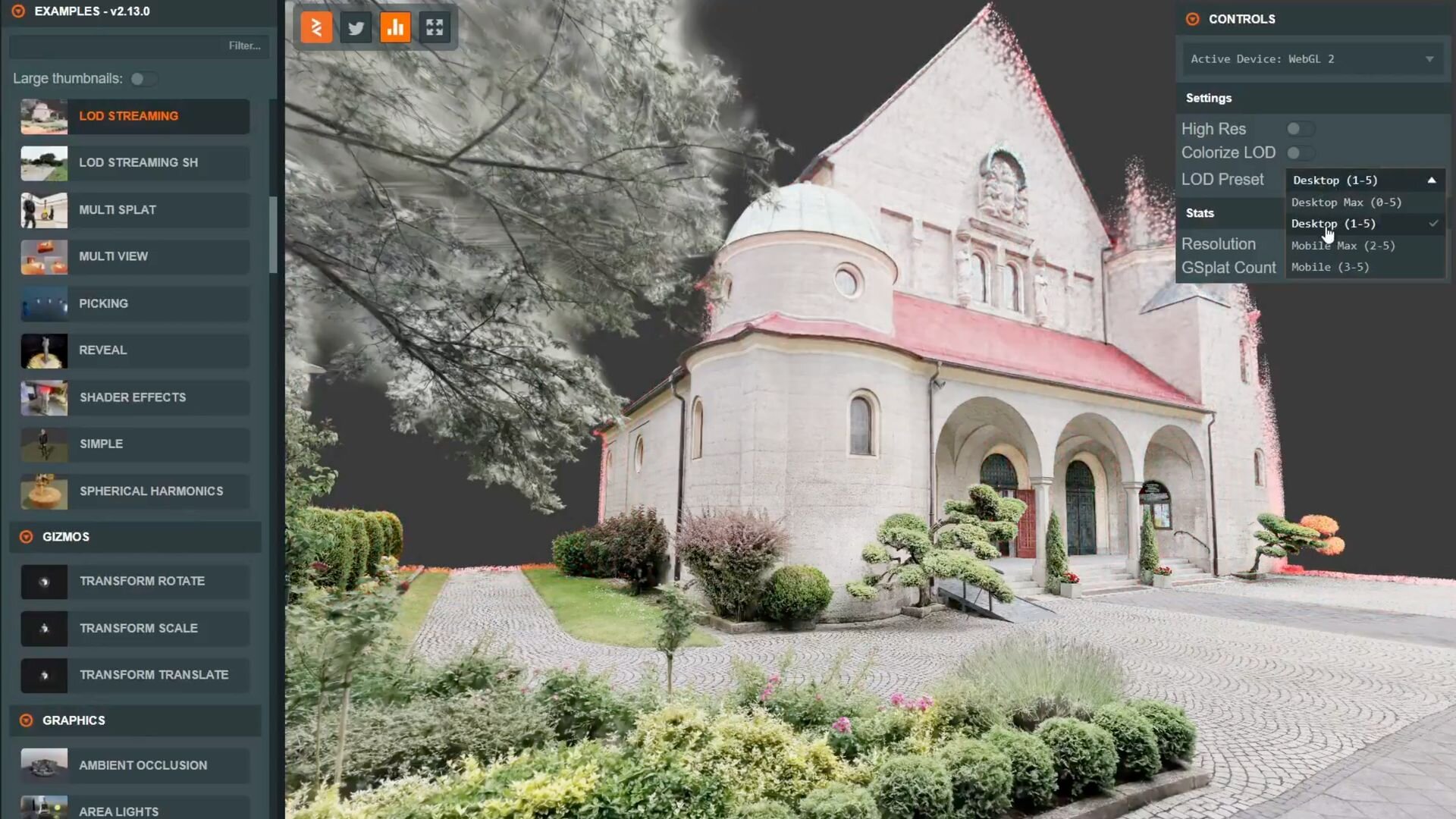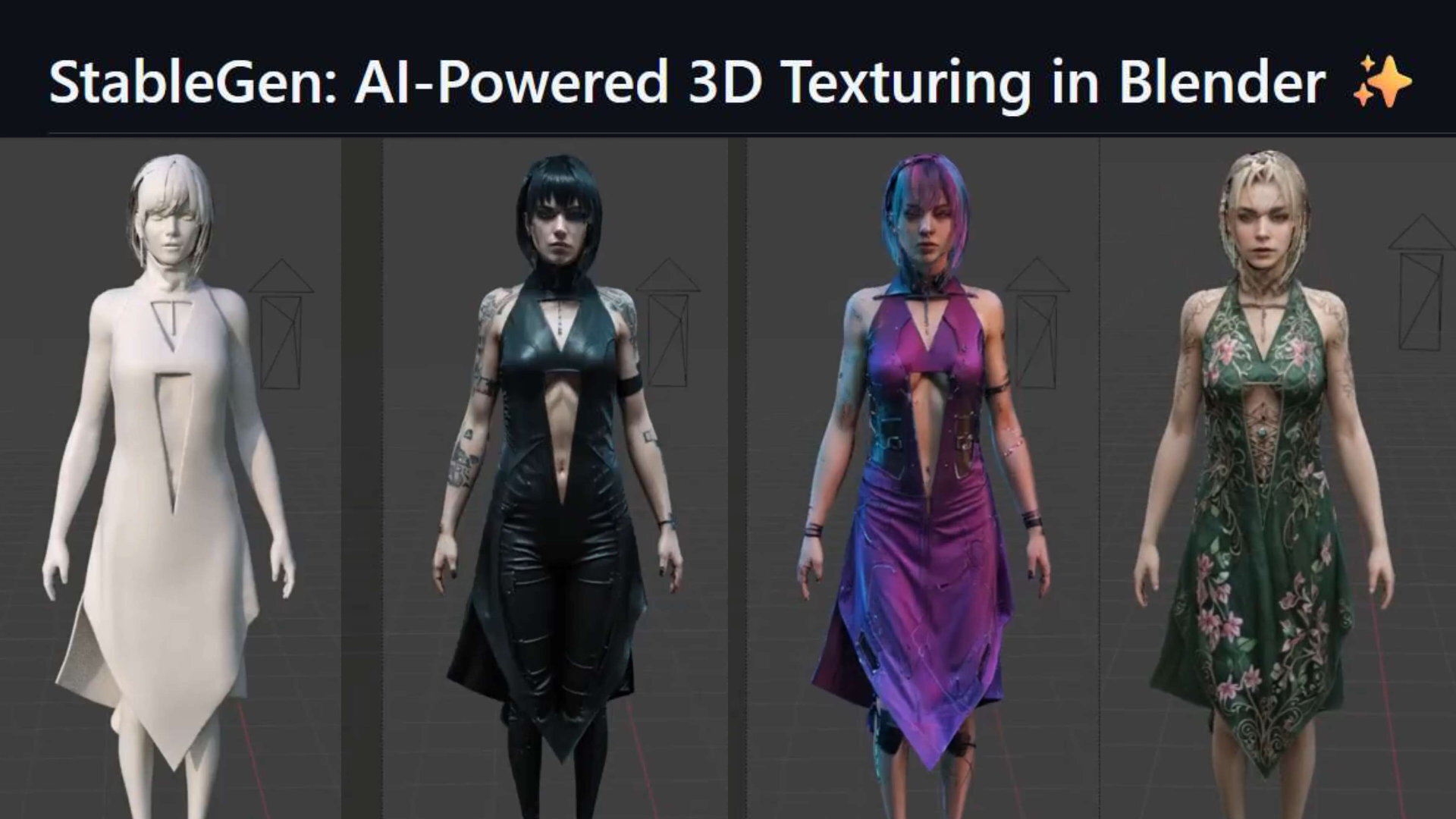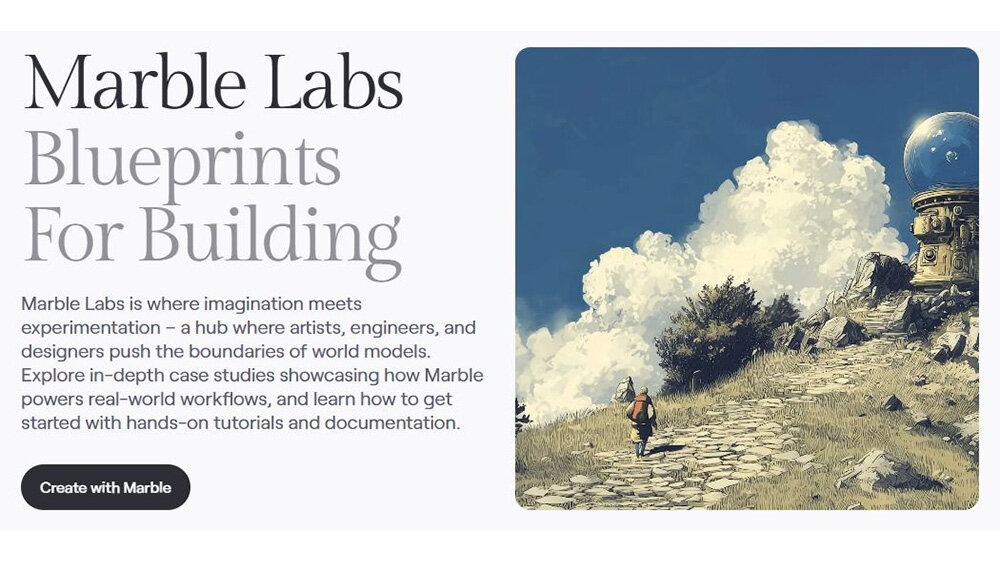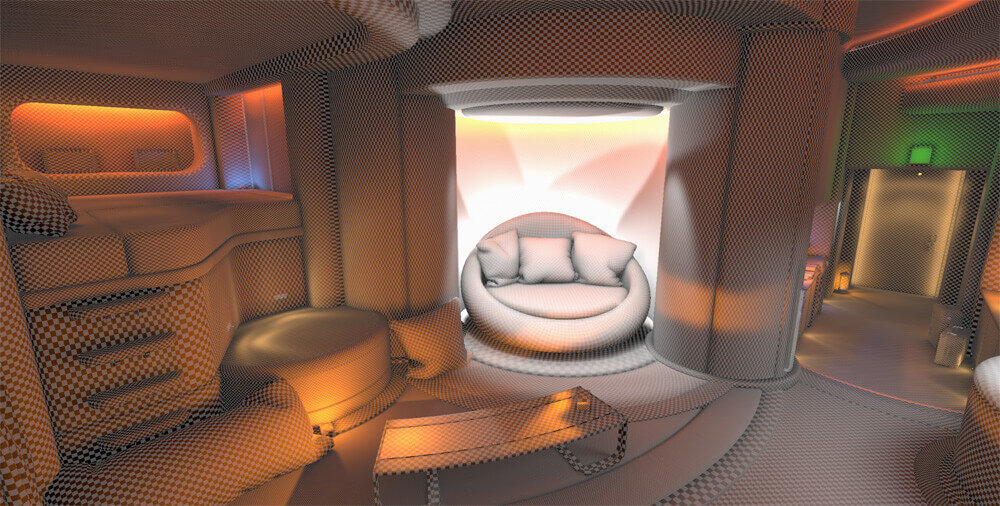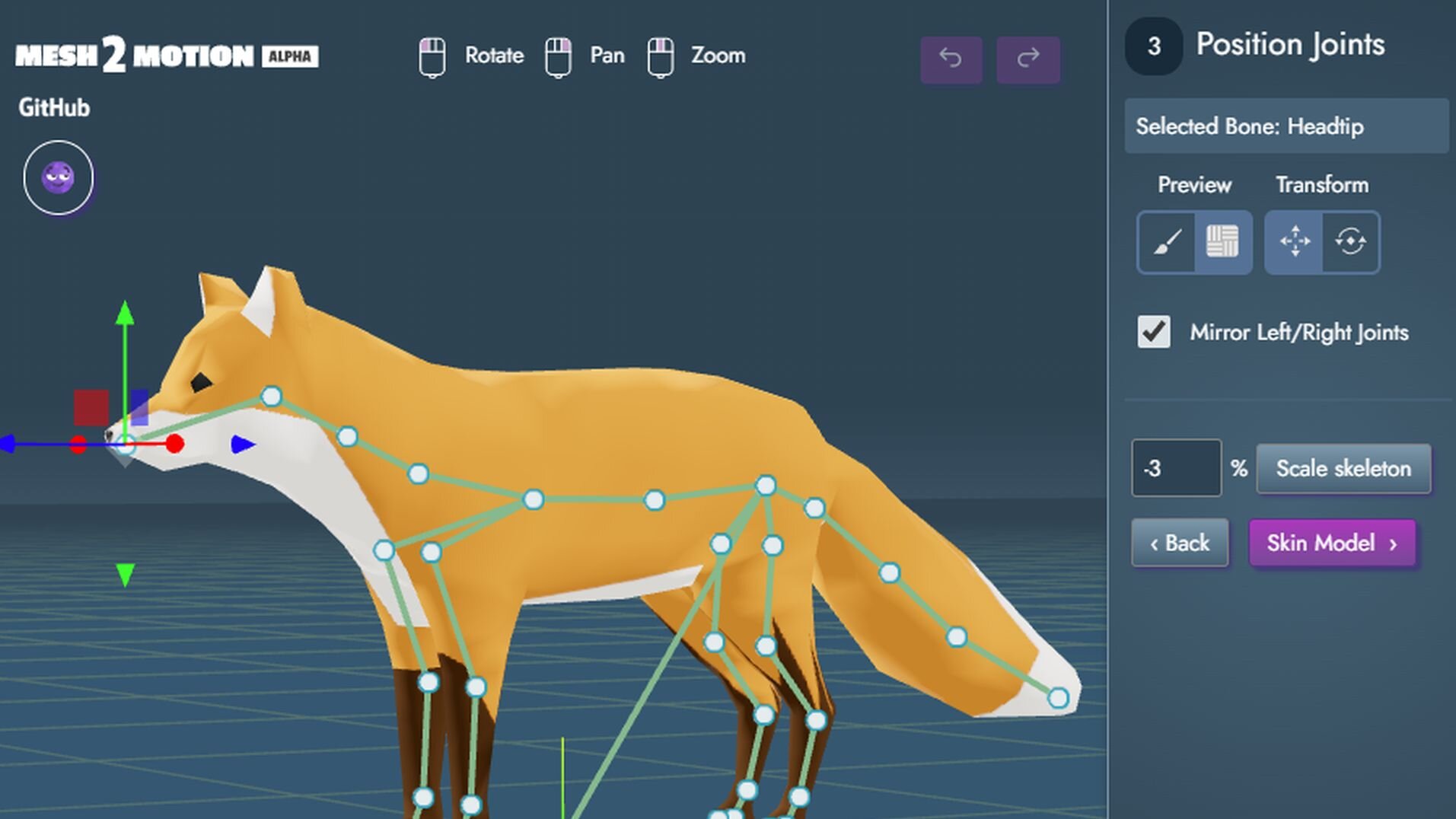「第1回 CGWORLDノベルズコンテスト」では、受賞候補2作品を選出し、CGWORLD.jpにて各作品を全12回にわたって掲載いたします。その後読者投票により各賞を決定し、それぞれ書籍として刊行する予定です。
「CGWORLDノベルズコンテスト」概要
第1回 CGWORLDノベルズコンテスト

■今後の予定
12月8日(金)〜:CGWORLD 305号とCGWORLD.jpで掲載と読者投票スタート
2024年3月頃:書籍時の扉絵イラスト募集
2024年6月頃:読者投票&扉絵イラスト結果発表
本文
一行の車は、中心街にある駐車場に停車している。
「来たいとは言ったけど、食事が代わり映えしないとなあ」
ぼやきながら、車内でシーナはノウム専用食をかじった。
「しょうがないだろ? ノウムとして、栄養状態の管理は徹底したいって二宮さんたちが言うんだから」
「その上、見張りまでいるとなあ……」
シーナはじろっとタンを見た。
「うるさいな! 連れて来てやったんだからありがたいと思え!」
そんな口論を聞きながら、純一は窓から外の景色を見ていた。
「何黄昏てんだよ」
ティトだ。
「いや別に。久々に来てみると、意外と悪くないなって思って」
「まだこれからだろ?」
「そうだけどさ」
昼食を終えた一行は、いよいよ街へと繰り出す。
「―俺はお前たちに見えないところにいるけど、絶対目は離さないからな。逃げようと思っても、シードの位置は追跡できるし、はめ外しすぎんなよ。あと、買い食い厳禁。発見したら今回の外出は終わりだ」
「はーい」
「あいよ」
「はい」
「はい……」
二時間後に再び車に集合することを条件に、被検体たちは自由行動となった。
「じゃあ、行くぞ!」
「よし!」
ティトとシーナが気合いを入れて向かったのは、ゲームセンターだ。ティトとシーナは自室の端末でもゲームに励んでいるらしいが、この手の遊戯施設に設置されている体感型ゲームの話を耳にしてから、ずっとプレイしてみたかったらしい。
「こいつ! 死ね!」
「ティト、そっち行ったよ! さっさと始末して!」
物騒な言葉を叫びながらゲーム内で共闘する二人を、しばらく純一とマレは眺めていた。
「ちょっと水買ってくるよ」
「うん」
その、純一がほんの少し目を離した一瞬に、マレは消えていた。
「ねえ、マレがいないんだけど?」
「なんだって?」
「マレが! いない!」
ティトが周囲を見渡すと、確かに彼女の姿はどこにも見えない。だが、彼はそれほど心配していなかった。
「あいつも子どもじゃねえし、気になる店にでも行ったんじゃねえの? 時間になったら戻ってくるって」
そう言われても、時間が経てば経つほど、純一はじわじわとマレが気になっていった。その気持ちが頂点に達し、純一は二人をその場に置いて店外へと出ていく。
マレの姿はどこにも見えない。子ども時代から馴染みのある街が、今の純一には迷宮のように思えた。遠くには行っていないはずだが、マレの行きそうな店を連想することが純一にはできない。しばらくの間、純一は町の中心部を右往左往する羽目になった。
路地裏で、ようやく純一はマレを発見した。フードを被っているとはいえ、その隙間からはみ出た青白い髪と、長い手袋はよく目立つ。
彼女がいたのは、古い紙書籍を扱う店だ。読書をインプラントを介して行うようになってからは、紙の書籍に触れる機会は、こんな店くらいしかない。
「……」
マレは、何やら分厚い本を両手で開き、立ち読みしている。
「マレ」
呼びかけても反応はない。だが、その紫の瞳には、これまで見たこともない光が灯っていることがわかった。
「マレ!」
びくっとマレが反応し、純一を見る。紫の目を素早く瞬かせながら驚くその表情もまた、純一が初めて見る彼女の顔だった。
「―どうしたの?」
マレは、普段通り鋭い表情に戻っていた。
純一はしゃがみこんで、マレの読んでいた本の表紙を見た。そこには、『星の海の夜明け』と書かれている。
マレが開いているページに目を落とすと、そこには新天地となる星に向かって突き進む船のイラストが描かれていた。おそらくは、生存可能領域の探査を行う計画が浮上し始めた時期の本だろう。だが、未だに夜明けは来ていない。純一は、本の中に広がる宇宙空間を見て、そこで散った両親のことを想像せずにはいられなかった。
「で、なんで私のところに来たの?」
とマレが純一に聞いてきた。
「その……いきなりいなくなったからさ。そろそろみんなの所に戻ろう」
返事の代わりにマレは本を閉じたが、本を店頭の棚には戻そうとしない。持ったまま、じっと表紙を眺めている。
「そんなに欲しいなら、買えばいいんじゃないか?」
と言うと、マレは
「それが、高くて……」とこぼした。
背表紙に貼られている値札を見ると、確かにそこそこの値段がした。事前に被検体たちに支給されている小遣いでは、やや届かない。
「いいよ、買おう。僕も読んでみたいから」
石のようにその場に立ちすくむマレを、そのままにしておくわけにもいかなかった。放っておいたら、明日の朝まで居続けそうだったからだ。実際、純一自身も、興味がないわけではない。
「本当に?」
「うん。その代わり、僕にも読ませてよ」
「―ありがとう、純一」
それは、純一が初めて見る彼女の笑顔だった。
ゲームセンターに戻ると、疲れ切ったティトとシーナがベンチに座っていた。
「あのデブとガリのコンビには、勝てなかったな」
「そうだね……」
どうもゲームで強敵と対峙していたらしい。
それからしばらくの間、純一たちは繁華街を散策した。ティトとシーナから「あの店は何だ?」「じゃあ、あれは!?」と聞かれる度に解説するのに疲れはしたものの、答える度に二人が目を輝かせるため、悪い気はしなかった。
「よし、そろそろ移動時間だ」
タンが四人の前に現れたことで、散策の時間は終わった。不意に現れたところを見ると、どうやら本当に付かず離れず監視していたらしい。
「えー! もう!?」
「あのモールに行きたいんだろ? だったら今行かないと、時間なくなるぞ」
確かに、中心部から郊外までは車で一時間ほどかかる。ティトとシーナもそれはわかっていたため、渋々と従った。
車でモールに向かう道中も、着いてからも、マレは先ほど購入した本の魅力に取り憑かれていた。
「ほら、もう着いたよ」
とシーナが声を掛けるまではモールに着いたことにも気付いておらず、モールの中でも、歩きながら本を読んでいる。
「マレ、歩きながら読んじゃダメだよ」
と純一が声を掛けると、マレは顔を上げ、「うん」と答え、一度はしまう。
だが、しばらくするとまた取り出し、読むのを再開するのだった。
一方のティトとシーナは、モールに着くやいなや各店舗を回り、ひたすらに物色をし始めていた。二人は特に菓子類に興味を示し、店頭に並ぶ色鮮やかなケーキをじっと眺めている一幕もあった。専用食以外の食料の類は施設内に持ち込むことが禁止されていたが……。
そんな二人が、それまでとは少し違う反応を見せた瞬間があった。モールの一角にある、異国のアクセサリーを扱う店でのことだ。
「わあ!」
柔らかい笑顔を見せて、シーナは真鍮色のブレスレットを手に取る。ティトも、見たこともないような優しい顔つきになって、それを眺めている。
「懐かしいな……。お前、あの頃覚えてるか?」
「そりゃもちろん! みんな、こういうの着けてたよね」
そう答えて、シーナは愛おしげにブレスレットの表面を撫でた。
(そういえば、二人は昔番号で呼ばれていたって言ってたな……)
そのとき、純一の左腕が振動する。そろそろ門限に設定された時間が近いことを腕時計が訴えかけているのだ。
「みんな、そろそろ行かなきゃ」
そんな純一の言葉を聞いて、相変わらず本を読みふけっているマレはともかく、ティトとシーナの顔には少なからず落胆があった。
「はあ……」
「せめて何か食べていきたかったよねえ」
と二人はぼやいている。
「おい、お前ら。時間だ」
四人の背後から、タンが現れた。
「おい、タン。お前、せっかく出かけたんだから……その……」
エスカレーターに乗りながら、タンの背中に向かってティトが投げかける。
「どこかで食事を……とかはねえのかよ」
「いや、俺はお前らと違って、施設で何を食べてもいいからな」
タンは振り向かずに答えた。
「哀れな被検体に、ちょっとだけお目こぼしをするみたいなのは?」
「ない」
ティトの質問に、タンは即答した。
そんな話をしていると、いろいろな飲食物の匂いが混ざった、なんとも空腹感を刺激する香りが漂ってきた。一階には、多様な飲食店がならんでいるのだ。
「ああ、いいないいなー!」
シーナの目は、ガラス越しに見える、夕飯を楽しむ人々に向けられていた。
「いいな……」
それに同調したのか、後ろに立つマレが、ぼそっと呟いたのが純一にだけ聞こえていた。
モールの入口に歩いて向かうまで、主にティトとシーナから、外食を求める声が上がり続けた。すると突然タンが振り向き……。
「しょうがねえな……」
と言った。
「……ほんとか?」
と言ったのはティトだ。シーナは何も言わずに……とても悪い笑顔になっていた。
「ああ。まあ、たまにはいいだろ……。ただ、絶対今後の訓練と内覧会ではヘマしないこと! もしこのせいで失敗でもしたら、俺はクビだけじゃ済まない。わかったら、さっさと店を選べ」
厳正な討議の末に、今晩の夕食は、モールの一階にあるファストフード店に決まった。純一にとってはまったく特別感のない食事だが、ティトとシーナは、以前からハンバーガーに憧れていたらしい。
席で紙袋を開き、実物を見た途端、二人の目は、獲物に襲いかかる爬虫類のそれへと変貌した。
「うまい! こんなうまいもん初めてだ!」
そう言いながら、ティトは笑顔で巨大なハンバーガーをむさぼっている。同じ物を食べているシーナも、感動の余り目に涙を浮かべながら、大きな口でかぶりついている。純一の脳裏では、それが一瞬ノウムとなったときの姿を連想させたが、さすがに失礼かと思い、言わなかった。
「ほんと、感謝しろよ」
タンが苦笑している。そのとき、純一はふと気になっていたことを口にした。
「そういえば、二人は被検体になるまではどんな暮らしだったの?」
アクセサリー屋でティトとシーナが見せた表情が、純一の心の中に引っかかっていた。
それを聞いたティトとシーナが、顔を見合わせる。
「―別に隠してねえけど、可哀想すぎて同情しちゃうかもよ?」
ニヤニヤしながら、ティトが言った。
「そんなに……?」
「私たちの国はとっても貧しかったんだよ。で……金に困ってた親は、幼い私たちを人買いに売ったって、私たちを買ったやつらは言ってたね」
「クアドロの二宮の部署が俺たちを買い取って、被検体に選ばれてからは、ずっと今みたいな暮らしだ」
あっけらかんと話す二人に対して、純一は口ごもることしかできなかった。
(僕はこの地球のことだって、何も知らなかったんだな……)
改めて、自分が見ていた世界の狭さを、思い知らされた。
「気にしないでよ。少なくとも私たち二人は、とりあえず生活が保障されているだけで満足してるんだから」
ティトも、うなずいてそれに同意する。
「外で暮らしたいとかは思わないの?」
「んー……。今日みたいなのは楽しかったけど、今のままの生活でいいかな。安定が一番!」
そういうシーナの横で、遠くを見るティトの視線の先には、遠い故郷の風景が広がっているように純一には見えた。
「だけど、もし追い出されでもしたら、また子どもの頃に戻っちまう。だからそれなりには二宮たちに従ってるんだ。まあ、宇宙に興味はないけどな」
純一がどう返そうか迷っていると、突然ティトは眉間にしわを寄せる。
「だからって、俺らに変に気を遣ったり、上から目線で何か教えてやるって感じの態度はやめろよな!」
「わ、わかったよ」
本人が気にするなと言っているのだから……純一は、ひとまずこの件については触れないでおくことにした。
「ま、せいぜい頑張ってくれ。俺の人生もかかってる」
そう言って、タンは笑う。
「タンさんの人生も?」
「ああ。俺は二宮さんの助手と、お前らの補助が仕事だからな。お前らが宇宙に行くときは、同行することになるだろう。ほかにできる仕事もないしな」
やや深刻な話にもかかわらず、タンは笑顔を絶やさない。だが、その瞳は笑っていないように、純一には感じられた。
「―……早く行きたいね」
本から顔を上げたマレが、ぽつりと呟いた。
「そうだね、マレにはそれが一番だもんね」
シーナが微笑む。
「マレは俺たちより先にケージにはいたが、年は下でな。あの頃は無茶ばっかりしてて、後から来た俺たちがヒヤヒヤするくらいだった」
「そ、そういう話はしなくていいって!」
紫の目を見開き、やや慌てているマレの顔が、純一には新鮮だった。この場では続きを聞けそうにないのはやや心残りだったが。
「……必ずみんなで行こう! あと、さっき買った本のことでわからないことがあったら、なんでも聞いて。父さんと母さんの受け売りも多いんだけど……」
純一がそう言うと、マレは小さく笑って、上を見上げる。吹き抜け構造になっているモールの天井はガラス張りで、頭上では雲に包まれた月が、ぼんやりと光を放っていた。
「―いやー、食った食った!」
「楽しかったね!」
外に出ると、ティトとシーナが大きく伸びをしながら口々に今日の外出の感想を述べる。
「僕も、こんなに楽しい外出は、家族で出かけたとき以来だったなあ」
「なんだ、お前。友達とかいなかったのか?」
単刀直入に聞いてきたティトに対して、純一が嫌な顔をしてみせると、ティトは意地悪そうに口角を上げる。純一は、自分の想像以上にこの日の外出を楽しみ、何よりも、このような軽いやりとりを仲間たちとできるようになれたことが、とてもうれしかった。
(マレはどうだったんだろう……)
純一がマレを見ると、夜空を見上げ、月明かりに照らされている彼女の表情は明るい。愚問だと思った。
このときマレは、心の中で今日の記憶を噛みしめ、反復していた。宇宙港を見たことや、街角での本との出会い、みんなで食べた外の食事。そして、駐車場に立ちこめる、木々から発せられた青い香りまで、今日触れたもののすべてを取っておきたい。そう思っていた。
続きは毎週月・木曜に順次公開予定です!(祝日及び年末年始を除く)
次回は、1月5日公開予定です。
日程は公開リストよりご確認ください。
『美術商ローラと家路を急ぐ青年』はこちらに掲載しています。
読者投票
読者投票は以下からご参加ください。ぜひお気に入りの作品に投票をお願いします!
読者投票はこちらから※締切:2024年1月25日(木)23:59まで
※回答は1人1回までとさせていただきます。