現在バンクーバーのILMに所属する世界的なコンセプトアーティスト・田島光二氏。画像生成AIにも早くから着目し、専用のコミュニティを起ち上げるなど積極的に活動している。「AI」をテーマとした表紙ビジュアルの制作過程を通して、田島氏の思考の足跡を辿っていく。
画像生成AIとの接し方とアーティストとしての想い
国内外の多数の大作映画に名を連ねるコンセプトアーティスト・田島光二氏は、その卓越したアートの手腕はもちろんのこと、SNS上では新しい技術への情報収集・発信への積極性を窺い知ることができる。画像生成AI技術についてもここ数年の発展を追ってきた田島氏だが、今年6月の「Midjourney」との出会いはひとつの転機になったことだろう。

田島光二/Kouji Tajima
1990年生まれ、東京出身。2011年に日本電子専門学校コンピューター・グラフィックス科を卒業。2012年4月にロンドンのVFX制作会社ダブル・ネガティブに入社しコンセプトアーティストとしてのキャリアをスタート。2018年9月にシニアコンセプトアーティストとしてルーカスフィルムのVFX部門であるILMへ移籍し、現職。
Twitter:@Kouji_Tajima Instagram:@koujitajima
www.artstation.com/koujitajima
「基本的には『実際には存在しないもの』をデザインする仕事をしていますが、当然ながら資料やアイデアソースは非常に限られます。これまでは画像検索や画像収集サイトを活用してきましたが、どうしても情報収集能力や視点の影響を受けます。画像生成AIを使えば、完全に考えがないところからでも多数のバリエーションを得ることができ、自分の引き出しになかった視点での参考資料にすることができるんです」と田島氏が語るように、最もメリットを発揮するのはデザイン対象の資料が乏しいとき、方向性が定まっていないときだ。「自分の思いつかないものが出てくるのは面白いですね。イメージが具体的にある状態で『これがほしいんだ』という使い方は難しい。なんとかねらいのものを出そうと試行錯誤していると意外と時間がかかってしまったりします(苦笑)。最終イメージを求めるのではなく、現段階では創作のお供くらいの接し方がいいと考えています」(田島氏)。
一方で、生成したアートを業務にそのまま用いるには様々な論点があり難しい。例えば、活躍している現役アーティストの特徴を学習したモデルを用いて、そのアーティストの作品と見まごう画像がSNSに投稿されることもある。「そういうことをされた場合、自分だったら……面白い気もするかもしれないし、ちょっと嫌かもしれないし、複雑ですね。またデメリットかどうかはわからないですが、何が良いのかわからなくなってくる怖さはあるかもしれないです。カッコ良い・綺麗な画像ばかり大量に生成していると、ゲシュタルト崩壊のような感覚が起きてきます」(田島氏)。画像生成AIはアイデアが乏しくコンセプトが曖昧なときに強みを発揮するが、だからこそユーザーはそれに振り回されないよう、自分なりの審美眼を強くもっておく必要があるだろう。現状の田島氏の使い方としては、デメリットよりは得られるメリットに着目し、デザインの着想や資料画像の一種として用いているという。
画像生成AIが広く普及することとなった現在、絵の仕事も「この人に頼みたい」と思われるような何かがなければ減っていくのではないかと田島氏は予想する。アーティストによっては職が狭まり、または失うこともあるかもしれない。「今はアイデアをもらうのに使っていますが、逆にわれわれがアイデアを出してAIが完成させるという未来もありえます。ただ、つまらなくなる部分もあれば面白くなる部分もあるはずなので、自分なりのアイデアを込めて『自分の作品』として取り組める範疇があると楽しいなと思いますね」(田島氏)。
<01>画像生成AIとの出会いと初期の活動
Midjourneyへの没頭からコミュニティを起ち上げる
ここ数年は何度となく話題になってきた画像生成AIだが、その都度新しいものに触れてきたという田島氏。これまでは「用意された画像を混ぜて新しい画像を生成する」「シンプルな図像から顔などを生成する」などに留まっていたAIアートの印象が、「Midjourney」の登場により一変したという。「数ヶ月前、僕がフォローしている著名アーティストさんがどんどんとものすごいアートを投稿するようになりました。AIアートらしく一定のクセのようなものは感じられて、みんなが投稿しているコレはなんだろうとタグを辿っていって、Midjourneyに出会いました」(田島氏)。
それまで触れてきた画像生成AIの印象から最初は半信半疑だったという田島氏だが、プロンプトに沿った画像が出てくる様子に認識を改め、「一気に来たな」とAI技術の進歩の目覚ましさに驚いたという。「ちょうどAIアート投稿に興味を示したコンセプトアーティストの方と意気投合し、ビッグウェーブに乗る勢いで有料プランに課金して、一緒に一晩中アートを生成しました。新しいゲームが出たときのような楽しさでしたし、交流が始まるきっかけにもなりました」と、画像生成AIサービスを起点に新たな出会いもあったとのこと。
この頃はMidjourneyのユーザーはほぼ海外アーティストのみという状況で、日本語での情報発信はほとんどみられなかった。そこで田島氏は、日本のユーザーに向けた情報発信や、みんなで楽しめる場としてTwitterコミュニティ「全日本AIアート同好会」を起ち上げた。情報共有やAIアート作品発表が行えるゆるい集まりとして、現在は約700名の大所帯となっている。
ちなみに田島氏はMidjourneyの探求やコミュニティ起ち上げに着手する一方、並行してUnreal Engine 5の学習を進める様子も投稿。アート・テクニカル両面に幅広くアンテナを張るのに余念がない様子が窺われる。今後もひき続き新しい情報は積極的に取り入れていくと意欲をのぞかせた。
現在の田島氏の画像生成AIの使用割合としては、個人制作では自分が想像して手を動かす楽しみを最優先に、時折刺激をもらうために使用する程度。一方、イメージの共有等では大きな助けになると感じていることから、仕事で用いる割合の方が高くなる見込みとのこと。
メインで使用している画像生成AI
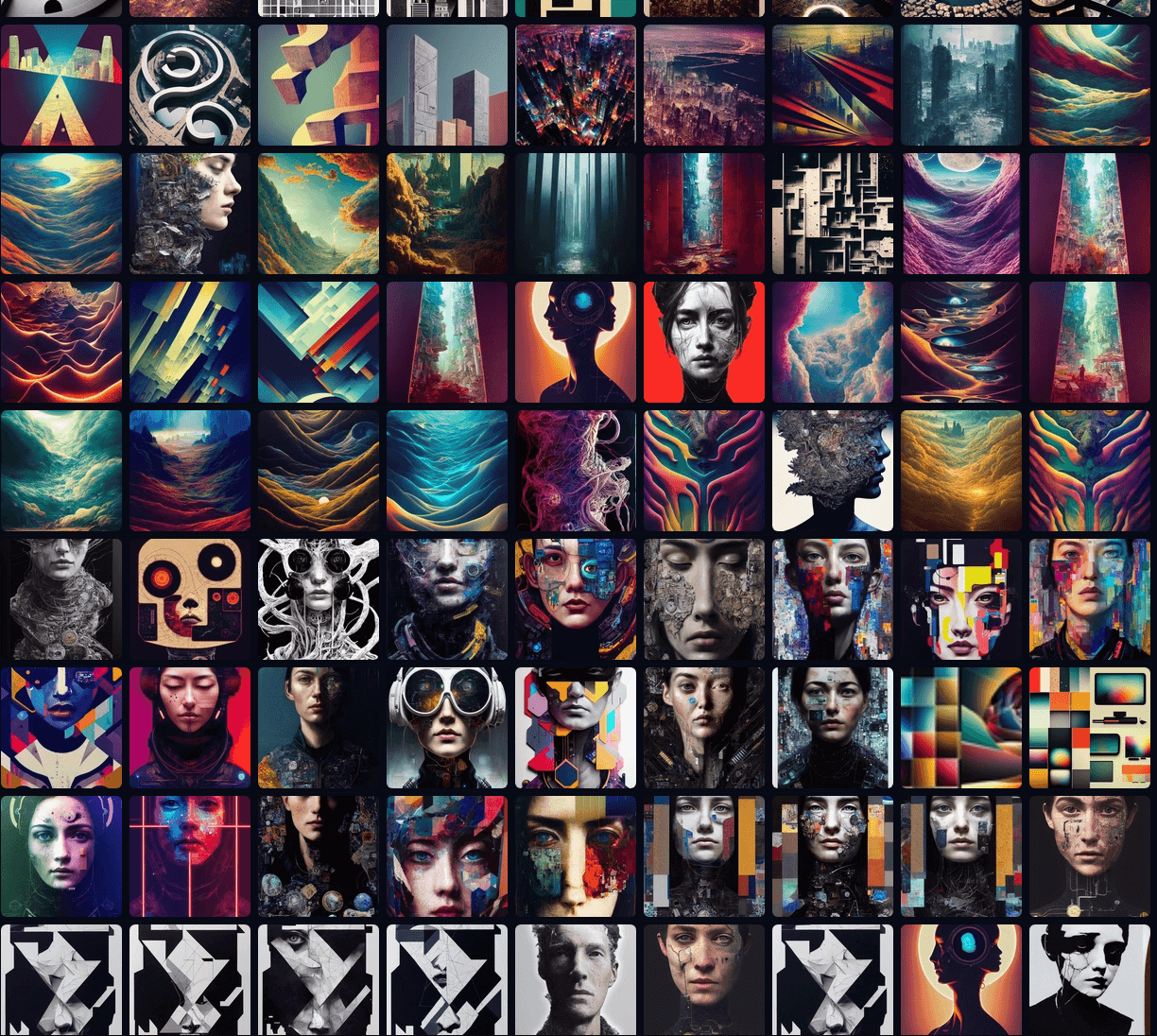
Midjourneyの面白いところ


最初に生成した作品

Midjourneyでの様々なテスト


コミュニティの起ち上げ

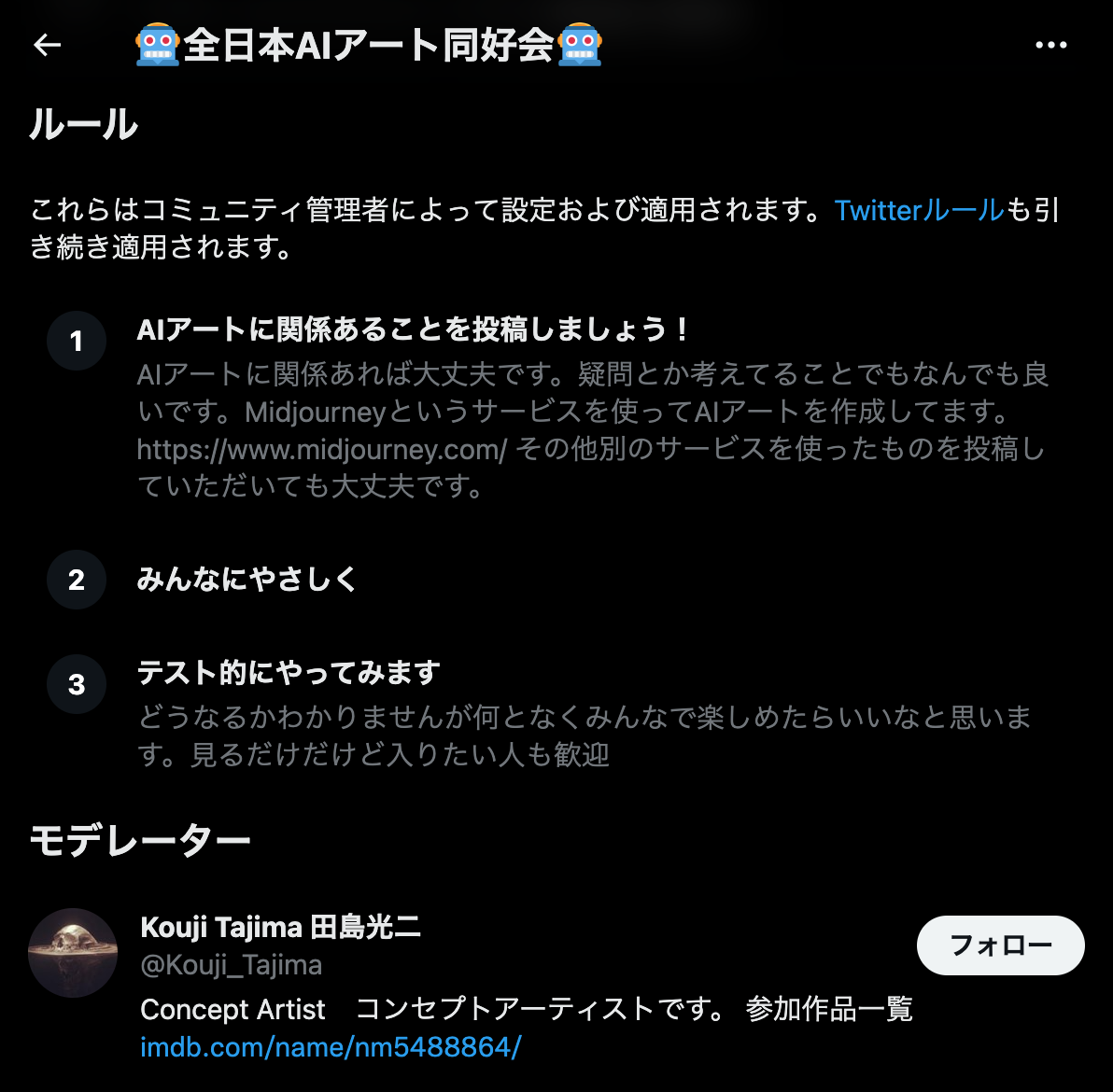
参考にしているアーティスト
-
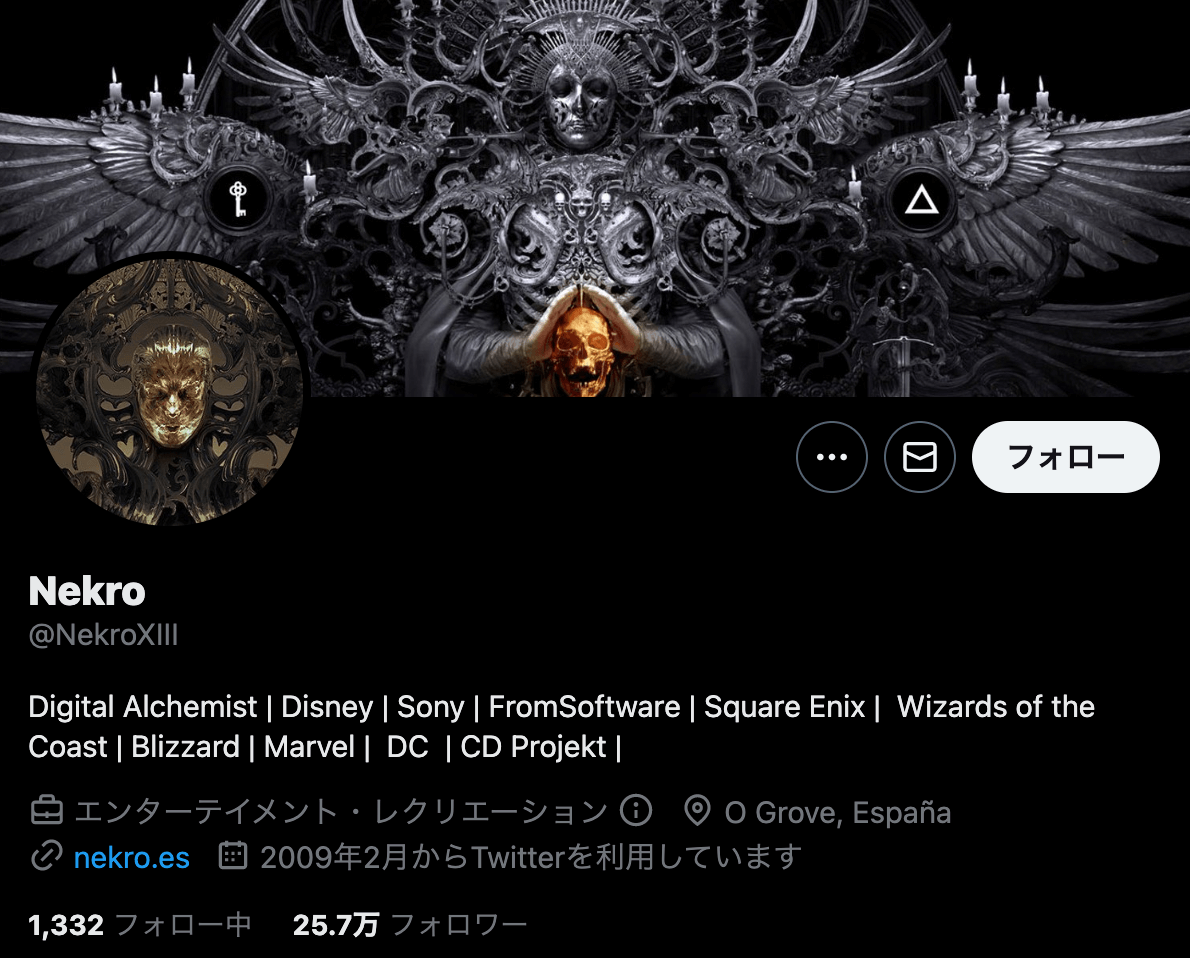
かねてよりコンセプトアーティストとして田島氏も作品を参考にしてきたNekro氏(@NekroXIII)は、もともとコーラジュアート的な手法を作品に組み込んで きた。「Midjourneyで生成した絵を切り貼りして新しいアートを構成していて、そういうやり方もあるのかと感嘆しました」(田島氏) -
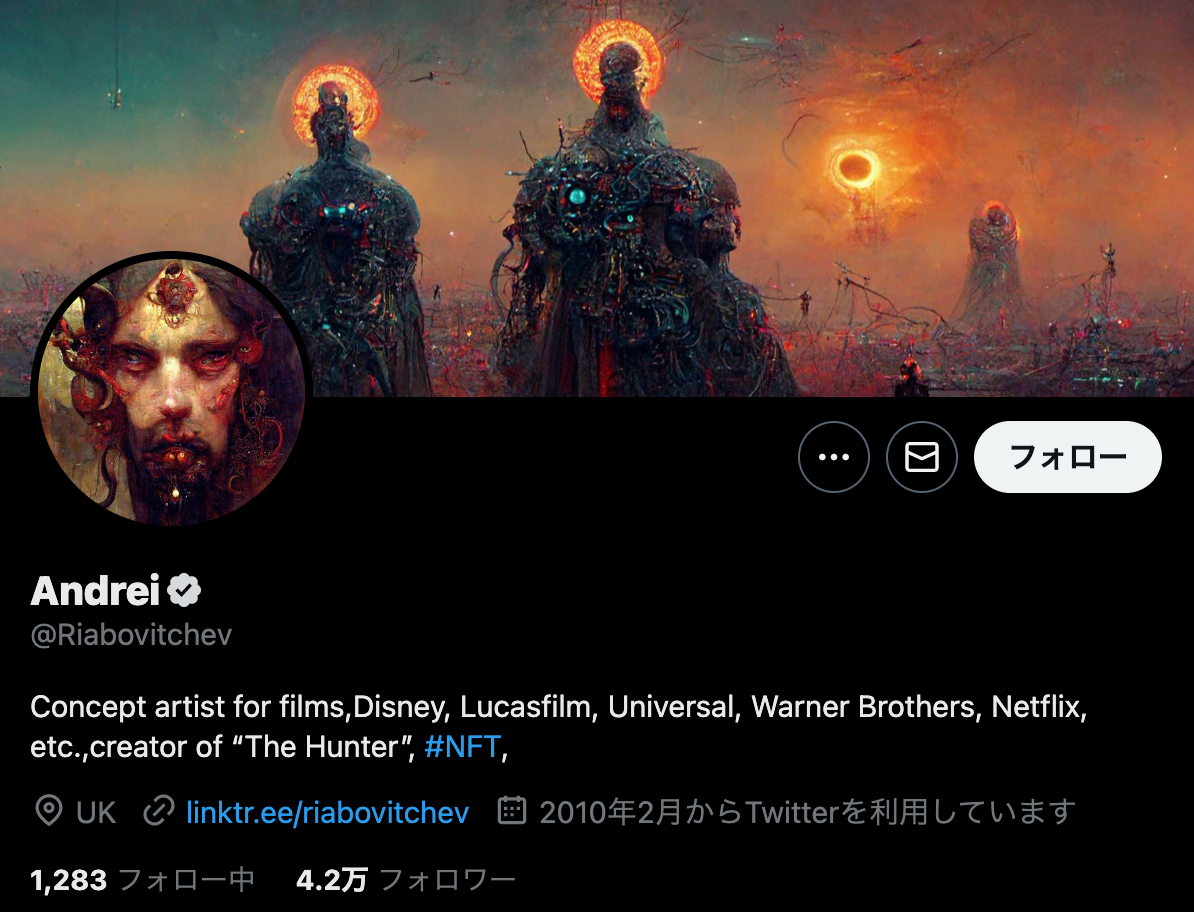
また、多種多様な素材を合成・加筆する手法で独自のアートを展開するAndrei氏(@Riabovitchev)は、ベータ版への参加時に生成結果を好評しつつ、これまでのモデルも使用できるのが望ましいと指摘。「Midjourneyがおもしろいのは、更新によって1~2ヶ月前と今とで得られるスタイルや品質が向上する点で、それもAIアートの楽しさですね」(田島氏)
<02>テーマ設定とラフ案
AIが生成した絵は自身の作品たり得るか
今回の表紙制作に取り組むにあたり、シンプルに「楽しそう」という所感と共に「AIアートを自分の作品とするかどうか」という疑問に向き合うことになったという田島氏。「そういう議論はアーティストの間でもすごく出ていて。表紙になるわけですから自分の作品として世に出ることになる。そのあたりをどう捉えようかというのがありました」(田島氏)。
着想としては、まず表紙としての面白み・インパクトに加えて「アーティスト、あるいは世界全体がAIについてどう思っているか」を出発点とし、希望的な捉え方と脅威とする捉え方の二面性に注目。「そのどちらも感じられるのが良いんじゃないかと考えました。人によってAIアートの受け止め方は様々で、肯定的な人もいれば拒絶反応を示す人もいます。尊敬しているアーティストは『このながれには逆らえない。受け入れるか死ぬかどちらかだ』と言っていました。気に入らないのだとしても、勉強してどういうものかを知るというのは大切だろうと思います」(田島氏)。
そこに「AIがつくった作品は自分の作品なのか」「自分がやる上でのオリジナリティは?」という問答も加え、最初のステップとした。そこからプロンプトを考えて生成、さらにバリエーション生成を重ね多種多様なイメージを模索。結果的に、ラフ段階での生成枚数は約800ほどになったという。「写実性を高める新機能が追加されていたのでそれを使ってみたりもしましたが、無難な結果になりがちだったり、過度に写真に寄りすぎて『これを自分の作品だと言えるか』と考えると、あまり納得できないなと」(田島氏)。同様に、より新しいバージョンのモデルでは高精細・高品質な結果を得やすくなる反面、AI生成らしい絵的な面白みを欠く傾向にあり、古いモデルを使った方が個人的には面白い結果が得られるとのこと。
そうしたラフ案生成の中でより実感を深めることとなったのは、コンセプトの大切さ。たとえ綺麗な画像が生成されたとしても表紙を飾るようなインパクトやメッセージ性は得られない。そこで画像を基に別の画像を生成するimage to imageを使って過去の自作をベースにしてみたところ、自分の世界に近づいてくる感覚が得られたという。編集部へは14点のラフが提出されたが、最終的に本制作へはこのimage to imageの案が選定された。
編集部からのお題
・画像生成 AI サービスを用いること
・AIを想起させつつも、いかにも AI が生成した絵柄ではないもの
・田島光二の作品として成立するもの
表紙ビジュアルについて編集部から田島氏に依頼した内容は、おおまかに上の3点。具体的なテーマ設定や絵柄そのものは田島氏の感性に委ねつつMidjourneyでバリエーションを作成してもらい、出力された絵の中から田島氏がチョイスしたものを比較検討した上でベースとなる案を決めていった
「人とテクノロジーの融合」
AIによる人類の進化に思いを馳せたもの


PROMPT
portrait of someone from future made of patchesofdifferentmediums, analogand digital,hyperdetailed,cinematic lighting, intricate detail, 8k, high resolu-tion,surrealism, cyberpunk, contempo-rary art,
「強大な何か」


PROMPT
gigantic monstrous massive machinery, fear, cyberpunk
「操れるかは自分次第」
AIを使いこなせるかどうかはユーザー次第というコンセプトで、プロンプトは「強大な何か」からある程度引き継ぎつつ、特徴的な「コクピットの少女」が追加されている


PROMPT
inside of the gigantic monstrous massive machinery, reveal a girl inthecockpit,massive,dark,cyberpunk, photorealistic, cine-matic
「まったく新しいキャンバス」

PROMPT
What will happen to the digital art world with AI art?, autodesk maya, 3dsmax, zbrush, modo,blender 3d, octane render, 3d coat, houdini, nuke
「自分も予想できない新作」
田島氏自身の過去作からimage to image 機能によって新作を生み出すという試み


PROMPT
crazy art by Kouji Tajima,
「未知」

PROMPT
mysterious world ahead of us, feel offear, feel of hope, amazing details ,hyper details, photorealistic, 32K,
<03>出力画像に対するアプローチ
生成されたディテールに自らの意図を加える
ラフ案からの本制作では、まずラフ案をベースにさらなるバリエーション出しが行われた。バリエーションのそれぞれから合成するかたちで作品を完成させるという方針である程度まで作業が進められたが、結果的には方針転換を促されることとなった。「最初はAIアートの組み合わせと加筆だけで仕上げようと考えていたんですが、それでは腑に落ちないし楽しみきれない部分があり、ZBrushで造形を始めました。やはり自分でつくる作業をしないと自分の作品らしさが出ないなとも思いましたし、AIが生成したもののみでは、仮にインパクトのある作品ができても『なぜここがこうなっているのか』といった説明ができません。それではやはり自分の作品とは言えないなという思いがありました」(田島氏)。
描かれたディテール全てに意図を込め、どういうメッセージを伝えたいか、それを表現できるものでなければ『自分の作品』とは言えない。バリエーションを切り貼りする工程の中で、そうした思いが改めて確認できたという。「例えば『目』が特徴的な作品になりましたが、AIを使えば良いものができてしまう中では最終的にはユーザーの審美眼が問われますし、またその判断は合っているのかとAIから見られているような気持ちになります。顔の周囲のもやもやについては無限に湧き立つアイデアを表したい、といったことを考えながら3Dモデルを調整し、素材を重ねていきました」(田島氏)。
今回はAIアートを資料とした3DCG制作を経て、さらに両者を混合するかたちで作品を仕上げた田島氏。どのあたりがCGでどのあたりが生成によるものか、ディテールに込めた意味に思いを馳せながら鑑賞していただくのも面白いだろう。ただ、実は画像生成AIの現状に若干の飽きを感じ始めてもいるという。「今後は、求めるイメージがますます簡単に得られ、チューニングしやすさなど使い勝手も向上していくと思います。一方で『テキストを打ってカッコ良い絵が出て』というのは最初はすごく楽しかったんですが、やはり自分で手を動かしている方が好きなので、その領分が減ってしまうのは面白くありません。AIだけで『自分の作品』と言える作品をつくれるかというと、自分はそういうことはせず、自分の作品を自分の手でつくるということを今のところは続けていくと思います」(田島氏)。
Step1 バリエーション出し


Step2 ベースとなる出力画像

Step3 3Dモデル作成


Step4 蔦状のディテールを追加

Step5 明暗のコントラストを強調

Step6 気に入った目のディテールを追加

Step7 全体の色調調整

Step8 完成


月刊CGWORLD + digital video vol.293(2023年1月号)
特集:アーティストのためのAI活用
定価:1,540円(税込)
判型:A4ワイド
総ページ数:128
発売日:2022年12月9日
TEXT_岸本ひろゆき
EDIT_藤井紀明 / Noriaki Fujii(CGWORLD)、山田桃子 / Momoko Yamada





























