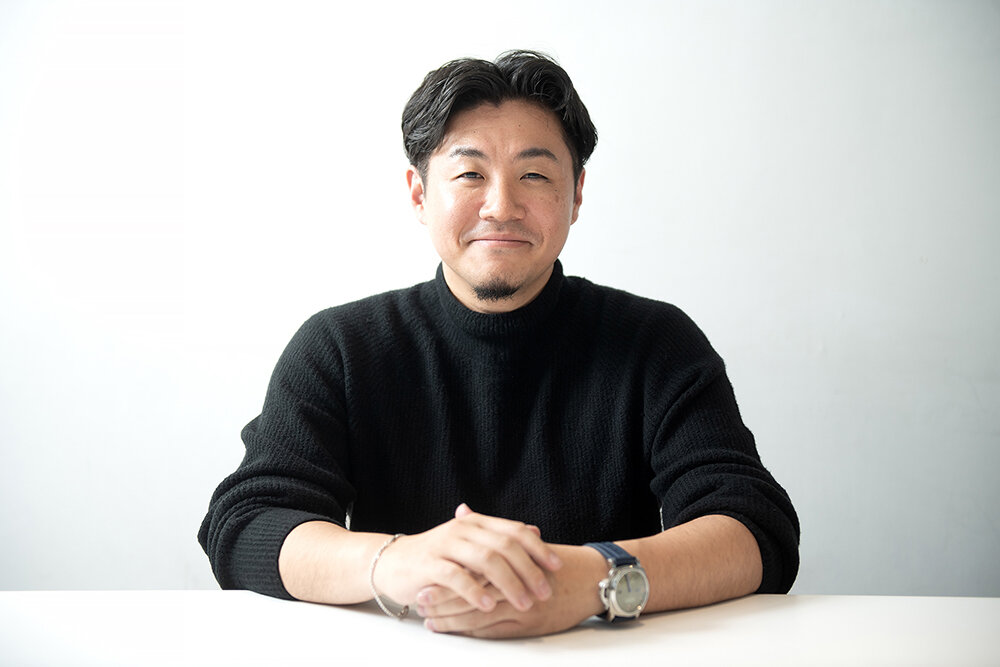日本でも話題を巻き起こしアカデミー賞にて監督賞を受賞した映画『パワー・オブ・ザ・ドッグ』や『幽遊白書』など、多岐に渡る映像においてVFXを手掛け、世界に6つの拠点を持つスタジオ・Alt VFX。その東京オフィスを担うVFXプロデューサーが齋藤剛史氏だ。
今年で40歳を迎えるという齋藤氏が、同社に入社したのはなんと37歳の頃。新卒から10年以上CGやVFXには無縁だったところから入社したものの、この3年で手掛ける作品は大手クライアントのCM作品やNetflixドラマなど一流の大型タイトルばかり。
そんなVFXの世界では異色ともいえる経歴を持つ齋藤氏に、VFXプロデューサーの仕事とは何か話を聞いた。
Alt VFX

Alt VFX
「近所のお兄ちゃん」に誘われ未経験からVFXプロデューサーへ
――今回は「非常に専門性の高い仕事として知られるVFX業界に、他業界から転職し、プロデューサーを務めている方がいる」という話を耳にし、取材に伺いました。まずはそのあたりから、これまでのキャリアや軽い自己紹介をお願いできますか?
齋藤:まずは自己紹介から、Alt VFXという会社でプロデューサーをやってます、齋藤といいます。Alt VFXはオーストラリアに4つ、アメリカに1つ、東京に1つ拠点を持つVFXスタジオでして、その東京の拠点を任せてもらっているのが僕ということになります。
僕のキャリアについては、先ほど「不動産からVFXに」と言って頂きましたが、実はもっと複雑でして。不動産業界にいたこともあるんですが、恥ずかしながらそれ以外にも3、4回ほど転職をしてまして、良い言い方をすれば僕は新卒から、多くの業界経験を経て今の会社にいるんですね。
――詳しくお聞きしてもいいですか?
齋藤:僕は今年で40歳なんですけど、Alt VFXに入ったのが37歳の頃。新卒からおおよそ15年はVFXとは無関係の仕事でした。まず新卒で入ったのが住宅メーカー。次に入ったのが、スマートフォンをはじめとした携帯電話の法人営業。その次は、HR業界。そして次、web系のいわゆるIT業界。ここまで計15年で、それからAlt VFXです。
周りには転職するたびに色々言われましたが、僕個人としては全部同じ営業職という印象でしたので、なんでみんな心配そうに見てくるんだろうと思ってました。toCからtoB、法人携帯や人材、Webサービス、扱う商材が有形から無形に変化しただけで、実のところ営業という点ではある意味一貫していると思っています。
――それぞれの仕事間での転職動機は何だったんですか?
齋藤:どうせ営業やるなら流行っているものや興味のある世界を覗きに行った方が面白そうという社会人としてかなりゆるい思考があった部分が大きいかな、と思います(笑)。
有形商材から無形商材へ、という流れ自体も興味からですし、僕の世代にしか伝わらないと思いますが、スマートフォンを当たり前のように使う時代ではないところからの大きな変化があり、人材紹介もキャンディデートの皆さんが培ってきたキャリアを商品化して営業する、全部そうですね。もちろん「その仕事の本質的な価値、お客様に喜んでもらう」とかもちゃんと考えてはいますが、基本は「自分の知らない世界に入ってみよう」みたいな動機が多かったように思えます。

――とはいえ、それまではVFXとは無縁な会社務めですし、偶然「VFX業界がいま来てる!」と耳にすることもありませんよね? web系のIT企業からAlt VFXへの転職に至ったきっかけは何だったのでしょうか?
齋藤:御社を前にしてかなり言いにくいですが、全然耳にしませんでしたね(笑)。Alt入社への経緯としては、以前の会社で人材サービス事業を立ち上げることになり、その責任者となったんです。そこで、いわゆるクリエイティブ系専門職に特化した人材サービスを企画したわけですが、その中にはCG系の人材もカバーすべきという判断をしまして。しかし、そうは言ったものの、それまで全くと言っていいほど馴染みのない業界で、CGのことをまったく知らないわけです。そもそもどんな仕事で、どういう役割があって、この業界で働く人が何を課題視してるのか学ばないといけない。その際にCG/VFX業界のことを訊いた相手が、弊社社長の高田でして。
――え? その頃の高田社長はオーストラリアにいらっしゃったと思うんですが、いきなり日本の東京から「CG業界のことを教えて」と尋ねていったということですか?
齋藤:いえいえ、僕と高田は旧知の仲なんです。僕は5歳くらいの頃にオーストラリアに住んでいたんですが、その頃の「近所のお兄ちゃん」が高田でして。僕は10歳で日本に戻り、高田はオーストラリアに残り、そこから僕が大学生になるくらいまでは付き合いが続いていて。そこから10年くらいポツポツとしか連絡をとってなかったんですけど、「あ、そういえばCGの会社で仕事してるって言ってたな」と思い出して。
――全5部作のペプシのCMまでやっていたのに。
齋藤:そうですよね。今思うとゾッとします(笑)。連絡をする前に一応調べるんですよね。何をしているかわからないといけないから。そこでAltに行き着いて、え、あれもこれも高田の仕事なのか!って思いました。近所のお兄ちゃんに軽く相談というつもりだったのですが、すごい人と連絡することになってしまったと。かなり親切に、そして親身に話を聞いてくださり、無事サービスもローンチを迎えました。そのあと少し時間は経って、一緒に仕事しない?と言われたのがきっかけですね。
VFXプロデューサーまでの道は「もうとにかく訊くこと」
――ちなみに、プロデューサーとしての役割が務まるまで何をどう埋めていったんですか?
齋藤:英語は、幼少期のオーストラリア生活しかなかったので不安でしたが、日本に帰った後母親が英語を忘れないように僕を奮い立たせ続けてくれたおかげで、1年くらいでなんとか英語が戻ってきた感覚になりました。何よりも発音だけは維持できていたのでそれは本当に親に感謝です。
知識面については……もうとにかく訊くことでしたね。
これに関しては、Alt VFXがほぼ外国人の非日本文化な会社なのが良かった。日本よりも「わからないなら訊かないといけない」という考えが強いし、上下関係分け隔てなく誰に訊いてもいい。そこにありがたく乗っかって、とにかく訊く、めちゃくちゃ訊く。それのみです。今思えばよく何度も聞けたなという質問も数えきれないほどあります。
――VFXのプロデューサーというと世間的には耳慣れない肩書だと思うのですが、具体的にはどういったお仕事をされているのでしょう?
齋藤:ざっくりと言ってしまえば、営業とプロジェクト管理が主な業務内容ですね。
職を転々としつつもずっと営業職、管理職をやってきたという話をしましたが、VFXプロデューサーも営業職なのは変わらなくて。映画やCMをつくるという話や相談を受けては見積もりをして、プロジェクトを受注する営業の仕事。
それと、お金の管理や進行の管理をして、社内全体のスケジュールやどのタイミングで進捗を出すのかを決定していくこと。それをオーストラリアのスタッフに共有しながら進めていく。このあたりが僕の仕事です。
より個別にCGアーティストたちのスケジュール管理をして、どのタイミングでどのパートの何の作業をするかコントロールするラインプロデューサーというのもあるんですが、僕の主な仕事としてはプロジェクトの相談を受けて、お見積もりを作成し、プロジェクトを管理します。クライアントからの要望を僕がスーパーバイザーやラインプロデューサーに伝えて、それを現場に落とし込んでもらうように動いています。
――それまで扱っていた住宅や携帯電話と違って、VFXの営業、言い換えれば「画をつくることに値付けをして売り込む」ことは、実体がないぶん正解が掴みにくいように思うのですが、そこはどのように捉え、考えられたのでしょうか?
齋藤:たしかに、決まった金額があるわけではないので、その通りですね。ただ、作業1つずつに分解すると値付けをすること自体はそこまで難しい話ではないんですよ。VFXのコストになるのは大部分が人件費なので、1つ1つの作業、1人1人の担当者に分解していけば、トータルがいくらになるかは意外と計算しやすい。特にグローバルはスペシャリスト制というか、アーティストの役割がかなり明確なのでお見積もりはかなり正確に出ると思います。
その一方、クライアントの予算は決まっているので、その予算の中で何を作るのか、どのレベルに持っていくのかを合意形成をとりながら進めていく。あとはどれだけ適切に作業を進めるかというのがこの仕事、ものづくりの特徴でもあり醍醐味なのだと思います。
難しいことがあるとすれば、長編など長期のプロジェクトになるほど予測とのブレが生じてくることですね。CMの仕事であれば作業期間は1、2ケ月なので大きく作業量が変わることはないのですが、長編映画とかドラマシリーズなんかになると作業期間が半年〜年単位になるので小さな変更が結果的に大きなブレになってくるわけです。
金額的にも内容的にも、計画通りに最初から最後まで作業が遂行されるようにコントロールすることが楽しくもあり、難しくもあるところだったりします。
――そういった制作中の変更について、プロデューサーの立場からはどのように考えたり、バランスをとっているのでしょうか?
齋藤:ありがとうございます。まさにバランスがものすごく大事な仕事だと思っております。つくるものに関しても、リアルであれば良いかというとそうではなくて、かっこいい方が良かったり、美しい方が良かったりします。クライアントの感性によって「良い」が違ったりもして、ともすると、80%くらいリアルの方が良いことすらあったりします。なので、僕がやるのはその目線の違いをひたすらにすり合わせバランスコントロールをすること、ですかね。
僕たちはものづくりが大好きですが、一方ビジネスなので、そのことも決して忘れてはいけないと思います。これもバランスですね。それゆえにしんどいプロジェクトもありますが、納期のない作業はないという格言をいただいているので、とにかく時間いっぱいプロデューサーは奔走して細かなズレを修正し続ける。
当たり前が通じない人たちとルールを共有する大変さ
――業界と言語とふたつの違いを抱えてVFX業界に来られたわけですが、そこに起因する失敗エピソードなんかをお聞きすることってできますか?
齋藤:最初は失敗しかなかったですね。先ほどお話した通り、僕のキャリアってVFXにどっぷり浸かって来たわけではないので、技術的な知識がほとんどないところからスタートしてます。それでもなんとかプロジェクトの管理はできるわけです。ただ、何をどのタイミングだと修正ができて、どのタイミングだとできない、今その修正をやるとこれまでにやってきたことが全て無駄になる、ということが多く発生します。
そんなことはつゆ知らず、当初は受け取ったフィードバックをそのままアーティストに伝えるだけの無能でしたので、当然社内からは集中砲火。例えば、ショットワークに入っているのに、アニメーション修正に戻るとか、モデル修正に戻るとか。「これは無理でしょ」と最初は何度言われたか。……今思い出すと、この歳でその経験ができるのもある種新鮮でした。ただ、僕もわからないことを理由に負けじと、「やんないとダメなんだー!」と言ってました(笑)。
言語の方だと、言葉そのものは時間と共に良くなっていくのですが、それより気にかけなくてはいけないのが、国による感覚や感性の差があることです。
――国による感覚や感性の差とはなんでしょう?
齋藤:例えば、害虫を除去する商品のCMをつくろうってなったら、日本人の僕らの感覚では「食事の時間帯に流れるCMだから見ててもご飯が食べれるくらいのイメージでCGをつくろう」と考えるわけなんですが、海外のアーティストはとにかくリアルに、フォトリアルにつくろうとしたりするんですよ。なので、前提の文化観がまず違うこと。そこを理解してひとつずつ共有することから始まる大変さはあると思います。
あとは日本語の「間(ま)」と “moment” は違うし、速い遅いの感覚も違う。だから「もう少し間が欲しい」は「あと1.5秒空けて」と定量的に言い換える必要があったりする。
Altは日本の仕事も多く制作してきているので、理解してくれようとする度量があるのは本当に助かっておりますし、それがゆえにオリジナルな世界観がつくれているのかとも良い面としてはあると思います。
――となると、仕事の進め方やワークフローも日本の企業と異なったりするのでしょうか?
齋藤:根本的な違いはほとんどないと思います。ただ、見積もりをしっかりつくるというのは違うところかもしれません。先に話した、プロデューサーとして値付けの話にも繋がるんですけど、見積の段階で全部かっちりと作業工程や担当人員、動き方や日数まで弾いて、金額の理由を明快にする。ここからここまでどのレベルのNukeアーティストが何日かけて、とか全部決めます。
日本の企業だといろんな技術を持ったゼネラリストの方が多いのでなかなか線引きが難しいと思うのですが、僕らの場合は基本的にソフトウェアや専門性ごとのスペシャリストで構成されてますし、ゼネラリストにしても1人で2パートを担うことは前提にしない。この工程はこの人というのがハッキリしている。だから、工程数や日数が厳密に出ます。
もちろん、VFX予算も無尽蔵ではないので、そこに収まるように提案や調整をして見積もりを組んでいく必要があるんですが、長編映画のVFXだと見積もりがまとまって落ち着くまで1ヶ月くらいかかることもありますね。なので、ある人のがんばりで予算に収まるようになんとかする、とかはないです。
――修正や変更が生じたらどうされるんですか?
齋藤:修正分や変更分を見積もって、作業人員と作業量を提示して追加予算のお願いをしますね。
グローバルルールというと聞こえはいいですが、入れ替わりの激しい僕らの業界はとにかくアーティストを第一に考えています。なので、しっかりと対価を求めずに作業をしてしまうと彼らの価値を大事にできていないということになるので、許されない。直します、修正します、追加やります、それはいくらでもやりますけど、その分のご予算は用意しておいてくださいね、というルールというのがあります。
ただ、制作期間が1~2ヶ月しかないCMなんかだと、修正や変更が起こるたびに極めてハードな調整が発生しうるので、なるべくそうしたことが起きないように事前調整とすり合わせをする部分がプロデューサーの実力の試され所ですね。
VFX業界でも「気持ち」が大事
――その後も現状も長編を含め様々な作品を手掛けられるわけですが、これは先ほどお話いただいたような学びを生かしてプレゼン、受注されたわけですか。
齋藤:そこは結構昭和なやり方で、仲良くなる、熱意を伝える。なので、僕のやり方は今のプロデューサーとして何の参考にもならないと言われて。
――もっとシステマチックというか、スマートな運びなのかと思っていました。
齋藤:できればスマートにしたいですが、この業界は人のつながりが全ての部分もあって、結局つくっているのが人なので、人同士の練磨や摩擦の先にクリエイティブが左右される世界なんだと思いますし、そこが辛かったり、それによってブレイクスルーしたりもします。でも、人がとにかく中心にいる世界なんだと思います。
以前はweb系のIT企業にいたのもあり、世界の流れで大きくデジタル化が進むと思っていたから「意思伝達はすべてメールとslackで完結、飲んだりもせず、必要最低限の意思伝達だけで回るシステマチックでスマートなやり方」が正しいと思っていました。初めて入った時もこんなにも熱で伝わる部分があるんだ、と思いました。
僕は元々住宅メーカーの出身で、スマートさよりも泥臭さに育てられた部分が大きいから、業界は違うのに精神的には帰ってきたような心地があるんですよね。「おっ、コレコレ!コレだよ~!」みたいな。まあ、全然スマートじゃないんだけど。
――そうした泥臭さがいまだに求められてる部分があるのでしょうか?
齋藤:さっきも言った通り、やっぱり人と人とが練磨していく世界なので、泥臭いというと悪い言葉に聞こえるけど、良いものをつくりたい、その目標に向かって最短で進む道は常に荊なんですよね。うまくいかないプロジェクトってどうしても生じる。いろんな理由でどうしようもなくなって、収拾がつかなくなっちゃうことってあって。でもその中でもがきながらも全員で荊を潜り抜けるには、最後はやっぱり人と人の関わり合い、ハートの問題になるんですよね。だからこそ、そういう熱さ泥臭さみたいなものは必要になるときがあるし、伝わるし伝わってくる。

――ちなみに、そういった収拾がつかない事態の際、齋藤さんはどうされているんですか?
齋藤:僕の精神世界ではひたすら土下座してます。でも、関わっている人が多くなってくると一概に特定の何が悪いというのはないから、誰が悪いというわけでもない。結果としてこうなったと思うようにしつつも、だからと言って僕たちが悪くないとも言いたくない。でも、誰かはこの収集をつけなくてはいけない。そのロールを担う方には頭が上がらない。
初期の頃、本当に難しいプロジェクトから入って、やれるところまでやったのに、もう戻れないところでフィードバックが来ました。でも監督のフィードバックを聞いていたら、もしかしたらこういう解釈もできた可能性があって、やりきれなかった。でも時間もなくてオンラインもすぐそこで、その時のプロダクションの方に土下座でもなんでもするので、オンラインいかせてください!って言ったら、その方が「その言葉が聞けてよかった、あとは任せてください」と言われたことがあって。悔しすぎてしんどかったんですけど、最後の最後に全員で戦っているんだということに気づきました。やっぱり制作のレイヤーにいると、ある種自分たちだけがつくっている感覚に陥ることがあります。でも、違うんです。全員でつくっているんだと、その時強く心に刻みました。
――そうした気持ちの部分を大事にするのは社内でも同じですか?
齋藤:優秀なプロデューサーに最も大事なことって、社内のみんなの気持ちを上げ続けることなんじゃないかと思っていて。プロジェクトが開始後に僕が一番気を使うのも、アーティストのメンタルなんです。
だから僕はアーティストを超褒めます。もちろん嘘はないです。ただ、ものすごく言葉を選んで、シチュエーションも加味しながら、最もこの気持ちを正しく伝えるようにしてます。「最高にかっこいいじゃん、え、ホントにこれつくったの? え、マジ?」とか「ホントごめん、上げてもらったやつね、これ、ここだけの話なんだけど……めちゃくちゃ大好評だった」とかひたすら言ってる。
とにかく悪いフィードバックや難しいフィードバックが来ても、アーティストを否定しない。
「いや、スゲーいいのを上げてもらいました、ありがとうございます、感謝。最高っす。その上で、もしできるんであれば、ここ、もう少しだけ “上” 狙えたりしない?狙うかどうかは俺ら次第だし、ぶっちゃけやらなくても全然イケてると思うんだけど、どうする? ……行く? やってみるか……!?」みたいな。
みんなの中に人それぞれの美や好き嫌いがあって、綺麗にシンクロすることもあれば、驚くほど交わらないこともあって。でもアーティストがつくっているものを否定するなんて僕にはできないし、プロデューサーがいる限り、その違和感の原因は常に僕にあると考えています。
これがうまいのが高田で、彼はアーティストが気落ちする二手三手先にそれをやるんですよ。そうして先回り先回りで気持ちを上げて、後々に踏ん張りが利く下地をつくっておく。危機察知能力が高く、やる気を引き出す力が高いんだと思います。僕は高田から全ての責任を背負う覚悟でプロデューサーをやるということをまだまだできていないですが、教えてもらったと思っております。
――とにかく鼓舞する?
齋藤:そうですね、あと、その言葉が響くように普段からまめに接しておく。やっぱり、褒めたところで「なんか言ってんな」と思われたり、発言をちゃんと受け取ってもらえない可能性もあるわけじゃないですか。そうならないように、コンタクトもコミュニケーションの量も意識的に確保してます。
良くも悪くもCGって、最後はどれだけ根を詰められるかの勝負が待っていて、どうしてもそこには気持ちが必要なんですよね。日本人はそういう褒めがなくても仕事は最後までやる気質なところがありますけど、外国人を相手にしているとその部分は大きいなと感じます。
英語、文化をハードルと捉えるかはあなた次第
――異業種からVFXの世界に来て経験された苦労の話をいろいろとお聞きしましたが、逆に、異業種ゆえに得や強みを感じたことはあったりしますか?
齋藤:基本的に大変なことの方が多いんですけど、今になって振り返るとよかったなと思うことはいくつかあって。
ひとつは、先に言った話にも重なるけれど、クライアントの気持ちがよくわかること。
僕はクライアント側にいた期間が長いので、求められてることが自分事でわかるんですよね。「多分こういうことを言いたいんだろうな」とか「これが言いづらいんだろうな」といったことがわかるから、業界にどっぷり浸かって来た方よりも鳥瞰的、俯瞰的に見やすいと思う。
ふたつ目は、こだわりがないこと。言い換えればなんでも好きになることができるんですよね。VFXが大好きでこの業界に特段の贔屓目があるわけでもない分、Altのケイパビリティーによく馴染めたという気がしています。例えば、AltにはVFXをつくるチーム以外にも、AI/VR/ARなどの最新デジタルテックを担うT&DAやデザイン、コンセプトを得意とするNew Holland Creativeや最近はSteel bridge studioというVPスタジオを自前でつくったり、Altのニーズ解決能力は多岐に渡っています。CM、ドラマも、インタラクティブインスタレーション、オフラインイベントの作品、データビジュアライズ、AI作品、とにかくなんでもチャレンジさせてもらえているのも、こだわりがないというところが大きいかもしれないです。
もちろん、すでにVFX業界での成功を志しているなら、下手に他業界に行ったりせず、最初からVFX業界に入る方がいいとは思います。
――CGWORLDをご覧になっている方には業界志望者の方も多いと思うのですが、異業種出身の齋藤さんから見たグローバル市場のVFX業界の魅力ってなんでしょう?
齋藤:そもそもこの業界の魅力は「自分のつくったものが未来まで残る」こと。これ以外ないのかもしれない。やっぱりこの業界ってものすごく爪痕が残りやすい業界だから、良い意味も悪い意味もありますが、それが魅力なんだと思います。さらにグローバルで考えれば、それはもうステータスでありアーティストの価値を表すものなので如実です。みんなIMDBに刻まれるその人が残してきた爪痕を見て、アーティストの価値を計ります。すごいわかりやすい指標で、ドライで、その爪痕を残すために切磋琢磨しています。なのでその対価もそれ相応なのではないかと思います。日本では考えられないくらい稼いでるアーティストもざらです。
――儲かる、というと、どれくらい……?
齋藤:全てを知っているわけではないですが、青天井です。例えばウチは入ってすぐのジュニアクラスのクリエイターでも30代前半の平均年収くらいはある。
技術があって、勤勉で、英語を喋れれば1000万、2000万という金額も全く夢ではない、それが僕たちがいるこの業界のアーティストの実情です。羨ましいですよね。
基礎的な英語力があれば、あとは業界共通の語彙で会話はできますし、全世界的に人が足りてないので、とにかく飛び込んで稼ぎ散らかす日本人がもっと増えてほしい。NUKEは世界で仕事ができるゴールデンパスポートと高田が言っていたのですが、本当にそうで、世界各国からAltの門を叩くアーティストがいるんです。なので日本人でも英語を学んで、デモリールを海外の会社に送りつけて1年の契約社員を経験して、実績をつける。
高田ともよく、良いアーティストを見つけては「この人が英語さえ勉強してくれたらなぁ」なんて話すことがあるんですが、逆を言えば、もう、それだけで良いんです。英語、Nuke、それさえやってくれればグローバルに飛び込める。
意気込みと有限実行の前向きさがあれば僕らも伸びる場を提供したいと思っているので、恐れずに来てほしいと思います。
――本日はありがとうございました。
TEXT_稲庭淳
PHOTO_弘田 充
EDIT_池田大樹(CGWORLD)