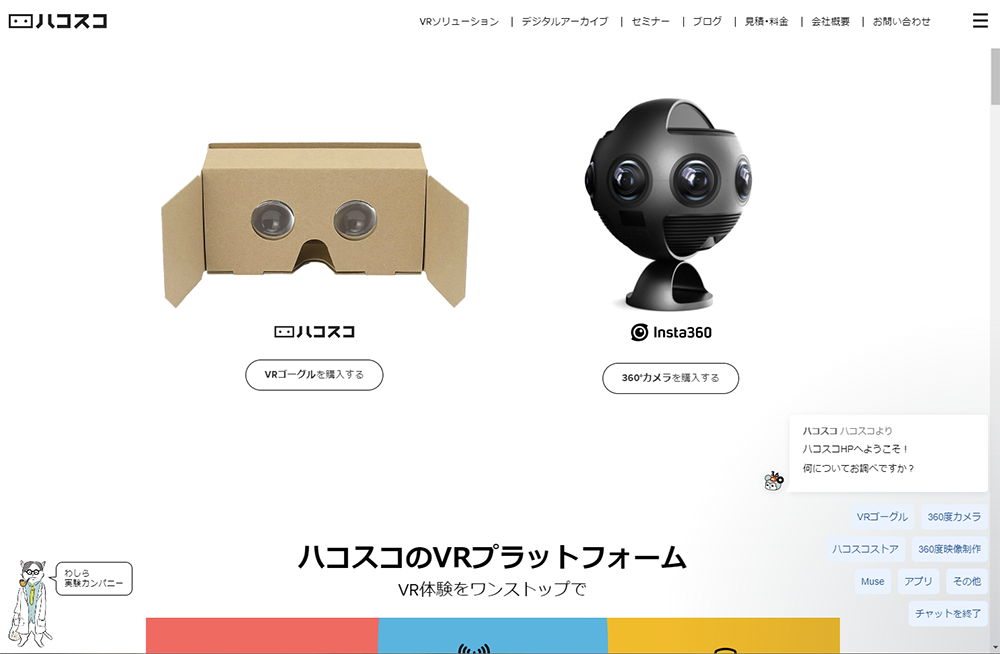感染対策に留意しつつ、1年ぶりに4月14日(水)から16日(金)まで東京ビッグサイトで開催された「コンテンツ東京 2021」(主催:リード エグジビジョン ジャパン)。会場では、ブース展示に加えて18本のセミナーが行われた。本稿では「最新テクノロジーが実現する新たなコミュニケーションとは?」と「XRがもたらす可能性とは?」をレポートする。
TEXT&PHOTO_小野憲史 / Kenji Ono
EDIT_三村ゆにこ / Uniko Mimura(@UNIKO_LITTLE)

テクノロジーがコミュニケーションを変える!
パネルディスカッション「最新テクノロジーが実現する新たなコミュニケーションとは?」では、クリエイター集団1→10 (以下、ワントゥーテン)の澤邊芳明氏と、アバターロボットnewmeで知られるavatarinの深掘 昴氏、そしてブロックチェーン事業などを営むgumi國光宏尚氏が登壇し、テクノロジーとコミュニケーションの関係について議論を交わした。
もっとも、昨今のNFT(非代替性トークン)アートの盛り上がりを受けて、國光氏がNFTの現状と可能性について解説を行うなど、ディスカッションはアドリブ感満載で展開。「コンテンツ東京 2021」を取り巻く現状が反映された内容となった。
パネルディスカッションは3社の紹介からスタートした。ワントゥーテンは、XRやAIなどの先端技術にエンターテインメントやストーリーをかけ合わせることで、新しい体験を創造・実現してきたクリエイター集団だ。その代表を務める澤邊芳明氏は、バイク事故による頸髄損傷のため手足が一切動かない、車椅子の経営者として知られている。
澤邊氏はまず、2月10日(水)に配信されたNPO法人「Earth & Human」by 1→10 設立記念講演の内容を紹介した。本法人は歌舞伎俳優の市川海老蔵氏が代表理事を務め、環境保護に取り組むことをミッションに掲げている。映像ではワントゥーテンの映像技術を駆使して、市川海老蔵の祈りの舞踊に呼応して木々が美しく生い茂ってゆくさまをCGで演出。川崎市にあるスタジオ、キヤノンが昨秋開設したVolumetric Video Studio - Kawasakiからリアルタイム配信されたものだ。
澤邊氏は「コロナ禍において、能や歌舞伎をはじめとした舞台芸術が大きな制約を受ける中、技術を用いてどのように内容をアップデートしていけるかに挑戦した」と解説。あえてリアルタイムCGを使用したのも、演劇の一回性を重視したためだという。もっとも、リハーサルはトラブル続きで、場の雰囲気が重苦しいものに。本番では奇跡的に上手くいったと舞台裏を明かした。なお、VRバージョンも別途作成しており、今後配信予定だという。
これに対して、アバターロボットを介したコミュニケーションという、フィジカルな要素を重視しているのがavatarinだ。航空会社大手ANAホールディングスのアバター準備室を経て、2020年4月に事業会社として設立した同社。アバターロボットを「全ての人の新しい能力」にすることで、人類のあらゆる可能性を広げていくことをミッションに掲げている。
「コロナ禍で弊社のオフィスはガラガラだが、変わりにアバターロボットのnewmeが走り回っている」と語る深掘氏。ミュージアム、ショッピング、教育、ビジネス、カンファレンスなど様々な場で実証実験を実施中だ。同社のアバターは、今や地上のみならず国際宇宙ステーション(ISS)でも活躍中。2020年11月には、ISS内のspace avator を一般人が地上から操作する技術実証を実施し、注目を集めた。
「意識だけを電送し、好きな体(ロボット)を選んで活動をすれば、人間は光の速度で移動できる。こうした社会参加のあり方は、Withコロナ時代でますます重要になる」と話す深掘氏。2021年2月には内閣府が主催する「ムーンショット型研究開発制度」に参加し、「アバターを活用するための次世代のクラウドサービスの研究開発」と「人のスキルを学習して能力を拡張する研究開発」を進めていると語った。
両社に対して、よりエンターテインメントの領域に近い分野で活動しているのがgumiだ。モバイルオンラインゲーム事業を皮切りに、XR事業、ブロックチェーン事業、そしてファンドの運用と様々な事業を進めている。代表の國光氏は「2020年11月にFacebookがOculus Quest 2を発売したことで、VR市場が急速に拡大した」とコメント。今後もPSVR2の発売などが控えており、さらに市場が広がるとした。
続いてグループ会社のThirdverseが開発・運営するVRマルチプレイ剣戟アクションゲーム『ソード・オブ・ガルガンチュア』を紹介。國光氏は本作で培ったVRゲームのノウハウと、同社のブロックチェーン技術を活かしてアニメ『ソードアート・オンライン』の世界を5年以内に実現したいという。VRでフルダイブでき、独自の経済圏をもつMMORPGを創り出すというわけだ。
もっとも、同社はその先の未来も見据えている。あるVR世界をベースに、参加者が自由にハードフォーク(システムの永久的な分裂)できるようにすることだ。これにより、仮想世界でも民主的な政権交代が可能になるとした。ある世界に不満をもつ人がいたら、別の世界をハードフォークすれば良いからだ。新たな世界の賛同者が多ければ、自然に移住者が増えて栄えていく。これを10年以内に実現したいという。
MR、ロボット、ゲーム......、三者三様の関わり方
続いて、議論は互いの製品やサービスに関する質疑応答に移った。その1つが、avatarinのアバターロボットとワントゥーテンのXR技術の融合だ。深掘氏はアバターロボットには「足」が必要で、「水族館で実証実験を行なったとき、動き回ることでマナティが反応した」とコメント。同じように制止したままでは子供がなつかなかった。こうした実験から、アバターロボットには動き回れる点が重要だという。
これに対して澤邊氏は、XRグラスを装着したまま戸外で活動する世界が一般化すれば、アバターロボットとXR技術を組み合わせることで、さらに面白いことが可能になると回答した。國光氏はVR HMDの基礎技術にスマートフォンと共通する部分が多く、スマートフォンのスケールメリットを上手く引き継ぐことができていると分析。米軍がHoloLens 2を10万台導入したニュースなどにも触れつつ、常にXRデバイスを装着し、画面越しに世界を見る時代が到来する日も近いとした。
▲ワントゥーテン 澤邊芳明氏
▲avatarin 深掘 昴氏
とはいえ課題も残されている。「バーチャルとリアル」のバランスの取り方だ。深堀氏は「画面越しでは声をかけにくくても、オフィスでブラブラしていると話しかけやすかったりする。何か共同作業を始めるときは、実際にその場にいなくても存在が感じられるようにするのが良い」とコメント。澤邊氏も「コロナ禍で人と会えなくなり、雑談の重要性に気付いた営業マンが多かった」という事例を紹介。「構えないコミュニケーション」を、どのようにデジタルで実現するかが重要だとした。
また、澤邊氏はオンライン会議が増えたことで、地方や郊外に移住するエグゼクティブが増加していると指摘し、自身も校外に土地を買ったと明かした。ここから「バーチャルでビジネスは効率化されたが、Zoomでの飲み会はつまらない。ここはまだバーチャルで補えないところ。Zoomだと映像が遅延するため、相づちがしにくかったり会話が被ったりもする。ノンバーバルなコミュニケーションの重要性を再確認した」(國光氏)。「アバターロボットでも所作や間合いの重要性について指摘を受けている。どのように実装するか研究中だ」(深掘氏)と議論が盛りあがった。
続いて話題はコロナ禍での働き方に移った。澤邊氏はPCやツールの価格低下で、フリーランスや副業でデジタルアートを制作するクリエイターが増加したと説明。コロナ禍で自分の働き方を見つめ直す人が増えたのも、こうした傾向を後押ししているという。また、NFTのようにアーティストが収益を得られるしくみが整ってきたことも大きいのではないかとした。
▲gumi 國光宏尚氏
これを受けて國光氏は、NFTの現状やしくみについて解説した。NFTはブロックチェーンを用いたコンテンツフォーマットの1つで、この技術を使うことで「デジタルデータで限定商品をつくることが可能になった」、「限定商品にWeb上で誰でもアクセスできるようになった」、「限定商品が転売されるごとに、クリエイターが手数料を得ることが可能になった」と指摘。ピカソの絵と複製画のちがいを例に出しつつ、デジタルデータ自体はコピー可能だが、オリジナルであることが担保できるのがNFTの特徴だとした。
「もっとも、これまで人々はリアルの限定商品には価値を感じてきました。これが純粋なデジタルデータでも、限定品であることに価値を感じられるか否かについてはまだ答えが出ていません。今後議論が必要なところだと思います」(國光氏)。他にもNFT上の経済活動が活性化すると、基軸通貨の問題が出てくる。Facebookが仮想通貨「Libra(リブラ)」を発行したがっているのも、これをねらってのことだろうと話した。
こうした議論に対して深堀氏も、「海外在住の人がアバターロボットを使って日本で経済活動を行うと、税金をどのように払うのかなど新たな問題が出てくる。今、まさに議論を進めているところ」だと明かした。また、今後は人の動きを深層学習し「その人らしい所作」をロボットができるようになる。つまり、個人のモーションデータにNFTを紐付けて販売できる時代が来ると指摘。技術の進化によって、新たな商材が生まれる可能性を示唆した。
最後に登壇者から10年後の未来に向けての抱負が語られた。澤邊氏はバイク事故で頸椎を損傷し、車椅子生活を送っている現状に触れつつ「再生医療に期待する一方で、どこまで自分をデジタルデータとして拡張させられるか、自分自身で実験したい」と語った。深堀氏はロボットがフィジカルな身体をもつことで、実際に人を助けたり商店でモノを買ったりできるとコメント。自宅にいながらアバターロボットを脳波でコントロールできる時代も遠い未来ではないとした。最後に國光氏は、VR世界をハードフォークできる未来をつくりたいとして、ディスカッションを締めくくった。
次ページ:
パネルディスカッション「XRがもたらす可能性とは?」
パネルディスカッション「XRがもたらす可能性とは?」
パネルディスカッション「XRがもたらす可能性とは?」では、角川ドワンゴ学園で理事を務める川上量生氏と、一般社団法人XRコンソーシアムで代表理事を務める藤井直敬氏。そして2021年4月に新設されたiU(情報経営イノベーション専門職大学)で学長を務める中村伊知哉氏が登壇した。奇しくも3名とも教育関係に名を連ねていることもあり、議論は学校教育のあり方からコロナ禍における社会変化まで、様々な議論が展開された。
ディスカッションは、混乱されがちな「XR」という用語の整理から始まった。藤井氏は「僕らが2015年に一般社団法人を設立したときは『VRコンソーシアム』と言っていた。それが技術が進化して、ARだMRだと様々な表現方法が出てきた。今後も同じ事態が予想されることから、みんなまとめてXRという言葉になった」とコメント。その上で、ヘッドマウントディスプレイなどを使用し、仮想空間に没入するのがVR。現実に3DCGの映像を重ねるのがAR。現実をデジタルでマッピングし、より高度な重ね合わせをするのがMRだとまとめた。ただその境界は現在も曖昧だという。
またXRに含まれる産業には、デバイスもあればクラウドもあるし、コンテンツもツールもインフラもある。「何をしてXRなのか」という質問に対して、藤井氏は「こうした状況は当初からわかっていた。そのため、何か特定の業界の人々がリードするというかたちではなく、コンソーシアムというかたちにして様々な業界の人々に参加してもらう場をつくった」とふり返った。
続いてトピックは「人間と認知のあり方」に移った。川上氏はXRデバイスの普及を「人間という種族を大きく進化させるほどの変化」だとする。人間は網膜に映った情報ではなく、大脳で情報処理をした上で映像として認識している。つまり人間は、現実の世界を有機物でできたニューラル・ネットワーク上で情報処理した上で認識している。このしくみがXRデバイスとAIが組み合わさることで、さらに拡大する可能性があるという。
藤井氏も「自分は大学で脳科学の研究を続けてきた。そんな自分がなぜXRに関する取り組みをしているか、よく質問される。テクノロジーを適切に用いることで、脳を上手くだますことができ、そうした技術の中にAIが入ってきた。これからはAIと脳が協業していく時代。自分もXRやAIといったテクノロジーを用いて、現実をより良くしていきたい」と補足した。
▲iU 中村伊知哉氏
では、現実にXRは私たちの暮らしをどのように変えていくのか。藤井氏は「わかりやすいのはエンターテインメントだが、追加のデバイスを購入する必要がある。そのためまだ普及台数が少ない点がネック」だとした。川上氏もXRは市場が小さく、マニアのための域を出ていないと話し、最初に成功するXRコンテンツはスマートフォンをベースのものだとした。『ポケモンGO』(2016)は好例で、次に来るのはスマートフォンを用いたアバターコミュニケーションサービスではないかという。
むしろ川上氏は、XRで有望なのは教育産業だとした。その実践例が、川上氏が理事を務めるN高等学校(以下、N高)だ。2016年4月に開校し生徒数が約1万5,000人、いわゆる通信制高校としては日本一の規模を誇るN高。2021年度からは新たに「S高等学校(以下、S高)」も開校した。それと同時にスタートしたのが、VRを本格的に採り入れた教育コース「普通科プレミアム」だ。同コースと契約するとOculus Quest 2が生徒に貸与され、PCとVRの両方を使って受講できる。
▲ドワンゴ 川上量生氏
川上氏は「VRを使った教育で最も重要なのは、余計な情報が入らず学習に集中させられること」とした。その上で「他人の視線を擬似的に感じさせられる点」が有効だという。これにより通信制教育の欠点を改善できるというわけだ。「通信制は1人で勉強するので心が折れやすい。VRを使うと他人の視線を擬似的に感じさせられるので、複数で勉強している感じを出すことができる」。
ここで重要なのは、学習が非同期で行われている点だ。授業コンテンツは動画教材でつくられているいわゆる「座学スタイル」だ。これに対してVR教室で学ぶ他の生徒の動きは、過去の学習時に収集されたモーションデータで表現されている。これにより通信量を劇的に減らすことができる。他の生徒とリアルタイムにコミュニケーションをとる必要性がない場合、これで十分というわけだ。
このように「普通科プレミアムコース」では、講師が授業を行う動画教材パートと、教室内の風景や他の生徒、クイズ部分などの3DCGパートが別々でつくられている。そのため3DCGパートはそのままに、動画教材を切り替えるだけで別の授業コンテンツにできる。講師も通常の授業を行うのと同じスタイルで、動画だけを収録すれば良いため授業のクオリティ向上が期待できるという。
また英会話の授業では、講師の替わりにテキストを読みあげるAIキャラクターの導入も検討中だ。「VR教材というと派手なものをつくりたがるが、採算を考慮することも重要。動画教材にしても、4Kカメラと360度カメラが1台ずつあればすぐにできる」(川上氏)。これに対して中村氏も、「iUの学生の出身校で一番多いのがN高。本学でも、こうした取り組みを進めなければいけない」とコメントした。
▲XRコンソーシアム 藤井直敬氏
人類はXRでさらに進化する
藤井氏も教育や研修用途におけるXR技術の可能性は高いとしつつ、解像度やリアルな映像が本質ではないとした。「工場やコンビニの研修でいえば、必要なのは手順を覚えさせること。XRを用いた研修教材では、映像のクオリティではなくインタラクションを伴った体験をデザインすることが重要だ。実際に建築現場など、人の生き死にに関わるような分野からXR研修が始まり、近年ではそれ以外の分野にも広がってきている。それだけコンテンツを開発するコストが見合ってきた」(藤井氏)。
他にXR技術で期待されるのがテレワークだ。コロナ禍でテレワークの導入が加速しており、「実際にXR技術を用いたテレワーク向けのサービスやプラットフォームも増加している。ただしハードウェアの普及度がネック。また、Zoomなどで満足できている点もある。Zoomを越えるだけのメリットをいかに提示できるかがポイントだ」(藤井氏)。他人の存在感が感じられたり、同じ資料を一緒に見て議論するなどの体験が鍵を握るのではないかという。
川上氏も「高齢の経営者でも、必要に迫られればZoomを使うようになることがわかった。XRも同じで、経営者が得になるようなアプリケーションを開発することが重要」だと指摘。経営者の思考を模したAIキャラクターがVR空間に登場し、管理職や部下に対して直接訓話したり、指導したりするようなアプリケーションが開発できれば、大いに喜ばれるのではないかと語った。
これに対して中村氏は「去年、大学の設立を準備していた頃からコロナ禍になり、開校後もオンライン授業が続いている。自分もスマートフォンやPCではなく、より大型の画面を自宅の壁に設置して、家と大学を地続きにするような環境を構築中。いわばヘッドセットを被らないXR環境をつくりたいと思っている」という。藤井氏も「XRだからといってデバイスを使う必要はない。壁の向こうに世界が地続きで存在すると思わせることができれば良い」とした。
▲藤井直敬氏が代表を務める株式会社ハコスコのホームページ
「リアルの方が良いとされていることも、今後は全てXRになる」と指摘する川上氏。面接や観光なども含めてバーチャルの方がより豊かな体験ができる......、そんな世界になると断言する。例えば、実際に人と会うよりも「現実のように見える映像の上」にその人の名前や属性などが表示された方が(それはARやMRデバイス越しに見る世界かもしれない)、より便利ということだ。「還暦を過ぎてますます人の名前が思い出せなくなってきたので、それはとても良いですね」(中村氏)。
そうした世界が到来するためには、何はなくともハードウェアの普及が必要だ。藤井氏は「ハコスコを始めたのも無料で配れるから。紙製の箱にスポンサー企業がロゴを印刷してくれたら、協賛費で相殺できる可能性がある」。川上氏も「1人1台の環境を実現できてしまっているのが学校。オンライン教育はXRとも相性が良い。ビジネスとして成立させつつ、新しい可能性を模索していきたい」と話した。
登壇者のコメント
最後に三名の登壇者が次のようにコメントを投げかけ、セッションが終了した。
「XRは技術でしかなく、そこで何をするかがポイントで、そのためには想像力が必要。僕らがターゲットにしているのはXR技術ではなく、あくまで人であり、もっと言えば脳。そこをどうやって攻めるかが面白くて、これまでとは異なるノウハウが求められる。実際に、ここ5~6年で面白いコンテンツがどんどん出てきた。今後必ず報われる市場だと考えている」(藤井氏)。
「日本人はXRと親和性が高い。これだけオタクが市民権を得ていることからもわかるように、現実よりも人間がつくったデータに価値を見出す人の割合が、諸外国よりも多いと思う。最近はネットでもAIでも日本は後塵を拝しているが、XRなら日本の元気な姿を見せられると思う。みんなでがんばっていきましょう」(川上氏)。
「XRが私たちの生活に身近な存在になっていること。XRを使うことで豊かな未来がつくれるということ。今日はこの2つの見通しが得られた。コロナ禍はいつか終息する。Afterコロナに向けて面白い議論ができたことに加え、この議論をこれだけ多くの人と同じ場所で共有できた点がポイント。今後のXRの発展を祈願して、このパネルディスカッションを終了したい」(中村氏)。