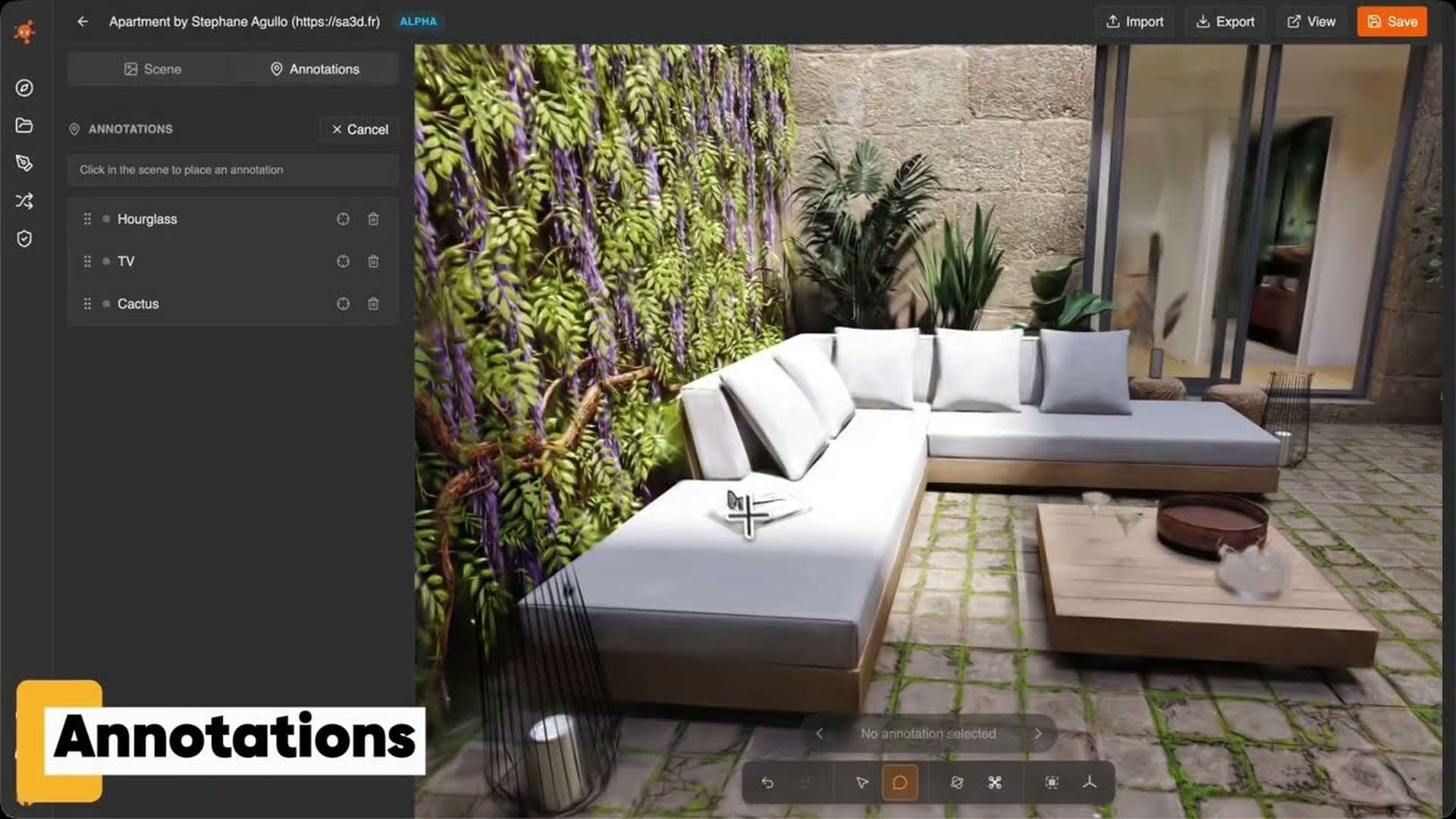Digital Domain(現Digital Domain 3.0, INC.)バンクーバー スタジオにてDigital Environment Leadを務める佐々木 稔氏が、2015年3月に一時帰国し、母校である東洋美術学校(東京都新宿区)にて講演を行なった。会場には在校生だけでなく一般参加者も詰めかけ、長年の実体験に裏打ちされた佐々木氏の話に多くの聴衆が聞き入った。後半には質疑応答の時間も設けられ、ハリウッド映画の最新VFX事情から、業界を目指す学生へのアドバイスまで、話題は広範囲におよんだ。本記事では、講演と、その直前に実施した佐々木氏へのインタビューの模様をお伝えする。
自分が培ってきたゼネラリスト のスキルが生きている
佐々木氏は東洋美術学校に2年間在籍してイラストレーションやデザインを学んだ後、国内の映像制作会社における8年間の勤務を経て、2000年に渡米した。
「"大学を卒業していて当たり前" という当時の風潮のなかで、大卒じゃなくても馬鹿にされない結果を出さなければと、必死にSIGGRAPHのComputer Animation Festivalなどのコンペに作品を応募していたのです。そのときの受賞がきっかけで、海外のいくつかのプロダクションからオファーをいただきました」と佐々木氏はふり返る。渡米後はアメリカ、サンタモニカのCafeFX Inc.に10年間在籍し、ゼネラリストのVFXアーティストとしてCMやミュージックPVなどを手がけた。同社にいた6人のゼネラリストたちは全員が得意分野をもっており、佐々木氏の場合はEnvironment(背景)を担当することが多かったという。
しかし、2008年のリーマン・ショックに端を発する世界的な金融危機の余波を受けて、CafeFXの閉鎖が決定。2010年にカナダにわたり、Digital Matt PainterとしてDigital Domainに移籍した。
「映画制作に携わりたいという思いがあったので、大手のVFXスタジオに照準を絞って移籍先を探しました。ただし大手の場合は細かく分業化されているので、従来のゼネラリストではなく、職種を選ぶ必要があったのです。そこで、Environment専門のDigital Matte Paint(以降、DMP)に特化したデモリールを制作しました」とのことだが、DMPだけを専門にするつもりはいっさいなかったと佐々木氏は語る。「移籍の準備を始めた2009年の時点から、5年後には、自分が培ってきたゼネラリストのスキルが生きてくるだろうと予想していました」。

その後、佐々木氏はIndustrial Light & Magic(ILM)、Method Studioなどのバンクーバー スタジオを渡り歩き、再びDigital Domainに戻り、現在はDigital Environment Leadとして活躍している(※2015年4月末現在)。
「近年、DMPという職種は、Environmentという枠組みのなかに吸収されつつあります。DMPを担えるだけの絵画力のあるアーティストが、MayaやNUKEなどのソフトウェアも駆使して、最終ショットのEnvironmentを仕上げていくのです」。
つまり、Environment専門のゼネラリストのような職種が確立しつつあるというのだ。実際、佐々木氏は1人でEnvironmentのConcept、Design、Modeling、Texture、Lighting、DMP、Composite を担えるという。「もちろん、日本の3DCGプロダクションのように、1人で全部を担当するケースは少ないです。しかし、全部を知っていることで、チームのコミュニケーションが円滑になり、作業効率が各段に良くなります」。
ショットのEnvironmentをDMPだけで制作してしまうと、ライティングやカメラワークを容易に変更できない。その一方、3DCGならば、正確かつ柔軟に、しかも全体の均一感を維持したまま変更できる。「例えば、クライアントが『太陽の位置を逆にしよう』と言いだした場合、DMPだとそう簡単に対応できません。しかし現実には、ライティングも、カメラの位置やアングルも、頻繁に変更されます。だったら3DCGでつくった方が、早く安く柔軟に良い結果を出せるのです」。そのため最近のEnvironmentは、基本的に3DCGで制作し、3DCGだけでは自然な表現ができない部分をDMPで補う、あるいはDMPの方が効果的と判断できる場合のみDMPを選択する方法が主流になっているそうだ。
「夢にも思わないようなリクエストが出されたとしても、髙い瞬発力や柔軟性を発揮する......、そういう姿勢をどの会社も心がけていましたね。特にギガリッチなクライアントが相手だと、その傾向が顕著です。日本でTVの映像制作に関わっていた頃に培った、努力し、改善し、最後まで諦めない姿勢が、上手く生かせていると思います。それに対して、クライアントも上司も、強く感謝してくれる点は素晴らしいですね。その感謝は、休暇や報酬にも反映されます」。
[[SplitPage]]現段階では、アナログの熟練者たちから学ぶことが山ほどある
VFXアーティストとしてEnvironmentを担当するからには、ソフトウェアを使いこなす技術力が欠かせない。それに加えて、"スーパーリアル(サーリアル)なEnvironment"を表現し、しかもリアルを維持しつつ、クライアントのリクエスト通りに修正できる判断力が必要だと佐々木氏は語る。
「経験豊富な監督やVFXスーパーバイザーですら、『理由はわからないけど、このショットの背景は好きじゃない』としかコメントできないケースが、実はすごく多いのです。ときには20年の業界経験者が錯覚に気づかず、何日も問題を探っている......などという信じられない事態も起こります。そのくらい、人の目は慣れによって狂いますし、その日の視覚体験によっても変わります」。
そんな事態の突破口を高い確率で発見してくれるのが、本当にリアルな絵を描いてきた人や、ミニチュア模型をつくってきた人だという。
「アナログな方法で、自分の手を使ってリアルな絵やミニチュアを何度も完成させてきた人は、どんなレイアウトや平面構成であれば、人の目は動きを感じるのか、静寂を感じるのか、躍動を感じるのか、あるいはスッキリ落ち着いて見えるのか......といった傾向を熟知しています。加えて、つくる前から完成形が頭のなかに描けているので、どんな手を使ってでも完成させようとする推進力が桁ちがいです。彼らは決して、ジオメトリの重さや、GI(Grobal Illumination)の不具合、レンダリング時間、マシンスピードといったテクノロジーの限界を言い訳にしません。将来、もっと直感的に使えるデジタルツールが開発されるかもしれませんが、現段階ではアナログの熟練者たちから学ぶことが山ほどあります」。
佐々木氏自身も、東洋美術学校で学んだクラシックなリアルイラストやデッサン、平面構成、色彩概論などが、今の仕事の土台になっていると感じるそうだ。
「われわれが使うソフトウェアや制作スタイルは常に変わり続けますし、もし販売会社が倒産すれば、ソフトウェアに関する知識の50%以上が必要なくなります。けれども、絵を描きながら磨いた洞察力、平面構成や色彩概論を通して学んだ人間の視覚の原理は、使うツールが変わっても、何年経っても役に立ち続けています」。
クラシックな絵画やデザインの力は、いつの時代であろうと、映像をつくる全ての職業で役に立つ......20年以上におよぶ実体験がそれを確信させるのだと、佐々木氏は語る。

ハリウッドを中心とした映画制作では、流行やスタイルを気にせず、ただひたすらリアルに見せるという、シンプルで高いゴールがある。ただし、単にリアルな映像をつくれば良いだけの仕事ではないと佐々木氏は釘を刺す「リアルに見せられることは当たり前であり、われわれが目指すのはさらにその先です。クライアントが望む演出やデザインを実現するため、リアルを利用する職人なのです」。
例えば人物のポートレート写真を自然光で撮影する場合、カメラマンはレフ板を使って太陽光を反射させ、人物の顔に落ちた濃い陰をやわらげる。多くの場合、前述のように光を演出した方が、ありのままのライティングで撮影するよりも効果的な写真を撮影できる。
3DCG を使う場合にも、同様のことが言えると佐々木氏は続ける。「3DCGギーク、VFXギークの人は"物理的に正確なEnvironmentをつくることが正解だ"と誤解しがちです。しかしわれわれに期待されているのは、ヒーローキャラクターやストーリーを引き立てるEnvironmentの制作です。そのショットで表現したいものは何か、前後のショットにどんな影響を与えるのかを把握して、視聴者の心理や視覚を予測し、映画自体をよりよくするためのEnvironmentを心がけています」。
危険なシーンであれば、より危険に感じるような空気感やデザイン。主人公が前向きになり、明るい気持ちになるシーンでは、ピュアでストレートな色彩表現やシルエットの見栄えなどを意識しているという。「加えて、背景は恐ろしいほどヘビーなファイルサイズになりがちなので、不必要な労力を使ったり、過度なクオリティにならないようにも気を付けています。これが一番難しい職人判断ですね」。
講演の最後、「仕事をする上で大切なことは何でしょう?」という問いに対して、佐々木氏は「本人が楽しくやっているかどうかが大事」と答えた。
「どんなに辛いことがあっても、楽しむことができればがんばれます。日本でもアメリカでも、私はずっと必死に楽しんできました。今日お話した私の経験は、特別なものでも何でもありません。世の中には、私のような人間は腐るほどいます。私の話を特別視せず、ご自身の可能性を理解するための糧にしてもらえればと願っています」。
TEXT_尾形美幸(EduCat)