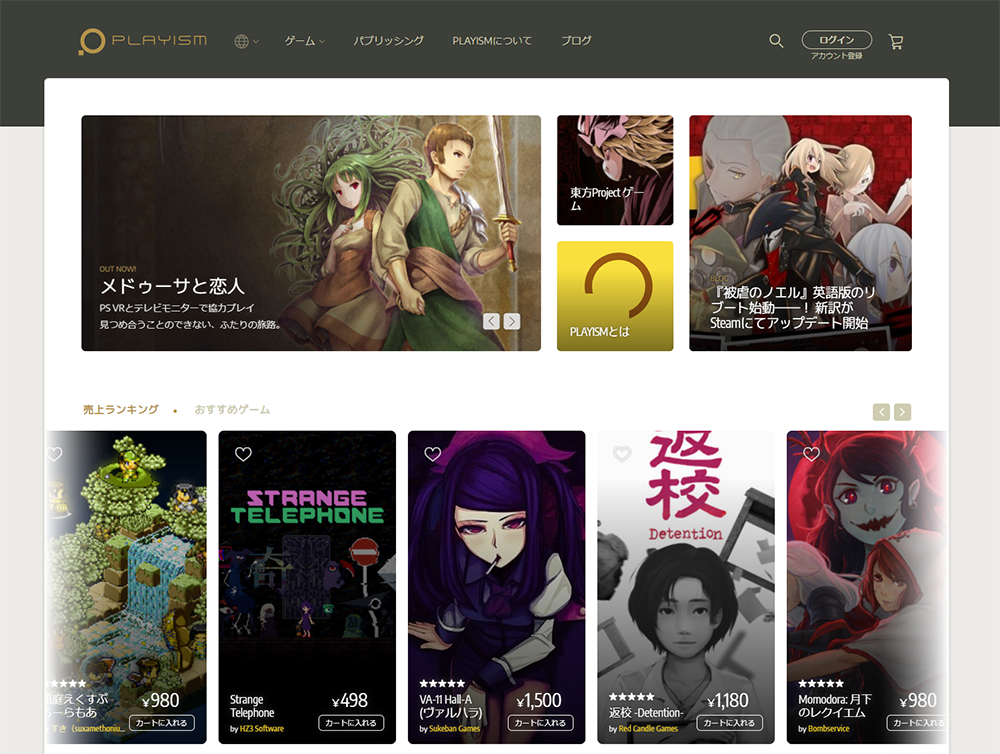星の数ほどのコンテンツが存在する時代。発売されたことも気づかれないまま、市場で埋もれてしまう作品も少なくない。大切なのは、消費者にコンテンツの存在を知ってもらうこと。良質なコンテンツをつくることは大前提で、ユーザーに正しくその価値を伝え、選択してもらうことが求められているのだ。エンタメ業界でプロモーションやマーケティングが、今ほど重要になっている時代はないだろう。
その一方で、2020年はコロナ禍に伴い、東京ゲームショウをはじめとした多くのイベントがオンラインに移行した。ここで大きな影響を受けたのがインディゲームだ。インディゲーム開発者はこれまで、イベント出展をはじめとした対面マーケティングを中心に据えてきた。そのため、コロナ禍に伴って自分たちのタイトルを世に知らしめることが困難な状況に陥った。
こうした中、インディゲーム向けのネット情報番組「INDIE Live Expo」をいち早く起ち上げた人物がいる。リュウズオフィス代表の小沼竜太氏だ。同社はまた、ゲーム専門でプロモーション・マーケティング支援を行うユニークな企業でもある。そんな小沼氏が本年、書籍『伝え方は「順番」がすべて: 分単位のコミュニケーションが心を動かす』を上梓した。2020年をふり返りつつ、その内容について聞いた。
INTERVIEW&PHOTO_小野憲史 / Kenji Ono
EDIT_三村ゆにこ / Uniko Mimura(@UNIKO_LITTLE)
ゲーム専門のユーザー・コミュニケーションプランナー
CGWORLD(以下、CGW):遅ればせながら書籍『伝え方は「順番」がすべて: 分単位のコミュニケーションが心を動かす』の出版おめでとうございます。ゲームを専門にマーケティングやプロモーション支援を行う会社の代表として、業界では知る人ぞ知る存在かと思いますが、改めて自己紹介をお願いします。
小沼竜太氏(以下、小沼):ありがとうございます。もともと父親がファミコン時代からゲーム業界でプロモーションのお手伝いをしていて、自分も紆余曲折を経て同じ仕事を手がけるようになりました。2004年3月にリュウズオフィスを起ち上げたのですが当時は父親と2人だけの事務所で、その後、ほどなくして父親は離脱し、ゲームをメインとしたユーザーコミュニケーションのプランニング事業を1人でやっていました。
-

-
小沼竜太/Ryuta Konuma
株式会社リュウズオフィス代表取締役
ryusoffice.co.jp
小沼:当時手がけた主なタイトルに、アトラスから発売されたRPG『ペルソナ3 』(2006)があります。本作のプロモーションを通して仕事の幅がぐっと広がりました。そこから『世界樹の迷宮』(2007)、『ペルソナ4』(2008)を担当し、その後、セガから発売された『セブンスドラゴン』(2009)のプロモーションを契機に開発を担当したイメージエポックとご縁ができたのです。マーベラスから発売された『Fate/EXTRA』(2010)の後に、イメージエポックに合流して、「JRPG宣言」のプロモーション戦略を手がけることになりました。
CGW:それまでデベロッパーだったイメージエポックがパブリッシャーになると共に、JRPGを盛り上げていく決意表明をされたイベントでしたね。当時「JRPG」はイノベーションに乏しい国産RPGを揶揄する言葉として、欧米圏を中心に広まっていた言葉だっただけに衝撃的でした。あのイベント戦略を担当されていたのですね。
小沼:個人的にも契機となるイベントでした。その後2年して取締役を退任して、再び『ペルソナ5』(2016)をはじめとする『ペルソナ』シリーズの4タイトルのプロモーションを一気に引き受けることになります。私とアシスタントの2人で進めましたが、さすがに限界を感じていました。そこで2014年頃から本格的にスタッフを増やしはじめて、現在は30名くらいの規模になっています。もっとも、会社が成長しても業務内容は変わらず、ゲーム業界におけるユーザーコミュニケーションのプランニングと実施を中心に事業を進めています。
CGW:今年からインディーゲームのネット紹介番組『INDIE Live Expo』も始められましたね。
小沼:6月に第1回を行い、第2回が11月でした。現在は第3回の準備を進めているところで、2021年の中ごろまでに実施したいと考えています。おかげさまで『INDIE Live Expo I』で紹介したタイトルの中から、『クラフトピア』という大ヒットタイトルが生まれました。『INDIE Live Expo II』で紹介したタイトルでも『天穂のサクナヒメ』をはじめ、話題作や注目作を取り扱うことができました。インディゲームの登竜門ではありませんが、『INDIE Live Expo』できちんと情報を発信するとヒットする、という実績を積み上げていきたいですね。関心のある方がいたら、ぜひ公式サイトからご連絡いただければ幸いです。
CGW:そもそもゲーム専門でマーケティングやプロモーション業務を担当されている会社を勉強不足で知らなかったのですが、他にあるのでしょうか?
小沼:珍しいと思います。大手の広告代理店がゲーム専門のユニットを起ち上げることもありますが、あまり長続きしない傾向にありますね。これは書籍にも書きましたが、ゲーム市場自体は過去40年間で一貫して成長を続けていて、動くお金も大きくなっています。そのため市場で勢いが出てくるたびに大手が参入を試みて、少し経つと撤退するというサイクルが続いています。移り変わりの早い業界である一方で、過去40年間における文脈の蓄積もあるわけで、その時々のトレンドを切り取るだけではなかなか上手くいかないのではないでしょうか。
CGW:ハードウェアも変わるし業態も変わるし、さらに担当者も変わりますよね。余談ですが、昔は企業ごとにプロモーションのキーマンがいましたよね。「任天堂ならあの人」、「セガならこの人」という感じで、その人さえ捕まえておけば大丈夫みたいな。ただ、今はそうしたキーマンがわかりにくくなりましたね。
小沼:ゲームに限らず、様々な業界で宣伝やユーザーコミュニケーションの垣根がどんどん壊れています。その一方で、扱うメディアも昔は雑誌が中心で、たまにテレビCMがあった程度だったものが、Webサイト、SNS、イベント、生放送......、とどんどん広がっていきました。
こうした流れに対して、大企業を中心にメディアの増加にあわせて部署を新設してきたわけですが、その結果とてもじゃないけど1人で全ての内容を管理できなくなってきたんです。これは、弊社のように外部で宣伝をお手伝いさせていただく側にとっても課題になっていて、あまりにも広がりすぎている各専門部署に対して、どのように対応していくかが問われています。
CGW:ちなみに、そうした案件におけるカウンターパートはどういった部署になるんでしょうか? プロモーション担当の部署なのかプロデューサーなのか......。
小沼:ケースバイケースですが、プロデューサーや経営者の方と戦略を練っていくことが多いですね。その上で、プロモーション担当の方と個別のお話をしていきます。ただ、冒頭で話したようにプロモーションの分野が多種多様にふくれあがっているので、現場で実務を担当されるプロモーション担当の方は大変だろうなと思います。
CGW:なるほど。つまりプロデューサーの下に様々な分野のプロモーション担当がいて、大手パブリッシャーだとそれが日本と北米と欧州とかに分かれていて。それらが本来であれば1つの目標に向かってゴール思考で連携を取って進めていくべきなんだけど、人が多いと調整が大変なので、上手く戦略を組み立てていくといったことが鍵になっているんですね。
小沼:そうですね。ただ、そうした経験のある人がまだまだ少ないので、大変だろうなと思います。
キーワードは「in Minutes Operation」
CGW:こうしたメディアの現状を踏まえて、本書では「in Minutes Operation」という概念を提唱されていますね。ゲームに限らず、今のプロモーションやユーザーコミュニケーションで求められていることを上手く言語化している感じがあり、膝を打ちました。
-
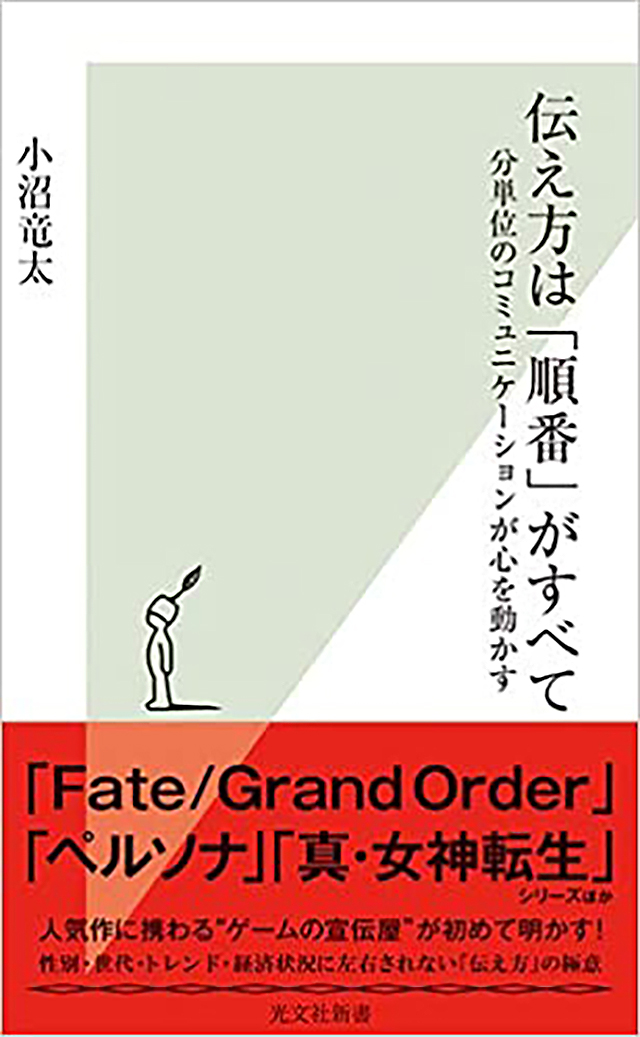
-
◀『伝え方は「順番」がすべて 分単位のコミュニケーションが心を動かす』(光文社新書)
www.kobunsha.com/shelf/book/isbn/9784334044930
CGW:その一方で、誰もが「それが理想」だと知りながらもいろいろな理由で実現できない......、そういった現場のジレンマが透けて見えるような印象もあります。簡単に説明していただけますか?
小沼:in Minutes Operationはまさに言葉通りの意味で、分単位のマーケティングオペレーションのことを指します。大前提として、情報にはそれが世に出た瞬間、注目に値する内容であれば人から人へと自然に拡散していく性質があります。それが昔は「人の噂も75日」ではありませんが伝達速度が遅かったので、その価値が減衰しにくかったんですね。ある情報が数日から数週間かけて広がっていくことも珍しくありませんでした。
それが今では、SNSなどの発達で何分、何十秒、下手すれば数秒で世界中に拡散される世の中になりました。ただ、そんなふうに情報の伝達速度が速くなったことで、価値の低下が激しくなったのも事実です。その結果、重要な情報であればあるほど、長期間にわたって話題を集めることが難しい社会になってしまったのです。そこで弊社では、情報の価値が新鮮なうちに最大限拡散させるための手法や考え方を「in Minutes Operation」と呼んでいます。
CGW:まさに分単位で様々な施策をリアルもバーチャルも含めて展開していくということなんですね。
小沼:そうですね。その一方で本のタイトルを「伝え方は「順番」がすべて」としたように、情報を出す順番を間違えるとせっかくの情報も十分に広がらないという問題が生じます。そこで、その設計を丁寧にしようということですね。ただ、先ほどもお話しした通り、実際の施策では複数の専門部署が関わるので、それらを有機的に連携させるところが大事なポイントになります。
CGW:まさに本書で書かれていることですが、SNS、Web、生放送といった具合に、「何をやるか」が重要なのではなく、「どのような順番でやるか」が重要だという話ですね。読みながら、ゴール思考の考え方に似ているなと思いました。学生のレポートなどに顕著なのですが、人は課題を与えられると反射的に「何をするのか」と考えがちです。そうなると次から次へとアイデアが浮かんできて、優先順位がつけられず中途半端な内容になることが少なくありません。そのため授業では、まず「なぜやるのか」という理由を固めるように言っています。そうすれば、「どうやるのか」「何をやるのか」と自然に発想が繋がっていくからと。
小沼:そうですね。本来、実施するアクションには理由があり、解決したい課題に紐付いているはずです。それを忘れないようにすれば手段を誤ることはないと思います。「何かやること」が大事なのではなくて、常に「何を伝えたいのか」、「何を解決したいのか」に立ち戻って考えることが大切だと思います。
CGW:そうした考え方や問題意識は、業務を通じて徐々に生まれてきたものでしょうか? 影響を受けた人やエピソードなどはありますか?
小沼:『Fate』シリーズで知られるTYPE-MOONの武内 崇さんの影響がすごく大きいですね。以前、同社の仕事を手がける中でミスをしたことがあります。出すべきではない情報を出すべきではないタイミングで出してしまった。まさに手順を間違えてしまったわけです。その際、武内さんに「情報の価値をわかっていますか」と叱っていただきました。もちろん、自分も情報の価値について理解しているつもりでしたが、言葉に出して言われたのは初めてでした。それがきっかけで、情報には必ず価値があることを強く意識したのです。
この気づきをきっかけに、それまで試していた様々な手法の中で、上手くいったケースと情報の価値という概念が融合していきました。これがin Minutes Operationという概念に体系化されていったのです。
CGW:大きな気づきをもたらした一言になりましたね。
小沼:そう思います。
コロナ禍に適したゲームイベントの設計
CGW:2020年はコロナ禍に伴い、東京ゲームショウをはじめとした多くのゲームイベントがオンライン開催に移行しました。どのイベントも手探りで、上手くいったこともあったし反省や改善すべき点もありました。それらを踏まえて、現状をどのように見られてますか?
小沼:業界の中でも、今年初めていわゆるオンラインイベントや生放送の仕事に携わった人が大勢いると思います。その上であえて言うと、こと東京ゲームショウに関しては、率直に言って成功とは言いづらいと思っています。それ以外にも失敗しているオンラインイベントは非常に多いですね。その理由はよくわかります。「イベントをオンライン化する」という発想だとこのようになるんですよ。
小沼:東京ゲームショウをはじめとしたイベント会場では、そこを歩くだけで様々な情報が目に飛び込み音が聞こえてきますし、それらに反応する多くの来場者がいます。その結果、情報密度がものすごく高い空間になります。それがイベントの特徴であり面白さだと思います。
その一方で、オンラインイベントにはインタラクティブな要素はあるものの、基本的には情報の流れが一方通行なんです。また、体験がモニタという二次元の空間に閉じています。つまり、まったく別物なんですよ。そのため、単純に三次元でやっていたものを二次元にしようとしてもなかなか難しいと思います。
ただし、これはイベントの内容によってもちがいますね。音楽ライブやカンファレンスのように、来場者の意識がステージに向かって集中している二次元的な催しならオンラインにも向くと思います。
CGW:それぞれで適したやり方があるはずということですね。INDIE Live Expo はいかがでしたか?
小沼:当初から「オンラインイベント」と称していました。私自身、生放送の黎明期から生放送制作に携わっていたため生放送の特性については熟知していますし、制作のスタッフも「ニコニコ超会議」、「闘会議」といった、オンラインを前提としたイベントの制作実績がありました。そのため、当初から生放送フォーマットに最適化したオンラインイベントを志向しデザインしました。
プロモーション面では、関係者を意識して増やして自然発生的な話題の醸成を目指しました。その際、in Minutes Operationという言葉こそ使いませんでしたが、出展してただいたクリエイター、デベロッパー、パブリッシャーの皆さんには、INDIE Live Expo内での情報公開にあわせて独自のプロモーションを同時に展開してもらうように提案させていただきました。
こうした中で、1回目から特性を理解してプロモーションに成功した方々もいますし、2回目では特性を理解して行動した方がより増えたように思っています。
CGW:ちなみに、ゲームプロモーションにおいてコロナの前後で決定的に変わったと感じられることはありますか?
小沼:実は何も変わっていないと思うんですよ。少なくとも、ゲーム・プロモーションに携わっている私の立場や仕事に関していうと、コロナの影響は極めて少ないと言うか何も変わっていません。
CGW:興味深いですね。もう少し詳しく説明していただけますか?
小沼:当然ユーザーの生活習慣は大きく変わったと思います。相対的に家の中で過ごす時間が増えたりインターネットに繋がる時間が圧倒的に長くなったり。ただ、そもそも情報を届ける行為であったり、何か新しい情報を望んでいたり情報を受け取ってくれる人がいたりという状況自体は変わっていません。その手段として、リアルのイベントが封じられたというだけです。手段が少なくなった点では変わりましたが、本質的なものは変わっていないと言えます。
CGW:これまでリアルイベントの存在感が大きかったため、それがなくなった喪失感が大きかったというか、多くの人が注目しがちなんでしょうか?
小沼:はい。リアルイベントは手段の1つであって、それが全てではない。目的ではないので手段が1つ減ったという認識です。
[[SplitPage]]
INDIE Live Expo開催への道
CGW:そうした認識はコンシューマゲームとインディゲームでは異なるかもしれませんね。様々なプロモーション手段を駆使できるコンシューマゲームとはちがい、インディゲームではイベント出展を中心とした対面マーケティングが主流でした。
小沼:そうですね。INDIE Live Expoも、そうした問題意識から生まれました。ゲームの宣伝ができなくて困っている人たちがたくさんいるので、その助けになろうという気持ちです。その一方でインディゲームの開発者には、リアルイベントが唯一のプロモーション手段だと思い込んでいる人が多いと感じていました。そのため、ほかの手段があることを知ってもらいたかったという想いもありました。
CGW:INDIE Live ExpoはインディゲームブランドPLAYISMを展開するアクティブゲーミングメディアが協力していますね。どのように企画が起ち上がり、どのような知見が得られたのか、お聞かせください。
小沼:もともとインディゲーム専門のパブリッシャーで、自らも開発を手がけるWhy so serious, Inc.の方から、コロナ禍で困っているインディゲーム開発者が多いという話を聞いていました。そこでインディゲーム向けに宣伝機会を提供する試みについて提案したところ、賛同をいただいて。そこで、このアイデアを実現させるために日本で最大級のインディパブリッシャーである、アクティブゲーミングメディアの水谷俊次さんを紹介していただいたというながれです。水谷さんからも協力を快諾していただけました。
実際、水谷さんには情報集めの段階からご協力いただいています。どんなタイトルがあるのか、協賛していただけそうなを企業はどこか、といったレベルからですね。もっとも、コロナ禍でPLAYISMの側も課題を抱えていました。そこで我々の提案にご協力いただけたのだと思います。
前述したように、弊社ではインディゲームの方々に「プロモーションの手段は対面イベントだけではない」ことを知っていただく良い機会になるという考えがありました。この想いが通じて、東京ゲームショウの直前にPLAYISMが主催する『PLAYISM Game Show』という生放送番組が配信され、弊社も協力させていただきました。
CGW:良い話ですね。
小沼:生放送番組の費用は、それまで同社が確保されていたイベント出展向けの年間予算が原資になったそうです。実は先方でも、これまで国内外のイベントに出展されている中で「本当に意味があるんだろうか?」という疑問があったそうです。そうした中、INDIE Live Expoの開催を通して、生放送番組におけるプロモーション効果について認識していただけて。そこで、改めて自社で番組を配信したところ、大きな手応えを感じられたそうです。
CGW:興味深いですね。ただ、一般論としてインディゲーム関係者はお金をあまりもっていません。ビジネスという意味では旨みに乏しい気もしますが......。
小沼:おっしゃるとおりで、INDIE Live Expoだけでは儲かりません。ただ、将来に期待できる分野だと思っています。日本のインディゲームに不足しているものとして、次の3つの要素が挙げられます。第1に資本力。第2に「売れる製品をつくる」という意味でのプロデューサー。そして第3にマーケティングの知見と手段です。ただ、それでもヒットするタイトルはヒットするんですよ。
CGW:最近だと『天穂のサクナヒメ』が好例ですね。
小沼:はい。だからこそ、そこに対して弊社のマーケティング手法や知見を活用すれば、期待がもてる市場になる......、このことをINDIE Live Expoの初回開催を通して確信しました。こうした理由から、これからゆっくり育っていけば良いと思っています。
それに、INDIE Live Expoを通してすでに何社かプロモーションの相談を受けています。もちろん予算が潤沢にあるわけではないので、例えばロイヤリティ契約などを通してお互いにリスクを分け合いつつ、効果的な施策を打ち出していくといったことを進めています。
CGW:ワールドワイドで見れば『Untitled Goose Game 〜いたずらガチョウがやって来た!〜』が好例ですね。メルボルン(オーストラリア)のインディゲーム開発者が4人で開発したゲームで、世界中で大ヒットしました。開発中の動画をYouTubeに投稿したら、それが勝手にバズったのがきっかけです。宝くじに当選したようなものですが、まだまだそういったことが起こりうるんだなと驚かされました。
小沼:はいはい。INDIE Live Expoで徳岡正肇さんが解説されていましたね。
CGW:その上で気になるのは、そうしたヒットに再現性があるか否かで、世界中の関係者が答えを知りたいところだと思います。もちろん絶対の法則はないと思いますが、可能性を高める努力はできる。リュウズオフィスがもつ知見がその一助になって、もっとヒットタイトルが出て業界が活性化していけば個人的に嬉しいです。
小沼:ありがとうございます。
一周してパッケージゲームが最先端になってきた
CGW:インディゲームと、家庭用ゲームやスマートフォンといった大手企業が手がけるゲームで、マーケティングやプロモーションの施策を行なっていく場合、何かちがいはありますか?
小沼:実はこれもあまりちがいはないんですよね。考え方ややってることは基本的に一緒なんです。インディゲームと言ってもほぼ普段の仕事の知見が適用できるし、インディゲームの仕事をして得た知見というのも通常タイトルにもって来れる。まったく同じです。
CGW:インディゲームは規模が小さいので、プロデューサーやディレクターがプロモーション担当を兼ねている場合が大半ですよね。これが個人制作者であれば、1人で全部こなすことになります。だからこそ、in Minutes Operationのようなきめ細かいプロモーションがしやすい印象もあります。その一方で、どうしてもつくるだけで大変になってしまいプロモーションまで気が回らないところがあるのかな......、という気もします。
小沼:そうですね。ケースバイケースですが、意思の疎通に必要な人数が少ないので、スピーディな意思決定ができるところはインディゲームの強みだと思います。
CGW:あとは大手企業のプロモーションであれば、御社のような会社は黒子に徹すると言うか、表舞台に出てくる例は珍しいですよね。その一方で、インディゲームでは宣伝する側が表に出てアピールしていかないと、タイトルが埋もれてしまう感じもします。
小沼:そこもケースバイケースなんですよ。INDIE Live Expoについては、リュウズオフィスが旗振り役なので弊社の名前を出していきます。ただ、個々のタイトルをプロモーションする上で鍵を握るのは、ゲームを実際に開発している方々だと思います。そういう意味では変わらないですね。
CGW:本質的なことは規模の大小は問わず同じだということですね。
小沼:そう思います。
CGW:話は変わりますが、上海で開催されているインディゲームの展示イベント「WePlay 2019」に参加されましたね。自分もWePlay 2017を取材して、その熱気に驚かされました。まだまだWePlayに注目している関係者は少ないと思いますが、よく参加されましたね。
小沼:たまたま『INDIE Live Expo II』でテーマ曲の作曲をお願いした、『東方Project』で知られるインディゲーム開発者のZUNさんとご一緒に、会場を視察する機会がありました。自分が見た中でも、『東方Project』のステージイベントは一番盛り上がっていたように思います。
CGW:自分が取材したときもファミコンのアクションゲームでクリアタイムを競う大会が行われていて、とても盛り上がっていました。日本と中国で同じようなゲームで盛り上がっているんだなと、文化圏の近さを改めて感じました。
小沼:そういったところはありますね。
CGW:また、WePlayでは2019年度から、新たに「上海WePlayインディーズグランプリ・ノベルゲームコンテスト部門」が設置されました。日本では、JAGSA(一般社団法人日本ゲームシナリオライター協会)が窓口となり、ゲームの募集とプレイアブル展示が行われました。2020年度は自分が教えている専門学校からも応募があり、6作品を展示していただけました。
ただ、いずれも日本語のまま展示されたので、現地の人は満足に遊べないんですね。それでも先方からJAGSAに協力依頼があった理由として、「中国では原作に相当するストーリーを制作する力が弱いので、日本からも応募してもらって刺激を与えたい」という要望があったと聞いています。そういったことからも、現地の熱気が窺えました。
小沼:なるほど。自分自身もWePlay 2019がきっかけになって、海外市場や海外ユーザーに対する興味が広がりました。これは書籍にも書きましたが、WePlay 2019に参加していなければINDIE Live Expoは生まれていなかったと思います。
CGW:INDIE Live Expoは、当初から日本語・英語・中国語の三カ国語で配信されていて、日本だけでなく東アジア、そして世界に広がっていますね。今後の市場を考えると、100億円以上の開発費で開発された一握りのAAAゲームが10年くらい売れ続ける一方で、大量のインディゲームが発売されてそのいくつかがヒットするというように、世界中で二極化が進んでいく気がしています。
小沼:そのとおりですね。その上でインディゲームに関して言うとSteamというプラットフォームと切っても切り離せない関係があります。ただ、Steamは困ったことに国内の普及数がまだ小さいので、インディゲームに関わると必然的に中国語圏や英語圏のユーザーについて気にせざるを得ません。そのため、いかに彼らに情報を届けるかが課題となってきます。INDIE Live Expoが3カ国語対応を行なっているのも、そうした理由からです。
特に東アジアとは時差も近いですし、言語はちがってもゲームに関する文脈を一部共有できていると思っています。こんなふうに、日本のインディゲームにとって東アジアはものとても重要だと思っています。
CGW:一方で大手のゲームタイトルはいかがでしょうか?
小沼:インディゲームに限らず日本のコンシューマゲームも、もはや海外を意識せざるを得ないと思っています。言い方を変えると、今や「海外に出しさえすれば売れる」という世界に変わりました。あらゆるゲームが国外に意識を向けるべきだし、情報を伝えようと思えば伝わるんじゃないかと。
CGW:PS3世代の頃は、出す前にちゃんとカルチャライズしないと売れるものも売れない、みたいな風潮がありましたよね。その最大の成功事例が『ポケモン』シリーズの世界展開でした。それに対して、最近では無理にカルチャライズしなくてもこれは日本のゲームだから、日本のゲームはこうだからという風に受け入れてもらえるようになってきたように思います。
小沼:そうですね。日本のゲームを文化的な文脈まで含めて受け入れてくれる人の数が、以前より確実に増えてきています。もちろん、それらはニッチであることに変わりはないのですが、世界中のニッチをかき集めてくると、とんでもない数になってきたというのが、最近の特徴ではないでしょうか。北米だけでも、かつては数十万人くらいだったものが、今では数倍に増加していると言うか。
CGW:あくまで主観ですが、『ファイナルファンタジー(以下、FF)』シリーズが好例ではないでしょうか? 『FF』シリーズは長く「究極のRPGをつくる」ことをミッションに掲げる一方で、市場や顧客の定義は不明瞭なところがありました。「究極のRPGをつくれば全世界で売れる」といった具合です。しかし、『FF XV』から自分たちをグローバルニッチであると再定義した......、そんな印象があります。「全世界の『FF』ファンを糾合し、彼ら・彼女らに喜んでもらえるものをつくる」といった感じでしょうか。これが過去10年間の変化を象徴している気がします。
小沼:それはありますね。私もグローバルニッチの考え方であったり、「海外に届けようと思えば届くのだ」という感覚を『FF』シリーズのプロモーションを通して教えてもらいました。実は、『FF XV』のSNSコミュニケーションは弊社でお手伝いしていました。我々のミッションは、英語と日本語で世界中のユーザーと同時にコミュニケーションを取ることでした。その際、完全に日本人目線のやり方を貫いたんですね。つまり、日本のやり方を受け入れてくれる消費者を相手にしたんです。それをワールドワイドでやった結果、そういったユーザーは世界中に存在して、届けようと思えば届くのだという確信を得ました。
CGW:一方でスマートフォンゲームのプロモーションはいかがでしょうか? スマホゲームの世界展開はなかなか難しいところがありますね。
小沼:はい、そうした案件も弊社で手がけていますし、そう感じます。スマホゲームでは世界の市場がリージョンで分かれているので、ドメスティックな状態が続いていますね。
CGW:パブリッシャーのモチベーションも下がっていて、国内で固く当てる戦略にシフトしている印象を受けます。
小沼:そうですね。今からふり返ると、2010年代の前半はコンシューマゲームが本当にボロボロでした。当時と比べると、グローバルニッチ市場に日本人が気づいた点が大きな変化だと思います。そのためコンシューマゲームではタイトル数も減りましたが、楽観的なムードが漂っていますね。その一方で、スマホゲームでは国内市場を取り合うといったように視野が狭くなっている気はします。
CGW:そんなふうに10年単位でトレンドが変わっていくため、リュウズオフィスが手がけられている分野に対する、大手企業の参入が難しいのかもしれないですね。
小沼:スマホゲーム、コンシューマゲーム、インディゲームでは、それぞれ常識がちがうので、我々も案件ごとに頭を切り替えながら対応しています。今は状況が一周して、コンシューマゲームやインディゲーム、いわば「売り切り型のゲーム」の方が、宣伝や売り方の面では最先端に来ているのかなと思います。
CGW:今のコロナ禍の状況が来年どうなるかは不明ですよね。そうは言っても、ゲームのマーケティングやプロモーションの本質的な部分では規模の大小を問わず、やるべきことは変わらない。これまでと同じことを粛々とやっていくだけということでしょうか。
小沼:それで良いと思っています。もちろん細かいトレンドは変わるので、それらを把握しながらではありますが。我々としても対応すべき分野が増え続けているので、各分野のプロの採用に注力しています。ただ、弊社はコンシューマ向けのビジネスをしていませんので、なかなか募集が集まらないというのが正直なところです。これは我々にとっての課題ですね。
CGW:ちなみに、どういった方を希望されているのでしょうか?
小沼:Webのディレクターが急務ですね。Webでプロモーションを行う上で、インタラクティブなコンテンツの制作は欠かせません。その際にWebコンテンツの設計をしたり、制作ディレクションをしたりできる人ですね。その上でゲームが好きな人、ゲームに関心がある人が良いですね。通常考えられないくらい莫大なアクセス量のあるWebサイトを作ることが多いので、楽しいとは思いますよ。
CGW:なるほど。
小沼:弊社ではこれまで、対クライアントへの新規営業をしないというスタイルを貫いてきました。おかげさまで、それでも本当に大量のお仕事のご相談をいただいています。だからこそ、もっと個々の案件に対してより多くの労力を割きたいと思っています。そのためには、スタッフの採用と人材育成が必要になるのですが、それだけで結構な時間が必要になります。だからこそ、営業に時間が割けないという点もあるので、1人でも多くの優秀なスタッフを迎えて、個々の案件の精度をひとつずつ上げていきたいですね。
CGW:楽しみですね。2020年はようやく日本でもインディゲームが注目されるようになった年だったかなと。より業界を盛り上げるためにも、ますますのご活躍を期待しています。まずはINDIE Live Expo IIIの開催ですよね。
小沼:そうですね。番組配信を通して、一本でも多くのヒット作品が生まれるようにしていきたいです。