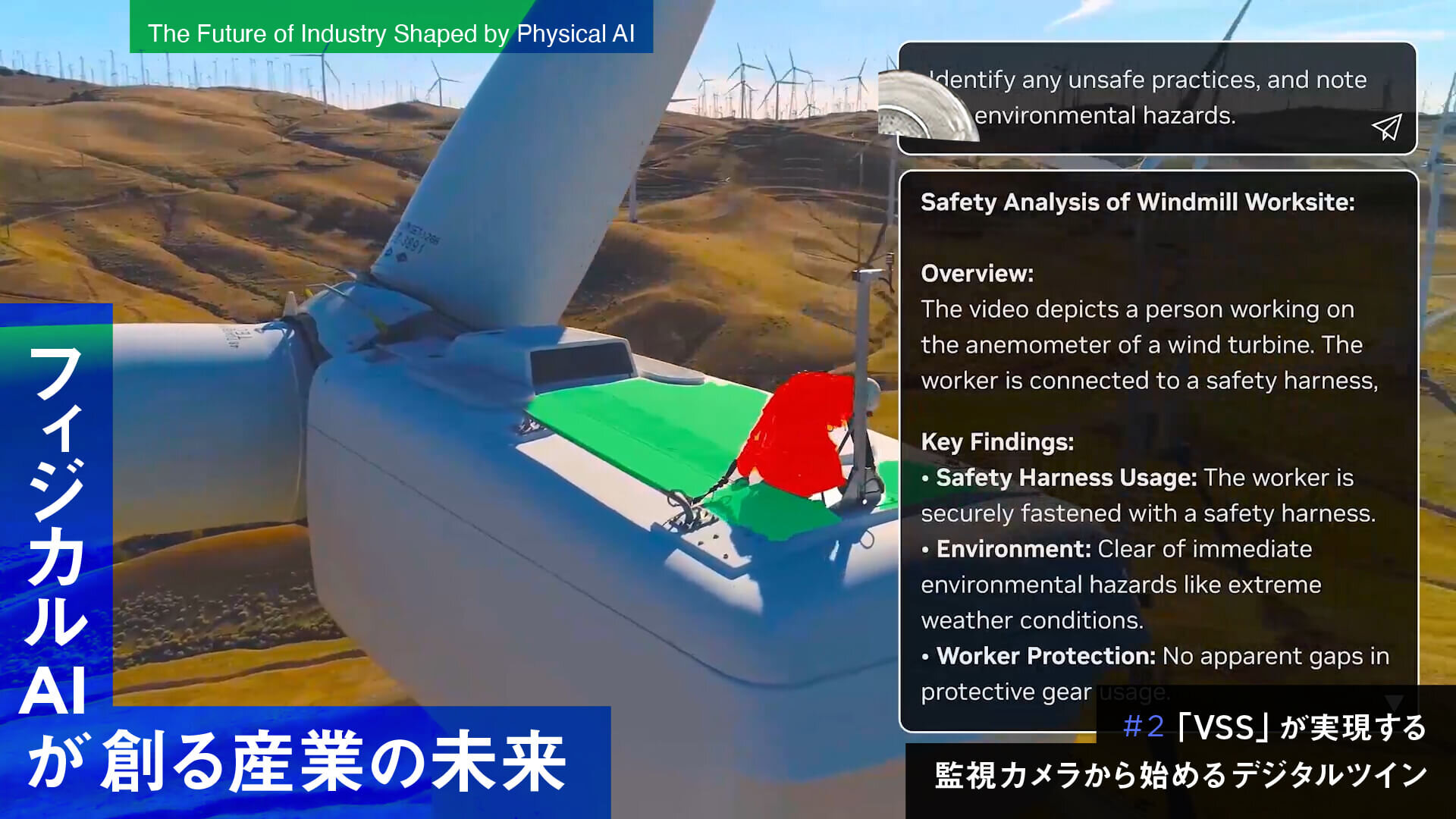ゲーム開発環境のオープン化や販路の整備によって切り開かれた、個人・小規模チームでゲームをつくって配信する「インディーゲーム開発者」という生き方。本連載は、日本でインディーゲーム開発者として活躍する人々を紹介し、どのようにしてゲームをつくり、どうしてインディーゲームという表現を選んだのかを聞くシリーズである。
今回は第5回として、和風ホラー『御祝呪』を手掛けるTENJO GAMESのプロデューサーさしみやま氏、作曲を手がけた柊キライ氏に話を聞いた。イラスト、映像制作で活躍するさしみやま氏がゲーム制作の中で感じた、ゲームと映像の違い、柊キライ氏のホラーゲームにおける楽曲制作におけるこだわりなど興味深い内容に迫っていく。
映像作家が挑む初のゲーム開発!開発期間はわずか3ヶ月
――最初に自己紹介をお願いします。
さしみやま氏(以下、さしみやま):さしみやまと申します。『御祝呪』ではプロデューサーを務めました。
柊キライ氏(以下、柊キライ):柊キライです。ティザーとオープニング作曲を担当しました。
―― これまでは、柊キライさんの楽曲のMVをさしみやまさんが制作するという関係性だったと思います。今回は、さしみやまさんが企画、そして初のゲーム開発。全く新しい挑戦だったと思いますが、柊キライさんは、本プロジェクトをどのように感じていましたか?
柊キライ:さしみやまさんからお声がけいただいた時、「がんばってるな、自分もまぜてくれ!」と思いましたね。 企画書をみた時、登場人物名の姓名判断まで設定してあってかなり細部までつくり込んでいると感じたからです。他の人が考えないようなことまで考えるのが、自分は割と好きなので純粋に面白そうだと思いましたね。
さしみやま:そういうところで気が合うんですよね。作品をつくり込むのが楽しくてつくってるまである(笑)。「神は細部に宿る」とも言いますし。
柊キライ:余談ですが、ユーザーさんが僕らが考えていないところまで考察していることもあるんですが、それに対し自分は肯定的に「考えるのは楽しいですよね」って共感します。
さしみやま:自分も作品を体験してくださるユーザさんには、ミスリードも含めて考察してくれることに、拾ってくれてありがとうございますっ!って思っています。
――今回なぜそもそも、これまでイラスト、映像制作をメインに活動されていたさしみやまさんがインディーゲームを開発されたのでしょうか?
さしみやま:私の身の周りで、だんだん祖父母が亡くなったりしていて、「もしかしたら、100年来の日本の古い家屋って、私の世代で見られなくなるんじゃないか」と思ったんです。 「若い世代の子たちは、こういった古民家を見ることができないんじゃないか」と思った時に、80年代・90年代の、私の原風景みたいなものを残しておきたいと思ったのがきっかけです。
そこから最初に思い浮かんだアートのイメージから連想したゲームを思いつき、社内でプレゼンをして開発メンバーを集めました。もともと『SIREN』や『SILENT HILL』『零』などの作品が大好きだったので当時のゲームへのラブレターの意味合いも込めてローポリ表現にしています。
――開発メンバーは何人ですか。また、ゲーム開発の経験はあったのでしょうか。
さしみやま:エンジニアが1人とデザイナーが2名、プロデューサーの私で4人です。足りない部分は私ができるだけ手を動かしたり、柊キライさんや原口沙輔さんなど手伝ってくださる方に声をかけました。デザイナー2名はエフェクト制作など経験がありましたが、私自身はゲーム開発の経験はありませんでした。
――開発の期間はどのくらいあったのでしょうか。
さしみやま:3ヶ月ですね。
――かなり短期間ですね! アセットはどのぐらい使用されましたか?
さしみやま:実は、アセットは使用していないんです。メンバーの1人がアセットを使うのは避けたいと言っていたので、じゃあ全部つくるかってことになって(笑)。通勤時間が往復4時間と長いので、その時間を制作に充てていました。
――ゲーム制作未経験で、開発期間3か月、アセットなし......! これはスピードが求められますね。
さしみやま:ゲームのつくり方がわからないところからのスタートでしたが、桜井政博さんの動画を見て学びながら制作を進めました。
普段映像制作を行う際は、頭の中で流れた映像からストーリーをを描き起こしてイラストにするシーンを抜き出しつくっていくのですが、今回は先にキービジュアルが浮かんでいたので、1週間で世界観とストーリーを固めてすぐに作業を開始しました。
――特に参考になった動画はありますか?
さしみやま:ほぼ毎日見ていたのでピックアップが難しいのですが、強いていうなら、チーム運営の動画が特に参考になりました!「思ったことはすぐに言え」の部分は特に今回の開発を完遂する上で役立ちました。
さしみやま:ちなみに、自分に喝を入れたい時はこれを見ていました(笑)。
「ゲームには違和感が必要」映像制作とゲーム開発の違い
――初のゲーム開発にも関わらず3ヶ月という短期間で完成に至った要因は何でしょう?
さしみやま:大きく3つあると思います。1つ目は、メンバー同士、意志共有を我慢しないように努めてくれたこと、2つ目は、出来る限り楽しい空間になるように互いに配慮を忘れなかったこと、3つ目はスケジュールを細かく設定し、毎週2時間ほどは打ち合わせをしコミュニケーションをとっていたことです。遅れたタスクがあっても、コミュニケーションを取り合い、助け合えていました。
――制作に使用したツールを教えてください。
さしみやま:開発メンバー全員がイチからゲームを開発するのは初めてで、同時に開発期間も短かったので、参考情報が多いUnityを選択しました。モデリングにはMayaを、質感の表現には、Substance Painterを使用しています。
――こだわった部分を教えてください。
さしみやま:モデリングを担当したデザイナーの作品の質感が以前から好きだったのでその質感を取り入れてもらいました。UnityとSubstancePainterの組み合わせで、テクスチャとライティング処理に工夫をして、個性的な質感を生み出しています。
また、短い制作期間の中でも、ベイクした光源とSubstancePainterで予め作った光沢や陰影の組み合わせによって、雰囲気を大切にしつつ負荷を抑えられる手法を探りながら制作してくれました。
ほかにもレトロな質感をpixel8rで取り入れたり、SubstanceDesignerで素材の敷き詰めやテクスチャを作り上げたりしている点も、モデラーのこだわりがあります。
――今回ゲーム開発を経験してみて、映像演出とゲーム演出にどんな違いがあると感じましたか?
さしみやま:映像は、時間軸が決まっていて、見ていたら終わりますから、基本的に受動的なコンテンツだと思います。しかし、ゲームはユーザーが動かなければ何も始まらない。ユーザーに「先に進みたい」「動かしたい」って思ってもらう仕掛けが必要なんです。
ミュージックビデオなどの映像演出を行う際は、ユーザーが違和感を持たないようにストーリーを構築する方が大事だと考えています。でも逆にゲームには違和感が必要なんです。ゲームの場合、その違和感を解いていく過程が面白いか?が基本的なユーザーの評価基準だと考えています。普段とは逆の考え方でつくっていたので、そういう意味でも今回の制作は面白かったですね。
――興味深い視点だと思います。「先に進みたい」と感じてもらうための仕掛けの例をお聞きかせください。
さしみやま:ホラーゲームに関して言えば、違和感と不快感のバランスかなと思っています。ゲーム内では、叔母の部屋の中心に遺影が落ちていたり、家の中にブルーシートが置いてあったりします。これは不自然にものを配置することで、ユーザーに「ここの住人と鉢合わせしたくないな…早く調べて出ていきたい…」と思ってもらえればと考え配置しています。

――違和感と不快感という観点で言えば、サウンドも重要な要素だと思います。
さしみやま:『SIREN』の曲を参考にしてもらったのですが、『SIREN』っぽさも踏襲しつつ、ちゃんと柊キライさんの曲になっていて感激しました。
ティーザーの音楽については、薄味と濃い味のバランスが欲しいと考えていました。ミュージックビデオで言うところの序盤とサビのようなイメージで、演出の抑揚を大切にしたいと考えていました。見る人の感覚を考えると、ティーザー音楽や映像が進むにつれて、徐々に味や匂いが強くなっていくような構成が良いのではないかなと。
そんな概念的な話をお伝えしたら、すぐに理解してくださり、理想的な作品をつくり上げてくださいました。本当にさすがだなと思いました!
柊キライ:ホラーゲームなので、普段の歌が乗っている音は使えないと思い、全て違う音でつくりました。
――特にどんな点を工夫したのでしょうか?
柊キライ:導入のピアノのメロディの後で鳴るピチカートを工夫しました。弦を弾いた音が聴こえると人間はその後の余韻を想像してしまうのですが、その余韻を波形編集で切り、音を完全に消しています。こうすることで、ユーザーの予想を裏切ることができます。予想が裏切られると人間はびっくりすると思うのでホラーにぴったりではないか?と思い試みました。
その後で鳴っているノイジーなパートも、ビットクラッシャーというディストーション系のエフェクトを使い、アナログの音をデジタルに落とし込む際のエラー音を意図的に起こしています。ノイズの強弱や質感の表情は丁寧に調節してイチからつくっていきました。音ひとつひとつ、消えている部分まで意図をもって制作しています。
――先ほどのピチカートなどの演出アイデアは、どのように発想したのでしょうか?
柊キライ:ノイズ部分のビットクラッシャーによる演出は、ビットクラッシャーの特性を知っていたので、今作のコンセプトを聞いた時、応用できると考えました。ピチカートの演出は楽曲制作の過程で本能的に感じていたことだったので導入してみたという感じですね。
ちなみに、びっくりさせるということを目的にした場合、一番想起されやすいのは、音量をあげる演出だと思います。しかし、これは録音芸術ではご法度なんです。流れてきた広告の音が大きいと驚きよりも、不快感を覚えた経験は皆さんにもあるのではないでしょうか?なので、音量の変化による演出は避け、音の質感による演出にこだわりました。
――本編のサウンドについてはいかがでしょうか?
柊キライ:最終的に3曲制作したのですが、共通の音色、旋律で構成しています。基本的な旋律、音色は固定し、音の高さやエフェクトなどの演出で抑揚をつけました。
さしみやま:印象は変えつつも、同じ空気感の音楽で構成したいという気持ちが強かったので、「ああ、もうこれこれこれ!」みたいな感じでした(笑)。私は詳しい音楽知識がないので、いつも匂いや世界観をお伝えするんですが、抽象的で少ない情報から素晴らしいものを即座に出してくださるので、本当に天才だと思っています。
――最後になりますが、これからインディーゲームを開発したいと考えている人にメッセージをお願いします。
さしみやま:技術面で難しいこと、不得意なことがあったら同志を募って一緒につくっちゃえー!です!
――ありがとうございました。