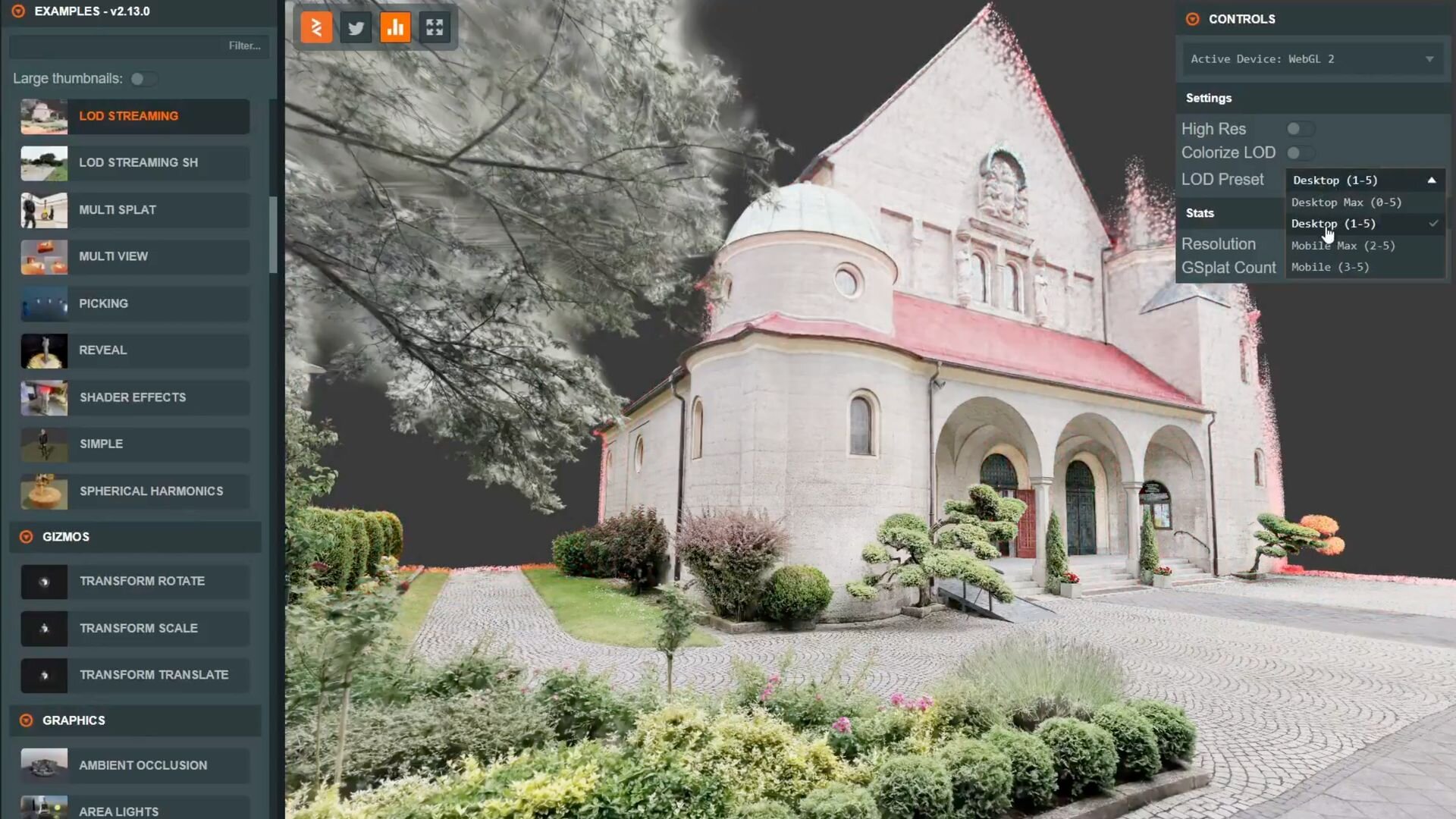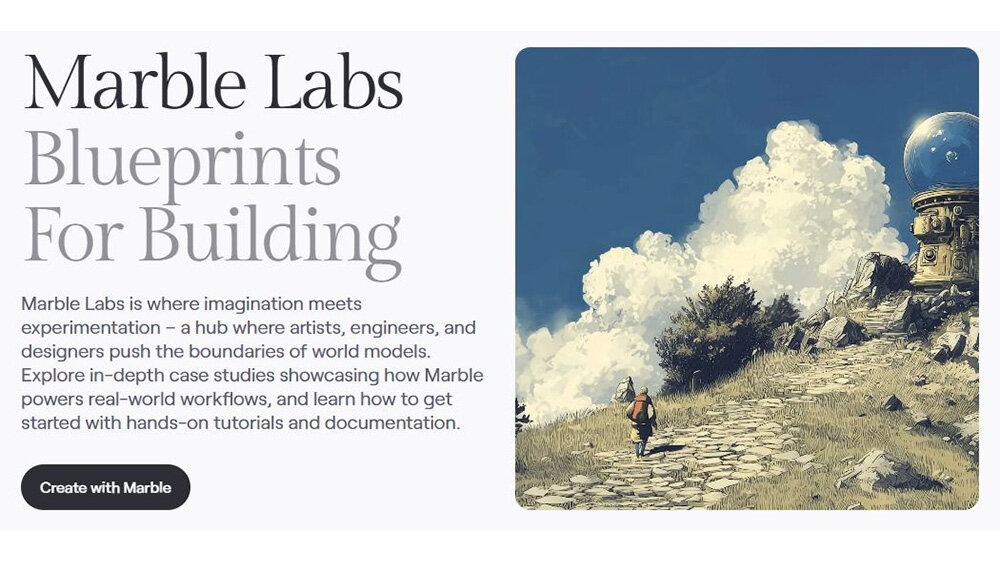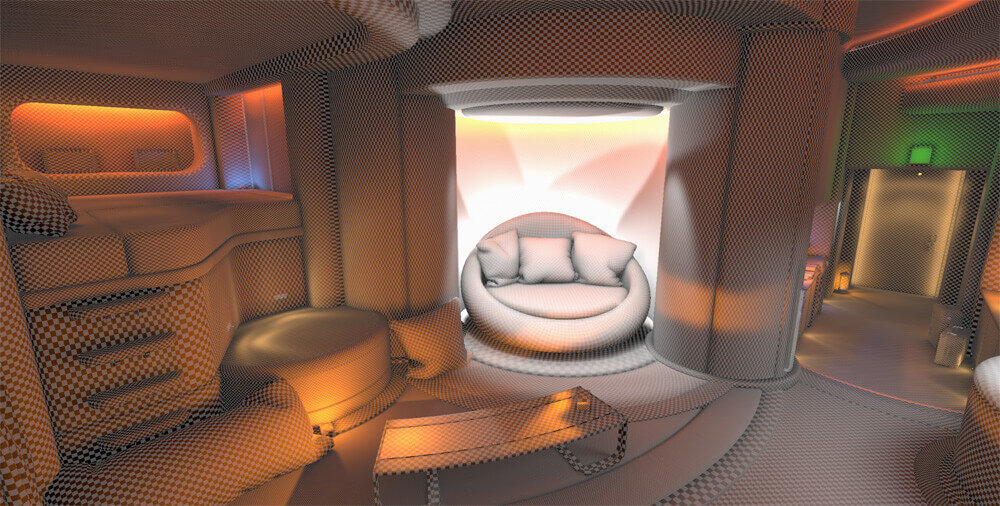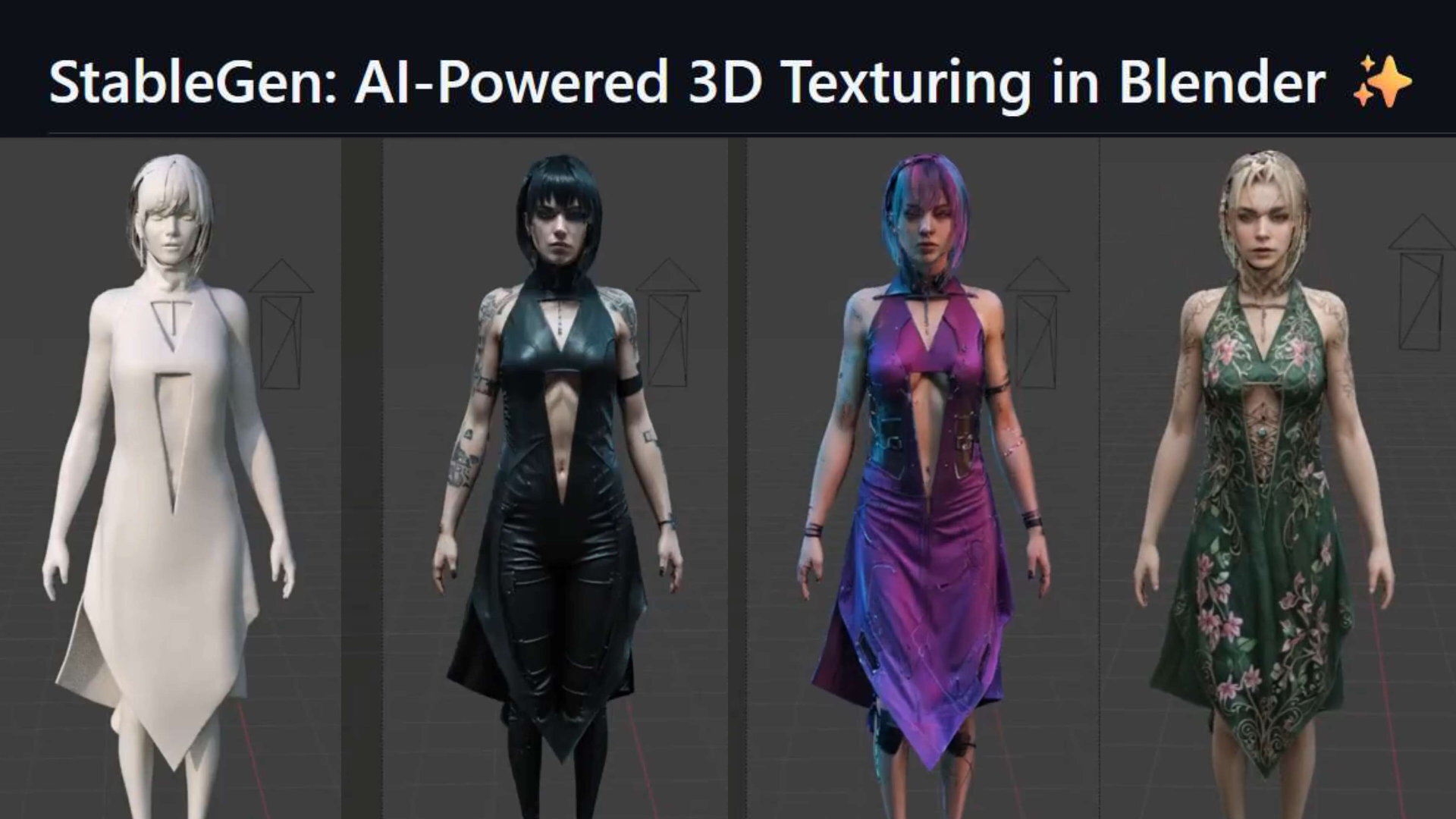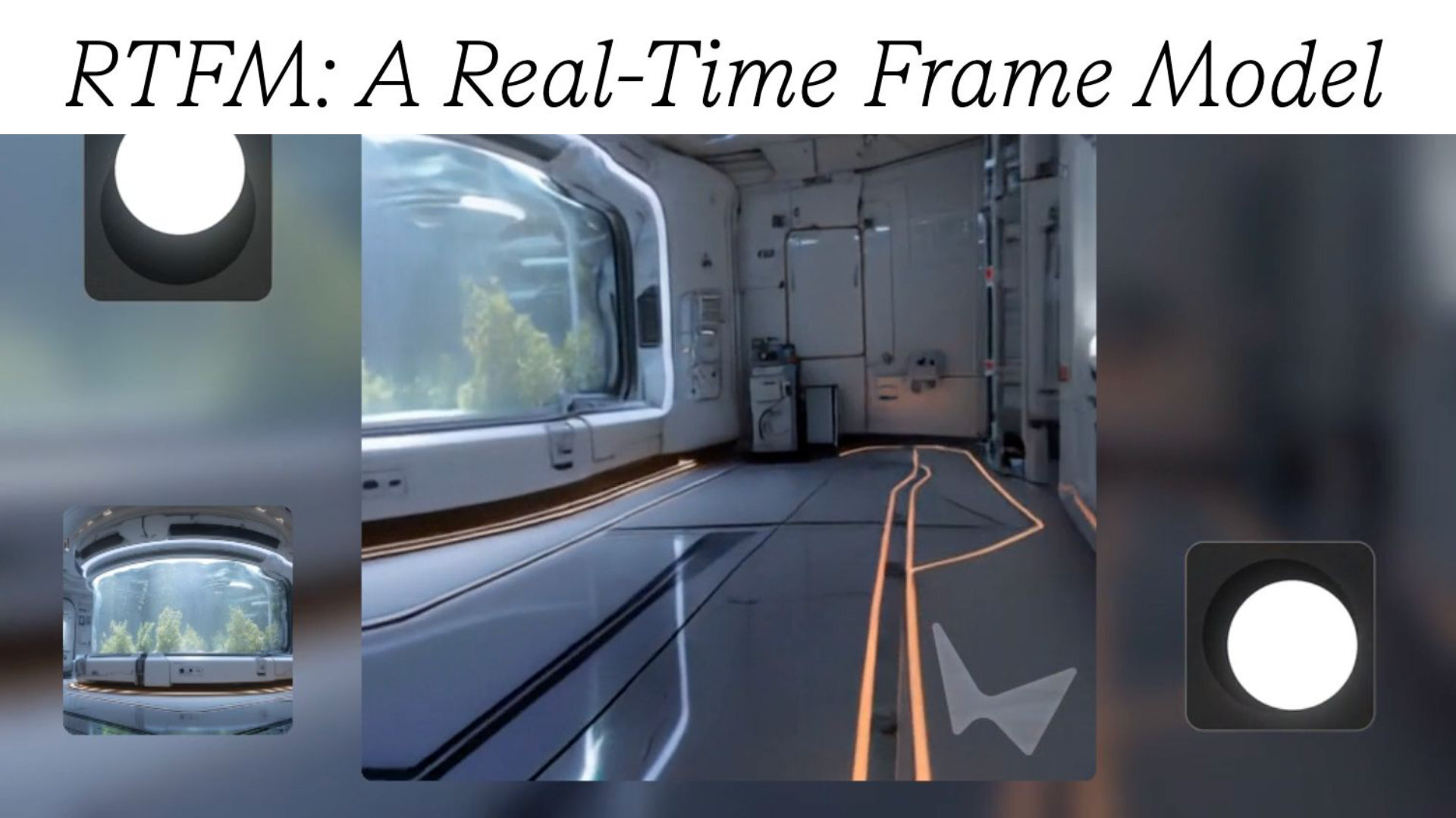「第1回 CGWORLDノベルズコンテスト」では、受賞候補2作品を選出し、CGWORLD.jpにて各作品を全12回にわたって掲載いたします。その後読者投票により各賞を決定し、それぞれ書籍として刊行する予定です。
「CGWORLDノベルズコンテスト」概要
第1回 CGWORLDノベルズコンテスト

■今後の予定
12月8日(金)〜:CGWORLD 305号とCGWORLD.jpで掲載と読者投票スタート
2024年3月頃:書籍時の扉絵イラスト募集
2024年6月頃:読者投票&扉絵イラスト結果発表
本文
一・蒼い狼
狼は、空を眺めていた。視界いっぱいに広がる夜空、その暗闇の中で宝石のように輝く星々の中に、彼女の行きたい場所がある。狼が狼として地を蹴り、空に吠え、己として生きることができる星……。
川浜市は、地球と衛星軌道上にある“ターミナル”とを結ぶ小さな宇宙港を中心に発展した、郊外の港町だ。宇宙に送る物資を製造するための工場エリアや、そこで働く人々と、その家族が住む住居エリアが大半を占めている。中には、定期的にターミナルに常駐して働き、物流の管理や、停泊する宇宙船の整備といった仕事に従事している者もいる。そんな住民たちにとって、宇宙とは比較的身近な存在だ。
一般的に、宇宙空間が身近なものだったとしても、その限りなく広大な闇に比して自分の存在があまりに小さいことに落胆する人間は少ない。そんな途方もないことを考えても仕方ないと、だいたいの人間は考えるし、誰もが明日や来週の予定をこなすのに精一杯なのだ。
だが、市内の橋の上から夜空を見上げる杉崎純一は違った。彼は、この橋から見上げる雲一つない星空が好きだった。少し前までの彼にとって、見上げる夜空は希望に満ちた大海だったのに、今の彼には、夜空が何もかもを飲み込むどす黒い塊のように見えていた。
抱いていた夢が宇宙の果てで霧散してしまって以来、彼はずっとそんな気持ちを抱えて生きている。
「純一、しばらく会えなくなるけど、通信状況がいいときはすぐに連絡するよ」
「体調には気を付けてね。何かあったら叔父さんたちを頼って」
一年前、再会を約束して両親は宇宙へと向かって行き……その半年後に消滅した。
人類は、地球外の生存可能領域―ハビタブルゾーンに新天地となり得る惑星を発見した。その後、国際宇宙局(International Space Committee)―通称ISC―は、幾度の戦火や環境汚染によって限界が訪れつつある地球から脱出するために、試験的に人口の一部を新惑星へ移住させる”ウィア計画”を考案した。一年前、その第一波調査隊として、多彩な人々と物資を搭載したアルゴー級調査船を向かわせることとなった。
だが、その旅の途上で、調査船は動力炉の爆発事故を起こし、乗員諸共閃光となって消滅した。ウィア計画に多額の出資を行っていた会社の一つ、クアドロ・ダイナミクス社に所属していた純一の両親は、新惑星の開拓に従事するため、その調査船に乗り込んでいたのだ。
多くの人々と物資を一度に失った事件を受けて、世論は宇宙開拓に対して消極的になり、現在ではウィア計画自体の凍結が、ISCから公式に発表されている。
「将来は、宇宙に出た両親の元に行き、人類の新しい故郷を作ります!」
大人たちから将来の夢を聞かれ、そう答えるたびに、純一の心は高揚感と自信でいっぱいになったものだが、今では思い出したくもない。
“宇宙に行って何者かになる”と、そう確信していた純一は、一年の浪人を経て大学への進学こそ決まっていたものの、その道が絶たれ失意の底にあった。
「大学を出ていれば、就職先の選択肢はいくらでもある。絶対に無駄にはならない」
現在の純一の保護者である叔父と叔母は口を揃えてそう言ったが、純一にとって、地球で職に就いて無難に定年退職を迎える平穏な……ある意味では退屈な人生など、考えられないものだった。
夜空を眺めていると、空にゆっくりと光の筋が描かれていくのが見えた。宇宙港から、軌道上のターミナルへと定期便が出発したのだ。
それを見た純一がため息をついたとき、彼の手の甲が光る。その表面には【着信・二宮鴻大】と表示されている。純一の手に埋め込まれたインプラントに、連絡が入ったのだ。
「二宮……」
その名前にうっすら見覚えがあった純一は、手の甲を軽く叩き、通話を許可する。
「はい。杉崎です」
「二宮だ。ご両親とはクアドロで一緒に働いていた。……覚えているかい?」
しばしの沈黙が接続されたインプラント越しに流れた後、ようやく純一の頭の中に、葬儀に参列していた中年の男性の姿がうっすらと浮かび上がる。
「ああ! あのときはどうも」
半年前の純一は両親の死を受け入れるのに精一杯で、人の顔を覚えている余裕はなかった。
「それで、どんなご用件でしょうか?」
「今、川浜市に来ているんだ。週末にちょっと会わないか? 君に見せたいものがあってね」
「わかりました」
そう言って、純一は二宮と週末に会う約束をし、通話を切った。何を見せてもらうかも聞かずに切ってしまったが、それは空虚な日常に、少しでも新しい刺激を求めていたからでもある。そして何より、
「会社の研究者に、おもしろい人がいたんだ。頑固だが、悪い男じゃない」
と、昔父が言っていたのを思い出したからだ。その“おもしろい人”が二宮とは限らない。だが、なんとなく純一にはそんな気がしていた。
週末、市内の喫茶店で純一と二宮は向かい合っていた。純一から見た彼は記憶よりもやつれており、その頬から顎にかけて、手入れされていない無精髭が生えている。だが、その目には確かな輝きがあった。
「高校の卒業が近いと生前のお父さんからは聞いていたが、進路はどうしたんだ?」
年長者はいつも挨拶代わりに進路の話をするな、と純一は思った。
「一年遅れになりましたが、大学への進学が決まっています。テラフォーミングについて学ぼうかと思っていて……」
「ほう、そうか」
「でも、意味がないかもしれません」
「なぜ?」
二宮は眉間にしわを寄せる。
「宇宙にはもう行けませんから。両親も、計画も消えてしまって……」
二宮はゆっくりとうなずき、黙った。店には他の席の談笑の声だけが響いている。
しばらくして、二宮が沈黙を破った。
「今日は、君に見せたいものがあって連絡をしたんだ。私もつい最近までは、君と同じく進路に迷っていてね。というのも、ウィア計画の凍結を受けて、クアドロが私の所属する部署を切り捨てることになった。だが、新たな仕事が見つかってね」
二宮はテーブルから身を乗り出すと、純一に小声でささやいた。
「まだ公式には発表されていないが、ISCの中で、ウィア計画は立ち消えになってはいない。水面下だが、既に第二波の調査隊を送り込む準備が行われている」
「それって……!」
純一は、気付けば立ち上がり、座っていた椅子が大きな音を立てた。
「とりあえず、座ってくれ」
二宮は周囲を見た後、再び小声で話を再開する。
「私の部署もそれに際してISCに買い取られ、研究予算が出ることになった。今、郊外でそのための施設を建設中なんだ」
「どんな研究を?」
「君のご両親は地質学を学んでいて、新惑星を見つけた後は、専用の機材で惑星の土壌や大気などの環境を人間にとって最適なものに変質させる……いわゆるテラフォーミングを行う技術を持つ所員だった。それは知っているかい?」
純一はうなずく。
「はい。以前から両親の仕事については聞いていましたし、だから僕も同じ進路を希望していたんです」
「私の研究も、本質的にはそれに近い」
二宮はカップを揺らしながら、そう言った。露骨にもったいぶり始めたため、純一は少々じれったさを覚える。
「で、どんな研究ですか?」
「……人間を変異させる研究。私たちは"コクーン・プロジェクト"と呼んでいるがね」
純一は口を開け、返事に困った。突拍子もない話だ。
「人間を……?」
「そう。惑星を開拓するには、過酷な環境での作業も想定されるだろう? その際、通常はドローンや作業用のパワーアシストスーツといった機材に頼るわけだが、私の発想は違う。過酷な環境に対応した姿に、人間そのものを変えるんだ」
目的はわかるが、どのような過程を経て、どのような結果をもたらすのか、純一には想像がつかなかった。二宮はそんな彼の様子を見て、強くうなずく。
「で、そのデモンストレーションが、一か月後にあるんだ。もしよければ見学に来ないか? というのも、ご両親の葬儀のときのショックを受けた君の様子が気になっていてね。何か将来を考えるきっかけになればいいと思ったんだ」
聞いただけでは信じられない、嘘のような話だ。のこのこと見学に行ったら、空っぽの部屋で二宮の妄想を夜まで聞かされるだけかもしれない。
しかし事実だとすれば、今の空虚な日々よりは、“何か”をもたらしてくれる予感がした。
「わかりました。行かせてください」
「じゃあ、来月の五日にこの住所の場所に来てくれ」
二宮が自分の手の甲を軽く指で撫でると、純一に研究所の所在地が送信された。
純一は灰色だった日々の風景に、少しだけ色が付いた気がした。
約束の日、純一は川浜市の郊外を訪れていた。このあたりは自然保護区域となっており、昔から存在する住居が点々とある以外は、木々の生い茂る森と山ばかりの土地だ。少し離れた所には大型商業施設があり、純一も、かつて両親と共に訪れたことがある。
その一角に、塀に囲まれた建物が建っている。純一はどこから入っていいのか迷い、塀に沿って歩き回った末にやっと、大型引戸門扉へと辿り着いた。
「警備の人間には言ってあるから、入ってくれていい」
インプラントから二宮に到着した旨を伝えると、そんな言葉が返ってきた。その言葉通り、純一が開いたままの扉から施設内に入っても、グレーの服に身を包んだ警備の人間は何も言わない。
恐る恐る施設内に入った純一を迎えたのは、硬質な床材が輝きを放つロビーだ。
「おはようございます。杉崎様ですね」
純一の顔を見た受付の女性は、インプラントを操作し、純一の情報を確認している。
「こちらになります」
と、女性が言うと同時に、ロビー奥の入場ゲートから警備員が現れた。
「ようこそ“ケージ”に」
ケージというのがこの施設の名前らしい。警備員は無言のまま施設の中へと進んでいく。あまりの会話のなさに不安を覚えつつ、純一は警備員の男性に付いて行った。
外にいた警備員とこの男性が共通して腰から下げている銃は、純一も見たことがある。以前、彼は両親に付いて行ってクアドロ・ダイナミクス社を訪れたことがあった。そのとき警備員が持っていたものも、今日目にしたものと同じ、電極を発射する非殺傷型のテーザー銃だったからだ。所持には届け出が必要な高出力タイプで、その装備こそ、先日の二宮の話がただの妄想ではないことを物語っていた。
「こちらです」
ロビーから廊下まで真っ白な施設の中を歩き、純一が通されたのは、吹き抜け構造になっている施設の中心にある、緑が広がる中庭を見下ろせる部屋だ。
さまざまな計測機器を所員と思われる人間たちが操作しており、巨大な窓の上下左右にあるモニターには、中庭の各ポイントに設置されたカメラからの映像が表示されている。
壁際には、ISCや関係各社の人間たちだろうか。スーツを着た人々が窓辺に立ち、実験の開始を待ちつつ下を見下ろしていた。
「すごい……」
と、思わず純一が呟いたとき、
「そうだろう?」
と声が聞こえた。二宮だ。
「よく来てくれた。今日見るものは、きっと君も驚くと思う。―ここから、未来が始まるんだ」
大勢の客を迎えているからだろう。先日の喫茶店で会ったときとは違い、二宮の顔からは無精髭も消え、髪もしっかりと……というよりは、塗りすぎた整髪料が過剰に光沢を放つほど、整えてあった。
「テストの準備、完了しました」
ややギョロッとした目の男性所員が近付いて来てそう言うと、二宮は無言でうなずいた。
「純一くん、こっちに」
二宮は純一を窓の方に連れて行き、指を差す。その先には、人間一人が入るくらいの大きなカプセルが設置され、数人の所員が周囲で作業しているのが見えた。カプセルは楕円体で、表面には透明素材のハッチがはめ込まれていた。大量のケーブルが接続されているそのカプセルは、どのケーブルがどんな機能を果たしているかもわからない純一にとって、どこかグロテスクに感じられた。
「あれはなんですか?」
「人間の肉体を変換する装置、コクーンだ」
「なる……ほど」
瞬きしている純一の顔がよほどおかしかったのだろう。二宮は笑った。
「まあ、見ればわかるさ。ここにいてくれ」
スーツ姿の人間に囲まれ、ラフな格好で来たことに後悔しながらも、純一はその言葉に従った。
二宮は所員たちの前に立ち、真剣な表情を作ると、手を二回叩き、
「よし、テスト開始だ!」
と、所員たちに号令を出した。中庭を見下ろすと、白い服に身を包んだ三人の人物がやってきたのが見える。一人は長身の女性で、もう一人は少し小柄で痩せた男性、そしてもう一人は、青白い髪をし、長い手袋をはめた少女だ。それぞれカプセルへと歩み寄っていく。
「あの三人が被検体か」
「そうみたいですね」
隣で話す男たちのそんな会話が、純一にも聞こえてきた。
二人の男女が、こちらを見上げ、純一と一瞬目が合う。何かを話している様子だが、内容は聞こえない。
「インプラントの動作、問題ありません」
「よし、入らせろ」
ギョロ目の所員に、二宮が指示を飛ばす。
おそらく、インプラント越しに管制室の状況が伝えられているのだろう。コクーンの横に立つ所員が指示をし、まずは一人目、長身の女性が入っていくのが見えた。
「健康状態に変化はないな?」
「問題ありません。バイタルも脳波も、正常です」
「よし、動作チェックの後、ノウム・シーケンスに入れ」
続きは毎週月・木曜に順次公開予定です!(祝日及び年末年始を除く)
日程は公開リストよりご確認ください。
『美術商ローラと家路を急ぐ青年』はこちらに掲載しています。
読者投票
読者投票は以下からご参加ください。ぜひお気に入りの作品に投票をお願いします!
読者投票はこちらから※締切:2024年1月25日(木)23:59まで
※回答は1人1回までとさせていただきます。