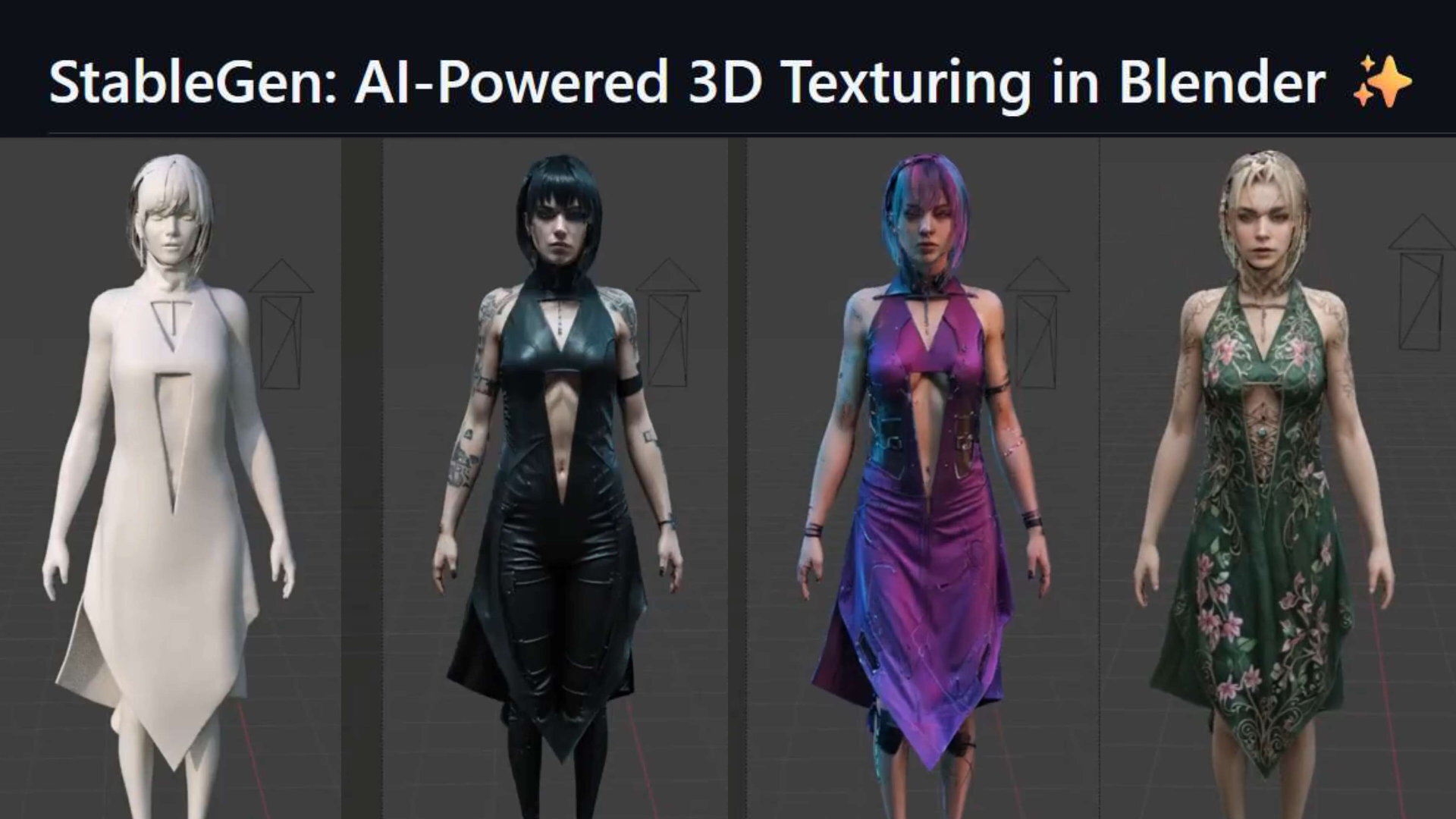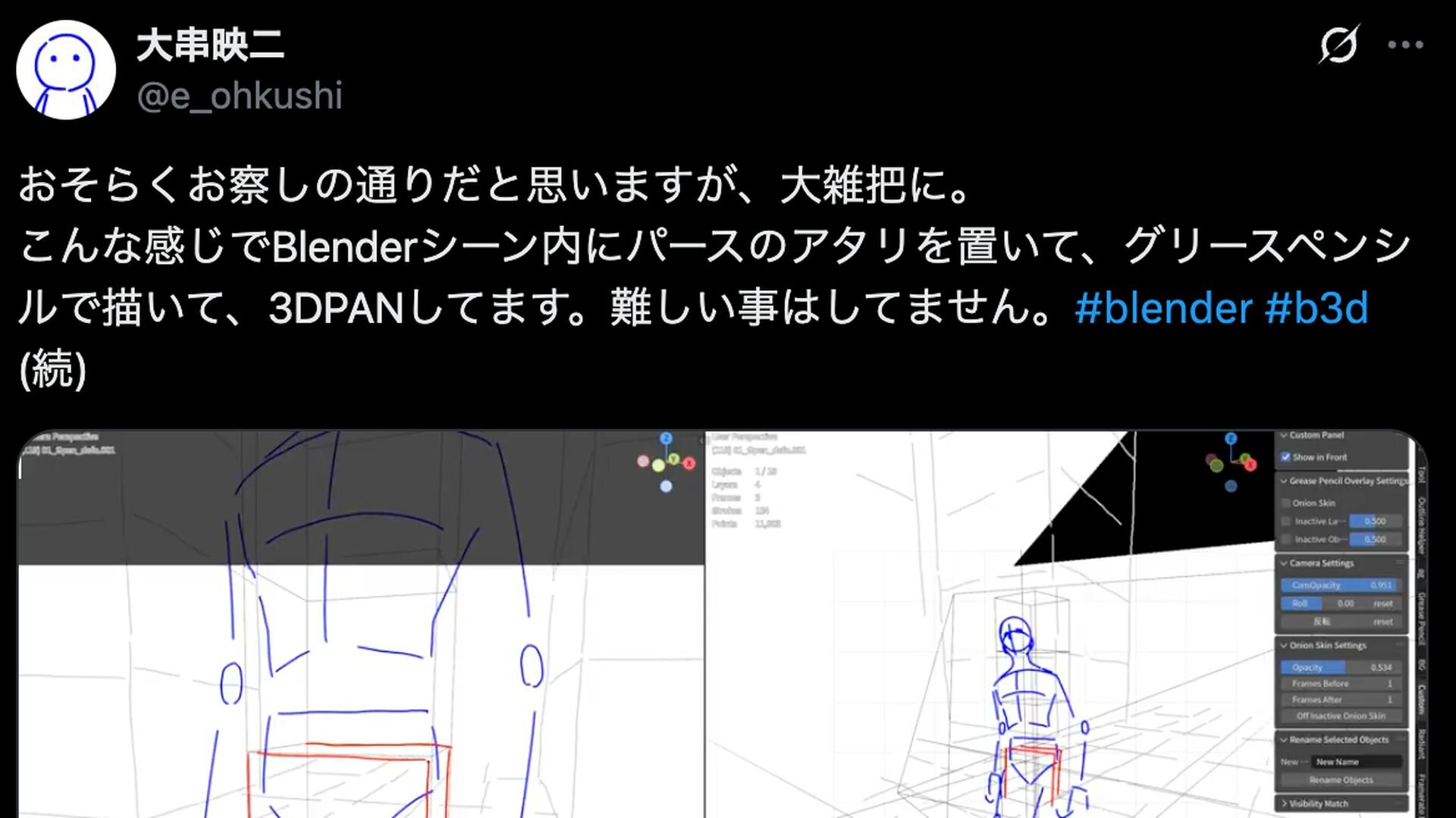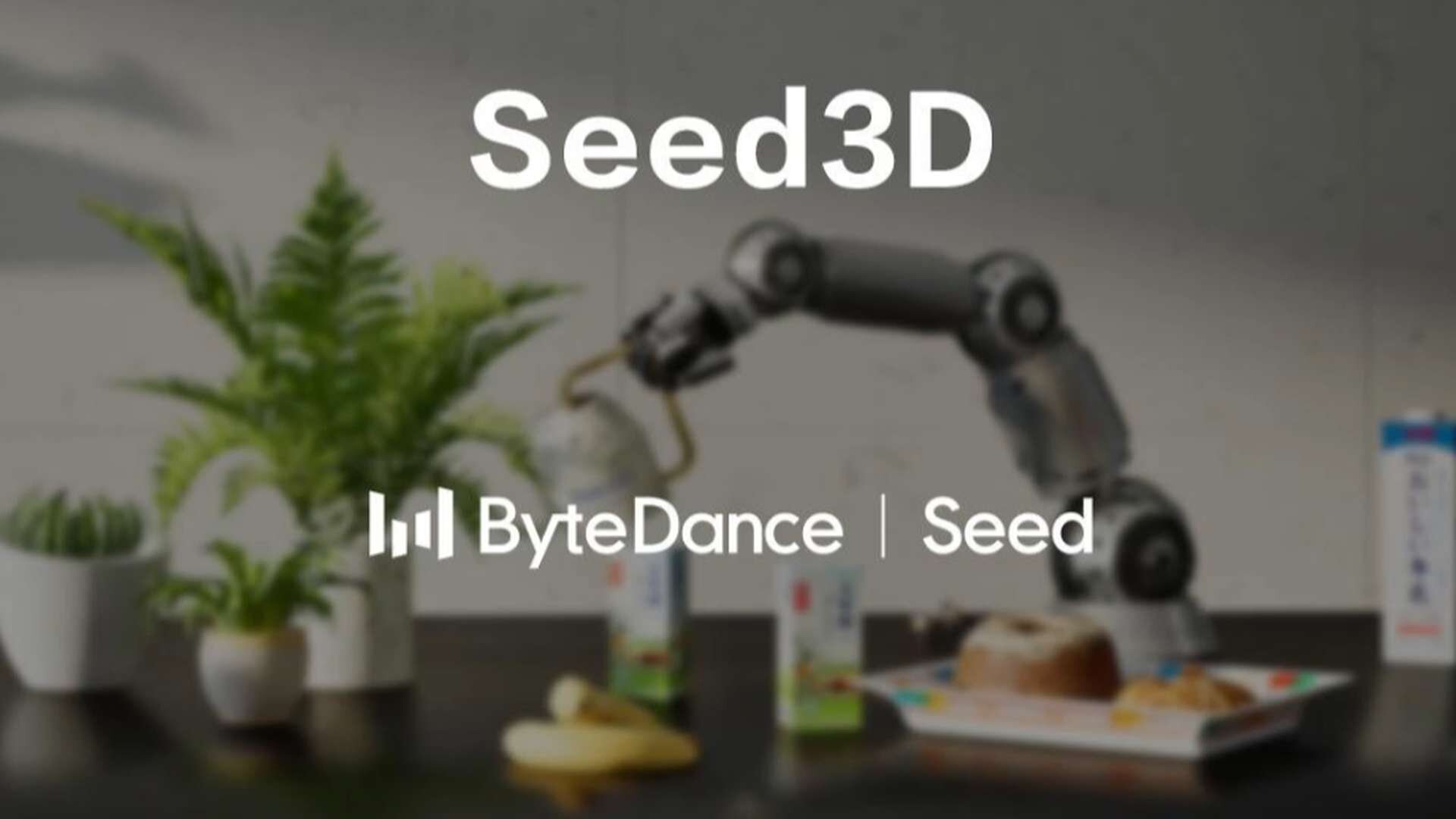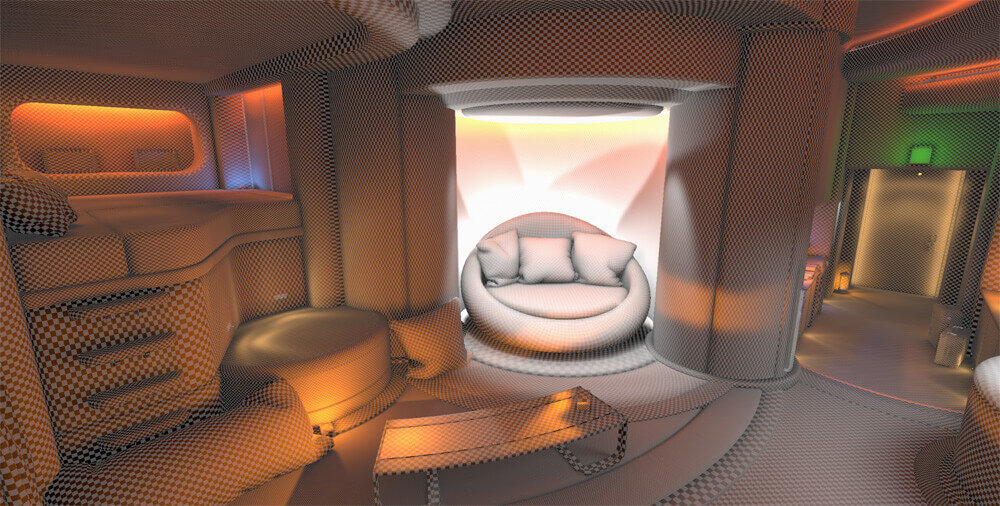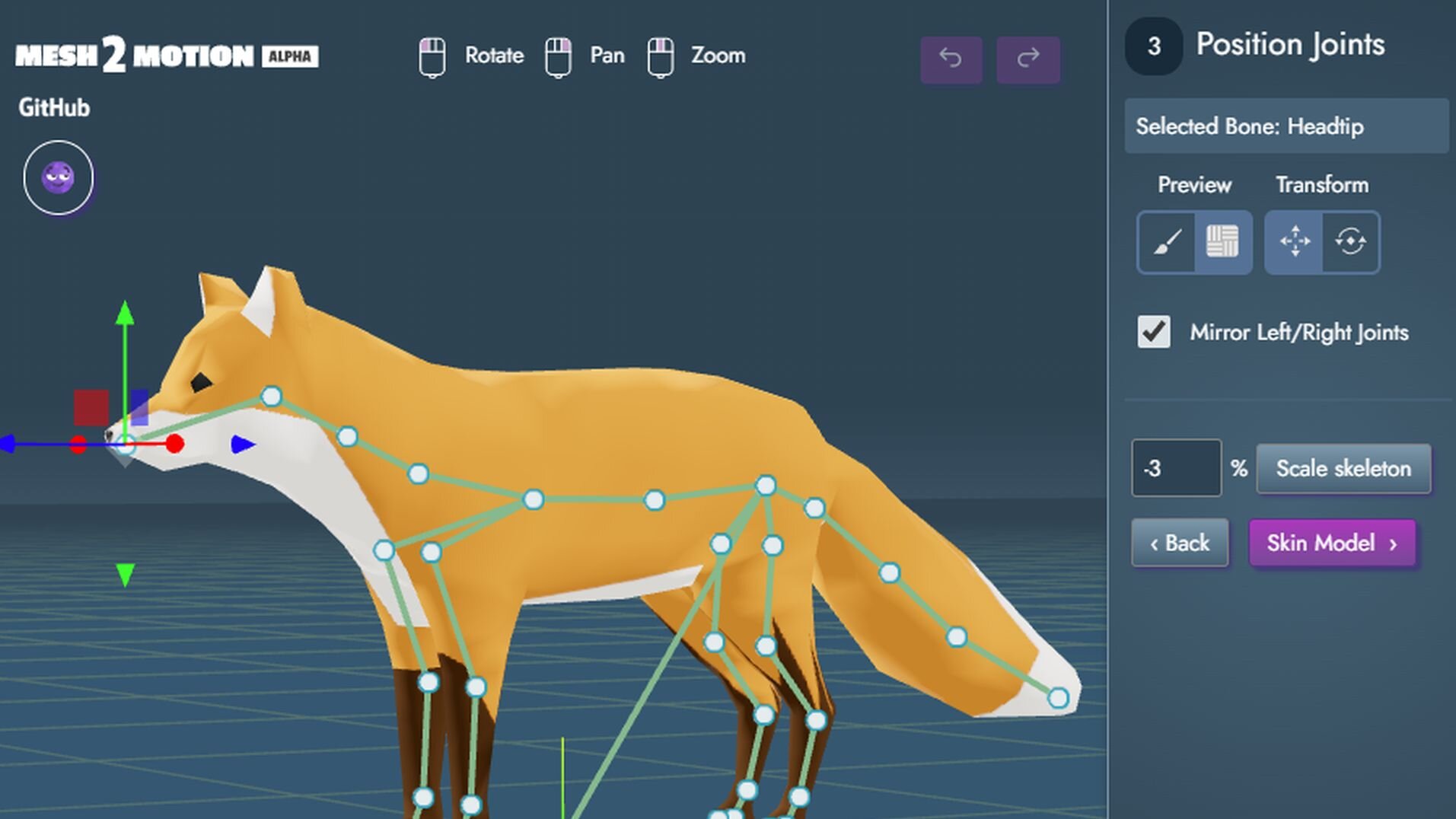「第1回 CGWORLDノベルズコンテスト」では、受賞候補2作品を選出し、CGWORLD.jpにて各作品を全12回にわたって掲載いたします。その後読者投票により各賞を決定し、それぞれ書籍として刊行する予定です。
「CGWORLDノベルズコンテスト」概要
第1回 CGWORLDノベルズコンテスト

■今後の予定
12月8日(金)〜:CGWORLD 305号とCGWORLD.jpで掲載と読者投票スタート
2024年3月頃:書籍時の扉絵イラスト募集
2024年6月頃:読者投票&扉絵イラスト結果発表
本文
長年住んでいるこの小屋には、もう何年も未完成のままの絵がある。絵の中では軽やかに裾をひるがえした少女がこちらを見ている。青い瞳の垂れ目、顔にはそばかすがあって、鼻は少し低い。淡い水彩で描いたその少女の髪──僕が今まで見てきた中で一番美しかったその髪だけは、一切の色が塗られていない。未完成の少女の絵を眺め一つ息をついた僕は、今日もその絵を物置の一番いい場所にしまい込んだ。
一
パサロの市場の賑やかさには、いつまでたっても慣れない。片手に朝絞めたばかりの鶏を五羽ほど下げて歩いていると、道ゆく人がこの町の人間かそうじゃないかすぐにわかる。ギョッとした顔で二度見していくのが外から来た人間、素通りあるいは「どこで卸すの?」と聞いてくるのが町の人間だ。ちなみにこの鶏は森から市場の出口(本来は入口なのだろう。森の方から歩いてくる僕にとっては出口だが)までをまっすぐ歩いて二十軒目の屋台に卸すものだ。まだ本格的な冬には早いけど、すでにその店からはトマトの匂いがする湯気が立ち上っていた。この店は基本的に大鍋いっぱいの煮込み料理で稼いでいるが、鶏を一枚にさばいて丸ごと揚げたものを軒に吊るしておくと、外から来た人間が釣れるらしい。客寄せ商品なので、別に売れなくてもかまわない。市場まで来て揚げ鶏一枚でお腹をいっぱいにする客というのも珍しいし、実際は夕方になって余っているものを市場の人間が買うことの方が多い。客を寄せるだけなら別のものでもいいわけだし、何も僕に頼まなくてもいいのではないかと思うことはある。けれどこれで絵具なんかを買えることを思えば、余計な口は出さず粛々と鶏を絞める方が得だ。
大鍋の真っ赤なスープがぽこぽこと音を立てているのを横目に見つつ、鶏を差し出す。
「来たか、ジル」
「いつものです」
「はいよ、代金はそこに置いてある。取っていきな」
相変わらず不用心な店だ。もっとも、髭面で縦にも横にもでかいこの男に喧嘩を売る人間なんてほとんどいないだろうが。
「ちょうどいい具合に煮えてきてるぞ、食うか?」
「……いえ、お腹空いてないので」
男は肩をすくめた。いつもこんな態度ばかり取っている僕に、よくもまあ狩猟の依頼なんてするものだ。もっともこれで絵具が買えるので以下略。男は器にスープを盛り付けると、自分で食べ始めた。味見も兼ねているらしいが、それにしては量が多い。髭に付いた赤い汁を拭いながら、男は「それにしてもよ」と言った。
「お前、こんだけ狩猟がうめえなら絵描きなんざやらなくても食ってけるだろう? そもそもあの森に出入りできるってだけでも市場じゃ重宝されるぞ」
「はは……」
男は時折思い出したかのようにこのセリフを繰り返す。この鶏五羽をどうやって獲ってきたか知ればそんなこと言えなくなるぞ、と思いつつ実際に口にしてしまうと大変面倒なことになるに違いないので、いつものように笑ってごまかした。
あの森、パサロの人間が「マレの森」と呼ぶその場所で僕は暮らしている。地元の住民によれば、マレの森には基本的に立ち入ることもできないのだという。マレの森に入って弾き出される経験は、この辺りに住む大人なら誰でもしている。子どもたちはちょっとした冒険、あるいは度胸試しの感覚で森へと勇んで入っていき、三十歩も進まないうちに、森の入口まで戻されてしまう。どの道をどのように進もうと、少し進めば森の入口へ戻される。子どもたちは冒険のあっけなさに拍子抜けし、それ以降森には立ち入らなくなるのだった。恐怖は人を寄せ付けるが、退屈は人を寄せ付けない。なかなかどうして、マレの森は人間を拒絶するのがうまい。
そんな森に僕がどうして入れるのかといえば、マレの森に歓迎されているからにほかならない──それはもう熱烈に、迷惑なほどに、だ。
市場は長く続いているが、僕は端の方まで行ったことがない。一度市場の中心と思わしきところまで行ったことがあるのだが、冒険中の子どもたちよろしく森の入口が目の前に現れたので諦めた。
「そういやお前、ここ来て結構経つよな。どれくらいだ?」
「さあ……三年くらい、じゃないですかね」
「もうそんな経ったのか? いっつも初対面みてえなツラしてよ!」
遠慮なくバシバシと背中を叩かれ、また曖昧に笑う。滞在期間を少なめに見積もってもなおこんなことを言われてしまう僕は、きっとこの町には一生馴染めないんだろう。男は自分の作ったスープを美味しそうに飲み干すと、外に向かって声を張り上げた。
「らっしゃい! トマトと鶏肉のスープだよ! 一杯たったの五リラン!」
客引きが始まったので、僕はとっとと男の店を後にした。商売の邪魔をするわけにもいかないし、これ以上返事のバリエーションもない。
森に一番近くて、店の中では一番小さいであろう場所に広げた布の上に座り込む。地面に置き、重りとしてその辺の石を載せていた二枚の完成画と、スケッチブック。それに筆と絵具。どれも盗まれた様子はない。
ここに来たばかりの頃は常に肌身離さず持っていたけれど、どうやらこの町で絵はたいして価値があるものでもないようだと気付いてからは、置きっぱなしにしている。朝、布を広げてキャンバスを立てかけ、頼まれものがある場合はそれを渡しに行き、あとはずっとこの布の上で絵を描き続ける。この五年、ずっとそんな生活をしていた。
ちなみに絵はほとんど売れない。別に売れても売れなくてもかまわなかった。この場所で描いているのは森だとなかなか都合が悪いからで、絵を売りたいわけじゃない。もちろん買うって人がいたら、それなりに交渉して売るけれど。
スケッチブックを開いて昨日の続きから始める。前に真っ黒な猫を描いたから、今は仲間を作ってやるために真っ白な猫を描いている。毛が長くて青い瞳を持つ気高く美しい猫。あの黒猫とは気が合うだろうか。猫を白くは塗れないから周りに影を作って囲ってやる。凛とたたずむ猫が浮かび上がるにつれて、自然と口角が上がった。
「ねーもうかえろーよ!」
筆が止まる。少女が駄々をこねていた。少女の母親らしき女は、斜向かいで売られているアクセサリーに夢中だ。少女はまだ装飾品に興味を持つ年齢でないのか、単に疲れているのか、ふてくされた顔で僕の方へやって来た。
「それ何?」
ぶっきらぼうな口調で背後を指差され、僕は振り返る。空っぽの鳥籠の絵だった。絶対に鳥を出さないと決めたような造りのそれは、しかしドアが開け放たれていた。肝心の鳥の姿はどこにもない。僕は筆で猫の耳に影を入れてやりながら答えた。
「本当は鳥を描いていたんだ。緑と薄青色で白い斑点がある鳥だよ。でもまあ、最後にくちばしを塗ったら逃げちゃったのさ」
「……それほんと?」
少女は目を丸くしている。視線は鳥籠に釘付けだ。あげちゃってもいいかな、とちらっと思った。どうせ絵では稼いでいないし、鳥もいない鳥籠の絵を欲しがる人も少ないし。純粋そうな少女からお金をふんだくろうと目論むほどおとなげなくもなかった。
「よかったらそれ──」
「こら、お店の邪魔しないの! もう帰るわよ」
母親が少女の腕を取って強引に引っ張った。少女は大人の歩幅に必死でついていこうとしながら、何度も僕の方を振り返った。母親は僕の方をいっさい見ない。さっき目が合ったときも不気味なものを見るように、目を思い切り逸らされた。その様子を見るに、まるっきり外の人間というわけでもなさそうだ。おおかたマレの森に出入りできる怪しげな人間だと思っているのだろう。実際そうだから何も言えないけれど。風貌はそこまで怪しくないはずだ、と自分に言い聞かせる。髪は定期的に切っているし、湖で体も洗っているし、困ったときは怒るのではなく笑ってどうにかやり過ごそうとしている。これほど無害な人間もなかなかいないと思うのだが、住んでいる場所で怪しい認定をされてしまったらもうどうしようもない。
「『もう帰るわよ』ねえ……」
帰りたい。ふと胸に浮かんだ思いを頭を振って誤魔化した。もう五年、たいして居心地の良くないこの場所にもう五年だ。さっき渡し損ねた鳥籠の絵を指で弾いてため息をつく。絵の中の鳥でさえ籠の中から出られているのに、僕はここからどこへも行けない。
「籠の鳥は逃げてしまったのですか」
不意に声が降ってきた。さっきの会話を聞いていたんだろうか。適当に話を合わせようと顔を上げる。少女とも少年とも言えない風貌の人間が、好奇心の強そうな瞳で僕の絵を見ていた。麻のレースアップシャツにパンツ、シンプルなのは服装だけでなく、顔もこれといった特徴がない。しかし少女の動きに合わせて揺れるその髪は、僕が今まで見てきた誰よりも美しかった。ブロンドの髪は高い位置で結ばれ、陽に透けてきらきら光る。僕が少女に見惚れている合間に、彼女は僕のスケッチブックを覗き込んでいた。
「こちらは猫ですか。いいですね、賢く気高い雰囲気があります。目を塗ったら動き出しそうだ」
「……出来上がったら持っていきますか?」
褒められれば悪い気はしない。少女はうなずいて「では出来上がるまでここで待っていましょう」と言った。
「困ります。どこかで適当に時間を潰しててください。今日出来上がるとも限らない」
「いえいえ、私ももう一歩も動ける気がしないのですよ。気配は消しますしお邪魔はいたしませんから。見てください、この荷物。もう一度背負うのは至難の業です」
少女が指差したところには大きなリュックがあった。少女の背中を覆ってもなお余るほどの大きさで、何が詰められているのかぱんぱんに膨らんでいる。僕は無言で少女の滞在を許し、スケッチブックに向き直った。毛並みを整えたばかりの猫は、瞳のない目でこちらをまっすぐに見つめている。気に入った箇所は一番最後に塗る。こだわりというほどでもないが、いつの間にかそういう風になっていた。だから猫に瞳が入るときは完成する直前だ。
「そうだ、この籠の中の鳥は今どちらにいるのですか?」
「……まさか本気でここの鳥が逃げたって思ってる?」
気付けば僕の隣にすっかりくつろいだ様子の少女がいた。リュックは地面に転がしたままで、少女は奔放に足を伸ばしている。ずいぶんと気配の薄い子だ。これなら確かに邪魔にはならないだろうけれど、少し気味が悪かった。少女は無邪気に僕が放った戯れの言葉を蒸し返してくる。皮肉混じりに答えてみたものの、少女は気に留めた様子もなかった。
「ええ。タイトルを付けるなら、『鳥のいた風景』といったところでしょうか。こっちも……」
少女は鳥籠の絵の隣のキャンバスを指差す。なんの変哲もない、森を描いただけの風景。ただ絵の中心に目が行く構図になっているため、何かがいて欲しいのにいないような、奇妙な不在感が際立っている。
「これも、真ん中に何かがいたんですよね。リスとか、ネズミとか、そういうものが。逃げてしまったのではないですか? 周囲を描き込むことで主役の不在感を演出しているような。これ、あなたの作風で?」
「違う」
僕は即座に否定する。思ったより声が苦々しくなってしまった。少女はこてりと首をかしげると、再び僕のスケッチブックに目を落とした。
「この猫も、瞳を塗ったら逃げてしまったりして──」
「邪魔はしないんじゃなかったの?」
僕はスケッチブックを手元に引き寄せると、少女から目を逸らした。妙な雰囲気のある少女だ。見た目はともかく、中身が幼いとは到底思えない。雑念を払って、筆を取って猫に向かう。耳や鼻の細かい場所を塗っていく。一匹ぽつんと立たせているのも可哀想だからと周りに花や草木を足していると、この間描いたキャンバスと同じような構図になってしまう。動物を描きたいのだから仕方ないじゃないか。それなのに動物は、僕のキャンバスに、スケッチブックに留まってくれた試しがない。
少女が聞いているかもわからないまま、独り言のように言葉を重ねた。
「完成すると実体化して何処かへ逃げていくんだ。また現れても、絵に戻ってくれることはない。僕は動物を主に描いているから、主役に逃げられちゃこんな半端な絵しか売れない。君も僕の絵が欲しいなら、この場で描き上げるまで待ってくれないか? ここなら動物が逃げ出さないから」
後半は少女に向けて話していたが、本気にしてもらえるとは思っていなかった。しかし少女は緩やかに弧を描いていた唇を引き結び「美しい」と言った。
「はい?」
「私は美しいものが好きです。完成した瞬間に鳥籠が開いて逃げていく鳥、どんな風に飛んでいくのでしょう。瞳を入れた瞬間に生を得た猫は、どこへ行くのでしょう。ぜひ見たい、見せてください!」
熱を持ったように語り出す少女に、僕の心はすごいスピードで後退を始めていた。ヤバいやつだと思われた方がどれだけマシだっただろう。興味を持たれた場合が一番困るのだ。なぜなら僕以外、マレの森には立ち入れない。そして描いた動物がするりと絵から抜け出し「最初からここにいましたよ」なんて態度でそこら辺を闊歩するのは、森の中だけだ。地元の住民やマレの森の噂を知っている人間なら、この話をするだけで立ち去る。でもこの少女は絶対にそんなタイプではないと、直感でわかる。
少女は立ち上がると埃を軽く払い、こほんと一つ咳払いをしてお辞儀をした。頭を下げた拍子に肩へ流れるブロンドは、やはり平凡な顔のつくりとミスマッチなほど綺麗だ。
「申し遅れました、私は美術商のローラと申します。あなたの作品をぜひ見せていただきたい。できれば、完成して彼らが放たれるまでの一部始終をすべて」
続きは毎週月・木曜に順次公開予定です!(祝日及び年末年始を除く)
日程は公開リストよりご確認ください。
『龍が泳ぐは星の海』はこちらに掲載しています。
読者投票
読者投票は以下からご参加ください。ぜひお気に入りの作品に投票をお願いします!
読者投票はこちらから※締切:2024年1月25日(木)23:59まで
※回答は1人1回までとさせていただきます。