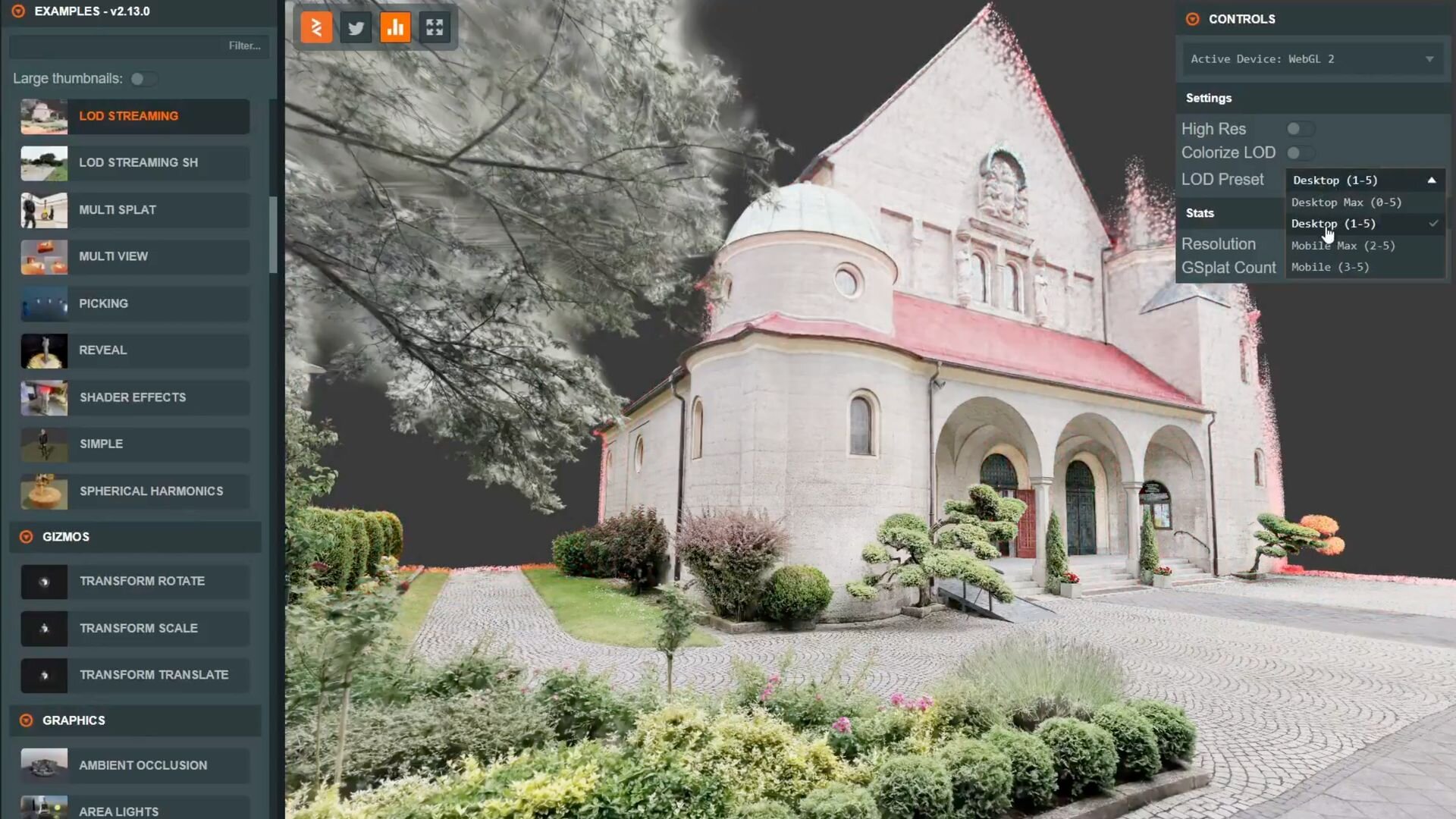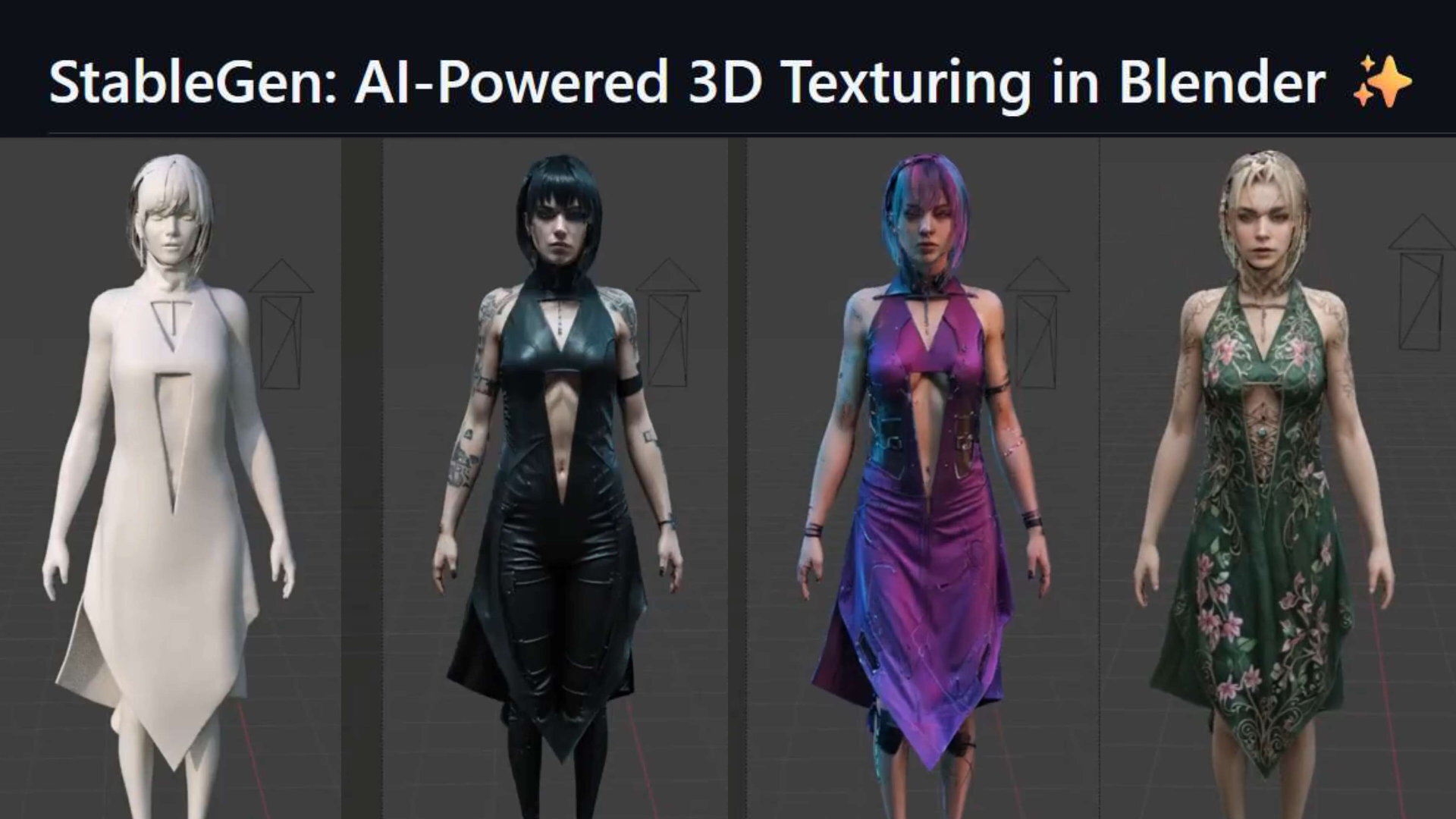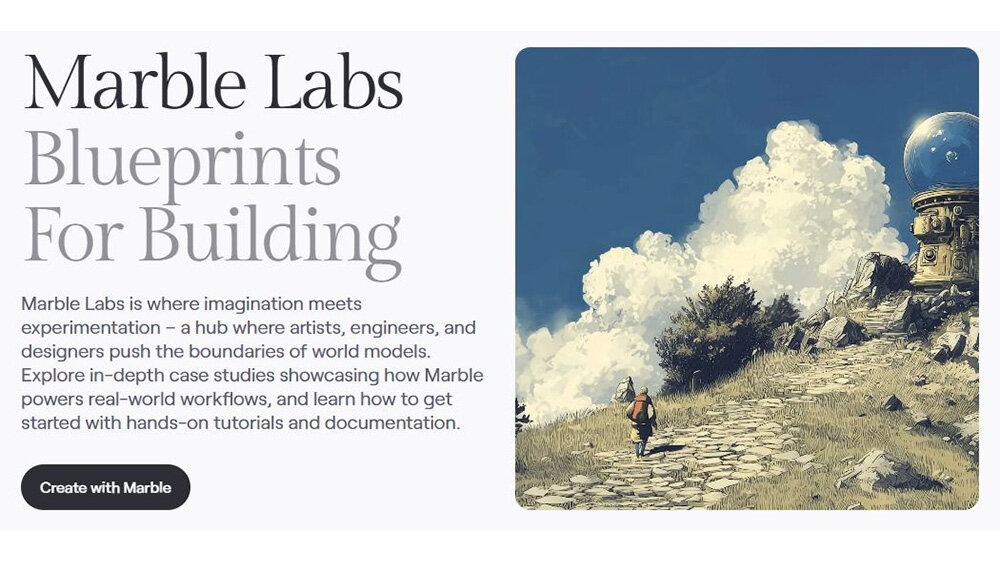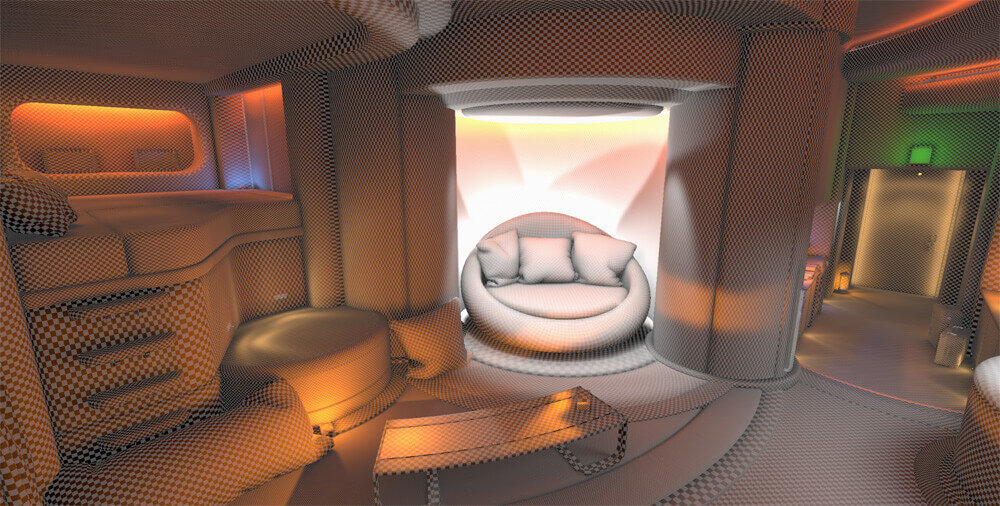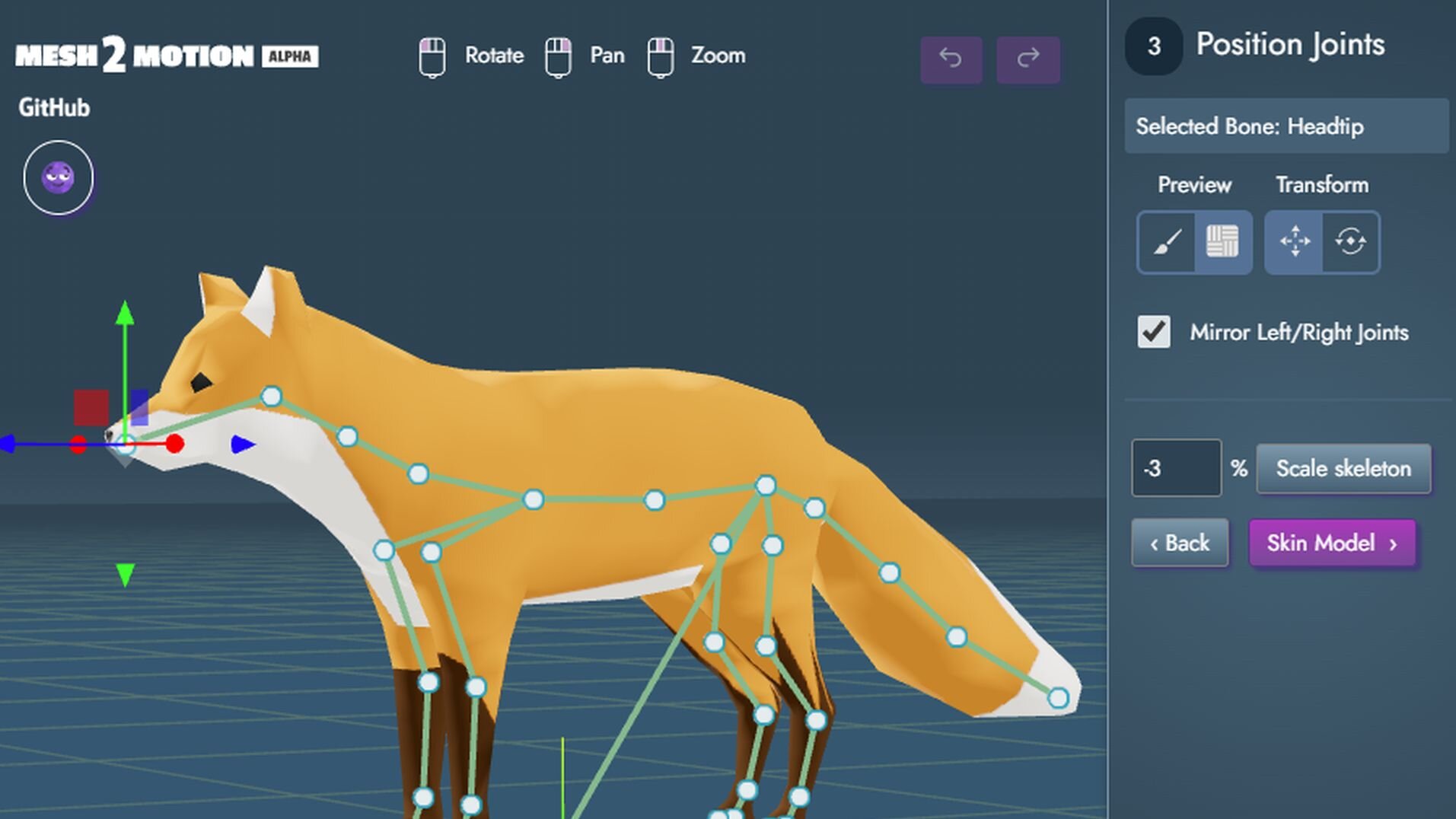「第1回 CGWORLDノベルズコンテスト」では、受賞候補2作品を選出し、CGWORLD.jpにて各作品を全12回にわたって掲載いたします。その後読者投票により各賞を決定し、それぞれ書籍として刊行する予定です。
「CGWORLDノベルズコンテスト」概要
第1回 CGWORLDノベルズコンテスト

■今後の予定
12月8日(金)〜:CGWORLD 305号とCGWORLD.jpで掲載と読者投票スタート
2024年3月頃:書籍時の扉絵イラスト募集
2024年6月頃:読者投票&扉絵イラスト結果発表
本文
三
「ふむふむ。タヌキは出る、龍は出ない、ゾウは小さいサイズなら出ると。でも人間は出せないんですね」
ローラはぶつぶつと呟きながら紙に書きつけている。絵はあれだけ壊滅的なのに、字は妙にうまい。出る、出ないのリストを見ていると、僕の想像力が足りないと言われているみたいだ。見たことのないものは描くのに筆が止まるし、絵にもなんだか生気がない。
「やはり森の主はジルさんの頭の中を頼りに絵を連れ出しているみたいですね。だからリラはジルさんの実家にいる猫とそっくりな性格になったんでしょう。反対に、見たことがないものはジルさんの中の解像度が低いから実体化しなかったり、してもなんだか違うものだったりするんでしょう」
なるほど、とうなずく。黒猫を描いたとき、僕はきっと無意識にリラのことを考えていた。それだけじゃない。ほかの動物が絵から抜け出すなり森の奥へ逃げていくのも、僕が毎度決して止まってくれない自然の動物を相手に絵を描いていた記憶があるからだろう。リスもウサギも逃げるもの、同じ場所に留まらないものだと認識していたから、あんなにも忙しなくいつも森の奥へ駆けていったのだ。似顔絵の人たちが出てこなかったのも、よく知らない人たちだったから。しかしそう考えると──
「え、もしかして家族の絵とか描いてたら出てきた……?」
「可能性はありますねえ」
顔から血の気が引いていく。もしかしたら絵から連れ出されてきた偽物の家族と、マレの森で暮らし続ける道があったのだ。きっとそれは、二割の幸せで八割の虚無感を上塗りするような生活。森の中で人物画は描かないと決めた過去の自分に、これほど感謝したことはなかった。
それにしても「知らないものは出せない」と言うのなら。
「龍を出すなんて一生かかっても無理じゃないか。僕は龍を見たことがないし、目の前に現れたときの想像すらできない」
「いいえ、逆ですよ、逆。頭にイメージを叩き込めさえすれば、なんだって描けるし実体化させられるんです。そういうわけなので、今日からみっちり龍について講義しますから、思いつくままにどーんどん描いちゃってください」
描いちゃってと言われても。僕はピクリとも動かなかった紙たちを見つめる。ここまで描き上げる間に冬は深さを増して、もう市場に行くのも難しくなってきた。春が来るまでの折り返し地点と言ってもいいくらいの時期だ。僕は描くのは遅い方ではなかったが、それは描き慣れたものしか描いていなかったからだ。見知らぬものを実在するように描くには、それなりに時間もかかるし紙も絵具も必要そうだった。
「絵具足りるかな……」
「私の手持ちも貸しますから。大丈夫ですよ」
ローラの「大丈夫」に根拠はなさそうだった。それでもその言葉で、いっそ開き直りに近いような、どうにでもなるだろうという気持ちになる。我ながら単純なことだ。
その日からローラの寝物語は、彼女の気まぐれな旅の話から、龍の話に変わった。
「龍はとにかくプライドが高くて扱いにくい生き物です。私が山へ行ったときも、乗せてもらうためにお土産からお金から積み上げたものです」
「ふーん。だったら龍を描いても乗せてもらうのは難しくなるかもね」
「……いえ、攻略法があります。彼ら、ハムが大好物なのでそれで釣るのです」
「へえ、ハムが大好物……ハム?」
突然出てきた単語に僕は思わず体を起こした。毛布がめくれて、ローラが「寒いです」と元に戻そうとする。一つ深呼吸して仰向けに寝転がると、ローラは話を続けた。天井を見たまま、真顔である。僕をからかいたいわけではないみたいだった。
「彼らは人間と同じような手を持たないので、肉が食べたかったら、豚や鳥を襲って生肉を丸々食べるしかないのです。一度ダメもとで加工肉を持っていったら、それはそれはたいそうな感動ぶりで……」
「そんなに俗っぽいの、龍って」
「ええ。でもそう思われたくないから、普段はあくまでも『山に生えてる新鮮な草で生きてます』なんて顔をしているんですよ。人間を下に見る割に、人間が作りだしたものに目がない。まあ、こういう種族は案外少なくありませんけど」
前の旅の話でも、似たような話は出てきた気がする。五十年そこそこで死ぬし空も飛べないのに数が多い人間というのは、ほかの種族からしてみれば奇妙奇天烈な生き物に写るのだろう。ローラの話に相槌を打っていたら、だんだんと瞼が下がってきた。ローラが「今日はここまでにしましょうか」と言った頃には、眠りの世界に半身が浸かっていた。
翌朝、試しに龍の足元にハムの塊を描いてみたが、話はそう簡単なものでもないらしい。結局その日も紙はピクリとも動かず、そううまくいくものだとは思っていなかったけどがっかりした。ローラは龍の絵に添えられたハムを見て、なぜか笑いをこらえていた。
最初に語られた威厳やプライドはどうしたのか、ローラの話す龍はだんだん親しみやすさを帯びていく。
「龍は初めて自分の背中に乗った者を主とみなします。いわゆる刷り込みですね」
「刷り込み」
「ほかの生き物から見たら、プライドが高くて傲慢な龍ですが、主からしてみればちょっと大きな犬みたいなものですね。その程度には懐きます」
「……本当?」
「ええ」
ローラはけろりとした顔で、千年生きるという彼らを「大きな犬」呼ばわりしている。もしかしたらずっと昔に龍の主だったことがあったのだろうか。ローラの話を聞くたびに、僕の絵の龍からは角が取れて丸くなっていく。おかしい、龍というのはもっと美しく颯爽とした生き物ではなかったか。僕はだんだん頭身が低くてかわいらしくなっていく龍を見ながら唸った。足元には相変わらずハムの塊が落ちていて、その組み合わせも余計にペット感を強調している。
微動だにしない龍たちが三十匹を超えた頃、さすがに僕も焦りを感じ始めていた。この調子じゃ春を越しても出来上がらない気がした。
続きは毎週月・木曜に順次公開予定です!(祝日及び年末年始を除く)
次回は、1月9日公開予定です。
日程は公開リストよりご確認ください。
『龍が泳ぐは星の海』はこちらに掲載しています。
読者投票
読者投票は以下からご参加ください。ぜひお気に入りの作品に投票をお願いします!
読者投票はこちらから※締切:2024年1月25日(木)23:59まで
※回答は1人1回までとさせていただきます。