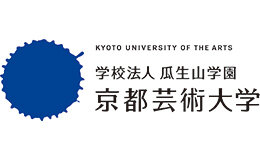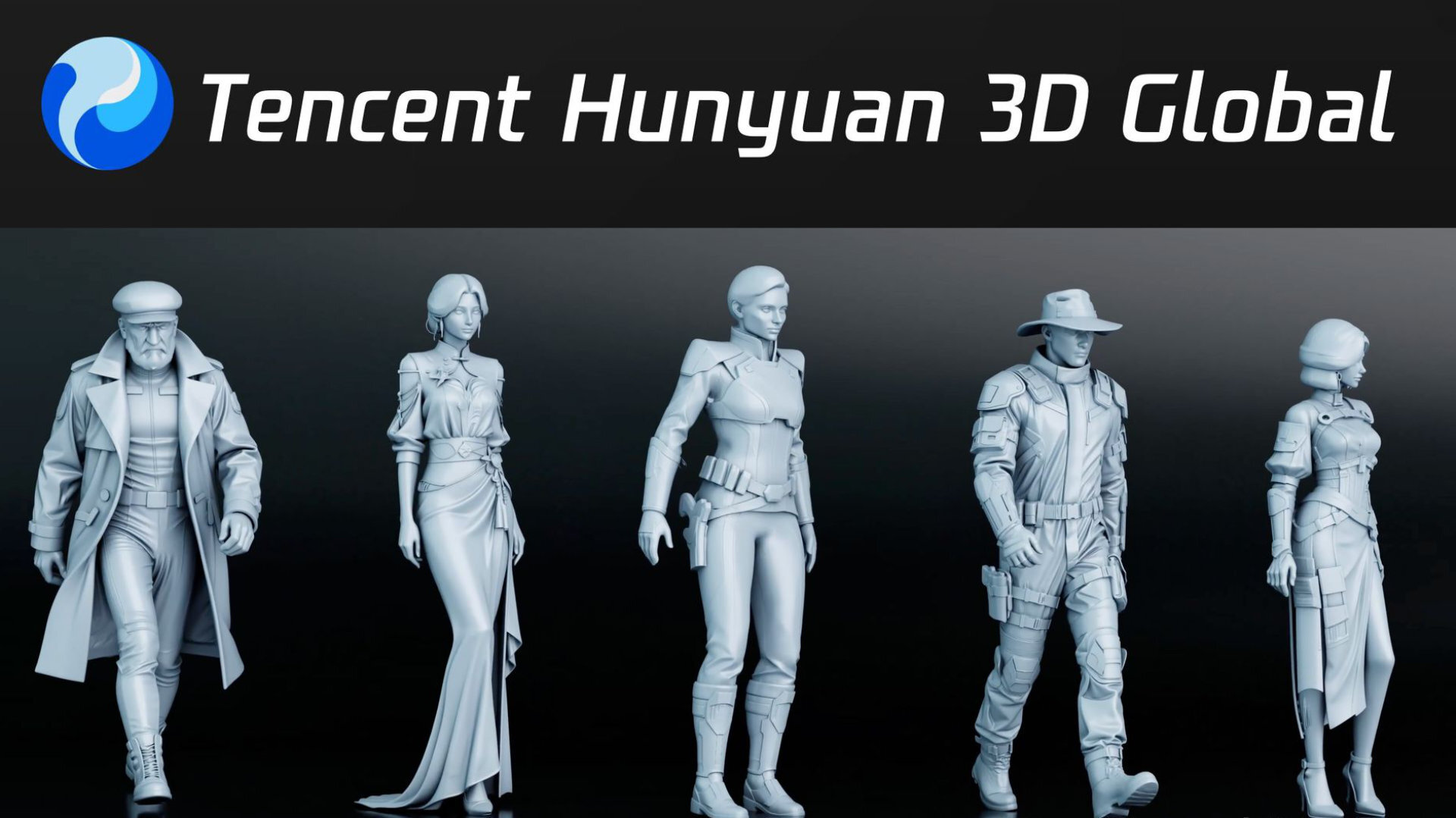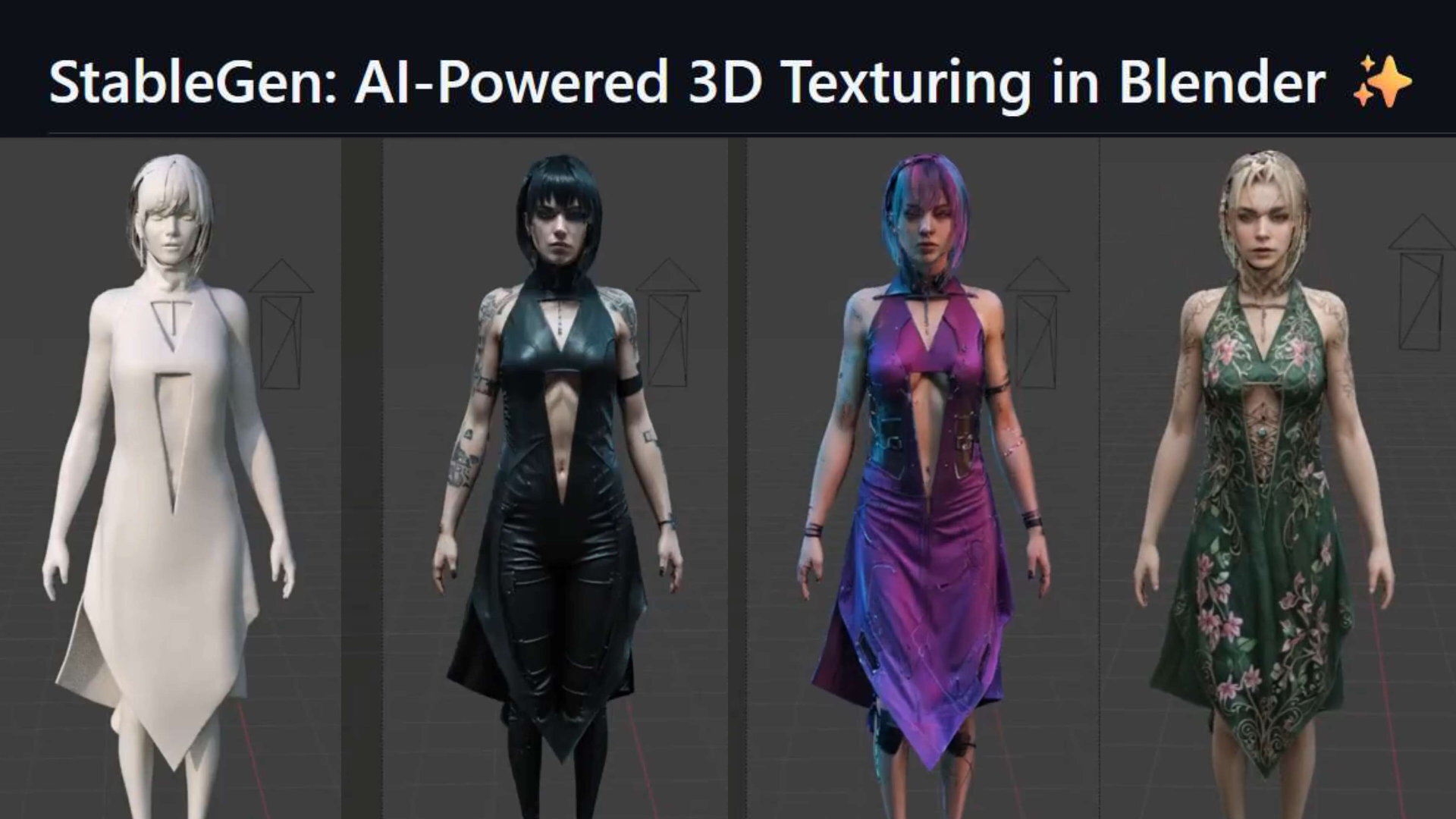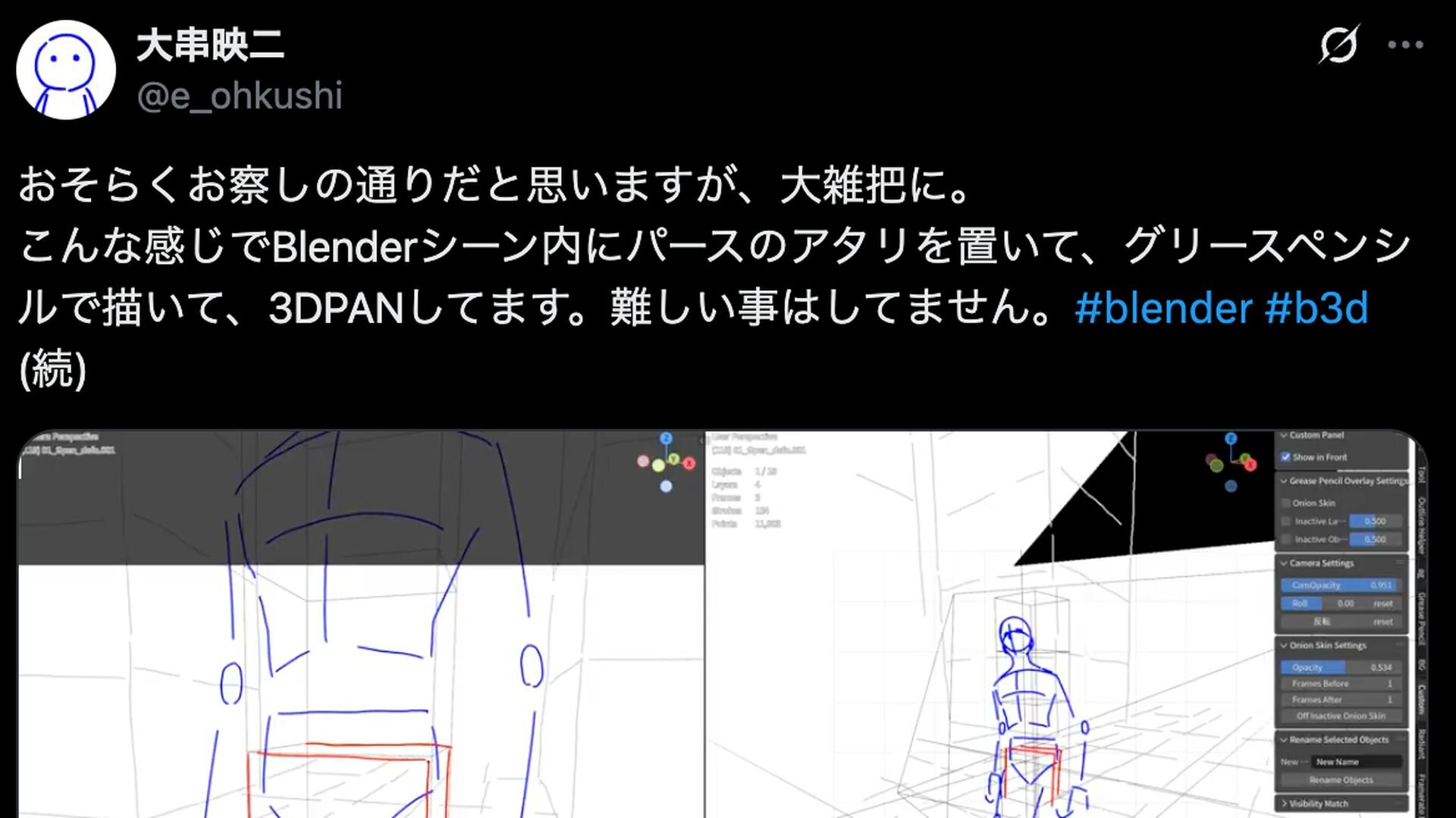「第1回 CGWORLDノベルズコンテスト」では、受賞候補2作品を選出し、CGWORLD.jpにて各作品を全12回にわたって掲載いたします。その後読者投票により各賞を決定し、それぞれ書籍として刊行する予定です。
「CGWORLDノベルズコンテスト」概要
第1回 CGWORLDノベルズコンテスト

■今後の予定
12月8日(金)〜:CGWORLD 305号とCGWORLD.jpで掲載と読者投票スタート
2024年3月頃:書籍時の扉絵イラスト募集
2024年6月頃:読者投票&扉絵イラスト結果発表
本文
五・鮮血
「よし、純一くん、さっき言っていた“あれ”をやってみてくれ」
その日の訓練で、純一はコクーンに入る前に自ら考案した、急降下しながらのきりもみ回転を披露することになった。内覧会で少しでも目を惹くための何かが欲しいという二宮の希望を受けての提案だったが、飛行するスペースがあるとはいえ、それほど広大でもない中庭で行うには難易度は高い。
(でも、今の僕なら……)
コクーンから飛び出していった純一は、中庭の高度限界ギリギリまで到達した後、思い切り体を捻った。中庭の地面が、どんどん純一の視界の中で広がっていく。翼の角度を変えることで、回転を加えると、その速度はさらに上がった。
(へえ、あいつもうまくなったな……)
ティトは木の幹に体を巻き付け、空中を舞う純一を見上げていた。
(ここで体を上げれば!)
地面に激突する寸前で急上昇してみせれば、見映えはさらによくなる……その考えが甘かった。
純一の体に、今までで一番の衝撃と、何かが軋む嫌な音が鳴った。その体は思い切りバウンドし、中庭の壁へと一直線に飛んでいく。
(あっ!)
純一の足首が、突然何かに掴まれた感覚があった。勢いに負けて、すぐに外れてしまったが、少しだけ速度が落ちる。ティトの尻尾だ。
さらに、正面に目を向けると、青白い体毛……マレが素早く駆け寄り、壁になってくれたのがわかった。だが、マレがクッションとなっても純一の速度は殺し切れず、体毛に包まれた体に跳ね返った彼は池に転落していく。そんな純一を、最終的にはシーナが救出したのだった。
傷はコクーンからの再構成時に消えるため、問題ではない。そもそも、彼の羽毛は衝撃を与えると硬化する性質があるため、あれほどの衝撃を受けても、それほど外傷は生じない。だが……
「あまり気にするな。また試せばいい」
と二宮が言ったときの、少し落胆の混じった表情が堪えた。
そんなノウム訓練の後、シャワーを浴び、着替えた純一が施設の廊下を歩いていると、背後から透き通るような声が聞こえた。
「この後、ちょっといい?」
振り返れば、マレがいる。
「あー、さっきは本当にごめん」
「やろうとしてること自体は、間違っていないと思う。ここに外から来る人たちは、いつも派手なものを見るのが好きだから……その話じゃなくて」
先ほど、ティトとシーナもぼやきつつ許してくれたが、マレも、特に先の失敗には何も思うところはないらしい。それを知って、純一は少し安心した。
「ああ、うん。いいよ。じゃあ、食堂で」
訓練の合間を見つけては、マレは本を開き、まだ日取りも決まっていないウィア計画の話を質問してきた。ここ数日はずっとそうだ。
「船にいる間、乗っている人たちはこのケージみたいに、訓練だけをするの?」
「両親からアルゴー級くらいの大きい船なら娯楽施設があるって、聞いたことがあるよ。室内でできることなら、一通りの娯楽があるんじゃないかな。あとは、展望フロアとか」
純一は本の中の写真を指差した。船体の最上部に位置する展望フロアは、安全な宙域では合金製のシャッターが解放され、壁と天井一面に張り巡らされた窓越しに宇宙空間を観察することができる構造となっている。
調査船で星の向こうに行くまでの生活や、着いてからの日々。
「マレならきっと、どこへだって走って行けるよ」
「純一ならもっとでしょう? だって、飛べるんだから」
その紫に輝く瞳で見つめられると、自分の心がすべて透かされるようで、今でも緊張してしまう。実際のところ、このときの純一にはマレの気を惹きたい下心がなかったと言えば、嘘になる。だが、それ以上に、宇宙についての気持ちを共有し、語り合えることがうれしかった。
「長距離はどうだろ?元々体力がないからなあ」
ノウムの姿を活かして、どのような活躍ができるのか。純一は自分がノウムの姿となって開拓地で活躍する姿を夢想しつつ、青白い髪の少女と語り合う日々が続いていった。
―だが、うまく事が運び、自分たちが宇宙に行ったとすれば、このような日々を含めて、自分たちは変わっていかざるを得ない。純一は、時間が止まってこのケージでの生活がずっと続けばと、少しだけ思う。それだけ、彼にとってマレは、特別な存在になりつつあったし、二つの体を行き来する日常は、両親を失って以来、この地球上で初めて純一が得た、捨てるのが惜しいものだった。
いよいよ、内覧会の日が近付いてきた。さすがの二宮も緊張しているのか、そわそわとすることが増えている。何やら考え事を口にしながら廊下を歩き回る姿を、タンをはじめとする所員はもちろん、純一たちも何度か目撃した。
「まあ、いつも通りにやればいいんだ」
昼食を口にほおばりながら、ティトが三人に言った。内覧会での純一たちの役割は、こうだ。まず二宮が、ISCの人間たちの前で説明を行い、ティトとシーナが、庭に出されたコクーンを使用し、それぞれノウムへと変異する。さらにマレも変異することで、幼少期から体をコクーンとノウムに適応させてきた被検体たちが紹介されるのだ。そして最後に純一が、民間人として過ごした後、少しの訓練でノウムになれるモデルケースとして変異をし、指示通りに動ける姿をアピールする。
「うまくいったらどうなるのかな?」
「ISCのやつらが気に入ったら、もっと被検体を増やして、誰でもコクーンに入れるようにするみたいなのはあるかもなあ」
やや不安そうな純一に、ティトはそう答えた。
「新人がやってきたら、純一も教える側になるとかね」
シーナが口を挟んでくる。
「なるほど……」
自分が他人に何かを教えるなど、純一は想像もしていなかった。だが、ノウムになる者がこの先も増えるならば、つい最近仲間入りを果たした純一も、自然に先達となっていく。その姿を想像したとき、純一は胸が高鳴るのを感じた。
内覧会の朝、純一は自分の個室でいつもより早く目を覚ました。窓から差し込む陽光のもとで着替えを済ませると、昨夜から続く緊張による体の強ばりを抑えるために、少し施設内を散歩することにした。
所員たちはもうそれぞれの部署で仕事に就いているのだろうか。窓一つない施設内の廊下に響いているのは、純一の足音だけだった。初めてこの施設に入ったときとは違い、今では我が家のようにリラックスして歩くことができるようになっていた。廊下を抜け、ロビーに出ると、青白い髪が目に入った。
「マレ……? おはよう、今日は早いね」
「大勢の前でノウムになる日は、いつもこんな感じだから」
「慣れてても、そういうことあるんだね」
マレは、両手に着けている長い手袋を外す。そこから出てきたのは、青白い体毛に包まれた手だ。髪と手の変化……それが、マレの肉体に起きたシードからの逆流だった。その手の平を窓の向こうの太陽にかざすと、指先から爪が飛び出す。
「毎回、明日こそ何かが起きるかもしれないって思うと、前の日の夜は眠れなくなる。でも、変わったことは起こらない。先生たちにいつものように褒められて、いつもの毎日に戻るだけだった」
純一ではなく、自分の手を見つめながら話し続けるその姿は、今日もかすかな希望を抱く自分に対して言い聞かせているようだった。
「でも、今日は何かが起きるかもしれないでしょ? 毎回期待するのだって、きっと無駄じゃないよ」
特に根拠はない。ただ、マレを明るい気持ちにしたいがために出た言葉だ。
「―かもね」
マレが、少し笑った。
「そうだ! 今日の内覧会がうまくいったらさ……」
純一の方を向いた紫の瞳は、朝日を反射し、キラキラと輝いていた。ノウムのときと同様の凜々しさを持った彼女の顔が近い。
「その……二人で外に行かない?」
口をついて出た言葉。純一は、少し鼓動が速くなるのを感じた。
「そんなことできるの? 前だってやっと納得してもらえたし……」
そんな緊張とは裏腹に、マレは少し目を丸くした。素直に疑問といったふうに。
「そりゃあ、僕らが大活躍すれば、そのくらいは余裕だよ、たぶん。もう、地球を見て回れる日も残り少なくなるだろうしね!」
「―最初から、自信だけはあったよね。いいよ、行こう」
マレが小さく笑う顔を見ながら、純一は胸に温かい感覚が広がるのを自覚していた。
午前十時。施設の管制室には、純一が最初に見学に来たとき以上に、ISCの人間が詰めかけ、大企業の幹部や財界の人間たちも集まっていた。
「本当に人が姿を変えるのか?」
「私は以前も見せてもらったから本当よ。今回は被検体が増えるらしいわ」
集団の中から不安や期待の言葉が飛び交うのを耳にしながら、二宮は中庭を見下ろす窓に向かって歩いていくと、出資候補者たちの方へと向き直った。
「我々は宇宙という広大な新天地の開拓に、一度失敗しています」
二宮がその集団に語り始める。
「だが、第二波では、あなたがたの新たな調査船に、我々が研究開発した生体インプラントのシード、そして……」
二宮が人差し指を立てると、研究所員が機器を操作し、中庭をモニターに映す。
「このコクーンによって生み出されるノウムたちがいれば、やがて我々に未開の地はなくなるでしょう」
二宮はモニターを指しながら、集団に向けて話を続ける。
「先日、三名の被検体の姿をお見せしましたが、今回は新たな被検体の少年もご紹介します」
二宮は、出資候補者一人一人の目を見つめていき、じっくりと間を取ると
「さあ、共に未来を見ましょう」
と告げた。
同時刻、被検体たちは変異室のゲートの前で待機していた。先ほどからの二宮のスピーチは、中庭へ入るタイミングがわかるよう、スピーカーを通して変異室にも聞こえている。横でタンたち所員も並ぶ中、沈黙が室内を支配していた。
「―ふう」
という純一のため息にティトとシーナが気付き
「あんまり緊張すんなよ」
「そうそう。他人の視線を気にしすぎると、意思の統一が難しくなるから」
二人同時に笑顔を向ける。
「ありがとう」
うなずく純一は、改めて二人の顔を見た。軽口を叩いているが、ティトの頬の鱗と、シーナの首の棘には少し汗が付着しているのがわかった。二人とも、少なからず緊張しているのだ。
「……」
その間も、マレは黙ったままだ。鋭い目つきで、ゲートを見つめている。今朝伝えた言葉が、彼女の励みに少しでもなっていれば……純一はそう願わずにはいられない。
「まず、ご紹介するのは、ティトとシーナ。彼らはそれぞれ爬虫類をベースとした、まったく新しい姿のノウムに変異し、閉所や水中といった環境で力を発揮します」
二宮が廊下を歩きながら何度も暗唱していたセリフだ。それを言い終えたところで、重い音と共に、ゲートが開く。中庭に溢れる陽の光が変異室に差し、被検体たちは思わず目を細めた。
「よし、今だ。頑張れよ」
と、タンが言った。
「じゃ、行ってくる」
「また後で」
二人が中庭に出ると、まずはティトがコクーンに入った。
「コクーンの中で被検体は、一度すべての細胞が完全に分解され―」
以前純一も聞いた説明が、スピーカーから鳴り響いている。少しの間を置いて、コクーンから、ノウムとなったティトが出てきて、続いてシーナも、コクーンへ入り変異する。美しい光沢を放つ四つ目の大蛇のような姿と、岩のような体表を持ち、ワニを思わせるシルエットの姿……その二体のノウムに対する驚きの声が、スピーカー越しに聞こえてくる。続いて、ティトが二宮の指示に従って木の上に配置されているボールを取り、シーナは池の底深くにある機材を、言われた通りに陸へと運び、操作してみせる―訓練の中でやる行動を披露したところ、歓声が上がった。
純一自身、最初に見たときは驚いたし、今回の内覧会の場も緊張しつつ楽しみにしていたはずだが、その光景にはどこか違和感を覚えた。
「さて、次に紹介するのは、蒼き狼に変身するマレ―」
静かな変異室の中に、二宮の声が鳴り響く。マレはゆっくりと動き出し、中庭へと歩を進めた。
「えっと、気を付けて……」
我ながら気の利かない励ましの言葉だと純一は思った。
(気を付けるのは、一番最後に被検体になった僕のほうじゃないか)
「ありがとう」
逆光の中から、確かに言葉が聞こえた。
マレの青白い髪は、登場した時点で注目の的だったが、変異し、美しいノウムの姿になったときも、ティトとシーナの時以上に大きな歓声を浴びることとなった。それを気にする様子もなく、マレは中庭に設置されたアスレチックの中を自由自在に駆け回り、最後は外壁を走って中庭を一周して見せた。
そんな中、一人変異室にいる純一は、目をつむってその場に立っていた。とにかくこれからノウムになることに集中しようと考えたのだ。
「続いて紹介するのは杉崎純一。この国の少年で、つい最近までは平凡な市民生活を送っていました」
(出番だ)
中庭のコクーンに向かうと、その脇に、ノウムとなったティトとシーナ、マレがたたずんでいた。歩く中で、純一は自分の足の動きが硬いことに気付いた。あえてそちらに顔を向けないようにしていたが、それでも中庭を見下ろす窓から純一へと向けられた奇異な視線は、それぞれが細い針となって純一の全身を突き刺している。ティトが、その四つの目の右半分を一瞬閉じた。彼流のウィンクだ。純一はうなずき返し、コクーンの中に入っていく。
『ノウム・シーケンス、開始します』
照明が点き、徐々に自身の肉体が崩れ落ちていく中で、緊張までもが溶けていくようだった。中庭を生身で歩いてきたことに比べれば、この空間のなんて落ち着くことだろう。あとは、意識を集中させ、目をつむるだけだ―。
「空で一回転してみてくれ」
無事にノウムへの変異を遂げた後は、二宮の指示に従って動く。言われたとおりに空を旋回すると、歓声が聞こえてきた。
「次は、“あれ”だ」
きりもみ回転しながらの急降下……墜落して以来練習を重ねていたが、まだ五回に一回しか成功していない。二宮もそれを不安視していたが、あえて、今回は賭けてみることにしたのだろう。
(やってやる!)
高度を上げ、体を捻って一気に急降下し、全身を回転させる。およそ四秒で地上に到達することは、これまでの経験からわかっている。その墜落するかしないかのギリギリの瞬間に、成功があるのだ。
(今だ!)
純一は目をつむり、思い切り羽ばたいて、体を上に向けた。
光量を増幅して映し出す純一の瞳は、着地を成功させた際、管制室内が盛り上がっているのを、明確に認識することができた。
自身がノウムの姿を衆目に晒すことで、はっきりと理解できたことがあった。窓越しに自分を見る人々の表情には尊敬も尊重も敬意もない。ただ、そこにあるのは秘境に住む不気味な生物の生態を覗き見たかのような、好奇心と喜びに満ちた目だけだ。
「ふう……今回もなんとかなったな」
そう言って、ティトが自分のロッカーを開き、着替え始める。
「あれでよかったのかな……」
純一は、自身の抱いた違和感をティトに打ち明けてみることにした。
「なんだ? 今更」
「みんな、僕らの表面的なとこしか見ていないんだ。おもしろい格好になって曲芸をやってるってだけだよ」
ティトは、ふっと鼻で笑う。
「―何?」
「いや、今更気付いたんだなって思って。いや、そうか……。外のやつらに見せるのは、初めてだもんな」
そう言ったティトの顔は、いつもより少しだけ寂しげに見えた。
続きは毎週月・木曜に順次公開予定です!(祝日及び年末年始を除く)
次回は、1月9日公開予定です。
日程は公開リストよりご確認ください。
『美術商ローラと家路を急ぐ青年』はこちらに掲載しています。
読者投票
読者投票は以下からご参加ください。ぜひお気に入りの作品に投票をお願いします!
読者投票はこちらから※締切:2024年1月25日(木)23:59まで
※回答は1人1回までとさせていただきます。